>>116
�M���A�N�Y�l��
�T��
�퍑������Ƃ����b50
�� ���̃X���b�h�͉ߋ����O�q�ɂɊi�[����Ă��܂�
117�l�Ԏ����l�N
2022/04/02(�y) 00:48:41.91ID:jw+hxvLW118�l�Ԏ����l�N
2022/04/03(��) 13:25:58.33ID:PZfYpEcu ����L�i��g��L�j�ɁA�z�O�E���������̉Ɛb�A�Ћ˒O�g��͐�ɒ����̊��C���Ă����̂����A
���Ă̐w�ɍۂ��A���̐w�ɔE��ŋ��������ɋ����B
���̎p��{���ɓ���i�x���j�����āA�������b�̑O�ɗ��Č�����
�u�Ћ˒O�g��̎��ł����A���A�E��Ō䋟�d��A����ɉ�����ċ��܂��B���̋C�F�́A�������Ŋ���
�����ɂ߂��l�q�Ɍ����܂��B
�䊨�C���ꂽ�܂ܓ������ɂ𐋂��Ă��܂��A���y�A����̏��Ƃ��Ȃ�A�s���Ȏ��Ɏv���܂��B
���������Ɏv���A�䊨�C����Ƃ���A�̎v���o�ƂȂ�ƍl���܂��B�v
�����A�܂𗬂��đi����ƁA�����i�����j�́u���C��Ƃ��̂ŁA���X�ɏ����o���ׂ��B�v�Ɛ\���ꂽ�B
����ɂ��g�Ԃ̐[�V�����q�傪�����Đ�֒ʂ�A�O�g��Ɏz���Ɛ\���n���ƁA���̂܂܊��{�֗��āA
�n���~��Ċ���E���ň܂�A������ɗ��܂��Ă����B
���̎p�𒉒����b�������A�u�ЋˁA���C��Ƃ��v�Ɛ\�����ƁA�Ћ˂͓���n�ɕt���A��炵��
�����オ�������A�u���ɂȂ��ċ����Ƃ͕������Ȃ����Ƃ��v�i�����ɂȂ苖���Ƃ͕������鎖�j��
�v���Ă���悤�ȋC�F�ł��̏��ނ��A�n�ɏ���ċ삯�o�����B
���������̖����n�܂�Ɠ����ɁA���t���̍����i����t�������҂���邱�Ɓj���āA���Q�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
���Ă̐w�ł̉z�O�Ƃ̈�R�}
���Ă̐w�ɍۂ��A���̐w�ɔE��ŋ��������ɋ����B
���̎p��{���ɓ���i�x���j�����āA�������b�̑O�ɗ��Č�����
�u�Ћ˒O�g��̎��ł����A���A�E��Ō䋟�d��A����ɉ�����ċ��܂��B���̋C�F�́A�������Ŋ���
�����ɂ߂��l�q�Ɍ����܂��B
�䊨�C���ꂽ�܂ܓ������ɂ𐋂��Ă��܂��A���y�A����̏��Ƃ��Ȃ�A�s���Ȏ��Ɏv���܂��B
���������Ɏv���A�䊨�C����Ƃ���A�̎v���o�ƂȂ�ƍl���܂��B�v
�����A�܂𗬂��đi����ƁA�����i�����j�́u���C��Ƃ��̂ŁA���X�ɏ����o���ׂ��B�v�Ɛ\���ꂽ�B
����ɂ��g�Ԃ̐[�V�����q�傪�����Đ�֒ʂ�A�O�g��Ɏz���Ɛ\���n���ƁA���̂܂܊��{�֗��āA
�n���~��Ċ���E���ň܂�A������ɗ��܂��Ă����B
���̎p�𒉒����b�������A�u�ЋˁA���C��Ƃ��v�Ɛ\�����ƁA�Ћ˂͓���n�ɕt���A��炵��
�����オ�������A�u���ɂȂ��ċ����Ƃ͕������Ȃ����Ƃ��v�i�����ɂȂ苖���Ƃ͕������鎖�j��
�v���Ă���悤�ȋC�F�ł��̏��ނ��A�n�ɏ���ċ삯�o�����B
���������̖����n�܂�Ɠ����ɁA���t���̍����i����t�������҂���邱�Ɓj���āA���Q�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
���Ă̐w�ł̉z�O�Ƃ̈�R�}
119�l�Ԏ����l�N
2022/04/06(��) 22:39:17.57ID:CeypfKfb �u���B�R�L�v����u���ؖ�|�̎��v�Ƃ����A
�D�c�Ɩk����E��[�e�q�Ƃ̐킢�ł����͓���̍���̈�R�}
����Ƃ��M�����{�w�E�j���R�ɂāA�D�c�R�̈�l�����̑�ɂ�����Ȃ���k���R�̏钆�Ɍ�������
�u�啠�䏊(�k����[�A�얞�̂ł������Ƃ���)�̖ݐH���I�v
�ƚ}�������߁A�镺�����͕��𗧂āu��Ŏ˂Ă��܂��I�v�ƍl�����B
���̍��A��a�H�R�Ƃ̎��Ɏˎ肪�O�l����A���ؖ��O�Y�A�H�R�����A�H�R�u����A�Ƃ������B
���̒��ł����ؖ삪�����o����A���ؖ��O�Y�͂����ꂢ��Ȃ����|�ɑ傫�Ȗ�������A�˂����B
�G�����Ƃ��Ɍ������Ă����Ƃ���A��͂���܂����l�A�ܒ�(500m�O��)���z���āA�}�����҂����̖��Ǝ˔������B
�M�����͊��S���A���̖���ď钆�ɕԊ҂����B
�G�����Ƃ��ɑ傢�Ɋ��x�����Ƃ������Ƃ��B
�D�c�Ɩk����E��[�e�q�Ƃ̐킢�ł����͓���̍���̈�R�}
����Ƃ��M�����{�w�E�j���R�ɂāA�D�c�R�̈�l�����̑�ɂ�����Ȃ���k���R�̏钆�Ɍ�������
�u�啠�䏊(�k����[�A�얞�̂ł������Ƃ���)�̖ݐH���I�v
�ƚ}�������߁A�镺�����͕��𗧂āu��Ŏ˂Ă��܂��I�v�ƍl�����B
���̍��A��a�H�R�Ƃ̎��Ɏˎ肪�O�l����A���ؖ��O�Y�A�H�R�����A�H�R�u����A�Ƃ������B
���̒��ł����ؖ삪�����o����A���ؖ��O�Y�͂����ꂢ��Ȃ����|�ɑ傫�Ȗ�������A�˂����B
�G�����Ƃ��Ɍ������Ă����Ƃ���A��͂���܂����l�A�ܒ�(500m�O��)���z���āA�}�����҂����̖��Ǝ˔������B
�M�����͊��S���A���̖���ď钆�ɕԊ҂����B
�G�����Ƃ��ɑ傢�Ɋ��x�����Ƃ������Ƃ��B
120�l�Ԏ����l�N
2022/04/06(��) 23:55:03.22ID:Vw+cZHK+ ����ۂǍׂ����̊��������̂�
���邢�͍��b��
���邢�͍��b��
121�l�Ԏ����l�N
2022/04/07(��) 07:07:24.27ID:YDHzngnu ���Ԃ�˔����ď��̖ɓ˂��h�������̂���
122�l�Ԏ����l�N
2022/04/07(��) 07:37:33.95ID:oTEmwTn/ 500m������Ĕl�荇�����Ă��̂��H
�g������Ȃ������
�������ɉR��
�g������Ȃ������
�������ɉR��
123�l�Ԏ����l�N
2022/04/07(��) 07:39:37.33ID:YDHzngnu ���łɌ����ł�
�ސl�^�����ˊі�(�ނ̐l�A���Ƌ��Ɏˊт��Ȃ�)�ƂȂ��Ă܂�
�ސl�^�����ˊі�(�ނ̐l�A���Ƌ��Ɏˊт��Ȃ�)�ƂȂ��Ă܂�
124�l�Ԏ����l�N
2022/04/10(��) 14:40:35.76ID:HpImF3ZA ����{�ɂ��ƁA�{����ˎ琬�d�́A�썶�q��d���̑��ł���B��������B���l���ĒO���Ə̂����B
���d�����̂����ď㑍�����������ċ��������A���d���o�d���~�߂�ꂽ�B
�փ�����w�̎��A���ɐw���A�c���\���N�z�O���ۉ��̏�������A�i�����j�������b�ɑ������B
���Ă̐w�A�܌������ɁA��ӂɍ�����n�߁A�^�c�̐w��ł��j��A����G��R���a���ė��Ƃ��A
�吨�̓G��ǂ������A�ނ̕����͎��S���\�O�����A���̏���j���č��̘e������ɏ�荞�݁A
�����������ɉ������A���\�����a�����B
��̎ҋ��œ����ꂽ�̂͌ܐl�A�r�������͎̂��l�ł������B
���a��N�A�������b�z���̌�ɁA�Ăя��R�Ƃɏ�����A�c���l�N�\�ɑ������B���ɘZ�\��ł������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�L���Ȗ{���d���̎莆�u��M�[�� �̗p�S ���勃������ �n��₹�v�́u����v���Ɩ{�����d�ɂ��āB
���d�����̂����ď㑍�����������ċ��������A���d���o�d���~�߂�ꂽ�B
�փ�����w�̎��A���ɐw���A�c���\���N�z�O���ۉ��̏�������A�i�����j�������b�ɑ������B
���Ă̐w�A�܌������ɁA��ӂɍ�����n�߁A�^�c�̐w��ł��j��A����G��R���a���ė��Ƃ��A
�吨�̓G��ǂ������A�ނ̕����͎��S���\�O�����A���̏���j���č��̘e������ɏ�荞�݁A
�����������ɉ������A���\�����a�����B
��̎ҋ��œ����ꂽ�̂͌ܐl�A�r�������͎̂��l�ł������B
���a��N�A�������b�z���̌�ɁA�Ăя��R�Ƃɏ�����A�c���l�N�\�ɑ������B���ɘZ�\��ł������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�L���Ȗ{���d���̎莆�u��M�[�� �̗p�S ���勃������ �n��₹�v�́u����v���Ɩ{�����d�ɂ��āB
125�l�Ԏ����l�N
2022/04/16(�y) 15:32:47.72ID:zIGJ4adC ����{�ɁA���Ă̐w�ł̑�㗎��̎��A�א쌺�ד��������A�������킹���Ƃ�������
�ƍN��������������A���ɂȂ�ꂽ
�u�������킷�Ƃ������́A�āX�ɗL��悤�Ȏ��ł͂Ȃ��B
���āA���̒��P�R�̖k�Ɍ����鏟�։@�̎R�ɁA���v�ԕs���i�M�h�j�A���䏇�c�A�r�ؑ��d���Ă����āA
���̖�Ղ��U�߂Ă������A�������킹���ƕ������B
���̑��ɏ���ɂ����āA�������킹���Ƃ����b�͕����y��ł��Ȃ��B�v
���̎��A���v�Ԕ��O��i�����j�����o�Č�����
�u��ӂ̔@���Ɍ����B���̓��́A���͓����s���̎�ɕt���A���x�̖�������܂����B
�V���Z�N�܌��O���̎��ł��B
���͒��P�R�̐��Ɍ�����A��g�̊L�˂ł̍���ɂ����āB�s���̗^�͂́A���v�ԋv�E�q��A�����V���A
�����O�Y�A���쌹���v�A�i�����O�Y�A���̘Z�l�i�{���ρj���������킹�A���̔ӁA���։@�̎R�ɂ����āA
�s���ƒ��̎u���V�s�A�]���폕�A���L�����A������܉E�q��̎l�{�A�������킹�܂����B
�����́A�����͏��E�q��Ɛ\���A����ɋ���܂��B�v
�ƁA�\���グ���Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�ƍN��������������A���ɂȂ�ꂽ
�u�������킷�Ƃ������́A�āX�ɗL��悤�Ȏ��ł͂Ȃ��B
���āA���̒��P�R�̖k�Ɍ����鏟�։@�̎R�ɁA���v�ԕs���i�M�h�j�A���䏇�c�A�r�ؑ��d���Ă����āA
���̖�Ղ��U�߂Ă������A�������킹���ƕ������B
���̑��ɏ���ɂ����āA�������킹���Ƃ����b�͕����y��ł��Ȃ��B�v
���̎��A���v�Ԕ��O��i�����j�����o�Č�����
�u��ӂ̔@���Ɍ����B���̓��́A���͓����s���̎�ɕt���A���x�̖�������܂����B
�V���Z�N�܌��O���̎��ł��B
���͒��P�R�̐��Ɍ�����A��g�̊L�˂ł̍���ɂ����āB�s���̗^�͂́A���v�ԋv�E�q��A�����V���A
�����O�Y�A���쌹���v�A�i�����O�Y�A���̘Z�l�i�{���ρj���������킹�A���̔ӁA���։@�̎R�ɂ����āA
�s���ƒ��̎u���V�s�A�]���폕�A���L�����A������܉E�q��̎l�{�A�������킹�܂����B
�����́A�����͏��E�q��Ɛ\���A����ɋ���܂��B�v
�ƁA�\���グ���Ƃ����B
�i�V���Ӂj
126�l�Ԏ����l�N
2022/04/17(��) 16:54:42.08ID:sJ6g5wvU ����{�ɁA���Ă̐w�A�܌������̍���ŁA����G�����̌��N�E�R���ˎ�i���r�j�̑g��
�y���F�E�q��A�Ԗ[�����Y����삯���Ė������킹�����A������l���˂��������A����ɓG����
�|�����Ă����Ƃ�����A�y���A�Ԗ[�͂��̎蕉���̖��������Ɋ|���đނ����B
���̎���l�X�́u���l�Ƃ�����˂����v�Ɛ\�������A�ƍN�����������A
�u�����̍���A���Ė��͖����B���l�̎ҁA����˂�����ɂ͂��炸�v
�Ƌ��ɂȂ�ꂽ���A�e�X�ɐ�̉������������B
�Âɂ͋|���ɂĐ�������A��ؐ������ْ��̖g���͂��āA����p���n�߂��̂����A�P�|���ɂ��Ă�
�]���͂��Ă��A���ɂ��Ă̕]���͂Ȃ������B
���c�M���̎�����A�����ɂ��Ă̐��w�������悤�ɂȂ����B
�}���A�G���������𗧂��A�|�S�C�ɂĔ��荇���A���̌�킢���������Ȃ��ĂȂ��ċ|�S�C�����������
�g��`�i�ق������傤�j�ƂȂ�B���̎��i��Ŗ�������̂��u��Ԗ��v�Ɩ��t�����B
�������Ԗ��A�����͑����S�C�ɂĈ�Ԗ��̘e�����Ԃ̂��u���e�v�Ƃ����A�܂����̎����������̂��A
�����̌����ƌ����B
���A���̏�ŕ����������������ɂ����đނ����Ƃ��A�u�ꒆ�ɍ����v�ƌ����K�킵���B
���A�s�R�̎��A�G�����Ԃ����ē����̂�˂������Ď����邱�Ƃ́u��v�ƌ����A���Ƃ͌���Ȃ������B
����ɂ����Ă��A���������̂��Ƃ��u���v�Ɩ��t�����̂ł���B
����ΓV���\��N�����A����x�͎�`���ƁA�D�c�����M�G�̍���̎��A�O�B������ɉ����č��킪���������A
���쐨�̎l���R���A��x�ə�Ɠ����Ċ|���������A�D�c���̎l��R�A���ꗧ���Ĕs�k�������A
�M�G�̐�w�ł���D�c���O�Y�����Ԃ������Č��������B�����ĐD�c����V��A�������߁A���c���߁A
���c���E�q��сA���X���l���A�������̎��R�i��œG��˂����Ă��A�̂Ɂu���{���v�Ɩ��t����ꂽ�B
���V���\��N�l���A�G�g���Ǝēc���Ƃ̍���Łu�˃��x�̎��{���v�ƌ����̂��A�G��������ĐF�Â������́A
��������̖��ł���B
�܂����X��U�߂ŁA�O�c���Ƌ��̉Ɛl�E�R��Z���q��͏������A�R��F�E�q��A�쑺�����͖��Ő������
�i����͓V���\��N�A�G�͍��X�������i�����j�ł���j�A�Z���q�傪��ԂɎ����������ŁA
���Ƌ�����Ԗ��̊���A���тɈꖜ�̉������������B
���̎��F�E�q�傪�u���ꂪ��������Ԗ��Ȃ�v�Ƒ��������A���Ƌ��͌䋖�e�Ȃ�
�u�����͖������Z���A�̂ɐ�ɐi��ł������ƕ����ł���v
�Ɣᔻ���ꂽ�B
�܂��A�_�z�A���ԉz�A���˂́u�����v�ƌ����Ďカ���Ƃ���Ă���̂����A���Ԃ��S�C�������o�����ɁA
���ɂċ��Ԃ����ɉ����Ắu���v�Ƃ��ׂ��B���_�z�����̎��̏ɂ���Ĕ��f�����B
�����˂��A���n��̐킢�̎����]�����q�͓��ݎ~�܂�A�������킢�̏�ł������̂œ��˂ɂ������A
����͌����Ƃ͌�����Ƃ��ꂽ�B
���āA�ƍN�����܌������̐킢�Ɂu���͖����v�Ɛ��ꂽ�̂́A���ɂ��G�����͎�N�ł���̂�
���v���ł������ƌ�����B����͓~�ė��x�̌�w���A�u����͗��a�v�Ƌ��ɂȂ��Ă����������
�v���ʂ�ׂ��ł���B�����̌�ꌾ�͕\�����̎��ł͂Ȃ��A�[����q�v��������̂��Ɖ]���Ă���B
�i�V���Ӂj
�u���v�ɂ��Ă̂��b
�y���F�E�q��A�Ԗ[�����Y����삯���Ė������킹�����A������l���˂��������A����ɓG����
�|�����Ă����Ƃ�����A�y���A�Ԗ[�͂��̎蕉���̖��������Ɋ|���đނ����B
���̎���l�X�́u���l�Ƃ�����˂����v�Ɛ\�������A�ƍN�����������A
�u�����̍���A���Ė��͖����B���l�̎ҁA����˂�����ɂ͂��炸�v
�Ƌ��ɂȂ�ꂽ���A�e�X�ɐ�̉������������B
�Âɂ͋|���ɂĐ�������A��ؐ������ْ��̖g���͂��āA����p���n�߂��̂����A�P�|���ɂ��Ă�
�]���͂��Ă��A���ɂ��Ă̕]���͂Ȃ������B
���c�M���̎�����A�����ɂ��Ă̐��w�������悤�ɂȂ����B
�}���A�G���������𗧂��A�|�S�C�ɂĔ��荇���A���̌�킢���������Ȃ��ĂȂ��ċ|�S�C�����������
�g��`�i�ق������傤�j�ƂȂ�B���̎��i��Ŗ�������̂��u��Ԗ��v�Ɩ��t�����B
�������Ԗ��A�����͑����S�C�ɂĈ�Ԗ��̘e�����Ԃ̂��u���e�v�Ƃ����A�܂����̎����������̂��A
�����̌����ƌ����B
���A���̏�ŕ����������������ɂ����đނ����Ƃ��A�u�ꒆ�ɍ����v�ƌ����K�킵���B
���A�s�R�̎��A�G�����Ԃ����ē����̂�˂������Ď����邱�Ƃ́u��v�ƌ����A���Ƃ͌���Ȃ������B
����ɂ����Ă��A���������̂��Ƃ��u���v�Ɩ��t�����̂ł���B
����ΓV���\��N�����A����x�͎�`���ƁA�D�c�����M�G�̍���̎��A�O�B������ɉ����č��킪���������A
���쐨�̎l���R���A��x�ə�Ɠ����Ċ|���������A�D�c���̎l��R�A���ꗧ���Ĕs�k�������A
�M�G�̐�w�ł���D�c���O�Y�����Ԃ������Č��������B�����ĐD�c����V��A�������߁A���c���߁A
���c���E�q��сA���X���l���A�������̎��R�i��œG��˂����Ă��A�̂Ɂu���{���v�Ɩ��t����ꂽ�B
���V���\��N�l���A�G�g���Ǝēc���Ƃ̍���Łu�˃��x�̎��{���v�ƌ����̂��A�G��������ĐF�Â������́A
��������̖��ł���B
�܂����X��U�߂ŁA�O�c���Ƌ��̉Ɛl�E�R��Z���q��͏������A�R��F�E�q��A�쑺�����͖��Ő������
�i����͓V���\��N�A�G�͍��X�������i�����j�ł���j�A�Z���q�傪��ԂɎ����������ŁA
���Ƌ�����Ԗ��̊���A���тɈꖜ�̉������������B
���̎��F�E�q�傪�u���ꂪ��������Ԗ��Ȃ�v�Ƒ��������A���Ƌ��͌䋖�e�Ȃ�
�u�����͖������Z���A�̂ɐ�ɐi��ł������ƕ����ł���v
�Ɣᔻ���ꂽ�B
�܂��A�_�z�A���ԉz�A���˂́u�����v�ƌ����Ďカ���Ƃ���Ă���̂����A���Ԃ��S�C�������o�����ɁA
���ɂċ��Ԃ����ɉ����Ắu���v�Ƃ��ׂ��B���_�z�����̎��̏ɂ���Ĕ��f�����B
�����˂��A���n��̐킢�̎����]�����q�͓��ݎ~�܂�A�������킢�̏�ł������̂œ��˂ɂ������A
����͌����Ƃ͌�����Ƃ��ꂽ�B
���āA�ƍN�����܌������̐킢�Ɂu���͖����v�Ɛ��ꂽ�̂́A���ɂ��G�����͎�N�ł���̂�
���v���ł������ƌ�����B����͓~�ė��x�̌�w���A�u����͗��a�v�Ƌ��ɂȂ��Ă����������
�v���ʂ�ׂ��ł���B�����̌�ꌾ�͕\�����̎��ł͂Ȃ��A�[����q�v��������̂��Ɖ]���Ă���B
�i�V���Ӂj
�u���v�ɂ��Ă̂��b
127�l�Ԏ����l�N
2022/04/17(��) 19:41:45.90ID:F3beJKik �x�W�^���A���H���c�M�����i�\�\�O�N�\�ꌎ����ɏ������N������蔲��
��A���x�����x�B�o�w�A����������A���������O�A�x�B
�~�ߐ�捁A�B�M���{�ӎҁA�]���M�ߍ�(�i�\�\�l�N)�w�V��V���s
�V���A
�t�A�]�Ȗ�(�i�\�\�O�N)�\�ꌎ�֓��H�A(������A�Ȗ��\�ꌎ�����H���ւ�)
���ڂ͍Ō�ŁA�M���͂��̌�������H�����Ă����͗l
�x�͍U���Ƃ����S�肪���A����Η��N����s���Ƃ����V��@�̏C�s�ɔ����A�g�𐴂߂Ă�����ł��傤��
�ق��Ƃ��ɂ͒����Ƃ�����ꂽ�����ŁA������_����������߂��_��
�����ɗD���������H�A�M���̂�����Ƃ����b
��A���x�����x�B�o�w�A����������A���������O�A�x�B
�~�ߐ�捁A�B�M���{�ӎҁA�]���M�ߍ�(�i�\�\�l�N)�w�V��V���s
�V���A
�t�A�]�Ȗ�(�i�\�\�O�N)�\�ꌎ�֓��H�A(������A�Ȗ��\�ꌎ�����H���ւ�)
���ڂ͍Ō�ŁA�M���͂��̌�������H�����Ă����͗l
�x�͍U���Ƃ����S�肪���A����Η��N����s���Ƃ����V��@�̏C�s�ɔ����A�g�𐴂߂Ă�����ł��傤��
�ق��Ƃ��ɂ͒����Ƃ�����ꂽ�����ŁA������_����������߂��_��
�����ɗD���������H�A�M���̂�����Ƃ����b
128�l�Ԏ����l�N
2022/04/17(��) 20:17:49.52ID:l6UsOGHj �M���u��������r�r�͏����v
129�l�Ԏ����l�N
2022/04/17(��) 20:22:58.65ID:l6UsOGHj ��H�҂��ĉi�\13�N��4���܂ŁB�i�\12�Nor���T1�N11���̊ԈႢ�H
130�l�Ԏ����l�N
2022/04/17(��) 20:28:59.43ID:wytywmt5 �Ȗ�=�i�\�\��N�̂悤��
��r�r�������Ƃ���ƓV��@�̎��_�̎R���̌�g�������������߂��낤
�����x�͂ʼn��͂��������ȋC�����邯��
��r�r�������Ƃ���ƓV��@�̎��_�̎R���̌�g�������������߂��낤
�����x�͂ʼn��͂��������ȋC�����邯��
131�l�Ԏ����l�N
2022/04/17(��) 20:29:45.53ID:F3beJKik >>129
�����͏����҂̏㗢���̔N���ɏ�������
�m���ɌȖ��N�͌�������Ɖi�\�\��N�Ȃ��
���������Ǔ����Ǝ��̗�f���Ă�Ƃ����邩������Ȃ����A�i�\�\�O�N�Ƃ�������Œ��ߓ��ꂽ
�����͏����҂̏㗢���̔N���ɏ�������
�m���ɌȖ��N�͌�������Ɖi�\�\��N�Ȃ��
���������Ǔ����Ǝ��̗�f���Ă�Ƃ����邩������Ȃ����A�i�\�\�O�N�Ƃ�������Œ��ߓ��ꂽ
132�l�Ԏ����l�N
2022/04/20(��) 18:59:23.26ID:JwisvsqA �u��F���p�L�v����u�ˎ��ӘA�A�Ώ@�ɌR�z���`�_��̎��A�Ȃ�тɏ����E���̎��v
�y���e�����t�S�������߁A��F�@�ٌ��͓V���Z�N(1572�N)��ЎO����{�A�����R���䔭���Ȃ��ꂽ�B
�y������ɋ߂Â��ƘT�������������߁A���Ă͎F�����ւ̍��}���Ƃ݂Ȑg�\�����B
�����ɏ@�ٌ��̌R�z�ҁE�p�G�Ώ@�͕��c���A���}�����A���̂ق����X�̌R�z���`�����l�ł�������
�Ώ@�u���̘T���͍��}�ł͂���܂���B������ɂ͖��������邼�ƍ��o�����邽�߂̍�ł��B
���͗��C�ɂ̂ڂ炸�A�C�C���r���Ă��邽�߁A�G�̉^���悭�Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�v
���̌�A����悭�叟���A�y���e���߂ɂ����B
�����Q��̐������������e���͐ؕ��������A��������l�X�́A���Ɏ���܂œ��̋ȕ���ւ��̂��ėE��ʼn̂����B
�����ҋ��͕s���Ɏv���u�l��遂肪���킹��̂��v�Ɩ@�x���������������߁A���̐V�ȕ��͂�B
�y���e�����t�S�������߁A��F�@�ٌ��͓V���Z�N(1572�N)��ЎO����{�A�����R���䔭���Ȃ��ꂽ�B
�y������ɋ߂Â��ƘT�������������߁A���Ă͎F�����ւ̍��}���Ƃ݂Ȑg�\�����B
�����ɏ@�ٌ��̌R�z�ҁE�p�G�Ώ@�͕��c���A���}�����A���̂ق����X�̌R�z���`�����l�ł�������
�Ώ@�u���̘T���͍��}�ł͂���܂���B������ɂ͖��������邼�ƍ��o�����邽�߂̍�ł��B
���͗��C�ɂ̂ڂ炸�A�C�C���r���Ă��邽�߁A�G�̉^���悭�Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�v
���̌�A����悭�叟���A�y���e���߂ɂ����B
�����Q��̐������������e���͐ؕ��������A��������l�X�́A���Ɏ���܂œ��̋ȕ���ւ��̂��ėE��ʼn̂����B
�����ҋ��͕s���Ɏv���u�l��遂肪���킹��̂��v�Ɩ@�x���������������߁A���̐V�ȕ��͂�B
133�l�Ԏ����l�N
2022/04/20(��) 19:02:54.19ID:JwisvsqA ���Čˎ����ˎ��������̎q���E�R���ӘA�̐w���̗ƂɌR�z�ҁE�Ώ@�͏h���Ƃ��Ă�������
�ˎ��ӘA�͐Ώ@�Ɂu�ق��݂̂Ȃ��T���������̂ɋM���͍ƌ������܂����B
�ǂ����킽���ɌR�z���c��Ȃ����`�������ꂽ���v�Ə��]�����Ƃ���
�Ώ@�u�������Ƃł��B�t��ƂȂ�����͎c�炸�`���������܂��傤�B
�܂���̋C�ɂ��Ăł��B���������C�Ƃ����̂��|���_�ȂǂʼnM���m�邱�Ƃ��ł��܂��B
��U�߂̍ہA�C�����D�̂悤�ɂȂ��Ă���A��͖ŖS����^���ɂ���܂��B
��̋C�������r���A���邵�ɂ����̂ōK�v�ł��B
��̋C������r���A�U�߂Ă������Ȃ��̂ōK�v�ł��B
��̋C�������r���A�U�ߎ�̏����ŏ�͍~�Q���邱�ƂɂȂ�܂��B
��̋C���k���r���A��̏����ōU�ߎ�̕����ł��B
��̋C���ǂ��ւł��s������ɖ߂��Ă���悤�Ȃ�A���͓��S���܂��B
��̋C���U�ߎ�ɂ�����A�U�ߎ�ɕa�l���������ƂɂȂ�܂��B
��̋C�������オ���Ăǂ��ɍs�������킩��Ȃ��悤�Ȃ�A���s�͌����Ȃ����ߎ��v��ƂȂ�܂��B
��U�߂��ď\���߂��āA�����J���Ȃ��悤�Ȃ�A�G��ɏ��������邩�A�������ɗ���҂��o�܂��B
�w��߂��������ƂɁA���ꂼ�ꏟ��ɒ�߂��Ƃ�����悤�ł���Ε����ł��B
�܂����҂̏��F�E���F�Ƃ������̂�����܂��B
�l���̔������������肵�Ă��Đl�n�̑��������Ȃ��悤�Ȃ珟���ł��B
�������o���o���Ől�n�̑���������悤�Ȃ畉���ł��B
�܂��b�Ƃ������Ƃ�����܂��B
��l���ق��̑��̗l�q���C�ɂȂ��Ă��ɂ��A�ق��̂��̂��e������ċ߂Â��A���J��Ɋ��悤�ł���Δb�̂悤�Ɍ����܂��B����������ł��B
�܂������̂��Ƃł����A
�u�����̋g���͓G�ɂƂ��Ă��g����������p�������̗v�ł���v�ƌ����҂����܂�����낵������܂���B
���̑叫�ɂƂ��ċg���ł���A�ق��̑叫�ɂƂ��ċg���Ƃ͂Ȃ�܂���B
�܂��������g���A�������g���ɕς����p������܂��B
���̂悤�Ȃ��Ƃ�m�炸���Đ��ɏo��҂́A�h�̂Ȃ������C���ɂ���悤�ȁA���̂Ȃ�������R�ɂ���悤�ȁA�ƂȂ����ďM�ɏ��悤�Ȃ��̂ł��B
�܂��킽���̎t�́u�Ðl�H���A���͐�����ʂ䂦�A�����𔒐n�̑O�ɑ����͗Ǐ��ɂ��炸�v�Ɛ\���Ă���܂����v
�ӘA�u�ʔ����b�����肪�Ƃ��������܂��B���`�̏��߂ɂ͋C�ɂ��Ă��������܂��傤�v
�Ώ@�u����͉P�n�ɂ����đ��`�������܂��傤�v
�ˎ��ӘA�͐Ώ@�Ɂu�ق��݂̂Ȃ��T���������̂ɋM���͍ƌ������܂����B
�ǂ����킽���ɌR�z���c��Ȃ����`�������ꂽ���v�Ə��]�����Ƃ���
�Ώ@�u�������Ƃł��B�t��ƂȂ�����͎c�炸�`���������܂��傤�B
�܂���̋C�ɂ��Ăł��B���������C�Ƃ����̂��|���_�ȂǂʼnM���m�邱�Ƃ��ł��܂��B
��U�߂̍ہA�C�����D�̂悤�ɂȂ��Ă���A��͖ŖS����^���ɂ���܂��B
��̋C�������r���A���邵�ɂ����̂ōK�v�ł��B
��̋C������r���A�U�߂Ă������Ȃ��̂ōK�v�ł��B
��̋C�������r���A�U�ߎ�̏����ŏ�͍~�Q���邱�ƂɂȂ�܂��B
��̋C���k���r���A��̏����ōU�ߎ�̕����ł��B
��̋C���ǂ��ւł��s������ɖ߂��Ă���悤�Ȃ�A���͓��S���܂��B
��̋C���U�ߎ�ɂ�����A�U�ߎ�ɕa�l���������ƂɂȂ�܂��B
��̋C�������オ���Ăǂ��ɍs�������킩��Ȃ��悤�Ȃ�A���s�͌����Ȃ����ߎ��v��ƂȂ�܂��B
��U�߂��ď\���߂��āA�����J���Ȃ��悤�Ȃ�A�G��ɏ��������邩�A�������ɗ���҂��o�܂��B
�w��߂��������ƂɁA���ꂼ�ꏟ��ɒ�߂��Ƃ�����悤�ł���Ε����ł��B
�܂����҂̏��F�E���F�Ƃ������̂�����܂��B
�l���̔������������肵�Ă��Đl�n�̑��������Ȃ��悤�Ȃ珟���ł��B
�������o���o���Ől�n�̑���������悤�Ȃ畉���ł��B
�܂��b�Ƃ������Ƃ�����܂��B
��l���ق��̑��̗l�q���C�ɂȂ��Ă��ɂ��A�ق��̂��̂��e������ċ߂Â��A���J��Ɋ��悤�ł���Δb�̂悤�Ɍ����܂��B����������ł��B
�܂������̂��Ƃł����A
�u�����̋g���͓G�ɂƂ��Ă��g����������p�������̗v�ł���v�ƌ����҂����܂�����낵������܂���B
���̑叫�ɂƂ��ċg���ł���A�ق��̑叫�ɂƂ��ċg���Ƃ͂Ȃ�܂���B
�܂��������g���A�������g���ɕς����p������܂��B
���̂悤�Ȃ��Ƃ�m�炸���Đ��ɏo��҂́A�h�̂Ȃ������C���ɂ���悤�ȁA���̂Ȃ�������R�ɂ���悤�ȁA�ƂȂ����ďM�ɏ��悤�Ȃ��̂ł��B
�܂��킽���̎t�́u�Ðl�H���A���͐�����ʂ䂦�A�����𔒐n�̑O�ɑ����͗Ǐ��ɂ��炸�v�Ɛ\���Ă���܂����v
�ӘA�u�ʔ����b�����肪�Ƃ��������܂��B���`�̏��߂ɂ͋C�ɂ��Ă��������܂��傤�v
�Ώ@�u����͉P�n�ɂ����đ��`�������܂��傤�v
134�l�Ԏ����l�N
2022/04/20(��) 19:05:47.88ID:JwisvsqA �ӘA�u�ł͔��w�ɂ��Ăł����A�w���͔��ɒ�܂��Ă���̂ł��傤���v
�Ώ@�u���w�Ƃ����ٍ͈̂��̏����E���̔��w�̐}�������č������Ă���܂��B
���w�Ƃ�
���A�ߗ��A���ցA��A�N��A���~�A�t�́A��s
�����{�Ƃ��Ă��܂��܂Ȑw��肪����܂��B������ɂ��挹�͂��̔��w�ł��B��������ʂő��`�������܂��傤�B
�ӘA�u�E���Ƃ͂����Ȃ�E�m�ł��傤���v
�Ώ@�u�E���Ƃ�冂̌��l�ł��B
�ْ̈��ɁA���̑����A冂̗����A鰂̑����Ƃ����O�l������A�V�i�l�S�B���O�����Ă��܂����B
�����͍˒q���ɂ�����Ėd���߂��炵�G��h���A�����͎m��J���O���A�Ƃ��Ɍ̍������𗩂߂���̂��W�܂�A��s��N���Ă��܂����B
�����͍ŋ߉������番���ꂽ����ŁA�m�`�����藘�~��Y�ꂽ���߂ɒ��b�E�F�q���l�����炫�ċ������������s�Ȃ��Ă��܂����B
�������ĎO�l�Ƃ��q�m�E������Ă������߁A���冂͓C�����Ă���܂����B
�����ɏ����E���Ƃ������l���B�ق���冂̓�z�R�ʼn̂��̂��ĕ�炵�Ă���܂������A�����ɏ��ق���Ă��f��܂����B
�����ŗ����͎O�x���I�Ɏ��畋���u�䂪�g�̗~�ł͂Ȃ��V�������̂��߂ɂ��̍˂����Ă��炢�����v
�Ɛ���s��������s�������ɂȂ������߁A�E���͂���冂̏告�ƂȂ�܂����B
�����́u���ɍE������͋��ɐ����邪���Ƃ��v�ƕ���ƍ������܂����B
鰂̑����͉痴�E�E����������A�i�n���B�Ƃ������R�Ɏ��\���R���������冂ɐN�U�����܂����B
�������E���ɎO�\���R����������A�冂̍����ł���䌴�ŗ��R�͂����܂݂��܂����B
�������\���̊��ɂݍ����������������߁A鰕��͕s���Ɏv���i�n���B�ɐi�R������̂ł����A�i�n���B�͋����܂���ł����B
���鎞�A���B�͐��߂ɂ���冕�����E���̗l�q�����Ƃ���
�u�E���͎m���ɗ�V���������A�������̂�H�ׁA��͖��炸���猩�������A���͎m���Ɩr�܂������ۂ���B
���̂��ߎO�\���̌R���͐S����ɂ��Ă���̂��v�ƌ���������
�i�n���B�́u�����͎��\�������S�͈�ɂȂ��Ă��Ȃ��A�E�����ߘJ�ƍ����̂��߂ɕa�ƂȂ�܂ł͑҂ׂ��ł���v
��鰂̎m�����u�l�\�����u�ĂēG���̖���m�邱�Ƃ����낤���A�痴������邽�ߌ����Ă���̂��v�ƚ}��̂��������ďo�w���܂���ł����B
�����A���w�̊Ԃɋq���������A�����Ԃ��P���Ă���܂����B
������݂����B�́u�����̂����ɓV���̐l�����������ł���A�E���͕K�����ʂł��낤�v�Ɗ�т܂����B
������ɍE���͎��ɂ܂������A册R�͍E���̎����B����鰌R�ɕ���i�߂܂����B
�i�n���B�͐킦��鰂��s�k����ƍl���Ă������߁A���ɂ��y���\���ދp���܂����B
�������āu������E���A�����钇�B�𑖂炷�v�ƌ�����悤�ɂȂ����̂ł��B
�R���U�����̂��A冕��͍E���̎���m��S�R�����B�ɍ~��܂����B
��������冂��܂��łсA���Ɍ����ł��鰂̑������V���ꂵ�Ă̂ł��B
�����v���܂��ɁA�����E���̂悤�ɁA���ۂ��A���Ɉ��ꂽ�Ƃ����̂́A�Ƃ��ɑ叫���w�Ԃׂ����_�ł��B
�����Ƃ����N�@�ٌ������������߂���Ќ��ɂ͂��Ȃ�Ȃ��ł��傤���B�v
����͊ӘA�̎�经]�̕����������L�������̂ł���B
����A�ӘA�͉P�n�O�����o��̐܁X�ɌR�z�ꊪ��`�����ꂽ�������B
�Ώ@�u���w�Ƃ����ٍ͈̂��̏����E���̔��w�̐}�������č������Ă���܂��B
���w�Ƃ�
���A�ߗ��A���ցA��A�N��A���~�A�t�́A��s
�����{�Ƃ��Ă��܂��܂Ȑw��肪����܂��B������ɂ��挹�͂��̔��w�ł��B��������ʂő��`�������܂��傤�B
�ӘA�u�E���Ƃ͂����Ȃ�E�m�ł��傤���v
�Ώ@�u�E���Ƃ�冂̌��l�ł��B
�ْ̈��ɁA���̑����A冂̗����A鰂̑����Ƃ����O�l������A�V�i�l�S�B���O�����Ă��܂����B
�����͍˒q���ɂ�����Ėd���߂��炵�G��h���A�����͎m��J���O���A�Ƃ��Ɍ̍������𗩂߂���̂��W�܂�A��s��N���Ă��܂����B
�����͍ŋ߉������番���ꂽ����ŁA�m�`�����藘�~��Y�ꂽ���߂ɒ��b�E�F�q���l�����炫�ċ������������s�Ȃ��Ă��܂����B
�������ĎO�l�Ƃ��q�m�E������Ă������߁A���冂͓C�����Ă���܂����B
�����ɏ����E���Ƃ������l���B�ق���冂̓�z�R�ʼn̂��̂��ĕ�炵�Ă���܂������A�����ɏ��ق���Ă��f��܂����B
�����ŗ����͎O�x���I�Ɏ��畋���u�䂪�g�̗~�ł͂Ȃ��V�������̂��߂ɂ��̍˂����Ă��炢�����v
�Ɛ���s��������s�������ɂȂ������߁A�E���͂���冂̏告�ƂȂ�܂����B
�����́u���ɍE������͋��ɐ����邪���Ƃ��v�ƕ���ƍ������܂����B
鰂̑����͉痴�E�E����������A�i�n���B�Ƃ������R�Ɏ��\���R���������冂ɐN�U�����܂����B
�������E���ɎO�\���R����������A�冂̍����ł���䌴�ŗ��R�͂����܂݂��܂����B
�������\���̊��ɂݍ����������������߁A鰕��͕s���Ɏv���i�n���B�ɐi�R������̂ł����A�i�n���B�͋����܂���ł����B
���鎞�A���B�͐��߂ɂ���冕�����E���̗l�q�����Ƃ���
�u�E���͎m���ɗ�V���������A�������̂�H�ׁA��͖��炸���猩�������A���͎m���Ɩr�܂������ۂ���B
���̂��ߎO�\���̌R���͐S����ɂ��Ă���̂��v�ƌ���������
�i�n���B�́u�����͎��\�������S�͈�ɂȂ��Ă��Ȃ��A�E�����ߘJ�ƍ����̂��߂ɕa�ƂȂ�܂ł͑҂ׂ��ł���v
��鰂̎m�����u�l�\�����u�ĂēG���̖���m�邱�Ƃ����낤���A�痴������邽�ߌ����Ă���̂��v�ƚ}��̂��������ďo�w���܂���ł����B
�����A���w�̊Ԃɋq���������A�����Ԃ��P���Ă���܂����B
������݂����B�́u�����̂����ɓV���̐l�����������ł���A�E���͕K�����ʂł��낤�v�Ɗ�т܂����B
������ɍE���͎��ɂ܂������A册R�͍E���̎����B����鰌R�ɕ���i�߂܂����B
�i�n���B�͐킦��鰂��s�k����ƍl���Ă������߁A���ɂ��y���\���ދp���܂����B
�������āu������E���A�����钇�B�𑖂炷�v�ƌ�����悤�ɂȂ����̂ł��B
�R���U�����̂��A冕��͍E���̎���m��S�R�����B�ɍ~��܂����B
��������冂��܂��łсA���Ɍ����ł��鰂̑������V���ꂵ�Ă̂ł��B
�����v���܂��ɁA�����E���̂悤�ɁA���ۂ��A���Ɉ��ꂽ�Ƃ����̂́A�Ƃ��ɑ叫���w�Ԃׂ����_�ł��B
�����Ƃ����N�@�ٌ������������߂���Ќ��ɂ͂��Ȃ�Ȃ��ł��傤���B�v
����͊ӘA�̎�经]�̕����������L�������̂ł���B
����A�ӘA�͉P�n�O�����o��̐܁X�ɌR�z�ꊪ��`�����ꂽ�������B
135�l�Ԏ����l�N
2022/04/21(��) 08:28:36.74ID:CX+G3e4b �����Ɏq���͂��Ȃ�����n�삾�낤
136�l�Ԏ����l�N
2022/04/21(��) 09:17:05.98ID:4iHUaxAG ����A�ˎ����A(����̗P�q)�ł���
�ӘA���Ɠ���{�l��
�ӘA���Ɠ���{�l��
137�l�Ԏ����l�N
2022/04/21(��) 15:01:14.99ID:P7oGifBM �u�����R ��̗��� �U��ɂ��� ���l�ɂ͍����� �F�a�̗��l�v
�@�˓c�����ɋ��̈��g�Ɖ������g�����g�҂��K��A��Ái��F�j�܂ŏo�����鎖�ɂȂ������������L���o���O�Ɏc���������̋�ł��B
�@���̎��A经]�����q�\���͎�y�̏������܂߂đS�Ă���N�ɏ}����o��̎҂���ŁA���L���g�����ˈ��j�̑������ژZ���]��̖����ɑ喁�グ���������������Ƃ��āA�a�莀���o�債�Ă����ƁB
�@�����ɂ́A�ɗ\�������Ƃ̖ŖS�͋G�߂��ڂ낤�悤�ɋt�炢����̂ł���A�x�������ɑ����̂��x����ĎE�����̂ł͂Ȃ��A�����������V���Ȃ̂��Ɗo�債�Ă���S�����r�����ƁB
�@�c�c�o��̏�ł��A�Ăяo�������Ď��Q����̂ł͂Ȃ��A�h�q�A��ɑS�͂Ŏa�莀������Əo�g�őm���オ��ł��퍑�喼���������������L�́A�퍑����炵�����b�B
�@�˓c�����ɋ��̈��g�Ɖ������g�����g�҂��K��A��Ái��F�j�܂ŏo�����鎖�ɂȂ������������L���o���O�Ɏc���������̋�ł��B
�@���̎��A经]�����q�\���͎�y�̏������܂߂đS�Ă���N�ɏ}����o��̎҂���ŁA���L���g�����ˈ��j�̑������ژZ���]��̖����ɑ喁�グ���������������Ƃ��āA�a�莀���o�債�Ă����ƁB
�@�����ɂ́A�ɗ\�������Ƃ̖ŖS�͋G�߂��ڂ낤�悤�ɋt�炢����̂ł���A�x�������ɑ����̂��x����ĎE�����̂ł͂Ȃ��A�����������V���Ȃ̂��Ɗo�債�Ă���S�����r�����ƁB
�@�c�c�o��̏�ł��A�Ăяo�������Ď��Q����̂ł͂Ȃ��A�h�q�A��ɑS�͂Ŏa�莀������Əo�g�őm���オ��ł��퍑�喼���������������L�́A�퍑����炵�����b�B
138�l�Ԏ����l�N
2022/04/21(��) 15:02:50.43ID:P7oGifBM �������B
�~����
�Z����
��ϊ��ɋC�Â��܂���ł����A�f�ڎ��ɂ͂��萔�ł����C�������肢���܂��B
�~����
�Z����
��ϊ��ɋC�Â��܂���ł����A�f�ڎ��ɂ͂��萔�ł����C�������肢���܂��B
139�l�Ԏ����l�N
2022/04/22(��) 06:15:31.88ID:uQZkWR+e NHK�j���[�X�bNHK NEWS WEB
WEB���W
����ƍN�̍b�h�i�������イ�j�̋����`�����̓�ɔ��钤���t�`
2022�N4��21�� 19��37��
����ƍN�̍b�h�i�������イ�j�̋����`�����̓�ɔ��钤���t�`
���N����������̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v�ɍ��킹�āA�É��s�ɐV���ȗ��j�����ق��I�[�v�����܂��B
�ő�̌Ăѕ��́A�����̍ޗ���Z�@���g���ĐV���ɐ��삪�i�߂��Ă��鍑�̏d�v�������ŁA����ƍN���փ����̐킢�Őg�ɂ����Ƃ����b�h�i�������イ�j�u���S��i�����������j�v�B���̋����͓����̋Z�p�ł͍�������Ƃ���鎽���ŏo���Ă��܂��B
�����͂ǂ̂悤�ɂ��č��ꂽ�̂��A�b�{�s�̒����t�ɂ���Ă��̓䂪���炩�ɂȂ�܂����B�i�b�{�����NjL�� �ѓc�͕F�j
�����̍b�h�i�������イ�j �ƍN�̎��S��i�����������j
����ƍN���V��������ʂ����傫�ȐߖڂƂȂ����փ����̐킢�B
�����Őg�ɂ��Ă����Ƃ����̂������̍b�h�A���S��ł��B
�퍑����A���ł̕������������߂ɐF�N�₩�ł���т₩�ȍb�h���嗬�������Ȃ��A�����̐F�͓V���l�A�ƍN�̏ے��Ƃ������A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B
���̎��S����̍ޗ���Z�@�ŐV���ɐ��삵�A���N1���ɐÉ��s�ɃI�[�v��������j�����ق̌Ăѕ��Ƃ��ēW�����悤�Ƃ������g�݂��n�܂��Ă��܂��B
���̎��S��̋����̕�����C����Ă���̂��b�{�s�̒����t�A����삳��ł��B
��₳���������̂́A�S���L���̕�̂܂��E�b�{�s�B
�����̕���i���[�J�[��E�l���W�܂�A�����ŗ��ʂ������i�̂��悻3����1�Y���Ă��܂��B
�ƋƂ��p���ŕ���E�l�ƂȂ�����₳��
����E�l�̉Ƃɐ��܂�A��w���ƌ�A�ƋƂ��p������₳��ł����A�����Z�p�͂��F�߂��A�����t�Ƃ��čb�h�̋����̕����Ɍg���悤�ɂȂ�܂����B
�����t�Ƃ́A�g�����ˁh�Ƃ�����`���H����g���ċ����̑����Ȃǂ��{���E�l�̂��Ƃł��B
�����t�Ƃ��ĕ��ݏo������₳��̓]�@�ƂȂ����̂��A�ӂ邳�ƎR���̍���A�|���Z�i���ĂȂ��̂�낢�j�̕����ł����B
�b�㌹���̑c�A���`���̐����l�₱�����A����𐧍삵�������t�̋Z�p���J��z�����Ȃ��畜�����Ă������Ƃɖ��͂��������Ƃ����܂��B
�u�����ɂƂ��čb�h�i�������イ�j�͎��ɑ����݂����Ȃ��́B�����̍ō��̋Z�p�����W���Đ��삳��Ă��܂��B����Ɍg���邱�Ƃ����͂��Ɗ����Ă��܂��v
WEB���W
����ƍN�̍b�h�i�������イ�j�̋����`�����̓�ɔ��钤���t�`
2022�N4��21�� 19��37��
����ƍN�̍b�h�i�������イ�j�̋����`�����̓�ɔ��钤���t�`
���N����������̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v�ɍ��킹�āA�É��s�ɐV���ȗ��j�����ق��I�[�v�����܂��B
�ő�̌Ăѕ��́A�����̍ޗ���Z�@���g���ĐV���ɐ��삪�i�߂��Ă��鍑�̏d�v�������ŁA����ƍN���փ����̐킢�Őg�ɂ����Ƃ����b�h�i�������イ�j�u���S��i�����������j�v�B���̋����͓����̋Z�p�ł͍�������Ƃ���鎽���ŏo���Ă��܂��B
�����͂ǂ̂悤�ɂ��č��ꂽ�̂��A�b�{�s�̒����t�ɂ���Ă��̓䂪���炩�ɂȂ�܂����B�i�b�{�����NjL�� �ѓc�͕F�j
�����̍b�h�i�������イ�j �ƍN�̎��S��i�����������j
����ƍN���V��������ʂ����傫�ȐߖڂƂȂ����փ����̐킢�B
�����Őg�ɂ��Ă����Ƃ����̂������̍b�h�A���S��ł��B
�퍑����A���ł̕������������߂ɐF�N�₩�ł���т₩�ȍb�h���嗬�������Ȃ��A�����̐F�͓V���l�A�ƍN�̏ے��Ƃ������A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B
���̎��S����̍ޗ���Z�@�ŐV���ɐ��삵�A���N1���ɐÉ��s�ɃI�[�v��������j�����ق̌Ăѕ��Ƃ��ēW�����悤�Ƃ������g�݂��n�܂��Ă��܂��B
���̎��S��̋����̕�����C����Ă���̂��b�{�s�̒����t�A����삳��ł��B
��₳���������̂́A�S���L���̕�̂܂��E�b�{�s�B
�����̕���i���[�J�[��E�l���W�܂�A�����ŗ��ʂ������i�̂��悻3����1�Y���Ă��܂��B
�ƋƂ��p���ŕ���E�l�ƂȂ�����₳��
����E�l�̉Ƃɐ��܂�A��w���ƌ�A�ƋƂ��p������₳��ł����A�����Z�p�͂��F�߂��A�����t�Ƃ��čb�h�̋����̕����Ɍg���悤�ɂȂ�܂����B
�����t�Ƃ́A�g�����ˁh�Ƃ�����`���H����g���ċ����̑����Ȃǂ��{���E�l�̂��Ƃł��B
�����t�Ƃ��ĕ��ݏo������₳��̓]�@�ƂȂ����̂��A�ӂ邳�ƎR���̍���A�|���Z�i���ĂȂ��̂�낢�j�̕����ł����B
�b�㌹���̑c�A���`���̐����l�₱�����A����𐧍삵�������t�̋Z�p���J��z�����Ȃ��畜�����Ă������Ƃɖ��͂��������Ƃ����܂��B
�u�����ɂƂ��čb�h�i�������イ�j�͎��ɑ����݂����Ȃ��́B�����̍ō��̋Z�p�����W���Đ��삳��Ă��܂��B����Ɍg���邱�Ƃ����͂��Ɗ����Ă��܂��v
140�l�Ԏ����l�N
2022/04/22(��) 06:16:58.61ID:uQZkWR+e ���ꂩ��10�N���܂�B
�����̋��������Ă����Z�p���]������A��₳��͎��S��̋����̕�����C����邱�ƂɂȂ�܂����B
�����́A�v��S��f�ނɂ����Ȃǂ��Ȃ�����A�\�ʂɖ͗l���k�ɒ��肠���A�b�h���₩�ɍʂ���̂ł��B
���̂��ߋ����Ȃǔh��ȐF�̂��̂������݂��܂����A���S��̋����͍��A����������h�����悤�Ȑ[�����������ł��B
��₳��ɂ��܂��ƁA�����͋����������F�ɂ���̂͋Z�p�I�ɓ�������Ƃ����܂��B
�����Ɏc���Ă��铺�ɋ���������u�ԓ��v�Ƃ����Z�@�ł́A�݂��������������\���ł��܂���ł����B
���̂��ߕ�₳��́A�����ǂ̂悤�ɂ��ďo�����̂��𓌋��|�p��w�ƌ����邱�Ƃɂ��܂����B
�����ŋ����̊ܗL�ʂ���ׂ鑕�u���g���ĕ��͂���ƁA���ɔ��ʂ̋₪�܂܂�Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B
���̕��͂���ɁA��₳��͎���������������n�߂܂����B
�����ł́u���������v�Ƃ����铖���̋Z�@��p���A1000�x�ȏ�ɉ��M������ڂŗn�����������������ɗ�������ĉ�ɂ��܂��B
��̓Y���ʂ�ς��Ȃ�������̐�����J��Ԃ��Ȃ��ŁA�����ꂷ����ƕ\�ʂɕ����o�Ă��܂��A�����Ȃ�Ȃ����Ƃ��킩��܂����B
���悻4�N�A���s������J��Ԃ������ʂ��ǂ蒅�����̂�2���̋�B
�ł����������S��60�x�̂����ŗn�����������ɂ���ƁA���������Ŏ����ɕω����邱�Ƃ����܂����B
2���̋���܂S�𗰉��̓��ɂ���
��₳��ɂ��܂��ƁA��ɓ���ċ����������ɂ���Z�@�͂���܂Ō������Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�����̋Z�@���𖾂�����₳��B
���悢�敜�����{�i�I�Ɏn�܂�܂����B
�E�l���{�����͗l�������˂��g���Ē����ɍČ��B
�u�����v�⋛�̗��������ǂ����u�ȂȂ��v�̖͗l�����Ă����܂��B
�d�グ�ɗ���������������ƁA1�ڂ̋���������܂����B
�u�ƍN�̎v������ӎ��A�b�h�̐���Ɍg����������̐E�l�̎v�������L���A���̎��Ă�Z�p�ƒm���������ĕ�������ɂ̂��݂����ł��v
�b�h�͓����̌��͎҂��ō��̋Z�p��ޗ��A�l�ނ��W�߂č�点�����̂ŁA���j���Ђ��Ƃ��M�d�Ȏ����ł��B
�������A���������������Đ킢�ɗՂލۂɐg�ɂ����_���Ȃ��̂ł��邽�߁A����܂Ŕ����قȂǂő�ɕۑ�����A�Ȋw�I�Ȓ����͂قƂ�Ǎs���Ă��܂���ł����B
����A�ƍN�̎��S��̋������Ȋw�I�ȃA�v���[�`�Œ������A�V���ȋZ�@���������ꂽ���ƂŁA�b�h�ⓖ���g���Ă����������i�̌������i�݁A�ƍN�����������������ɏڂ����m�邱�ƂɂȂ���̂ł͂Ȃ����ƁA���j�w�҂̕��R�D����͕]�����܂��B
�u����g���Z�@�����{�Ǝ��ɐ��ݏo���ꂽ���̂Ȃ̂��A�C�O�̋Z�p���A������čb�h�i�������イ�j�ɗp����ꂽ�̂��A�������L�܂�傫�ȃX�P�[�����������������ƍl���Ă��܂��B�����̍��ی��Ղ̍L�����b�h�������i�ނ��ƂɊ��҂������Ǝv���܂��v
�ƍN�̍b�h�̋����ɊC�O�̋Z�p���g��ꂽ�Ƃ���A�����̐V���Ȏ�����m��傫�Ȕ����ƌ����邩������܂���B
����̒��������������ɁA���̎���̌������i�ނ��ƂɊ��҂������Ǝv���܂��B
�����̋��������Ă����Z�p���]������A��₳��͎��S��̋����̕�����C����邱�ƂɂȂ�܂����B
�����́A�v��S��f�ނɂ����Ȃǂ��Ȃ�����A�\�ʂɖ͗l���k�ɒ��肠���A�b�h���₩�ɍʂ���̂ł��B
���̂��ߋ����Ȃǔh��ȐF�̂��̂������݂��܂����A���S��̋����͍��A����������h�����悤�Ȑ[�����������ł��B
��₳��ɂ��܂��ƁA�����͋����������F�ɂ���̂͋Z�p�I�ɓ�������Ƃ����܂��B
�����Ɏc���Ă��铺�ɋ���������u�ԓ��v�Ƃ����Z�@�ł́A�݂��������������\���ł��܂���ł����B
���̂��ߕ�₳��́A�����ǂ̂悤�ɂ��ďo�����̂��𓌋��|�p��w�ƌ����邱�Ƃɂ��܂����B
�����ŋ����̊ܗL�ʂ���ׂ鑕�u���g���ĕ��͂���ƁA���ɔ��ʂ̋₪�܂܂�Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B
���̕��͂���ɁA��₳��͎���������������n�߂܂����B
�����ł́u���������v�Ƃ����铖���̋Z�@��p���A1000�x�ȏ�ɉ��M������ڂŗn�����������������ɗ�������ĉ�ɂ��܂��B
��̓Y���ʂ�ς��Ȃ�������̐�����J��Ԃ��Ȃ��ŁA�����ꂷ����ƕ\�ʂɕ����o�Ă��܂��A�����Ȃ�Ȃ����Ƃ��킩��܂����B
���悻4�N�A���s������J��Ԃ������ʂ��ǂ蒅�����̂�2���̋�B
�ł����������S��60�x�̂����ŗn�����������ɂ���ƁA���������Ŏ����ɕω����邱�Ƃ����܂����B
2���̋���܂S�𗰉��̓��ɂ���
��₳��ɂ��܂��ƁA��ɓ���ċ����������ɂ���Z�@�͂���܂Ō������Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�����̋Z�@���𖾂�����₳��B
���悢�敜�����{�i�I�Ɏn�܂�܂����B
�E�l���{�����͗l�������˂��g���Ē����ɍČ��B
�u�����v�⋛�̗��������ǂ����u�ȂȂ��v�̖͗l�����Ă����܂��B
�d�グ�ɗ���������������ƁA1�ڂ̋���������܂����B
�u�ƍN�̎v������ӎ��A�b�h�̐���Ɍg����������̐E�l�̎v�������L���A���̎��Ă�Z�p�ƒm���������ĕ�������ɂ̂��݂����ł��v
�b�h�͓����̌��͎҂��ō��̋Z�p��ޗ��A�l�ނ��W�߂č�点�����̂ŁA���j���Ђ��Ƃ��M�d�Ȏ����ł��B
�������A���������������Đ킢�ɗՂލۂɐg�ɂ����_���Ȃ��̂ł��邽�߁A����܂Ŕ����قȂǂő�ɕۑ�����A�Ȋw�I�Ȓ����͂قƂ�Ǎs���Ă��܂���ł����B
����A�ƍN�̎��S��̋������Ȋw�I�ȃA�v���[�`�Œ������A�V���ȋZ�@���������ꂽ���ƂŁA�b�h�ⓖ���g���Ă����������i�̌������i�݁A�ƍN�����������������ɏڂ����m�邱�ƂɂȂ���̂ł͂Ȃ����ƁA���j�w�҂̕��R�D����͕]�����܂��B
�u����g���Z�@�����{�Ǝ��ɐ��ݏo���ꂽ���̂Ȃ̂��A�C�O�̋Z�p���A������čb�h�i�������イ�j�ɗp����ꂽ�̂��A�������L�܂�傫�ȃX�P�[�����������������ƍl���Ă��܂��B�����̍��ی��Ղ̍L�����b�h�������i�ނ��ƂɊ��҂������Ǝv���܂��v
�ƍN�̍b�h�̋����ɊC�O�̋Z�p���g��ꂽ�Ƃ���A�����̐V���Ȏ�����m��傫�Ȕ����ƌ����邩������܂���B
����̒��������������ɁA���̎���̌������i�ނ��ƂɊ��҂������Ǝv���܂��B
141�l�Ԏ����l�N
2022/04/22(��) 08:32:52.58ID:PcKV0DTx �Ȃ�Ō��_���C�O�ɂȂ��
�ޗǂ̊����_�Ђɂ��[�߂��������Ă���قNjM�d�ł��Ȃ�������
���̌セ�̋Z�p���p�ꂽ����
�ޗǂ̊����_�Ђɂ��[�߂��������Ă���قNjM�d�ł��Ȃ�������
���̌セ�̋Z�p���p�ꂽ����
142�l�Ԏ����l�N
2022/04/22(��) 10:31:05.46ID:0WRzKbEH ��q�݂̂ɓ`��������q���`���A�E�l�̋Z�\���ĕK���p����
143�l�Ԏ����l�N
2022/04/22(��) 11:56:50.04ID:PcKV0DTx ���ɐV�X���Ō@��N�������Ƃ����Â̒b���p���p��Ă�����
144�l�Ԏ����l�N
2022/04/22(��) 12:27:30.84ID:BLpusYEu �u��F���p�L�v���u�叫�S���̎��@���E�����F�鎖�v
�F���̑���E���Ë`�v���̉Ɛb�A�͓c��V�����x��(�������������ł����c�`�N�H)�͍����ȌR�@�҂ł���A�_�ϊ���̂��Ƃ����������B
���Ƃ��Η͍U�߂��Ă����Ƃ��Ȃ��悤�ȏ�s���A�F���ɂ��V������������Ƃŏċp����悤�Ȑ_�ς��������B
�܂��Ƃɔ�Ԓ��𗎂Ƃ��قǂ̊�����Ȃ��A���ꂪ�s���Ƃ���叟�Ȃ����Ƃ��Ȃ������B
����قǂɁA���Ë`�v���͓V���\�l�N(1586�N)�����̓~�A������L��ɔ������ׂ����^��肦�Ƌx���ɐ\���t�����B
�x���u�^�͂͂���܂ł������Ȃ���B
�L�㗼�叫�̐��́A���ꂪ�����m�̂��ƂȂ�A��F�@�َq���`���̐����Ղ�������ׂ���B
���̊�A����ɂȂ����낵�����v�Ɛ\���B
���ď@�ٌ��̐��͘\�����A�`���̐��͔j�R���ɓ������Ă������߁A�x���͗��������ꂼ��F�������Ƃ���A���R�Ƃ��Ċ�����������B
���̐����ł���A�^�̍b�͉��ƂȂ�A���Â������������Ƃ͂���܂��A�Ƌx���͊�x�̔����J�����B
����A�L��ɂ����Ă��Ö�G�z�O��(�p�G�Ώ@�Ǝv���邪���łɎ���̐킢�Ő펀���Ă���͂�)�Ƃ����R�@�҂������āA�@�ٌ����q�̐����������̂������
�z�O��u�����̂��Ƃ��͓G�̂��߂ɂȂ��Ƃ���̍Ђ����A�܂��͍����̑嗐���A��̂��Ƃɂ͂��炸�B�䂩�������́A�O���Ԃ���v
�Ǝv���A�@�ٌ��Ɍ���\�������䓯�S�Ȃ��A
�@�ٌ��u�^�͓V�ɂ���v�Ƃ����V�^�ɔC����Ƃ̌�ӂł������B
�E�q�H���u�Ղ邱�ƍ�(����)�����@�����A�_���Ղ邱�Ɛ_�݂����@�����B�v
�@�ٌ��̂����t�͂�낵���Ȃ��Ɛl�X�͌����������B
���Â̌R�t�������F�����āA��F�@�فE�`���e�q�̉^��]�����Ƃ����b
�F���̑���E���Ë`�v���̉Ɛb�A�͓c��V�����x��(�������������ł����c�`�N�H)�͍����ȌR�@�҂ł���A�_�ϊ���̂��Ƃ����������B
���Ƃ��Η͍U�߂��Ă����Ƃ��Ȃ��悤�ȏ�s���A�F���ɂ��V������������Ƃŏċp����悤�Ȑ_�ς��������B
�܂��Ƃɔ�Ԓ��𗎂Ƃ��قǂ̊�����Ȃ��A���ꂪ�s���Ƃ���叟�Ȃ����Ƃ��Ȃ������B
����قǂɁA���Ë`�v���͓V���\�l�N(1586�N)�����̓~�A������L��ɔ������ׂ����^��肦�Ƌx���ɐ\���t�����B
�x���u�^�͂͂���܂ł������Ȃ���B
�L�㗼�叫�̐��́A���ꂪ�����m�̂��ƂȂ�A��F�@�َq���`���̐����Ղ�������ׂ���B
���̊�A����ɂȂ����낵�����v�Ɛ\���B
���ď@�ٌ��̐��͘\�����A�`���̐��͔j�R���ɓ������Ă������߁A�x���͗��������ꂼ��F�������Ƃ���A���R�Ƃ��Ċ�����������B
���̐����ł���A�^�̍b�͉��ƂȂ�A���Â������������Ƃ͂���܂��A�Ƌx���͊�x�̔����J�����B
����A�L��ɂ����Ă��Ö�G�z�O��(�p�G�Ώ@�Ǝv���邪���łɎ���̐킢�Ő펀���Ă���͂�)�Ƃ����R�@�҂������āA�@�ٌ����q�̐����������̂������
�z�O��u�����̂��Ƃ��͓G�̂��߂ɂȂ��Ƃ���̍Ђ����A�܂��͍����̑嗐���A��̂��Ƃɂ͂��炸�B�䂩�������́A�O���Ԃ���v
�Ǝv���A�@�ٌ��Ɍ���\�������䓯�S�Ȃ��A
�@�ٌ��u�^�͓V�ɂ���v�Ƃ����V�^�ɔC����Ƃ̌�ӂł������B
�E�q�H���u�Ղ邱�ƍ�(����)�����@�����A�_���Ղ邱�Ɛ_�݂����@�����B�v
�@�ٌ��̂����t�͂�낵���Ȃ��Ɛl�X�͌����������B
���Â̌R�t�������F�����āA��F�@�فE�`���e�q�̉^��]�����Ƃ����b
145�l�Ԏ����l�N
2022/04/22(��) 14:26:21.25ID:yvMRKNQz https://digital.asahi.com/sp/articles/ASQ4M6D4YQ45UUHB00K.html
�I�����_�̓N�w�ґ����Ȃ��d���u�����Ƃ��k�v���Ɂ@400�N�̓�
>17���I�ɋ�B�ɕY�������I�����_�D�̑D���ɂ���������400�N�]����p���ł����Ȗ،�����s�̗��]�@�ŁA�n���̐l�����������Љ�鎑���ق��J�����B
>���͓������������قɊ������Ă���u�ؑ��G���X���X�����v�i���d�v�������j�����ǂ��Ă����A����ȉ^���̕�����L���m���Ă��炤�̂��_�����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-12894.html
�Ȗ̃G���X���X�ؑ�
�ł��Љ��Ă����A�E�B���A���E�A�_���Y(�O�Y�j)�̃��[�t�f���ɍڂ��Ă����G���X���X���̎����ق��ł����悤��
�L���ɂ͏����Ƃ��k�ɂ���Ă��܂������R(�����܂ň��)�ɂ��Ă��G��Ă���
�I�����_�̓N�w�ґ����Ȃ��d���u�����Ƃ��k�v���Ɂ@400�N�̓�
>17���I�ɋ�B�ɕY�������I�����_�D�̑D���ɂ���������400�N�]����p���ł����Ȗ،�����s�̗��]�@�ŁA�n���̐l�����������Љ�鎑���ق��J�����B
>���͓������������قɊ������Ă���u�ؑ��G���X���X�����v�i���d�v�������j�����ǂ��Ă����A����ȉ^���̕�����L���m���Ă��炤�̂��_�����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-12894.html
�Ȗ̃G���X���X�ؑ�
�ł��Љ��Ă����A�E�B���A���E�A�_���Y(�O�Y�j)�̃��[�t�f���ɍڂ��Ă����G���X���X���̎����ق��ł����悤��
�L���ɂ͏����Ƃ��k�ɂ���Ă��܂������R(�����܂ň��)�ɂ��Ă��G��Ă���
146�l�Ԏ����l�N
2022/04/23(�y) 21:51:27.66ID:5fJXLANX http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-6484.html
�V����N�A����N��(���Ԃ�����Ⴂ)��
��L�̘b�́u��F���p�L�v�ł͈���N��(����)�ÎE�̎��ɏo�Ă��邪�A�Í��̗�ɂ��Ă͏ȗ�����Ă���̂ł������܂߂ē��e
�u��F���p�L�v���
���a���̊���@���E��~�@��E���X��̕���
����N����(����)�̉ƖłтāA�V����N�b���ɖL�㍑�ɓn�C�Ȃ������B
��ق��o���Ȃ���Ƃ��ɁA�N���鑠�̓��ɉɌ�̂��߂ɖ�O����߂�A�n�̕ڂœ��̎��ŏグ�Ȃ�����
�u�A���������@�r�̓��g�@�S����@���N����́@�炭�ȓ����ȁv
�ƗV�ꂽ���Ɠn�C�Ȃ������B
���̂̂��A���@�䕔���e�����a�䎩���̓������悤�ƑO�q�̌䏊�ɗ������������A���̓��͈�[���炢�ĂȂ������B
�l�X���s�R�����Ă���ƁA吐�V�E�q��т̖���œ��g(吐�e���A���W)�Ƃ����l�����e�̂��ɂ�����
���g�u�N���͂��̓��ɖ��c��ɂ����
�u�A���������@�r�̓��g�@�S����@���N����́@�炭�ȓ����ȁv
�Ɖr�����Ȃ̂ŁA����������Ƃ��̂��߂ł͂Ȃ��ł��傤���v
�Ɛ\�����Ƃ���
���e�u���͂Ƃ������A���̖���ł��̂悤�Ȋ�����Ȃ��낤�v�Ɠ��ӂ��Ȃ������B
�V����N�A����N��(���Ԃ�����Ⴂ)��
��L�̘b�́u��F���p�L�v�ł͈���N��(����)�ÎE�̎��ɏo�Ă��邪�A�Í��̗�ɂ��Ă͏ȗ�����Ă���̂ł������܂߂ē��e
�u��F���p�L�v���
���a���̊���@���E��~�@��E���X��̕���
����N����(����)�̉ƖłтāA�V����N�b���ɖL�㍑�ɓn�C�Ȃ������B
��ق��o���Ȃ���Ƃ��ɁA�N���鑠�̓��ɉɌ�̂��߂ɖ�O����߂�A�n�̕ڂœ��̎��ŏグ�Ȃ�����
�u�A���������@�r�̓��g�@�S����@���N����́@�炭�ȓ����ȁv
�ƗV�ꂽ���Ɠn�C�Ȃ������B
���̂̂��A���@�䕔���e�����a�䎩���̓������悤�ƑO�q�̌䏊�ɗ������������A���̓��͈�[���炢�ĂȂ������B
�l�X���s�R�����Ă���ƁA吐�V�E�q��т̖���œ��g(吐�e���A���W)�Ƃ����l�����e�̂��ɂ�����
���g�u�N���͂��̓��ɖ��c��ɂ����
�u�A���������@�r�̓��g�@�S����@���N����́@�炭�ȓ����ȁv
�Ɖr�����Ȃ̂ŁA����������Ƃ��̂��߂ł͂Ȃ��ł��傤���v
�Ɛ\�����Ƃ���
���e�u���͂Ƃ������A���̖���ł��̂悤�Ȋ�����Ȃ��낤�v�Ɠ��ӂ��Ȃ������B
147�l�Ԏ����l�N
2022/04/23(�y) 21:53:24.81ID:5fJXLANX ���g�u����͂����ł����A���ɍ炭�Ԃ͖���ɂ��炭�͓̂����ł��B
�����t�͉ԍ炫�A�Ă͔ɂ�A�H�͎���A�~�͌͂��ł��傤�B
���̂悤�ɓV�n�̂��Ԃ��������o�邽�߁A�Ԃɂ͕���������Ƃ�����̂ł��B
���ׂĂ̂��͓̂V�������Ȃ��Ă���̂ł�����A���̓��ɂ��S�������āA�̂̐S��V���̐��Ɏ��̂ł��傤�B
���̐́A�V�_(�������^��)���}���ɍ��J���ꂽ���A��Ղ����Ĕ~�͔�сA���͖��c��ɂ���Ō͂ꂽ�Ƃ���
���������s�v�c����A����Ɏv��
�u�~�͔�с@���͌͂��@���̒��Ɂ@�ȂɂƂď��́@��Ȃ�����v
�Ɖr�܂ꂽ�Ƃ��돼����юQ���āA���̐��܂ł��u��~�v�u�ǂ����v�Ɩ����c���Ă��܂��B
�܂���웨�Y(������݂̂˂�)�Ƃ����l�́A�ʂ��Q���A�Ȃ�e�����̖ɑ���
�u�ӂ����́@��ӂɍ����@�S����@���̏t����@�n���߂ɍ炯�v
�Ɖr�Ƃ���A���ɐS�͂Ȃ��Ɛ��̐l�͌����܂����A���̂̈����m���Ėn���߂ɍ炢���Ə����Ă���܂��B
�����t�͉ԍ炫�A�Ă͔ɂ�A�H�͎���A�~�͌͂��ł��傤�B
���̂悤�ɓV�n�̂��Ԃ��������o�邽�߁A�Ԃɂ͕���������Ƃ�����̂ł��B
���ׂĂ̂��͓̂V�������Ȃ��Ă���̂ł�����A���̓��ɂ��S�������āA�̂̐S��V���̐��Ɏ��̂ł��傤�B
���̐́A�V�_(�������^��)���}���ɍ��J���ꂽ���A��Ղ����Ĕ~�͔�сA���͖��c��ɂ���Ō͂ꂽ�Ƃ���
���������s�v�c����A����Ɏv��
�u�~�͔�с@���͌͂��@���̒��Ɂ@�ȂɂƂď��́@��Ȃ�����v
�Ɖr�܂ꂽ�Ƃ��돼����юQ���āA���̐��܂ł��u��~�v�u�ǂ����v�Ɩ����c���Ă��܂��B
�܂���웨�Y(������݂̂˂�)�Ƃ����l�́A�ʂ��Q���A�Ȃ�e�����̖ɑ���
�u�ӂ����́@��ӂɍ����@�S����@���̏t����@�n���߂ɍ炯�v
�Ɖr�Ƃ���A���ɐS�͂Ȃ��Ɛ��̐l�͌����܂����A���̂̈����m���Ėn���߂ɍ炢���Ə����Ă���܂��B
148�l�Ԏ����l�N
2022/04/23(�y) 21:55:09.45ID:5fJXLANX �܂��ٍ��ł����̂悤�Ȃ��Ƃ�����܂��B
�c�^�E�c�c�E�c�L(�ȉ��u��\�l�F�v�Ɏ��߂��Ă���b�B酈�H�����ώE�����c�L�Ƃ͕ʐl)�Ƃ����O�Z�킪���܂����B
���̎���A���e�̈��������X��(�ԑh�F)�Ƃ������O�ɐ��Č`���������悤�Ƃ����Ƃ���A�͌͂�Ă��܂��܂����B
�O�l���u���ꂩ��͓C�Ɉ͂�Ō��悤�v�ƌ������Ƃ���h���Č��̐F�ɂȂ萷��ɍ炢���Ƃ������Ƃł��B
�܂��������Ƃ������Ƃ�����܂��B
�����@�t(�O���@�t)������ɍs�����A��ގ��̏��łĂ����ɂ�
�u�ᐼ�ɋ���Γ������ɒ����ׂ��B��A����Ȃ킿���������v�Ɩ��܂����B
�͂����Ă̂��ɏ��͂����܂����Ɍ����������߁A�����̒�q�͂�������Ďt�̋A�҂�m�����ƌ����܂��B
�N�����u���Ƃ�����́v�Ɖr�܂ꂽ�̂ŁA���t�͌��̂悤�ɍ炭�ł��傤�A�����Ȃ�Ή̂̊���Ɣ[�������ł��傤�v
�c�^�E�c�c�E�c�L(�ȉ��u��\�l�F�v�Ɏ��߂��Ă���b�B酈�H�����ώE�����c�L�Ƃ͕ʐl)�Ƃ����O�Z�킪���܂����B
���̎���A���e�̈��������X��(�ԑh�F)�Ƃ������O�ɐ��Č`���������悤�Ƃ����Ƃ���A�͌͂�Ă��܂��܂����B
�O�l���u���ꂩ��͓C�Ɉ͂�Ō��悤�v�ƌ������Ƃ���h���Č��̐F�ɂȂ萷��ɍ炢���Ƃ������Ƃł��B
�܂��������Ƃ������Ƃ�����܂��B
�����@�t(�O���@�t)������ɍs�����A��ގ��̏��łĂ����ɂ�
�u�ᐼ�ɋ���Γ������ɒ����ׂ��B��A����Ȃ킿���������v�Ɩ��܂����B
�͂����Ă̂��ɏ��͂����܂����Ɍ����������߁A�����̒�q�͂�������Ďt�̋A�҂�m�����ƌ����܂��B
�N�����u���Ƃ�����́v�Ɖr�܂ꂽ�̂ŁA���t�͌��̂悤�ɍ炭�ł��傤�A�����Ȃ�Ή̂̊���Ɣ[�������ł��傤�v
149�l�Ԏ����l�N
2022/04/23(�y) 22:00:10.93ID:5fJXLANX �Ƙa���̖��̊�����q�ׂ��Ƃ���A���e���ߏK�������Ƃ����Ƃ͎v�������̂́A���t�炭�܂ł͏����ł����˂�A�ƌ����������B
���N�̏t�A��N���܂��Ԃ�A���͎O�ڂقǂɍ炢������
�l�X�́u���g�����N���������Ƃ͓����������B���g�̗\���ʂ�̊�����v�Ɗ��S�����B
���e�����܂��āA���̊����F�߂��B
���̂̂��A���̊���}�G�g�����������߂��A���̓���������点�āA���s�ɂ����Ĉ��a(������H����̑��q�̓����̌���������s���Ă���)�ɐi��Ȃ��������߁A��ϑ厖�ɂ��ꂽ�B
����Ƃ��t�������Ƃ���A�V�q�����̓����䗗�ɂ��ꂽ�������B
����Α��������̂悤�ɐU�镑���̂ɁA���㑊�`�̐b���������ɐ�܂������Ƃ������Ƃ����̂��A�N�����̌��Ɉ���̉Ǝ��œ����̎��߂������Ƃ������Ƃ��낤�B
���N�̏t�A��N���܂��Ԃ�A���͎O�ڂقǂɍ炢������
�l�X�́u���g�����N���������Ƃ͓����������B���g�̗\���ʂ�̊�����v�Ɗ��S�����B
���e�����܂��āA���̊����F�߂��B
���̂̂��A���̊���}�G�g�����������߂��A���̓���������点�āA���s�ɂ����Ĉ��a(������H����̑��q�̓����̌���������s���Ă���)�ɐi��Ȃ��������߁A��ϑ厖�ɂ��ꂽ�B
����Ƃ��t�������Ƃ���A�V�q�����̓����䗗�ɂ��ꂽ�������B
����Α��������̂悤�ɐU�镑���̂ɁA���㑊�`�̐b���������ɐ�܂������Ƃ������Ƃ����̂��A�N�����̌��Ɉ���̉Ǝ��œ����̎��߂������Ƃ������Ƃ��낤�B
150�l�Ԏ����l�N
2022/04/24(��) 19:18:43.37ID:oi+Wmvg6 �c����\�N�i1615�j�܌������A��䏊�i����ƍN�j�͒��P�R���l�A�ܒ��Ƃ������܂Ŏ��������A
����{�ۂ̕ӂ肩�牌������������B
���x���̍��A���o�����O������䏊�̂��Ƃɒy�������B
��䏊�͑����Ɂu���̉�������v�Ƌ��ɂȂ����B
����ɎO�������ĞH��
�u�ߍ��Ύ~�Ȃ鎖�Ɍ����i�ŋ߂ɂȂ��C�̓łȂ��Ƃł��j�v
�Ɛ\���グ���B�Q�b�����́u����̎����ȁv�Ƃ����₫���������A�ƍN���͋���ꂽ
�u���͏G���ɋؖڂ�����̂�����A�ނ��̈ꌾ�ł���B�v
�����āA����Ɏv��������C�F�ɂ����������B
���̗l�q�ɁA��㗎��̉x�т�\���x�ꂶ�ƁA�����ɎQ��W�܂����l�X�̒��ł��A�L�b�Ƃ̌䉶�������y�́A
���ɒp�����������ƂɎv�����Ƃ����B
���̌����䏊�́A�h�V�̎҂Ɍ������āu����炪�\�������A�_���̎���ł���B�v�ƁA
�䊴�ł��炴��l�q�ł������B
����{�ɁA���o�����̕��G���́A���B�����̐l�ł���A�G�g���Ɠ����n�ɐ��܂ꂽ���߁A
�c������葊�e�����A���̌�G�g���Ɏd���ĕ���̘J��ς݁A���ɐ�B�ݘa�c����������Ƃ����B
�܂�����{�ɁA�V�䔒�ΐ搶�H���A���o�d����i�G���j�͑吭���̖��i�h���@�j���Ȃɂ����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
����{�ۂ̕ӂ肩�牌������������B
���x���̍��A���o�����O������䏊�̂��Ƃɒy�������B
��䏊�͑����Ɂu���̉�������v�Ƌ��ɂȂ����B
����ɎO�������ĞH��
�u�ߍ��Ύ~�Ȃ鎖�Ɍ����i�ŋ߂ɂȂ��C�̓łȂ��Ƃł��j�v
�Ɛ\���グ���B�Q�b�����́u����̎����ȁv�Ƃ����₫���������A�ƍN���͋���ꂽ
�u���͏G���ɋؖڂ�����̂�����A�ނ��̈ꌾ�ł���B�v
�����āA����Ɏv��������C�F�ɂ����������B
���̗l�q�ɁA��㗎��̉x�т�\���x�ꂶ�ƁA�����ɎQ��W�܂����l�X�̒��ł��A�L�b�Ƃ̌䉶�������y�́A
���ɒp�����������ƂɎv�����Ƃ����B
���̌����䏊�́A�h�V�̎҂Ɍ������āu����炪�\�������A�_���̎���ł���B�v�ƁA
�䊴�ł��炴��l�q�ł������B
����{�ɁA���o�����̕��G���́A���B�����̐l�ł���A�G�g���Ɠ����n�ɐ��܂ꂽ���߁A
�c������葊�e�����A���̌�G�g���Ɏd���ĕ���̘J��ς݁A���ɐ�B�ݘa�c����������Ƃ����B
�܂�����{�ɁA�V�䔒�ΐ搶�H���A���o�d����i�G���j�͑吭���̖��i�h���@�j���Ȃɂ����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
151�l�Ԏ����l�N
2022/04/24(��) 19:53:20.62ID:VIZvEaiS �Ύ~�͌���̈Ӗ��ő������Ⴄ�Ɗ낤���ȃz���gw
152�l�Ԏ����l�N
2022/04/25(��) 19:25:46.07ID:X2x17hql �ŁA����ł͏Ď�������
153�l�Ԏ����l�N
2022/04/25(��) 19:55:46.78ID:IAJmmHLZ �܂��
154�l�Ԏ����l�N
2022/04/26(��) 05:46:42.54ID:kDwMC3+v �����悩����
155�l�Ԏ����l�N
2022/04/26(��) 12:06:05.83ID:hib2q/pm156�l�Ԏ����l�N
2022/04/26(��) 19:47:04.65ID:eBmPl9pu �����Ƃ����w�҂ł��Ύ~�̑��������������l���܂��ɂ��邩��Ȃ�
157�l�Ԏ����l�N
2022/04/26(��) 20:21:48.09ID:xmJK+njz �T�����F���́u�V�������ڂ̊փ����̍���͂Ȃ������vp113
�Ő��Ώ��[�͉ƍN�̃u���[���ł͂Ȃ������̗F�l�̗���ŏ���𑗂����Ƃ���
���̍����̈�ɁA����̖`���Ō��g���h������鎖�Ԃ��u�Ύ~�v�Ə����Ă��邱�Ƃ������Ă���
�u���g�̔h�����u�Ύ~�v�ƕ̂ގ莆���A���g���g���g�����ƍl����͖̂���������B�v
�Ə����Ă�����
�Ő��Ώ��[�͉ƍN�̃u���[���ł͂Ȃ������̗F�l�̗���ŏ���𑗂����Ƃ���
���̍����̈�ɁA����̖`���Ō��g���h������鎖�Ԃ��u�Ύ~�v�Ə����Ă��邱�Ƃ������Ă���
�u���g�̔h�����u�Ύ~�v�ƕ̂ގ莆���A���g���g���g�����ƍl����͖̂���������B�v
�Ə����Ă�����
158�l�Ԏ����l�N
2022/04/27(��) 22:36:49.46ID:2M22ybcL �̂ނ����A���ÉƂ̓��傪�\�ܑ�M�v�̍��̘b�B
�M�v�̌��Ɏd�����l�̎�҂������B
�Ƃ��閺�����̎�҂ɗ��������B
���鎞�A��҂���ő��������Ƃ̒m�点
�����̂Ƃ���ɓ͂����B
���������́A������������}���Ŏ�҂Ƃ����
���������B
�������A�ǂ�ǂ������ꂠ����͈Â��Ȃ�܂��Ō��������������A���ɉ��������Ȃ���
�薺�͈�����i�ނ��Ƃ��o���Ȃ��Ȃ����B
���̎��A���͋F��������Ɖ_����������������������𗊂�ɖ��͖����Ɏ�҂̏��ɒH�蒅�����Ƃ��ł��܂����B
����A���̘b�������M�v�͖����F�����ꏊ���u�������v�Ɩ��t���܂����B
�����������u�s�̒n���u�������v�̗R���̘b�B
�i����{�V���ɍڂ��Ă����b�j
���Ȃ݂Ɂu�������v�o�X��܂œV���ق���P���Ԃقǂ����邻���ł��B
�M�v�̌��Ɏd�����l�̎�҂������B
�Ƃ��閺�����̎�҂ɗ��������B
���鎞�A��҂���ő��������Ƃ̒m�点
�����̂Ƃ���ɓ͂����B
���������́A������������}���Ŏ�҂Ƃ����
���������B
�������A�ǂ�ǂ������ꂠ����͈Â��Ȃ�܂��Ō��������������A���ɉ��������Ȃ���
�薺�͈�����i�ނ��Ƃ��o���Ȃ��Ȃ����B
���̎��A���͋F��������Ɖ_����������������������𗊂�ɖ��͖����Ɏ�҂̏��ɒH�蒅�����Ƃ��ł��܂����B
����A���̘b�������M�v�͖����F�����ꏊ���u�������v�Ɩ��t���܂����B
�����������u�s�̒n���u�������v�̗R���̘b�B
�i����{�V���ɍڂ��Ă����b�j
���Ȃ݂Ɂu�������v�o�X��܂œV���ق���P���Ԃقǂ����邻���ł��B
159�l�Ԏ����l�N
2022/04/28(��) 11:10:25.26ID:ZqnN/qCm �ŁA���̓�l�͌��ꂽ�̂��낤���E�E
160�l�Ԏ����l�N
2022/04/28(��) 15:35:02.06ID:HeXbkUKV �c����\�N�i1615�j�܌������A���Ă̐w�A���엊�鋨�͑�䏊�i����ƍN�j�̌��Ɍ���������
�p��ɏ��R��i�߂Ă������A�A�̊����𗽂����ˁA�n���萅�����ꂽ���A�O�Y�����M���̕t���l�ł���
���ؐ����q�Ƃ����҂��A�n���ۂɂĐ�������ō����o���ƍ������B
��䏊�Ɍ�Ζʂ����ƁA��䏊�͗��鋨�̔��ł��
�u�����͂��̕����Ɏ�����O�����鎖���o���Ȃ������B�c�O�ł���B�v�Ƌ��ɂȂ����B
���鋨������
�u���������Ȃ������̂ɁA�F�������ɍ����ڂ��A��ɗՂ߂Ȃ��������ƁA���O���ɂł��B�v
�Ɛ\���ꂽ�B
������������E�q�呾�v�i���j�j���A
�u�����A��ɍ��킷���Ƃ��o���Ȃ������Ƃ��Ă��A���N�Ȃ̂ł�����A������x������ɑ����ł��傤�B�v
�ƈԂ߂��̂����A���鋨��
�u�����\�l�̂��̎��́A�Ăт͖����̂��I�i�\���\�l�̎���������ׂ����j�v
�ƁA�p��ɗ��܂����āA�{�苋������Ƃ���B
�i�V���Ӂj
�p��ɏ��R��i�߂Ă������A�A�̊����𗽂����ˁA�n���萅�����ꂽ���A�O�Y�����M���̕t���l�ł���
���ؐ����q�Ƃ����҂��A�n���ۂɂĐ�������ō����o���ƍ������B
��䏊�Ɍ�Ζʂ����ƁA��䏊�͗��鋨�̔��ł��
�u�����͂��̕����Ɏ�����O�����鎖���o���Ȃ������B�c�O�ł���B�v�Ƌ��ɂȂ����B
���鋨������
�u���������Ȃ������̂ɁA�F�������ɍ����ڂ��A��ɗՂ߂Ȃ��������ƁA���O���ɂł��B�v
�Ɛ\���ꂽ�B
������������E�q�呾�v�i���j�j���A
�u�����A��ɍ��킷���Ƃ��o���Ȃ������Ƃ��Ă��A���N�Ȃ̂ł�����A������x������ɑ����ł��傤�B�v
�ƈԂ߂��̂����A���鋨��
�u�����\�l�̂��̎��́A�Ăт͖����̂��I�i�\���\�l�̎���������ׂ����j�v
�ƁA�p��ɗ��܂����āA�{�苋������Ƃ���B
�i�V���Ӂj
161�l�Ԏ����l�N
2022/04/28(��) 15:51:14.83ID:9a1G/Nyl http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-709.html
���엊��̏��w�E�����b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-3364.html
���엊��u��[��I��[��I�v
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-9708.html
�x���Ƃ���́A��ӂƂ�������炸
�����悤�Șb�͂���������������
���엊��̏��w�E�����b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-3364.html
���엊��u��[��I��[��I�v
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-9708.html
�x���Ƃ���́A��ӂƂ�������炸
�����悤�Șb�͂���������������
162�l�Ԏ����l�N
2022/04/29(��) 17:58:46.21ID:EA4ErCyW ����{�ɁA�c����\�N�i1615�j�܌��\���̎��ł��������A�a����̏������A�����q��Ƃ����ҁA
�e�̊����ɓ�����Ƃ��āA�ߗׂ̉W�œ����W�ߒ������A�l���R�̕�������Ă������A
�N���\�Η]��̕��m�A�ނ͒����݂̏�ɛ�q�A��тɌR�H�D�𒅂��A�������ɂĒ����q��̂��Ƃɗ��āB�A
�P��E����
�u�䖳�S�Ȃ���A���̊��Ă����炭�����ɒu���Ē��������B�v
�Ƃ̌��t���I���ʂ����ɁA���ԂɎ����������Ă����ɓ�������ė����������B
�����q��͐l���o���Ĕނ�ǂ����������A�u��m�Ȃł������̂ɁA�ނ�݂ɗa����悤�Ȃ��Ƃ�
���Ȃ�܂���B���X�Ɏ����A���Ă��������I�v�Ɠ`���悤�Ƃ����̂ł��邪�A���̕��m�ƒ��Ԃ͋��ɁA
�������s�����m�ꂸ�A���킵���҂����A�����B
���̏�ɏW�܂苏���ҒB�͌��X�ɁA�u����͒�߂đ��̗��l�ł��낤�B�H���ɂē����Ɉ����Ă�
��V����̂ɁA���̉ו��������ɒu���A�g���y�����ē�����Ǝv���A���̂悤�ɂ����̂��낤�B
�����͂��Ȃ��̌�e���̊����Ȃ�A���_�����Ȃ��ɁA����^���������̂ł͂Ȃ����낤���B�v
���̂悤�ɐ\�������A�����q��͔����Ђ���
�u���₢��A����͎��ɂ��ׂ��B�����Ă�����̂��E���̂����A�S����l�͑P���Ƃ��Ȃ��B
������A�l���a�������̂Ɏ���o���ȂǗL��ׂ����ł͂Ȃ��B���Ƃ���l�͎E���ꂽ�̂��Ƃ��Ă��A
���̐l�̕����Ƃ���͔@���ł��낤���B�v
���������āA���l�O�A�l�l�������A��A�҈��r�J�i�������j���āA�ړ��Ă��Ȃ����{�̕���
�q�ˍs�������A�ꗢ������i���ꏊ�ɂ���A��̉A�ɂ�����a�̒[�ɁA�őO�̕��m���A
�������Ɏ菝���āA����ł����B
���߂ċ��ɂ��������ԂɂȂ�Ƃ��A�q�ˈ����Ǝv���Ă������A�Ȃ̏�ɁA�N�̂قǏ\���A���ƌ�����w�l�A
����̛�q�ɁA�����ɏH�̖��`�������̂������d�ˁA���܂�Č\������̎q������ē|��Ă����B
�ޏ��͍A����˂���A��ɐ��܂��Ď���ł����B���̖T��ɁA�����j��ꂽ����ł��̂Ă��Ă����B
�ޏ��̕����Ă���Ԏq�̐����͔@�����ƉM�������A������A�Q���Ď��̂��낤���A�������Ă��炸�A
�����ׂ����Ƃ����������B
�����q��́A������\�������̎R��ɒm���Ă���m���݂����̂ŁA�}���g�����ȂĂ��̎��m�点�A
�ނ�𑒂点���B
���āA�����q��͂��ꂩ���N�قǂ��߂�����ɁA���̊��Ă̊W���J�����B
���̒��ɂ͕w�l�̈ߕ��A��тɐ��@�̘e�����ꍘ�A���̑��A�|���������������B����́A���悢�悱��́A
���̏�Ŏ���ł��������̉ו��ɑ��ᖳ���ƍl���A���̈ߕ����甦���d���āA���ȂǁA�Ƃ��̑m�̈����֊�t���A
���̘e�����͉Ƃ̏d��Ƃ����B
�����q��̉Ƃ͂�����܂��܂��x�݉h���A��X�L���ɂĕ�炵���B
�܂��A���m�̍����Ă����召�́A��������m������A����ɂ���ĒǑP�̉c�݂��ł�����ɂ����Ƃ����B
���̘b�́A�Ð썶�߁i�ߎ��j�̎��ł͂Ȃ����ƍl�����A����Ă����ɋL���B
�i�V���Ӂj
�e�̊����ɓ�����Ƃ��āA�ߗׂ̉W�œ����W�ߒ������A�l���R�̕�������Ă������A
�N���\�Η]��̕��m�A�ނ͒����݂̏�ɛ�q�A��тɌR�H�D�𒅂��A�������ɂĒ����q��̂��Ƃɗ��āB�A
�P��E����
�u�䖳�S�Ȃ���A���̊��Ă����炭�����ɒu���Ē��������B�v
�Ƃ̌��t���I���ʂ����ɁA���ԂɎ����������Ă����ɓ�������ė����������B
�����q��͐l���o���Ĕނ�ǂ����������A�u��m�Ȃł������̂ɁA�ނ�݂ɗa����悤�Ȃ��Ƃ�
���Ȃ�܂���B���X�Ɏ����A���Ă��������I�v�Ɠ`���悤�Ƃ����̂ł��邪�A���̕��m�ƒ��Ԃ͋��ɁA
�������s�����m�ꂸ�A���킵���҂����A�����B
���̏�ɏW�܂苏���ҒB�͌��X�ɁA�u����͒�߂đ��̗��l�ł��낤�B�H���ɂē����Ɉ����Ă�
��V����̂ɁA���̉ו��������ɒu���A�g���y�����ē�����Ǝv���A���̂悤�ɂ����̂��낤�B
�����͂��Ȃ��̌�e���̊����Ȃ�A���_�����Ȃ��ɁA����^���������̂ł͂Ȃ����낤���B�v
���̂悤�ɐ\�������A�����q��͔����Ђ���
�u���₢��A����͎��ɂ��ׂ��B�����Ă�����̂��E���̂����A�S����l�͑P���Ƃ��Ȃ��B
������A�l���a�������̂Ɏ���o���ȂǗL��ׂ����ł͂Ȃ��B���Ƃ���l�͎E���ꂽ�̂��Ƃ��Ă��A
���̐l�̕����Ƃ���͔@���ł��낤���B�v
���������āA���l�O�A�l�l�������A��A�҈��r�J�i�������j���āA�ړ��Ă��Ȃ����{�̕���
�q�ˍs�������A�ꗢ������i���ꏊ�ɂ���A��̉A�ɂ�����a�̒[�ɁA�őO�̕��m���A
�������Ɏ菝���āA����ł����B
���߂ċ��ɂ��������ԂɂȂ�Ƃ��A�q�ˈ����Ǝv���Ă������A�Ȃ̏�ɁA�N�̂قǏ\���A���ƌ�����w�l�A
����̛�q�ɁA�����ɏH�̖��`�������̂������d�ˁA���܂�Č\������̎q������ē|��Ă����B
�ޏ��͍A����˂���A��ɐ��܂��Ď���ł����B���̖T��ɁA�����j��ꂽ����ł��̂Ă��Ă����B
�ޏ��̕����Ă���Ԏq�̐����͔@�����ƉM�������A������A�Q���Ď��̂��낤���A�������Ă��炸�A
�����ׂ����Ƃ����������B
�����q��́A������\�������̎R��ɒm���Ă���m���݂����̂ŁA�}���g�����ȂĂ��̎��m�点�A
�ނ�𑒂点���B
���āA�����q��͂��ꂩ���N�قǂ��߂�����ɁA���̊��Ă̊W���J�����B
���̒��ɂ͕w�l�̈ߕ��A��тɐ��@�̘e�����ꍘ�A���̑��A�|���������������B����́A���悢�悱��́A
���̏�Ŏ���ł��������̉ו��ɑ��ᖳ���ƍl���A���̈ߕ����甦���d���āA���ȂǁA�Ƃ��̑m�̈����֊�t���A
���̘e�����͉Ƃ̏d��Ƃ����B
�����q��̉Ƃ͂�����܂��܂��x�݉h���A��X�L���ɂĕ�炵���B
�܂��A���m�̍����Ă����召�́A��������m������A����ɂ���ĒǑP�̉c�݂��ł�����ɂ����Ƃ����B
���̘b�́A�Ð썶�߁i�ߎ��j�̎��ł͂Ȃ����ƍl�����A����Ă����ɋL���B
�i�V���Ӂj
163�l�Ԏ����l�N
2022/04/30(�y) 16:26:03.18ID:SqHdkmEL �e�n�̐퍑�֘A�̂��Ղ肪�悤�₭3�N�Ԃ�ɓ�������܂����A�݂Ȃ���̂Ƃ���͂������ł��傤���H
�����G�`�P�b�g�ɋC��z���đ傢�Ɋό��i�ƈ��H�j���y���݂������̂ł��B
�����V�� 29������đ�㐙�܂�3�N�Ԃ�J�Á@5��3���Ƀ��C���̐쒆������
2022�N4��23��
https://www.asahi.com/articles/ASQ4Q72HDQ4QUZHB008.html
�R�`���đ�s�̏t�̕������u�đ�㐙�܂�v�ɂ��āA��Â���đ�l�G�̂܂�ψ���i�=���쏟�s���j��22���A
29��~5��3����3�N�Ԃ�ɊJ�Â���Ɣ��\�����B�R���i�Ђň��N�A��N�͒��~�������B�o���҂͗�N��菭�Ȃ��Ȃ�B
�đ�s�㐙������
���ʓW�u�퍑���s�Ə㐙�Ɓv
https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/124kyouto.html
��@���F�O�� �S��16���i�y�j~�T��15���i���j
�@�@�@�@��� �T��21���i�y�j~�U��19���i���j
���u�܌Ցށv���������R���{���͌�����
�����G�`�P�b�g�ɋC��z���đ傢�Ɋό��i�ƈ��H�j���y���݂������̂ł��B
�����V�� 29������đ�㐙�܂�3�N�Ԃ�J�Á@5��3���Ƀ��C���̐쒆������
2022�N4��23��
https://www.asahi.com/articles/ASQ4Q72HDQ4QUZHB008.html
�R�`���đ�s�̏t�̕������u�đ�㐙�܂�v�ɂ��āA��Â���đ�l�G�̂܂�ψ���i�=���쏟�s���j��22���A
29��~5��3����3�N�Ԃ�ɊJ�Â���Ɣ��\�����B�R���i�Ђň��N�A��N�͒��~�������B�o���҂͗�N��菭�Ȃ��Ȃ�B
�đ�s�㐙������
���ʓW�u�퍑���s�Ə㐙�Ɓv
https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/124kyouto.html
��@���F�O�� �S��16���i�y�j~�T��15���i���j
�@�@�@�@��� �T��21���i�y�j~�U��19���i���j
���u�܌Ցށv���������R���{���͌�����
164�l�Ԏ����l�N
2022/04/30(�y) 17:13:12.13ID:BtnZy3Uu >>163
�����g�傳����ȃS�~�J�X
�����g�傳����ȃS�~�J�X
165�l�Ԏ����l�N
2022/05/03(��) 09:46:10.21ID:rJTBUjzh �u�F�ˋ��`�W�v�u�F�B���`�W�v���փ����̓��Ñނ����Ŋ������@�앺�q(�ܑ�@�@��)�̘b
�E�]�˂ʼnΎ������������A�F���̏O���吨�Ώ����̂��߂ɓ������B
�݂Ȃ��Ύ��̕����ɂ܂���č�Ƃ��Ă���̂��������@�앺�q��
�u���̂��́A�����͕����ł���B���̘e�ʼn��������v�ƌ�����
�݂Ȃ́u��C�Ȃ��Ƃ�������߁A�����Ώ�����ɂȂ�A�Ă����ˁA�Ă����ˁI�v�ƌ����Ȃ���������B
���������A�N�����䂵�����̂͂Ȃ�������
�앺�q���������Ƃɂ́u����ȉΎ��ňꖽ���̂Ă����Ă͂Ȃ�ʂƎv���Ă����\�������A�t���ʂł������B
�����ƌ��t�ɋC������ׂ��ł������v
���鎞�A�앺�q�����l�ɗ��O�����������ߒ����Ŏa��E�����B
����l���u���l���E���̂ɒ�����Ȃǎg���Ƃ͑�U���ȁA�����g���������̂��v
�ƌ������Ƃ���A
�앺�q�u�����g���Ė����������Ă͂Ȃ�܂��璷������g���܂����B
���ł͂������ɉ��l��ɒ�������ѓ���Ȃǂ͗p���܂����v�ƌ������B
���鎞�A�Ƃɗ����Ă��Ă���҂����āA�앺�q�ɕߔ���������ꂽ�B
�앺�q��]�݂͂ȋ�𒅗p�����������ĕߔ������B
�l�X�u�Z�Ȃǒ���Ƃ͉��a�҂��v�Ɣ�����
�앺�q�u���̂悤�ȗ��ĘU������x�ŁA���ꂵ�����ĉ�������Ă͂����܂���ȁv�Ɠ������B
�E�]�˂ʼnΎ������������A�F���̏O���吨�Ώ����̂��߂ɓ������B
�݂Ȃ��Ύ��̕����ɂ܂���č�Ƃ��Ă���̂��������@�앺�q��
�u���̂��́A�����͕����ł���B���̘e�ʼn��������v�ƌ�����
�݂Ȃ́u��C�Ȃ��Ƃ�������߁A�����Ώ�����ɂȂ�A�Ă����ˁA�Ă����ˁI�v�ƌ����Ȃ���������B
���������A�N�����䂵�����̂͂Ȃ�������
�앺�q���������Ƃɂ́u����ȉΎ��ňꖽ���̂Ă����Ă͂Ȃ�ʂƎv���Ă����\�������A�t���ʂł������B
�����ƌ��t�ɋC������ׂ��ł������v
���鎞�A�앺�q�����l�ɗ��O�����������ߒ����Ŏa��E�����B
����l���u���l���E���̂ɒ�����Ȃǎg���Ƃ͑�U���ȁA�����g���������̂��v
�ƌ������Ƃ���A
�앺�q�u�����g���Ė����������Ă͂Ȃ�܂��璷������g���܂����B
���ł͂������ɉ��l��ɒ�������ѓ���Ȃǂ͗p���܂����v�ƌ������B
���鎞�A�Ƃɗ����Ă��Ă���҂����āA�앺�q�ɕߔ���������ꂽ�B
�앺�q��]�݂͂ȋ�𒅗p�����������ĕߔ������B
�l�X�u�Z�Ȃǒ���Ƃ͉��a�҂��v�Ɣ�����
�앺�q�u���̂悤�ȗ��ĘU������x�ŁA���ꂵ�����ĉ�������Ă͂����܂���ȁv�Ɠ������B
166�l�Ԏ����l�N
2022/05/03(��) 09:49:10.13ID:rJTBUjzh �ܑ�@�@�ɂ���Ȃ������A
���@�@�d��
���@�@�d��
167�l�Ԏ����l�N
2022/05/03(��) 11:40:15.49ID:y3cn3XZq �O�͖����@�x�X��
https://dotup.org/uploda/dotup.org2791689.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org2791689.jpg
168�l�Ԏ����l�N
2022/05/04(��) 17:34:58.60ID:Rtv2PDY4 �c����\�N�܌��\����A���͐ےÎ璉�[�͖������āA�a�ɓ����đ��̎c�}��{�������B
���ؒ}��琳���A�R�c�\���v�d�����Ďg�Ƃ��āA�a�B�̏����ł���K�R�A�ʏ��A���q���������ɒT�����B
���̏镺�ł������R��ѓ����M�A�k�쎡�Y���q�鏟�́A�����̑�{�V�ɔE��ł������A
���\����A���̎R�ɗ��l���B��Ă���Ƃ��������������������߁A�H���A�n��ג��ɖ����Đq�ˑ{�������B
���̎��A�R�{�A�k���̗��l�́A��{�V�̖@��ɐ\����
�u��F�c���L�����ꍇ�A����Ɍ����邱�Ƃ��o���Ȃ��ł��傤�B�Ȃ̂ʼn�痼�l�͔��o�ŁA�ؕ��d��܂��B�v
����ɑ��Ė@���
�u�������{����̂��q�˂��݂�A�w��h�͒v�����܂������A���̌�͉����֎Q�����̂������܂���B�x��
�\���グ�܂��B���̏�ł̂��v�炢����ɂ��ׂ��ł���A�Ԃ��Ԃ������l�Ƃ��A�ؕ��̂��Ƃ͎v���~�܂��ĉ������B�v
�����\�������߁A�R��A�k���͂����ɒ��d�����B����������ɂ���Ė��{���͑�{�V��߂��A
�q�ɉ��i���d�j�̌��ɏ����Ă߂�ꂽ
����{�ɁA���\�����A�R��ѓ��A�k�쎡�Y���q�͖{�\���֗��āA
�u��痼�l�͑��̗��l�ł���A��ɑ�{�V�̏��ɉB�ꋏ���̂����A���̑m�����s�ɐ����߂�ꂽ�Ə������B
��킭�Ή�痼�l�����Y�ɑ����A��{�V�͖̎Ƃ�����I�v
���̂悤�Ɍ����A���̎|�͖{�\����苞�s���i��֑i����ꂽ�B
���̎��A�{������i�����j����䏊�i����ƍN�j�ɑ��A�u�i���o�Ă������l���A�����ւ������a����
�ׂ��ł��傤���v�ƉM�������A����
�u�`��m���ďo�Ă����҂ɁA������������B�v
�ƁA���̂܂ܖ{�\���ɍ����u���ꂽ�B
���̌�A��䏊�́u���l�̎ҋ��́A���ɂėǂ�����ۂ݂������낤����A���ŏo����鎿�̈������ɂ�
���f����ł��낤�B���̒�����点��B�v�Ƌ����A��Â��琳�����킳�ꂽ�B�����͂��̒���
��g�̉��^�ɓn���A���^�͎����Ă��̎��֍s���āA�R��A�k��̗��l��
�u�����ɐؕ������t�����邾�낤�B���̐S������ׂ��B�v�ƁA��ӂ̎�������n�������A
���̌�A���̗l�q�A���тɍ��喼�A��g���g�Ɋ�炸�A�S��ʂ����҂͖����������Ɛq�˂����A���l��
�u���ꂪ���͊O�l�Ҍ́A���������܂���B�v
�Ɠ������B
���̂��ߎg���̎҂́A�u���l�ɐ\���グ�����������A��l�ɂ��̂悤�ȕԓ��͔��Ȃ�Ȃ��B
�ꃖ���ł����Ă��\���グ����ׂ��B�v�ƌ��������A���l�͏d�˂�
�u����Ǒ����ʂ��Ƃ́A�\����܂���B�v�ƌ������B
��g�͖��������u���l�̎������ꂪ�����\���悤�Ɏ��萬���̂ŁA���̌����ʂ�\���グ����B�v
����ɎR��ѓ��͗������āu�L�b�ƖŖS�̏�́A������肽�����͂��ꖳ���I�R����A
�l�����܂ʂ��Ƃ���莝��������l�A���͂��̕��𗊂ސl����莝���Ă�낤�I�v
���������ėl�X�Ɉ����������߁A��g���傢�ɓ{��A�u������̒ʂ�����シ�ׂ��I�v�Ɛ\���A
�����Ԃ��đ�䏊�ֈ�X�ɐ\���グ�A�U�X�Ɉ����������B
�Ƃ��낪�ƍN���͕����ʌ��ɂāA
�u�ނ痼�l�́A���ɉ����ėE�҂ƌĂꂽ�ҒB���B��x�m��ʂƐ\���o���̂��A�d�˂Ė₤���Ƃ����邩�I�v
�ƁA�g���̎҂�������������B
���̗��l�ɂ͐ؕ������t������ׂ��Ƃ̌䍹���ł������̂����A�@���Ȃ鎖���A�����O���A�Ҍ�̎���
��͖Ƃ����āA���l���ɋ��s�ɏZ���A���N�A��䏊���I�������ƁA���N�����A���s�̘Q�l���̂��߁A
�R��ѓ��͕��˂ɁA�k�쎡�Y���q�͑呺���킳�ꂽ�Ƃ����B
�i�V���Ӂj
���ؒ}��琳���A�R�c�\���v�d�����Ďg�Ƃ��āA�a�B�̏����ł���K�R�A�ʏ��A���q���������ɒT�����B
���̏镺�ł������R��ѓ����M�A�k�쎡�Y���q�鏟�́A�����̑�{�V�ɔE��ł������A
���\����A���̎R�ɗ��l���B��Ă���Ƃ��������������������߁A�H���A�n��ג��ɖ����Đq�ˑ{�������B
���̎��A�R�{�A�k���̗��l�́A��{�V�̖@��ɐ\����
�u��F�c���L�����ꍇ�A����Ɍ����邱�Ƃ��o���Ȃ��ł��傤�B�Ȃ̂ʼn�痼�l�͔��o�ŁA�ؕ��d��܂��B�v
����ɑ��Ė@���
�u�������{����̂��q�˂��݂�A�w��h�͒v�����܂������A���̌�͉����֎Q�����̂������܂���B�x��
�\���グ�܂��B���̏�ł̂��v�炢����ɂ��ׂ��ł���A�Ԃ��Ԃ������l�Ƃ��A�ؕ��̂��Ƃ͎v���~�܂��ĉ������B�v
�����\�������߁A�R��A�k���͂����ɒ��d�����B����������ɂ���Ė��{���͑�{�V��߂��A
�q�ɉ��i���d�j�̌��ɏ����Ă߂�ꂽ
����{�ɁA���\�����A�R��ѓ��A�k�쎡�Y���q�͖{�\���֗��āA
�u��痼�l�͑��̗��l�ł���A��ɑ�{�V�̏��ɉB�ꋏ���̂����A���̑m�����s�ɐ����߂�ꂽ�Ə������B
��킭�Ή�痼�l�����Y�ɑ����A��{�V�͖̎Ƃ�����I�v
���̂悤�Ɍ����A���̎|�͖{�\����苞�s���i��֑i����ꂽ�B
���̎��A�{������i�����j����䏊�i����ƍN�j�ɑ��A�u�i���o�Ă������l���A�����ւ������a����
�ׂ��ł��傤���v�ƉM�������A����
�u�`��m���ďo�Ă����҂ɁA������������B�v
�ƁA���̂܂ܖ{�\���ɍ����u���ꂽ�B
���̌�A��䏊�́u���l�̎ҋ��́A���ɂėǂ�����ۂ݂������낤����A���ŏo����鎿�̈������ɂ�
���f����ł��낤�B���̒�����点��B�v�Ƌ����A��Â��琳�����킳�ꂽ�B�����͂��̒���
��g�̉��^�ɓn���A���^�͎����Ă��̎��֍s���āA�R��A�k��̗��l��
�u�����ɐؕ������t�����邾�낤�B���̐S������ׂ��B�v�ƁA��ӂ̎�������n�������A
���̌�A���̗l�q�A���тɍ��喼�A��g���g�Ɋ�炸�A�S��ʂ����҂͖����������Ɛq�˂����A���l��
�u���ꂪ���͊O�l�Ҍ́A���������܂���B�v
�Ɠ������B
���̂��ߎg���̎҂́A�u���l�ɐ\���グ�����������A��l�ɂ��̂悤�ȕԓ��͔��Ȃ�Ȃ��B
�ꃖ���ł����Ă��\���グ����ׂ��B�v�ƌ��������A���l�͏d�˂�
�u����Ǒ����ʂ��Ƃ́A�\����܂���B�v�ƌ������B
��g�͖��������u���l�̎������ꂪ�����\���悤�Ɏ��萬���̂ŁA���̌����ʂ�\���グ����B�v
����ɎR��ѓ��͗������āu�L�b�ƖŖS�̏�́A������肽�����͂��ꖳ���I�R����A
�l�����܂ʂ��Ƃ���莝��������l�A���͂��̕��𗊂ސl����莝���Ă�낤�I�v
���������ėl�X�Ɉ����������߁A��g���傢�ɓ{��A�u������̒ʂ�����シ�ׂ��I�v�Ɛ\���A
�����Ԃ��đ�䏊�ֈ�X�ɐ\���グ�A�U�X�Ɉ����������B
�Ƃ��낪�ƍN���͕����ʌ��ɂāA
�u�ނ痼�l�́A���ɉ����ėE�҂ƌĂꂽ�ҒB���B��x�m��ʂƐ\���o���̂��A�d�˂Ė₤���Ƃ����邩�I�v
�ƁA�g���̎҂�������������B
���̗��l�ɂ͐ؕ������t������ׂ��Ƃ̌䍹���ł������̂����A�@���Ȃ鎖���A�����O���A�Ҍ�̎���
��͖Ƃ����āA���l���ɋ��s�ɏZ���A���N�A��䏊���I�������ƁA���N�����A���s�̘Q�l���̂��߁A
�R��ѓ��͕��˂ɁA�k�쎡�Y���q�͑呺���킳�ꂽ�Ƃ����B
�i�V���Ӂj
169�l�Ԏ����l�N
2022/05/04(��) 21:24:12.40ID:/7YhvoxA �u�F�ˋ��`�W�v����
���@�@�d�A�փ����ɂ�
�E�ҐV�l(���Ë`�O)�́A�փ�������Ŗ������s�R�����������ߌ�펀�����ӂȂ��ꂽ�B
���������낢��Ђߐ\���グ�āA�������т邱�ƂɂȂ����B
�������ǂ̕��p�ɗ������т���ǂ��낤�ƂȂ������A���@�앺�q�@�d���\���グ�����Ƃɂ�
�u�������A���{��(�ƍN)�͐w����ړ������ł��傤����A���̐w����˂����Ĉɐ��H�֗������т�ׂ����Ǝv���܂��v
���̌��t�ɂ����킸�A���{���͐w����J�Y���a�̐w��Ɉړ����n�߂��̂ŁA���̐w����˂����āA�ɐ��H�֗������т邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ��B
�E�ҐV�����փ������痎�����т鎞�A�钆�̓G�ɂނ����Č��@�앺�q��
�u���Õ��ɓ�(�`�O)�A�������܂܂���ʂ�I�v�Ɛ����ɐ\���グ���B
�ҐV�l���͂��߂݂Ȃ��u���̂悤�Ȃ��Ƃ�\���ȁI�v�ƌ������Ƃ���
�앺�q�u���̂悤�ɂ����A�F�K���ɂȂ�̂ŋ��݂������ł��傤�v�Ɠ������Ƃ������Ƃ��B
����ɂ��Ă͌��@�ł͂Ȃ���ۈ��(����)���������Ƃ�����������B
����ɂ��Ζ�ۈ��a�͈ɉ���̓G�鉺�ɂāu���ɓ��������܂܂���ʂ�I�v�Ɛ����ɐ\�������߁A
�u���͖��҂�����ォ����Ă����v�ƌ����Ă��܂��A��ǂ��o����A�ォ����Ă������ƂɂȂ����Ƃ����B
����Ȃ�ΓG�������o�Ă��Đ�������Ƃ��낤�B
�㔼�͎����b���O�ɏo�Ă���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-4775.html
1600�N�A�ɉ�R���ɂ�
���@�@�d�A�փ����ɂ�
�E�ҐV�l(���Ë`�O)�́A�փ�������Ŗ������s�R�����������ߌ�펀�����ӂȂ��ꂽ�B
���������낢��Ђߐ\���グ�āA�������т邱�ƂɂȂ����B
�������ǂ̕��p�ɗ������т���ǂ��낤�ƂȂ������A���@�앺�q�@�d���\���グ�����Ƃɂ�
�u�������A���{��(�ƍN)�͐w����ړ������ł��傤����A���̐w����˂����Ĉɐ��H�֗������т�ׂ����Ǝv���܂��v
���̌��t�ɂ����킸�A���{���͐w����J�Y���a�̐w��Ɉړ����n�߂��̂ŁA���̐w����˂����āA�ɐ��H�֗������т邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ��B
�E�ҐV�����փ������痎�����т鎞�A�钆�̓G�ɂނ����Č��@�앺�q��
�u���Õ��ɓ�(�`�O)�A�������܂܂���ʂ�I�v�Ɛ����ɐ\���グ���B
�ҐV�l���͂��߂݂Ȃ��u���̂悤�Ȃ��Ƃ�\���ȁI�v�ƌ������Ƃ���
�앺�q�u���̂悤�ɂ����A�F�K���ɂȂ�̂ŋ��݂������ł��傤�v�Ɠ������Ƃ������Ƃ��B
����ɂ��Ă͌��@�ł͂Ȃ���ۈ��(����)���������Ƃ�����������B
����ɂ��Ζ�ۈ��a�͈ɉ���̓G�鉺�ɂāu���ɓ��������܂܂���ʂ�I�v�Ɛ����ɐ\�������߁A
�u���͖��҂�����ォ����Ă����v�ƌ����Ă��܂��A��ǂ��o����A�ォ����Ă������ƂɂȂ����Ƃ����B
����Ȃ�ΓG�������o�Ă��Đ�������Ƃ��낤�B
�㔼�͎����b���O�ɏo�Ă���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-4775.html
1600�N�A�ɉ�R���ɂ�
170�l�Ԏ����l�N
2022/05/05(��) 22:36:45.19ID:2DXCFnUB �u�F�ˋ��`�W�v�ɂ͌��@���ɐ��H��I���R�ɂ���
�u�������ɓ���Ď����Ă����单�l���ɐ��H�������Ă�������v
�Ƃ����b������
�u�F�ˋ��`�W�v�����@�@�d�̑��q����
���@�앺�q�A�������ĒW�ւ͕��\�̖��ォ�瓇�ÉƂɎd���Ă����B
(���ǁ����Á����X�����������Â̂悤����)
�ҐV�l(�`�O)�����������̏鉺�A�݈�c���ő���V���ꂽ���A�c�ɔn�ɏ�����݂��ڂ炵���V�l�ɍs�����������B
�V�l�͓a�l������Ȃ�n�����э~�肨���ɎQ�������A
�ҐV�l�͂��Ƃ̂ق����J�ɂ����A�������ꂽ�B
�V�l���u��@�����f���ɎQ�낤�Ǝv���Ă���܂������A�������Ă��ڂɂ������Ƃ́v�Ɛ\���グ���
�ҐV�l�́u�A�鎞�͂܂�������Ɋ�낤���v�ƌ�ӂ������ꂽ�B
�W�ւ̒��j�A�������O�Y�͂��̂Ƃ��ҐV�l�̂��������Ă������A�����̏O�ɂ��̘V�l�̖���q�˂��Ƃ���A
�l�c�������q������p��(�l�c�o�d)�ł���A�Ɠ�����ꂽ�B
���̎��A���O�Y�͋��̐��߂���ł������A�A����̂����̒W�ւɑ���
���O�Y�u���������Ƃ����킯�ŁA�݂��ڂ炵���g�Ȃ�������V�l�͑��}�l�ɂ܂Ŗ��������Ă����A���ӎ҂̕l�c�h�Ղł���܂����B
����قǂ̕��ӎ҂ł����̂悤�ȕ�炵�Ԃ�ł́A��X�̕�炵�Ԃ�ł͌䓖�ƂɂƂ��Ēp�Ƃ����A�Ƃ��Ă��o���̌����݂͂Ȃ��ł��傤�B
����֕���ɏo�����Ǝv���܂��v�ƌ�����
�W�ցu���������Ȃ��̗��Ȏ���ł���v
�Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA���O�Y�͈�������ɏ���������ꂽ�ƌ������Ƃ��B
�Ȃ��W�ւ̎��j�A���V��͂Ƃ����Ɨw(������)����Ŗ邪���ނ܂ŗw���S���Ă������߁A�W�ւ�
�u���ӎ҂̎q�����悤�ɗV�|�ɂ���Ƃ́A�Ȃ�ƌ��ɂ������Ƃ�B
�a�l(���Ò��P)�͔\������Ȃ̂ŁA����w�̂����ł��ɏ�����������悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂������Ė��f���v
�Ɛ\�����Ƃ������Ƃ��B
�u�������ɓ���Ď����Ă����单�l���ɐ��H�������Ă�������v
�Ƃ����b������
�u�F�ˋ��`�W�v�����@�@�d�̑��q����
���@�앺�q�A�������ĒW�ւ͕��\�̖��ォ�瓇�ÉƂɎd���Ă����B
(���ǁ����Á����X�����������Â̂悤����)
�ҐV�l(�`�O)�����������̏鉺�A�݈�c���ő���V���ꂽ���A�c�ɔn�ɏ�����݂��ڂ炵���V�l�ɍs�����������B
�V�l�͓a�l������Ȃ�n�����э~�肨���ɎQ�������A
�ҐV�l�͂��Ƃ̂ق����J�ɂ����A�������ꂽ�B
�V�l���u��@�����f���ɎQ�낤�Ǝv���Ă���܂������A�������Ă��ڂɂ������Ƃ́v�Ɛ\���グ���
�ҐV�l�́u�A�鎞�͂܂�������Ɋ�낤���v�ƌ�ӂ������ꂽ�B
�W�ւ̒��j�A�������O�Y�͂��̂Ƃ��ҐV�l�̂��������Ă������A�����̏O�ɂ��̘V�l�̖���q�˂��Ƃ���A
�l�c�������q������p��(�l�c�o�d)�ł���A�Ɠ�����ꂽ�B
���̎��A���O�Y�͋��̐��߂���ł������A�A����̂����̒W�ւɑ���
���O�Y�u���������Ƃ����킯�ŁA�݂��ڂ炵���g�Ȃ�������V�l�͑��}�l�ɂ܂Ŗ��������Ă����A���ӎ҂̕l�c�h�Ղł���܂����B
����قǂ̕��ӎ҂ł����̂悤�ȕ�炵�Ԃ�ł́A��X�̕�炵�Ԃ�ł͌䓖�ƂɂƂ��Ēp�Ƃ����A�Ƃ��Ă��o���̌����݂͂Ȃ��ł��傤�B
����֕���ɏo�����Ǝv���܂��v�ƌ�����
�W�ցu���������Ȃ��̗��Ȏ���ł���v
�Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA���O�Y�͈�������ɏ���������ꂽ�ƌ������Ƃ��B
�Ȃ��W�ւ̎��j�A���V��͂Ƃ����Ɨw(������)����Ŗ邪���ނ܂ŗw���S���Ă������߁A�W�ւ�
�u���ӎ҂̎q�����悤�ɗV�|�ɂ���Ƃ́A�Ȃ�ƌ��ɂ������Ƃ�B
�a�l(���Ò��P)�͔\������Ȃ̂ŁA����w�̂����ł��ɏ�����������悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂������Ė��f���v
�Ɛ\�����Ƃ������Ƃ��B
171�l�Ԏ����l�N
2022/05/05(��) 22:39:45.94ID:2DXCFnUB ����ȑ��V��ł��������A
�c���ܔN�̊փ������킩��Z�N�ځA�ҐV�l���\�̎��A�g��Ō�n�ǂ��s���邱�ƂɂȂ����B
���ʂɓ��(�ɂ�)�O�ɂ͈ٗl�̎p�ł܂���o�邱�Ƃ������ꂽ���߁A�������̓�ˏO���������������̊i�D�Ŕn�ɏ��܂���o�钆�A
���@���V����͖�тŔn�ɂ���炸�ɏo�Ă����B
��ˏO�́u���̔��Ɛg�Ȃ���݂��v�ƊF�X�����B
���ċg��Ŗ{�痎�Ƃ�(���n�H)�̎��A���V����Ԃ���H�ו������o���n�ɐH�킹�A�����Ɣn�ɔ�я���O�������ނƐ^����ɋ삯�o�����B
���̎��u���Ă����Ă��W�ւ̎q�����͂���v�ƊF�X���\�����B
�ҐV�l���{�痎�Ƃ����Ȃ������������B
�c���ܔN�̊փ������킩��Z�N�ځA�ҐV�l���\�̎��A�g��Ō�n�ǂ��s���邱�ƂɂȂ����B
���ʂɓ��(�ɂ�)�O�ɂ͈ٗl�̎p�ł܂���o�邱�Ƃ������ꂽ���߁A�������̓�ˏO���������������̊i�D�Ŕn�ɏ��܂���o�钆�A
���@���V����͖�тŔn�ɂ���炸�ɏo�Ă����B
��ˏO�́u���̔��Ɛg�Ȃ���݂��v�ƊF�X�����B
���ċg��Ŗ{�痎�Ƃ�(���n�H)�̎��A���V����Ԃ���H�ו������o���n�ɐH�킹�A�����Ɣn�ɔ�я���O�������ނƐ^����ɋ삯�o�����B
���̎��u���Ă����Ă��W�ւ̎q�����͂���v�ƊF�X���\�����B
�ҐV�l���{�痎�Ƃ����Ȃ������������B
172�l�Ԏ����l�N
2022/05/07(�y) 18:21:40.53ID:vcsZqKO6 �c����\�N�܌���\���A���C�����i�����j�̏d�b�ŁA��㗎���߂���ꂽ�đ����E�q�傪
�����o����A���钆�ɒ���������ɂ��Ă̋��ׂ�q�˂�ꂽ�B�đ��́A�m��Ȃ��Ƃ�������
�\�������A���������s�́u���͏C�����̒��m�ł���B�ǂ����Ēm��Ȃ��Ƃ����������邩�I�v
�Ɣl�����B
����܂ŕđ��͌m��i����[������Ēn�ɂ��邱�Ɓj���Ă������A���̌��t����z���グ�A
�u����͌��s�̌��t�Ƃ��o���ʂ��̂��ȁI���ꂪ���͔ڑG�ł������̂��A��l�̗���݂��ȂāA
�m�̒��ɓ���Ē������i�ʋL�ɁA�đ��͑�쎡���̑�����肾�����Ƃ�������j�B
���̎�l�͑��ɍ݂��āA�R�w�̐��s�������Ă����ȏ�A�^���̑��S���������[�Ɍv�葱���A
�\�ċ�����݂�S�Ƃ����B������Ȃĉ��˂̎҂ƌ����ǂ��A�G������Ƃ��Ƃ̂ݎv���A
���Ɏv�������炷���͂Ȃ������B����ɂ���ċ�����݂����邱�ƁA�H�̔@���B
�����ȂĐ\���A�钆����ɕ��������́A��̂����ۂ��Ƃ͏o�����A�疜�̍��݂��L�����Ƃ��Ă�
���̖��ɗ����낤���B�����āA�������R�������A�����R�i�ƍN�E�G���j�̌䍘�̕��܂ł��F
���̕��ƂȂ�A���߂����č��݂͖O���[�邾�낤�B
�����ׂ��|������Ή}�����Ƃ͎v��Ȃ��B�����������ׂ������Ȃ��̂Ȃ�A�����
�����Ă��A�����q�ׂ悤���I�v
�����A�݂�C�F�����\�������Ƃ��A��䏊������������A�u���ނ̍��̎҂Ȃ�v�ƁA��͖Ƃ������B
�i�V���Ӂj
�����o����A���钆�ɒ���������ɂ��Ă̋��ׂ�q�˂�ꂽ�B�đ��́A�m��Ȃ��Ƃ�������
�\�������A���������s�́u���͏C�����̒��m�ł���B�ǂ����Ēm��Ȃ��Ƃ����������邩�I�v
�Ɣl�����B
����܂ŕđ��͌m��i����[������Ēn�ɂ��邱�Ɓj���Ă������A���̌��t����z���グ�A
�u����͌��s�̌��t�Ƃ��o���ʂ��̂��ȁI���ꂪ���͔ڑG�ł������̂��A��l�̗���݂��ȂāA
�m�̒��ɓ���Ē������i�ʋL�ɁA�đ��͑�쎡���̑�����肾�����Ƃ�������j�B
���̎�l�͑��ɍ݂��āA�R�w�̐��s�������Ă����ȏ�A�^���̑��S���������[�Ɍv�葱���A
�\�ċ�����݂�S�Ƃ����B������Ȃĉ��˂̎҂ƌ����ǂ��A�G������Ƃ��Ƃ̂ݎv���A
���Ɏv�������炷���͂Ȃ������B����ɂ���ċ�����݂����邱�ƁA�H�̔@���B
�����ȂĐ\���A�钆����ɕ��������́A��̂����ۂ��Ƃ͏o�����A�疜�̍��݂��L�����Ƃ��Ă�
���̖��ɗ����낤���B�����āA�������R�������A�����R�i�ƍN�E�G���j�̌䍘�̕��܂ł��F
���̕��ƂȂ�A���߂����č��݂͖O���[�邾�낤�B
�����ׂ��|������Ή}�����Ƃ͎v��Ȃ��B�����������ׂ������Ȃ��̂Ȃ�A�����
�����Ă��A�����q�ׂ悤���I�v
�����A�݂�C�F�����\�������Ƃ��A��䏊������������A�u���ނ̍��̎҂Ȃ�v�ƁA��͖Ƃ������B
�i�V���Ӂj
173�l�Ԏ����l�N
2022/05/08(��) 00:48:29.51ID:xEsd93HH �F���ˁu�{�ːl���u�v�u�F�B���`�W�v����>>170�̕l�c�o�d�̘b
�u�{�ːl���u�v�̕l�c�������q��o�d�����h�Ղ̋L�q
���c�z�O��o��(���c�e�̊J���ҁA���c�o�F�̑c�悾�낤��?)�̕��O�ł��������R�����Q�̂䂦�A������(���Ë`�v)���������ɏ����ꂽ�B
�G�g������B�ɏo�w���ꂽ���͑䒮�ɒB���A���ڌ�����������A��葄���������ꂽ�B
(����:���[����(�����H)��ň�ړB�q���ɓ`������Ă���)
�m�s�ܕS��q�̂��������������A��N�ŗ������ɕԏサ���B
�c���\�Z�N�̗�����������̎��ɂ͏}�������\�ܐl�̈�l�ƂȂ����B
�����̋�
��Ȃ��A�����N�ɕ��@������̂����́A���߂錎����
���̂̂ӂ̎��`�ւ��鈲�|�@�N�ɂЂ����A��̐��܂ł�
���c�z�O��̔z���̎��͏�U�߂̍ہA�G����钆�ɔE�эs���ĕ������������B
�M�v���A�`�v���̌��܂ŏo�w���A���ƂɔE�т̕������������B
�u�{�ːl���u�v�̕l�c�������q��o�d�����h�Ղ̋L�q
���c�z�O��o��(���c�e�̊J���ҁA���c�o�F�̑c�悾�낤��?)�̕��O�ł��������R�����Q�̂䂦�A������(���Ë`�v)���������ɏ����ꂽ�B
�G�g������B�ɏo�w���ꂽ���͑䒮�ɒB���A���ڌ�����������A��葄���������ꂽ�B
(����:���[����(�����H)��ň�ړB�q���ɓ`������Ă���)
�m�s�ܕS��q�̂��������������A��N�ŗ������ɕԏサ���B
�c���\�Z�N�̗�����������̎��ɂ͏}�������\�ܐl�̈�l�ƂȂ����B
�����̋�
��Ȃ��A�����N�ɕ��@������̂����́A���߂錎����
���̂̂ӂ̎��`�ւ��鈲�|�@�N�ɂЂ����A��̐��܂ł�
���c�z�O��̔z���̎��͏�U�߂̍ہA�G����钆�ɔE�эs���ĕ������������B
�M�v���A�`�v���̌��܂ŏo�w���A���ƂɔE�т̕������������B
174�l�Ԏ����l�N
2022/05/08(��) 00:51:23.78ID:xEsd93HH �u�F�B���`�W�v�̕l�c�o�d�̘b
�l�c�������q��͋g���ʂ������A���ɏo���킵���̂Ŗɓo���Ēʂ�߂���̂�҂����B
�����֓�ˏO���ʂ肩�����Ē�����艟����
�u�������q��a�قǂ̕����Ȃ����̂悤�Ȕڋ��̐^�����Ȃ���̂ł����H�v�Ə����B
�������q��u���̐g�͌�p�̂��߂ɂ���̂ŁA���Ȃǂ���艟������ۂɉ�������Ă͎c�O�ł�����ȁv
�Ɠ������Ƃ����B
����l���l�c�������q��̓���q���������ƌ����Ă����̂ō����o�����Ƃ���A�������Ƃ����������Ȃ������B
�������q�傪�����Ŕ����Ă݂�ƐԎK���炯�������̂�
����l�u����ł͂����Ƃ��������ɗ����܂��܂��v
�Ə����Ƃ���
�������q��u�����ł��ˁB��������Ƃ������̂͋}�ɂ͋N���Ȃ����̂ł��B���\���̊Ԃ�����܂��̂ł��̂����Ɍ����܂��傤�B
����ɕ��m�Ƃ������̂͌��܂Ȃǂ��Ȃ����̂ł��B���꓁���K�v�Ȃ��Ƃ�����A�킽���͑������̂܂ܒ@���E���܂��傤�B
���Ȃ��͌����ł������������ł��傤���v
�Ɠ��������߁A����͕����Ă��܂����Ƃ����B
�l�c�������q��͋g���ʂ������A���ɏo���킵���̂Ŗɓo���Ēʂ�߂���̂�҂����B
�����֓�ˏO���ʂ肩�����Ē�����艟����
�u�������q��a�قǂ̕����Ȃ����̂悤�Ȕڋ��̐^�����Ȃ���̂ł����H�v�Ə����B
�������q��u���̐g�͌�p�̂��߂ɂ���̂ŁA���Ȃǂ���艟������ۂɉ�������Ă͎c�O�ł�����ȁv
�Ɠ������Ƃ����B
����l���l�c�������q��̓���q���������ƌ����Ă����̂ō����o�����Ƃ���A�������Ƃ����������Ȃ������B
�������q�傪�����Ŕ����Ă݂�ƐԎK���炯�������̂�
����l�u����ł͂����Ƃ��������ɗ����܂��܂��v
�Ə����Ƃ���
�������q��u�����ł��ˁB��������Ƃ������̂͋}�ɂ͋N���Ȃ����̂ł��B���\���̊Ԃ�����܂��̂ł��̂����Ɍ����܂��傤�B
����ɕ��m�Ƃ������̂͌��܂Ȃǂ��Ȃ����̂ł��B���꓁���K�v�Ȃ��Ƃ�����A�킽���͑������̂܂ܒ@���E���܂��傤�B
���Ȃ��͌����ł������������ł��傤���v
�Ɠ��������߁A����͕����Ă��܂����Ƃ����B
175�l�Ԏ����l�N
2022/05/08(��) 12:49:48.35ID:bHdxuNpE ���c�e�Ƃ����S�[���f���J���C�Ń}�^�M���g���Ă�����
176�l�Ԏ����l�N
2022/05/08(��) 20:01:35.59ID:MyNSl0Sh >>174
����܂�F���̐l���ۂ��Ȃ����i���Ă�������
����܂�F���̐l���ۂ��Ȃ����i���Ă�������
177�l�Ԏ����l�N
2022/05/09(��) 15:47:05.98ID:rDukSbJM �F���Ƃ���������
178�l�Ԏ����l�N
2022/05/09(��) 16:03:41.70ID:AbK5L8LX �u�F�B���`�W�v���牟�십���q(������߁A�l�c�o�d�̖���)�̘b
����Ƃ��A���십���q�͂��ߑ����̎҂���J�̂��߂ɖ�O�ł��炭�Q�邱�Ƃɂ����B
�Ԃ����Ă����҂��Q�Ă���҂̉A�X��T�����Ƃ���A�����Ă��͏k�݂���ł����B
�����q�͍����т��������ĐQ�Ă������A�u�����q�͍����̐l������ǂ�Ȃ��̂��낤�v�ƒT�����Ƃ���A�d���Ȃ��ĂȂ���������
�������͗E���̐l�ł���A�Ɗ��S�����Ƃ������Ƃ�
�Ȃ��F���ˁu�{�ːl���u�v�ɂ��Ή�����߂̊���Ƃ���
�փ�����Ɉɐ��R�ɓ��Õ���S�l���Ă�A���߂ƕl�c�吅(�l�c�o�d�̑��q)���H�Ƃ��m�ۂ��ĊF�ɔz�����B
���̂̂��Γc�O�������������������B���ė������т悤�Ƃ����Ƃ����߂炦��ꂽ���A���ÂƐe�����R�����F�ɂ��~������A�召�̓��������B
�����Ă������蒼�F�̉��~����ۍ��ŏo�����A�B���Ă����������������A��J�̂��ߓ��[�̂����Ŗ������B
�������A�k���̉��ɋC�Â��N����ƁA��e���̒j���a�肩�����Ă������߁A���̓���D���A�j�̎��藎�Ƃ��A���s�ɍs���߉q�l�̉��~�ɋ삯���B
�A����A�O���Q��̖��ڂœ��ÖL�v�̍s���⏔�����T�����B
���̂̂��A����A�˖��Y���q��(�˖엘�H�̐�c)�̈ē��ŕ��c���@(���������̕���)����ӂɏ]���ÎE�����B
�Ƃ��������Ƃ�������Ă���
����Ƃ��A���십���q�͂��ߑ����̎҂���J�̂��߂ɖ�O�ł��炭�Q�邱�Ƃɂ����B
�Ԃ����Ă����҂��Q�Ă���҂̉A�X��T�����Ƃ���A�����Ă��͏k�݂���ł����B
�����q�͍����т��������ĐQ�Ă������A�u�����q�͍����̐l������ǂ�Ȃ��̂��낤�v�ƒT�����Ƃ���A�d���Ȃ��ĂȂ���������
�������͗E���̐l�ł���A�Ɗ��S�����Ƃ������Ƃ�
�Ȃ��F���ˁu�{�ːl���u�v�ɂ��Ή�����߂̊���Ƃ���
�փ�����Ɉɐ��R�ɓ��Õ���S�l���Ă�A���߂ƕl�c�吅(�l�c�o�d�̑��q)���H�Ƃ��m�ۂ��ĊF�ɔz�����B
���̂̂��Γc�O�������������������B���ė������т悤�Ƃ����Ƃ����߂炦��ꂽ���A���ÂƐe�����R�����F�ɂ��~������A�召�̓��������B
�����Ă������蒼�F�̉��~����ۍ��ŏo�����A�B���Ă����������������A��J�̂��ߓ��[�̂����Ŗ������B
�������A�k���̉��ɋC�Â��N����ƁA��e���̒j���a�肩�����Ă������߁A���̓���D���A�j�̎��藎�Ƃ��A���s�ɍs���߉q�l�̉��~�ɋ삯���B
�A����A�O���Q��̖��ڂœ��ÖL�v�̍s���⏔�����T�����B
���̂̂��A����A�˖��Y���q��(�˖엘�H�̐�c)�̈ē��ŕ��c���@(���������̕���)����ӂɏ]���ÎE�����B
�Ƃ��������Ƃ�������Ă���
179�l�Ԏ����l�N
2022/05/09(��) 17:06:39.50ID:AbK5L8LX �ŏ��ǂ��A�u�k���̉��v�͓��������́u����̉��v�Ƃ��u�Ղ̉��v�̊ԈႢ���Ǝv��������
�ڂ��o�܂��قǂ̉��͂��Ȃ�����A�����̂��������u�k���̉��v�ł����͂�
�ڂ��o�܂��قǂ̉��͂��Ȃ�����A�����̂��������u�k���̉��v�ł����͂�
180�l�Ԏ����l�N
2022/05/09(��) 20:37:22.33ID:tcJFYPPt ����{�ɁA���C�����i�����j�̖��͓V���@�a�i��P�j�ɏ����d���A���C�����̏d�b�ł���
�đ����E�q��̖��́A���̑��̖��Ɏd�����B
���Ă̐w��A�đ����Q�l������ɁA�܁X�i��P�́j�䉮�݂֍s���ƁA�ߕ��A�������̔q�̕��Ȃǂ��������B
�R��ɁA�����̖����a��ς��A�u�����Ă��邤���ɁA���w�Ȃǒv���đ��ʂĂ����v�Ƃ̊肢�ɂ��A
��ɂ�������A���̏�ɕđ����E�q���������A
�u���̕��������A����オ��A笕��ɗ{����v������B�v
�ƁA�֏���`�B�����̎G�p��������ɋ����A���g�̖��ƂƂ��ɋ����ċ��ɏオ��A�l�X�ɗ{����
�Ȃ����̂ł��邪�A�I�ɑ��ʂĂ��B
�̂ɉΑ��Ƃ����̂ł��邪�A���̎����E�q�傪���S���̕��֍s���Ă���ԂɁA�ނ̖��������̖���
�Ă��̒��ɔ�ѓ���A���ɕ������ďĎ������B
���E�q��͋A���Ă��đ傢�ɋ��������A�ׂ��p���Ȃ��A���̂悤�ȏ������̂Ŏ�]�̍���
�����邱�Ƃ��o�����A�ꏊ�ɂ��č���R�֎����o��A�����ɔ[�߂��B�����Ē䔯���Ď��猠����
�������߁A���s���S���̓��A���a���ɐ������A���̌�]�˂ɉ���A�ł̓��T���ɍ݂��đ|���Ȃǂ��Ă����B
������A����a���Ɨ��a�����������A�������璷���i�����j�j�ɏ����ꂽ�̂����A����H��
�u�����ɂ͐����̐l����������Ă��܂����A���a���̎�����Ă���悤�Ȑl�͖����ł��傤�B�v
�ƌ������B�����͕����āu���Ă͉��Ɛ\���l�ł��傤���B�v�Ɓu�q�˂�ƁB
���������
�u���C�����ƘV�E�đ����E�q��Ɛ\���҂ł��B���̎҂͏C���̔z���ւ̋��������߁A�փ����������A
�F�쑽���[���i�G�Ɓj�Ɨ��E���m���Y�E�q��Ɛ\���҂�g�ݓ����ɒv���A���̌���~�w�Ō�a�k�̐܁A
�D�c�L�y�A���C�������ցA���̂��ߕ���S����������l�Âo���悤�ɂƂ��������A�L�y���͑��c�g���A
�����ďC�����͔ނ��o���܂����B�ނ͓x�X�钆���o�Č����s���A��a�k����������ƁA���P�R��
��w���ɂ����āA��䏊�i����ƍN�j�Ɍ�ڌ����d��A��̊O��ܔ��ɗa����܂����B
���݂͕��m���~�߁A���a���̕��ɔ��L��܂��B�v
����ɒ���
�u���̌��E�q��͐��ԂɉB�ꖳ���҂ł��B�َҁA�ނ��������������v���܂��B�C�����ł̒m�s��
�����قǂł������������m�Ȃ��ł��傤���B�v
����ɗ��a�����ɁA�u��m�͓�S�ł������ƕ����y��ł���܂��v�Ƃ���A�������
�u�ł͎l�S�Ό��킵�\���ׂ��B�v�ƌ����ƁA����́u�ǂ����Ă��A�ܕS�����킳���ׂ��ł��B�v
�Ɛ\�����B����ɑ�
�u�ܕS�Ƃ����m�s�ɂ��ẮB���X���������\���e�ׂ�����܂��A���̑���ɑ��y��
�a���܂��傤�B���A�ނ͍����S�҂̑̂ł���܂�����A�����������ł��傤�B
���́A���������ł͂���܂����A���N�̕������x�x���Ƃ��Č��킵�܂��傤�B�v
����ɂ���ĕđ��́A�I�ɐ�쒷���̉Ɨ��Ɛ������B
�i�V���Ӂj
�đ����E�q��̖��́A���̑��̖��Ɏd�����B
���Ă̐w��A�đ����Q�l������ɁA�܁X�i��P�́j�䉮�݂֍s���ƁA�ߕ��A�������̔q�̕��Ȃǂ��������B
�R��ɁA�����̖����a��ς��A�u�����Ă��邤���ɁA���w�Ȃǒv���đ��ʂĂ����v�Ƃ̊肢�ɂ��A
��ɂ�������A���̏�ɕđ����E�q���������A
�u���̕��������A����オ��A笕��ɗ{����v������B�v
�ƁA�֏���`�B�����̎G�p��������ɋ����A���g�̖��ƂƂ��ɋ����ċ��ɏオ��A�l�X�ɗ{����
�Ȃ����̂ł��邪�A�I�ɑ��ʂĂ��B
�̂ɉΑ��Ƃ����̂ł��邪�A���̎����E�q�傪���S���̕��֍s���Ă���ԂɁA�ނ̖��������̖���
�Ă��̒��ɔ�ѓ���A���ɕ������ďĎ������B
���E�q��͋A���Ă��đ傢�ɋ��������A�ׂ��p���Ȃ��A���̂悤�ȏ������̂Ŏ�]�̍���
�����邱�Ƃ��o�����A�ꏊ�ɂ��č���R�֎����o��A�����ɔ[�߂��B�����Ē䔯���Ď��猠����
�������߁A���s���S���̓��A���a���ɐ������A���̌�]�˂ɉ���A�ł̓��T���ɍ݂��đ|���Ȃǂ��Ă����B
������A����a���Ɨ��a�����������A�������璷���i�����j�j�ɏ����ꂽ�̂����A����H��
�u�����ɂ͐����̐l����������Ă��܂����A���a���̎�����Ă���悤�Ȑl�͖����ł��傤�B�v
�ƌ������B�����͕����āu���Ă͉��Ɛ\���l�ł��傤���B�v�Ɓu�q�˂�ƁB
���������
�u���C�����ƘV�E�đ����E�q��Ɛ\���҂ł��B���̎҂͏C���̔z���ւ̋��������߁A�փ����������A
�F�쑽���[���i�G�Ɓj�Ɨ��E���m���Y�E�q��Ɛ\���҂�g�ݓ����ɒv���A���̌���~�w�Ō�a�k�̐܁A
�D�c�L�y�A���C�������ցA���̂��ߕ���S����������l�Âo���悤�ɂƂ��������A�L�y���͑��c�g���A
�����ďC�����͔ނ��o���܂����B�ނ͓x�X�钆���o�Č����s���A��a�k����������ƁA���P�R��
��w���ɂ����āA��䏊�i����ƍN�j�Ɍ�ڌ����d��A��̊O��ܔ��ɗa����܂����B
���݂͕��m���~�߁A���a���̕��ɔ��L��܂��B�v
����ɒ���
�u���̌��E�q��͐��ԂɉB�ꖳ���҂ł��B�َҁA�ނ��������������v���܂��B�C�����ł̒m�s��
�����قǂł������������m�Ȃ��ł��傤���B�v
����ɗ��a�����ɁA�u��m�͓�S�ł������ƕ����y��ł���܂��v�Ƃ���A�������
�u�ł͎l�S�Ό��킵�\���ׂ��B�v�ƌ����ƁA����́u�ǂ����Ă��A�ܕS�����킳���ׂ��ł��B�v
�Ɛ\�����B����ɑ�
�u�ܕS�Ƃ����m�s�ɂ��ẮB���X���������\���e�ׂ�����܂��A���̑���ɑ��y��
�a���܂��傤�B���A�ނ͍����S�҂̑̂ł���܂�����A�����������ł��傤�B
���́A���������ł͂���܂����A���N�̕������x�x���Ƃ��Č��킵�܂��傤�B�v
����ɂ���ĕđ��́A�I�ɐ�쒷���̉Ɨ��Ɛ������B
�i�V���Ӂj
181�l�Ԏ����l�N
2022/05/09(��) 22:08:23.88ID:V0Qof8cd �ŋL���G�g�̘b
���ۋ�N�@�㌎�����̓��L
���}�G�g�A������̋A��ɋ����̎҂�������㗗�ɓ���悤�ƂāA���̑O��ʂ鋖�����肢�o���B�����������āA���̓������J���ď㗗���ꂽ�B�O�W�@�a�i�߉q�M���j�����̎����o�łł������̂ŁA�G�g��s�̑����̍ו��܂Ŏc�����L�^�Ȃ��ꂽ�B�����̐l���̚삵�����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��������A�܂����̎҂����A�ߕS�H��|�Ɍ��ѕt���ē��ɕ��сA�����Ċ��S�H���悤�ɂƂ������ӂ��ɁA�㗗�ɋ����邽�߂ɐr���ؔ��ɋ��s����Ă���ƌ������B�ƍN���͂��߂Ƃ���R�n�̎m�́A�݂ȑ����ɐ����Ēʂ����B�G�g�͒��N�̗`�ɏ���ē����ɓ����𒅂��n�C�^�J����ɐ����ē��̑O�܂ŗ���Ǝ������ꂽ�B�a��l�����݂ȏo�}���ē��̑O�ɉ��Ȃ�݂������A�G�g�̐����Ă����n�C�^�J�͎��͍�蕨�ŁA���̎�������ƒ��Ɏ��悪�����Ă����������B���}�̕�����͂��悤�Ȃ��̂ł������B
���ۋ�N�@�㌎�����̓��L
���}�G�g�A������̋A��ɋ����̎҂�������㗗�ɓ���悤�ƂāA���̑O��ʂ鋖�����肢�o���B�����������āA���̓������J���ď㗗���ꂽ�B�O�W�@�a�i�߉q�M���j�����̎����o�łł������̂ŁA�G�g��s�̑����̍ו��܂Ŏc�����L�^�Ȃ��ꂽ�B�����̐l���̚삵�����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��������A�܂����̎҂����A�ߕS�H��|�Ɍ��ѕt���ē��ɕ��сA�����Ċ��S�H���悤�ɂƂ������ӂ��ɁA�㗗�ɋ����邽�߂ɐr���ؔ��ɋ��s����Ă���ƌ������B�ƍN���͂��߂Ƃ���R�n�̎m�́A�݂ȑ����ɐ����Ēʂ����B�G�g�͒��N�̗`�ɏ���ē����ɓ����𒅂��n�C�^�J����ɐ����ē��̑O�܂ŗ���Ǝ������ꂽ�B�a��l�����݂ȏo�}���ē��̑O�ɉ��Ȃ�݂������A�G�g�̐����Ă����n�C�^�J�͎��͍�蕨�ŁA���̎�������ƒ��Ɏ��悪�����Ă����������B���}�̕�����͂��悤�Ȃ��̂ł������B
182�l��
2022/05/10(��) 21:03:38.91ID:XPxiA+Ql �ŋL�̋��ۏ\�N�㌎�\�Z���̋L������@�G�g�Ƒ\�C���̘b
�i���[���i�גʁj�̘b�ɁA���}�G�g�V���ꓝ�̂̂��A�������a�i�k�������j���܂˂ē��{���v�������A���߂����ɂЂ����Ɍ�����B���߂������u�����ꂽ���Ƃ����A������̌�C���ł͎~�߂��ƂĂ��������ꂠ��܂��v�ƉA�ʼn\���Ă���̂��l�l�O�̎��ɓ������B�O�H�ܘY���q��i�������Y���q��j�Ȃǂ͂ǂ��ɂ����Ď~�߂悤�Ǝv�������藧�Ă��Ȃ������B���ɑ\�C���Ƃ�����k�̂��܂���l�����āA���}�̋C�ɓ��肾�����B�ܘY���q��͂��̒j�Ɂu���}�a�������{���v�������ꂽ���A���O�������~�߂���������̏�Ȃ����ł��邼�v�Ɨ��ݍ��ނƁA�u�S���܂����B�܂����Đ\���グ�܂��傤�v�Ƒ]�C���͐����������B
���鎞�A�]�C������O�ɏo���Ƃ��ɁA�u�����ς�������Ƃ͂Ȃ����v�Ɩ����ƁA�����āA�u�ŋߕς�������ƂƂ����A���̍��ȂĂ̊O�ɔ����s���Ă���܂��B�������������������A�s���ɑ吨�l���W�܂��āA���������œq����J���Ă͏����𑈂��Ă���܂��B�ߍ��A�����Ɛ����Ƃ̏�������C�ɂ��悤�ƁA����̂�����ɏW�܂��Ă���Ƃ���ցA���l�ƌ�����R���̂ǂ�����Ƃ��Ȃ�����ď������������Ă���܂����B
�������āw�����l���ɉ��������B�ꏟ�����������x�ƎR���������ƁA�e���O������āw�܂��͌�����������Ȃ����x�ƌ����B�R���A�w����ɂ͋y�Ԃ܂��B���N��̔@�������ɂ���A�����̓q���͂��ׂĉ䂪���ƂȂ낤���A�����炩�͌�����������Ă���x�Ƌ��O�S�����o���Ă�������Ƃ��ď������܂����B���t�Ɉ�킸�R���͑傢�ɏ����܂����č����̋������Ƃ��Ƃ������グ�Ă��܂��܂����B�����̐e���O�A�������قNj����āw���Ȃ��͂ǂ��̍��̕��ł����x�Ɩ₤�ƁA�w���͂��̎R�[�ɏZ�܂��A�V�����v���̂܂܂ɂ��锎��̑�e�����B����܂����x�ƌ����A�����̎҂݂ȍĔq�m�܂��B
����ɎR������Ă��킭�A�w����Ɍ��炸�A���͓V�n���ЂƂ��݂ɂ��A�R������݂ɑ���A�������Ɨ~�����̈����R���Ɠ�����ׁA�������Ɨ~�������̌N�̓�����肻����̌N�̐����ɓ͂��܂Œ����Ȃ�B��Ȃ��Ɨ~���ΓV�n�ɏ[�����A���Ȃ��Ɨ~���Ύϓ��قǂɏ������Ȃ�x�ƌ��܂��ƁA��l�i�ݏo�āA�w���Ă��Đ��ɂ��H�Șb�ł��B���Ƃ��Ă����蓤�قǂɂȂ�̂����������̂ł������܂��x�ƌ�ƁA��u�̂����ɐ��蓤�ƂȂ����Ƃ��������Č��ɓ���A�|���|���Ƃ��ݍӂ��A�w����ň���S���x�Ɗ�Ƃ������Ƃł������܂��v�ƌ�����B
�G�g�傢�Ɋ��S���āA�u���Ă��āA���͈����z����B�]���ߍ����v�����������Ƃ����|�߂��̂��ȁB���O�̌������Ƃ����Ƃ��ł���B�]�͓V����L���Ă���Ƃ����ǂ��A�V���l�̈ʂɂ����Ă��̐E�����������Ă����邪�A�g��ł��Ă͎v�������ʖڂɉ��ʂƂ�����ʁv�Ǝv���~�܂�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
���̘b�̋����͂Ƃ������A�r�����k�ł���ƁA���ˉ���̎̂Ȃɂ����̒��킵���]�C���̓`�L�ɍڂ��Ă���܂��A�߂������ɂ��ڂɂ����܂��傤�Ɨ[�����\���グ���B
�i���[���i�גʁj�̘b�ɁA���}�G�g�V���ꓝ�̂̂��A�������a�i�k�������j���܂˂ē��{���v�������A���߂����ɂЂ����Ɍ�����B���߂������u�����ꂽ���Ƃ����A������̌�C���ł͎~�߂��ƂĂ��������ꂠ��܂��v�ƉA�ʼn\���Ă���̂��l�l�O�̎��ɓ������B�O�H�ܘY���q��i�������Y���q��j�Ȃǂ͂ǂ��ɂ����Ď~�߂悤�Ǝv�������藧�Ă��Ȃ������B���ɑ\�C���Ƃ�����k�̂��܂���l�����āA���}�̋C�ɓ��肾�����B�ܘY���q��͂��̒j�Ɂu���}�a�������{���v�������ꂽ���A���O�������~�߂���������̏�Ȃ����ł��邼�v�Ɨ��ݍ��ނƁA�u�S���܂����B�܂����Đ\���グ�܂��傤�v�Ƒ]�C���͐����������B
���鎞�A�]�C������O�ɏo���Ƃ��ɁA�u�����ς�������Ƃ͂Ȃ����v�Ɩ����ƁA�����āA�u�ŋߕς�������ƂƂ����A���̍��ȂĂ̊O�ɔ����s���Ă���܂��B�������������������A�s���ɑ吨�l���W�܂��āA���������œq����J���Ă͏����𑈂��Ă���܂��B�ߍ��A�����Ɛ����Ƃ̏�������C�ɂ��悤�ƁA����̂�����ɏW�܂��Ă���Ƃ���ցA���l�ƌ�����R���̂ǂ�����Ƃ��Ȃ�����ď������������Ă���܂����B
�������āw�����l���ɉ��������B�ꏟ�����������x�ƎR���������ƁA�e���O������āw�܂��͌�����������Ȃ����x�ƌ����B�R���A�w����ɂ͋y�Ԃ܂��B���N��̔@�������ɂ���A�����̓q���͂��ׂĉ䂪���ƂȂ낤���A�����炩�͌�����������Ă���x�Ƌ��O�S�����o���Ă�������Ƃ��ď������܂����B���t�Ɉ�킸�R���͑傢�ɏ����܂����č����̋������Ƃ��Ƃ������グ�Ă��܂��܂����B�����̐e���O�A�������قNj����āw���Ȃ��͂ǂ��̍��̕��ł����x�Ɩ₤�ƁA�w���͂��̎R�[�ɏZ�܂��A�V�����v���̂܂܂ɂ��锎��̑�e�����B����܂����x�ƌ����A�����̎҂݂ȍĔq�m�܂��B
����ɎR������Ă��킭�A�w����Ɍ��炸�A���͓V�n���ЂƂ��݂ɂ��A�R������݂ɑ���A�������Ɨ~�����̈����R���Ɠ�����ׁA�������Ɨ~�������̌N�̓�����肻����̌N�̐����ɓ͂��܂Œ����Ȃ�B��Ȃ��Ɨ~���ΓV�n�ɏ[�����A���Ȃ��Ɨ~���Ύϓ��قǂɏ������Ȃ�x�ƌ��܂��ƁA��l�i�ݏo�āA�w���Ă��Đ��ɂ��H�Șb�ł��B���Ƃ��Ă����蓤�قǂɂȂ�̂����������̂ł������܂��x�ƌ�ƁA��u�̂����ɐ��蓤�ƂȂ����Ƃ��������Č��ɓ���A�|���|���Ƃ��ݍӂ��A�w����ň���S���x�Ɗ�Ƃ������Ƃł������܂��v�ƌ�����B
�G�g�傢�Ɋ��S���āA�u���Ă��āA���͈����z����B�]���ߍ����v�����������Ƃ����|�߂��̂��ȁB���O�̌������Ƃ����Ƃ��ł���B�]�͓V����L���Ă���Ƃ����ǂ��A�V���l�̈ʂɂ����Ă��̐E�����������Ă����邪�A�g��ł��Ă͎v�������ʖڂɉ��ʂƂ�����ʁv�Ǝv���~�܂�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
���̘b�̋����͂Ƃ������A�r�����k�ł���ƁA���ˉ���̎̂Ȃɂ����̒��킵���]�C���̓`�L�ɍڂ��Ă���܂��A�߂������ɂ��ڂɂ����܂��傤�Ɨ[�����\���グ���B
183�l�Ԏ����l�N
2022/05/12(��) 18:00:36.77ID:cmrYwXvY �������璷���̉Ɨ��Ɛ������đ����E�q��́A���\�L�]�̔N��ɋy�Ԃ܂ő��߂Ă������A
�ƒ���ꠔ������q�Ƃ�������s�����������B���̎҂́A���͌̔��c���l���i�����j�̋ߏK�ŁA
�����Ȃ�Ҍ́A�����炪�ڂ������Ďg���Ă����B
���鎞�A��������㗎��̎��A�V���@�a�i��P�j���钆���o�������܂̎������q�˂ɂȂ������A
ꠔ������q����A����ɂĎ�荹������Ă���ʂ�A�u�{���G���ƌ�ꏊ�ɂ���ׂ��͂��Ȃ���A
�䏗�V�Ƃ͐\���Ȃ���A�b��Ȃ��䎖�ł���ƁA���̍����\���G���Ă��܂��B�v�ƌ������B
���߂��Ă���đ����E�q��͂��̘b���đ傢�ɓ{��A�Ɠ��̏�����܂ł��������Еt���A
���̏�ł��̂悤�ɑi���o��
�uꠔ������q�ɂ��āA���鍠�A��O�ɂ����ēV���@�l�̌�\��\�����Ə���܂����B
�钆����o�V���ꂽ���́A�L�b�����q�����̋V�����肢������悤�ɂƁA���C������������
�\���グ���̂ł���܂��B�����q���\�����e�ł́A�V���@�l�Ɉ�������点�܂��B�܂����̂悤�ł́A
�C�����̐g�ɂƂ��Ă��傢�ɖ��f�d��܂��B
�R����炱�̂悤�ȕГc�ɂɉ����āA�����q��ɂ��čً��ɗa�������Ƃ��Ă��A����ւ̐\����ɂ�
�Ȃ�܂���B
�����ŁA���͌�ɂ��A�]�˕\�ɎQ��A���V�ɑ��肢�A�V���@�l�p�J�̐\������d��Ȃ���A
�̎�ł���C�����ւ̕�����������܂���I�v
����ɁA�ƘV�̎R�c�ĕ��A��ዷ���傢�ɓ�V���A���X�ɂėl�X�ɐ����������A�đ��͓��S���Ȃ������B
���̂��߈�����ɂ��̎���\���グ��ƁA�������ꠔ������q����X�ɏ�����
�u���̕��̌̎�ł��锹�l���͘Z���ɓ������ɂ��A���̉Ɨ��͓����ӕ��ɏ钆�𗧂��ނ����Ƃ����B
�R��A�V���@�a�̋V�͎����̎��ł��邩��A���O�͒�߂āA����ꓝ�̎�荹����\�����ɉ߂��Ȃ����낤�B
���̕��͔@�˖����C�������Ă���̂�����A�đ����E�q��ւ���ɂ��Ēf���\���č��_�v�����A
���X�Ɏ����ς܂���̂����̕��ׂ̈Ȃ̂�����A�X�������v�炤�悤�ɁB�v
�Ƃ������̂ɁA�����q�͕đ��ɑ�
�u�ߍ��A�����@�̎���A���f���d�点�܂����B�v
�Ƃ̎����q�ׂĎӍ߂��A�đ�������ɂĊ��E�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�ƒ���ꠔ������q�Ƃ�������s�����������B���̎҂́A���͌̔��c���l���i�����j�̋ߏK�ŁA
�����Ȃ�Ҍ́A�����炪�ڂ������Ďg���Ă����B
���鎞�A��������㗎��̎��A�V���@�a�i��P�j���钆���o�������܂̎������q�˂ɂȂ������A
ꠔ������q����A����ɂĎ�荹������Ă���ʂ�A�u�{���G���ƌ�ꏊ�ɂ���ׂ��͂��Ȃ���A
�䏗�V�Ƃ͐\���Ȃ���A�b��Ȃ��䎖�ł���ƁA���̍����\���G���Ă��܂��B�v�ƌ������B
���߂��Ă���đ����E�q��͂��̘b���đ傢�ɓ{��A�Ɠ��̏�����܂ł��������Еt���A
���̏�ł��̂悤�ɑi���o��
�uꠔ������q�ɂ��āA���鍠�A��O�ɂ����ēV���@�l�̌�\��\�����Ə���܂����B
�钆����o�V���ꂽ���́A�L�b�����q�����̋V�����肢������悤�ɂƁA���C������������
�\���グ���̂ł���܂��B�����q���\�����e�ł́A�V���@�l�Ɉ�������点�܂��B�܂����̂悤�ł́A
�C�����̐g�ɂƂ��Ă��傢�ɖ��f�d��܂��B
�R����炱�̂悤�ȕГc�ɂɉ����āA�����q��ɂ��čً��ɗa�������Ƃ��Ă��A����ւ̐\����ɂ�
�Ȃ�܂���B
�����ŁA���͌�ɂ��A�]�˕\�ɎQ��A���V�ɑ��肢�A�V���@�l�p�J�̐\������d��Ȃ���A
�̎�ł���C�����ւ̕�����������܂���I�v
����ɁA�ƘV�̎R�c�ĕ��A��ዷ���傢�ɓ�V���A���X�ɂėl�X�ɐ����������A�đ��͓��S���Ȃ������B
���̂��߈�����ɂ��̎���\���グ��ƁA�������ꠔ������q����X�ɏ�����
�u���̕��̌̎�ł��锹�l���͘Z���ɓ������ɂ��A���̉Ɨ��͓����ӕ��ɏ钆�𗧂��ނ����Ƃ����B
�R��A�V���@�a�̋V�͎����̎��ł��邩��A���O�͒�߂āA����ꓝ�̎�荹����\�����ɉ߂��Ȃ����낤�B
���̕��͔@�˖����C�������Ă���̂�����A�đ����E�q��ւ���ɂ��Ēf���\���č��_�v�����A
���X�Ɏ����ς܂���̂����̕��ׂ̈Ȃ̂�����A�X�������v�炤�悤�ɁB�v
�Ƃ������̂ɁA�����q�͕đ��ɑ�
�u�ߍ��A�����@�̎���A���f���d�点�܂����B�v
�Ƃ̎����q�ׂĎӍ߂��A�đ�������ɂĊ��E�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
184�l�Ԏ����l�N
2022/05/13(��) 16:58:04.81ID:uwclWyl4 �u��F���p�L�v���u�M�����@�S���тƂ������n��L����킳��鎖�v
�i�\�̖��A�M�������V���̌��������邱�ƂƂȂ�A�Ђ��C���ɐU�邤���ƂƂȂ������߁A��F�@�ٌ��͖L�ォ���j���̎g�҂𑗂����B
���̂̂��M��������S���тƂ������n��L��Ɍ��킳��邱�ƂƂȂ����B
���̔n�͐q��̔n���y���ɒ�����Ŕ��A�㐡�قǂ���A���������������������B
��͎���������悤�ŁA�����{��A��ɂ��ȂȂ��A�����݂��A�l�ɂ��n�ɂ��H�炢���悤�������̂ŁA�S���тƖ��t����ꂽ�B
�@�ٌ��͂��̔n��N�ɏ�点�悤���ƍl�����Ƃ���A���}���Y����v���@�Ƃ����A���Ƃ��Ƌ`�P�����̎�������A���̎q���ő�w���q(��F���p�L�ɂ���恂͐���)�Ƃ������̂��r�n���̒B�l�ł������B
���}����w���q�ł͂Ȃ��Ă͏�肱�Ȃ����Ȃ����낤�Ƃ������ƂŁA�����ɏ�邱�ƂɂȂ����B
�S���т͋����ւ̈ƁA�g�̑�[�ɐ^�g�̓���A�ɐl���l�������A���̂ق��ɍj���{���Čv�\�l�Ŕn��Ɉ����Ă��������B
�S���т͌D�����ݐ��Ă��ȂȂ��Ă���Ă����B
�@�ٌ��͂��ߏ������̂ق����l���������ɂ���Ă��Č���钆�A��w���q�т͔��������ɂ�����̏㉺�A���̂̂��t���ɂ����召�������āA�Z�ڂ��܂�̋��̂ł���Ƒł�������B
��j�A�ƁA�Z�Ȃǂ�Ꭾ�̂��Ƃ��ɂ��āA���Ղ��瑁�삯�����A���݂ɑ������B
�̂��ɂ͋ȏ��̔�p�������A��q�܂�����A��Ղ̏�Ɏl�̒����k�߂ė���������A
���邢�͕ڂ̌��������ɓ����̂āA���̌䂠�܂�̕����z�������A�ڂ̏���܂������ɂ����������肵���B
�@�ٌ��͌䗗�ɂȂ芴������A���e�̐��@���ւ��܂��܂ȖJ����^�����B
�S���т͑�w���q����肱�Ȃ������߁A��葬���삯��悤�ɂȂ��B��̖��n�ƂȂ����B
���ɓ��Ɍ����l�͑����Ȃ�A�����]�̔n����A�l���l�܉������₷����������悤�ȏr���ł������B
���̌�A�n�p�̏��Ȃ��̂����l�����킵�����A�\�l�Ɉ�l����l�͍������낷���̂́A�n�����ݏo���O�ɒ��߂Ă��܂��A
���̂ق��̔��A��l�͔n�����������ŋ���ď��Ȃ������B
�������đ�w���q�͎��R���݂̌�҂Ƃ��Ė��_�ɗa�������B
�X�ɕʓ��̗Y�閳���
�u��̔n�ł���Ή��Ƃ����ς��Ȃ��悤�Ɍ����邪�A���̋S���т���͏�肾���ł͂Ȃ��͏��łȂ���Ώ�肱�Ȃ��Ȃ��B
��w���q�̗͔͂n�����܂���A���������̂��߂��̂悤�ɏ�肱�Ȃ���̂��낤�v
�Ɛ\���������ł���B
�i�\�̖��A�M�������V���̌��������邱�ƂƂȂ�A�Ђ��C���ɐU�邤���ƂƂȂ������߁A��F�@�ٌ��͖L�ォ���j���̎g�҂𑗂����B
���̂̂��M��������S���тƂ������n��L��Ɍ��킳��邱�ƂƂȂ����B
���̔n�͐q��̔n���y���ɒ�����Ŕ��A�㐡�قǂ���A���������������������B
��͎���������悤�ŁA�����{��A��ɂ��ȂȂ��A�����݂��A�l�ɂ��n�ɂ��H�炢���悤�������̂ŁA�S���тƖ��t����ꂽ�B
�@�ٌ��͂��̔n��N�ɏ�点�悤���ƍl�����Ƃ���A���}���Y����v���@�Ƃ����A���Ƃ��Ƌ`�P�����̎�������A���̎q���ő�w���q(��F���p�L�ɂ���恂͐���)�Ƃ������̂��r�n���̒B�l�ł������B
���}����w���q�ł͂Ȃ��Ă͏�肱�Ȃ����Ȃ����낤�Ƃ������ƂŁA�����ɏ�邱�ƂɂȂ����B
�S���т͋����ւ̈ƁA�g�̑�[�ɐ^�g�̓���A�ɐl���l�������A���̂ق��ɍj���{���Čv�\�l�Ŕn��Ɉ����Ă��������B
�S���т͌D�����ݐ��Ă��ȂȂ��Ă���Ă����B
�@�ٌ��͂��ߏ������̂ق����l���������ɂ���Ă��Č���钆�A��w���q�т͔��������ɂ�����̏㉺�A���̂̂��t���ɂ����召�������āA�Z�ڂ��܂�̋��̂ł���Ƒł�������B
��j�A�ƁA�Z�Ȃǂ�Ꭾ�̂��Ƃ��ɂ��āA���Ղ��瑁�삯�����A���݂ɑ������B
�̂��ɂ͋ȏ��̔�p�������A��q�܂�����A��Ղ̏�Ɏl�̒����k�߂ė���������A
���邢�͕ڂ̌��������ɓ����̂āA���̌䂠�܂�̕����z�������A�ڂ̏���܂������ɂ����������肵���B
�@�ٌ��͌䗗�ɂȂ芴������A���e�̐��@���ւ��܂��܂ȖJ����^�����B
�S���т͑�w���q����肱�Ȃ������߁A��葬���삯��悤�ɂȂ��B��̖��n�ƂȂ����B
���ɓ��Ɍ����l�͑����Ȃ�A�����]�̔n����A�l���l�܉������₷����������悤�ȏr���ł������B
���̌�A�n�p�̏��Ȃ��̂����l�����킵�����A�\�l�Ɉ�l����l�͍������낷���̂́A�n�����ݏo���O�ɒ��߂Ă��܂��A
���̂ق��̔��A��l�͔n�����������ŋ���ď��Ȃ������B
�������đ�w���q�͎��R���݂̌�҂Ƃ��Ė��_�ɗa�������B
�X�ɕʓ��̗Y�閳���
�u��̔n�ł���Ή��Ƃ����ς��Ȃ��悤�Ɍ����邪�A���̋S���т���͏�肾���ł͂Ȃ��͏��łȂ���Ώ�肱�Ȃ��Ȃ��B
��w���q�̗͔͂n�����܂���A���������̂��߂��̂悤�ɏ�肱�Ȃ���̂��낤�v
�Ɛ\���������ł���B
185�l�Ԏ����l�N
2022/05/14(�y) 14:09:06.03ID:p90IDzup �i���Ɠ��V�i�s�L�j�Ƃ��̎q�O�Z��̐ؕ��̌�j��䏊�i����ƍN�j�͓����ɓ���ꂽ���A���̎�
����V�V�C�͏��m�������A���O�ɏo�A
�u���Ɠ��V���͌�G�𐬂�����Ɉ˂��āA���̎q�����E�Q���ꂽ���Ƃ͌䗝�ł���܂��B
�ł����A���̏��m�͂��̓��V�̎q�i�O�j�j�ł���܂����A�ّm�̒�q�ƂȂ�\���܂����B�ł��̂ŁA
�����Ɖ�����ׂ��B�v�ƌ������B
�ƍN���͂��̎|����
�u���Ƃ���N�̉����ׂɈꖽ���̂Ă��̂�����A�o�Ƃ������q���ɍ߂������铹���͂Ȃ��B
�S�����v���悤�ɁB�v
�Ƌ��ɂȂ����B
����L�ɁA���̏��m�͓���V�V�C�ɏ]���āA���B���b�R�ɋ����B���̍��A���b�R���i���ɂ͈�l�̘Q�l��
�݂����̂����A��ɋ������A�����Ė{�V�ؓ������B����Ɏ����H�͌����ɋy���A������m��
�������������A���V���̎O�j�̎�m�͂��̋��l��g�ݕ����A����������D��������B
��ɁA�R�鍑�����R�N�y���̏Z���ƂȂ����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
����V�V�C�͏��m�������A���O�ɏo�A
�u���Ɠ��V���͌�G�𐬂�����Ɉ˂��āA���̎q�����E�Q���ꂽ���Ƃ͌䗝�ł���܂��B
�ł����A���̏��m�͂��̓��V�̎q�i�O�j�j�ł���܂����A�ّm�̒�q�ƂȂ�\���܂����B�ł��̂ŁA
�����Ɖ�����ׂ��B�v�ƌ������B
�ƍN���͂��̎|����
�u���Ƃ���N�̉����ׂɈꖽ���̂Ă��̂�����A�o�Ƃ������q���ɍ߂������铹���͂Ȃ��B
�S�����v���悤�ɁB�v
�Ƌ��ɂȂ����B
����L�ɁA���̏��m�͓���V�V�C�ɏ]���āA���B���b�R�ɋ����B���̍��A���b�R���i���ɂ͈�l�̘Q�l��
�݂����̂����A��ɋ������A�����Ė{�V�ؓ������B����Ɏ����H�͌����ɋy���A������m��
�������������A���V���̎O�j�̎�m�͂��̋��l��g�ݕ����A����������D��������B
��ɁA�R�鍑�����R�N�y���̏Z���ƂȂ����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
186�l�Ԏ����l�N
2022/05/15(��) 18:59:32.65ID:Davxrel8 �z��̑�֏��ɑ�����Ƃ����l���������B
�������N�̍��A�[��r��������Ă����Ƃ���A�Α����䶔��̒�������̂��E���Ă͌��ɓ���Ă��鏗�������B
����U�藐���A���͍����A�S�����Ǝv�����������ߊ�낤�Ƃ����Ƃ���A���͓ˑR�����o�����B
����߂܂����������u�Ȃ��l����H�ׂ�̂��I�v�Ɛq�˂��Ƃ���A���́u�����ĉ��������̂ł͂���܂���B䶔��̉œS���i�������j�����߂�Ɣ����Ȃ��Ȃ�ƕ����Ă������Ă���̂ł��v�ƉΒ����炨��������ꂽ��������o���Ă݂����B
�����͂��̍��_���Ɋ����āA�����ȂƂ����B
�����ē�l�̊Ԃɐ��܂ꂽ���q��펵�Ɩ��t�����B
��̐�������e���ł���B
�������N�̍��A�[��r��������Ă����Ƃ���A�Α����䶔��̒�������̂��E���Ă͌��ɓ���Ă��鏗�������B
����U�藐���A���͍����A�S�����Ǝv�����������ߊ�낤�Ƃ����Ƃ���A���͓ˑR�����o�����B
����߂܂����������u�Ȃ��l����H�ׂ�̂��I�v�Ɛq�˂��Ƃ���A���́u�����ĉ��������̂ł͂���܂���B䶔��̉œS���i�������j�����߂�Ɣ����Ȃ��Ȃ�ƕ����Ă������Ă���̂ł��v�ƉΒ����炨��������ꂽ��������o���Ă݂����B
�����͂��̍��_���Ɋ����āA�����ȂƂ����B
�����ē�l�̊Ԃɐ��܂ꂽ���q��펵�Ɩ��t�����B
��̐�������e���ł���B
187�l�Ԏ����l�N
2022/05/15(��) 20:02:59.75ID:w74wCBni �z��ɂ�������������������
�������z��s�̊J�Í����
�������z��s�̊J�Í����
188�l�Ԏ����l�N
2022/05/17(��) 16:15:21.99ID:g40oUKwA ����L�ɁA���o�H��i�����j�����R�Ƃ����ݎQ�点�āA�Ȃ��h�����Ă��������A���{�̎����̐l�X��
���c���āA�o�H��̘V�b�̌��ɕ������āA
�w������l�A�t���̍ߓق��ׂ��炸�A���̉Ɛ₦������v��A������l�Ɋ��߂Ď��Q������B
�������ɉ����ẮA���p���𗧂Ă邾�낤�B�x
�Ƃ����|�����m���ׂ��Ƌc�肵���B
���̎��A�{������i�����j�͐l�X�Ɍ�����
�u���ɉƘV����l�ɕ���点���ꍇ�A���̉Ƃ𑶑�������̂��v�Ɩ₤���B
�l�X�́u�ǂ����Ă��̖d���l�̉Ƃ𑶑������邾�낤���B�v�Ɠ������B
�����͂�����Ɓu�R��A���̕�������邱�ƁA�R��ׂ��炸�B
���o�H��̕s�b���邽�߂ɁA���̐b�ɕs�b�����߂�ȂǁA�V���̉��m�ɗL��ׂ����Ƃ��v��ꂸ�B
���₩�ɌR���������������n������ׂ����̂ł���I
�l�b�ւ̋����Ƃ��ׂ��ł͖��������q�ׂāA�U���s���A�V���̕����𗐂��ׂ��ł͂Ȃ��I�v
�������������A�O�c�ꌈ���Ȃ��������߁A�u�����̘A�������ׂ��炸�I�v�Ə��������ۂ����Ƃ����B
�V�䔒�ΐ搶�H���A�u�{�������̑����͔@���ɂ�����A���̈ꌾ�͓V���̖����ƌ����ׂ��ł���B�v��
�]�����A�����A�n��@����A��ɔނɊ��������Ă����Ƃ����B
���ɂ��̈ꌾ���ȂČ���ɁA���̐l���Ⴂ�������䏊�̌�o�����ǂ������Ƃ����̂��ނׂȂ邩�ȁB
�܂��A�ނ����E�̐l�X�Ƃ̊W���s���ł������Ƃ��������A�����Ēm�鎖���ł���B
�i�V���Ӂj
���c���āA�o�H��̘V�b�̌��ɕ������āA
�w������l�A�t���̍ߓق��ׂ��炸�A���̉Ɛ₦������v��A������l�Ɋ��߂Ď��Q������B
�������ɉ����ẮA���p���𗧂Ă邾�낤�B�x
�Ƃ����|�����m���ׂ��Ƌc�肵���B
���̎��A�{������i�����j�͐l�X�Ɍ�����
�u���ɉƘV����l�ɕ���点���ꍇ�A���̉Ƃ𑶑�������̂��v�Ɩ₤���B
�l�X�́u�ǂ����Ă��̖d���l�̉Ƃ𑶑������邾�낤���B�v�Ɠ������B
�����͂�����Ɓu�R��A���̕�������邱�ƁA�R��ׂ��炸�B
���o�H��̕s�b���邽�߂ɁA���̐b�ɕs�b�����߂�ȂǁA�V���̉��m�ɗL��ׂ����Ƃ��v��ꂸ�B
���₩�ɌR���������������n������ׂ����̂ł���I
�l�b�ւ̋����Ƃ��ׂ��ł͖��������q�ׂāA�U���s���A�V���̕����𗐂��ׂ��ł͂Ȃ��I�v
�������������A�O�c�ꌈ���Ȃ��������߁A�u�����̘A�������ׂ��炸�I�v�Ə��������ۂ����Ƃ����B
�V�䔒�ΐ搶�H���A�u�{�������̑����͔@���ɂ�����A���̈ꌾ�͓V���̖����ƌ����ׂ��ł���B�v��
�]�����A�����A�n��@����A��ɔނɊ��������Ă����Ƃ����B
���ɂ��̈ꌾ���ȂČ���ɁA���̐l���Ⴂ�������䏊�̌�o�����ǂ������Ƃ����̂��ނׂȂ邩�ȁB
�܂��A�ނ����E�̐l�X�Ƃ̊W���s���ł������Ƃ��������A�����Ēm�鎖���ł���B
�i�V���Ӂj
189�l�Ԏ����l�N
2022/05/17(��) 16:37:38.40ID:pgI56b42 �R���ĉ��Ƃ����悤�Ƃ���G���C������ă�����
190�l�Ԏ����l�N
2022/05/18(��) 21:31:30.49ID:dj1xSr2p �ŋL���ۏ\�l�N�l���\�O���̋L������@�D���ƃ��N������
���̌�̎l���R�b�̂��łɁi�����l���b���ꂽ�j�u���N�����ՂƂ��������̒����ꂪ����B���̎Ȃ��̂����̗R���Ƃ����B�D�����N���ƒ��̓���������A�鑠�̒�����𒃖V��ɕЕt���������Ƃ���A���V�傪������̂Ȃ��Ɏw�����Ē���@���Ă������A�w���ǂ�����Ă������Ȃ��̂ŁA���@�������Ďw�����B������܂ƈꏏ�ɐD���̑O�ɏo���A�w������̎�Ɛl�Ԃ̎�Ƃ��A�܂�������ւ��ɂ͂Ȃ���Ȃ��ł��傤�x�Ɛ\�����Ƃ����b���B���̒�����͖����L�ɂ��ڂ��Ă���v
���̌�̎l���R�b�̂��łɁi�����l���b���ꂽ�j�u���N�����ՂƂ��������̒����ꂪ����B���̎Ȃ��̂����̗R���Ƃ����B�D�����N���ƒ��̓���������A�鑠�̒�����𒃖V��ɕЕt���������Ƃ���A���V�傪������̂Ȃ��Ɏw�����Ē���@���Ă������A�w���ǂ�����Ă������Ȃ��̂ŁA���@�������Ďw�����B������܂ƈꏏ�ɐD���̑O�ɏo���A�w������̎�Ɛl�Ԃ̎�Ƃ��A�܂�������ւ��ɂ͂Ȃ���Ȃ��ł��傤�x�Ɛ\�����Ƃ����b���B���̒�����͖����L�ɂ��ڂ��Ă���v
191�l�Ԏ����l�N
2022/05/19(��) 12:49:07.64ID:1Lx5XXEG ����O�ɕ��Ă��ꂽ��w��藎�Ƃ����̂ɂ�
192�l�Ԏ����l�N
2022/05/19(��) 23:13:26.62ID:ra+2wtGb �ŋL���ۏ\��N�\���\�ܓ��̋L������@���X�@�a�Ɖ����^
����吅��o����C�@�a�i�����@�e���j�ɂ������b���\���グ���B�u�́A�����z����͕��ГV���ɉB��Ȃ��҂��������A���̓��̂��Ƃ͂��قǐ��ɕ������Ă���܂���ł����B���鎞�A���X�@�a�ɒ��̓������]���āA�r���ܒQ���āA�w�@�a�̒��͖��l�ƌ����ׂ��ł���B���͒��̓������]�����̂ł͂Ȃ��B���̋C�̂Ђ��ς�Ƃ�����������Ɨ~�����䂦�ł���B�ʂ��ƒY��������ė���ꂽ�Ƃ��납���炳���Ƃ���܂ŁA������Ζ������悤�Ƒ_���Ă������A�C�������Ă��Ĉ�т̓��錄���Ȃ��A���ɖ������邱�Ƃ��o���Ȃ������x�ƌ���������ł��B���ɂ����ł������Ə���y��ł��܂��v������o����C�@�a�Ɍ��ƁA�u���ɂ����ł������낤�v�Ə�C�@�a�͑傢�Ɋ�������ꂽ�B
�u�Ђ��ς�v�u�ʂ��Ɓv�͌����}�}�B�ʔ����\���Ȃ̂Ŗ����̂܂܂ŁB
�����z����ɂ͓K������l�������Ȃ��̂ŁA���O�����ʂɌ�肪����̂͊m���B�����z����͔�O��Ƃ��Ă���ٖ{�����邻���ŁA��g�̓��{�ÓT���w��n�̋ߐ����z�W�ł́A��O��͔���̌��Ő����̂��Ƃ��Ƃ��Ă���B�����Ə@�a�ł͔N����Ȃ藣��Ă���̂ŁA���邢�͐����Ə@�a�̕��d�Ƃ̘b���B�E�B�L�y�f�B�A�̏@�a�̍��ł͉������Ƃ̘b�Ƃ��Ă��邪�A���͏o�H��ŁA�o�T��������Ă��Ȃ��B
����吅��o����C�@�a�i�����@�e���j�ɂ������b���\���グ���B�u�́A�����z����͕��ГV���ɉB��Ȃ��҂��������A���̓��̂��Ƃ͂��قǐ��ɕ������Ă���܂���ł����B���鎞�A���X�@�a�ɒ��̓������]���āA�r���ܒQ���āA�w�@�a�̒��͖��l�ƌ����ׂ��ł���B���͒��̓������]�����̂ł͂Ȃ��B���̋C�̂Ђ��ς�Ƃ�����������Ɨ~�����䂦�ł���B�ʂ��ƒY��������ė���ꂽ�Ƃ��납���炳���Ƃ���܂ŁA������Ζ������悤�Ƒ_���Ă������A�C�������Ă��Ĉ�т̓��錄���Ȃ��A���ɖ������邱�Ƃ��o���Ȃ������x�ƌ���������ł��B���ɂ����ł������Ə���y��ł��܂��v������o����C�@�a�Ɍ��ƁA�u���ɂ����ł������낤�v�Ə�C�@�a�͑傢�Ɋ�������ꂽ�B
�u�Ђ��ς�v�u�ʂ��Ɓv�͌����}�}�B�ʔ����\���Ȃ̂Ŗ����̂܂܂ŁB
�����z����ɂ͓K������l�������Ȃ��̂ŁA���O�����ʂɌ�肪����̂͊m���B�����z����͔�O��Ƃ��Ă���ٖ{�����邻���ŁA��g�̓��{�ÓT���w��n�̋ߐ����z�W�ł́A��O��͔���̌��Ő����̂��Ƃ��Ƃ��Ă���B�����Ə@�a�ł͔N����Ȃ藣��Ă���̂ŁA���邢�͐����Ə@�a�̕��d�Ƃ̘b���B�E�B�L�y�f�B�A�̏@�a�̍��ł͉������Ƃ̘b�Ƃ��Ă��邪�A���͏o�H��ŁA�o�T��������Ă��Ȃ��B
193�l�Ԏ����l�N
2022/05/20(��) 11:21:24.27ID:0N1cL2JJ �������ƌ��߂Ċ|�����Ă邩��l�@�����������Ȃ�
���������w�҂��s���l�܂����Ƃ��ɂ��̂͝s����
�`������������
���������w�҂��s���l�܂����Ƃ��ɂ��̂͝s����
�`������������
194�l�Ԏ����l�N
2022/05/22(��) 20:19:15.64ID:U8GqlHSQ �u����G�ځv����G���փ����r��̏�c�U�߂̎��̘b
�c���ܔN�㌎�����A�G�����͖{�c���n��(���M)�������āA��������^�c���ɐ����Đ�������ꕔ�n�I�����������Ƃ���
���n��u��v�ے��ׂ�q��N���̔z���̎҂ǂ������m�Ȃ�����i�߂��̂͏�������ׂ��ł��B
�R�@��j����͕̂s���ł���A�s���̎҂͂��̍߂�܂���B
��v�ہE�q��̕����ɕ���点��ׂ��ł��v
�ƊЂ߂��Ƃ���A�G���������ӂ��ꂽ���߁A��v�ہE�q��ɂ��̎|�������n�����B
���l�͎d���Ȃ��Ɛl�ɕ���点�悤�Ƃ����Ƃ���A�q��N���̑��q�A�V���Y(�q�쒉��)��
�u�蕿�𗧂Ă��Ɨ��ɕ���点�ẮA�N���g�����̂Ăē����ł��傤���v
�Ɠƒf�Ƃ������Ƃɂ��āA�����|���������A��Đw���𗧂��ނ��Ă��܂����B
����ɂ��N�����N�ǂ��Ă������A�G������N�a���ɂ��V���Y�͌�͖Ƃ���A�N�������̂悤�ɏo�d�����B
�V���Y�������ނ����ƕ�������v�ے��ׂ̑��q�̐V�\�Y(��v�ے���)���A����s�̐��Y�y���q��v���������A��ďo�z���悤�Ƃ������A
�y���q��͏��������u��u�͐g�ɗ]��܂����A�䂪�����~�����߂Ɍ��N���Q�l����Ƃ����͖̂{�ӂł͂���܂���B���͋`�����y���̂ł��v
�ƌ����Ă����܂����Q���Ă��܂����B
���Y�̒��j�⎟�j�̖��͏������A���j�E�����v�v���͂̂��ɑ�v�ے���Ɏd���A
���j�E�\���q�v�^�́A�y���q��̎u���������͂��ɂȂ����G�����ɏ����o���ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
�c���ܔN�㌎�����A�G�����͖{�c���n��(���M)�������āA��������^�c���ɐ����Đ�������ꕔ�n�I�����������Ƃ���
���n��u��v�ے��ׂ�q��N���̔z���̎҂ǂ������m�Ȃ�����i�߂��̂͏�������ׂ��ł��B
�R�@��j����͕̂s���ł���A�s���̎҂͂��̍߂�܂���B
��v�ہE�q��̕����ɕ���点��ׂ��ł��v
�ƊЂ߂��Ƃ���A�G���������ӂ��ꂽ���߁A��v�ہE�q��ɂ��̎|�������n�����B
���l�͎d���Ȃ��Ɛl�ɕ���点�悤�Ƃ����Ƃ���A�q��N���̑��q�A�V���Y(�q�쒉��)��
�u�蕿�𗧂Ă��Ɨ��ɕ���点�ẮA�N���g�����̂Ăē����ł��傤���v
�Ɠƒf�Ƃ������Ƃɂ��āA�����|���������A��Đw���𗧂��ނ��Ă��܂����B
����ɂ��N�����N�ǂ��Ă������A�G������N�a���ɂ��V���Y�͌�͖Ƃ���A�N�������̂悤�ɏo�d�����B
�V���Y�������ނ����ƕ�������v�ے��ׂ̑��q�̐V�\�Y(��v�ے���)���A����s�̐��Y�y���q��v���������A��ďo�z���悤�Ƃ������A
�y���q��͏��������u��u�͐g�ɗ]��܂����A�䂪�����~�����߂Ɍ��N���Q�l����Ƃ����͖̂{�ӂł͂���܂���B���͋`�����y���̂ł��v
�ƌ����Ă����܂����Q���Ă��܂����B
���Y�̒��j�⎟�j�̖��͏������A���j�E�����v�v���͂̂��ɑ�v�ے���Ɏd���A
���j�E�\���q�v�^�́A�y���q��̎u���������͂��ɂȂ����G�����ɏ����o���ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
195�l�Ԏ����l�N
2022/05/22(��) 23:42:55.82ID:N8u6mvGT �ŋL���ۏ\�O�N�����\����̋L�����@�؉����r�Ət����
�����q�͗��X�̎҂ƌ�����B�����o�̘b�ɁB
�́A�t���ǂ��㗌��������ɁA�q���h�炪���U�����ċ_���̐����֎Q�������A�������i��o�j�͏\�O�ł����d�������A��̉��̍��|���Ɉꓯ���|���đ���܊サ�Ă����Ƃ���A���̑�ő������Ă����F���u�t���ǂ����āA�u���ɋv�������Ƃ��ڂɂ������Ă���܂���ł������A���オ��Ȃ���悵������܂��āA�����������F�삩��Q�����Ƃ���ŁA�����䈥�A�\���グ�܂���ł����v�Ɛ\���A
�u���̓�̐\���ʂ�ł��B�̂����č��ӂɂ��Ă���̂ł����A���̌��m���̂�����ɏZ�����Ă���Ƃ̂悵�A���h��l����X���ڂɂ����ĉ������܂��B���̎҂Ɖ���ĂӂƎv���o���܂������A�����l�̂����������R�͂��̋߂��ɂ������܂��̂ŁA�Q��Ă�������������܂��v�ƁA����A��Ă�����Ɍ�����ꂽ�B���h��́A�����͓��{�莛�̖�傪��l�ɂȂ��ċ_���тʼn��Ȃ��đ҂��Ă���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�ꑫ��ɂɂ�����Ɍ�����ꂽ�B
���āA�����q�̂Ƃ���֎Q��ƁA�����͎��q�̌y���ŋC�y�ɉ����ɏo�āA�u�悭�����������������B��K�̕����i�F���ǂ�����オ�苋���B���̈�t���U�镑���ׂ������A���Ȃ��̂������̒��̕����㓙�ł��傤�v�ƌ������B���ٓ��Ȃǂ���K�֏グ�Ď�q�Ƃ��Ɋy���܂ꂽ���A���h�炩��u���{�莛�̖�傪���҂����˂ł��B�������o�ʼn������v�Ɗ��x���g�����Q�����̂ŁA�����A��ꂽ�B�ނ̏t���ǂɑ���ԓx�͂܂�Ŏ�l�ł��邩�̂悤�������B
���āA�_���֎Q��ƁA�ш�ʂɏ��~���Đ��܂̒�d���т��������A�����̌����s�����ꂽ���ƌ���ɐ₵�Ă����B������o���\���グ��ƁA�����l���A���̂悤�Șb�������Ƃ�����Ƌ�ꂽ�B
�����q�͗��X�̎҂ƌ�����B�����o�̘b�ɁB
�́A�t���ǂ��㗌��������ɁA�q���h�炪���U�����ċ_���̐����֎Q�������A�������i��o�j�͏\�O�ł����d�������A��̉��̍��|���Ɉꓯ���|���đ���܊サ�Ă����Ƃ���A���̑�ő������Ă����F���u�t���ǂ����āA�u���ɋv�������Ƃ��ڂɂ������Ă���܂���ł������A���オ��Ȃ���悵������܂��āA�����������F�삩��Q�����Ƃ���ŁA�����䈥�A�\���グ�܂���ł����v�Ɛ\���A
�u���̓�̐\���ʂ�ł��B�̂����č��ӂɂ��Ă���̂ł����A���̌��m���̂�����ɏZ�����Ă���Ƃ̂悵�A���h��l����X���ڂɂ����ĉ������܂��B���̎҂Ɖ���ĂӂƎv���o���܂������A�����l�̂����������R�͂��̋߂��ɂ������܂��̂ŁA�Q��Ă�������������܂��v�ƁA����A��Ă�����Ɍ�����ꂽ�B���h��́A�����͓��{�莛�̖�傪��l�ɂȂ��ċ_���тʼn��Ȃ��đ҂��Ă���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�ꑫ��ɂɂ�����Ɍ�����ꂽ�B
���āA�����q�̂Ƃ���֎Q��ƁA�����͎��q�̌y���ŋC�y�ɉ����ɏo�āA�u�悭�����������������B��K�̕����i�F���ǂ�����オ�苋���B���̈�t���U�镑���ׂ������A���Ȃ��̂������̒��̕����㓙�ł��傤�v�ƌ������B���ٓ��Ȃǂ���K�֏グ�Ď�q�Ƃ��Ɋy���܂ꂽ���A���h�炩��u���{�莛�̖�傪���҂����˂ł��B�������o�ʼn������v�Ɗ��x���g�����Q�����̂ŁA�����A��ꂽ�B�ނ̏t���ǂɑ���ԓx�͂܂�Ŏ�l�ł��邩�̂悤�������B
���āA�_���֎Q��ƁA�ш�ʂɏ��~���Đ��܂̒�d���т��������A�����̌����s�����ꂽ���ƌ���ɐ₵�Ă����B������o���\���グ��ƁA�����l���A���̂悤�Șb�������Ƃ�����Ƌ�ꂽ�B
196�l�Ԏ����l�N
2022/05/23(��) 19:42:12.20ID:tGyeQDo6 �u����G�ځv���A���c���펞�̌˓c����(�˓c�ꐼ)�̐i��
�c���ܔN(1600�N)�㌎��\�O���̖�A�{�c����(����)����
�u���{��(�ƍN)�A�䎝�a�����������܂����̂ŁA�����G�����Ɍ�ΖʂȂ����܂��B
�܂����x�䋟�ɏ����A�ꂽ�ʁX�ɂ���ڌ��̌䍹��������܂��v
�Ɛ\�����肳�ꂽ���߁A�����G�����͑�Â̏�ɕ����Ȃ����āA�ƍN���ƌ�Ζʂ��ꂽ�B
�䋟�ɏ����A�ꂽ�y�����O�ɂЂ��ꂽ�B
�G�����u�փ����ɒx�Q���Ă��܂��A��̌���ɎQ���ł����A����f�ɂ��ڂ��߂���Ă��邱�Ƃł��傤�v
�ƍN���u�Q�w�̎��߂�\���グ���g�҂������������ȏ�A���������̂Ȃ����Ƃł��邪�A
�����ēV�������ڂ̐�Ƃ������͈̂͌�̏����Ɠ������ƂŁA��ɂ������ĂA������ɐ������炠�낤������̗p�ɂ͂����ʂ��̂ł���B
����ꂪ�փ����̈��ɑł����Ȃ�A�^�c���Ƃ��̏��g�҂������ɏ�����łɂ��悤�ƁA���ǂ͏�𖾂��n���č~�Q������ق��ɂȂ��̂��B
���O�̌��ɍT���Ă���҂ǂ��̂����ɁA���̂悤�ɐ\�����҂͈�l�����Ȃ������̂��H�v�Ɛq�˂�ꂽ�B
�G�������u�������Ƃ��˓c����(�ꐼ)���\���Ă���܂����v
�Ƌ�ꂽ�Ƃ���A
�ƍN���́u�Ȃ�Ɛ\�����̂��H�v�Əd�˂Ă��q�˂ɂȂ����̂�
�G�����͍���̐i���̈ύׂ���ꂽ�B
�ƍN���͌�Ɛl����̕����䗗�Ȃ��荶��������ꂽ���A�����ɂ������ߕ������Ȃ������̂��������Ȃ������B
�����ŏG�����͐����Ɂu���{���͍�������������I�v�Ƌ���ƁA����͂�����O�߂��ɏo���B
�ƍN���͂����ɏ����A�䗼��ɂ��َq���R����ɂ������A���肸���炨�َq������
�ƍN���u���̕��A���g�ɂČ��������ʂ��A�����Ɍ��������悤�ɂ��Ă�낤�v�Ƃ�����������B
����͂��܂�̂��肪�����ɂ���������Ȃ���������
�G����������Ɂu����ł����A���������̌�ӂ������ނ�A���������Ȃ������킹�ɑ����Ă���܂��v�Ƌ�ꂽ�Ƃ����B
�c���ܔN(1600�N)�㌎��\�O���̖�A�{�c����(����)����
�u���{��(�ƍN)�A�䎝�a�����������܂����̂ŁA�����G�����Ɍ�ΖʂȂ����܂��B
�܂����x�䋟�ɏ����A�ꂽ�ʁX�ɂ���ڌ��̌䍹��������܂��v
�Ɛ\�����肳�ꂽ���߁A�����G�����͑�Â̏�ɕ����Ȃ����āA�ƍN���ƌ�Ζʂ��ꂽ�B
�䋟�ɏ����A�ꂽ�y�����O�ɂЂ��ꂽ�B
�G�����u�փ����ɒx�Q���Ă��܂��A��̌���ɎQ���ł����A����f�ɂ��ڂ��߂���Ă��邱�Ƃł��傤�v
�ƍN���u�Q�w�̎��߂�\���グ���g�҂������������ȏ�A���������̂Ȃ����Ƃł��邪�A
�����ēV�������ڂ̐�Ƃ������͈̂͌�̏����Ɠ������ƂŁA��ɂ������ĂA������ɐ������炠�낤������̗p�ɂ͂����ʂ��̂ł���B
����ꂪ�փ����̈��ɑł����Ȃ�A�^�c���Ƃ��̏��g�҂������ɏ�����łɂ��悤�ƁA���ǂ͏�𖾂��n���č~�Q������ق��ɂȂ��̂��B
���O�̌��ɍT���Ă���҂ǂ��̂����ɁA���̂悤�ɐ\�����҂͈�l�����Ȃ������̂��H�v�Ɛq�˂�ꂽ�B
�G�������u�������Ƃ��˓c����(�ꐼ)���\���Ă���܂����v
�Ƌ�ꂽ�Ƃ���A
�ƍN���́u�Ȃ�Ɛ\�����̂��H�v�Əd�˂Ă��q�˂ɂȂ����̂�
�G�����͍���̐i���̈ύׂ���ꂽ�B
�ƍN���͌�Ɛl����̕����䗗�Ȃ��荶��������ꂽ���A�����ɂ������ߕ������Ȃ������̂��������Ȃ������B
�����ŏG�����͐����Ɂu���{���͍�������������I�v�Ƌ���ƁA����͂�����O�߂��ɏo���B
�ƍN���͂����ɏ����A�䗼��ɂ��َq���R����ɂ������A���肸���炨�َq������
�ƍN���u���̕��A���g�ɂČ��������ʂ��A�����Ɍ��������悤�ɂ��Ă�낤�v�Ƃ�����������B
����͂��܂�̂��肪�����ɂ���������Ȃ���������
�G����������Ɂu����ł����A���������̌�ӂ������ނ�A���������Ȃ������킹�ɑ����Ă���܂��v�Ƌ�ꂽ�Ƃ����B
197�l�Ԏ����l�N
2022/05/23(��) 21:21:46.50ID:pFEDWaRQ �ŋL���ۏ\��N�܌��\�����̋L�����@���B�ƍ��c����
���̍����肪�b������A�O�̘b�̒��ɁB
�u�̒}�O��i���c�����j�͌É��B�̖�l�łƂ�킯�����ɔM�S�ł��������A���鎞�]�˂Œ}�O�炪���B�ɁA�w���x�A�D���Ƃ����ǂ��A���ɂ͂���͌��ȕ����A�ǂ�������ł���Ȃ��Ƃ������̂��Ǝv�����Ƃ�����܂������A���B�̂Ȃ���邱�Ƃ͈�Ƃ��Č��炵�����Ƃ͂Ȃ��A�����������̖��_�o���܂��B�����Ɛ\���グ��������ł��x�Ɛ\���グ���B
���B�A�w����͋M�a�̒��̓��ɂ܂�����ʂƂ��낪���邩�炻���v����̂ł��x�Ɠ������B�����w�͂��x�Ɠ����Ē}�O��͉�����ꂽ���A���_���䂩�Ȃ������̂ŁA�o����̒��l��ʂ��Ă���ƂȂ��^�ӂ���ꂽ����ǂ��A�����������Ȃ������B
�قǂȂ����ɉ�����ĉ��B�͕����A���邱�ƂɂȂ������A�}�O�炪�w�������������ɉ������ł��傤�B�A��r�������ɂ��܂����炨�������������������̂ł��x�Ɛ\���グ��ƁA�w�����ɂ��i�ア�����܂��傤�x�Ɩ��ĉ��B�͋��ɋA�����B
�������������w����������ʂ�܂��̂ŁA�����������������Ƃ͂ł��܂����x�Ɛ\���悱���ƁA�w���͂��Ă��������グ�܂��傤�x�Ɖ��B�͖��ꂽ���A���̓��͓�����@�̂��p�ŏ㋞�����Ƃ��낾�����̂ŁA�Ɨ��̉��^�Ɂw�����͒}�O�炪���������邩��A��̑|�����͂��߁A�����������������̏��������Ă����悤�Ɂx�ƌ������ď㋞���ꂽ�B
���O���ċA���Ă����x���������đ傢�ɋC�ɓ��������A�͋��ɓ���Ƒ傢�ɕs�@���ɂȂ��āA�}�O��Ɏg�҂𗧂ĂāA�w�����̒��͈͋��ō����グ�邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA���@�ɂč����グ�܂��傤�B�H�D�ɂĂ��o�ʼn������B���������������܂�����x�ƌ����Ă悱�����B�}�O��͈ӊO�Ɏv�������H�D�ŎQ��ƁA���B���H�D�ŏo�}���A���ւ�菑�@�ɒʂ��A�������^�̂��Ƃ��A�Z�����o���ꂽ�B
���ׂďI����āA�}�O�炪�w�{���͂ǂ�������ň͋��ł͂Ȃ������̂ł��傤���x�Ɩ����ƁA�w���̂��Ƃł��B����͂��p���������ď㋞�������߂ɁA����̎҂ɍ����̏�����\���t���Ă������̂ł����A�͋��̏��ւ����͂��߂Ƃ��đ��|�܂Ő^�V�������̂Ɍ������Ă��܂��܂����B���̂��߂Ɉ͋��ł�����i�サ�Ȃ������̂ł��x
�w����͂ǂ��������Ƃł����x�w����A�����ł��B�����⎄�߂͗��x��D�������ɂ͋y�Ȃ��Ɛ\���グ�����Ƃ������_�������B�M�a�͍]�˂łق��ڂ��̌��\�Ȉ͋��ł̒���ɂ͂��o�Ȃ��s����Ă��܂�����A���̂Ƃ���ł͒��|�ɌÏ�ł�����i���悤�Ǝv���Ă����̂ɁA�Ăɑ��Ⴕ�Ĉ͋��ł�����i��ł��Ȃ������_�����A���x�D���̗����Ɏ����y�ʂƂ���Ȃ̂ł��x�Ɛ\���ꂽ�v�Ɖ��肪������B�i�����l�́j��i�Ƃ����Ƃ��Ȃ��Ƃ��Ƌ����B
���̍����肪�b������A�O�̘b�̒��ɁB
�u�̒}�O��i���c�����j�͌É��B�̖�l�łƂ�킯�����ɔM�S�ł��������A���鎞�]�˂Œ}�O�炪���B�ɁA�w���x�A�D���Ƃ����ǂ��A���ɂ͂���͌��ȕ����A�ǂ�������ł���Ȃ��Ƃ������̂��Ǝv�����Ƃ�����܂������A���B�̂Ȃ���邱�Ƃ͈�Ƃ��Č��炵�����Ƃ͂Ȃ��A�����������̖��_�o���܂��B�����Ɛ\���グ��������ł��x�Ɛ\���グ���B
���B�A�w����͋M�a�̒��̓��ɂ܂�����ʂƂ��낪���邩�炻���v����̂ł��x�Ɠ������B�����w�͂��x�Ɠ����Ē}�O��͉�����ꂽ���A���_���䂩�Ȃ������̂ŁA�o����̒��l��ʂ��Ă���ƂȂ��^�ӂ���ꂽ����ǂ��A�����������Ȃ������B
�قǂȂ����ɉ�����ĉ��B�͕����A���邱�ƂɂȂ������A�}�O�炪�w�������������ɉ������ł��傤�B�A��r�������ɂ��܂����炨�������������������̂ł��x�Ɛ\���グ��ƁA�w�����ɂ��i�ア�����܂��傤�x�Ɩ��ĉ��B�͋��ɋA�����B
�������������w����������ʂ�܂��̂ŁA�����������������Ƃ͂ł��܂����x�Ɛ\���悱���ƁA�w���͂��Ă��������グ�܂��傤�x�Ɖ��B�͖��ꂽ���A���̓��͓�����@�̂��p�ŏ㋞�����Ƃ��낾�����̂ŁA�Ɨ��̉��^�Ɂw�����͒}�O�炪���������邩��A��̑|�����͂��߁A�����������������̏��������Ă����悤�Ɂx�ƌ������ď㋞���ꂽ�B
���O���ċA���Ă����x���������đ傢�ɋC�ɓ��������A�͋��ɓ���Ƒ傢�ɕs�@���ɂȂ��āA�}�O��Ɏg�҂𗧂ĂāA�w�����̒��͈͋��ō����グ�邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA���@�ɂč����グ�܂��傤�B�H�D�ɂĂ��o�ʼn������B���������������܂�����x�ƌ����Ă悱�����B�}�O��͈ӊO�Ɏv�������H�D�ŎQ��ƁA���B���H�D�ŏo�}���A���ւ�菑�@�ɒʂ��A�������^�̂��Ƃ��A�Z�����o���ꂽ�B
���ׂďI����āA�}�O�炪�w�{���͂ǂ�������ň͋��ł͂Ȃ������̂ł��傤���x�Ɩ����ƁA�w���̂��Ƃł��B����͂��p���������ď㋞�������߂ɁA����̎҂ɍ����̏�����\���t���Ă������̂ł����A�͋��̏��ւ����͂��߂Ƃ��đ��|�܂Ő^�V�������̂Ɍ������Ă��܂��܂����B���̂��߂Ɉ͋��ł�����i�サ�Ȃ������̂ł��x
�w����͂ǂ��������Ƃł����x�w����A�����ł��B�����⎄�߂͗��x��D�������ɂ͋y�Ȃ��Ɛ\���グ�����Ƃ������_�������B�M�a�͍]�˂łق��ڂ��̌��\�Ȉ͋��ł̒���ɂ͂��o�Ȃ��s����Ă��܂�����A���̂Ƃ���ł͒��|�ɌÏ�ł�����i���悤�Ǝv���Ă����̂ɁA�Ăɑ��Ⴕ�Ĉ͋��ł�����i��ł��Ȃ������_�����A���x�D���̗����Ɏ����y�ʂƂ���Ȃ̂ł��x�Ɛ\���ꂽ�v�Ɖ��肪������B�i�����l�́j��i�Ƃ����Ƃ��Ȃ��Ƃ��Ƌ����B
198�l�Ԏ����l�N
2022/05/24(��) 15:39:42.57ID:emE/uutk199�l�Ԏ����l�N
2022/05/24(��) 17:26:34.67ID:bJqQkG0r �{�����M���i�������̂ɂȂ��������Ƃɂ���Ă�
200�l�Ԏ����l�N
2022/05/24(��) 21:54:11.27ID:UW7pG4Rp �ŋL���ۏ\�N�����\�O���̋L�����
�߉q�M�q�ƈɒB���@�ƕ��������@�㔼�����͊��o�ł���
���̓x�֓��̕P�N�l�i����p�F�ɉł��������̑������ȕP�j����������ꂽ���߁A����Ƃĉ��ɂ��点��ꂽ�B�����ɎQ�������A�ƂĂ����X�����ĉ��̋����Ȃ��������A�X���s�������ɉJ������A���ڂ낰�Ȃ��猎������o���ď��������o�Ă����̂ŁA�����̋g�����G�ƍ����q�т݂̂Ŏl���R�b�����Ă���ƁA�i�����l�����̂悤�Ɍ��ꂽ�j
�u���̉����~�͂��ɂ������̌䏊�ɂ����������̌䏑�@�ŁA���B�̐��@�╟�����i���������j�Ȃǂ������ΎQ����Ƃ���ł������B���̉�������͓͐̂���~���ł��������A���鎞�l�������đ������������̂��A���R�i�߉q�M�q�j���w�l�ł��낤�x�Ƌ���������A�Жڐ��@�ƕ������̓�l�Ƃ������ĉ�������ɓ����Ă����������ƒT�����߂����A�O���牞�R��������Ɂw��蓦���������x�Ƃ��q�˂��������A�c�O�Ȃ����蓦�����Ă��܂����B��l������������o��Ȃ�w�ǂ��ł������B�ǂ��ł������x�Ƃ��q�˂���A���A�w���ʍ��܂��Ď�蓦�������͖̂��O�̎���ł��B�l�Ȃ�Ύ�蓦�����͂��܂������̂��x�Ƌނ�Ő\���グ���Ƃ̂��Ƃ��B�����ɂ��l�Ȃ�Ύ�蓦�����͂��܂����҂ǂ��ł������A���ɉ������Ƃł������Ɖ��R���͂悭���b�ɂȂ����v
�u�������͕��i�͂������ĕ��_�炩�Ȑl�ŁA�l�ɉ\����Ă���悤�Ȑl���ł͂Ȃ������B���鎞���R�������������ɂ��āA�����̋��̉��~�֒��̓�������ɂ����łɂȂ����B�ҍ��܂ŕ��������}���ɏo�悤�ƒ����ʂ낤�Ƃ���ƁA�w偂̑��������̊�ɂЂ��Ƃ��������B
��������Œw偂̑��������ʂ����āA�����A��\���グ�悤�Ƃ���̂����āA�����A�w����͑�ςȂ��ƂɂȂ����B������|�������҂͂����Ɏ�ł��ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B���z�Ȃ��Ƃ��x�ƐS�Ɏv�����B
���R���w�����͉������������y���ɂ�������܂����B�ҍ��ɂ��Ȃ�A������̏��̍��}����w偂������~��Ē���̑��_�����đ���D��A����Əo���オ�����Ƃ���֒���a�����o�łɂȂ��A���������Ă��������̂��Ǝ��ɖ��c�ɂ����v���܂����B���̒w偂̐U�����悤�͂��˂Ă�肨�\���t���ɂȂ��Ă����̂ł͂���܂��x�ƌ��k����ƁA�������ɋ����邱�Ƃ��Ɗ����Ė��_�Ɏv���A�|���̂��c���ɂ͑S���C���t���Ȃ����B���̂��Ƃ͂̂��Ɍ��k�R���Ƃ����������ɋL�ڂ��Ă���v
�M�q�̐��N��1599�N�A������1619�N�̉��ՈȑO���Ƃ���ƐM�q�͂��̎��\��B�O���̌����̎q�����ۂ����炷��Ə\��O�����B
�����͌\�䔼����㔼�A���@�͌\�O��B�ŋL�̑��̐M�q�̈�b������������邪�A�l���������l�D���̂���l���������̂ł͂Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA�ŋL�ł͊�{�A���Ƃ͐��v���X���ʂŌĂ�Ă��܂����A���@�͐��@�ĂтŁA�Жڐ��@�������}�}�B
�G�g�ƉƍN��恌Ăт��Ă���̂ŗL���l�����Ƃ������ƂȂ�ł��傤���B
�߉q�M�q�ƈɒB���@�ƕ��������@�㔼�����͊��o�ł���
���̓x�֓��̕P�N�l�i����p�F�ɉł��������̑������ȕP�j����������ꂽ���߁A����Ƃĉ��ɂ��点��ꂽ�B�����ɎQ�������A�ƂĂ����X�����ĉ��̋����Ȃ��������A�X���s�������ɉJ������A���ڂ낰�Ȃ��猎������o���ď��������o�Ă����̂ŁA�����̋g�����G�ƍ����q�т݂̂Ŏl���R�b�����Ă���ƁA�i�����l�����̂悤�Ɍ��ꂽ�j
�u���̉����~�͂��ɂ������̌䏊�ɂ����������̌䏑�@�ŁA���B�̐��@�╟�����i���������j�Ȃǂ������ΎQ����Ƃ���ł������B���̉�������͓͐̂���~���ł��������A���鎞�l�������đ������������̂��A���R�i�߉q�M�q�j���w�l�ł��낤�x�Ƌ���������A�Жڐ��@�ƕ������̓�l�Ƃ������ĉ�������ɓ����Ă����������ƒT�����߂����A�O���牞�R��������Ɂw��蓦���������x�Ƃ��q�˂��������A�c�O�Ȃ����蓦�����Ă��܂����B��l������������o��Ȃ�w�ǂ��ł������B�ǂ��ł������x�Ƃ��q�˂���A���A�w���ʍ��܂��Ď�蓦�������͖̂��O�̎���ł��B�l�Ȃ�Ύ�蓦�����͂��܂������̂��x�Ƌނ�Ő\���グ���Ƃ̂��Ƃ��B�����ɂ��l�Ȃ�Ύ�蓦�����͂��܂����҂ǂ��ł������A���ɉ������Ƃł������Ɖ��R���͂悭���b�ɂȂ����v
�u�������͕��i�͂������ĕ��_�炩�Ȑl�ŁA�l�ɉ\����Ă���悤�Ȑl���ł͂Ȃ������B���鎞���R�������������ɂ��āA�����̋��̉��~�֒��̓�������ɂ����łɂȂ����B�ҍ��܂ŕ��������}���ɏo�悤�ƒ����ʂ낤�Ƃ���ƁA�w偂̑��������̊�ɂЂ��Ƃ��������B
��������Œw偂̑��������ʂ����āA�����A��\���グ�悤�Ƃ���̂����āA�����A�w����͑�ςȂ��ƂɂȂ����B������|�������҂͂����Ɏ�ł��ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B���z�Ȃ��Ƃ��x�ƐS�Ɏv�����B
���R���w�����͉������������y���ɂ�������܂����B�ҍ��ɂ��Ȃ�A������̏��̍��}����w偂������~��Ē���̑��_�����đ���D��A����Əo���オ�����Ƃ���֒���a�����o�łɂȂ��A���������Ă��������̂��Ǝ��ɖ��c�ɂ����v���܂����B���̒w偂̐U�����悤�͂��˂Ă�肨�\���t���ɂȂ��Ă����̂ł͂���܂��x�ƌ��k����ƁA�������ɋ����邱�Ƃ��Ɗ����Ė��_�Ɏv���A�|���̂��c���ɂ͑S���C���t���Ȃ����B���̂��Ƃ͂̂��Ɍ��k�R���Ƃ����������ɋL�ڂ��Ă���v
�M�q�̐��N��1599�N�A������1619�N�̉��ՈȑO���Ƃ���ƐM�q�͂��̎��\��B�O���̌����̎q�����ۂ����炷��Ə\��O�����B
�����͌\�䔼����㔼�A���@�͌\�O��B�ŋL�̑��̐M�q�̈�b������������邪�A�l���������l�D���̂���l���������̂ł͂Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA�ŋL�ł͊�{�A���Ƃ͐��v���X���ʂŌĂ�Ă��܂����A���@�͐��@�ĂтŁA�Жڐ��@�������}�}�B
�G�g�ƉƍN��恌Ăт��Ă���̂ŗL���l�����Ƃ������ƂȂ�ł��傤���B
201�l�Ԏ����l�N
2022/05/25(��) 20:11:44.38ID:yj+RKTrs �u��F���p�L�v���u���X�ɗ\��A�u��e�x(�u����v�\�L���u�e�x�v�ɓ���)�ɉ������]�̂���
��㍑�̍��X�ɗ\��͑�F�@�ٌ��̖����ł���A��N�����ӌ��̋t�S�����ꔱ����ꂽ�̂��ނ̓����ł������B
���Ë`�v���̉ƘV�E�V�[������(����)�̌v���ɂ��A���Õ��̈�x�V�����ԎR�ɂčb�㑊�͎�(�b��e�p�A�b��@�^�̒��j)�ƍ��킵�����A���Õ��͔s�ꂽ�B
���̈⍦�ɂ��V�[������͍��X�̏�𗎂Ƃ����ƁA�V���\��N�\�\�O��(1585�N1��13��)�ɎO��R�ō��X�ɗ\��̏�ɍU�ߊ��B
�ɗ\������킵�݂��ɓS�C���������������A�Ƃ��Ƃ������j���A�ɗ\��͍~������𖾂��n�����B
���Ƃ��ɗ\��͕����̏��ł��������߁A����͈�U�����点�Ė��f����������ł������B
�\�ܓ��Ɉɗ\��͒M���X�̓y�Y���āu�a�r�̔u���ނ��킵�܂��傤�v�Ə�ɍs�����Ƃ���A��x�͂�낱��ŏ�ɓ���ĉ���ƂȂ����B
�u���������킵�Ȃ����x���������Ƃɂ�
�u�������U��̎��A�卄�̎҂����͂܂��̕����҂⎀�l���o�܂����B
�l�߂̏�܂ōU�߂Ă����Ȃ�A�Ō�ɂ͗��邳���Ă����ł��傤���A��������ߔ���������Ă������Ƃł��傤�B
�ɗ\��̌�F�u�ɂ�莀�Ȃ��ɂ��݂܂����v
���̂Ƃ��A�ɗ\��݂͂������q�d�ˊo�̂Ȃ������ʎ҂Ǝv�킹�邽�߂����q�˂��B
�ɗ\��u���Ë`�v���͗����珙�X�ɒq�����߂��炵�A�����̎��ɓ��ʂ����A�ޓ��������ɂ����̂��ɖL��Ɍ�o���Ȃ���Ƃ��������Ă���܂��B
���m�̏K���Ƃ��āu����̖��ɍ����͂Ђ����(����̓G�͍����̗F�A�̈ӁH)�v�ƌ����܂��̂�
���ꂪ�����`�v����o���̎��ɂ͈�x�a�̑g�ɓ��肽���Ǝv���܂��v
��x�u�`�v���̖L���o���͂���܂���B
���͓��Â̗��Ȃ̂ŁA�����炪�ˊo�������Ă��낢�뒲�������܂������A����ł��{���̖����͏����ł��B
�܂��ĖL��͏@�ٌ�����ݍ��Ȃ̂Œ����̂̂��ɏo���Ȃǎv�������ʂ��Ƃł��v
��������ɗ\��͘b���ς����̂��A���̂悤�ɖ₤���B
�ɗ\��u����V���Z�N�̓~�A����������ɂ����ĖL��̏����Ɏ�̎��҂��o�܂����B(����̐킢)
�G�����������蓢�����ɂ����ł��傤���H�v
��x�u�G�����Z���Z��l�]��̓������ɂ����������ł��B
����(���ÉƋv)���L�㐨�̎��[���]�Q���Č����ɂ�
�u���m�̋���͎��[�ł킩����̂��B
�����͎��̉^�B�L�㐨�͓G�w�ɓ��������Ă���A�����Ɍ����������[�͂Ȃ��v�Ɗ�����ꂽ�����ł��B
�܂��A�`�v���̖��߂Œ��������܂����v
�ɗ\��u�������낢���b�ł��B���Ȃǂ͂����̎��[�Ƃ������Ȃ��̂ɁA���������̂悤�ɋC�Â����Ƃ́A�r�ɂƂ��Ă̖ʖڂƂ����܂��傤�v
��㍑�̍��X�ɗ\��͑�F�@�ٌ��̖����ł���A��N�����ӌ��̋t�S�����ꔱ����ꂽ�̂��ނ̓����ł������B
���Ë`�v���̉ƘV�E�V�[������(����)�̌v���ɂ��A���Õ��̈�x�V�����ԎR�ɂčb�㑊�͎�(�b��e�p�A�b��@�^�̒��j)�ƍ��킵�����A���Õ��͔s�ꂽ�B
���̈⍦�ɂ��V�[������͍��X�̏�𗎂Ƃ����ƁA�V���\��N�\�\�O��(1585�N1��13��)�ɎO��R�ō��X�ɗ\��̏�ɍU�ߊ��B
�ɗ\������킵�݂��ɓS�C���������������A�Ƃ��Ƃ������j���A�ɗ\��͍~������𖾂��n�����B
���Ƃ��ɗ\��͕����̏��ł��������߁A����͈�U�����点�Ė��f����������ł������B
�\�ܓ��Ɉɗ\��͒M���X�̓y�Y���āu�a�r�̔u���ނ��킵�܂��傤�v�Ə�ɍs�����Ƃ���A��x�͂�낱��ŏ�ɓ���ĉ���ƂȂ����B
�u���������킵�Ȃ����x���������Ƃɂ�
�u�������U��̎��A�卄�̎҂����͂܂��̕����҂⎀�l���o�܂����B
�l�߂̏�܂ōU�߂Ă����Ȃ�A�Ō�ɂ͗��邳���Ă����ł��傤���A��������ߔ���������Ă������Ƃł��傤�B
�ɗ\��̌�F�u�ɂ�莀�Ȃ��ɂ��݂܂����v
���̂Ƃ��A�ɗ\��݂͂������q�d�ˊo�̂Ȃ������ʎ҂Ǝv�킹�邽�߂����q�˂��B
�ɗ\��u���Ë`�v���͗����珙�X�ɒq�����߂��炵�A�����̎��ɓ��ʂ����A�ޓ��������ɂ����̂��ɖL��Ɍ�o���Ȃ���Ƃ��������Ă���܂��B
���m�̏K���Ƃ��āu����̖��ɍ����͂Ђ����(����̓G�͍����̗F�A�̈ӁH)�v�ƌ����܂��̂�
���ꂪ�����`�v����o���̎��ɂ͈�x�a�̑g�ɓ��肽���Ǝv���܂��v
��x�u�`�v���̖L���o���͂���܂���B
���͓��Â̗��Ȃ̂ŁA�����炪�ˊo�������Ă��낢�뒲�������܂������A����ł��{���̖����͏����ł��B
�܂��ĖL��͏@�ٌ�����ݍ��Ȃ̂Œ����̂̂��ɏo���Ȃǎv�������ʂ��Ƃł��v
��������ɗ\��͘b���ς����̂��A���̂悤�ɖ₤���B
�ɗ\��u����V���Z�N�̓~�A����������ɂ����ĖL��̏����Ɏ�̎��҂��o�܂����B(����̐킢)
�G�����������蓢�����ɂ����ł��傤���H�v
��x�u�G�����Z���Z��l�]��̓������ɂ����������ł��B
����(���ÉƋv)���L�㐨�̎��[���]�Q���Č����ɂ�
�u���m�̋���͎��[�ł킩����̂��B
�����͎��̉^�B�L�㐨�͓G�w�ɓ��������Ă���A�����Ɍ����������[�͂Ȃ��v�Ɗ�����ꂽ�����ł��B
�܂��A�`�v���̖��߂Œ��������܂����v
�ɗ\��u�������낢���b�ł��B���Ȃǂ͂����̎��[�Ƃ������Ȃ��̂ɁA���������̂悤�ɋC�Â����Ƃ́A�r�ɂƂ��Ă̖ʖڂƂ����܂��傤�v
202�l�Ԏ����l�N
2022/05/25(��) 20:16:39.85ID:yj+RKTrs ���̂̂��ɗ\��͉ƒ��̍��X�E���i���Ăяo����
�u���O�͍���̍~���O�Ɏv���Ă��邾�낤���A����͈�x�����܂��ē����߂̍����ł���B
���O�͖����ɖL��ɍs���āA�u��e�x�ɉ䂪�ӎu��`���A�����𗊂߁v
�ƌ����ƁA�E���i�͗������ĖL�㉪�̏�ɍs���A���X�ɗ\�炩��̏�����I�����B
�e�x�͏����ǂނƁA�ƒ����g�̓�(�ȗ�)�ɒN�����킷�ׂ����k�������B
�k���̌��ʁA��R�������ނ����Õ������Ƃ��Ƃ�������낤�ƒ�܂����Ƃ����
�e�x�̒��q�E�u�ꑾ�Y�e���͂��̎��\�Z�ł��������A�������������B
�u��e���u���X�ւ̉����̂��߂ɑ�R������������̂͂����Ă̂ق��ł���܂��B
���̂킯�ł����A��O�E�����F���ɖ������Ă���͖̂��炩�ł��B
���̂��э��X���U�߂Ă���͈̂ɗ\���G�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�ŏI�I�ɖL����Ƃ낤�Ɗ�ĂĂ��邩��ł��B
�킽���͗V�R������ƁA���A�ނ�̎��ɂ͓G���@���l����悤�ɂ��Ă���܂����A����͐�͗Ɏ��Ă��邩��ł��B
���͐Q�Ă��邤���ɐ��q�Ŏ��͂݁A���͑����Ȃ��悤�ɉ�������Ԃ��A���ꂼ��͂������߂Ă����܂��B
�������߂���߂��ɖԂ��Ƌ����������߁A�務�͌����߂Ȃ��ł��傤�B
�F���͖������叫�ł��̂ŁA�L�����邽�߂Ɏ��ӂ̍�����傫�ȖԂ����点�Ă���̂ł��傤�B
���A�F�������X���U�߂Ă���͖̂Ԃ̒��̐���菜���Ă���悤�Ȃ��̂ł��B
���Ë`�v�͓�A�O�N�̂����ɖL����U�߂悤�ƍl���Ă���܂��B
���������Ŕ��ɑ�R���o���ẮA�����炩������Ė�������̉����Ă��܂��܂��B
�Ō�ɑ�G�Ɛ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA���ܐl���Ȃ��͕̂s�ł���܂��B�v
�e�x�u�킵�������v�����A�F�����͎O����肠��A���X�ɗ\�炪���R�𐿂��Ă���̂��B�ǂ��������̂��v
���g���ꓯ�͐e���̌��t�ɐe�x�����ӂ������ƂŁA���Ƃ̍s�����͈��ׂ��Ɗ��܂̗܂𗬂��A
�u�e���l�͂܂��Ⴂ�̂ɂ��̂悤�Ȗ���������Ƃ́A���N���o��ǂꂾ���̌䕪�ʂ��o�Ă��邱�Ƃ��B
�����炭�͋�B�Ɍ�����ׂ���̂̂Ȃ����叫�ɂȂ�ł��傤�v�Ɛ\�����B
�e�x�u����ł͓��̕����o�����Ǝv�������A�e���ٌ̈��ɂ��G���������Đ�ܕS�̕����o�����B
���叫�ɂ͐e���A���q�y����(�u����̉Γ�v�̒��q�ꌺ���낤��)�A��X�e���𖽂���v
�u���O�͍���̍~���O�Ɏv���Ă��邾�낤���A����͈�x�����܂��ē����߂̍����ł���B
���O�͖����ɖL��ɍs���āA�u��e�x�ɉ䂪�ӎu��`���A�����𗊂߁v
�ƌ����ƁA�E���i�͗������ĖL�㉪�̏�ɍs���A���X�ɗ\�炩��̏�����I�����B
�e�x�͏����ǂނƁA�ƒ����g�̓�(�ȗ�)�ɒN�����킷�ׂ����k�������B
�k���̌��ʁA��R�������ނ����Õ������Ƃ��Ƃ�������낤�ƒ�܂����Ƃ����
�e�x�̒��q�E�u�ꑾ�Y�e���͂��̎��\�Z�ł��������A�������������B
�u��e���u���X�ւ̉����̂��߂ɑ�R������������̂͂����Ă̂ق��ł���܂��B
���̂킯�ł����A��O�E�����F���ɖ������Ă���͖̂��炩�ł��B
���̂��э��X���U�߂Ă���͈̂ɗ\���G�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�ŏI�I�ɖL����Ƃ낤�Ɗ�ĂĂ��邩��ł��B
�킽���͗V�R������ƁA���A�ނ�̎��ɂ͓G���@���l����悤�ɂ��Ă���܂����A����͐�͗Ɏ��Ă��邩��ł��B
���͐Q�Ă��邤���ɐ��q�Ŏ��͂݁A���͑����Ȃ��悤�ɉ�������Ԃ��A���ꂼ��͂������߂Ă����܂��B
�������߂���߂��ɖԂ��Ƌ����������߁A�務�͌����߂Ȃ��ł��傤�B
�F���͖������叫�ł��̂ŁA�L�����邽�߂Ɏ��ӂ̍�����傫�ȖԂ����点�Ă���̂ł��傤�B
���A�F�������X���U�߂Ă���͖̂Ԃ̒��̐���菜���Ă���悤�Ȃ��̂ł��B
���Ë`�v�͓�A�O�N�̂����ɖL����U�߂悤�ƍl���Ă���܂��B
���������Ŕ��ɑ�R���o���ẮA�����炩������Ė�������̉����Ă��܂��܂��B
�Ō�ɑ�G�Ɛ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA���ܐl���Ȃ��͕̂s�ł���܂��B�v
�e�x�u�킵�������v�����A�F�����͎O����肠��A���X�ɗ\�炪���R�𐿂��Ă���̂��B�ǂ��������̂��v
���g���ꓯ�͐e���̌��t�ɐe�x�����ӂ������ƂŁA���Ƃ̍s�����͈��ׂ��Ɗ��܂̗܂𗬂��A
�u�e���l�͂܂��Ⴂ�̂ɂ��̂悤�Ȗ���������Ƃ́A���N���o��ǂꂾ���̌䕪�ʂ��o�Ă��邱�Ƃ��B
�����炭�͋�B�Ɍ�����ׂ���̂̂Ȃ����叫�ɂȂ�ł��傤�v�Ɛ\�����B
�e�x�u����ł͓��̕����o�����Ǝv�������A�e���ٌ̈��ɂ��G���������Đ�ܕS�̕����o�����B
���叫�ɂ͐e���A���q�y����(�u����̉Γ�v�̒��q�ꌺ���낤��)�A��X�e���𖽂���v
203�l�Ԏ����l�N
2022/05/25(��) 20:19:35.96ID:yj+RKTrs ��㍑���X�̋߂��ɂ����u��e���͕����A�ɉB���A�g�҂̍��X�E���i�ƂƂ��ɍ��X�ɗ\��̏h���𖧂��ɖK�˂��B
�ɗ\��u����U�߂�Ε����҂⎀�l���吨�o��ł��傤�B
������Ė铢���ɂ��ď���Ă��A�G�͋Ă��������o�悤�Ƃ���ł��傤����A
�����͏�̈ē��͂킩���Ă���܂��̂ŝ��肩��l�߂����Đs�������܂��傤�v
�������ĖL�㐨�͓��m������h�����߁A���������ō����t�����߁A�铢�����ܕS�A�邩��o�Ă����Ƃ���������A�u�ꐨ�E���X���ł��ꂼ��炨�����B
�������ď\��\����̖������A�ɗ\��͂��˂ėp�ӂ��Ă����Ζ�⏼����E�ь���蓊������ŁA�钆�̑啔�����߂Ă����{���������コ�����B
�����őO���E�������騂̐����������Ƃ���A�钆�̈�x���͍Q�Ăӂ��߂������o���Ă����B
�����̕��͌��C������ɓ����A�݂��ɓG�𑽂����Ƃ��Ƒ������B
��x��������ɂ��܂��A�������|��Ă��ڂ݂��A���������ɏꏊ�ƒ�߂Đ�������A�ǂ�ǂ��ꏭ�Ȃ��Ȃ����B
��������x�͐�I�҂̂��߁A�킸���̐��Ő������������ߓ��������Ă��܂����B
�킪�I���A���[�𐔂���Ɛ甪�S�]�������Ă����B
�u�ꐨ�������҂͑����o�����A���l�͌܁A�Z�l�����Ȃ������B
��͍Ăэ��X�̂��̂ƂȂ�A�u�ꐨ�͖L��ɋA�҂����B
�u��e���́u���̂��т̐�ł͑傢�Ȃ�s�o���������܂����B�F�����͑����������܂������A�叫�ł����x�������܂����B�v
�Ǝu��e�x�ɐ\������
�e�x�u����ނłȂ��B��Ƃ������͕̂K�������G�̂������ł͂Ȃ��B�E�������đގU������̂������ł���B
����ɂ��Ă����X�ɗ\��̕����̂��߂ɑ叟�������̂��v�Ɗ�B
���̂̂��ɗ\�炩��u��e�x�ɉ����̗炪�������B
�e�x����F�`�����ɏڍׂ�������ƁA�`�����͑傢�Ɋ��x�����B
�`��������e�x�ƍ��X�Ɍ䊴�^����ꂽ�B
�̂��V���\�l�N�ɔ�㍑��V�[�������A�L�㍑�𓇒Ò���(�Ƌv)���������������A�u�ꂩ�獂�X�ɉ���̕����o����A�L�㍑�ɍ��X������������B
���N�A�F�������ނ�����A���X�͔�㍑�ɋA�҂����B
�b��@�^������̂̂��A�u�����̒��ɏ��炵�A������痢�̊O�Ɍ����v�Ƃ͍��X�ɗ\��̂��Ƃł��낤�B
�ɗ\��u����U�߂�Ε����҂⎀�l���吨�o��ł��傤�B
������Ė铢���ɂ��ď���Ă��A�G�͋Ă��������o�悤�Ƃ���ł��傤����A
�����͏�̈ē��͂킩���Ă���܂��̂ŝ��肩��l�߂����Đs�������܂��傤�v
�������ĖL�㐨�͓��m������h�����߁A���������ō����t�����߁A�铢�����ܕS�A�邩��o�Ă����Ƃ���������A�u�ꐨ�E���X���ł��ꂼ��炨�����B
�������ď\��\����̖������A�ɗ\��͂��˂ėp�ӂ��Ă����Ζ�⏼����E�ь���蓊������ŁA�钆�̑啔�����߂Ă����{���������コ�����B
�����őO���E�������騂̐����������Ƃ���A�钆�̈�x���͍Q�Ăӂ��߂������o���Ă����B
�����̕��͌��C������ɓ����A�݂��ɓG�𑽂����Ƃ��Ƒ������B
��x��������ɂ��܂��A�������|��Ă��ڂ݂��A���������ɏꏊ�ƒ�߂Đ�������A�ǂ�ǂ��ꏭ�Ȃ��Ȃ����B
��������x�͐�I�҂̂��߁A�킸���̐��Ő������������ߓ��������Ă��܂����B
�킪�I���A���[�𐔂���Ɛ甪�S�]�������Ă����B
�u�ꐨ�������҂͑����o�����A���l�͌܁A�Z�l�����Ȃ������B
��͍Ăэ��X�̂��̂ƂȂ�A�u�ꐨ�͖L��ɋA�҂����B
�u��e���́u���̂��т̐�ł͑傢�Ȃ�s�o���������܂����B�F�����͑����������܂������A�叫�ł����x�������܂����B�v
�Ǝu��e�x�ɐ\������
�e�x�u����ނłȂ��B��Ƃ������͕̂K�������G�̂������ł͂Ȃ��B�E�������đގU������̂������ł���B
����ɂ��Ă����X�ɗ\��̕����̂��߂ɑ叟�������̂��v�Ɗ�B
���̂̂��ɗ\�炩��u��e�x�ɉ����̗炪�������B
�e�x����F�`�����ɏڍׂ�������ƁA�`�����͑傢�Ɋ��x�����B
�`��������e�x�ƍ��X�Ɍ䊴�^����ꂽ�B
�̂��V���\�l�N�ɔ�㍑��V�[�������A�L�㍑�𓇒Ò���(�Ƌv)���������������A�u�ꂩ�獂�X�ɉ���̕����o����A�L�㍑�ɍ��X������������B
���N�A�F�������ނ�����A���X�͔�㍑�ɋA�҂����B
�b��@�^������̂̂��A�u�����̒��ɏ��炵�A������痢�̊O�Ɍ����v�Ƃ͍��X�ɗ\��̂��Ƃł��낤�B
204�l�Ԏ����l�N
2022/05/25(��) 23:28:29.94ID:8WaBkeoQ �ŋL���ۏ\�N�\����\����̋L�����@�G���Ɛ��@�Ǝ��䒉��
�i���[���̘b�Ɂu�䓿�@�a�̌䎞�A�����ٓ��i���炭�����j�Ɖ��B�̐��@���䑊���ɂȂ��āA�䓿�@�a���炪��������Ŋl��������l�ɉ����ꂽ���A��l�Ƃ��ɂ��̊��J�߂��Ƃ���A���̎����o�~�����s���Ă����̂ł��낤���A�w���r�߂邩�x�Ƃ��q�˂���Ƃ������܉�ٓ��A
�@�������@��`�������с@�������
�Ɖr�܂ꂽ�B�䊴�S�̂��܂�w���@�A�e��t����x�Ƃ����]����A���@�A
�@�x�����d�́@�����܂͂镗
�ƕt����ƁA�������ɖʔ�����ꂽ�B�w�ȂɂƂ���O��͂��オ���t���������܂��x�Ɠ�l���\���グ��ƁA
�@�R�X�́@���Ԃ��̉Ԃ́@����ɂ�
�ƕt����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��v
�����l���u�̂̐l�́v�Ƒ�����ꂽ���A�O�l�̐��i�̈Ⴂ���܂��܂��ƕ\��Ă���͎̂��ɋ������肾�B
�i���[���̘b�Ɂu�䓿�@�a�̌䎞�A�����ٓ��i���炭�����j�Ɖ��B�̐��@���䑊���ɂȂ��āA�䓿�@�a���炪��������Ŋl��������l�ɉ����ꂽ���A��l�Ƃ��ɂ��̊��J�߂��Ƃ���A���̎����o�~�����s���Ă����̂ł��낤���A�w���r�߂邩�x�Ƃ��q�˂���Ƃ������܉�ٓ��A
�@�������@��`�������с@�������
�Ɖr�܂ꂽ�B�䊴�S�̂��܂�w���@�A�e��t����x�Ƃ����]����A���@�A
�@�x�����d�́@�����܂͂镗
�ƕt����ƁA�������ɖʔ�����ꂽ�B�w�ȂɂƂ���O��͂��オ���t���������܂��x�Ɠ�l���\���グ��ƁA
�@�R�X�́@���Ԃ��̉Ԃ́@����ɂ�
�ƕt����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��v
�����l���u�̂̐l�́v�Ƒ�����ꂽ���A�O�l�̐��i�̈Ⴂ���܂��܂��ƕ\��Ă���͎̂��ɋ������肾�B
205�l�Ԏ����l�N
2022/05/27(��) 15:18:13.77ID:1yQqJgug ���a�O�N��\����A�́E����ƍN�ɑ��A���Ƒ匠���̑������Ȃ��ꂽ�B
����L�ɁA�n�߂͑匠���ł͂Ȃ��喾�_�̐_���R��ׂ��Ƃ̌v�c�����āA����Ɍ��肹��Ƃ����̂����A
�V�C�m���͂�����āA�u���_�͔�Ȃ�B�����Ƃ����đR��ׂ��B�v�ƌ������̂����A���̏�̏O�͊F
�u�����́i�_���j�K���Ȃ̂�����@�����B�v�ƌ������B
�����ł͂��������A�V�C�̌���������������킯�ɂ͂������A�����������Č��_�͉������ꂽ�B
���̎��ɂ��āA����G�����͘V�������ċc�肹���ߋ��������A���̎����F�A���_�����ȂĐ��Ȃ�Ƃ��A
���ɒ�܂��Ƃ����B���������̎��V�C�͖ق��ĉ����������Ȃ������B���̂��ߘV���͍ĎO�V�C��
�q�˂�ꂽ���A�ނ�
�u�L���喾�_�A�K�����B�v
�ƌ������B
����ɉ���������邱�Əo�����A�����ɒ�܂����B
��ɐ_�̂��A�g�c�i�g�c���N��j�ɖ����Ē��ւ��悤�Ƃ������A�V�C��
�u�g�c�������m���B��m��������v�ƌ��������߁A�F�^���āA���̌��t���G�����ɐ\���グ���B
�����ŏG�����͘V�����ȂĂ��̎���q�˂�ꂽ���A�V�C�͈ꎲ���������B����͌�z���@����
�V�C�Ɏ������A�_�̊����`�̛��M�ł������B�a���̎ҒB�A�傢�ɋ������B
���̓��Ƌ{�̐_�̂́A�V�C��l�����ւ������̂ł���B
�����ē��b�R���i���̑m�k���_�̂��������鎖��̂́A���̉��ł���B
�V�C�����̒��`���o�܂́A�c���̖��ɉƍN���A�L�b�G��������Ǝv�������A��z�����
�����������A��͜��݂Ɏv��������A������a���Ȃ����߂�Ƃ̉b����������Ă����B�̂�
�G�������̎��t���ĎO�ɋy�Ԃ�嫂��A��������Ȃ������B����ɉƍN���͌䕮����A�̂ɂ��̎���
��V�����F����Ċ����Č����o���҂͖��������B
���̎��A�V�C�͉ƍN�����Ђ߂��B���̎��͐r���������A�I�ɉƍN�����㏳���������B
�V�C�͂����ɏ㋞���A���̎����ɑt�������B��͓V�C�̌�����Ƃ��A�u���̊肤�����ׂ���v�Ƃ�
���肪�������B�V�C�͂��Ȃ킿�A���̐_�̊����`���Ȃđt�����B��͂���������������Ƃ����B
�ʋL�ɁA�V�C��m���͑��������E�`�����̖��q�ł���i����ɁA�����O�Y�̖��t�E��؎��ł���Ƃ����j�A
��͉���b�������̖��ŁA�i�����N�ɒa���A�`�����I���ɕt���A��Ɠ�������Â։������A�O�c�̎���
�̂��ĕ����ƂȂ�A���i�\��N�\������Ɏ₵���B�S�O�\�l�ł������Ƃ����B
�c�����N�l���A�����t��拂��������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�V�C�m���A���q���G�ǂ��납�������R�̗��Ƃ������܂ŗL������ł��ˁB
����L�ɁA�n�߂͑匠���ł͂Ȃ��喾�_�̐_���R��ׂ��Ƃ̌v�c�����āA����Ɍ��肹��Ƃ����̂����A
�V�C�m���͂�����āA�u���_�͔�Ȃ�B�����Ƃ����đR��ׂ��B�v�ƌ������̂����A���̏�̏O�͊F
�u�����́i�_���j�K���Ȃ̂�����@�����B�v�ƌ������B
�����ł͂��������A�V�C�̌���������������킯�ɂ͂������A�����������Č��_�͉������ꂽ�B
���̎��ɂ��āA����G�����͘V�������ċc�肹���ߋ��������A���̎����F�A���_�����ȂĐ��Ȃ�Ƃ��A
���ɒ�܂��Ƃ����B���������̎��V�C�͖ق��ĉ����������Ȃ������B���̂��ߘV���͍ĎO�V�C��
�q�˂�ꂽ���A�ނ�
�u�L���喾�_�A�K�����B�v
�ƌ������B
����ɉ���������邱�Əo�����A�����ɒ�܂����B
��ɐ_�̂��A�g�c�i�g�c���N��j�ɖ����Ē��ւ��悤�Ƃ������A�V�C��
�u�g�c�������m���B��m��������v�ƌ��������߁A�F�^���āA���̌��t���G�����ɐ\���グ���B
�����ŏG�����͘V�����ȂĂ��̎���q�˂�ꂽ���A�V�C�͈ꎲ���������B����͌�z���@����
�V�C�Ɏ������A�_�̊����`�̛��M�ł������B�a���̎ҒB�A�傢�ɋ������B
���̓��Ƌ{�̐_�̂́A�V�C��l�����ւ������̂ł���B
�����ē��b�R���i���̑m�k���_�̂��������鎖��̂́A���̉��ł���B
�V�C�����̒��`���o�܂́A�c���̖��ɉƍN���A�L�b�G��������Ǝv�������A��z�����
�����������A��͜��݂Ɏv��������A������a���Ȃ����߂�Ƃ̉b����������Ă����B�̂�
�G�������̎��t���ĎO�ɋy�Ԃ�嫂��A��������Ȃ������B����ɉƍN���͌䕮����A�̂ɂ��̎���
��V�����F����Ċ����Č����o���҂͖��������B
���̎��A�V�C�͉ƍN�����Ђ߂��B���̎��͐r���������A�I�ɉƍN�����㏳���������B
�V�C�͂����ɏ㋞���A���̎����ɑt�������B��͓V�C�̌�����Ƃ��A�u���̊肤�����ׂ���v�Ƃ�
���肪�������B�V�C�͂��Ȃ킿�A���̐_�̊����`���Ȃđt�����B��͂���������������Ƃ����B
�ʋL�ɁA�V�C��m���͑��������E�`�����̖��q�ł���i����ɁA�����O�Y�̖��t�E��؎��ł���Ƃ����j�A
��͉���b�������̖��ŁA�i�����N�ɒa���A�`�����I���ɕt���A��Ɠ�������Â։������A�O�c�̎���
�̂��ĕ����ƂȂ�A���i�\��N�\������Ɏ₵���B�S�O�\�l�ł������Ƃ����B
�c�����N�l���A�����t��拂��������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�V�C�m���A���q���G�ǂ��납�������R�̗��Ƃ������܂ŗL������ł��ˁB
206�l�Ԏ����l�N
2022/05/28(�y) 19:00:22.20ID:13JLuMtD �\�ł��������ǓV�C�����{�l�͂ǂ��v���Ă��̂��˂�
�{�l�ɕ����z�����\�����Ǝv�����
�{�l�ɕ����z�����\�����Ǝv�����
207�l�Ԏ����l�N
2022/05/28(�y) 19:37:58.79ID:OVmpUAW9 �ق��Ƃ��V�C�Ƃ��v���Ă���Ȃ���
208�l�Ԏ����l�N
2022/05/28(�y) 19:48:02.73ID:13JLuMtD �L���喾�_�A�K�����
�Ђǂ��L�b�����̌��t����
�Ђǂ��L�b�����̌��t����
209�l�Ԏ����l�N
2022/05/28(�y) 22:20:06.53ID:BBDU84zs �V�C�u�����A���̍D���Ȍ��t�ł��v
210�l�Ԏ����l�N
2022/05/28(�y) 22:36:46.38ID:FtB32KSb �o���֘A�ɂ́u���O���v���Ȃ炻���Ȃ�A���O�̒��ł͂ȁv�I�ȕԂ����ĂȂ����������V�C
211�l�Ԏ����l�N
2022/05/28(�y) 22:52:19.77ID:BBDU84zs �쒆������j���وāu�ّm���\�[�X�v�Ƃ�����
212�l�Ԏ����l�N
2022/05/29(��) 12:30:56.67ID:9IYKMAH/ �ŋL���ۏ\��N�O����\�������@�G���ƓV�C
�䓿�@�̌䎞�A����V���Q��ꂽ���A���傤�ǂ��o�����̍ۂł�������g�x�x����Ă��Ζʂ��������A�䓿�@������Ă�Ă���̂����Ƃ��߂āA�u���̂��߂Ɉ��Ă�Ă���������̂ł����v�Ƃ��f������ƁA��������Ɍ䍇�_�������āu����͑��̐l�ɖ����邽�߂ɒĂ���̂��v�Ƃ����������ƁA�u����҂����A��ɂȂ�͉̂��̂��߂ł��傤���v�Ɛ\���グ���B������䓿�@�͐��U����Ă���Ȃ������Ƃ������Ƃ��B
�䓿�@�̌䎞�A����V���Q��ꂽ���A���傤�ǂ��o�����̍ۂł�������g�x�x����Ă��Ζʂ��������A�䓿�@������Ă�Ă���̂����Ƃ��߂āA�u���̂��߂Ɉ��Ă�Ă���������̂ł����v�Ƃ��f������ƁA��������Ɍ䍇�_�������āu����͑��̐l�ɖ����邽�߂ɒĂ���̂��v�Ƃ����������ƁA�u����҂����A��ɂȂ�͉̂��̂��߂ł��傤���v�Ɛ\���グ���B������䓿�@�͐��U����Ă���Ȃ������Ƃ������Ƃ��B
213�l�Ԏ����l�N
2022/05/29(��) 12:34:52.85ID:oGCrHrDD ���ˉ���u���V�̉A�X���ڂɓ����̂��I�v
214�l�Ԏ����l�N
2022/05/29(��) 13:02:09.01ID:AqsKSy9S ���ˌ����u�N�v�̒����͒j�Ə������悤�ɂ���B���Ȃ���ł�����邪�j���m�ł͒ɂ��邾���ł���B�v
215�l�Ԏ����l�N
2022/05/29(��) 13:09:28.85ID:9IYKMAH/ �ŋL�������̈�b���
���ۏ\�N�܌��\�����̋L�����@����ƉG�ی��L
�����A���ł̉����l�̂��b�ɁA�u�t���̏��͉��B�����Ă͂₵�����߂ɑ���A�]���̏��ƂƂ��ɐ���ɗ��z���Ă��邪�A�@�a�͏t�����匙���ł������B�悭���T���b���Ă������A�@�a���w�������悫���̓��ɌĂꂽ�B�����牽�܂ł悭�o���Ă�������ǂ��A��̖V��߂����̊Ԃɂ�������x�ƚ}���Ă����������B���R���t���قlj���ȏ��͂Ȃ��ƁA���̈��M�Ԃ���˂Â˂��Ȃ���Ă����B
����͎]���������Ƃ����܂�ɑ��������̂Ŏ]����ƌĂ�Ă����B�킯�Ă��̂̎]�����������B����͉̂��G�ی��L�Ɏt�����Ă�قǏC�s�����������B���L���ٌ����ĉ̂��r�ނ��Ƃ�������Ɏ~�߂āw�T�ɂ͘a�̂͂���ʂ��̂��x�Ǝ莆�𑗂������A���̕Ԏ��̍Ō�ɁA�w�����ɒ�̕Ȃ���B��M�ɉ�̕Ȃ���B���ɘa�̂̕Ȃ���x�Ə����āA����ɂ��̂��ƂɁw���̒��́@�l�ɂ͕Ȃ́@������̂��@��ɂ͂�邹�@�~���̓��x�Ə����đ���ꂽ�Ƃ����B��������L�������Ďw�삳�ꂽ�Ƃ��B�v
���ۏ\��N�����\�Z���@����Ƌ߉q�M�q
�i�����l�̂��b�j���̐́A���R���̌�O�ɑ���a�����f�āA���ɂ��q�ׂĉ����낤�Ƃ������A�u�����炭�v�Ɖ��R�������~�߂���ƁA�u�����͖@�ؔ��u�̒����ł��̂ŁA�܂����ɂ������܂��傤�v�Əo�悤�Ƃ����B���R���A�ĂѕԂ���āu���u�Ȃ̂ɒ����Ƃ͂ǂ��������Ƃ��v�Ɩ₤�ƁA����A�u�l�o�̒��o�̂悤�Ȃ��̂Ǝv�������v�Ɠ����ĉ��������Ƃ��B���������ڒq�̂���l���͒�߂Ē��̓������ł��낤�B
�@�ؔ��u�́A�@�،o�������ߑO�ߌ�Ɉꊪ���A���ɓ��u����@��̂��ƁB
�l�o�͔јo�A�`�o�A���o�A��o�̎l��g�̘o�B���o�͓�Ԗڂɑ傫�Șo�i�����͏`�o�j�̂��ƁB
������������Ȃ̂Ő^�͂Ȃ��킯�ł��ˁB
���ۏ\�N�܌��\�����̋L�����@����ƉG�ی��L
�����A���ł̉����l�̂��b�ɁA�u�t���̏��͉��B�����Ă͂₵�����߂ɑ���A�]���̏��ƂƂ��ɐ���ɗ��z���Ă��邪�A�@�a�͏t�����匙���ł������B�悭���T���b���Ă������A�@�a���w�������悫���̓��ɌĂꂽ�B�����牽�܂ł悭�o���Ă�������ǂ��A��̖V��߂����̊Ԃɂ�������x�ƚ}���Ă����������B���R���t���قlj���ȏ��͂Ȃ��ƁA���̈��M�Ԃ���˂Â˂��Ȃ���Ă����B
����͎]���������Ƃ����܂�ɑ��������̂Ŏ]����ƌĂ�Ă����B�킯�Ă��̂̎]�����������B����͉̂��G�ی��L�Ɏt�����Ă�قǏC�s�����������B���L���ٌ����ĉ̂��r�ނ��Ƃ�������Ɏ~�߂āw�T�ɂ͘a�̂͂���ʂ��̂��x�Ǝ莆�𑗂������A���̕Ԏ��̍Ō�ɁA�w�����ɒ�̕Ȃ���B��M�ɉ�̕Ȃ���B���ɘa�̂̕Ȃ���x�Ə����āA����ɂ��̂��ƂɁw���̒��́@�l�ɂ͕Ȃ́@������̂��@��ɂ͂�邹�@�~���̓��x�Ə����đ���ꂽ�Ƃ����B��������L�������Ďw�삳�ꂽ�Ƃ��B�v
���ۏ\��N�����\�Z���@����Ƌ߉q�M�q
�i�����l�̂��b�j���̐́A���R���̌�O�ɑ���a�����f�āA���ɂ��q�ׂĉ����낤�Ƃ������A�u�����炭�v�Ɖ��R�������~�߂���ƁA�u�����͖@�ؔ��u�̒����ł��̂ŁA�܂����ɂ������܂��傤�v�Əo�悤�Ƃ����B���R���A�ĂѕԂ���āu���u�Ȃ̂ɒ����Ƃ͂ǂ��������Ƃ��v�Ɩ₤�ƁA����A�u�l�o�̒��o�̂悤�Ȃ��̂Ǝv�������v�Ɠ����ĉ��������Ƃ��B���������ڒq�̂���l���͒�߂Ē��̓������ł��낤�B
�@�ؔ��u�́A�@�،o�������ߑO�ߌ�Ɉꊪ���A���ɓ��u����@��̂��ƁB
�l�o�͔јo�A�`�o�A���o�A��o�̎l��g�̘o�B���o�͓�Ԗڂɑ傫�Șo�i�����͏`�o�j�̂��ƁB
������������Ȃ̂Ő^�͂Ȃ��킯�ł��ˁB
216�l�Ԏ����l�N
2022/05/29(��) 17:25:21.08ID:3aTZmvuu �u����G�ځv�������ƉG�ی��L�̘b
�G�ی��L�����������Ƃɂ�
�u���̐��ɂ�������l����B
����͉̖̂��l�ł��邪�A�����̋Z�ʂ��킫�܂������ɓY����˗�����B����͂����ł���B
�܂��A��������̋Z�ʂ��킫�܂����˗��ɉ����đ���̉̂��B������܂������ł���v
�G�ی��L�����������Ƃɂ�
�u���̐��ɂ�������l����B
����͉̖̂��l�ł��邪�A�����̋Z�ʂ��킫�܂������ɓY����˗�����B����͂����ł���B
�܂��A��������̋Z�ʂ��킫�܂����˗��ɉ����đ���̉̂��B������܂������ł���v
217�l�Ԏ����l�N
2022/05/29(��) 20:47:29.02ID:bxvNmP/+ >>215 �ɏo�Ă��閳�T�͞ŋL���ۏ\��N�����\�Z���̋L���ɏڂ����o�����ڂ��Ă��āA�܂Ƃ߂��
�u���̎��ɒ��R���ɏ����g���Ĉȗ��A�O�W�@��(�M��)�A���R��(�M�q)�A�ǎR��(���k)�A�T�t(���)�A�y�@(���)�A�֔�(��꤂̒��j�Ƌv)�̎���Ɏd���A�Ƌv���Z�̎��ɖS���Ȃ����B�N�͕S�\��������Ƃ������A�{�l���N�͌���Ȃ������̂Œ肩�ł͂Ȃ��v
���R���̓O�O��Ƌ߉q���k�̓����ƂȂ��Ă��邪�A�����ł͏��k�̓����͗ǎR�ƂȂ��Ă���B�܂��A�Ƌv���琔���Ď���O�͋߉q�O�v�����A�E�B�L�ɂ��Ɠ����͗��R�B�ǂ��炪���������͕�����܂���B
���̎����\�Z���̋L���ɂ́A�܂Ƃ߃T�C�g�Ɂu���̘Q�l���b�h��ттĔ��������v�̃^�C�g���ōڂ��Ă���b�Ɠ���̘b���ڂ��Ă��āA�V���ӂ̕M�҂͞ŋL�̂��̋L�����Q�l�ɂ����\�����������ł��B
�u���̎��ɒ��R���ɏ����g���Ĉȗ��A�O�W�@��(�M��)�A���R��(�M�q)�A�ǎR��(���k)�A�T�t(���)�A�y�@(���)�A�֔�(��꤂̒��j�Ƌv)�̎���Ɏd���A�Ƌv���Z�̎��ɖS���Ȃ����B�N�͕S�\��������Ƃ������A�{�l���N�͌���Ȃ������̂Œ肩�ł͂Ȃ��v
���R���̓O�O��Ƌ߉q���k�̓����ƂȂ��Ă��邪�A�����ł͏��k�̓����͗ǎR�ƂȂ��Ă���B�܂��A�Ƌv���琔���Ď���O�͋߉q�O�v�����A�E�B�L�ɂ��Ɠ����͗��R�B�ǂ��炪���������͕�����܂���B
���̎����\�Z���̋L���ɂ́A�܂Ƃ߃T�C�g�Ɂu���̘Q�l���b�h��ттĔ��������v�̃^�C�g���ōڂ��Ă���b�Ɠ���̘b���ڂ��Ă��āA�V���ӂ̕M�҂͞ŋL�̂��̋L�����Q�l�ɂ����\�����������ł��B
218�l�Ԏ����l�N
2022/05/30(��) 19:02:33.60ID:tH4eb+3+ ���~�̐w�A������ɂĒO�H�ܘY���q�咷�d���͎d���t����ꂽ���A�㐙�i�������o���A
�u�䓙���d���t���\���ׂ��v�ƂāA�Ɨ��ɐ旧���A�u����Ȃ�a�ɋ�����v�Ɋ|����v��
�\���t���Ĉ������B
�n�߂͊F�i�d��ł͂Ȃ������|���鎖�Ɂj�u��ɂ��l���ȁv�Ǝv���C�F�ɂāA�܂����������|����
���Ȃ������̂����A�����Ɍi�����o�āu���Ƃċ����|�����邼�v�Ɛ\���ꂽ���߁A����������
�u�����ɂ����͊|���\���ׂ���B�v�Ƒ����Ɋ|�������A�i�����͂�������āA���̎d���������u���A
�e�ɓy�U��u���A�S�C���|���@���𗧂āA�u����ɓy�U���|��������I�v�Ɖ��m�����B
�����́A�㐙���̓����ɏ��߂͗p�S���Ă������̂́A�a�ɋ����|���悤�Ƃ���l�q�����āA
�u�㐙�͌R�̏p��m��ʂ��A�͂����������͂Ȃ��B�v�ƈ��������Ă��܂��Ă����B
�܂��㐙�̉Ɛb��������A���m�𐿂�����C�F�ł������B
����̂ɁA�i�����͓G�̖��f���v��A�@���𗧂Ă����߁A�����Ɏd���ɓy�U���Ђ��Ђ��Ǝ����āA
�d���t�����̂��B
��ɓy�U��u�����ꏊ�͎d�ƂȂ�A�����镺�͎d��̖h���ɏo�āA��������Ċ̂��������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�u�䓙���d���t���\���ׂ��v�ƂāA�Ɨ��ɐ旧���A�u����Ȃ�a�ɋ�����v�Ɋ|����v��
�\���t���Ĉ������B
�n�߂͊F�i�d��ł͂Ȃ������|���鎖�Ɂj�u��ɂ��l���ȁv�Ǝv���C�F�ɂāA�܂����������|����
���Ȃ������̂����A�����Ɍi�����o�āu���Ƃċ����|�����邼�v�Ɛ\���ꂽ���߁A����������
�u�����ɂ����͊|���\���ׂ���B�v�Ƒ����Ɋ|�������A�i�����͂�������āA���̎d���������u���A
�e�ɓy�U��u���A�S�C���|���@���𗧂āA�u����ɓy�U���|��������I�v�Ɖ��m�����B
�����́A�㐙���̓����ɏ��߂͗p�S���Ă������̂́A�a�ɋ����|���悤�Ƃ���l�q�����āA
�u�㐙�͌R�̏p��m��ʂ��A�͂����������͂Ȃ��B�v�ƈ��������Ă��܂��Ă����B
�܂��㐙�̉Ɛb��������A���m�𐿂�����C�F�ł������B
����̂ɁA�i�����͓G�̖��f���v��A�@���𗧂Ă����߁A�����Ɏd���ɓy�U���Ђ��Ђ��Ǝ����āA
�d���t�����̂��B
��ɓy�U��u�����ꏊ�͎d�ƂȂ�A�����镺�͎d��̖h���ɏo�āA��������Ċ̂��������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
219�l�Ԏ����l�N
2022/05/30(��) 20:54:27.36ID:u4RuVBEe �ŋL���q�d�@�O�b
���ۏ\�l�N�l���\�Z���̋L�����@�߉q�M�q�Əd�@
�q���h��i�d�@�j�͌`�̔@�����l�ŁA���R���Ƃ��S�Ղ��ԕ��ł����Ό���K�₵�����A���i��ł��������ɂ͂��т��ђ��̓��Ɍ����������B���h��͎��璃�P�������Ē���҂����Ƃ��D�B
���鎞���R�������K�˂����ƁA���h��͑ҍ��ł����̏��P�Œ���҂��Ă������A�u���̒��͌�O�ɍ����グ��Z���ŁA���҂��Ă����Ƃ���ł����A�����������łɂȂ����ʖڂȂ���B���߂͏���Ȃǂ����U���ĎQ��܂��̂ŁA���Ȃ����݂Ɍ�O�����̉P�Œ���҂���Ă݂Ă͂������v�ƉP�������グ�ď���ɓ��낤�Ƃ���Ƃ�����ĂѕԂ���āA�u��������ɔ҂����āA�h�B�̒��͎��̊֔����҂��ꂽ�̂��ƁA�l�X�ɘb����������݂ł��낤�v�Ƌ�A���h���듪��@���āA�u���������܂���B����\���A���l�Ɏv���t�������̓��ł���܂������A�����ɂ��������Ȃ��ꂽ���ɂ�����v�Ɠ�l�Ƃ�����Ȃ��ꂽ�Ƃ��B
���ۏ\���N�㌎�\����̋L�����@������@�Əd�@
������@�͊i�ʂ̑��̂����ł��点��ꂽ���Ƃ��i�����l�́j��X���ɂȂ��Ă����B�q���h�炪���i����߂Ă������̂��Ƃł������B�㐅���@���J�ɂ��Y�݂ɂȂ��A���X�̌�e�Ԃ����\���グ�Ă������A���ꂾ���ł͐S���ƂȂ��v�������ꂽ���A���h���������ċߓ��s�[�Ȃ���ׂ��悵���������ꂽ�B
���h�炪�\���グ�āA�u���R�s�K�̂��Ƃ͕����̂��Ƃł͂������܂���B�܂��֓��ɐ\�����킵�A���̎�����Ȃ���A�ɂ킩�ɂł��邱�Ƃł͂������܂���v�Ɛ\���グ��ƁA�u����ł͍s�[�͎���߂悤�B���̑���ɁA�֒��̒C���̊p�̒z�n���@�̌䏊�̜���̊p�܂ŁA��q�ō��L���������ɉ˂���B�֗��̓����s�K����̂͏�̂��Ƃł���B�L������L���ֈڂ�̂�N���s�[�Ɛ\�������B���X�ɍ��L�����d���Ă�ׂ��v�Ƌ��āA���ɉ@�̂��Ƃ֍s�[���ꂽ�Ƃ����B
���ۏ\��N��\�l���̋L�����@�㐅���@�Əd�@
�i�C�x�����{�̒��N�����c�����̂��������₤�Ɖ����������āj�u���ꂱ��������͂��߈�؈ꑐ�Ɏ���܂ł��Ƃ��Ƃ��㐅���@�̌䐻�ɂȂ������̂��v
�i���̂ɂ��̂悤�ȗ��ꂽ�Ƃ���ɂ�����������ꂽ�̂��q�˂�Ɓj�u�s�ӂɂ��̎R������ɓ�����Ă��A�n������R�������l���Ȃ���āA����̐��`�������Ȃ���Ă���A�����͂��ߓ��A�̐ɂ�����܂ł݂ȓy�Ŗ͌^�������炦�A���`�̏��X�ɒu���Ă݂Č`�ǂ��Ȃ�悤�ɂ�������A���A�����ł�������ɁA�����d���̏����ɒ둢��̍I�݂Ȏ҂������̂ŁA�����Â݂̗`�ɏ悹�āA�����S�Ɣl�̉��^�Ȃǂ����ɂ��Ă��т��ь����Ɍ��킳�ꂽ�B
���������@�c�̌䏊�ɂȂ�Ƃ����\�����h��̎��ɂ܂œ͂��A�䏊�܂ŎQ��A�w���������̉\���܂������A���������ɍs�K�Ȃ���邨�u�̂������܂�����A���䂦�ɂ��ꂪ���ɋ�������Ȃ��̂ł����B���X�Ɋ֓��\�����킵�A�ǂ���ւȂ�Ƃ��s�K�Ȃ���܂��悤���v�炢�܂��̂ɁA���̎e�ׂ��������܂��傤�x�Ɛ\���グ���B�b���ɒB���A�w���V�ɂ͏������S�z�͂���ʁB���l�ȉ\�͑S�������t���Ȃ����Ƃ��B�g�����������Ă���Ɠ��V�ɐ\����������B�g�����������̂��B�N�����ƌ������ƁA�݂ȋ����ł���Ǝv���x�Ƌ������ꂽ�̂ŁA���h��͈ꌾ���Ȃ��ޏo�����v
���ۏ\�l�N�l���\�Z���̋L�����@�߉q�M�q�Əd�@
�q���h��i�d�@�j�͌`�̔@�����l�ŁA���R���Ƃ��S�Ղ��ԕ��ł����Ό���K�₵�����A���i��ł��������ɂ͂��т��ђ��̓��Ɍ����������B���h��͎��璃�P�������Ē���҂����Ƃ��D�B
���鎞���R�������K�˂����ƁA���h��͑ҍ��ł����̏��P�Œ���҂��Ă������A�u���̒��͌�O�ɍ����グ��Z���ŁA���҂��Ă����Ƃ���ł����A�����������łɂȂ����ʖڂȂ���B���߂͏���Ȃǂ����U���ĎQ��܂��̂ŁA���Ȃ����݂Ɍ�O�����̉P�Œ���҂���Ă݂Ă͂������v�ƉP�������グ�ď���ɓ��낤�Ƃ���Ƃ�����ĂѕԂ���āA�u��������ɔ҂����āA�h�B�̒��͎��̊֔����҂��ꂽ�̂��ƁA�l�X�ɘb����������݂ł��낤�v�Ƌ�A���h���듪��@���āA�u���������܂���B����\���A���l�Ɏv���t�������̓��ł���܂������A�����ɂ��������Ȃ��ꂽ���ɂ�����v�Ɠ�l�Ƃ�����Ȃ��ꂽ�Ƃ��B
���ۏ\���N�㌎�\����̋L�����@������@�Əd�@
������@�͊i�ʂ̑��̂����ł��点��ꂽ���Ƃ��i�����l�́j��X���ɂȂ��Ă����B�q���h�炪���i����߂Ă������̂��Ƃł������B�㐅���@���J�ɂ��Y�݂ɂȂ��A���X�̌�e�Ԃ����\���グ�Ă������A���ꂾ���ł͐S���ƂȂ��v�������ꂽ���A���h���������ċߓ��s�[�Ȃ���ׂ��悵���������ꂽ�B
���h�炪�\���グ�āA�u���R�s�K�̂��Ƃ͕����̂��Ƃł͂������܂���B�܂��֓��ɐ\�����킵�A���̎�����Ȃ���A�ɂ킩�ɂł��邱�Ƃł͂������܂���v�Ɛ\���グ��ƁA�u����ł͍s�[�͎���߂悤�B���̑���ɁA�֒��̒C���̊p�̒z�n���@�̌䏊�̜���̊p�܂ŁA��q�ō��L���������ɉ˂���B�֗��̓����s�K����̂͏�̂��Ƃł���B�L������L���ֈڂ�̂�N���s�[�Ɛ\�������B���X�ɍ��L�����d���Ă�ׂ��v�Ƌ��āA���ɉ@�̂��Ƃ֍s�[���ꂽ�Ƃ����B
���ۏ\��N��\�l���̋L�����@�㐅���@�Əd�@
�i�C�x�����{�̒��N�����c�����̂��������₤�Ɖ����������āj�u���ꂱ��������͂��߈�؈ꑐ�Ɏ���܂ł��Ƃ��Ƃ��㐅���@�̌䐻�ɂȂ������̂��v
�i���̂ɂ��̂悤�ȗ��ꂽ�Ƃ���ɂ�����������ꂽ�̂��q�˂�Ɓj�u�s�ӂɂ��̎R������ɓ�����Ă��A�n������R�������l���Ȃ���āA����̐��`�������Ȃ���Ă���A�����͂��ߓ��A�̐ɂ�����܂ł݂ȓy�Ŗ͌^�������炦�A���`�̏��X�ɒu���Ă݂Č`�ǂ��Ȃ�悤�ɂ�������A���A�����ł�������ɁA�����d���̏����ɒ둢��̍I�݂Ȏ҂������̂ŁA�����Â݂̗`�ɏ悹�āA�����S�Ɣl�̉��^�Ȃǂ����ɂ��Ă��т��ь����Ɍ��킳�ꂽ�B
���������@�c�̌䏊�ɂȂ�Ƃ����\�����h��̎��ɂ܂œ͂��A�䏊�܂ŎQ��A�w���������̉\���܂������A���������ɍs�K�Ȃ���邨�u�̂������܂�����A���䂦�ɂ��ꂪ���ɋ�������Ȃ��̂ł����B���X�Ɋ֓��\�����킵�A�ǂ���ւȂ�Ƃ��s�K�Ȃ���܂��悤���v�炢�܂��̂ɁA���̎e�ׂ��������܂��傤�x�Ɛ\���グ���B�b���ɒB���A�w���V�ɂ͏������S�z�͂���ʁB���l�ȉ\�͑S�������t���Ȃ����Ƃ��B�g�����������Ă���Ɠ��V�ɐ\����������B�g�����������̂��B�N�����ƌ������ƁA�݂ȋ����ł���Ǝv���x�Ƌ������ꂽ�̂ŁA���h��͈ꌾ���Ȃ��ޏo�����v
220�l�Ԏ����l�N
2022/05/30(��) 21:09:49.36ID:u4RuVBEe ���ʓV�c�̊O�o�͍s�K�A�c���q�Ȃǂ̊O�o�͍s�[�ł����A�����Ō�����V�c�����g�̊O�o��
�s�[�ƌ����Ă���̂́A���e�ł���㐅���@�̂��Ƃ�K��邽�߁A���̌����\���Ȃ̂ł��傤��
�s�[�ƌ����Ă���̂́A���e�ł���㐅���@�̂��Ƃ�K��邽�߁A���̌����\���Ȃ̂ł��傤��
221�l�Ԏ����l�N
2022/05/31(��) 00:45:01.48ID:cpU+9pie �㐅���@���̑�ȓV�c���������Ƃ̕\������
222�l�Ԏ����l�N
2022/05/31(��) 07:15:37.64ID:W1yvV688 >>218
����(����)���͐M�Z�̍��l�̎�o�g�ŁA���c�㐙��n��������悭����o���̉�
�đ�˂ł̉��~�ɓV�_���܂��J��A�Ւn�����݂͕đ�s�̐����V�������Ƃ��Đ�������Ă��܂�
���q���͓����ݏZ�ł�
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/1810.html
����(����)���͐M�Z�̍��l�̎�o�g�ŁA���c�㐙��n��������悭����o���̉�
�đ�˂ł̉��~�ɓV�_���܂��J��A�Ւn�����݂͕đ�s�̐����V�������Ƃ��Đ�������Ă��܂�
���q���͓����ݏZ�ł�
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/1810.html
223�l�Ԏ����l�N
2022/05/31(��) 09:40:20.63ID:d3csJQJL �ǂ݂́u�ɂ����傤�v
�㐙�ƒ��̏ꍇ�A������k���ꂼ��̏�����́A�M�z�̒n���̓ǂݗR�����炩
�������傤�A�Ђ������傤�A�݂Ȃ݂��傤�A�ł���
�㐙�ƒ��̏ꍇ�A������k���ꂼ��̏�����́A�M�z�̒n���̓ǂݗR�����炩
�������傤�A�Ђ������傤�A�݂Ȃ݂��傤�A�ł���
224�l�Ԏ����l�N
2022/05/31(��) 09:57:18.29ID:d3csJQJL �����ď㉺�̏�����͂ǂ����ƂȂ�ƁA�������͂��傤���傤�A�����傤�Ȃ�ł���
225�l�Ԏ����l�N
2022/05/31(��) 10:04:25.96ID:d3csJQJL �����吳���̉�d�̑啨�ɉ����j�J(�����傤��������)�Ƃ����ЂƂ����܂����A�đ�o�g�ł�
226�l�Ԏ����l�N
2022/05/31(��) 23:03:58.88ID:Nwrw8Vlj �ŋL���ۏ\�Z�N�����\����̋L�����@���@����
�E����v�̘b�ɁB�o�~�͒��z�͓����ł��\���̗ǂ������Ŗʔ����������ς���Ă���B�́A���@�O���{�i�ʖj�͔��Ȕ얞�ł�������j���������A�㐼�@�̌�O�ŁA�u�I���̖݂͝n���悤�������ƐH�ׂ��˂���̂ł��B�傫�����Ă������ĐH��˂Ȃ�ʂ悤�ł͂��̕��������Ȃ��Ă��܂��B�Ђƌ��ɐH�ׂ���傫���ɍ��̂��悢�̂ł��v�Ɛ\���グ��̂��A�T�ŕ����Ă����Ⴂ�a��l�������A�ŁA�u�ǂ�قǑ傫���Ƃ����@�Ȃ�Ђƌ��ɐH�ׂ��邾�낤�v�Ƒ�����Ă������A�N��炪
���@�@���̍L�����@�m���ʂ�@���܂��ɒʂ�@�G�ϖ݂ł�
�Ƌ��̂��r�B������������̒��[���i���ʂ��j���A�u�w���܂��ɒʂ�x�ł͂Ȃ��w���ꂸ�ɗ�����x�Ƃ��������̂��v�Ƌ����̂ŁA�܂�����ɂȂ����B�b���ɒB���Ď��������ɂȂ�ꂽ�Ƃ��B
����������\���������炵��
�E����v�̘b�ɁB�o�~�͒��z�͓����ł��\���̗ǂ������Ŗʔ����������ς���Ă���B�́A���@�O���{�i�ʖj�͔��Ȕ얞�ł�������j���������A�㐼�@�̌�O�ŁA�u�I���̖݂͝n���悤�������ƐH�ׂ��˂���̂ł��B�傫�����Ă������ĐH��˂Ȃ�ʂ悤�ł͂��̕��������Ȃ��Ă��܂��B�Ђƌ��ɐH�ׂ���傫���ɍ��̂��悢�̂ł��v�Ɛ\���グ��̂��A�T�ŕ����Ă����Ⴂ�a��l�������A�ŁA�u�ǂ�قǑ傫���Ƃ����@�Ȃ�Ђƌ��ɐH�ׂ��邾�낤�v�Ƒ�����Ă������A�N��炪
���@�@���̍L�����@�m���ʂ�@���܂��ɒʂ�@�G�ϖ݂ł�
�Ƌ��̂��r�B������������̒��[���i���ʂ��j���A�u�w���܂��ɒʂ�x�ł͂Ȃ��w���ꂸ�ɗ�����x�Ƃ��������̂��v�Ƌ����̂ŁA�܂�����ɂȂ����B�b���ɒB���Ď��������ɂȂ�ꂽ�Ƃ��B
����������\���������炵��
227�l�Ԏ����l�N
2022/06/01(��) 22:24:41.03ID:bE9TNziO �ŋL���ۏ\�Z�N�����\����̋L�����@���ؓ֒�
����i�����l�j�̂��b�ɁB��̓֒��i���ؓ֒��j�͋ߍ��̖��M�ŕ��Ԏ҂����Ȃ����A�\��܂ňꕶ�s�ʂŃC���n�̃C�̎����m��Ȃ������B�O���̋��̏�ŁA�n�q���������o���āu������ǂ�ʼn������܂��v�ƌ����̂ɁA�ǂ߂Ȃ��������Ƃ�[���p���Ď�K�����n�߂��ƕ����B���ɂ���قǂ̐l���ɂȂ����̂́A�܂��ƂɎu�Ƃ������t�̌��{�ƌ�����̂͂������A�����Ė��l���Ƃ����l�́A���܂���̍˔\�݂̂ɂĖ��l���ƂȂ�̂͏��Ȃ��A���炩�̋@������āA���l���ƂȂ铹���J���[��������̂��낤�Ǝv����B
����i�����l�j�̂��b�ɁB��̓֒��i���ؓ֒��j�͋ߍ��̖��M�ŕ��Ԏ҂����Ȃ����A�\��܂ňꕶ�s�ʂŃC���n�̃C�̎����m��Ȃ������B�O���̋��̏�ŁA�n�q���������o���āu������ǂ�ʼn������܂��v�ƌ����̂ɁA�ǂ߂Ȃ��������Ƃ�[���p���Ď�K�����n�߂��ƕ����B���ɂ���قǂ̐l���ɂȂ����̂́A�܂��ƂɎu�Ƃ������t�̌��{�ƌ�����̂͂������A�����Ė��l���Ƃ����l�́A���܂���̍˔\�݂̂ɂĖ��l���ƂȂ�̂͏��Ȃ��A���炩�̋@������āA���l���ƂȂ铹���J���[��������̂��낤�Ǝv����B
228�l�Ԏ����l�N
2022/06/03(��) 21:16:19.80ID:IglZJe0y �u�~���L�v����u�֒f(�ւт���)�̑����v
�O��(1555-1558)�̍��A���Ԃɒ|���Ƃ����l�������B
�Z������A�c�̌l������Ă����Ƃ���A����ă}���V�̓���藎�Ƃ��Ă��܂����B
���̎�͂ǂ��ɍs�������m��Ȃ������B
���N�A�|���͂��̂������ʂ肩���������A�O�N�̂��Ƃ͖Y��Ă��܂��Ă����B
�Ȃ����Ђǂ����C���Â��đς����Ȃ��Ȃ������߁A���ɉ炵�ĉ������Ƃ��Ă���ƁA���������̕��ł���߂����C�������̂ŁA�ڊo�߂Ă�������݂��B
����ƁA���N�藎�Ƃ����ւ̓����A���ɍ����Ă����㐡�ܕ��̏��e���ɂ��т���Ă����B
���e���͎���₩�甲���o�����̂ł������B
�|���͂�����݂đ傢�Ɋ�сA�v���Ύւ̓���藎�Ƃ����������S���������ƕs�v�c�Ɏv���A
�ւ̎���т����܂܂̏�ԂŁA���ԓa�ɂ��̏��e���������ɓ��ꂽ�B
�@���(���ԊӍN)�͊�ł���Ƃ������ƂŁA�Ɩ��Â��A�˂ɂ����Γ������B
������(�����@�H)�̖�������A�̂��ɂ͒|���I�Ɏ�ɗa���u���ꂽ�����ł���B
�O��(1555-1558)�̍��A���Ԃɒ|���Ƃ����l�������B
�Z������A�c�̌l������Ă����Ƃ���A����ă}���V�̓���藎�Ƃ��Ă��܂����B
���̎�͂ǂ��ɍs�������m��Ȃ������B
���N�A�|���͂��̂������ʂ肩���������A�O�N�̂��Ƃ͖Y��Ă��܂��Ă����B
�Ȃ����Ђǂ����C���Â��đς����Ȃ��Ȃ������߁A���ɉ炵�ĉ������Ƃ��Ă���ƁA���������̕��ł���߂����C�������̂ŁA�ڊo�߂Ă�������݂��B
����ƁA���N�藎�Ƃ����ւ̓����A���ɍ����Ă����㐡�ܕ��̏��e���ɂ��т���Ă����B
���e���͎���₩�甲���o�����̂ł������B
�|���͂�����݂đ傢�Ɋ�сA�v���Ύւ̓���藎�Ƃ����������S���������ƕs�v�c�Ɏv���A
�ւ̎���т����܂܂̏�ԂŁA���ԓa�ɂ��̏��e���������ɓ��ꂽ�B
�@���(���ԊӍN)�͊�ł���Ƃ������ƂŁA�Ɩ��Â��A�˂ɂ����Γ������B
������(�����@�H)�̖�������A�̂��ɂ͒|���I�Ɏ�ɗa���u���ꂽ�����ł���B
229�l�Ԏ����l�N
2022/06/06(��) 14:32:15.36ID:wwC56brm �u����G�ځv���猋��G�N�ƍ���
�G�N�������鎞����ɏo���Ƃ���A�ؗ����������w�����Ă��������Ă�������������B
�敥���̂��̂��e�֒ǂ���������A�G�N��������ʂ��Ă���Œ��ɂ��̖Ӑl���G�N���̌���Ăɋ߂Â����̂ŁA
�G�N���u���͂ǂ��ɍs���҂��v
�����u���͍����̉�ɎQ��̂ł����A�����J���~��A�������������߁A�����O�̖ؗ��𑐗��Ǝ��ւ��Ė߂�Ƃ���Ȃ̂ł��B
�a�l�̂��ʂ�Ƃ������ƂŁA���������M�ɒǂ�����Ă��܂��v�����������Ԃ��₵�Ă��܂��܂����B
�����Ȃ��Ă͂��Ƃ����ċl�߂ɂ����Ă���ނ����Ȃ��ƍs������������̂ł��v
�Ƌ��������\���グ���B
�G�N�����u�ӖڂɂȂ邾���łȂ��A�����Ӑl���炱���g���āA�������܂Ŏ��������Ƃ͕s���Ȃ��Ƃ��B
�����a�l�ƌĂԂ͉�̂��Ƃł���B
�������Z�ɂ��ė̓��̍������艺�ɂ��Ă�낤�v
�Ƌ�ꂽ�Ƃ���A
�Ӑl�͂��炩���Ă���Ǝv��
�u�a�l�͂��łɂ��ʂ�ɂȂ����ł��傤�ɁA�R���������ł��ȁB
���Ƃ��a�l�̂͂��炢�ł���w�⏊�͂��Ă����A�l���O�ƌ�����ׂ邱�Ƃ������ł��傤�v
�ƂԂ₢�čQ���������ʂ�߂����B
�����ŏG�N���͂����ɌN���������A���̍��������Z�Ƃ����B
�������Č䍑���̍����͔ނɗ��������Ƃ����B
�G�N�������鎞����ɏo���Ƃ���A�ؗ����������w�����Ă��������Ă�������������B
�敥���̂��̂��e�֒ǂ���������A�G�N��������ʂ��Ă���Œ��ɂ��̖Ӑl���G�N���̌���Ăɋ߂Â����̂ŁA
�G�N���u���͂ǂ��ɍs���҂��v
�����u���͍����̉�ɎQ��̂ł����A�����J���~��A�������������߁A�����O�̖ؗ��𑐗��Ǝ��ւ��Ė߂�Ƃ���Ȃ̂ł��B
�a�l�̂��ʂ�Ƃ������ƂŁA���������M�ɒǂ�����Ă��܂��v�����������Ԃ��₵�Ă��܂��܂����B
�����Ȃ��Ă͂��Ƃ����ċl�߂ɂ����Ă���ނ����Ȃ��ƍs������������̂ł��v
�Ƌ��������\���グ���B
�G�N�����u�ӖڂɂȂ邾���łȂ��A�����Ӑl���炱���g���āA�������܂Ŏ��������Ƃ͕s���Ȃ��Ƃ��B
�����a�l�ƌĂԂ͉�̂��Ƃł���B
�������Z�ɂ��ė̓��̍������艺�ɂ��Ă�낤�v
�Ƌ�ꂽ�Ƃ���A
�Ӑl�͂��炩���Ă���Ǝv��
�u�a�l�͂��łɂ��ʂ�ɂȂ����ł��傤�ɁA�R���������ł��ȁB
���Ƃ��a�l�̂͂��炢�ł���w�⏊�͂��Ă����A�l���O�ƌ�����ׂ邱�Ƃ������ł��傤�v
�ƂԂ₢�čQ���������ʂ�߂����B
�����ŏG�N���͂����ɌN���������A���̍��������Z�Ƃ����B
�������Č䍑���̍����͔ނɗ��������Ƃ����B
230�l�Ԏ����l�N
2022/06/06(��) 20:44:32.72ID:sDzb0bcz �ڂȂ��@�Ȃ�
231�l�Ԏ����l�N
2022/06/08(��) 15:28:40.64ID:75f8/pZz ���B�i�O�c�Ɓj�̉Ɛb�E�g�c�呠�́A���ꗐ�̎��ɍ��̎w�Ύː��A�d�w�ƐH�w�i�l�����w�j�̂�
�S���ł��������A�|�͗P����Ă����B
�O�c���킪������A����ɏo���̂����A���߂̑��叏�i��̑��v�Ɍ��т���傫�ȑg���̏��j�Ƌ���
�������Ă��܂��A�ӂ�̐X�ɓ���A�̎}�Ɏ~�܂������A�叏�����܂��āA��͋t���܂��v���Ă����B
����͋g�c�呠���ĂсA�u�ǂ��ɂ����āA��Ȃ�ʂ悤�Ɏˎ��v�Ɩ������B
�呠�͈�U�͎��ނ������̂́A�ߏd���u�����v�Ə������A��҂�Ԃ��A��̐^���˂��悤�Ɍ��������A
���̂܂ܔ�ы������̂��A������̐Ղ����Ĕ�я�����B
����͑呠�Ɂu���Ǝ˂����̂��A���_�̎��ł���I�v�Ə̎^�������A�呠��
�u�ɗ��܂����叏�́A�˂Ă��������Ƃ͏o���܂���B���̂��ߐ��q�i���Ƃ����E�叏�ɗp���锪�̎��^�̋���j
���ˊ������̂ł��B�܂��������������A��ɘh�̉H��p����̂͌����܂��B�H���C��đ�ɂ�����������
���ɒɂ�����ł��B�̂ɏ_�炩���H��p���Ď˂邱�Ƃ��A�̎��ł�����܂��B�v
�Ɛ\�����Ƃ���
�i�V���Ӂj
�S���ł��������A�|�͗P����Ă����B
�O�c���킪������A����ɏo���̂����A���߂̑��叏�i��̑��v�Ɍ��т���傫�ȑg���̏��j�Ƌ���
�������Ă��܂��A�ӂ�̐X�ɓ���A�̎}�Ɏ~�܂������A�叏�����܂��āA��͋t���܂��v���Ă����B
����͋g�c�呠���ĂсA�u�ǂ��ɂ����āA��Ȃ�ʂ悤�Ɏˎ��v�Ɩ������B
�呠�͈�U�͎��ނ������̂́A�ߏd���u�����v�Ə������A��҂�Ԃ��A��̐^���˂��悤�Ɍ��������A
���̂܂ܔ�ы������̂��A������̐Ղ����Ĕ�я�����B
����͑呠�Ɂu���Ǝ˂����̂��A���_�̎��ł���I�v�Ə̎^�������A�呠��
�u�ɗ��܂����叏�́A�˂Ă��������Ƃ͏o���܂���B���̂��ߐ��q�i���Ƃ����E�叏�ɗp���锪�̎��^�̋���j
���ˊ������̂ł��B�܂��������������A��ɘh�̉H��p����̂͌����܂��B�H���C��đ�ɂ�����������
���ɒɂ�����ł��B�̂ɏ_�炩���H��p���Ď˂邱�Ƃ��A�̎��ł�����܂��B�v
�Ɛ\�����Ƃ���
�i�V���Ӂj
232�l�Ԏ����l�N
2022/06/08(��) 19:38:04.31ID:1fky5inv �̎��ł�����܂����đO�ɂ�������l������c
233�l�Ԏ����l�N
2022/06/09(��) 14:17:59.05ID:dZuFsclC �S���S13�݂����Ȏ�����
234�l�Ԏ����l�N
2022/06/11(�y) 18:36:07.05ID:E6KPR8lH �u����G�ځv���璷�@�䕔���e�̉Ɛb�A�c���V�E�q��̘b
�c���V�E�q�傪�������Ƃɂ�
�u��͖��M�ł���B
�u���a�v�Ƃ�����������m�ɐq�˂��Ƃ���A�u���̂�܂��v�ƌ���ꂽ�B
����قǖނ��Ȏ��͂���܂��B
��ɗՂ�œf���҂����邪�A����͋��ɂ��̎��a�����邽�߂��낤���B
���a�͑D�����Ɠ������Ƃł���B
�M�ɏ�鎞�A���ɋ��𐘂��A�@�ɋk�̔���������߂A���g�̎��͐��킸�A��g�̎��͋��̓������݂����ēf���Ă��܂��B
�N�ł���̎��́A����n�������݂��Ƃ��Ȃ��U�镑���Ȃǂ��Ȃ��B
��킷�鎞�́A���܂���Ă̋��̂�܂����N����A�S�������A�`�����O�����̂ĂĂ��܂��̂��B�v
�c���V�E�q�傪�������Ƃɂ�
�u��͖��M�ł���B
�u���a�v�Ƃ�����������m�ɐq�˂��Ƃ���A�u���̂�܂��v�ƌ���ꂽ�B
����قǖނ��Ȏ��͂���܂��B
��ɗՂ�œf���҂����邪�A����͋��ɂ��̎��a�����邽�߂��낤���B
���a�͑D�����Ɠ������Ƃł���B
�M�ɏ�鎞�A���ɋ��𐘂��A�@�ɋk�̔���������߂A���g�̎��͐��킸�A��g�̎��͋��̓������݂����ēf���Ă��܂��B
�N�ł���̎��́A����n�������݂��Ƃ��Ȃ��U�镑���Ȃǂ��Ȃ��B
��킷�鎞�́A���܂���Ă̋��̂�܂����N����A�S�������A�`�����O�����̂ĂĂ��܂��̂��B�v
235�l�Ԏ����l�N
2022/06/11(�y) 19:51:06.22ID:q+6P8a6t �挎�̋L���ł����A���������t�@���������ʗ�Ԃ��A�Ȃ�ƐV������{�݂���ʼn^�s���ꂽ�����ȁE�E
�Ȃ��A�����܂ł�����͕đ�㐙�����ق̐퍑����W�u�퍑���s�Ə㐙�Ɓv
�̈�ł���܂�
���������ƃR���{�A�đ�ւ��Վ���ԁ@�t�@��380�l���u���n����v�̗�
�R�`�V��5��29��
https://news.yahoo.co.jp/articles/19f007969b1a2585d77cc8aecaa120d9aec60530
���J���̐l�C�A�j���u���w���������\�Ԋہ\�x~�ጎ��~�v�ƃR���{���[�V���������i�q�����{�̒c�̗Վ���Ԃ�28���A�R�`�V�������̎ԗ����g�p���A
���\�đ�Ԃʼn^�s����A��380�l�̃t�@���炪�đ�s��K�ꂽ�B���������͑S���̖������[�l�������j���L�����N�^�[���o�ꂷ��X�g�[���[�ŁA
�V���[�Y�ɂ͓��s�̏㐙�����قœW�����̒Z����͂����L�������o�ꂷ��B
�t�@���͓������ق�K�˂�Ȃǁu���n����v���y���B
JR�����{�����R���{�T�C�g
https://www.jreast.co.jp/sendai/hanamaru-yuinroku/
�Ȃ��A�����܂ł�����͕đ�㐙�����ق̐퍑����W�u�퍑���s�Ə㐙�Ɓv
�̈�ł���܂�
���������ƃR���{�A�đ�ւ��Վ���ԁ@�t�@��380�l���u���n����v�̗�
�R�`�V��5��29��
https://news.yahoo.co.jp/articles/19f007969b1a2585d77cc8aecaa120d9aec60530
���J���̐l�C�A�j���u���w���������\�Ԋہ\�x~�ጎ��~�v�ƃR���{���[�V���������i�q�����{�̒c�̗Վ���Ԃ�28���A�R�`�V�������̎ԗ����g�p���A
���\�đ�Ԃʼn^�s����A��380�l�̃t�@���炪�đ�s��K�ꂽ�B���������͑S���̖������[�l�������j���L�����N�^�[���o�ꂷ��X�g�[���[�ŁA
�V���[�Y�ɂ͓��s�̏㐙�����قœW�����̒Z����͂����L�������o�ꂷ��B
�t�@���͓������ق�K�˂�Ȃǁu���n����v���y���B
JR�����{�����R���{�T�C�g
https://www.jreast.co.jp/sendai/hanamaru-yuinroku/
236�l�Ԏ����l�N
2022/06/11(�y) 19:54:49.46ID:q+6P8a6t �����3���̓Ȗ،������s�̏ꍇ��
�����t�@����45���ԂłQ��5587�l�@�g���n�h�����̓��ʓW��
����V��3/29
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/570615
�y�����z�����䂩��̖����u�R�W�؍��L�i��܂���肭�ɂЂ�j�v�i���d�v�������j�Ȃ�100�_�̖��i���s�����p�قœW������
�s��100���N�L�O���ʓW�u�퍑�����@���������i���������Ȃ����j�̕��Ɣ�-���̖����͉i���i�Ƃ�j��-�v���A27���������B
�����Ǒ�̂��ߓ�������S�\�Ƃ��A45���Ԃ̉�����̉��ד���Ґ��͂Q��5587�l�������B
�����t�@����45���ԂłQ��5587�l�@�g���n�h�����̓��ʓW��
����V��3/29
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/570615
�y�����z�����䂩��̖����u�R�W�؍��L�i��܂���肭�ɂЂ�j�v�i���d�v�������j�Ȃ�100�_�̖��i���s�����p�قœW������
�s��100���N�L�O���ʓW�u�퍑�����@���������i���������Ȃ����j�̕��Ɣ�-���̖����͉i���i�Ƃ�j��-�v���A27���������B
�����Ǒ�̂��ߓ�������S�\�Ƃ��A45���Ԃ̉�����̉��ד���Ґ��͂Q��5587�l�������B
237�l�Ԏ����l�N
2022/06/11(�y) 20:01:01.84ID:q+6P8a6t ���ꂪ�������������ʂ�
��ނ͂Ƃ�����A�t�@���ƍs���A�����ّo�����悢�����Ɍ������Ă��邱�̗���͂��肪�����ł���
���������܂œ����ȊO�̐퍑�W�����[�����Ă���Ă܂�
�����u�R�W�؍��L�v�����s���擾���ց@�Q�[���u���������v�Ől�C
�����V��6/10
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5983df327381fc3596a1cd9fd1e63cb6a7ee7d7
���y���R����̓��H�E�x�썑�L�������̎�E���������̈˗��Œb�����Ƃ���铁�u�R�W�i��܂����j���L�v�i�l���A���d�v�������j�ɂ��āA
�Ȗ،������s�̑��쏮�G�s����10���̎s�c��S�����c��ŁA���L�҂��s�ɊǗ���C�������ӌ���`���Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ��A
�擾�Ɍ��������ɓ���l�����������B
��ނ͂Ƃ�����A�t�@���ƍs���A�����ّo�����悢�����Ɍ������Ă��邱�̗���͂��肪�����ł���
���������܂œ����ȊO�̐퍑�W�����[�����Ă���Ă܂�
�����u�R�W�؍��L�v�����s���擾���ց@�Q�[���u���������v�Ől�C
�����V��6/10
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5983df327381fc3596a1cd9fd1e63cb6a7ee7d7
���y���R����̓��H�E�x�썑�L�������̎�E���������̈˗��Œb�����Ƃ���铁�u�R�W�i��܂����j���L�v�i�l���A���d�v�������j�ɂ��āA
�Ȗ،������s�̑��쏮�G�s����10���̎s�c��S�����c��ŁA���L�҂��s�ɊǗ���C�������ӌ���`���Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ��A
�擾�Ɍ��������ɓ���l�����������B
238�l�Ԏ����l�N
2022/06/11(�y) 20:33:27.11ID:E6KPR8lH �u����G�ځv����㐙���M�̈���
�㐙���M�̑����͏������i���q�s���O�ڈꐡ�B�쒆���ɂĐM���Ɨ������������̑����ł���j�A
�J�i�����r��j�A�|�Ҍ����Ƃ����A����̂�������̎O�����������B
�|�Ҍ����́A�����z��V�Â̕S���̓��ł��������A�s�v�c�̗쌕�Ƃ������ƂŔ鑠���Ď����Ă����̂��A�|�ҎO�͎�i�|���c�j�j�����]���ĉƕ�Ƃ����B
�₪�Č��M�̎��ɓ���A���M�͌����Ďw���Ƃ����B
�O����N�i1556�N�j�O����\�ܓ���A��x�ڂ̐쒆������̂Ƃ��A�M���̉Ɛl�E�`�ڕ����v�Ƃ������̂���擛�̓S�C���\���Ă����Ƃ���ɁA���M�����Ďa�肩����A���̒|�Ҍ����Ő蕚�����B
��͉F�����x�͎��s�̘Y�}�E�˓�������������B
�邪�����čb�B�O���`�ڂ̎��[�������Ƃ���A�����Ă�����擛�̓�̖ړ��̏��ؒf���Đ^����ɂ��Ă����B
�u�������������g���Đ����̂��낤�H�v�ƊF�����B
�钆�̂��߁A�����l�����Ȃ��������A��߂Č��M������Ȃ������̂��낤�ƌ����������B
���̓��A�i���̑�ɋ��s�ւ̂ڂ点�����炦���Ƃ���A��N�قǂւĂ悤�₭�����炦���ł��A�z��ɖ߂��Ă����B
�i���̉ƘV�A���]�E�{�����͂��߁A���̂ق��h�V�ǂ����ĂъA���̓��������Ȃ������B
�u�������s�̐��Ŗ��������������āA�����ɂł������̂��B�܂�ŐV���̂悤���v�Ƃ��̂��̂͗_�߂��₵���B
�㐙���M�̑����͏������i���q�s���O�ڈꐡ�B�쒆���ɂĐM���Ɨ������������̑����ł���j�A
�J�i�����r��j�A�|�Ҍ����Ƃ����A����̂�������̎O�����������B
�|�Ҍ����́A�����z��V�Â̕S���̓��ł��������A�s�v�c�̗쌕�Ƃ������ƂŔ鑠���Ď����Ă����̂��A�|�ҎO�͎�i�|���c�j�j�����]���ĉƕ�Ƃ����B
�₪�Č��M�̎��ɓ���A���M�͌����Ďw���Ƃ����B
�O����N�i1556�N�j�O����\�ܓ���A��x�ڂ̐쒆������̂Ƃ��A�M���̉Ɛl�E�`�ڕ����v�Ƃ������̂���擛�̓S�C���\���Ă����Ƃ���ɁA���M�����Ďa�肩����A���̒|�Ҍ����Ő蕚�����B
��͉F�����x�͎��s�̘Y�}�E�˓�������������B
�邪�����čb�B�O���`�ڂ̎��[�������Ƃ���A�����Ă�����擛�̓�̖ړ��̏��ؒf���Đ^����ɂ��Ă����B
�u�������������g���Đ����̂��낤�H�v�ƊF�����B
�钆�̂��߁A�����l�����Ȃ��������A��߂Č��M������Ȃ������̂��낤�ƌ����������B
���̓��A�i���̑�ɋ��s�ւ̂ڂ点�����炦���Ƃ���A��N�قǂւĂ悤�₭�����炦���ł��A�z��ɖ߂��Ă����B
�i���̉ƘV�A���]�E�{�����͂��߁A���̂ق��h�V�ǂ����ĂъA���̓��������Ȃ������B
�u�������s�̐��Ŗ��������������āA�����ɂł������̂��B�܂�ŐV���̂悤���v�Ƃ��̂��̂͗_�߂��₵���B
239�l�Ԏ����l�N
2022/06/11(�y) 20:35:15.85ID:E6KPR8lH ���������̎�����̒|�ҎO�͎�͂�������ƌ��āA
�u����͌䓖�Ƃ̌����ł͂������܂���B��߂Ď��ւ������̂ł��傤�v�ƌ������B
�i���u���̖ڗ����͂ǂ��������Ƃ��H�v
�O�͎�u���̌䓁�͂͂������ꐡ�ܕ���A���̂��ɔn�̖ш�Ƃ����قǂ̌�������A
�w�\����w���ɒʂ��Ă��܂����B
���ꂪ���łȂ���Βm��l�����Ȃ��ł��傤�v
�����ŎO�͎�����s�ɂ̂ڂ点�āA�O�͎�͂��炭���ɑ؍݂��A���O�����̈�ڔ�������O�ڂ̔��������߂��Ƃ���A�͂����Đ����̓���莝���ė���҂������B
�����ł��ꂱ�����|�Ҍ����̐��^�̂��̂ł���A�ƎO�͎�͂��̎��Γc��������ɑi�����Ƃ���A�U�����o�����ߐl�\�O�l������߂Ƃ�A���쉪�������ɂ������B
�̂��ɐ��^�̌������O�͎�͉z��Ɏ����A��A�i���̑O�ł��̂��̌��ɔn�̖т���؈����ʂ��Č����\�����B
�i�����͂��ߏ��l�́u��̓��v���Ɗ������B
���̂��Ƃ��G�g���̏㕷�ɒB���A�قǂȂ��i���Ɍ䏊�]������A�G�g���Ɏw����点���B
��◎��̂Ƃ��A�钆���Ă��Ă����Q�l�͂��������Ęa��E�͓��̊Ԃɗ����Ă������Ɖ\�����������߁A
���R�Ƃ�������܂��܂Ɍ�F�������������A�Ƃ��Ƃ����̂��肩�͂킩��Ȃ������Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-546.html
�㐙���M�Ɓu�|�������v�E�����b
�ȑO�ɏo���̂Ƃ͔����ɈႤ�b
�u�F������s�v�̖��O���o�Ă���̂Řb�����ł�낵�����肢���܂��B
�u����͌䓖�Ƃ̌����ł͂������܂���B��߂Ď��ւ������̂ł��傤�v�ƌ������B
�i���u���̖ڗ����͂ǂ��������Ƃ��H�v
�O�͎�u���̌䓁�͂͂������ꐡ�ܕ���A���̂��ɔn�̖ш�Ƃ����قǂ̌�������A
�w�\����w���ɒʂ��Ă��܂����B
���ꂪ���łȂ���Βm��l�����Ȃ��ł��傤�v
�����ŎO�͎�����s�ɂ̂ڂ点�āA�O�͎�͂��炭���ɑ؍݂��A���O�����̈�ڔ�������O�ڂ̔��������߂��Ƃ���A�͂����Đ����̓���莝���ė���҂������B
�����ł��ꂱ�����|�Ҍ����̐��^�̂��̂ł���A�ƎO�͎�͂��̎��Γc��������ɑi�����Ƃ���A�U�����o�����ߐl�\�O�l������߂Ƃ�A���쉪�������ɂ������B
�̂��ɐ��^�̌������O�͎�͉z��Ɏ����A��A�i���̑O�ł��̂��̌��ɔn�̖т���؈����ʂ��Č����\�����B
�i�����͂��ߏ��l�́u��̓��v���Ɗ������B
���̂��Ƃ��G�g���̏㕷�ɒB���A�قǂȂ��i���Ɍ䏊�]������A�G�g���Ɏw����点���B
��◎��̂Ƃ��A�钆���Ă��Ă����Q�l�͂��������Ęa��E�͓��̊Ԃɗ����Ă������Ɖ\�����������߁A
���R�Ƃ�������܂��܂Ɍ�F�������������A�Ƃ��Ƃ����̂��肩�͂킩��Ȃ������Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-546.html
�㐙���M�Ɓu�|�������v�E�����b
�ȑO�ɏo���̂Ƃ͔����ɈႤ�b
�u�F������s�v�̖��O���o�Ă���̂Řb�����ł�낵�����肢���܂��B
240�l�Ԏ����l�N
2022/06/11(�y) 21:17:11.88ID:q+6P8a6t �������̉���̘b�ɂ�����܂������A�����̋��̓����Ǝ҂낭�ł��Ȃ�w
�퍑����̋��}�X�^�[�̘b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-4462.html
�퍑����̋��}�X�^�[�̘b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-4462.html
241�l�Ԏ����l�N
2022/06/12(��) 10:58:32.97ID:oljx+cCd �|���Ō��������m�Ńt�W�e���r�A�i�E���T�[�̒|���g���v���o������
���̒|���c�j�̎q��������
���̒|���c�j�̎q��������
242�l�Ԏ����l�N
2022/06/12(��) 19:35:25.84ID:7TbLK4mt �Q�n�������j������
�u�퍑��B�̓����ƍb�h�v
https://grekisi.pref.gunma.jp/event/1767/
�퍑����̏�B�̋��y���́A�܉Ɠ`�̒��̑��B�`����b�ɂ��Ă���ƌ����܂��B���B�`�͐��@�Ȃǂł����ւ��ȓ����݁A
���̌n�����p����B�̋��y����W�����܂��B�b�h�ł́A�㐙�═�c�Ƃ������퍑�喼�ɂ����p���ꂽ��B�b�h�t�̐��삵���M�d�Ȋ���
�m�F����Ă��܂��B�Õ�����G������킹�ēW�����A����҂��܂߂���B�̓����ƍb�h�̎p�Ƃ��̗��j�ɔ���܂��B
�ߘa4�N7��9���i�y�j~8��28���i���j
�E�O�� [ 7��9���i�y�j~7��31���i���j]
�E��� [ 8��2���i�j~8��28���i���j]
�W�����̂��̂͏�B�b��ɂ�铁���Ɗ��i�����j���S�ł��Ȃ�n���}�j�A�b�N�Ȃ��̂ɂȂ�\��ł����E�E�E
����̖ڋʂ͂Ȃ�Ƃ����Ă����]�����́u���̊��v�I
�đ�s�A�㐙�_�Ђ���݂��o���W�������̂͂Ȃ�Ə��߂Ăł��B�ߋ��A�����̕ʂ̍b�h�݂͑��o��������܂���������͖{���ɏ��߂Ă��Ƃ̂��ƁB
���̊��͊����i�����S�̔��������j����B�b��̍�A�Ƃ����킯�łق�400�N�Ԃ�̗��A��W���ł���܂��B
�������邩�͂킩��Ȃ��̂ŁA�R�`���O�ł̓W���͂��ꂩ��悱�̎������Ȃ���������܂���B��������݂̂Ȃ̂œ����ɋC��t���Đ����K���B
�����E�؉����@�Ɖ��L��b�̖{�����������W���ł��B
�u�{�����@�v�R��
http://iiwarui.blog90.fc2.com/?q=%E6%9C%AC%E5%BA%84
�u�퍑��B�̓����ƍb�h�v
https://grekisi.pref.gunma.jp/event/1767/
�퍑����̏�B�̋��y���́A�܉Ɠ`�̒��̑��B�`����b�ɂ��Ă���ƌ����܂��B���B�`�͐��@�Ȃǂł����ւ��ȓ����݁A
���̌n�����p����B�̋��y����W�����܂��B�b�h�ł́A�㐙�═�c�Ƃ������퍑�喼�ɂ����p���ꂽ��B�b�h�t�̐��삵���M�d�Ȋ���
�m�F����Ă��܂��B�Õ�����G������킹�ēW�����A����҂��܂߂���B�̓����ƍb�h�̎p�Ƃ��̗��j�ɔ���܂��B
�ߘa4�N7��9���i�y�j~8��28���i���j
�E�O�� [ 7��9���i�y�j~7��31���i���j]
�E��� [ 8��2���i�j~8��28���i���j]
�W�����̂��̂͏�B�b��ɂ�铁���Ɗ��i�����j���S�ł��Ȃ�n���}�j�A�b�N�Ȃ��̂ɂȂ�\��ł����E�E�E
����̖ڋʂ͂Ȃ�Ƃ����Ă����]�����́u���̊��v�I
�đ�s�A�㐙�_�Ђ���݂��o���W�������̂͂Ȃ�Ə��߂Ăł��B�ߋ��A�����̕ʂ̍b�h�݂͑��o��������܂���������͖{���ɏ��߂Ă��Ƃ̂��ƁB
���̊��͊����i�����S�̔��������j����B�b��̍�A�Ƃ����킯�łق�400�N�Ԃ�̗��A��W���ł���܂��B
�������邩�͂킩��Ȃ��̂ŁA�R�`���O�ł̓W���͂��ꂩ��悱�̎������Ȃ���������܂���B��������݂̂Ȃ̂œ����ɋC��t���Đ����K���B
�����E�؉����@�Ɖ��L��b�̖{�����������W���ł��B
�u�{�����@�v�R��
http://iiwarui.blog90.fc2.com/?q=%E6%9C%AC%E5%BA%84
243�l�Ԏ����l�N
2022/06/12(��) 19:37:25.45ID:7TbLK4mt http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13095.html
��b�L��URL�͂������ł����B
��b�L��URL�͂������ł����B
244�l�Ԏ����l�N
2022/06/12(��) 22:25:05.26ID:XbCAg6GT �A�t�B�J�X���E�܂��H
245�l�Ԏ����l�N
2022/06/13(��) 16:33:10.50ID:fimvgw9r ���~�̐w�A�I�{�ꈢ�g��i�����j�̐w�ɑ����̏镺���铢���̎��i�{�����̖��j�A
���g���肱�̎���e�ׂɏ��t�����ꂽ�B
���̌��g�Ƃ��Ė��{���A���I���s�����킳�ꂽ�B�Ƃ��낪�ނ͖I�{����̍���A
���s�̌v�炢�Ƃ��Ď�菜���������B�I�{��Ƃ̉Ɛb�������S����v�������A���{��
���g�̎w�}�ł���̂ŁA����ɔC�����B
���\�����A��䏊�i����ƍN�j�͖{�����䏄�����ꂽ�B�����Ė铢���̏�A����̗l�q��
�����ɂȂ��āu���g��A��y�����嫂��A�|���Ɍ����d���Ȃ�B�v�ƁA�r���䊴�������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
���g���肱�̎���e�ׂɏ��t�����ꂽ�B
���̌��g�Ƃ��Ė��{���A���I���s�����킳�ꂽ�B�Ƃ��낪�ނ͖I�{����̍���A
���s�̌v�炢�Ƃ��Ď�菜���������B�I�{��Ƃ̉Ɛb�������S����v�������A���{��
���g�̎w�}�ł���̂ŁA����ɔC�����B
���\�����A��䏊�i����ƍN�j�͖{�����䏄�����ꂽ�B�����Ė铢���̏�A����̗l�q��
�����ɂȂ��āu���g��A��y�����嫂��A�|���Ɍ����d���Ȃ�B�v�ƁA�r���䊴�������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
246�l�Ԏ����l�N
2022/06/15(��) 19:22:14.33ID:5g8e6ETv �u�~���L�v��葫���͓���̍���
�~��(����)�̉Ɛb�A�����͓���Ƃ����҂͏��߂͔n����ƂƂ��Ă������A�ҕ��E�͂�����A�g���Z�ڗ]�A�ᒆ����l�ƈ�����B
(�ʖ{�ɂ��u��̂����Ƀj�N�~����v�Ƃ���̂ŏd����)
�����Ŏ᎘�Ƃ����nj��p�������A���Ԓ��������A�~�c�ꔽ��^�����Ă����B
���������}���w����M�����ꂽ���A�͓���͂��}���ɏo�����A�g���ɉ߂����o�����ŁA�k�m�̎ҏ\��l�A�Ⴂ���\��l�A���F�𑵂��Ē�������r���L���ɋ��������B
���������s�R�Ɏv�����������Ƃ���A�̒n��r���������̂��Ă������߁A�n�E���ׂ��ƌ��܂����B
�����Œ��{�̊قŔn�̎��Â�����A�Ɖ͓�����Ăяo���A�b��E�n���Ɗ≮����R���q��ɎE�������B
�͓���̍Ȏq�͋����A�w�G�̍��ɂ͂����Ȃ��Ɣ�㍑���h�R�̘[�ɋ��Z�����B
�������Ԗv���̌�͌̋���Y�ꂪ���������̂��A���ďZ�����Ă����B
�E�n���͒䔯���Ĉ�p�Ə̂��ċ��Z���Ă������A
�u�����͓���̑��q�̌��������͌̋��ɋA���Ă���悤�����A�������ΐS���Ⴂ�ɂ��e�̋w�Ǝv�����낤�B�v
�Ƃ������������猹���̉Ƃ�K�ˁA�������J�ɘb��
�u��ӂƌ����Ȃ���A���Ȃ��̕��̎�����͉̂�ł���̂ŁA��������E���ĖS���ɕ�v
�ƌ������Ƃ���A
�����́u�����A�䂪���ɍ߂������Ď�N�ɂ���n�E���ꂽ�̂ɁA�ǂ����Ă������Ƃɋw��闝������܂��傤��v�ƌ������B
�������Ĉ�p�E�������l�͑��e���݁A���ۂ���悤�ɂȂ����B
�~��(����)�̉Ɛb�A�����͓���Ƃ����҂͏��߂͔n����ƂƂ��Ă������A�ҕ��E�͂�����A�g���Z�ڗ]�A�ᒆ����l�ƈ�����B
(�ʖ{�ɂ��u��̂����Ƀj�N�~����v�Ƃ���̂ŏd����)
�����Ŏ᎘�Ƃ����nj��p�������A���Ԓ��������A�~�c�ꔽ��^�����Ă����B
���������}���w����M�����ꂽ���A�͓���͂��}���ɏo�����A�g���ɉ߂����o�����ŁA�k�m�̎ҏ\��l�A�Ⴂ���\��l�A���F�𑵂��Ē�������r���L���ɋ��������B
���������s�R�Ɏv�����������Ƃ���A�̒n��r���������̂��Ă������߁A�n�E���ׂ��ƌ��܂����B
�����Œ��{�̊قŔn�̎��Â�����A�Ɖ͓�����Ăяo���A�b��E�n���Ɗ≮����R���q��ɎE�������B
�͓���̍Ȏq�͋����A�w�G�̍��ɂ͂����Ȃ��Ɣ�㍑���h�R�̘[�ɋ��Z�����B
�������Ԗv���̌�͌̋���Y�ꂪ���������̂��A���ďZ�����Ă����B
�E�n���͒䔯���Ĉ�p�Ə̂��ċ��Z���Ă������A
�u�����͓���̑��q�̌��������͌̋��ɋA���Ă���悤�����A�������ΐS���Ⴂ�ɂ��e�̋w�Ǝv�����낤�B�v
�Ƃ������������猹���̉Ƃ�K�ˁA�������J�ɘb��
�u��ӂƌ����Ȃ���A���Ȃ��̕��̎�����͉̂�ł���̂ŁA��������E���ĖS���ɕ�v
�ƌ������Ƃ���A
�����́u�����A�䂪���ɍ߂������Ď�N�ɂ���n�E���ꂽ�̂ɁA�ǂ����Ă������Ƃɋw��闝������܂��傤��v�ƌ������B
�������Ĉ�p�E�������l�͑��e���݁A���ۂ���悤�ɂȂ����B
247�l�Ԏ����l�N
2022/06/15(��) 19:23:16.94ID:5g8e6ETv �����͔_���Ƃ͂������܂�����n��ł������A�{�c�������オ��㍑�ɓ]�����ꂽ���A���̏]�m�A�O�l�������̉Ƃ̋߂���ʂ����B
�����͓c�ɍs���Ă������߉Ƃɂ͌����̍Ȃ������Ȃ��������A�]�m�����͉Ƃɗ�������A�u�H�������o���ĐH�킹��v�ƌ����Ă����B
�����̍Ȃ��u�n�����Ƃł��̂ŏo������̂�����܂���v�Ɠ������Ƃ���A�]�m�͓��Ɏ�������āu�����o���I�v�Ɠ{�����B
�����������A���Ă����̂�
�]�m�������u���̕��͒��傩�A����Α�|���˂����Ă��邪���D���Ȃ��Ƃ�B�����Ă݂�v
�ƌ����ƁA�]�m�����̘����s���Ԃ������������
�u�ł͌����č����グ�܂��傤�v�Ƒ�|����Ɏ��A���҂̖�������A�Ђƈ��������B
����������O�l�̏]�m�����͋����ē����A������낤�Ƃ����B
�����ō�̏�̖��̑�}���O�l�̏�Ɏ˗��Ƃ����Ƃ���A�O�l�́u��ƌ�Ɓv�ƌ����Ȃ��炩���܂�ɂȂ��ē������ƌ����B
�����͓c�ɍs���Ă������߉Ƃɂ͌����̍Ȃ������Ȃ��������A�]�m�����͉Ƃɗ�������A�u�H�������o���ĐH�킹��v�ƌ����Ă����B
�����̍Ȃ��u�n�����Ƃł��̂ŏo������̂�����܂���v�Ɠ������Ƃ���A�]�m�͓��Ɏ�������āu�����o���I�v�Ɠ{�����B
�����������A���Ă����̂�
�]�m�������u���̕��͒��傩�A����Α�|���˂����Ă��邪���D���Ȃ��Ƃ�B�����Ă݂�v
�ƌ����ƁA�]�m�����̘����s���Ԃ������������
�u�ł͌����č����グ�܂��傤�v�Ƒ�|����Ɏ��A���҂̖�������A�Ђƈ��������B
����������O�l�̏]�m�����͋����ē����A������낤�Ƃ����B
�����ō�̏�̖��̑�}���O�l�̏�Ɏ˗��Ƃ����Ƃ���A�O�l�́u��ƌ�Ɓv�ƌ����Ȃ��炩���܂�ɂȂ��ē������ƌ����B
248�l�Ԏ����l�N
2022/06/16(��) 07:36:11.87ID:zq9tP/lN �W���b�v�̍��Z�͋����Ƌ���������Ȃ�
249�l�Ԏ����l�N
2022/06/16(��) 11:44:22.01ID:T4UNuVOO ���ꔼ���̈�q���`�`���|�\�����
�܂��S�������`���Ă����
�܂��S�������`���Ă����
250�l�Ԏ����l�N
2022/06/17(��) 13:02:17.75ID:5J2Nx2M5 >>249
�₯�ɏڂ����Ǝv�����甼���l�ł�����w
�₯�ɏڂ����Ǝv�����甼���l�ł�����w
251�l�Ԏ����l�N
2022/06/17(��) 19:06:51.60ID:lpnKPrs/ �����E�����̒n���u�Ώ�u�v����g��(���̕�������)�̖��l�̘b
(���ۂ̍��ɏ����ꂽ�ߓc���E�q��u�����L�v�o�T�Ƃ���)
�j�֒��ɒ������@�L�Ƃ������̂������B
�����������ƁA���ɖ��l�Ə̂���Ă����B
���鎞�A���c���������ނ������č������Ȃ������B
�@�L�́u����͔��a�������Ȃ����Ă���u�j��}�v�ƍ����閼���ł��傤�v�Ɣ������B
�������͋����A�ǂ����Ă��̍���m���Ă���̂��Ɩ₢�Ȃ������B
�@�L�������Č����ɂ́A
�u�O�\�N�ȑO�A�����ŏ����Ă��Ă��鍁�����Ƃ���A�����ł��������߁A�o����q�˂��̂ł��B
����Ɣ��a�ߏK�̎m�����������j��}�Ƃ������Ɛ\���Ă���܂����B
���̍��͔j��}�ɑ��Ⴀ��܂���v
�Ɛ\�����������B
(���ۂ̍��ɏ����ꂽ�ߓc���E�q��u�����L�v�o�T�Ƃ���)
�j�֒��ɒ������@�L�Ƃ������̂������B
�����������ƁA���ɖ��l�Ə̂���Ă����B
���鎞�A���c���������ނ������č������Ȃ������B
�@�L�́u����͔��a�������Ȃ����Ă���u�j��}�v�ƍ����閼���ł��傤�v�Ɣ������B
�������͋����A�ǂ����Ă��̍���m���Ă���̂��Ɩ₢�Ȃ������B
�@�L�������Č����ɂ́A
�u�O�\�N�ȑO�A�����ŏ����Ă��Ă��鍁�����Ƃ���A�����ł��������߁A�o����q�˂��̂ł��B
����Ɣ��a�ߏK�̎m�����������j��}�Ƃ������Ɛ\���Ă���܂����B
���̍��͔j��}�ɑ��Ⴀ��܂���v
�Ɛ\�����������B
252�l�Ԏ����l�N
2022/06/18(�y) 06:38:30.39ID:uxja96LI ���������͒��N�l�̌���
���ꓤ��
���ꓤ��
253�l�Ԏ����l�N
2022/06/18(�y) 10:16:12.01ID:12RdhQTP �A���l�͐̂�����{���ɑ�R���邾��B
�����牽�����ẮH
�����牽�����ẮH
254�l�Ԏ����l�N
2022/06/18(�y) 11:54:50.77ID:piO9y7ec https://livedoor.blogimg.jp/unpinshishi/imgs/c/1/c12d0d83.jpg
���Ȃ݂ɓn���l�̈�`�q�̔Z���͋�B�͈ӊO�Ə��Ȃ��Ďl��������
�l���̒��ł����̎O���ƒf�₵�Ă�悤�ȃC���[�W�̓y�����m�ł�����
���Ȃ݂ɓn���l�̈�`�q�̔Z���͋�B�͈ӊO�Ə��Ȃ��Ďl��������
�l���̒��ł����̎O���ƒf�₵�Ă�悤�ȃC���[�W�̓y�����m�ł�����
255�l�Ԏ����l�N
2022/06/18(�y) 17:18:13.62ID:H3EuXJFu �u����G�ځv����
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-2483.html
�|���ƍ��c�O�~
�̏ڂ����o�[�W����
�ƍN���A�|���l�Ɛ\������Ă������A�����M�c�̒��l����u�����(�N���c�O�~)�v�Ƃ����A�����̕��^�����ł��钹�����コ�ꂽ�B
�ߏK�̎҂����͂��̒��̉����Ċ��S�����B
�������|���N�����������ɂ�
�u�����������Ƃ͎v������ǂ��A�Ԃ��̂Ŏ����A��v�Ƃ̌�ӂł������B
�u�Ȃ����Ԃ��Ȃ���̂ł��H�v�ƋߏK�̏O���\���グ���Ƃ���
�|���u����͂��Ԃ�A���̂ꎩ�g�̉����Ȃ����ł���B
���̎e�ׂł��邪�A�l�ł����܂��܂ȕ����Ɋ�p�Ȏ҂́A�����͂���قǒm�����[���Ȃ��҂��B
���̂悤�Ȃ��̂�叫����҂́A���Ă����ʂ̂��悢�B�v
�Ƃ�����������B
���̂̂��u������v�̎����Ă݂�ƁA���ۂɂ��̂ꎩ�g�̉����Ȃ����������������B
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/�N���c�O�~
> �I�X�͔ɐB���ɂ͑傫�����œƓ��̚�����s���B
>��������͕��G�ŁA���܂��܂Ȓ��̐��������̉̂Ɏ�����邱�Ƃ��悭����B
>���{�̉Ē��ōł����͓I�Ȃ�����������钹�̂ЂƂƂ�����B�n���́u�L���L���L���v�ȂǁB
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-2483.html
�|���ƍ��c�O�~
�̏ڂ����o�[�W����
�ƍN���A�|���l�Ɛ\������Ă������A�����M�c�̒��l����u�����(�N���c�O�~)�v�Ƃ����A�����̕��^�����ł��钹�����コ�ꂽ�B
�ߏK�̎҂����͂��̒��̉����Ċ��S�����B
�������|���N�����������ɂ�
�u�����������Ƃ͎v������ǂ��A�Ԃ��̂Ŏ����A��v�Ƃ̌�ӂł������B
�u�Ȃ����Ԃ��Ȃ���̂ł��H�v�ƋߏK�̏O���\���グ���Ƃ���
�|���u����͂��Ԃ�A���̂ꎩ�g�̉����Ȃ����ł���B
���̎e�ׂł��邪�A�l�ł����܂��܂ȕ����Ɋ�p�Ȏ҂́A�����͂���قǒm�����[���Ȃ��҂��B
���̂悤�Ȃ��̂�叫����҂́A���Ă����ʂ̂��悢�B�v
�Ƃ�����������B
���̂̂��u������v�̎����Ă݂�ƁA���ۂɂ��̂ꎩ�g�̉����Ȃ����������������B
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/�N���c�O�~
> �I�X�͔ɐB���ɂ͑傫�����œƓ��̚�����s���B
>��������͕��G�ŁA���܂��܂Ȓ��̐��������̉̂Ɏ�����邱�Ƃ��悭����B
>���{�̉Ē��ōł����͓I�Ȃ�����������钹�̂ЂƂƂ�����B�n���́u�L���L���L���v�ȂǁB
256�l�Ԏ����l�N
2022/06/18(�y) 20:29:14.49ID:S8CQs5r5 �܂��ƍN����̛�������
257�l�Ԏ����l�N
2022/06/18(�y) 21:52:36.11ID:uw2t0dxR ������Ȃ��ĒE������
258�l�Ԏ����l�N
2022/06/19(��) 03:24:22.14ID:MWgpioh5 �ƍN�u���V����Ȃ��ƌ����Ƃ��v���ăP�[�X����Ȃ�����
259�l�Ԏ����l�N
2022/06/20(��) 17:41:13.03ID:BoVD11zO �u����G�ځv��菬����Ƃ̉Ɛb�E�͓c�����Ƃ��̑c���E�͓c���l
�}�O���[���G�H(������G�H)�̘Y�]�E�͓c�����͂���߂ċ��͂̎҂ł���A�փ�������ł��������������B
�����̑c���E�͓c���l�͍א앺������(�א쏟�v�H)�Ɏd�������A�i��(1504-1521)�̍��A�蕉���̌Ö쒖�����ɏo�Ă��ĘV��j�����삯�E���A�����҂����m��ʂقǏo���B
�����`�e�����א�ɑގ�����Ƃ̖������������߁A��N�̖������͓c���l�͑g�ݕ����Ē��ɓ�������Čq�������B
���̔w�ɂ͑ۂނ����������O�{�����Ă��āA���25�{�������Ă����������B
�������c���ɗ��ʑ�͂ł���A�����엲�i�Ɏd���Ă����B
����Ƃ����ŗ��i�͔������ĂсA�c�����l�ɖ쒖�߂�ɂ���Ɩ������B
�����͂��̓��傫�Ȓ��߂�ɂ����B���̎��\���ł������B
�փ�������̎��͏����R�̘[�ő��߂������č���������킵���B
������Ƃ��₦����͒r�c���Ɏd�������A���̐w�̎��ɂ͓S�̑�|���y�X�Ǝ�����֓˂��āA�V���ɖ�������킵���Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-12218.html
�͓c�����ƓS�̏��ɂ��Ă͂�����ł��G����Ă���
���łɁu����G�ځv�ł͌��͗��̖��q�̖Ε�(�͗����E���ꂽ�����O��)���y��ɕی삳��ď�����ɂȂ����Ə����Ă���
�}�O���[���G�H(������G�H)�̘Y�]�E�͓c�����͂���߂ċ��͂̎҂ł���A�փ�������ł��������������B
�����̑c���E�͓c���l�͍א앺������(�א쏟�v�H)�Ɏd�������A�i��(1504-1521)�̍��A�蕉���̌Ö쒖�����ɏo�Ă��ĘV��j�����삯�E���A�����҂����m��ʂقǏo���B
�����`�e�����א�ɑގ�����Ƃ̖������������߁A��N�̖������͓c���l�͑g�ݕ����Ē��ɓ�������Čq�������B
���̔w�ɂ͑ۂނ����������O�{�����Ă��āA���25�{�������Ă����������B
�������c���ɗ��ʑ�͂ł���A�����엲�i�Ɏd���Ă����B
����Ƃ����ŗ��i�͔������ĂсA�c�����l�ɖ쒖�߂�ɂ���Ɩ������B
�����͂��̓��傫�Ȓ��߂�ɂ����B���̎��\���ł������B
�փ�������̎��͏����R�̘[�ő��߂������č���������킵���B
������Ƃ��₦����͒r�c���Ɏd�������A���̐w�̎��ɂ͓S�̑�|���y�X�Ǝ�����֓˂��āA�V���ɖ�������킵���Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-12218.html
�͓c�����ƓS�̏��ɂ��Ă͂�����ł��G����Ă���
���łɁu����G�ځv�ł͌��͗��̖��q�̖Ε�(�͗����E���ꂽ�����O��)���y��ɕی삳��ď�����ɂȂ����Ə����Ă���
260�l�Ԏ����l�N
2022/06/21(��) 13:22:33.00ID:5AhDOXhB �փ�������̎��A���O���[���i�F�쑽�j�G�Ƌ��̌㐨���A���Z�قǂ��A�������q���v�i�����j�̐�N�A
�����O�g�i���d�j�̔����ʂ������A�n�`���Ⴉ�������ߒO�g�̈ʒu����͌����Ȃ��������A������
���{�������A�ؐ��E�q����g���Ƃ��đ��X�ɂ����m�点�����A�O�g�͎�Ҍ܁A�Z�Z�����킵�A
���̏G�Ƌ��̐���ǂ������������B
���̎��A���c�Ƃ̐b�E�㓡�����q���O�g�̌��ɏ�藈�āu�ނ��x�ꂽ��G�����A���Z�قǁA�Ζʂ�
�����Ēʂ��Ă��邪�A�\���d���Ɍ�B�ǂ������Ď�ҋ��Ɏ�点��ցv�ƌ����Ă����B
��������O�g�����Ă��鏊�ɁA��Ɍ��킵���܁A�Z�Z�̎�҂������A�F�������ċA���Ă����B
��������������q�́u�ʂ���ʒO�g���ȁv�Ɗ����������B
�Ƃ��낪���̌�A���̎�荹���ɁA���̎��̐킢�͌㓡�����q���w�}���āA�g���ɍ������������̂ł���A
�S�������q�̂������ł���A�ƌ���ꂽ�B�O�g�͂�����āA�u�^�����Ȃ��㓡�̉ߌ��ł���B�v��
����Ɏv���A�������Ζʂ��Đ^�U�𐳂����Ǝv���Ă������A���̂悤�Ȓ��A�����q�͘Q�l���āA�����
�オ��Ƃ��āA�{���Œ��҂������Ă����B
���̎����A���|�̗̎�Ɛ����������������������A�O�g���g���Ƃ��āA�u�����q���Ƃŕ��������B�v��
�\�������A�����q�́u�O���Ȃ�Ό����\���ׂ��B�v�ƌ������B
�O�g�͖߂肱�̎|�𐳑��ɐ\���グ��ƁA�����͓���U����
�u����̂��̕��⏬�֊���ł���ł���A�O���Ȃǎv�������Ȃ��I�v
�ƌ������B�����������O�g�͊Ђ߂ĞH��
�u�����q���O���ɂď����o����A�Ό����َ҂��Ќ����t���܂��B���̂Ȃ�A�����q�ł����O����
�ɂȂ�̂Ȃ�A�Ό��A�O�g�Ȃǂ́A�O�֏o������l���̎��ł���A����̂ɏ��g�̂܂܂Ȃ̂��A��
������ł��傤�B�Ȃ�A�َ҂܂ł̖ʖڂȂ̂ł��B�v
���̂悤�ɊЂ߂����A�����͏��������A�ĂђO�g���g���Ƃ��āA�����q�ɒf���\�����킵���B
�����ĉɌ�ċA�鎞�A��B�Ă̐���̎�荹�����v���o�����B
�u��N�A�փ����ɂĔ��O���̑ނ��x�ꂽ�ҒB���䂪�肪����������B�Ƃ��낪������A�M�a�̎w�}�ɂ�
���Ɏ蕿�������̂��Ɛ���Ő\����Ă���Ƃ����B���������A����͂���B�v
���������Ė����q�ɋl�ߊ�������A�����q�͂���ɗ����
�u�M�a�Ǝ��̕��ӂ͌݊p�ł���B���ɂ����ċM�a�̎w�}�����͐����Ȃ��B
�R��A���̎w�}���M�a�������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�v
���̂悤�ɕԓ������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�����O�g�i���d�j�̔����ʂ������A�n�`���Ⴉ�������ߒO�g�̈ʒu����͌����Ȃ��������A������
���{�������A�ؐ��E�q����g���Ƃ��đ��X�ɂ����m�点�����A�O�g�͎�Ҍ܁A�Z�Z�����킵�A
���̏G�Ƌ��̐���ǂ������������B
���̎��A���c�Ƃ̐b�E�㓡�����q���O�g�̌��ɏ�藈�āu�ނ��x�ꂽ��G�����A���Z�قǁA�Ζʂ�
�����Ēʂ��Ă��邪�A�\���d���Ɍ�B�ǂ������Ď�ҋ��Ɏ�点��ցv�ƌ����Ă����B
��������O�g�����Ă��鏊�ɁA��Ɍ��킵���܁A�Z�Z�̎�҂������A�F�������ċA���Ă����B
��������������q�́u�ʂ���ʒO�g���ȁv�Ɗ����������B
�Ƃ��낪���̌�A���̎�荹���ɁA���̎��̐킢�͌㓡�����q���w�}���āA�g���ɍ������������̂ł���A
�S�������q�̂������ł���A�ƌ���ꂽ�B�O�g�͂�����āA�u�^�����Ȃ��㓡�̉ߌ��ł���B�v��
����Ɏv���A�������Ζʂ��Đ^�U�𐳂����Ǝv���Ă������A���̂悤�Ȓ��A�����q�͘Q�l���āA�����
�オ��Ƃ��āA�{���Œ��҂������Ă����B
���̎����A���|�̗̎�Ɛ����������������������A�O�g���g���Ƃ��āA�u�����q���Ƃŕ��������B�v��
�\�������A�����q�́u�O���Ȃ�Ό����\���ׂ��B�v�ƌ������B
�O�g�͖߂肱�̎|�𐳑��ɐ\���グ��ƁA�����͓���U����
�u����̂��̕��⏬�֊���ł���ł���A�O���Ȃǎv�������Ȃ��I�v
�ƌ������B�����������O�g�͊Ђ߂ĞH��
�u�����q���O���ɂď����o����A�Ό����َ҂��Ќ����t���܂��B���̂Ȃ�A�����q�ł����O����
�ɂȂ�̂Ȃ�A�Ό��A�O�g�Ȃǂ́A�O�֏o������l���̎��ł���A����̂ɏ��g�̂܂܂Ȃ̂��A��
������ł��傤�B�Ȃ�A�َ҂܂ł̖ʖڂȂ̂ł��B�v
���̂悤�ɊЂ߂����A�����͏��������A�ĂђO�g���g���Ƃ��āA�����q�ɒf���\�����킵���B
�����ĉɌ�ċA�鎞�A��B�Ă̐���̎�荹�����v���o�����B
�u��N�A�փ����ɂĔ��O���̑ނ��x�ꂽ�ҒB���䂪�肪����������B�Ƃ��낪������A�M�a�̎w�}�ɂ�
���Ɏ蕿�������̂��Ɛ���Ő\����Ă���Ƃ����B���������A����͂���B�v
���������Ė����q�ɋl�ߊ�������A�����q�͂���ɗ����
�u�M�a�Ǝ��̕��ӂ͌݊p�ł���B���ɂ����ċM�a�̎w�}�����͐����Ȃ��B
�R��A���̎w�}���M�a�������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�v
���̂悤�ɕԓ������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
261�l�Ԏ����l�N
2022/06/23(��) 20:03:00.28ID:ILFaMVm8262�l�Ԏ����l�N
2022/06/23(��) 20:50:53.27ID:ndG1O178 >>261
����
����
263�l�Ԏ����l�N
2022/06/25(�y) 22:49:22.14ID:POeF0AOd �u���L�L�v���u�ٍ��D���݁@���E�S�{�̎��v
���\�O�N(1530�N)�̉āA��؍������D���z���L��{���ɒ��݂����B
�����ړI�ł���A���z�E��킻�̂ق��d��̒������������ʂقǂ������B
���̂��Ƃ������ɒm��n�������߁A���X�̏��l������������������āA�������Ɣ����������B
������������ʂ��Ȃ��������A��ؐl�̕��͂��炩���ߗ\�����Ă����̂��喾�̎�҂��ق��Ă����B
�����炪�ێ���Ƃ����T�Ƃ̊w���������ď������킵���Ƃ���A�O���Ƃ�����҂��ǂ�ŁA�M�k�ňӎv�a�ʂ������B
��҂������ɂ́u��͑喾���̎҂ł��邪�A�ʖ�̂��߂Ɍق��ė����B
�D������ȉ��̎҂ǂ��݂͂ȓ�ؐl�ł���B
�����̂��Ƃɂ��Ă͂悭�m��Ȃ��̂����A�D��������ɁA�㉺�̗�V���Ȃ��A
���[�̐H�����吨����̑傫�Ȋ킩���Â��݂ŐH���Ă��āA���t�ɂł��ʂ��肳�܂��B�v�Ɛ\�����B
���̓�ؐl�ǂ��͉��`�Ɏ�X�̏d������サ�����A���̒��ɕ����������B
�����͎O�ڗ]�œS�{�ƌ������������B
���ꂪ�L��ɂ�����S�{�̎n�܂�ł���B
��ؐl�ǂ��͏��������܂����������ߏ��������ŋA�������B
���̂̂��V����\�N(1551�N)�ɒ��D�������ɂ́A��̏��傩��ΉΖ�Ƃ����傫�ȓS�{�����コ�ꂽ�B
�̂��ɉP�n�O�����ő�F�Ɠ��Â����킵�����A���̑哛�ŎF�B���������E���A�����h�����Ƃ������Ƃ��B
(�u��F���p�L�v�ł͓�����C�E�����������������͓̂V���l�N(1576�N)�Ƃ��Ă���)
��q���ȑO�Ƃ͂����S�{��ʎY�����킯�ł͂Ȃ��悤��
���\�O�N(1530�N)�̉āA��؍������D���z���L��{���ɒ��݂����B
�����ړI�ł���A���z�E��킻�̂ق��d��̒������������ʂقǂ������B
���̂��Ƃ������ɒm��n�������߁A���X�̏��l������������������āA�������Ɣ����������B
������������ʂ��Ȃ��������A��ؐl�̕��͂��炩���ߗ\�����Ă����̂��喾�̎�҂��ق��Ă����B
�����炪�ێ���Ƃ����T�Ƃ̊w���������ď������킵���Ƃ���A�O���Ƃ�����҂��ǂ�ŁA�M�k�ňӎv�a�ʂ������B
��҂������ɂ́u��͑喾���̎҂ł��邪�A�ʖ�̂��߂Ɍق��ė����B
�D������ȉ��̎҂ǂ��݂͂ȓ�ؐl�ł���B
�����̂��Ƃɂ��Ă͂悭�m��Ȃ��̂����A�D��������ɁA�㉺�̗�V���Ȃ��A
���[�̐H�����吨����̑傫�Ȋ킩���Â��݂ŐH���Ă��āA���t�ɂł��ʂ��肳�܂��B�v�Ɛ\�����B
���̓�ؐl�ǂ��͉��`�Ɏ�X�̏d������サ�����A���̒��ɕ����������B
�����͎O�ڗ]�œS�{�ƌ������������B
���ꂪ�L��ɂ�����S�{�̎n�܂�ł���B
��ؐl�ǂ��͏��������܂����������ߏ��������ŋA�������B
���̂̂��V����\�N(1551�N)�ɒ��D�������ɂ́A��̏��傩��ΉΖ�Ƃ����傫�ȓS�{�����コ�ꂽ�B
�̂��ɉP�n�O�����ő�F�Ɠ��Â����킵�����A���̑哛�ŎF�B���������E���A�����h�����Ƃ������Ƃ��B
(�u��F���p�L�v�ł͓�����C�E�����������������͓̂V���l�N(1576�N)�Ƃ��Ă���)
��q���ȑO�Ƃ͂����S�{��ʎY�����킯�ł͂Ȃ��悤��
264�l�Ԏ����l�N
2022/06/26(��) 22:05:18.83ID:mmbd0jN2 �^�c���q�卲�M���i�M�Ɂj�i�{���ɁA���ɍK���Ɖ]���͌��Ȃ�Ɖ]�X�j�́A�ƍN���Ɍ�G�ΐ\���n�߂��A
��q�����̑召����ɐg��������т��Ă����Ƃ����B�����̓���́A����Ƃ��M��Ƃ�������^�c�������āA
�����̐S�Ƃ����̂ł��낤�B�m����҂́A������肱�̂悤�Ȓ��`���܂݁A�S��s�����ׂ��B
�܂��Γc��������i�O���j�͈������炴��҂ł���B�@���Ȃ�l�ł����Ă��A�e�X���̎�l�̂��߂�
�����y�A�`�𗧂ĂĎ����s���҂́A�G�ł����Ă����ނׂ��ł͂Ȃ��B����͌N�b���ɐS����ׂ�
���ł���B
����͐��ˉ���������͐��ꂽ�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
��q�����̑召����ɐg��������т��Ă����Ƃ����B�����̓���́A����Ƃ��M��Ƃ�������^�c�������āA
�����̐S�Ƃ����̂ł��낤�B�m����҂́A������肱�̂悤�Ȓ��`���܂݁A�S��s�����ׂ��B
�܂��Γc��������i�O���j�͈������炴��҂ł���B�@���Ȃ�l�ł����Ă��A�e�X���̎�l�̂��߂�
�����y�A�`�𗧂ĂĎ����s���҂́A�G�ł����Ă����ނׂ��ł͂Ȃ��B����͌N�b���ɐS����ׂ�
���ł���B
����͐��ˉ���������͐��ꂽ�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
265�l�Ԏ����l�N
2022/06/28(��) 22:46:36.60ID:jbOcgdLv ���~�̐w�̎��A�I�{�ꈢ�g��i�����j�̐w�ɔ��c�E�q�傪�铢���������A�I�{��̉Ɛb�E��吅�Ƃ����ҁA
���̎��\�܍ł��������A�G����l�A���̗����ɍ݂����̂��A����˂����Ă����A���̎҂�
�u����������������I�H�v�ƌ����Ă����B������������̎ҒB���u���m��������ȁI�v��
���������Ă����̂ŁA��͂��̂܂ܖ����������B
����Ƃ��̎҂͑�����ɋ삯����A�n���T���āA
�u�����̎m�́A���ƌ������҂��I�H��͍���̑叫�A���c�E�q��Ȃ�I�I�v
�Ɩ����̂Ăē��ɓ������Ƃ����B��吅�͂��̎����B�V��܂Ō���Ă����Ƃ��B
�i�V���Ӂj
���̎��\�܍ł��������A�G����l�A���̗����ɍ݂����̂��A����˂����Ă����A���̎҂�
�u����������������I�H�v�ƌ����Ă����B������������̎ҒB���u���m��������ȁI�v��
���������Ă����̂ŁA��͂��̂܂ܖ����������B
����Ƃ��̎҂͑�����ɋ삯����A�n���T���āA
�u�����̎m�́A���ƌ������҂��I�H��͍���̑叫�A���c�E�q��Ȃ�I�I�v
�Ɩ����̂Ăē��ɓ������Ƃ����B��吅�͂��̎����B�V��܂Ō���Ă����Ƃ��B
�i�V���Ӂj
266�l�Ԏ����l�N
2022/06/30(��) 17:26:18.65ID:1TQVRMpv �u����G�ځv����]�C���V���q��̎�
�]�C���V���q��͓쏯�ڌ������̏�t�ł���A�H�ŗ_���������B
�����ɓ������������ƁA�����Ə�ɂ悭���������߈ٖ����u�����v�ƌ������B
�̂��ɑ��}�ɏ����o����A�H���������B
�������܂����߁A�H�̖��l�݂̂Ȃ炸�A�u����肪��v�ƂЂĐ����Ɍ����`����ꂽ�B
�]�C���̗ՏI�ɏG�g���͏�g�����킳��u�������̂��݂͂Ȃ����H�v�Ə�ӂ��������B
�]�C���u�]�݂͂���܂���B
�������y�̌���䕶�����킹����Ȃ�A�Еւł͂���܂����͂��\���܂��傤�v�Ɛ\�����B
�ՏI�܂ł���͂�߂Ȃ������Ƃ������Ƃ��B
�]�C���V���q��̖v�N��1597�N���Ƃ���ƁA�G����吭�������ł͂Ȃ��G��������ɓ����Ă��܂��悤��
�]�C���V���q��͓쏯�ڌ������̏�t�ł���A�H�ŗ_���������B
�����ɓ������������ƁA�����Ə�ɂ悭���������߈ٖ����u�����v�ƌ������B
�̂��ɑ��}�ɏ����o����A�H���������B
�������܂����߁A�H�̖��l�݂̂Ȃ炸�A�u����肪��v�ƂЂĐ����Ɍ����`����ꂽ�B
�]�C���̗ՏI�ɏG�g���͏�g�����킳��u�������̂��݂͂Ȃ����H�v�Ə�ӂ��������B
�]�C���u�]�݂͂���܂���B
�������y�̌���䕶�����킹����Ȃ�A�Еւł͂���܂����͂��\���܂��傤�v�Ɛ\�����B
�ՏI�܂ł���͂�߂Ȃ������Ƃ������Ƃ��B
�]�C���V���q��̖v�N��1597�N���Ƃ���ƁA�G����吭�������ł͂Ȃ��G��������ɓ����Ă��܂��悤��
267�l�Ԏ����l�N
2022/06/30(��) 22:54:30.69ID:k/g97SJB >>266
���O������ɓ���Ă邾����
���O������ɓ���Ă邾����
268�l�Ԏ����l�N
2022/07/02(�y) 11:34:21.30ID:zuvPQuU8 �D�c�M����������Ɏ��ɂ����ėR���[���R�����ڂ����q�˂�ƁA���X�M�����͌䐶���̊Ԃ���
�����J�R�E���ʏ�l�ƔN����ʍ��ł���A��ڂ��������Ă������A���ɉB��Ȃ����ł��������A
���̂悤�ȏ��ɖ��q��������G�̖d�����N�����A�V���\�N�Z������̑����A�M�����̌䗷�قł���
�{�\���ɉ�������ɋy�B
���̎��������ʏ�l�͕������A�傢�ɋ�����A��O�̖V��A���тɑm�k��\�l����������A��
��芸�����{�\���삯�������A�\��E���ǂ͌R���̂��߂ɂȂ��Ȃ��ߊ�邱�Əo�������ɂȂ���
�������B���ʏ�l�͗����A�x�a�̈ē���\���������Ă����̂ŁA�����ɂ܂��{�\���̗�����
�_��j���Ď����ւ悤�₭�삯�������A�ő��{�\���ɉ��|����A�M��������ؕ����ꂽ�ƕ�����
�͂𗎂Ƃ��A�ӂƖT�������ƁA��̌��A�M�̒��ŏ\�l�]�肪�������A�����t�̂悤�Ȃ��̂Ȃǂ�
�܂肭�ׂĉ��Ă����B���ʏ�l�͕s�v�c�Ɏv�����̏ꏊ�ɗ������ƁA�����ɂ����̂͊F
���m�������m�����ł������B
�u���͂����ɁA���āA�M�����͔@�����ꂽ�̂ł��傤���v
�ƁA�₤�ƁA
�u���͂��ؕ��V����A��⌾�ɂāA�w���[��G�Ɏ����ȁA���G���ɓn���ȁx�Ƌ��u����܂����B
�������A���[������ė����ނ��ɂ��l���G�̒��ł���A�����������Ēv���ׂ��v�Ă��Ȃ��̂ɁA�䎀�[��
��������ɂČ�Α��ɒv���A�D�Ɛ����ēG����B���A��X�͂��̌�ؕ��d��A�䋟�\����͂�ƍl���A
�����䑒����d���Ă���̂ł��B�v
�����A�e�X�ꓯ�ɓ�����ꂽ�B
���ʏ�l�͂�������āA�u�K���̎��ł��B���͓��X�ɁA�e�X�����䑶�m�̒ʂ�A�����䍧�ӂ̏�ӂɗa����A
�L����������Ă��܂����B�ł��̂ŁA������p���L�邩�Ǝv���A���X�ɂ�����ɋ삯���܂������A
���͂�䐶�Q�ɂĐ���ɋy�т܂���B�������Α��͏o�Ƃ̖��ł�����A��������m�ɂ��n�����������B
�m�k�����������A��Ă��܂��̂ŁA��Α��ɒv���䍜���䂪���Ɏ����A���đ������āA����z��
�䑗��A��@��������m�̗͂̌���߂܂��B�ł��̂ł��̎��͂��C�����Ȃ��A���������ɔC���āA
�G���\�Ɍ����܂�����A�e�X�͌䓭�������đ��₩�ɓ������ɂ��A�䋟�Ȃ���܂��悤�ɁB�v
�Ɛ\���ƁA�F�X�x�ѐ\���ꂽ�u���˂Č䍧��̎��Ȃ�A�v���������ɂɑ�����B
���l�ł�����ɏ]���A�M�m���ւ����𗊂ݒu���A��X�͔��o�āA�P���藈��G��h���A
�S�Â��ɐؕ��d��̂ŁA�ǂ������ݓ���B�v
�ƁA�ꗼ�l���c���ĊF�X�����ނ��\�ւƏo���B�̂ɐ��ʏ�l�͌�Α������A�b���ɉ��Ɛ������A
�䍜�����W�߈߂ɕ�݁A�{�\���̑m�O�������ނ�����Ĉ���Ɏ��A���A�䍜��悸�͐[��
�B���u���A�b���������߂��āA�����̑m�k����ɂĖ����Ɍ䑒�V������s���A�������Č���
�z�������A�䍜���[�߂��B
�M�����̍��{�̌�揊�͈���Ɏ��ɂ����āA���݂Ɏ���܂Ō䖽���̖@�����A��Ӗ��������ߕ���Ă���B
�@�M���L�ɁA�w�������߂���ǂ��X�Ɍ������肯��A���G�[�������ݎm���ɖ����Ď�̊O
�@�q�˂����炪���Ƃ������Ƃ��A�[���Ǝv�����������������x�ƗL��̂́A���̂��߂ł���B
�w�M�������\�Ɏ��R緖�V�L�^�x
�����J�R�E���ʏ�l�ƔN����ʍ��ł���A��ڂ��������Ă������A���ɉB��Ȃ����ł��������A
���̂悤�ȏ��ɖ��q��������G�̖d�����N�����A�V���\�N�Z������̑����A�M�����̌䗷�قł���
�{�\���ɉ�������ɋy�B
���̎��������ʏ�l�͕������A�傢�ɋ�����A��O�̖V��A���тɑm�k��\�l����������A��
��芸�����{�\���삯�������A�\��E���ǂ͌R���̂��߂ɂȂ��Ȃ��ߊ�邱�Əo�������ɂȂ���
�������B���ʏ�l�͗����A�x�a�̈ē���\���������Ă����̂ŁA�����ɂ܂��{�\���̗�����
�_��j���Ď����ւ悤�₭�삯�������A�ő��{�\���ɉ��|����A�M��������ؕ����ꂽ�ƕ�����
�͂𗎂Ƃ��A�ӂƖT�������ƁA��̌��A�M�̒��ŏ\�l�]�肪�������A�����t�̂悤�Ȃ��̂Ȃǂ�
�܂肭�ׂĉ��Ă����B���ʏ�l�͕s�v�c�Ɏv�����̏ꏊ�ɗ������ƁA�����ɂ����̂͊F
���m�������m�����ł������B
�u���͂����ɁA���āA�M�����͔@�����ꂽ�̂ł��傤���v
�ƁA�₤�ƁA
�u���͂��ؕ��V����A��⌾�ɂāA�w���[��G�Ɏ����ȁA���G���ɓn���ȁx�Ƌ��u����܂����B
�������A���[������ė����ނ��ɂ��l���G�̒��ł���A�����������Ēv���ׂ��v�Ă��Ȃ��̂ɁA�䎀�[��
��������ɂČ�Α��ɒv���A�D�Ɛ����ēG����B���A��X�͂��̌�ؕ��d��A�䋟�\����͂�ƍl���A
�����䑒����d���Ă���̂ł��B�v
�����A�e�X�ꓯ�ɓ�����ꂽ�B
���ʏ�l�͂�������āA�u�K���̎��ł��B���͓��X�ɁA�e�X�����䑶�m�̒ʂ�A�����䍧�ӂ̏�ӂɗa����A
�L����������Ă��܂����B�ł��̂ŁA������p���L�邩�Ǝv���A���X�ɂ�����ɋ삯���܂������A
���͂�䐶�Q�ɂĐ���ɋy�т܂���B�������Α��͏o�Ƃ̖��ł�����A��������m�ɂ��n�����������B
�m�k�����������A��Ă��܂��̂ŁA��Α��ɒv���䍜���䂪���Ɏ����A���đ������āA����z��
�䑗��A��@��������m�̗͂̌���߂܂��B�ł��̂ł��̎��͂��C�����Ȃ��A���������ɔC���āA
�G���\�Ɍ����܂�����A�e�X�͌䓭�������đ��₩�ɓ������ɂ��A�䋟�Ȃ���܂��悤�ɁB�v
�Ɛ\���ƁA�F�X�x�ѐ\���ꂽ�u���˂Č䍧��̎��Ȃ�A�v���������ɂɑ�����B
���l�ł�����ɏ]���A�M�m���ւ����𗊂ݒu���A��X�͔��o�āA�P���藈��G��h���A
�S�Â��ɐؕ��d��̂ŁA�ǂ������ݓ���B�v
�ƁA�ꗼ�l���c���ĊF�X�����ނ��\�ւƏo���B�̂ɐ��ʏ�l�͌�Α������A�b���ɉ��Ɛ������A
�䍜�����W�߈߂ɕ�݁A�{�\���̑m�O�������ނ�����Ĉ���Ɏ��A���A�䍜��悸�͐[��
�B���u���A�b���������߂��āA�����̑m�k����ɂĖ����Ɍ䑒�V������s���A�������Č���
�z�������A�䍜���[�߂��B
�M�����̍��{�̌�揊�͈���Ɏ��ɂ����āA���݂Ɏ���܂Ō䖽���̖@�����A��Ӗ��������ߕ���Ă���B
�@�M���L�ɁA�w�������߂���ǂ��X�Ɍ������肯��A���G�[�������ݎm���ɖ����Ď�̊O
�@�q�˂����炪���Ƃ������Ƃ��A�[���Ǝv�����������������x�ƗL��̂́A���̂��߂ł���B
�w�M�������\�Ɏ��R緖�V�L�^�x
269�l�Ԏ����l�N
2022/07/02(�y) 11:51:11.89ID:SZ/7KzMX http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-8079.html
�M���ؕ�����̖{�\��
�M���ؕ�����̖{�\��
270�l�Ԏ����l�N
2022/07/02(�y) 19:17:50.79ID:sNNpHE3Q �u��F���p�L�v����u���}���@���A��_����A�P�n��ʼn�A�n���̎��v
���}�����@�̎��j�A�@���͘Q�l�Ƃ��ĖL��ŔN���𑗂��Ă������A����܂���������ɘQ�l�̓��X���߂����Ă�����_����A�P�n��ʼn�ƂƂ���
�u���ׂɉ߂������͓��ɓn�茩�������悤�v�Ƃ������ƂŎO�l�Ƃ���O���肩��C���z���Ė��̑剤�̓s�ɓn�����B
���Ƃ��Ƒ�F�@�ٌ��͖��̑剤�ƒʌ����Č����g�▾�̒��g�̉��������������߁A�O�l���@�ٌ��̌䔻�̏�����Q�����
���̓V�q���u���ɋ����v�Ƃ��d�����Ă��ꂽ���߁A����͒ʂ��Ȃ��܂ł������ɂ�萔�����炵�Ă����B
����Ƃ��֒����牓���Ȃ��Ƃ���Ŗd�����N�������߁A���n�����d�������R�����ɐ\���t����ꂽ�B
�@�������O�l�́u�����O�l�ɐ�N���������������B���R�͌�w�ŗV�����v�Ɛ\�����Ƃ���A�V�q����̂�邵���ł��A
�O�l�͂�낱�ѐ��ƂȂ�A�킸����\�O�l���Ă��ւƌ��������B
�@���͏��}���̖��q�ł͂��邪�R�@���ɂ߂Ă���A���̔�p������Ă����B�ق��̓�l���ꗬ�̑��̎g����ł������B
�邩��o�Ă����G�����O�l�ŘZ�\���l�������A�叫�������ӂ�����Ƃ����B
�������҂ǂ��͌�R�̊��R���ގ������B
���̓V�q�̉b���͐Ȃ��A�]�݂̖J����^���悤�Ƌ�ꂽ�B
�O�l�������ɂ́u��N�A�M���������y�ɂ��킵���Ƃ��A���V�ƌ������̂�
�w�M�����ւ̈���̐i�������������B�����̉^���������Ǝv���܂��x
�Ɛ\�����Ƃ���A���̓��̐i���͓��K��ѕ������������̂ŁA�M�����͓��V�����Ƃ������Ƃł��B
���ł�����̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤����A����̌䒲���������ꂽ���v���܂��v
�Ƒt�������B
���������̓��̌䒲���͏�X�������Ȃ������B
������������҂��������߂ɂ��̂悤�ȉʕ����̂��낤�B
����Ȃ���ȂŖ��̓s�Ɉ�N�؍݂����̂��A�Δn�E���̊Ԃŗ��Ɉ����Ȃ�������ɂ����B
�@���u����g�� �D�����ւ邩�̂ݓf�� ��Ȃ��� ��(����)�̓������v
�������ĎO�l�Ƃ��喾���ɕ��E���c���A�ٍ����������ċA�������B
���}���@���̌Z�̏��}������ɂ��Ă̘b�͈ȉ��Q��
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13514.html
�M�����@�S���тƂ������n��L���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13522.html
���}�������n���̎�
���}�����@�̎��j�A�@���͘Q�l�Ƃ��ĖL��ŔN���𑗂��Ă������A����܂���������ɘQ�l�̓��X���߂����Ă�����_����A�P�n��ʼn�ƂƂ���
�u���ׂɉ߂������͓��ɓn�茩�������悤�v�Ƃ������ƂŎO�l�Ƃ���O���肩��C���z���Ė��̑剤�̓s�ɓn�����B
���Ƃ��Ƒ�F�@�ٌ��͖��̑剤�ƒʌ����Č����g�▾�̒��g�̉��������������߁A�O�l���@�ٌ��̌䔻�̏�����Q�����
���̓V�q���u���ɋ����v�Ƃ��d�����Ă��ꂽ���߁A����͒ʂ��Ȃ��܂ł������ɂ�萔�����炵�Ă����B
����Ƃ��֒����牓���Ȃ��Ƃ���Ŗd�����N�������߁A���n�����d�������R�����ɐ\���t����ꂽ�B
�@�������O�l�́u�����O�l�ɐ�N���������������B���R�͌�w�ŗV�����v�Ɛ\�����Ƃ���A�V�q����̂�邵���ł��A
�O�l�͂�낱�ѐ��ƂȂ�A�킸����\�O�l���Ă��ւƌ��������B
�@���͏��}���̖��q�ł͂��邪�R�@���ɂ߂Ă���A���̔�p������Ă����B�ق��̓�l���ꗬ�̑��̎g����ł������B
�邩��o�Ă����G�����O�l�ŘZ�\���l�������A�叫�������ӂ�����Ƃ����B
�������҂ǂ��͌�R�̊��R���ގ������B
���̓V�q�̉b���͐Ȃ��A�]�݂̖J����^���悤�Ƌ�ꂽ�B
�O�l�������ɂ́u��N�A�M���������y�ɂ��킵���Ƃ��A���V�ƌ������̂�
�w�M�����ւ̈���̐i�������������B�����̉^���������Ǝv���܂��x
�Ɛ\�����Ƃ���A���̓��̐i���͓��K��ѕ������������̂ŁA�M�����͓��V�����Ƃ������Ƃł��B
���ł�����̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤����A����̌䒲���������ꂽ���v���܂��v
�Ƒt�������B
���������̓��̌䒲���͏�X�������Ȃ������B
������������҂��������߂ɂ��̂悤�ȉʕ����̂��낤�B
����Ȃ���ȂŖ��̓s�Ɉ�N�؍݂����̂��A�Δn�E���̊Ԃŗ��Ɉ����Ȃ�������ɂ����B
�@���u����g�� �D�����ւ邩�̂ݓf�� ��Ȃ��� ��(����)�̓������v
�������ĎO�l�Ƃ��喾���ɕ��E���c���A�ٍ����������ċA�������B
���}���@���̌Z�̏��}������ɂ��Ă̘b�͈ȉ��Q��
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13514.html
�M�����@�S���тƂ������n��L���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13522.html
���}�������n���̎�
271�l�Ԏ����l�N
2022/07/02(�y) 19:25:24.05ID:zuvPQuU8 �m�F�s���Ŏ��炵�܂����B������͖����o�Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂�
�D�c�M�����̌䒷�j�ł���O�ʒ����M�����́A�{�\���̕ς̐܁A���o���ɋ���ꂽ���A�{�\���ɌR�����
���������āA����̐V��a�Ɍ�ڂ�V����A����ɂČ䐶�Q���ꂽ�B
����ɂ��Ă���⌾�ɂāA�w��[��G�ɓn���ȁA�Β��ɑł����ݏĂ��̂Ă�I�x�Ƌ��u����Ă������߁A
��Ɨ����͂��̎��[���Β��ɑł����݁A�����\�����̂ɒm���Ȃ��Ă��������A���������ʏ�l��
�����삯�����A�c�苏����Ɨ����ɐM�����̎��[��ł����߂��̏ꏊ���Ƃ��ƕ��������A�Β���
�Ă��̂Ă�ꂽ�⍜�Ȃǂ�s���E���W�߁A����Ɏ��֎����A��A�M�������ɑ����ׂČ���z���A
���Ɏ��肱����܂��A�䖽���䐅���𑊋ߐ\���Ă���B
�w�M�������\�Ɏ��R緖�V�L�^�x
�D�c�M�����̌䒷�j�ł���O�ʒ����M�����́A�{�\���̕ς̐܁A���o���ɋ���ꂽ���A�{�\���ɌR�����
���������āA����̐V��a�Ɍ�ڂ�V����A����ɂČ䐶�Q���ꂽ�B
����ɂ��Ă���⌾�ɂāA�w��[��G�ɓn���ȁA�Β��ɑł����ݏĂ��̂Ă�I�x�Ƌ��u����Ă������߁A
��Ɨ����͂��̎��[���Β��ɑł����݁A�����\�����̂ɒm���Ȃ��Ă��������A���������ʏ�l��
�����삯�����A�c�苏����Ɨ����ɐM�����̎��[��ł����߂��̏ꏊ���Ƃ��ƕ��������A�Β���
�Ă��̂Ă�ꂽ�⍜�Ȃǂ�s���E���W�߁A����Ɏ��֎����A��A�M�������ɑ����ׂČ���z���A
���Ɏ��肱����܂��A�䖽���䐅���𑊋ߐ\���Ă���B
�w�M�������\�Ɏ��R緖�V�L�^�x
272�l�Ԏ����l�N
2022/07/03(��) 10:29:49.56ID:2nwEiHig >>271
�����̌��̈Ӗ����悭�킩���̂����A�N���e�Ȑl������Ă��炦�܂��H
�����̌��̈Ӗ����悭�킩���̂����A�N���e�Ȑl������Ă��炦�܂��H
273�l�Ԏ����l�N
2022/07/03(��) 10:38:32.31ID:htPLDiVZ274�l�Ԏ����l�N
2022/07/03(��) 10:56:12.62ID:ZJgGd5kV �d�E���E�f�̒�
275�l�Ԏ����l�N
2022/07/03(��) 11:53:21.91ID:48uUtX46 ���肪��
276�l�Ԏ����l�N
2022/07/04(��) 04:39:46.11ID:aHB+oo0E ���m�֖��̃A�z������ƕ�����
277�l�Ԏ����l�N
2022/07/04(��) 05:51:06.91ID:Rm4JHItI ���ꏊ��T���ɗ�����
278�l�Ԏ����l�N
2022/07/04(��) 09:06:39.12ID:91Ll7VDC >>276
���ԒT���̗�����
���ԒT���̗�����
279�l�Ԏ����l�N
2022/07/04(��) 17:57:40.30ID:pd53eAzv �}�����ꂽ�̂��ނꂽ��w
280�l�Ԏ����l�N
2022/07/04(��) 20:00:07.99ID:BcLs7wOf �u��F���p�L�v����ɓ��������z�̎�
�ɓ��O�ʓ���(�ɓ��`�S)�͓��Âɔj��L��ɖS�����A�c���ДE�̐��b�ƂȂ��Ă����B
����r�ꎛ���C�ɓ��������߁A�����ŋC�Ԃŕ����Ȑ������y����ł����Ƃ���A���҂���
�u�݂̂���݁A�˂��݂ƂȂ�ĎO�ʓa�A���͂�̉����͂Ђ܂͂肯��v�ƍ��D�ɏ����Ė�O�ɗ��Ēu�����B
�c���ДE�͉̓��ɖ��邩��������
�O�ʓ����́u���Ă͂���͓c���̍�ł͂Ȃ����H�v�Ɖ������v���A�����n��������A�ŏI�I�ɋ��ɂ����Ċҍs���ꂽ�B
���q�̍�����v(�ɓ��`�v)�����łɖS���Ȃ��Ă������߁A�ɓ��ƖŖS�Ǝv��ꂽ�B
������������v�̒�E������v����(�ɓ��S��)�͐��l�̍s���ɕ킢�A���E������A���|�̕����̐l�ł������B
�Ƃ��₦�邱�Ƃ������݁A�_�������̂�ł����b�オ����A�G�g���̉����ŔN���𑗂��Ă����B
�����̖��z��
�u���ɑ����āA���߂Ƃ�т̂��ƂӂƂ��v
�Ƃ������Ƃ���Ŗڂ����߂��B
�u��(�K�삨��)�v�Ƃ͗ݑ�̖{�m�ł���A�u���ɑ����Ă��ƂӂƂ��v�Ƃ͍Ăєɉh����Ƃ����g�����Ɗ�сA�A�̋��s�������B
�قǂȂ����}�G�g���ɏ����o����A�{�̂̓��Œm�s���g�ƂȂ������Ƃ����s�v�c�ł���B
�ɓ��O�ʓ���(�ɓ��`�S)�͓��Âɔj��L��ɖS�����A�c���ДE�̐��b�ƂȂ��Ă����B
����r�ꎛ���C�ɓ��������߁A�����ŋC�Ԃŕ����Ȑ������y����ł����Ƃ���A���҂���
�u�݂̂���݁A�˂��݂ƂȂ�ĎO�ʓa�A���͂�̉����͂Ђ܂͂肯��v�ƍ��D�ɏ����Ė�O�ɗ��Ēu�����B
�c���ДE�͉̓��ɖ��邩��������
�O�ʓ����́u���Ă͂���͓c���̍�ł͂Ȃ����H�v�Ɖ������v���A�����n��������A�ŏI�I�ɋ��ɂ����Ċҍs���ꂽ�B
���q�̍�����v(�ɓ��`�v)�����łɖS���Ȃ��Ă������߁A�ɓ��ƖŖS�Ǝv��ꂽ�B
������������v�̒�E������v����(�ɓ��S��)�͐��l�̍s���ɕ킢�A���E������A���|�̕����̐l�ł������B
�Ƃ��₦�邱�Ƃ������݁A�_�������̂�ł����b�オ����A�G�g���̉����ŔN���𑗂��Ă����B
�����̖��z��
�u���ɑ����āA���߂Ƃ�т̂��ƂӂƂ��v
�Ƃ������Ƃ���Ŗڂ����߂��B
�u��(�K�삨��)�v�Ƃ͗ݑ�̖{�m�ł���A�u���ɑ����Ă��ƂӂƂ��v�Ƃ͍Ăєɉh����Ƃ����g�����Ɗ�сA�A�̋��s�������B
�قǂȂ����}�G�g���ɏ����o����A�{�̂̓��Œm�s���g�ƂȂ������Ƃ����s�v�c�ł���B
281�l�Ԏ����l�N
2022/07/04(��) 22:02:10.36ID:lty1qK8d �l������u�S�v�̑����̂��u���v�Ǝ��Ⴆ���̂�������Ȃ�
�S��(�X�P�^�P)���S��(�X�P�^�P)�������Ƃ������Ƃ��낤
�S��(�X�P�^�P)���S��(�X�P�^�P)�������Ƃ������Ƃ��낤
282�l�Ԏ����l�N
2022/07/04(��) 22:16:07.61ID:hXjZB30E ���߂��ƌ��̕������͂܂������ʕ������A�E�Ǝ҂��܂����Ă�����᎗�Ă邯�ǎ��Ⴆ�Ȃ��ł��傤
�ǂ������p�o�̕�������
�ǂ������p�o�̕�������
283�l�Ԏ����l�N
2022/07/04(��) 22:27:36.14ID:YHmjXRAA ���ꂪ�\�̖��m�֖����Ă������
284�l�Ԏ����l�N
2022/07/05(��) 19:43:13.55ID:ubBmdJR7 �G�t�̎��R�y�����͌��E�ؑ����ɂāA�L�b�G�g���Ɏd���Ă������A��ɍI�݂ł���̂�
���i���̗{�q���ɋ��t�����A�����莁�����Ƃ����B
���w�̎��A���R�y�͑���Ɏc�������A���̑��q�ł���ؑ��E���͖����̓S�C�ɓ������Ď��B
�R��ɁA��㗎�����A�R�y�͓����o�Ĕ����̑�{�V�ɔE�ы������ߕ߂��A�����n�E�����ׂ�
���ɁA���a���тɖ{�莛����@�a���A�u�ނ͊G�t�ł��蕐�ӂ̂��Ƃɂ͍S���ʎ҂ł���B�v
�Ƃ̋����A�����̋V�������݂������B
�����Łu�G�t�Ƒ��ᖳ���Ƃ�暝������邩�B�v�Ƃ��q�˂̏��A��B�ďG�g�����A�����������̖@����
���c���ꂽ�ۂɁA�V��ɑm�̖������M���������j��̎c�Ђ��������̂��A���i���ɕ��i�C���j
���������A�i���͂��̌��𐋂����ɑ������B����Ă��̐Ղ��R�y���`�����B
�����\�����ĂāA����Ƃꂽ�B
���݂Ɏ����Ă��A���̉���w暝��̗��x�ƌĂ�ł���Ƃ����B
�R�y�͌��݂̖D�a���̐�c�ł���B
�i�V���Ӂj
���i���̗{�q���ɋ��t�����A�����莁�����Ƃ����B
���w�̎��A���R�y�͑���Ɏc�������A���̑��q�ł���ؑ��E���͖����̓S�C�ɓ������Ď��B
�R��ɁA��㗎�����A�R�y�͓����o�Ĕ����̑�{�V�ɔE�ы������ߕ߂��A�����n�E�����ׂ�
���ɁA���a���тɖ{�莛����@�a���A�u�ނ͊G�t�ł��蕐�ӂ̂��Ƃɂ͍S���ʎ҂ł���B�v
�Ƃ̋����A�����̋V�������݂������B
�����Łu�G�t�Ƒ��ᖳ���Ƃ�暝������邩�B�v�Ƃ��q�˂̏��A��B�ďG�g�����A�����������̖@����
���c���ꂽ�ۂɁA�V��ɑm�̖������M���������j��̎c�Ђ��������̂��A���i���ɕ��i�C���j
���������A�i���͂��̌��𐋂����ɑ������B����Ă��̐Ղ��R�y���`�����B
�����\�����ĂāA����Ƃꂽ�B
���݂Ɏ����Ă��A���̉���w暝��̗��x�ƌĂ�ł���Ƃ����B
�R�y�͌��݂̖D�a���̐�c�ł���B
�i�V���Ӂj
285�l�Ԏ����l�N
2022/07/05(��) 23:11:42.48ID:u5LZH6cj ���h�G�t�̂قƂ�ǂ����쏫�R�ƌ�p�̉��G�t�Ƃ��č]�ˍݏZ�������̂ɑ��A�R�y�̌n���͋��s�ݏZ�ŋ����ƌĂ��
�R�y�̌�p�҂̎R��Ƃ��̎q���͑�X�D�a�����̂��Ă���
�R�y�̌�p�҂̎R��Ƃ��̎q���͑�X�D�a�����̂��Ă���
286�l�Ԏ����l�N
2022/07/07(��) 17:10:07.68ID:7LyLmL9R ���R�Ƃɉ����āA��N�������U�ɓe�̌�z���������オ���鎖�ɂ��āA���c�ł���
���Ǔc�������L�e�i����L�e�j�͏�썑����i����j��̂���A���q�����ł��鑫�����n��������
��Ɛl�ł������̂����A�i���N���A�����`�����R�Ƃ��̎����ƕs�a�̂��Ƃ����č��킠�肵�Ɂi�i���̗��j�A
���n�����ɑł������Ď��Q����A���̌�͊F���s���R�̉��m�ƂȂ�A�Ǘ̏㐙�����͐��@���������d��
����s�������߁A�А����X�ɐ���ɂȂ����B
�����Ċ��q�����̎c�}��{�����߂����A���ł��V�c�̈ꑰ�ɂ����ẮA����₿�t���͂炷�ׂ��Ƃ̎��́A
�L�e�͓���Ɉ��g�Ȃ��A���\��N�i�����͏\��N�Ƃ���j�O����{�A�L�e���тɂ��̎q���E�e����
�����ɋ����𗣂�o�āA���X�ɗ��Q���āA�E��ő��B����ɍ݂�A���@�̐��ɂĔ�����A
�L�e�͒�����A�e���͓�����i��Ɋґ����ď������Y���q��Ə̂��j�Ɩ����\�Ă��獧�ӂɂ��Ă���
���}�����@�̎O�j�A�ѓ��������Ƃ����ҁA�M�B�̎R�Ƃ�孋����Ă����̂ŁA�L�e���q�͓��N�\���{�A
���̏���q�˂Ď������B
�����͑傢�ɉx�сA�����������悤�Ǝv�������ꕨ�������A������\����A�������Ď���
�������A�e��D�����߁A���\�O�N�������U�ɁA���̓e���z���ɂ��Đi�߂��B
�����蓿��Ƃ̋g��ƂȂ����B
�����ē��N�Z���A�����̋��𗧂��z���A�O�B���̋��̎��E�Ƃ���A�L�e�͉Ëg��N�Ɏ��������B
�i�V���Ӂj
���쏫�R�Ƃ̐����V��ɂ��Ă̓`���B����̐�c���i���̗��̂��߂ɎO�͂ɗ���Ă����Ƃ����b��
�������̂ł��ˁB
���Ǔc�������L�e�i����L�e�j�͏�썑����i����j��̂���A���q�����ł��鑫�����n��������
��Ɛl�ł������̂����A�i���N���A�����`�����R�Ƃ��̎����ƕs�a�̂��Ƃ����č��킠�肵�Ɂi�i���̗��j�A
���n�����ɑł������Ď��Q����A���̌�͊F���s���R�̉��m�ƂȂ�A�Ǘ̏㐙�����͐��@���������d��
����s�������߁A�А����X�ɐ���ɂȂ����B
�����Ċ��q�����̎c�}��{�����߂����A���ł��V�c�̈ꑰ�ɂ����ẮA����₿�t���͂炷�ׂ��Ƃ̎��́A
�L�e�͓���Ɉ��g�Ȃ��A���\��N�i�����͏\��N�Ƃ���j�O����{�A�L�e���тɂ��̎q���E�e����
�����ɋ����𗣂�o�āA���X�ɗ��Q���āA�E��ő��B����ɍ݂�A���@�̐��ɂĔ�����A
�L�e�͒�����A�e���͓�����i��Ɋґ����ď������Y���q��Ə̂��j�Ɩ����\�Ă��獧�ӂɂ��Ă���
���}�����@�̎O�j�A�ѓ��������Ƃ����ҁA�M�B�̎R�Ƃ�孋����Ă����̂ŁA�L�e���q�͓��N�\���{�A
���̏���q�˂Ď������B
�����͑傢�ɉx�сA�����������悤�Ǝv�������ꕨ�������A������\����A�������Ď���
�������A�e��D�����߁A���\�O�N�������U�ɁA���̓e���z���ɂ��Đi�߂��B
�����蓿��Ƃ̋g��ƂȂ����B
�����ē��N�Z���A�����̋��𗧂��z���A�O�B���̋��̎��E�Ƃ���A�L�e�͉Ëg��N�Ɏ��������B
�i�V���Ӂj
���쏫�R�Ƃ̐����V��ɂ��Ă̓`���B����̐�c���i���̗��̂��߂ɎO�͂ɗ���Ă����Ƃ����b��
�������̂ł��ˁB
287�l�Ԏ����l�N
2022/07/09(�y) 11:09:41.07ID:/UX4P9R1 �V���N���A����ƍN���͍]�{�i�]�ˁj�Ɉڂ苋�������A�匴�������N����������A
�u����ɒ��炪���邩�v
�ƌ�q�˂ɂȂ�ꂽ�B�N������A�u��ȗւ̓��̖k�̕ӂ�ɁA���Ђ������܂����B�v�ƌ��サ���B
�����N�����ē��Ƃ��Ėk�ȗւɓ���ƁA����̏�ɁA�~�̖𐔑��A���Ă���̂������ɂȂ��āA
�u���c����͉̐l�ł������̂ɁA�V�_�����������̂��v
�Ƌ��ɂȂ����B�܂���Ђ̊z��������
�u����ɒ��炪�Ȃ���A��{�̎R�����������ׂ��Ǝv���Ă������A�ʂ炸���R���Ђ����Ēu���Ă��邼�v
�Ƃ̏�ӂ��������̂��A�N������
�u�����ɂ��̂����炻�̂悤�ɂȂ��Ă����̂́A�Ɍ�i�v�̋g���Ƒ������܂��v
�Ɛ\���グ��ƁA�ƍN������@���߂Ȃ炸���āA�������Ă��̎Ђ��g�t�R�Ɉڂ���A�V���ɑ������ꂽ�B
�i�V���Ӂj
���̍g�t�R�R���Ђ��A��ɍX�Ɉړ]���āA���݂̉i�c���̓��}�_�ЂƂȂ��������ŁB
�u����ɒ��炪���邩�v
�ƌ�q�˂ɂȂ�ꂽ�B�N������A�u��ȗւ̓��̖k�̕ӂ�ɁA���Ђ������܂����B�v�ƌ��サ���B
�����N�����ē��Ƃ��Ėk�ȗւɓ���ƁA����̏�ɁA�~�̖𐔑��A���Ă���̂������ɂȂ��āA
�u���c����͉̐l�ł������̂ɁA�V�_�����������̂��v
�Ƌ��ɂȂ����B�܂���Ђ̊z��������
�u����ɒ��炪�Ȃ���A��{�̎R�����������ׂ��Ǝv���Ă������A�ʂ炸���R���Ђ����Ēu���Ă��邼�v
�Ƃ̏�ӂ��������̂��A�N������
�u�����ɂ��̂����炻�̂悤�ɂȂ��Ă����̂́A�Ɍ�i�v�̋g���Ƒ������܂��v
�Ɛ\���グ��ƁA�ƍN������@���߂Ȃ炸���āA�������Ă��̎Ђ��g�t�R�Ɉڂ���A�V���ɑ������ꂽ�B
�i�V���Ӂj
���̍g�t�R�R���Ђ��A��ɍX�Ɉړ]���āA���݂̉i�c���̓��}�_�ЂƂȂ��������ŁB
288�l�Ԏ����l�N
2022/07/11(��) 18:20:37.96ID:cem3OHMR �u��F���p�L�v���u�����g�̎��v
�喾����蓂�D���L��ɓV���\�N(1541�N)�A���\��N�A���\�ܔN�A�i�\�N�ԁA�V���O�N(1575�N)�Ƃ��т��ѓ������A�ҌՎl���A��ہA�E���A�_���A�l���A����A�яJ�����A�����A���͂̔�Ȃǂ������炳�ꂽ�B
���̂��ߑ�F�@�ٌ������낢��i�����W�߁A���D��D���A�����g�𗧂Ă邽�߂ɕ��������̒B�l��I�ꂽ�B
�����ɐ������Z�̏Z�l�A�V���^�Ƃ������̂��������ꂽ���ߘa���ɋ��Z���Ă����̂��@�ٌ����������߂��A�g�҂��������Ă߂������ꂽ�B
���̂̂����������e�c�����ƍ������B
�@�ٌ���茭���g�𖽂����A���낢�뎫�ނ�������ǂ��ĎO�̋M���A�f�肪�����������A����̉��D�A�������g���āA���痢�̊C���z���ē���̂��ƂŒ����q�����B
�鉤�����{�̒��g���݂̈����������A�ɂ킩�ɏd�a�ƂȂ�A���薼�オ����������ꂽ����Ό��Ȃ����������B
��͂�������ݍ����̑m�������W�ߒ��d�ɋ��{���������̂��A�����̉Ɛl�Ɏ�X�̏d������������B
�c��̎҂����͋A��ɗ��ɑ�����j���A�����炪���\�]�l���ƂƂ��ɋA�������B
�����̒��j�Տ��ۂ͎O���ꋤ�ɏ@�ٌ��̉������A���̏t����F�`�����ɕ�����Ȃ��琬�������B
�Ȃ��e�c�����̐�c�͐��a�����ő��c�����̍����n�ӎ��ɓ���(�H)�A�������j�Ɖ������сA���Z�֓��Ƃ��p���A������o���Ƃ���s�v�c�Ȃ��Ƃ��������B
�ǂ��Ƃ�����ʗe�p�ɗD�ꂽ�������������l�ƂȂ������A����ď\��m�鑏�����ł���A�̎傪����ʂ�������v���ʂ�̓������������߁A�������ɒ��������B
�€�ĉ��D���A�o�Y����i�ɂȂ��ď��͎Y������点�A
�u�����̊ԁA�ǂȂ�������܂���悤�v�Ɠ`�����B
�O�����߂��ė̎�͉����݁A���Ԃ���Ђ����Ɍ����Ƃ���A���낵���p�̑�ւ��q��������āA�Ԃ�����o���Ďq�����r�߂Ă����B
�̎�͊̂�ׂ��A�l���W�߂ĎY���̔���j���ē������Ƃ���A�Ԏq�����Ŏւ͍s���m�炸�ł������B
�Y���͒r�ƂȂ�A���̓����������܂����Ȃ����B
���̎q����Ă��Ƃ���A�w���ɔb�̖䂪����A�q����X�����Ƃ���ɔb�̖䂪�����悤�ɂȂ����Ƃ����B
���ꂪ�e�c�̋N��ł���A���Ɏ���܂Ŕw���̖�͑����Ă���Ƃ����B
�喾����蓂�D���L��ɓV���\�N(1541�N)�A���\��N�A���\�ܔN�A�i�\�N�ԁA�V���O�N(1575�N)�Ƃ��т��ѓ������A�ҌՎl���A��ہA�E���A�_���A�l���A����A�яJ�����A�����A���͂̔�Ȃǂ������炳�ꂽ�B
���̂��ߑ�F�@�ٌ������낢��i�����W�߁A���D��D���A�����g�𗧂Ă邽�߂ɕ��������̒B�l��I�ꂽ�B
�����ɐ������Z�̏Z�l�A�V���^�Ƃ������̂��������ꂽ���ߘa���ɋ��Z���Ă����̂��@�ٌ����������߂��A�g�҂��������Ă߂������ꂽ�B
���̂̂����������e�c�����ƍ������B
�@�ٌ���茭���g�𖽂����A���낢�뎫�ނ�������ǂ��ĎO�̋M���A�f�肪�����������A����̉��D�A�������g���āA���痢�̊C���z���ē���̂��ƂŒ����q�����B
�鉤�����{�̒��g���݂̈����������A�ɂ킩�ɏd�a�ƂȂ�A���薼�オ����������ꂽ����Ό��Ȃ����������B
��͂�������ݍ����̑m�������W�ߒ��d�ɋ��{���������̂��A�����̉Ɛl�Ɏ�X�̏d������������B
�c��̎҂����͋A��ɗ��ɑ�����j���A�����炪���\�]�l���ƂƂ��ɋA�������B
�����̒��j�Տ��ۂ͎O���ꋤ�ɏ@�ٌ��̉������A���̏t����F�`�����ɕ�����Ȃ��琬�������B
�Ȃ��e�c�����̐�c�͐��a�����ő��c�����̍����n�ӎ��ɓ���(�H)�A�������j�Ɖ������сA���Z�֓��Ƃ��p���A������o���Ƃ���s�v�c�Ȃ��Ƃ��������B
�ǂ��Ƃ�����ʗe�p�ɗD�ꂽ�������������l�ƂȂ������A����ď\��m�鑏�����ł���A�̎傪����ʂ�������v���ʂ�̓������������߁A�������ɒ��������B
�€�ĉ��D���A�o�Y����i�ɂȂ��ď��͎Y������点�A
�u�����̊ԁA�ǂȂ�������܂���悤�v�Ɠ`�����B
�O�����߂��ė̎�͉����݁A���Ԃ���Ђ����Ɍ����Ƃ���A���낵���p�̑�ւ��q��������āA�Ԃ�����o���Ďq�����r�߂Ă����B
�̎�͊̂�ׂ��A�l���W�߂ĎY���̔���j���ē������Ƃ���A�Ԏq�����Ŏւ͍s���m�炸�ł������B
�Y���͒r�ƂȂ�A���̓����������܂����Ȃ����B
���̎q����Ă��Ƃ���A�w���ɔb�̖䂪����A�q����X�����Ƃ���ɔb�̖䂪�����悤�ɂȂ����Ƃ����B
���ꂪ�e�c�̋N��ł���A���Ɏ���܂Ŕw���̖�͑����Ă���Ƃ����B
289�l�Ԏ����l�N
2022/07/11(��) 18:28:06.43ID:cem3OHMR http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13394.html
��S�����̎��@�t�A���R�̒���
������̘b�ɏo�Ă���u�A�c��������̒��j�őP�O�Y�v���Տ��ۂ̂��Ƃ��Ǝv����B
�����u��F���p�L�v�o�T�ł͂��邪�A�u�e�c�v�Ɓu�A�c�v�Ŏ����قȂ��Ă���B
���łɐV�䔒�u���m�I���v�ł͖L��̗̎�ƃt�����V�X�R�E�U�r�G���ɂ��ăV�h�b�`������Ă���ӏ���
https://ja.m.wikisource.org/wiki/���m�I��
����ɁA�t�����V�X�N�X�́A���ɔg�������Z�l�A�Ŕ��Î҂Ƃ��ӂ��́A卽����A
沌�̉��`�́A��F���ʖ�����@�ٖ�A���g�������̂́A�A�c���������i�����A����淸�a�����ɂāA�n粂̉Ƃ����A���V���̉Ƃ����A�Ɩ�b�Ȃ�A���q���Տ��A���ɎO歲��Ƃ��Ӂj���Ƃ́A���Z���V���̑���A
�V���\��N�ɁA�@�ق����߂Ɏg���āA���[�}�Ɏ����A���l��ɂ����e�q�ɁA�ꓹ�l��甁�����āA���q�̒��ɟ����A㉂����������w���āA����沌�̑喼�̎q�́A�@���隤��Ƃ��ӁA�A��沌�̉��`�A���g���̐������ӂɁA�������́A���͂炸�Ƃ���
�ƐA�c���������ł͂Ȃ����[�}�ɍs�����Ƃ��Ă���
��S�����̎��@�t�A���R�̒���
������̘b�ɏo�Ă���u�A�c��������̒��j�őP�O�Y�v���Տ��ۂ̂��Ƃ��Ǝv����B
�����u��F���p�L�v�o�T�ł͂��邪�A�u�e�c�v�Ɓu�A�c�v�Ŏ����قȂ��Ă���B
���łɐV�䔒�u���m�I���v�ł͖L��̗̎�ƃt�����V�X�R�E�U�r�G���ɂ��ăV�h�b�`������Ă���ӏ���
https://ja.m.wikisource.org/wiki/���m�I��
����ɁA�t�����V�X�N�X�́A���ɔg�������Z�l�A�Ŕ��Î҂Ƃ��ӂ��́A卽����A
沌�̉��`�́A��F���ʖ�����@�ٖ�A���g�������̂́A�A�c���������i�����A����淸�a�����ɂāA�n粂̉Ƃ����A���V���̉Ƃ����A�Ɩ�b�Ȃ�A���q���Տ��A���ɎO歲��Ƃ��Ӂj���Ƃ́A���Z���V���̑���A
�V���\��N�ɁA�@�ق����߂Ɏg���āA���[�}�Ɏ����A���l��ɂ����e�q�ɁA�ꓹ�l��甁�����āA���q�̒��ɟ����A㉂����������w���āA����沌�̑喼�̎q�́A�@���隤��Ƃ��ӁA�A��沌�̉��`�A���g���̐������ӂɁA�������́A���͂炸�Ƃ���
�ƐA�c���������ł͂Ȃ����[�}�ɍs�����Ƃ��Ă���
290�l�Ԏ����l�N
2022/07/14(��) 15:02:37.22ID:uooA4Rmw �u����G�ځv����]�ˏ�V��t�Ə��x���B
�]�ˏ�V��t�̏�h��̔��y�����N������Č��ꂵ�����߁A���̂��тɔO����ɏ�h������Ă������A���J�������������߂������Ĕ��y���S�Ĕ�����Ă��܂����B
�ǂ�������悩�낤�ƌ�V�����c�_���Ă����Ƃ���A���x���B���o�邵�Ă�������
��V���́u���B�͐���̐l�ł���̂ŁA�V��t�̔��y�������Ȃ��H�v�͂Ȃ����낤���H�v�Ƒ��k�����B
���B�������Ă����ɂ́u��h����x�ł���قǂȂ�������ł��傤�B
�V��̕ǂ��A���n�̎��_�Ŕ����h��グ�Ďd�����A���J�������ď�h�肪���X�����悤�Ƃ��A���ꂵ�����Ƃ͂Ȃ��ł��傤�v
��V���͎��ł��āu�Ȃ�قǁA�����Ƃ����ɂł��v�ƂĂ��̂悤�ɂ����Ƃ������Ƃ��B
�]�ˏ�V��t�̏�h��̔��y�����N������Č��ꂵ�����߁A���̂��тɔO����ɏ�h������Ă������A���J�������������߂������Ĕ��y���S�Ĕ�����Ă��܂����B
�ǂ�������悩�낤�ƌ�V�����c�_���Ă����Ƃ���A���x���B���o�邵�Ă�������
��V���́u���B�͐���̐l�ł���̂ŁA�V��t�̔��y�������Ȃ��H�v�͂Ȃ����낤���H�v�Ƒ��k�����B
���B�������Ă����ɂ́u��h����x�ł���قǂȂ�������ł��傤�B
�V��̕ǂ��A���n�̎��_�Ŕ����h��グ�Ďd�����A���J�������ď�h�肪���X�����悤�Ƃ��A���ꂵ�����Ƃ͂Ȃ��ł��傤�v
��V���͎��ł��āu�Ȃ�قǁA�����Ƃ����ɂł��v�ƂĂ��̂悤�ɂ����Ƃ������Ƃ��B
291�l�Ԏ����l�N
2022/07/15(��) 11:54:08.91ID:BM9I11l+ �ː�G���͐��������A�_�a�ɂĐm������A�̂ɐ����ܔ��̎��ɂ��āA��N�ł���F�쑽���Ƃ�
�s�����L�鎞�́A���x�������Ԃ��Ђ߂Đ����ɍs���A�܂�����̂ɐl�X�͔ނ��h���������B
�������i�Ɨ��E��L���j�ƒ��D���O�Y�i��e�E��z����j�͋��ɒZ���ł���A�ǂ��������
���_�ɋy���A�G���͂����G�ߗ@���A
�u���̎O�l���s�a�ɂȂ������́A��Ɣj�p�̊�ł��邼�I�v
�Ɨ܂𗬂��Đ��������B�̂ɗ��l���a�������Ƃ����B
�܂��A�F�쑽���Ƃ͕\���L�鏫�ł���A���X�A���Ⴄ�����������Ƃ�����m���Ă��āA
�F�쑽�Ɖ�������c���鎖���L�鎞�́A�ނ�͌ː�G������N�����������Ă����
���ł���Ƃ����B
�i�ː�L�j
�F�쑽�Ƃɂ�����ː�G���ɂ��āB
�s�����L�鎞�́A���x�������Ԃ��Ђ߂Đ����ɍs���A�܂�����̂ɐl�X�͔ނ��h���������B
�������i�Ɨ��E��L���j�ƒ��D���O�Y�i��e�E��z����j�͋��ɒZ���ł���A�ǂ��������
���_�ɋy���A�G���͂����G�ߗ@���A
�u���̎O�l���s�a�ɂȂ������́A��Ɣj�p�̊�ł��邼�I�v
�Ɨ܂𗬂��Đ��������B�̂ɗ��l���a�������Ƃ����B
�܂��A�F�쑽���Ƃ͕\���L�鏫�ł���A���X�A���Ⴄ�����������Ƃ�����m���Ă��āA
�F�쑽�Ɖ�������c���鎖���L�鎞�́A�ނ�͌ː�G������N�����������Ă����
���ł���Ƃ����B
�i�ː�L�j
�F�쑽�Ƃɂ�����ː�G���ɂ��āB
292�l�Ԏ����l�N
2022/07/15(��) 12:03:06.68ID:QPIAvPs9 ���c�G�ƌ�
https://i.imgur.com/iq8BF7f.jpg
https://i.imgur.com/iq8BF7f.jpg
293�l�Ԏ����l�N
2022/07/16(�y) 11:08:02.39ID:T4jJtv0Z �u����G�ځv���疾�̓��{�ւ̉����v���̎��̘b
�ƌ����̌䎞�A����(��)������łڂ�������(1644�N�A���ۂɂ͖���łڂ����̂͗�����)�A�喾�̑叫(�A����)������{�։�������Ă����B
�\���̌R�����o�����ƌv�悵���Ƃ���Ɉ�ɑ|����(��ɒ��F)���q�ׂĂ������Ƃɂ�
�u�́A���}�����N���U�߁A�喾�̉����Ɛ�������ɂ����Ԃ鏟�������̂́A���{�̕��͋v���������ł��������ߐ�ɂȂ�Ă���A
����A�喾�̕��͋v���������ł��������ߐ�ɂȂ�Ă��Ȃ��������߂ł��B
���A���{�̕��͋v���������Ő��m�炸�A���̕��͑喾���Đ�ɂȂ�Ă���܂��B
�ᕺ�����킵���Ƃ���ŏ����͓����Ȃ��ł��傤�B
���{�̕��������s�ꂽ�Ȃ�A�������Ė����܂ňٍ��ɂ܂ŕ�����邱�ƂƂȂ�܂��傤�B�v
�Ɛ\�������߁A�����h���͍����~�݂ɂȂ����B
����ɂ͏�̔����͑�v�ەF���q��̂��̂��Ƃ���(��v�ے��ׂ�1639�N���S)
�ƌ����̌䎞�A����(��)������łڂ�������(1644�N�A���ۂɂ͖���łڂ����̂͗�����)�A�喾�̑叫(�A����)������{�։�������Ă����B
�\���̌R�����o�����ƌv�悵���Ƃ���Ɉ�ɑ|����(��ɒ��F)���q�ׂĂ������Ƃɂ�
�u�́A���}�����N���U�߁A�喾�̉����Ɛ�������ɂ����Ԃ鏟�������̂́A���{�̕��͋v���������ł��������ߐ�ɂȂ�Ă���A
����A�喾�̕��͋v���������ł��������ߐ�ɂȂ�Ă��Ȃ��������߂ł��B
���A���{�̕��͋v���������Ő��m�炸�A���̕��͑喾���Đ�ɂȂ�Ă���܂��B
�ᕺ�����킵���Ƃ���ŏ����͓����Ȃ��ł��傤�B
���{�̕��������s�ꂽ�Ȃ�A�������Ė����܂ňٍ��ɂ܂ŕ�����邱�ƂƂȂ�܂��傤�B�v
�Ɛ\�������߁A�����h���͍����~�݂ɂȂ����B
����ɂ͏�̔����͑�v�ەF���q��̂��̂��Ƃ���(��v�ے��ׂ�1639�N���S)
294�l�Ԏ����l�N
2022/07/16(�y) 11:15:13.67ID:WAJ05+SS �A��������Ȃ��ĕ��e�̓A�ŗ����A���̎���
295�l�Ԏ����l�N
2022/07/16(�y) 14:02:53.97ID:V+56qfjT296�l�Ԏ����l�N
2022/07/16(�y) 14:42:21.63ID:hQTuVJNr ���łɁu����G�ځv�̕ʂ̉ӏ��ɏ�����Ă���b�ł�
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-1677.html
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-12676.html
�ł͖����@������Z�N�̃Z���t�Ƃ���Ă���q�d���펀�̗\������v�ەF���q�傪�������ƂɂȂ��Ă܂�
�q�d�����펀�����̂͑�v�ەF���q��̎��̑O�N�����炱����͂܂��\��������܂���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-1677.html
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-12676.html
�ł͖����@������Z�N�̃Z���t�Ƃ���Ă���q�d���펀�̗\������v�ەF���q�傪�������ƂɂȂ��Ă܂�
�q�d�����펀�����̂͑�v�ەF���q��̎��̑O�N�����炱����͂܂��\��������܂���
297�l�Ԏ����l�N
2022/07/18(��) 14:38:41.02ID:3H39QenK �V���\�N�ɂ́A���A�k�̏����͊T�ː�捂ƂȂ�A�D�c�M�����͍ݗ�����Ă����B
�ː�G���͂��̍��a�C�������Ă���A���������܂������ŁA�֓����Ẩ���ɁA�×{�̂��ߕ������B
���̂悤�ȏ��ɁA�G�g��������������𐅍U�߂ɂ���A�F�쑽�Ƃ���}�̒ʍ�������A
�A�낤�Ƃ��Ă��鏊�ɁA�M�������q����s���̉����i�{�\���̕ρj�ɋy�сA�����ꓝ�ɑ������A
���C�k���̂�����͎�ɑS���ʍs����o�����˂�L�l�ŁA�G�����S�Ȃ炸�����ÂɁA�l�����甪���܂�
�������A�����ɏ���ɓo���ďG�g���ɔq�y�����B���̌�����ɋl�߂Ă����Ƃ����B
�������Ȃ���ނ͕a�C�̂��߂ɁA�N�X��w�ɂ��o���Ȃ����Ƃ������Ȃ����B
�V���\�l�A�ܔN���ɁA�F�쑽�G�ƌ��̏d�b�A�l�A�ܔy����̂����t�����A�G�������C��
����ƂȂ����B
�b�������ĕa�C��\�����āA��̂𒄎q�����Y�B���ɏ���A���g�͓������ėF���ƍ����A������R�̘[��
�����Ă���A�����A�A�́A���тɕ��͂��y���B
���X���@�@�𐒂݁A�a���i��͕����̊O�A�������������B
���O�̉F�쑽�ƉƐb�ŌØV�̖ʁX�́A�c�炸���@�@�����Ă����B
�c����N�����Z���A�G���͎��������B����͒��q�ł������B��������w�̂��ߗ�������Ă���Ԃ�
���ł������B��R�ɑ���ꂽ�B���̏ꏊ�ɂ͍����A�Γ�������B
�@�����C�֖V���F�тƍ������B
�ɂ������ȁA�ނɂ͐��U�̍s��L�������A���̎�����m�邱�Ƃ͏o�����A�͂��ɏ\�̂������
�����ɋ�����݂̂ł���B
�G���̕}�\�͓ܐ�A�O�ɗa����Ƃ��Č\�l�g�A�}�����킹�ĘZ���A�l���O��̐������ɂāA
�F�쑽���Ƒ��̏d�b�ł������B
�i�ː�L�j
�ː�G���̍Ŋ��ɂ���
�ː�G���͂��̍��a�C�������Ă���A���������܂������ŁA�֓����Ẩ���ɁA�×{�̂��ߕ������B
���̂悤�ȏ��ɁA�G�g��������������𐅍U�߂ɂ���A�F�쑽�Ƃ���}�̒ʍ�������A
�A�낤�Ƃ��Ă��鏊�ɁA�M�������q����s���̉����i�{�\���̕ρj�ɋy�сA�����ꓝ�ɑ������A
���C�k���̂�����͎�ɑS���ʍs����o�����˂�L�l�ŁA�G�����S�Ȃ炸�����ÂɁA�l�����甪���܂�
�������A�����ɏ���ɓo���ďG�g���ɔq�y�����B���̌�����ɋl�߂Ă����Ƃ����B
�������Ȃ���ނ͕a�C�̂��߂ɁA�N�X��w�ɂ��o���Ȃ����Ƃ������Ȃ����B
�V���\�l�A�ܔN���ɁA�F�쑽�G�ƌ��̏d�b�A�l�A�ܔy����̂����t�����A�G�������C��
����ƂȂ����B
�b�������ĕa�C��\�����āA��̂𒄎q�����Y�B���ɏ���A���g�͓������ėF���ƍ����A������R�̘[��
�����Ă���A�����A�A�́A���тɕ��͂��y���B
���X���@�@�𐒂݁A�a���i��͕����̊O�A�������������B
���O�̉F�쑽�ƉƐb�ŌØV�̖ʁX�́A�c�炸���@�@�����Ă����B
�c����N�����Z���A�G���͎��������B����͒��q�ł������B��������w�̂��ߗ�������Ă���Ԃ�
���ł������B��R�ɑ���ꂽ�B���̏ꏊ�ɂ͍����A�Γ�������B
�@�����C�֖V���F�тƍ������B
�ɂ������ȁA�ނɂ͐��U�̍s��L�������A���̎�����m�邱�Ƃ͏o�����A�͂��ɏ\�̂������
�����ɋ�����݂̂ł���B
�G���̕}�\�͓ܐ�A�O�ɗa����Ƃ��Č\�l�g�A�}�����킹�ĘZ���A�l���O��̐������ɂāA
�F�쑽���Ƒ��̏d�b�ł������B
�i�ː�L�j
�ː�G���̍Ŋ��ɂ���
298�l�Ԏ����l�N
2022/07/18(��) 15:40:06.22ID:/AevqENK ��}�̒ʍ��ĉ����
299�l�Ԏ����l�N
2022/07/19(��) 19:25:56.28ID:v0TjrcZ5 �L�b�G�g�����k�����U�ߋ��������i���c�������j�A����ƍN���͏��c���䒅�w��ɋ��ɂȂ���
�u���B�]�˂ɂ����āA�F�����ɐ���ׂ��V�䎛�ƁA��ɂȂ�ׂ���y���������Ă�悤�ɁB�v
���̏�ӂɑ��A
�u��y�@�ł͓`�ʉ@�Ƒ��㎛�Ɛ\������������܂��B�R��ǂ��`�ʉ@�͂����̍��ɂ���܂��B
���㎛�͑O�ɊC�A���ɎR������Ă���i�r�ł���܂��B
�܂���F�����ɂȂ�ׂ��V�䎛�Ƃ��ẮA���ω����̊O�ɂ͂���܂���B�v
�ƕ����コ�ꂽ�B
����ɂ�葝�㎛�A���̓�@�̏Z�������c���̌�w���ɏ�����A��ڌ��������t����ꂽ�B
���̌�A�����̋����ɂāA���W���̌䏑�t���������Ƃ��A�S�M��肱�̏��t�������グ�����A
���̓��e���䗗�̏�A���̓��t�ɑ�
�u���̕��́A�K�������ƔF�߂�����B�v
�Ƌ����������B
��S�M�����A�d�˂āu�T�˂������������ɂ��ẮA���ٖ̈��͏����\���܂���v
�Ə��@�ɂ��Ă̌��オ���������A����
�u���㎛�͕�Ȃ�A��������ׂ��B���͋F�����ł���̂�����A�ٖ��ɂĔF�߂�悤�ɁB�v
�Ə�ӂ������Ƃ����B
���̐��͌×����A�����ɖV���O�\�Z�����������B�R��ǂ����̓����͎�̊O�j�Ă���A
���̂����\�V����͐��m�ł��������A�c��͎R���̗ނł���A�ȑт̖V������������߁A
����Ƃ̌�F�����Ƃ��Ă͕s�s���ł���Ƃ̍������������B
�������ƍN���͖�̂悤�Ȃ��ƂɌ�\���������A�㌎�ɂ͏��c����������܂�A���i�]�ˏ�j�ɉ�����
��ʎ�o�]�ǂ��������B���̎��͖ܘ_�A���̑��̌�F���ɂ����Ă����m�ɂ������t����ꂽ�B
�̂ɍȑт̎҂͎��R�Ǝ����̜p�j���v����Ȃ�A�����͎q���A�����͒�q�𐴑m�Ƃ��A
���͎�������Ȃǂ��Ă��̐g�͑މ@�������߁A���Ȃ����m����ƂȂ����B
�i�V���Ӂj
�u���B�]�˂ɂ����āA�F�����ɐ���ׂ��V�䎛�ƁA��ɂȂ�ׂ���y���������Ă�悤�ɁB�v
���̏�ӂɑ��A
�u��y�@�ł͓`�ʉ@�Ƒ��㎛�Ɛ\������������܂��B�R��ǂ��`�ʉ@�͂����̍��ɂ���܂��B
���㎛�͑O�ɊC�A���ɎR������Ă���i�r�ł���܂��B
�܂���F�����ɂȂ�ׂ��V�䎛�Ƃ��ẮA���ω����̊O�ɂ͂���܂���B�v
�ƕ����コ�ꂽ�B
����ɂ�葝�㎛�A���̓�@�̏Z�������c���̌�w���ɏ�����A��ڌ��������t����ꂽ�B
���̌�A�����̋����ɂāA���W���̌䏑�t���������Ƃ��A�S�M��肱�̏��t�������グ�����A
���̓��e���䗗�̏�A���̓��t�ɑ�
�u���̕��́A�K�������ƔF�߂�����B�v
�Ƌ����������B
��S�M�����A�d�˂āu�T�˂������������ɂ��ẮA���ٖ̈��͏����\���܂���v
�Ə��@�ɂ��Ă̌��オ���������A����
�u���㎛�͕�Ȃ�A��������ׂ��B���͋F�����ł���̂�����A�ٖ��ɂĔF�߂�悤�ɁB�v
�Ə�ӂ������Ƃ����B
���̐��͌×����A�����ɖV���O�\�Z�����������B�R��ǂ����̓����͎�̊O�j�Ă���A
���̂����\�V����͐��m�ł��������A�c��͎R���̗ނł���A�ȑт̖V������������߁A
����Ƃ̌�F�����Ƃ��Ă͕s�s���ł���Ƃ̍������������B
�������ƍN���͖�̂悤�Ȃ��ƂɌ�\���������A�㌎�ɂ͏��c����������܂�A���i�]�ˏ�j�ɉ�����
��ʎ�o�]�ǂ��������B���̎��͖ܘ_�A���̑��̌�F���ɂ����Ă����m�ɂ������t����ꂽ�B
�̂ɍȑт̎҂͎��R�Ǝ����̜p�j���v����Ȃ�A�����͎q���A�����͒�q�𐴑m�Ƃ��A
���͎�������Ȃǂ��Ă��̐g�͑މ@�������߁A���Ȃ����m����ƂȂ����B
�i�V���Ӂj
300�l�Ԏ����l�N
2022/07/20(��) 10:53:45.62ID:KcG7usJM �V���\�O�N�A�G�g���ɂ�鍪���U�߂̎��A�a��Ζx�ɂ����Ĕ��O�i�F�쑽�j���͌R���L��A
�������j�p�̌�A�G�g���͋I�B�G��䔭������A�����͒�����Ē����z�����U�߂�����Ƃ������A
���O�O�̒���̒炪�ꐅ�����o�����B���̂��ߏG�g���̌�@�������B
���L�O��i�Ɨ��j�͑�����O�֏o�āA
�u�����s�O�̂ɒ������Ă��܂����̂ł��B�\����ɁA�ؕ��d��܂��v
�Ɛ\���グ��Ƃ����܂��@������
�u���̂悤�Ȏ��͗L����̂��B���X�Ɛ��𗯂߂�悤�Ɂi�z�l�̎��n�L���Ȃ葁�X���𗯌�ցj
�Ƃ̏�ӂɂđ��ς݁A�����ɐl�v���|���Č��̂悤�ɒ�����B�����Ē��Ȃ�����ɋy�B
���̍��A�F�쑽�O�V�̂����ː�G���͕a�C�A���D��e�͊��Ɏ������Ă���A��낸���O��1�l�����m�����B
�i�ː�L�j
�������j�p�̌�A�G�g���͋I�B�G��䔭������A�����͒�����Ē����z�����U�߂�����Ƃ������A
���O�O�̒���̒炪�ꐅ�����o�����B���̂��ߏG�g���̌�@�������B
���L�O��i�Ɨ��j�͑�����O�֏o�āA
�u�����s�O�̂ɒ������Ă��܂����̂ł��B�\����ɁA�ؕ��d��܂��v
�Ɛ\���グ��Ƃ����܂��@������
�u���̂悤�Ȏ��͗L����̂��B���X�Ɛ��𗯂߂�悤�Ɂi�z�l�̎��n�L���Ȃ葁�X���𗯌�ցj
�Ƃ̏�ӂɂđ��ς݁A�����ɐl�v���|���Č��̂悤�ɒ�����B�����Ē��Ȃ�����ɋy�B
���̍��A�F�쑽�O�V�̂����ː�G���͕a�C�A���D��e�͊��Ɏ������Ă���A��낸���O��1�l�����m�����B
�i�ː�L�j
301�l�Ԏ����l�N
2022/07/20(��) 18:57:52.39ID:Cc8tVQvQ >>300
�����}�}�H���O�ł͂Ȃ��L�O�ł�
�����}�}�H���O�ł͂Ȃ��L�O�ł�
302�l�Ԏ����l�N
2022/07/20(��) 19:26:43.84ID:4JPgyvZJ303�l�Ԏ����l�N
2022/07/21(��) 09:59:35.90ID:5bLs7FaN304�l�Ԏ����l�N
2022/07/21(��) 12:17:30.20ID:hseXzmco305�l�Ԏ����l�N
2022/07/21(��) 14:25:21.15ID:9of599z4 ����ƍN�����]�{�i�]�ˁj�Ɍ�����̎��́A�钆�̉ƍ�͐\���ɋy���A��A�O�̊ہA�O�s�ɂ���Ƃ܂ł��A
��̏��ł��������R���̎��̂������Ɖ������̂܂c���Ă����̂ɁA�����͂����������p����ꂽ�B
�R��ǂ������ɂ͖؍하�i�����畘�j�̉Ƃ���ꌬ���Ȃ��A�F�����킬�A�b�B�킬�ȂǂŎ敘�ɒv���A
��䏊�͊������ŁA��L���͂������̂�����̊O�Â��A�䌺�ւ̏�̒i�ɂ́A�D�̕��L�̂��̂�
��i�ɏd�˂�����ɂāA�~�����疳�������B
�{�����n��i���M�j�͂�������āA�u���܂�Ɍ��ꂵ���A�������Q��ꂽ�g�҂ւ̊O�����@������
�v���܂��B�Ȃ̂Ō䌺�։��͑�������t������̂��R��ׂ��ł��B�v�ƌ��サ�����A�ƍN����
�u���̕��͗v�炴�闧�h���Ă�\���v
�ƌ���ɂȂ�A�ƍ�̎��ɂ͂��\���Ȃ��A�u�{�ۂƓ�̊ۂɗL��x�߂�ׂ��v�Ƌ��t�����A
�������������͖̂����������u����āA��ƒ��̑�g���g�Ɍ��炸�A�m�s�����}�����ꂽ�B
����s�ɂ͌�V���ł���匴�������i�N���j�A���̉��ɐR�����A�ɓߌF���A���̑��ڕ��O���������A
���A�䋌�̎l�����ɒu����Ă�����㊯�A������̖ʁX�ɁA���X�ɓ��n�ɔ��o�āA���邩����
�m�s����v���悤�ɂƋ��n���ꂽ�B
�A���m�s���̎d�l�́A���{���g�̖ʁX�ɂ͍]�˂ɋ߂��œn���A�m�s���ɉ����A���X�ɓ��̂艓������
�n���悤�ɁB�A��������锑��艓���Ŋ��{�ɒm�s��n�����͖��p�ł���A�Ƌ��t����ꂽ�B
���A��g�̏O�֏�n��������ꍇ�ɂ́A���蓖�Ă̊O�A�F�䎩�g�̎v�������ɂČ��킳�ꂽ�B
�i�V���Ӂj
�ƍN���]�ˏ�̐��������ƒ��̒m�s����̍�Ƃ�D�悳�����Ƃ������b�B
��̏��ł��������R���̎��̂������Ɖ������̂܂c���Ă����̂ɁA�����͂����������p����ꂽ�B
�R��ǂ������ɂ͖؍하�i�����畘�j�̉Ƃ���ꌬ���Ȃ��A�F�����킬�A�b�B�킬�ȂǂŎ敘�ɒv���A
��䏊�͊������ŁA��L���͂������̂�����̊O�Â��A�䌺�ւ̏�̒i�ɂ́A�D�̕��L�̂��̂�
��i�ɏd�˂�����ɂāA�~�����疳�������B
�{�����n��i���M�j�͂�������āA�u���܂�Ɍ��ꂵ���A�������Q��ꂽ�g�҂ւ̊O�����@������
�v���܂��B�Ȃ̂Ō䌺�։��͑�������t������̂��R��ׂ��ł��B�v�ƌ��サ�����A�ƍN����
�u���̕��͗v�炴�闧�h���Ă�\���v
�ƌ���ɂȂ�A�ƍ�̎��ɂ͂��\���Ȃ��A�u�{�ۂƓ�̊ۂɗL��x�߂�ׂ��v�Ƌ��t�����A
�������������͖̂����������u����āA��ƒ��̑�g���g�Ɍ��炸�A�m�s�����}�����ꂽ�B
����s�ɂ͌�V���ł���匴�������i�N���j�A���̉��ɐR�����A�ɓߌF���A���̑��ڕ��O���������A
���A�䋌�̎l�����ɒu����Ă�����㊯�A������̖ʁX�ɁA���X�ɓ��n�ɔ��o�āA���邩����
�m�s����v���悤�ɂƋ��n���ꂽ�B
�A���m�s���̎d�l�́A���{���g�̖ʁX�ɂ͍]�˂ɋ߂��œn���A�m�s���ɉ����A���X�ɓ��̂艓������
�n���悤�ɁB�A��������锑��艓���Ŋ��{�ɒm�s��n�����͖��p�ł���A�Ƌ��t����ꂽ�B
���A��g�̏O�֏�n��������ꍇ�ɂ́A���蓖�Ă̊O�A�F�䎩�g�̎v�������ɂČ��킳�ꂽ�B
�i�V���Ӂj
�ƍN���]�ˏ�̐��������ƒ��̒m�s����̍�Ƃ�D�悳�����Ƃ������b�B
306�l�Ԏ����l�N
2022/07/21(��) 17:56:51.06ID:ptp19eSq �G�g�ɑ���A�s�[�������������낤��
307�l�Ԏ����l�N
2022/07/22(��) 20:54:53.38ID:QhlJ9xR6 �ł���ŏ��Ɏj�������L���Ăق���
�ǂމ��l�����邩�ǂ��������邩��
�ʂɂ��̎j���̉��l�Ƃ����킯�ł͂Ȃ�
�ǂމ��l�����邩�ǂ��������邩��
�ʂɂ��̎j���̉��l�Ƃ����킯�ł͂Ȃ�
308�l�Ԏ����l�N
2022/07/22(��) 21:23:53.60ID:Mb780gem ���ʂɍŏ��ɖ�����������������̘b�ł́c
309�l�Ԏ����l�N
2022/07/23(�y) 08:12:27.03ID:zz2id93h �V���\��N�̍��́A�F�쑽�G�Ƃ���������A�Q�c�ɔC�����A��ʍ����Ƃ����A���V��������
���̊o���͏��l�ɈقȂ�A�V���̌䖹�i�G�g�̗{���E���P�̖��j�Ƃ��ĈА��ł�����ł������B
���̏d�b�͂��ꂼ����ɋl�߂����A���ł����L�O��i�Ɨ��j�͉F�쑽�Ƒ��̏h�V�ɂāA
�E���˒q�l�ɒ����A���ɗǐb�Ƃ̖����������B�a���i�G�g�j�̌�O�\���A��낷���Ɍ��サ���B
�̂ɉF�쑽�ƒ��ɁA�ނɈًc�������҂͂Ȃ������B
�ː����i�B���j�́A���L�O��ɑ����ĈА����݂����B
�L��Ă̖�A�a���̏G�Ɠ@�ւ̌䐬���������B����̒����ɂċ���������A���̎������ےÎ�i�s���j��
��O�ɍ݂��āA���N�̍���䔭�i�̌R�c�������B���̎��ː����͒����̘L���ɍT���Ă����B
�a���͔ނɌ䐺�������A�u����ɏo�ČR�c���悤�Ɂv�Ƌ������ꂽ���߁A�����Ɉ܂����B
�����ےÎ�͒��N�̂��Ƃ����Ɏ�Ɉ��邪�@���\���q�ׁA�a���̌�@���͎߂Ȃ炸�ł������B
��ՂɂȂ����~�֓����鎞�A�����ƍ��~�̊ԂɌÒ炪����ꏊ�œa����
�u���A�w�����悤�Ɂv�Ə�ӂ�����A���̂��ߔw������Ă����~�A�点�������B
���̂Ƃ��u���Ă������Ȃ�w�����l���ȁv�ƁA�����Ȃ���J�߂�ꂽ�Ƃ����B
�i�ː�L�j
�G�g�̉F�쑽�G�Ɠ@�䐬�Ǝ��̎��ɂ��āB
���̊o���͏��l�ɈقȂ�A�V���̌䖹�i�G�g�̗{���E���P�̖��j�Ƃ��ĈА��ł�����ł������B
���̏d�b�͂��ꂼ����ɋl�߂����A���ł����L�O��i�Ɨ��j�͉F�쑽�Ƒ��̏h�V�ɂāA
�E���˒q�l�ɒ����A���ɗǐb�Ƃ̖����������B�a���i�G�g�j�̌�O�\���A��낷���Ɍ��サ���B
�̂ɉF�쑽�ƒ��ɁA�ނɈًc�������҂͂Ȃ������B
�ː����i�B���j�́A���L�O��ɑ����ĈА����݂����B
�L��Ă̖�A�a���̏G�Ɠ@�ւ̌䐬���������B����̒����ɂċ���������A���̎������ےÎ�i�s���j��
��O�ɍ݂��āA���N�̍���䔭�i�̌R�c�������B���̎��ː����͒����̘L���ɍT���Ă����B
�a���͔ނɌ䐺�������A�u����ɏo�ČR�c���悤�Ɂv�Ƌ������ꂽ���߁A�����Ɉ܂����B
�����ےÎ�͒��N�̂��Ƃ����Ɏ�Ɉ��邪�@���\���q�ׁA�a���̌�@���͎߂Ȃ炸�ł������B
��ՂɂȂ����~�֓����鎞�A�����ƍ��~�̊ԂɌÒ炪����ꏊ�œa����
�u���A�w�����悤�Ɂv�Ə�ӂ�����A���̂��ߔw������Ă����~�A�点�������B
���̂Ƃ��u���Ă������Ȃ�w�����l���ȁv�ƁA�����Ȃ���J�߂�ꂽ�Ƃ����B
�i�ː�L�j
�G�g�̉F�쑽�G�Ɠ@�䐬�Ǝ��̎��ɂ��āB
310�l�Ԏ����l�N
2022/07/23(�y) 22:04:08.06ID:46b6DecW �u����G�ځv����m�b�ɓ����Ə����M�j�̘b
�]�ˑ�Ύ�(����̑��)�̐߁A��V��ɉ��ڂ�Ă��オ���Ă��܂����B
���̏������O�ɏo�悤�Ƃ������A�����킩�炸����Ăӂ��߂����B
����������ɓ���͌䌺�ւ��牜�܂ŏ����̓�������
�u��̂Ȃ��Ƃ���������ɏo����v�Ɛ\���ꂽ�Ƃ����B
�܂��ɓ����̎��A�G�����̌�@���ɐG�ꂽ���߁A�G�����ɏh��(�Ƃ̂�)�܂ɓ�����Ă��܂��A��������Ă��܂����B
�G�����͌��l(�])�̂��Ƃɑ܂�a���A���̂܂܌����ɏo�䂳�ꂽ�B
�ɓ���a�͑܂ɓ����Ă��ƂȂ������Ă������A���̂������ւ��������Ȃ������߁u�܂��J���Ă�������v�Ə����O���ĂB
���l�������O�����f���āu���R�l����Â��畕���Ȃ��ꂽ�̂ŁA�J���邱�Ƃ͂Ȃ�ʂ̂ł��B�ǂ����܂��傤�v�ƌ������B
�ɓ���́u�D���ڂ��قǂ��Ȃ����B���ꂪ�����o���Ȃ����āA���p���I�����̌�ɂ��ꂪ�������Č��̂悤�ɖD���Ȃ�������B�v
���̂��̖��Ă��Ƒ傢�ɂ�낱��ňɓ�����o�����B
�ɓ���͏��ւ��I���A�܂��܂̒��ɓ��낤�Ƃ����Ƃ���
���l�́u���R�l�����A��ɂȂ���܂ł͂��̂܂ܗV�ԂƂ悢�ł��傤�B�v
�Ƃ��َq�₻�̑����܂��܂ȕ�����������A���ɋ����ꂽ�B
�G�������A�邳�ꂽ���A�ɓ���͂܂��܂̒��ɓ���A�����O�͖D���ڂ����̂悤�ɖD�������B
�₪�āu���R�l��a���̂��̂���Ԃ����������v�ƌ�g�����������߁A�܂��G�����̌��ɖ߂����B
�G�����͑܂̒��̈ɓ����
�u���̕��A���㒉���ނ��H�v�Ƃ��q�˂ɂȂ��
�ɓ���������ꂢ���āu�����A���f�Ȃ����܂�܂��v�Ɛ\���グ���Ƃ���A�G�����͌��Â���܂��ɓ�����o���ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
�]�ˑ�Ύ�(����̑��)�̐߁A��V��ɉ��ڂ�Ă��オ���Ă��܂����B
���̏������O�ɏo�悤�Ƃ������A�����킩�炸����Ăӂ��߂����B
����������ɓ���͌䌺�ւ��牜�܂ŏ����̓�������
�u��̂Ȃ��Ƃ���������ɏo����v�Ɛ\���ꂽ�Ƃ����B
�܂��ɓ����̎��A�G�����̌�@���ɐG�ꂽ���߁A�G�����ɏh��(�Ƃ̂�)�܂ɓ�����Ă��܂��A��������Ă��܂����B
�G�����͌��l(�])�̂��Ƃɑ܂�a���A���̂܂܌����ɏo�䂳�ꂽ�B
�ɓ���a�͑܂ɓ����Ă��ƂȂ������Ă������A���̂������ւ��������Ȃ������߁u�܂��J���Ă�������v�Ə����O���ĂB
���l�������O�����f���āu���R�l����Â��畕���Ȃ��ꂽ�̂ŁA�J���邱�Ƃ͂Ȃ�ʂ̂ł��B�ǂ����܂��傤�v�ƌ������B
�ɓ���́u�D���ڂ��قǂ��Ȃ����B���ꂪ�����o���Ȃ����āA���p���I�����̌�ɂ��ꂪ�������Č��̂悤�ɖD���Ȃ�������B�v
���̂��̖��Ă��Ƒ傢�ɂ�낱��ňɓ�����o�����B
�ɓ���͏��ւ��I���A�܂��܂̒��ɓ��낤�Ƃ����Ƃ���
���l�́u���R�l�����A��ɂȂ���܂ł͂��̂܂ܗV�ԂƂ悢�ł��傤�B�v
�Ƃ��َq�₻�̑����܂��܂ȕ�����������A���ɋ����ꂽ�B
�G�������A�邳�ꂽ���A�ɓ���͂܂��܂̒��ɓ���A�����O�͖D���ڂ����̂悤�ɖD�������B
�₪�āu���R�l��a���̂��̂���Ԃ����������v�ƌ�g�����������߁A�܂��G�����̌��ɖ߂����B
�G�����͑܂̒��̈ɓ����
�u���̕��A���㒉���ނ��H�v�Ƃ��q�˂ɂȂ��
�ɓ���������ꂢ���āu�����A���f�Ȃ����܂�܂��v�Ɛ\���グ���Ƃ���A�G�����͌��Â���܂��ɓ�����o���ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
311�l�Ԏ����l�N
2022/07/24(��) 08:29:14.50ID:Hx8mz+Tr �ʑ܂�������
312�l�Ԏ����l�N
2022/07/25(��) 15:31:56.54ID:SpzzsYtk ����ƍN�����]�˂Ɍ��������A�����ɓ������������荞�݁A�F�X��V���Ă���Ƃ������ɂȂ�A
�u���̒��{����҂��A��l�����߂炦��悤�Ɂv�ƕ�s���ɋ��n���ꂽ�B
�����Ă��̍��A�֓��ɂ����Ė��������̓��ł���Α�Ƃ����҂�߂炦�A��������シ��ƁA
�ƍN���͂��̎҂���������悤���t�����A�u�ނ̓������ȂāA�����̓��������荞�܂Ȃ��悤�ɂ���v
�Ƌ��n���ꂽ�B
�Α�͂��������ƁA
�u�����䏕�������������Ƃ͗L���̂ł����A�����̓��l�����荞�܂ʂ悤�ɂƂ����̂́A
����l�̗͂ł͋y�ʂ��Ƃł��B�����ł����Ă������̂ŁA���~�n�������u�����A���͎艺�̎҂�
�ĂяW�߁A�����ɍ����u���A�ނ�ɐ\���t���ċᖡ��������ł��傤�A
�������A�艺�̎ҒB�����݂��~�߂Ă��܂��Ă͐g�߂����o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�ł��̂ŁA
���n�̌Ò������̌����߂���Ɖ�����A���̑��̎҂����~����܂��悤�ɁB�v
�Ƒ���������A�ƍN���͂��̋`���������͂����A�V���X�̋ߕӂ́A�꒬�l�����ь������~�n�Ƃ���
��������B�Α�͂�����J���A�Α̖��t���A���ƂɎ�藧�āA�艺�̎ҒB�ɌÒ������������A
���X�֏o���ċᖡ���������߁A���Ȃ����������荞�ނ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A����Ɍ��捂ɂȂ����B
�����ČÒ��������������~�݁A�Α����͕x�Ƃ����B
�i�V���Ӂj
����ƍN�������̓Α�r������藧�Ă����b
�u���̒��{����҂��A��l�����߂炦��悤�Ɂv�ƕ�s���ɋ��n���ꂽ�B
�����Ă��̍��A�֓��ɂ����Ė��������̓��ł���Α�Ƃ����҂�߂炦�A��������シ��ƁA
�ƍN���͂��̎҂���������悤���t�����A�u�ނ̓������ȂāA�����̓��������荞�܂Ȃ��悤�ɂ���v
�Ƌ��n���ꂽ�B
�Α�͂��������ƁA
�u�����䏕�������������Ƃ͗L���̂ł����A�����̓��l�����荞�܂ʂ悤�ɂƂ����̂́A
����l�̗͂ł͋y�ʂ��Ƃł��B�����ł����Ă������̂ŁA���~�n�������u�����A���͎艺�̎҂�
�ĂяW�߁A�����ɍ����u���A�ނ�ɐ\���t���ċᖡ��������ł��傤�A
�������A�艺�̎ҒB�����݂��~�߂Ă��܂��Ă͐g�߂����o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�ł��̂ŁA
���n�̌Ò������̌����߂���Ɖ�����A���̑��̎҂����~����܂��悤�ɁB�v
�Ƒ���������A�ƍN���͂��̋`���������͂����A�V���X�̋ߕӂ́A�꒬�l�����ь������~�n�Ƃ���
��������B�Α�͂�����J���A�Α̖��t���A���ƂɎ�藧�āA�艺�̎ҒB�ɌÒ������������A
���X�֏o���ċᖡ���������߁A���Ȃ����������荞�ނ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A����Ɍ��捂ɂȂ����B
�����ČÒ��������������~�݁A�Α����͕x�Ƃ����B
�i�V���Ӂj
����ƍN�������̓Α�r������藧�Ă����b
313�l�Ԏ����l�N
2022/07/26(��) 19:52:15.23ID:gT3YMaZZ �������q���v�����́A�����̒��ł���̊O�����킵���l���������B
���A���Ă��Č����������Ȃ��܂ܐH�������A�H���̒��ɍ�������ƌ����ė����l���n��������
�x�X�ł������B�肦���̎��e�����Ŋт��A���邭��Ɖċ��������Ƃ��������Ƃ��B
����ǂ��A�v���̊O�̎����������B
������A�����Ƃ̈��O���W�܂�������������A���d�����Ă��������̒������鉽�^�Ƃ������������A
����肻�̎����ɏo����Ă����َq���O���Ƃ����B
�����͂�������đ傢�ɓ{��A���̎҂������č��o�ē���������A�E��ɓ��������āA
�����̌҂��h�����B�����삵�����ꂽ���A�ނ͏������������A�n�߂̔@�����d�������B
���̏�ɂ����ҒB�͉���������̋C����m���Ă����̂ɁA�I�Ɏ��߂ɋy�Ԏ���ɂ��݁A�ނ�Иe�ւ�
�����ނ����A�u�\�������L��̂��H�v�Ɛq�˂Ă݂����̂́A����ɕ�������Ȃ��������߂ɁA���ɂ�
�u���̎q����҂��A�ǂ����Ď����َ̉q�𓐂ނ悤�Ȕڗ�Ȏ��𐬂����̂��B���O�̐g�����߂ƂȂ��Ă�
�d�����Ȃ��B�����Ď����Ă����Z��܂ł̖ʉ����ł��邼�I�v�ƌ������B
����Ə����͂������
�u�\���ׂ���������܂����A�l�̖������悤�Ȏ��ɂȂ�{�ӂł͂���܂���B
���̐l�̖����~���Ē�����̂Ȃ�A�e�ׂ����܂��B
���̖��́A�Ƃ�����ׂ��ł͂���܂���B���������̖��܂�Ƌ����鎖�̌��ɂ����ɁA
���̂悤�ɐ\���̂ł��B�v
������ĉ����������
�u���̕��̂��Ƃ͗͋y�Ȃ��ɂ��Ă��A���̎��ɂ��āA���̐l�̖��͉�X�̖��ɂ����ċ~���B�v
�Ɛ\�������߁A���̏����͌����
�u�ނ̐l���A�a�l�̌�ƒ��̎Ⴋ�҂Ȃ̂ł����A���ɗ����ł���A���\�ʂ̕������͎���܂����B
�����������a�l�̌�����������g�ł�����A���グ�Ă������܂���ł����B����ł��O���N�̊ԁA
���X�ɕ��𑗂��Ă���S�̐Ȃ������ŁA���鎞���̕��̓��e�����Ă��̎u�������A�v�킸�Ԏ���
������A���̎҂͂��悢��ς����ˁA���J�̗l�ɔς����ƕ����܂����B
�����̂��߂ɐl�̖��������Ă��܂����Ƃ̏Ύ~���ɁA�ǂ��ɂ����Ĉ�x���������Ǝv�����̂ł����A
�o�d���Ă���Ԃ͊O�̌�T�ɂ���A�A��Ί�荇�������ł��蒇�Ԃ̖ڂ��E�ѓ�A�������ɂ�
�Ȃ�Ƃ������ׂ��Ǝv���A���̒j��Ԋ��Ă֓��ꂳ���A����O�ɓ���܂����B
�R��ǂ��܈������A�O���O�ӂ̌�����ƂȂ�A�v�����Ȃ���ɁA���̎҂��Q���邱�Ƃ̒ɂ܂����ɁA
���َ̉q�Ȃ�Ƃ����킳��Ɖ����ɓ��ꂽ�̂ł����A�^���s����O�ɉ����ė��Ƃ��Ă��܂����̂ł��B
��킭�A���̊��Ă��������킸�ɉ����Ă��������B���͖���ɂ��ނ悤�Ȃ��Ƃ͂��܂���B�v
���̔y�͂�����āu�����ɑ����̏����̖���������Ƃ��Ă��B���m���Ē����Ȃ��̂�
�K��ł��낤�B�������ނ��َq�𓐂͔̂ڗ�Ȃ鏊�Ƃł͖����̂�����A���߂Ď���̒p�J��
�~����点��B�v�ƁA���̎n���𐳑��Ɍ�����B
�����͂�����Ƌ@������
�u�䂪���ɏ����g���҂قǂ����āA�ڗ�̋Ƃ͂Ȃ��Ȃ��������B������j�Ɉ������Ƃ����̂́A�䂪�ڂ�
�\���ɂ����Ă��邪�A���������ΐ[����߂�ׂ����Ƃł��Ȃ��B
���̏㍡���̗l�q�A���Ɏ��̖ڋ������Ȃ������Ɗ������B�ł���ȏ�A�ނ̎��߂��������B
�܂��ނɐS���������z���A���̋C����m������ŁA����Ɉ������Ƃ����Ƃ����̂́A�p�ɗ��ׂ���
�Ȃ̂��낤�B���̘���A�������j�̏��Ɍ��킷�悤�ɁB�v
�Ƃ��āA����Ȃ�ʋ@���ł������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�������Ƃ��ꂽ���������������ɂ��Ă͑�ڂɌ����Ƃ������b
���A���Ă��Č����������Ȃ��܂ܐH�������A�H���̒��ɍ�������ƌ����ė����l���n��������
�x�X�ł������B�肦���̎��e�����Ŋт��A���邭��Ɖċ��������Ƃ��������Ƃ��B
����ǂ��A�v���̊O�̎����������B
������A�����Ƃ̈��O���W�܂�������������A���d�����Ă��������̒������鉽�^�Ƃ������������A
����肻�̎����ɏo����Ă����َq���O���Ƃ����B
�����͂�������đ傢�ɓ{��A���̎҂������č��o�ē���������A�E��ɓ��������āA
�����̌҂��h�����B�����삵�����ꂽ���A�ނ͏������������A�n�߂̔@�����d�������B
���̏�ɂ����ҒB�͉���������̋C����m���Ă����̂ɁA�I�Ɏ��߂ɋy�Ԏ���ɂ��݁A�ނ�Иe�ւ�
�����ނ����A�u�\�������L��̂��H�v�Ɛq�˂Ă݂����̂́A����ɕ�������Ȃ��������߂ɁA���ɂ�
�u���̎q����҂��A�ǂ����Ď����َ̉q�𓐂ނ悤�Ȕڗ�Ȏ��𐬂����̂��B���O�̐g�����߂ƂȂ��Ă�
�d�����Ȃ��B�����Ď����Ă����Z��܂ł̖ʉ����ł��邼�I�v�ƌ������B
����Ə����͂������
�u�\���ׂ���������܂����A�l�̖������悤�Ȏ��ɂȂ�{�ӂł͂���܂���B
���̐l�̖����~���Ē�����̂Ȃ�A�e�ׂ����܂��B
���̖��́A�Ƃ�����ׂ��ł͂���܂���B���������̖��܂�Ƌ����鎖�̌��ɂ����ɁA
���̂悤�ɐ\���̂ł��B�v
������ĉ����������
�u���̕��̂��Ƃ͗͋y�Ȃ��ɂ��Ă��A���̎��ɂ��āA���̐l�̖��͉�X�̖��ɂ����ċ~���B�v
�Ɛ\�������߁A���̏����͌����
�u�ނ̐l���A�a�l�̌�ƒ��̎Ⴋ�҂Ȃ̂ł����A���ɗ����ł���A���\�ʂ̕������͎���܂����B
�����������a�l�̌�����������g�ł�����A���グ�Ă������܂���ł����B����ł��O���N�̊ԁA
���X�ɕ��𑗂��Ă���S�̐Ȃ������ŁA���鎞���̕��̓��e�����Ă��̎u�������A�v�킸�Ԏ���
������A���̎҂͂��悢��ς����ˁA���J�̗l�ɔς����ƕ����܂����B
�����̂��߂ɐl�̖��������Ă��܂����Ƃ̏Ύ~���ɁA�ǂ��ɂ����Ĉ�x���������Ǝv�����̂ł����A
�o�d���Ă���Ԃ͊O�̌�T�ɂ���A�A��Ί�荇�������ł��蒇�Ԃ̖ڂ��E�ѓ�A�������ɂ�
�Ȃ�Ƃ������ׂ��Ǝv���A���̒j��Ԋ��Ă֓��ꂳ���A����O�ɓ���܂����B
�R��ǂ��܈������A�O���O�ӂ̌�����ƂȂ�A�v�����Ȃ���ɁA���̎҂��Q���邱�Ƃ̒ɂ܂����ɁA
���َ̉q�Ȃ�Ƃ����킳��Ɖ����ɓ��ꂽ�̂ł����A�^���s����O�ɉ����ė��Ƃ��Ă��܂����̂ł��B
��킭�A���̊��Ă��������킸�ɉ����Ă��������B���͖���ɂ��ނ悤�Ȃ��Ƃ͂��܂���B�v
���̔y�͂�����āu�����ɑ����̏����̖���������Ƃ��Ă��B���m���Ē����Ȃ��̂�
�K��ł��낤�B�������ނ��َq�𓐂͔̂ڗ�Ȃ鏊�Ƃł͖����̂�����A���߂Ď���̒p�J��
�~����点��B�v�ƁA���̎n���𐳑��Ɍ�����B
�����͂�����Ƌ@������
�u�䂪���ɏ����g���҂قǂ����āA�ڗ�̋Ƃ͂Ȃ��Ȃ��������B������j�Ɉ������Ƃ����̂́A�䂪�ڂ�
�\���ɂ����Ă��邪�A���������ΐ[����߂�ׂ����Ƃł��Ȃ��B
���̏㍡���̗l�q�A���Ɏ��̖ڋ������Ȃ������Ɗ������B�ł���ȏ�A�ނ̎��߂��������B
�܂��ނɐS���������z���A���̋C����m������ŁA����Ɉ������Ƃ����Ƃ����̂́A�p�ɗ��ׂ���
�Ȃ̂��낤�B���̘���A�������j�̏��Ɍ��킷�悤�ɁB�v
�Ƃ��āA����Ȃ�ʋ@���ł������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�������Ƃ��ꂽ���������������ɂ��Ă͑�ڂɌ����Ƃ������b
314�l�Ԏ����l�N
2022/07/27(��) 17:22:09.39ID:nFfr9l0Y �`�����Ēj�������Ȃ��˂����ނ�w
315�l�Ԏ����l�N
2022/07/28(��) 19:29:03.99ID:gc6Jj94U �u����G�ځv���珼���M�j�ɂ���ˁE���˂̗D��
�]�ˏ��Ԃ̏O����ˉ��˂̗D���_�����������Ȃ������B
�����ɓ��炪�o���������ߌ�ԏO���f���Ăق����Ɨ��ނ�
�����M�j�u�e�X���A�q���ɋ����鎞�͑�������ނ悤�ɋ����܂����H�������܂Ȃ��悤�ɋ����܂����H�v
�e�X�u�������܂Ȃ��悤�ɂƋ����܂��v
�M�j�u���˂̏����ł��B�䂪�q�ւ̋��P�������^���ł��v
�ƒf�������߁A�ꓯ���������Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-6940.html
�����M�j�͑剺�˂ł������B�y�䗘���͑��˂ł�����
�����M�j�̉��˂ɂ��Ă͂���Șb��������
�]�ˏ��Ԃ̏O����ˉ��˂̗D���_�����������Ȃ������B
�����ɓ��炪�o���������ߌ�ԏO���f���Ăق����Ɨ��ނ�
�����M�j�u�e�X���A�q���ɋ����鎞�͑�������ނ悤�ɋ����܂����H�������܂Ȃ��悤�ɋ����܂����H�v
�e�X�u�������܂Ȃ��悤�ɂƋ����܂��v
�M�j�u���˂̏����ł��B�䂪�q�ւ̋��P�������^���ł��v
�ƒf�������߁A�ꓯ���������Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-6940.html
�����M�j�͑剺�˂ł������B�y�䗘���͑��˂ł�����
�����M�j�̉��˂ɂ��Ă͂���Șb��������
316�l�Ԏ����l�N
2022/07/29(��) 20:17:48.73ID:yuTGgqLc �ΐ�܉E�q��Ƃ��������́A�召���A���m�Q�Q�̓��A�����т��ڊy�̉c���ɕ������A
���Ȃɒu����Ă���d��̕A�����͉s���̗Ǔ����A�����̉����ɑウ�đт��ނ��o���B
���̂��߁A����ւ���ꂽ�ҒB�ŐS�Ȃ炸���Ď�̉�������A�����݂����ĕ���y�����ł������B
���̂悤�Ȓ��A���K���͍l���ʂ�A�䌺�ւɂē����]�҂Ɍ��킵�A�Z�������ʼnc���ɓo�����B
�O�l�͂��̍˒q��Q�����A����ɕ킢�A�F�Ə]�ɓ�����������悤�ɂȂ������߁A�ΐ�܉E�q���
��v���₦�āA���̌�c���ɕ�����鎖���Ȃ��Ȃ����B
�܂������肱�̎����m���ƂȂ����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
���Ȃɒu����Ă���d��̕A�����͉s���̗Ǔ����A�����̉����ɑウ�đт��ނ��o���B
���̂��߁A����ւ���ꂽ�ҒB�ŐS�Ȃ炸���Ď�̉�������A�����݂����ĕ���y�����ł������B
���̂悤�Ȓ��A���K���͍l���ʂ�A�䌺�ւɂē����]�҂Ɍ��킵�A�Z�������ʼnc���ɓo�����B
�O�l�͂��̍˒q��Q�����A����ɕ킢�A�F�Ə]�ɓ�����������悤�ɂȂ������߁A�ΐ�܉E�q���
��v���₦�āA���̌�c���ɕ�����鎖���Ȃ��Ȃ����B
�܂������肱�̎����m���ƂȂ����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
317�l�Ԏ����l�N
2022/07/31(��) 06:23:44.57ID:3C0fGes/ ���̍���������Č��t���������̂�
318�l�Ԏ����l�N
2022/07/31(��) 11:07:00.94ID:qVtjpT1C �Ď�Ə��A�m���Ƀp�b�ƌ��ԈႦ���
319�l�Ԏ����l�N
2022/07/31(��) 11:39:51.51ID:8dPSwZGb �����������t�H���g�T�C�Y�����Ƒ傫�����āI
320�l�Ԏ����l�N
2022/07/31(��) 13:17:46.76ID:0WzcNxCn ����I�ɖ��m�֖����킭��w
321�l�Ԏ����l�N
2022/07/31(��) 19:28:13.25ID:DXD36y8P �t�H���g�ł���
322�l�Ԏ����l�N
2022/08/01(��) 21:51:27.44ID:0y6b9poa �������n���i�Ö��j�̉Ƃł́A�V�ዤ�ɑт����Ō��Ԃ��Ƃ͖@�x�ł���A�O�̕��̘e��
���Ƃ����B����́A�}���̐܂ɂ͑т������邱�Ƃ����邪�A���ł͌��ѓ�A
�O�̘e�Ō��ԏꍇ�͑���Ȃ���ł����Ԏ��̂ł���̂ł���B
�܂��ƒ��̎m�ł����Ă��A����𒅂���ΐ��ɂ����Č��m�����̂ł���Ƃ��āA
�ƒ��S���̋���A�O�����܂ś����̊G�ɏ������A�n�шȉ��A���������ʂ悤��
�ɍʐF�ɕ`�����A���̐������L���A��Â̏钆�̍L�Ԃ̔ԏ���菑�@�܂ŁA���̛�����
���o�ɗ��Ēu���A���m���݂��ɂ��������m��悤�ɂ������B
���̂��߁A�����N�ł����Ă�����n���������A���ł����Ă��i�̑ւ�鎖������A
��l�܂ł����͂��A����ƊG�t�����̎m�̋��֍s���A�ڍׂɌ��͂��čőO�̊G�������������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
���Ƃ����B����́A�}���̐܂ɂ͑т������邱�Ƃ����邪�A���ł͌��ѓ�A
�O�̘e�Ō��ԏꍇ�͑���Ȃ���ł����Ԏ��̂ł���̂ł���B
�܂��ƒ��̎m�ł����Ă��A����𒅂���ΐ��ɂ����Č��m�����̂ł���Ƃ��āA
�ƒ��S���̋���A�O�����܂ś����̊G�ɏ������A�n�шȉ��A���������ʂ悤��
�ɍʐF�ɕ`�����A���̐������L���A��Â̏钆�̍L�Ԃ̔ԏ���菑�@�܂ŁA���̛�����
���o�ɗ��Ēu���A���m���݂��ɂ��������m��悤�ɂ������B
���̂��߁A�����N�ł����Ă�����n���������A���ł����Ă��i�̑ւ�鎖������A
��l�܂ł����͂��A����ƊG�t�����̎m�̋��֍s���A�ڍׂɌ��͂��čőO�̊G�������������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
323�l�Ԏ����l�N
2022/08/04(��) 21:03:34.37ID:yLplrfvZ �]�ˏ�̐Ί_�������A���A�n�璷��ɋ��t����ꂽ���A����͐[�D�ł��������߁A���
��ɕ~�����̂����A�����̔��ɂ����ĐΊ_�͕���Ă��܂����B
���̂��߁u���Ƃ̐g���Ȃ���ׂ��v�Ɛl�X�ɉ\���ꂽ�B
���̂��߁A�ɒ�ł���я������d�́A�Z����ɑ��Ă��̂悤�ɊЂ߂�
�u������s�ɂ��̐ӔC����点����点�A���V�ɒӂ����ׂ��ł��v
����������͂�����������Ȃ������B���d�͂��悢��Ђ߂����
�u��ׂ��v���Č����Ă���̂ɁA�p�����Ȃ��v
�ƍ��ސF���������B
����͒��d��@���Č�����
�u���́A��썶�q�卲�ɖ����ĕ����̖���Ƃ����B�����ĕ�����s�͍��q�卲�̉��m�����B
�ł���A�Ί_�̕��ꂽ���ɂ��āA���̍߂͕�����s��l�̂��̂ł͂Ȃ��B
�߂�����Ƃ���A�悸���ɋA���B���̎������q�卲�ł���B
�g�̓��邽�߂ɍ߂Ȃ��҂�U���鎖�͕s�`�ł���A���͂��������ɔE�тȂ��B
���̕��͂���ȐS�ł���̂Ɏ��́A�������ȂĒ�����ӂ��̂ł͂Ȃ����ƈ��B
�`�͏㉺�Ƃ��ɕ��m�̎�鏊�ł���B�`���̂Ăė������̂͏����̕��ł���B
���A���݂ɕ��m�ɑ��āu�����̕�����v�ƌ����A���̎҂͕K���{���Ĉ�����
�������Ƃ��A�P���~�܂�Ȃ����͓��ɂ���ĎE�����낤�B
���̖����O�ɒp���āA���̎�����ɏȂ݂�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�v
���̂悤�ɐ\���ƁA���d�͂���ɓ����錾�t�����������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
��ɕ~�����̂����A�����̔��ɂ����ĐΊ_�͕���Ă��܂����B
���̂��߁u���Ƃ̐g���Ȃ���ׂ��v�Ɛl�X�ɉ\���ꂽ�B
���̂��߁A�ɒ�ł���я������d�́A�Z����ɑ��Ă��̂悤�ɊЂ߂�
�u������s�ɂ��̐ӔC����点����点�A���V�ɒӂ����ׂ��ł��v
����������͂�����������Ȃ������B���d�͂��悢��Ђ߂����
�u��ׂ��v���Č����Ă���̂ɁA�p�����Ȃ��v
�ƍ��ސF���������B
����͒��d��@���Č�����
�u���́A��썶�q�卲�ɖ����ĕ����̖���Ƃ����B�����ĕ�����s�͍��q�卲�̉��m�����B
�ł���A�Ί_�̕��ꂽ���ɂ��āA���̍߂͕�����s��l�̂��̂ł͂Ȃ��B
�߂�����Ƃ���A�悸���ɋA���B���̎������q�卲�ł���B
�g�̓��邽�߂ɍ߂Ȃ��҂�U���鎖�͕s�`�ł���A���͂��������ɔE�тȂ��B
���̕��͂���ȐS�ł���̂Ɏ��́A�������ȂĒ�����ӂ��̂ł͂Ȃ����ƈ��B
�`�͏㉺�Ƃ��ɕ��m�̎�鏊�ł���B�`���̂Ăė������̂͏����̕��ł���B
���A���݂ɕ��m�ɑ��āu�����̕�����v�ƌ����A���̎҂͕K���{���Ĉ�����
�������Ƃ��A�P���~�܂�Ȃ����͓��ɂ���ĎE�����낤�B
���̖����O�ɒp���āA���̎�����ɏȂ݂�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�v
���̂悤�ɐ\���ƁA���d�͂���ɓ����錾�t�����������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
324�l�Ԏ����l�N
2022/08/06(�y) 16:33:25.99ID:AvbsJgaH >>242
https://twitter.com/Gunma_Rekihaku/status/1554260038104928256
https://pbs.twimg.com/media/FZHXKKOUYAEIHl-?format=jpg
�Q�n�������j������
@Gunma_Rekihaku
�y���̊��o��?�z
�݂Ȃ���A���҂������܂���??�{��(8/2)���A���悢��@#���]���� (�Ȃ������˂�)�̂�����u����̊��̓W���X�^�[�g�ł�??
��������㐙�_�ЈȊO�œW�������̂������߂ł��̂ŁA���̋M�d�ȋ@��ɂ��Ў������ԋ߂ł���������??
#�퍑��B�̓����ƍb�h
Translate Tweet
9:17 AM �E Aug 2, 2022
������ƈȏ�ɗ��s�A�O�o�������T�����邲�����ł����A400�N�Ԃ�̗��A��ł���܂��̂ʼn\�ȕ��͂��C����������������ł��Ђ��K�₭�������B
�Ȃ��������œ��̂̊Z���Ȃ��̂́A����͂܂����R���E�E�E
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/Gunma_Rekihaku/status/1554260038104928256
https://pbs.twimg.com/media/FZHXKKOUYAEIHl-?format=jpg
�Q�n�������j������
@Gunma_Rekihaku
�y���̊��o��?�z
�݂Ȃ���A���҂������܂���??�{��(8/2)���A���悢��@#���]���� (�Ȃ������˂�)�̂�����u����̊��̓W���X�^�[�g�ł�??
��������㐙�_�ЈȊO�œW�������̂������߂ł��̂ŁA���̋M�d�ȋ@��ɂ��Ў������ԋ߂ł���������??
#�퍑��B�̓����ƍb�h
Translate Tweet
9:17 AM �E Aug 2, 2022
������ƈȏ�ɗ��s�A�O�o�������T�����邲�����ł����A400�N�Ԃ�̗��A��ł���܂��̂ʼn\�ȕ��͂��C����������������ł��Ђ��K�₭�������B
�Ȃ��������œ��̂̊Z���Ȃ��̂́A����͂܂����R���E�E�E
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
325�l�Ԏ����l�N
2022/08/07(��) 08:49:32.09ID:SlSuzWww ���D���ȉċx�݃L�b�Y�i�Ɛe�䂳��j�������為�ЌQ�n�܂ŖK��Ăق�����ł����A�̂̂܂Ƃ߂�
���̊��ɖ{�����̃y�[�p�[�N���t�g���Љ��Ă����悤�ł��̂ŁA�H��̏h�肪�Ă�{��������
�s���Ă݂܂��H
�R�`���đ�s�퍑�����ƕđ�s�̊ό����
�������y�[�p�[�N���t�g�����_�E�����[�h
http://www.yonezawa-naoe.com/information/080813.html
http://www.yonezawa-naoe.com/images/information/naoe_Ver2.0_yoko.jpg
http://www.yonezawa-naoe.com/images/information/honjou3.jpg
�R�`�s�ŏ�`�����j��
�_�E�����[�h�y�[�p�[�N���t�g
http://mogamiyoshiaki.jp/?p=list&c=1858
�G�k�E��m�J�`���̎��Ȃǂɂ���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-3719.html
�y�G�k�z��������O�ɏo�Ă��V���O���̃y�[�p�[�N���t�g
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-9442.html
���̊��ɖ{�����̃y�[�p�[�N���t�g���Љ��Ă����悤�ł��̂ŁA�H��̏h�肪�Ă�{��������
�s���Ă݂܂��H
�R�`���đ�s�퍑�����ƕđ�s�̊ό����
�������y�[�p�[�N���t�g�����_�E�����[�h
http://www.yonezawa-naoe.com/information/080813.html
http://www.yonezawa-naoe.com/images/information/naoe_Ver2.0_yoko.jpg
http://www.yonezawa-naoe.com/images/information/honjou3.jpg
�R�`�s�ŏ�`�����j��
�_�E�����[�h�y�[�p�[�N���t�g
http://mogamiyoshiaki.jp/?p=list&c=1858
�G�k�E��m�J�`���̎��Ȃǂɂ���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-3719.html
�y�G�k�z��������O�ɏo�Ă��V���O���̃y�[�p�[�N���t�g
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-9442.html
326�l�Ԏ����l�N
2022/08/07(��) 08:52:10.41ID:BryXnE1d �������[
327�l�Ԏ����l�N
2022/08/07(��) 21:43:22.51ID:SY5vKsav �L�b�G�g�������c���i���̎��ɁA�ɒB�����琭�@�i���̎��͍�����v�Ə̂��j�͎Q�w�����������ŁA
�G�g���͐r���{�苋��ꂽ�̂��A���@�����ď��c���w�Ɏ���A�����ꎁ�ɕt����
�u���ꂪ���͊֔��a�̌�剺�ɁA�K���n���q���ׂ��ؖڂ͂Ȃ��B����ɂ���ē������A���a�����Ă������A
�k�����łт���ɁA���B�䔭�������Ƃ����������������B
�R��ɉ����ẮA�K��h��͊낤���Ƒ��������߁A�����p���Œy���Q�����A
�́A������������t�L��̒x�Q���߂�ꂽ�悤�Ȍ�C�F���L��͖̂��f�ł���I�v
���̂悤�Ɍ��������A�G�g���͌��������
�u���@�͂���̘ԂȂ�҂Ȃ�B�v�ƁA���̍߂�Ƃ���ꂽ�B
�R��ɂ��̔N�̓~�A���B��˂ɈꝄ���N����A���@�����̖��������Ă���Ƃ̕����������������߁A
�G�g���͐��@�����܂�A�}���㗌���ׂ��Ƃ̋����������B
���@�͂��������ƁA�u���قǂ̎҂����ɂ����鎞�A���X�̂��̂ł͌��ɂ����B�v
�ƁA����ɂđ�������������^����Ɏ������ď㋞�����B
���̍��G�g���͕����̏�n�����ċ���ꂽ�̂����A���@�̏㗌���������ɂȂ��āA�u�����֗���悤�Ɂv
�Ƌ���ꂽ�B���̂��ߕ����ɎQ������ƁA�䑤�ɏ�����A���̓��g���Ă������i�����͐�q�j�ɂāA
���@�̎����������
�u���̕����㗌���Ȃ������ꍇ�́A���悤�ɐ\���t���悤�Ǝv���Ă������A���₩�ɒy�オ�������
�����Ƃ���Ȃ�B�v�Ƌ��ɂȂ����B
���@�͈܂��āA��O��ޏo�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�G�g���͐r���{�苋��ꂽ�̂��A���@�����ď��c���w�Ɏ���A�����ꎁ�ɕt����
�u���ꂪ���͊֔��a�̌�剺�ɁA�K���n���q���ׂ��ؖڂ͂Ȃ��B����ɂ���ē������A���a�����Ă������A
�k�����łт���ɁA���B�䔭�������Ƃ����������������B
�R��ɉ����ẮA�K��h��͊낤���Ƒ��������߁A�����p���Œy���Q�����A
�́A������������t�L��̒x�Q���߂�ꂽ�悤�Ȍ�C�F���L��͖̂��f�ł���I�v
���̂悤�Ɍ��������A�G�g���͌��������
�u���@�͂���̘ԂȂ�҂Ȃ�B�v�ƁA���̍߂�Ƃ���ꂽ�B
�R��ɂ��̔N�̓~�A���B��˂ɈꝄ���N����A���@�����̖��������Ă���Ƃ̕����������������߁A
�G�g���͐��@�����܂�A�}���㗌���ׂ��Ƃ̋����������B
���@�͂��������ƁA�u���قǂ̎҂����ɂ����鎞�A���X�̂��̂ł͌��ɂ����B�v
�ƁA����ɂđ�������������^����Ɏ������ď㋞�����B
���̍��G�g���͕����̏�n�����ċ���ꂽ�̂����A���@�̏㗌���������ɂȂ��āA�u�����֗���悤�Ɂv
�Ƌ���ꂽ�B���̂��ߕ����ɎQ������ƁA�䑤�ɏ�����A���̓��g���Ă������i�����͐�q�j�ɂāA
���@�̎����������
�u���̕����㗌���Ȃ������ꍇ�́A���悤�ɐ\���t���悤�Ǝv���Ă������A���₩�ɒy�オ�������
�����Ƃ���Ȃ�B�v�Ƌ��ɂȂ����B
���@�͈܂��āA��O��ޏo�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
328�l�Ԏ����l�N
2022/08/08(��) 02:29:08.03ID:cS6asV3w ����
���������̘b�͖k�𐪔��̎��̎��Ǝv���Ă����LjႤ���̘b�������̂�
���������̘b�͖k�𐪔��̎��̎��Ǝv���Ă����LjႤ���̘b�������̂�
329�l�Ԏ����l�N
2022/08/08(��) 17:15:20.67ID:7WahujQv >>324
����厖�ȓ_�́A�㐙�_�Еa�̓W���P�[�X�͕Ǎۂɂ���̂ŁA���ʓI�ɐ^���ʂ��炵�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���
����̂悤�ɒ����ɓW���P�[�X�������Đ^��납������w�ł���@��͓�x�ƂȂ����Ă��Ƃł�
����厖�ȓ_�́A�㐙�_�Еa�̓W���P�[�X�͕Ǎۂɂ���̂ŁA���ʓI�ɐ^���ʂ��炵�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���
����̂悤�ɒ����ɓW���P�[�X�������Đ^��납������w�ł���@��͓�x�ƂȂ����Ă��Ƃł�
330�l�Ԏ����l�N
2022/08/09(��) 21:33:24.95ID:OpEL8oi0 �փ����̌�w�́A�i������j����G�H�̗��肪����A��J�Y���i�g�p�j�������Ŗ��ʂāA
���̑��̏�����͑�����ƂȂ��Ĉɐ��R�̕��֔s�������B���Â̈��݂͔̂�����������C����
�����ނ����B���Ƃ̗��l���A����𗊂�ő����čs�����҂́A���܂Ŗ����Ɉ������҂����������Ƃ����B
����i�ː�B���j�͉����Ö��̐��ɉ����A��������i�Γc�O���j�w�ɔ������B
����ƐΓc�Ƃ̎ҘZ�A���\�R�����j��ꓯ�ɓˏo�����B����ɉÖ����͍��E�ɊJ��������݁A
��l���������ł��E�����B
���̎�̑y�O�͂��̑��ɔ����āA���������̎҂�����ΑłƂ��ƁA���ɂ����͓������āA���̑���
���Ō������Ă����B���Ƃ̏O�͂�������āA�u���Ă������Ȃ铢���l���ȁv�Ə̔������B
�O���͌R�]�c�̂��߂ɑ��̔����ɍs�����܂܂ŁA�䂪�w�ɋA�邱�Ƃ��o�����s�������B
�Ö��̐��Ɛ킢�a�������叫�́A�����߂ł���Ƃ����B
�փ����̖v����A���a�R�̏���j��ꂽ�B���̎�����������ƈꓯ�ɏ�荞�B
�����ĉƐb�̗^�E�q�傪����������Ĕ���֍����o�����B���̗^�E�q��͍��n��̐킢�ɉ����Ă�
�������������B�̂ɂ��̊��͗^�E�q��ɗ^����ꂽ�B
���̊��͌�X�܂Ŋݖ{�Ƃ̉ƕ�ƂȂ����B
�i�ː�L�j
�ː�L�Ɍ�����փ�������̖͗l
���̑��̏�����͑�����ƂȂ��Ĉɐ��R�̕��֔s�������B���Â̈��݂͔̂�����������C����
�����ނ����B���Ƃ̗��l���A����𗊂�ő����čs�����҂́A���܂Ŗ����Ɉ������҂����������Ƃ����B
����i�ː�B���j�͉����Ö��̐��ɉ����A��������i�Γc�O���j�w�ɔ������B
����ƐΓc�Ƃ̎ҘZ�A���\�R�����j��ꓯ�ɓˏo�����B����ɉÖ����͍��E�ɊJ��������݁A
��l���������ł��E�����B
���̎�̑y�O�͂��̑��ɔ����āA���������̎҂�����ΑłƂ��ƁA���ɂ����͓������āA���̑���
���Ō������Ă����B���Ƃ̏O�͂�������āA�u���Ă������Ȃ铢���l���ȁv�Ə̔������B
�O���͌R�]�c�̂��߂ɑ��̔����ɍs�����܂܂ŁA�䂪�w�ɋA�邱�Ƃ��o�����s�������B
�Ö��̐��Ɛ킢�a�������叫�́A�����߂ł���Ƃ����B
�փ����̖v����A���a�R�̏���j��ꂽ�B���̎�����������ƈꓯ�ɏ�荞�B
�����ĉƐb�̗^�E�q�傪����������Ĕ���֍����o�����B���̗^�E�q��͍��n��̐킢�ɉ����Ă�
�������������B�̂ɂ��̊��͗^�E�q��ɗ^����ꂽ�B
���̊��͌�X�܂Ŋݖ{�Ƃ̉ƕ�ƂȂ����B
�i�ː�L�j
�ː�L�Ɍ�����փ�������̖͗l
331�l�Ԏ����l�N
2022/08/10(��) 10:50:59.00ID:LosKS1LF ���ɑ̂̐Γc�w�ɋl�ߊ��w�^�����ł���w
332�l�Ԏ����l�N
2022/08/11(��) 20:20:05.19ID:n/mKMT7Y �փ����̐킢�̌��ʁA���[���i������j�G�H�͔��O����q�̂̌�A���R�ɍݏ邵�ĈЂ�k���A
�חW�̗̎��̂�ɂ��A�̋��Y�ꂽ�悤�ɐU�镑�����B���̂��߁A�������փ����̌�A
�����됣�O����̂�������̂Ɛڂ�������i�ː�B���j�Ƃ̊W���X�����͖��������B
���̂悤�Ȓ��A������G�H�Ƃ��̏d�b�̊Ԃ̊W���������A��������Ƃ𗧂��ނ����B
���̗��l�̓��A��t�������́A����𗊂��ĂЂƂ܂��됣�܂ŗ����ނ����Ɨ~�����B
���̎��������������āA������̂ƒ됣�̋��ɖx���ċ����|���A��ؓ���p�ӂ��A���
�h��̎x�x�������B���̓����́A�F�쑽�Q�l�̖��̗L��ҒB�����X�ɎU�݂��Ă���A�ނ�ɑ�
����͍��͒v���u���Ă������߁A�����Ƃ������͔ނ炪�됣�ɒy�W�܂�͂��ŁA�����Ȃ��
���염���̐l���ōU�߂������Ă��e�Ղɂ͎��ׂ���邱�Ƃ������ƌ������B
���āA��t�����������ނ������Ɏ���A������r�c�s�E�q��A�X�O�Y�E�q��Ƃ����������l�ɁA
���y�\�l��t���āA���ڂ̏�����̐�ɂ��锒�Ƃ������܂ŏo�}����t��������삵�A�됣�ւ�
�A�����B�����͎g�҂��Ȃ�
�u�i�X�̌�蓖��z�Ȃ������܂��B�����Y��邱�Ƃ͂���܂���B����\�����̖����Ȃ�
������������́A�����蒼�ɗ����ނ��܂��B�v
�Ǝӗ炵���B�����Ĕ���͒����܂ŏo�Ėʉ�A�݂��Ɏ��炵�ė����ʂꂽ�B
�����͎������È���D�ɏ���ď���֓o�����B
���̌�A������G�H��������֎���ꂪ�����āA
�u�ߗׂ̎��ł�����A���ɏh�V�̎��A��낸���݂���𑶂���v�|��\���z�����B
�̂ɁA�Ȍ�͔����������Ƃɏo���肷��悤�ɂȂ�A�됣�ɏG�H�������҂������A
�G�H���卶�����̓��𑗂��A���炩��͒ʓV�ƍ������x�n�𑗂����B����͊փ�����
����ŗp�����n�ŁA���ނ̏x���ł��������̂�i�サ���B������͂��悢�捧�ӂɂȂ�A
����͒�̌ː�吅���G�H�����킵�A�ނ͔��O�ɋ��Z�����B
���Ȃ��A�G�H�͐������ĉƂ͒f�₵�A���̌�ɂ͒r�c�P�����������ꂽ�B�r�c�ƂƂ͎�ɏ]�����
���ӂł������̂ŁA�חW�ƂȂ��āA���悢��悵�݁A�e�����Ȃ����B
�i�ː�L�j
�חW�̗̎��̂�ɂ��A�̋��Y�ꂽ�悤�ɐU�镑�����B���̂��߁A�������փ����̌�A
�����됣�O����̂�������̂Ɛڂ�������i�ː�B���j�Ƃ̊W���X�����͖��������B
���̂悤�Ȓ��A������G�H�Ƃ��̏d�b�̊Ԃ̊W���������A��������Ƃ𗧂��ނ����B
���̗��l�̓��A��t�������́A����𗊂��ĂЂƂ܂��됣�܂ŗ����ނ����Ɨ~�����B
���̎��������������āA������̂ƒ됣�̋��ɖx���ċ����|���A��ؓ���p�ӂ��A���
�h��̎x�x�������B���̓����́A�F�쑽�Q�l�̖��̗L��ҒB�����X�ɎU�݂��Ă���A�ނ�ɑ�
����͍��͒v���u���Ă������߁A�����Ƃ������͔ނ炪�됣�ɒy�W�܂�͂��ŁA�����Ȃ��
���염���̐l���ōU�߂������Ă��e�Ղɂ͎��ׂ���邱�Ƃ������ƌ������B
���āA��t�����������ނ������Ɏ���A������r�c�s�E�q��A�X�O�Y�E�q��Ƃ����������l�ɁA
���y�\�l��t���āA���ڂ̏�����̐�ɂ��锒�Ƃ������܂ŏo�}����t��������삵�A�됣�ւ�
�A�����B�����͎g�҂��Ȃ�
�u�i�X�̌�蓖��z�Ȃ������܂��B�����Y��邱�Ƃ͂���܂���B����\�����̖����Ȃ�
������������́A�����蒼�ɗ����ނ��܂��B�v
�Ǝӗ炵���B�����Ĕ���͒����܂ŏo�Ėʉ�A�݂��Ɏ��炵�ė����ʂꂽ�B
�����͎������È���D�ɏ���ď���֓o�����B
���̌�A������G�H��������֎���ꂪ�����āA
�u�ߗׂ̎��ł�����A���ɏh�V�̎��A��낸���݂���𑶂���v�|��\���z�����B
�̂ɁA�Ȍ�͔����������Ƃɏo���肷��悤�ɂȂ�A�됣�ɏG�H�������҂������A
�G�H���卶�����̓��𑗂��A���炩��͒ʓV�ƍ������x�n�𑗂����B����͊փ�����
����ŗp�����n�ŁA���ނ̏x���ł��������̂�i�サ���B������͂��悢�捧�ӂɂȂ�A
����͒�̌ː�吅���G�H�����킵�A�ނ͔��O�ɋ��Z�����B
���Ȃ��A�G�H�͐������ĉƂ͒f�₵�A���̌�ɂ͒r�c�P�����������ꂽ�B�r�c�ƂƂ͎�ɏ]�����
���ӂł������̂ŁA�חW�ƂȂ��āA���悢��悵�݁A�e�����Ȃ����B
�i�ː�L�j
333�l�Ԏ����l�N
2022/08/13(�y) 13:59:41.39ID:CU8pX0Nu �c���\��N�A����d���ɂČ��ƂȂ�A�Ћˎs���i�����j�͂��̏��̂ł����ɗ����Ă��������A
�������̌R�����ł��ׂ��Ƃ̕������p��ł������B
���̍��A����i�ː�B���j�͏x�{����ɂ�����A�ݏ��A��r���A���s�ɗ�����菊�i���
�q�ɉ��i���d�j�̋��֎Q���������A�ɉ��͂��̂悤�Ɍ�����B
�u�Ћˎs������ɍ݂�̂ł����A����肱����U�߂�悤�ł��B�����ő����A�Ћ˂ւ�
��������Â��Ă���Ƃ���ł��B�v
�����������͎����̂���芸����
�u���͒ʏ�̗��s�̂Ɉ�w�l�������Ȃ��̂ł����A�������璼�ɉ����ɍs���܂��傤�B�v
�ɉ��͑傢�Ɋ��S���āu���͔�B�a�A���Ȃ����䉇����������A������F�ƂȂ�ł��傤�B�v��
�\�������߁A���̏��蒼�ɔ���͈���������B�����ĕЋˎs���ƑΖʂ��A���ꂱ����o�܂�
�q�ׂ�ƁA�s���͑傢�ɗ͂āA����̐��厛�Ƃ����ꏊ�ɔ����u�����A
���炪�h�w���l�C�ܓ��ؗ����鏊�ɁA�����ł͈�؍U�߂ɂ��Ĉ٘_���o�A���̏���炪
�����ɗ������Ȃǂ������āA��؍U�߂͗e�ՂȂ炸�Ƃ̕]�肪����A���̎��͒��~�Ƃ���A���̕\��
�����ƂȂ����B����̂ɂЂƂ܂�������ݏ��A�����B
�i�ː�L�j
�ː�B���Ƒ��~�̐w�ɂ������؍U�߂ɂ���
�������̌R�����ł��ׂ��Ƃ̕������p��ł������B
���̍��A����i�ː�B���j�͏x�{����ɂ�����A�ݏ��A��r���A���s�ɗ�����菊�i���
�q�ɉ��i���d�j�̋��֎Q���������A�ɉ��͂��̂悤�Ɍ�����B
�u�Ћˎs������ɍ݂�̂ł����A����肱����U�߂�悤�ł��B�����ő����A�Ћ˂ւ�
��������Â��Ă���Ƃ���ł��B�v
�����������͎����̂���芸����
�u���͒ʏ�̗��s�̂Ɉ�w�l�������Ȃ��̂ł����A�������璼�ɉ����ɍs���܂��傤�B�v
�ɉ��͑傢�Ɋ��S���āu���͔�B�a�A���Ȃ����䉇����������A������F�ƂȂ�ł��傤�B�v��
�\�������߁A���̏��蒼�ɔ���͈���������B�����ĕЋˎs���ƑΖʂ��A���ꂱ����o�܂�
�q�ׂ�ƁA�s���͑傢�ɗ͂āA����̐��厛�Ƃ����ꏊ�ɔ����u�����A
���炪�h�w���l�C�ܓ��ؗ����鏊�ɁA�����ł͈�؍U�߂ɂ��Ĉ٘_���o�A���̏���炪
�����ɗ������Ȃǂ������āA��؍U�߂͗e�ՂȂ炸�Ƃ̕]�肪����A���̎��͒��~�Ƃ���A���̕\��
�����ƂȂ����B����̂ɂЂƂ܂�������ݏ��A�����B
�i�ː�L�j
�ː�B���Ƒ��~�̐w�ɂ������؍U�߂ɂ���
334�l�Ԏ����l�N
2022/08/13(�y) 14:13:22.08ID:jdX5Fg+t ���J����炩�܂��ł��傤�E�E
��͂茻�݂ł��e�n�ŋ��ˎ�ƂƂ̂��t���������đ����Ă�̂�
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/6341.html
�đ�s�c��c�����۔�
11��22�� �㐙�T���l�@��ߑ��l�̌�a�����j�i
��͂茻�݂ł��e�n�ŋ��ˎ�ƂƂ̂��t���������đ����Ă�̂�
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/6341.html
�đ�s�c��c�����۔�
11��22�� �㐙�T���l�@��ߑ��l�̌�a�����j�i
335�l�Ԏ����l�N
2022/08/14(��) 13:44:08.53ID:pKpwmqpE ���B���v��̐�ɁA�������l���i�����j�͏\���ł��������A�G�R�ɏ�荞�݊�������A
�ƍN���̌䗗�ɓ�����
�u���͗E�m�Ȃ�B���{�̕��ǂ��B�悸��������B�v
�Ƌ��ɂȂ������߁A��n�̐�ɂ����đ����p���ł����B
�Ƃ��낪��肪�G�R��焈Ղ��Ă���̂����āA�삯�o�����Ƃ������A�n�悪�D�������
�u���Ɍ����𐋂����܂����A�R���G�̒��ɓ��薽��S�����͉̂��̉v������ł��傤���I�v
�ƌ������B
������������͑傢�ɓ{��n���l�������������Ȃ��������߁A�����ĕ��ł����A
�u�������Â��`�������̂����m�̓����I�H�����̐�́A�G�j��w���ׂ�A�����鏊��ǂ��l�߂����
�~�ނ��̂��B�����m��ʎ��ɐg���ڂ݂鎖�ȂǏo���Ȃ��I�v
�������ڑł��Ă��l���Ă��A�n��͗P�������Ȃ������B
���̎��ƍN���͎O�\�Ԃ���u�Ă��ꏊ�ł���������ɂȂ��Ă������A
�u���������ߌ��˂Ă���B�s�m�̎��킷�ׂ����͂������I�������̎u�ɔC����I�v
�Ƌ��ɂȂ�ƁA�n�悱�̎��D��������B
�����͐^�ꕶ���ɏ�����A�܂�������l���āA������y���A������p�������߂�
�u�N���ԋ߂Ői�ލ������䗗�ɂȂ��Ă���̂ɁA�����Ȃ�����������A��̉��̖ʖڂ�������
��l�ɂ܂݂���̂��I�H�v
�����̂��̌��t�ɗ�܂���āA�����F�������҂����݂Ƃǂ܂�A�i�ގ҂͂��悢��E�B
�������āA���̔N�̕�A���������ɂ͍����O�\�l���a����ꂽ�B
�ƍN���́A�u�����̒��v��̓����́A�R���̎m�ɂ����Ȃ��v�ƁA�������ɂȂ�ꂽ�B
����Ƃɂ����ď\���ɂ��ď��ƂȂ����̂́A������l����ł���Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�ƍN���̌䗗�ɓ�����
�u���͗E�m�Ȃ�B���{�̕��ǂ��B�悸��������B�v
�Ƌ��ɂȂ������߁A��n�̐�ɂ����đ����p���ł����B
�Ƃ��낪��肪�G�R��焈Ղ��Ă���̂����āA�삯�o�����Ƃ������A�n�悪�D�������
�u���Ɍ����𐋂����܂����A�R���G�̒��ɓ��薽��S�����͉̂��̉v������ł��傤���I�v
�ƌ������B
������������͑傢�ɓ{��n���l�������������Ȃ��������߁A�����ĕ��ł����A
�u�������Â��`�������̂����m�̓����I�H�����̐�́A�G�j��w���ׂ�A�����鏊��ǂ��l�߂����
�~�ނ��̂��B�����m��ʎ��ɐg���ڂ݂鎖�ȂǏo���Ȃ��I�v
�������ڑł��Ă��l���Ă��A�n��͗P�������Ȃ������B
���̎��ƍN���͎O�\�Ԃ���u�Ă��ꏊ�ł���������ɂȂ��Ă������A
�u���������ߌ��˂Ă���B�s�m�̎��킷�ׂ����͂������I�������̎u�ɔC����I�v
�Ƌ��ɂȂ�ƁA�n�悱�̎��D��������B
�����͐^�ꕶ���ɏ�����A�܂�������l���āA������y���A������p�������߂�
�u�N���ԋ߂Ői�ލ������䗗�ɂȂ��Ă���̂ɁA�����Ȃ�����������A��̉��̖ʖڂ�������
��l�ɂ܂݂���̂��I�H�v
�����̂��̌��t�ɗ�܂���āA�����F�������҂����݂Ƃǂ܂�A�i�ގ҂͂��悢��E�B
�������āA���̔N�̕�A���������ɂ͍����O�\�l���a����ꂽ�B
�ƍN���́A�u�����̒��v��̓����́A�R���̎m�ɂ����Ȃ��v�ƁA�������ɂȂ�ꂽ�B
����Ƃɂ����ď\���ɂ��ď��ƂȂ����̂́A������l����ł���Ƃ����B
�i�V���Ӂj
336�l�Ԏ����l�N
2022/08/14(��) 17:34:46.37ID:siE1lCzG337�l�Ԏ����l�N
2022/08/16(��) 18:36:12.91ID:3gjOkIHM �c����\�N�i���a���N�j�A�����i����ƍN�E�G���j�͐������Ɍ�A�{���ꂽ���A���Ȃ����Ƃ�
��a�r�j��A���O���A��w�߂�����A���₩�ɏo�w���ׂ��Ƃ̗R�ɂāA�l���A���喼��������֓o��A
���䏊���l�����㗌���ꂽ�B
�����I�Ɏ炪����Ԃ����t�����A����i�ː�B���j��тɔ����g�͎c�炸�����Ԃ����t�����A
�e�X�����ɋl�ߔԏ����\���A���������߂��B
�܌��n�߁A������a����艟���l�߁B�����A�������A����ɐw�����B�܌��Z���A������o�n���ꍇ�킪�n�܂�A
�����������O���i���������B����͂�����₢�Ȃ�A���ŏ����{����������Ɛ\���f���āA
�Ԗ[�����q�i�E�G�j�Ɛ\�����킹�ēV�����\�֒y�����B
���������̓r���ɂđ��������ɉ��|����A�䏟���ƂȂ����B
�����Œ��P�R�̌�{�w�֎Q�サ�A�o���@��̎掟�ɂĉƍN���Ɍ�ڌ����\���グ���B
����͂��̎����Ɂu���̌�Ԃ����t�����܂������A����{�ɂ��ĐS���ƂȂ��v���A���Q
�d��܂����B�v�Ɛ\���グ��ƁA��ӂɁu���̓��v�Ƌ��ɂȂ��A��@���ǂ������B
���āA�Ԗ[�����q�i���̎��Z�\�Z�j�͉��Ă��������낳��Ĕ���̑��ɍ݂����B
�u�Ԗ[�����q���Q�サ�Ă��܂��B�v�Ɣ��炪��I�\���グ��ƁA��䏊�͂����ɂȂ�
�u���A�Ⴋ�����R�D�́A�����[�ɂĂ��o�w�A����ł���I�v�Ƃ̌�ӂ��������B
���l�������Č�O��ނ��ƁA�����q�͔����q���
�u���A���̌䌾�t���������A�ɌN�̂������ł���A���X���X�Y��Ȃ��B
�V��̖ʖځA����������ɓ��������낤���I�v
�����A��ςɊ�B
�����������i�G���j�̊x�R�{�w�֎Q�サ��ڌ����d��A���ւƋA�����B
����̒�ł���ː�吅�͌���{�ɍ݂������A�匴���Y���q�卲�i���ˎ�j�ƈꏏ�ɑ���֏�荞�݁A
���̌��܂Ŏ��������ŁA����ɉ������ē��邱�Ɗ��킸�A���̎��𒆎R����R�Ɋm�F���Ă��炢�A
��Ɍ���{�䌟�c�̎��A���R���ؐl�ɗ������B
�i�ː�L�j
��a�r�j��A���O���A��w�߂�����A���₩�ɏo�w���ׂ��Ƃ̗R�ɂāA�l���A���喼��������֓o��A
���䏊���l�����㗌���ꂽ�B
�����I�Ɏ炪����Ԃ����t�����A����i�ː�B���j��тɔ����g�͎c�炸�����Ԃ����t�����A
�e�X�����ɋl�ߔԏ����\���A���������߂��B
�܌��n�߁A������a����艟���l�߁B�����A�������A����ɐw�����B�܌��Z���A������o�n���ꍇ�킪�n�܂�A
�����������O���i���������B����͂�����₢�Ȃ�A���ŏ����{����������Ɛ\���f���āA
�Ԗ[�����q�i�E�G�j�Ɛ\�����킹�ēV�����\�֒y�����B
���������̓r���ɂđ��������ɉ��|����A�䏟���ƂȂ����B
�����Œ��P�R�̌�{�w�֎Q�サ�A�o���@��̎掟�ɂĉƍN���Ɍ�ڌ����\���グ���B
����͂��̎����Ɂu���̌�Ԃ����t�����܂������A����{�ɂ��ĐS���ƂȂ��v���A���Q
�d��܂����B�v�Ɛ\���グ��ƁA��ӂɁu���̓��v�Ƌ��ɂȂ��A��@���ǂ������B
���āA�Ԗ[�����q�i���̎��Z�\�Z�j�͉��Ă��������낳��Ĕ���̑��ɍ݂����B
�u�Ԗ[�����q���Q�サ�Ă��܂��B�v�Ɣ��炪��I�\���グ��ƁA��䏊�͂����ɂȂ�
�u���A�Ⴋ�����R�D�́A�����[�ɂĂ��o�w�A����ł���I�v�Ƃ̌�ӂ��������B
���l�������Č�O��ނ��ƁA�����q�͔����q���
�u���A���̌䌾�t���������A�ɌN�̂������ł���A���X���X�Y��Ȃ��B
�V��̖ʖځA����������ɓ��������낤���I�v
�����A��ςɊ�B
�����������i�G���j�̊x�R�{�w�֎Q�サ��ڌ����d��A���ւƋA�����B
����̒�ł���ː�吅�͌���{�ɍ݂������A�匴���Y���q�卲�i���ˎ�j�ƈꏏ�ɑ���֏�荞�݁A
���̌��܂Ŏ��������ŁA����ɉ������ē��邱�Ɗ��킸�A���̎��𒆎R����R�Ɋm�F���Ă��炢�A
��Ɍ���{�䌟�c�̎��A���R���ؐl�ɗ������B
�i�ː�L�j
338�l�Ԏ����l�N
2022/08/17(��) 20:55:57.03ID:tN2INKCJ �א�̗H�ցA���鎞�i�����j�Дb�̏��ɂ��q�˂ɂȂ������A���x�Дb�͒������Ă���A���̖���
�点���Ă����B�H�ւ͂�������āA�u�����ɏДb�����Ɂv�ƁA��A�O�x�A�l�A�ܓx�N�����ꂽ���B
�����グ�Ă͂܂��Q�A�����グ�Ă͂��ǂ��ǂƂ��Ă������A�ڂ��o�߂��ނ��ނ��Ƃ��Ă����̂ŁA
�i�ڂ��o���ނ��T�T�Ƃ��Ă��ꂽ��n�j
�ނ���ނ���Ɓ@�����܂�������@�H��
�����
����������@����Ƃ����炸�@��ւɂ˂ā@�Дb
���̂悤�Ɍ����ċN����ꂽ�B
�i��������M�L�j
�D�����ĐQ�Ă��Ă����̋��ǂނƙ�l�ɖڂ��o�܂��ċ���p�������藬�Α�\�I�A�̎t
�点���Ă����B�H�ւ͂�������āA�u�����ɏДb�����Ɂv�ƁA��A�O�x�A�l�A�ܓx�N�����ꂽ���B
�����グ�Ă͂܂��Q�A�����グ�Ă͂��ǂ��ǂƂ��Ă������A�ڂ��o�߂��ނ��ނ��Ƃ��Ă����̂ŁA
�i�ڂ��o���ނ��T�T�Ƃ��Ă��ꂽ��n�j
�ނ���ނ���Ɓ@�����܂�������@�H��
�����
����������@����Ƃ����炸�@��ւɂ˂ā@�Дb
���̂悤�Ɍ����ċN����ꂽ�B
�i��������M�L�j
�D�����ĐQ�Ă��Ă����̋��ǂނƙ�l�ɖڂ��o�܂��ċ���p�������藬�Α�\�I�A�̎t
339�l�Ԏ����l�N
2022/08/18(��) 21:35:36.85ID:u/CgpXqt >>338
�{���T�h�u���ꂪ�{���̃l�^�t���v
�{���T�h�u���ꂪ�{���̃l�^�t���v
340�l�Ԏ����l�N
2022/08/23(��) 20:27:55.74ID:JgZITNRM ������Z�A���\�N�O�̂��Ƃ����A�����Ƃ����o�~�̏��ƕ��������҂��������B
�O�D�C�����v�i���c�j�a�̏��ł̌��̔��ɁA�o�~�̔�����䏊�]�Ȃ��ꂽ�B
���x���̎��A�C�����v�a�̌�O�ɋ����킹���l�X�͊F�����ł���A�䑭�̂͑��v�a����ł������B
�܂��A���̍��͏\���ł������̂ŁA���̂܂�
�w�����~���@�݂�͑嗪�_�����x�@����
����ɑ�
�w�ЂƂ肵����̌ÉG�X�q���āx�@���v�a���c���b
�i��������M�L�j
�O�D�C�����v�i���c�j�a�̏��ł̌��̔��ɁA�o�~�̔�����䏊�]�Ȃ��ꂽ�B
���x���̎��A�C�����v�a�̌�O�ɋ����킹���l�X�͊F�����ł���A�䑭�̂͑��v�a����ł������B
�܂��A���̍��͏\���ł������̂ŁA���̂܂�
�w�����~���@�݂�͑嗪�_�����x�@����
����ɑ�
�w�ЂƂ肵����̌ÉG�X�q���āx�@���v�a���c���b
�i��������M�L�j
341�l�Ԏ����l�N
2022/08/27(�y) 18:28:50.89ID:nJHAYYUM ���a��N�l���\�����A���Ƒ匠�����䑼�E���ꂽ���ƂŁA�x�{�l�߂̖ʁX�͊F�]�˂ւƋA�����B
���ܔN�āA�䓿�@�a�i����G���j��㗌����A�����ɂ����ĕ������q��i�����j�̗̍���
�����グ�鎞�A���̉ƘV�ł��镟���O�g�������n�������ےv�����̂ɁA�����l���̑喼��
�|�B�L���֔������邱�ƂƂȂ�A�����Δn��i�d�M�j�A�i��E�ߑ��v�i�����j�A�ː����i�B���j��
�O��s�Ƃ��ďo�w�����B�ނ�ɑ��Ē����l���̗�A���h���邱�Ǝ߂Ȃ�ʂ��̂ł������B
�������A�����A�i��͏��R�Ɲ፧�̉ƕ��ł���̂ł�������ȂA����͊O�l�̐g���ł���Ȃ���
���̌�p��ւ邱�ƁA�S�����̕����Ɋ����̂ł������B
���̎��A�������n��i�Ö��j�ɐ�N�����t����ꂽ�̂����A�Ö���
�u�����͍ݍ����Ă��炸�A�����͉Ɨ�����Ȃ̂ł�����A����l�ł��ł��ׂ����Ƃ͗e�Ղ̎��ł��B�v
�Ɛ\���グ���B
�����̎��͕����ɂ����ċ��t�����A���ƒi�X�ɍL���։����l�߁A�d�˂Ă̌䉺�m��҂��Ă������A
�������Ԗ[�u������g���Ƃ��č]�˂Ɍ��킵�A�]�˂̕��������ɋ����킳�ꂽ���A�����͐S�����āA
��Ȃ��䐿���\���グ�����n���悤�ɁA�Ƃ���ؕ��𐳑��̎��M�ɂčL�����킵���B
�����O�g�͂�������āA�u�R���́v�ƂĖ����ɏ��n�����B
�����͉z���孋����A�l�����������ꂽ�B
�i�ː�L�j
�����������Ղɂ��Ă̌ː�L�̋L��
���ܔN�āA�䓿�@�a�i����G���j��㗌����A�����ɂ����ĕ������q��i�����j�̗̍���
�����グ�鎞�A���̉ƘV�ł��镟���O�g�������n�������ےv�����̂ɁA�����l���̑喼��
�|�B�L���֔������邱�ƂƂȂ�A�����Δn��i�d�M�j�A�i��E�ߑ��v�i�����j�A�ː����i�B���j��
�O��s�Ƃ��ďo�w�����B�ނ�ɑ��Ē����l���̗�A���h���邱�Ǝ߂Ȃ�ʂ��̂ł������B
�������A�����A�i��͏��R�Ɲ፧�̉ƕ��ł���̂ł�������ȂA����͊O�l�̐g���ł���Ȃ���
���̌�p��ւ邱�ƁA�S�����̕����Ɋ����̂ł������B
���̎��A�������n��i�Ö��j�ɐ�N�����t����ꂽ�̂����A�Ö���
�u�����͍ݍ����Ă��炸�A�����͉Ɨ�����Ȃ̂ł�����A����l�ł��ł��ׂ����Ƃ͗e�Ղ̎��ł��B�v
�Ɛ\���グ���B
�����̎��͕����ɂ����ċ��t�����A���ƒi�X�ɍL���։����l�߁A�d�˂Ă̌䉺�m��҂��Ă������A
�������Ԗ[�u������g���Ƃ��č]�˂Ɍ��킵�A�]�˂̕��������ɋ����킳�ꂽ���A�����͐S�����āA
��Ȃ��䐿���\���グ�����n���悤�ɁA�Ƃ���ؕ��𐳑��̎��M�ɂčL�����킵���B
�����O�g�͂�������āA�u�R���́v�ƂĖ����ɏ��n�����B
�����͉z���孋����A�l�����������ꂽ�B
�i�ː�L�j
�����������Ղɂ��Ă̌ː�L�̋L��
342�l�Ԏ����l�N
2022/08/28(��) 13:29:50.38ID:yhd8x8KM �]�ˏ�A����ۂ̊O�x��ٌc�x�ƌĂԂ̂́A�c���ܔN�A�փ�������̌�ɁA����O�ł͓������ՁA
�֓��O�ł͈ɒB���@�̗��l������ƂȂ�A�]�˂ɉ��~�n��q�̎d�肽���|�����ꂽ�B
�ƍN���͂����������A�u�e�X���ɉ��~�L��A���n�ɂĂ͖��p�̎��Ȃ�B�v�Ƌ��ɂȂ�ꂽ���̂́A
�����Ċ��ꂽ���߂ɁA�O���c�ӂ�i���̑喼���H�̏ꏊ�ł���j�ɂāA���������̑喼�A�����������n�߁A
���c�A�瓇�A�ї��A���ÁA�ɒB�A�㐙�A���A�암�A�T��A��A���n�A���J�A�H�c�A�y���A���̑��̏O
�i�O�c�͖F�t�@�]�ˉ����̎��A�G������������ɉ����ĉ�����Ă����B�܂����K���͒e��������
�旧���āA���c�����ւƂ�������q�̂����̂ɁA������㉮�~�ƂȂ��A�V���e���B�����Ɏd�肽����
��������߂ɁA�ʂɉ��~�������ꂽ�Ƃ����j
�䓖�Ɓi����Ɓj�ւ̌����n�߂Ƃ��āA�����̏���ɂ��ł����݂̌�x�������s��ꂽ�B
����͓����̕����V�ƌ�����S�ōs�����̂ŁA���X�͂��̖x���u�ٌc�x�v�Ɛ\���K�킵���B
���̍��A��x�͂悤�₭���\�ԁi��18���[�g���j���܂�ł������̂����A���~�q�̂̏������
�肢���ȂāA�x�̓y��g�����X�ֈ����A�n�グ�ɗp�������߁A����̂悤�Ɍ�x���L���Ȃ�A
����[���Ȃ����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�֓��O�ł͈ɒB���@�̗��l������ƂȂ�A�]�˂ɉ��~�n��q�̎d�肽���|�����ꂽ�B
�ƍN���͂����������A�u�e�X���ɉ��~�L��A���n�ɂĂ͖��p�̎��Ȃ�B�v�Ƌ��ɂȂ�ꂽ���̂́A
�����Ċ��ꂽ���߂ɁA�O���c�ӂ�i���̑喼���H�̏ꏊ�ł���j�ɂāA���������̑喼�A�����������n�߁A
���c�A�瓇�A�ї��A���ÁA�ɒB�A�㐙�A���A�암�A�T��A��A���n�A���J�A�H�c�A�y���A���̑��̏O
�i�O�c�͖F�t�@�]�ˉ����̎��A�G������������ɉ����ĉ�����Ă����B�܂����K���͒e��������
�旧���āA���c�����ւƂ�������q�̂����̂ɁA������㉮�~�ƂȂ��A�V���e���B�����Ɏd�肽����
��������߂ɁA�ʂɉ��~�������ꂽ�Ƃ����j
�䓖�Ɓi����Ɓj�ւ̌����n�߂Ƃ��āA�����̏���ɂ��ł����݂̌�x�������s��ꂽ�B
����͓����̕����V�ƌ�����S�ōs�����̂ŁA���X�͂��̖x���u�ٌc�x�v�Ɛ\���K�킵���B
���̍��A��x�͂悤�₭���\�ԁi��18���[�g���j���܂�ł������̂����A���~�q�̂̏������
�肢���ȂāA�x�̓y��g�����X�ֈ����A�n�グ�ɗp�������߁A����̂悤�Ɍ�x���L���Ȃ�A
����[���Ȃ����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
343�l�Ԏ����l�N
2022/08/30(��) 07:51:04.79ID:rNXzoC2O �q���h��i�d�@�j���]�˂ɉ������ꂽ���A�����ɓ���M�j�����̂悤�Ɍ�����
�u��l�i����ƌ��j�ɂ��A�i�X�Ɛ����Ɍ�S��s������Ă��܂��B����̂��Ƃ��e�ׂ�
�����Ă݂����v���Ă�����悤�ŁA����͒��ԂɌ��킳��鏑��ɂ��A������
��O�������A����̎����㕷�����悤�ɂȂ���ׂ��ł��傤�B�v
�i�d�@�͉������̌�@�����f���A����ɓ�����ɕʋV�Ȃ��V������������Ƃ����j
��������h���
�u�������S��\���u�ĂĂ���ȏ�A��l���ǂ�قnj䔭���ł����Ă��A���̏��͋y�э��ɂȂ�A
�䑶���ꖳ���V�ƂȂ�܂��B���̂��߂ɐَ҂������u����Ă���̂ł��B�ł��̂ŁA
�\���グ��ɂ͋y���鎖�Ƒ������܂��B�v
�ƌ�����
���̎����ƌ����͕���������A�u���h��́A�g�ݍ���ŋ�҂ł���B�v�ƁB
�䊴�x�߂Ȃ炸�ł������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�u��l�i����ƌ��j�ɂ��A�i�X�Ɛ����Ɍ�S��s������Ă��܂��B����̂��Ƃ��e�ׂ�
�����Ă݂����v���Ă�����悤�ŁA����͒��ԂɌ��킳��鏑��ɂ��A������
��O�������A����̎����㕷�����悤�ɂȂ���ׂ��ł��傤�B�v
�i�d�@�͉������̌�@�����f���A����ɓ�����ɕʋV�Ȃ��V������������Ƃ����j
��������h���
�u�������S��\���u�ĂĂ���ȏ�A��l���ǂ�قnj䔭���ł����Ă��A���̏��͋y�э��ɂȂ�A
�䑶���ꖳ���V�ƂȂ�܂��B���̂��߂ɐَ҂������u����Ă���̂ł��B�ł��̂ŁA
�\���グ��ɂ͋y���鎖�Ƒ������܂��B�v
�ƌ�����
���̎����ƌ����͕���������A�u���h��́A�g�ݍ���ŋ�҂ł���B�v�ƁB
�䊴�x�߂Ȃ炸�ł������Ƃ����B
�i�V���Ӂj
344�l�Ԏ����l�N
2022/08/31(��) 13:47:28.43ID:9t7KSC9U ���͓�����(���͔V��)�͌I�R��V��ƂƂ��ɍ��c���V�̉ƘV�Ƃ��Đ��ɗ�l���ł��邪�A���̎Ⴂ���̘b
�����傪�܂��쏕�ƌ����Ă����\�Z�̎��A�̓��̕S���̔n�������˂��E���Ă��܂����B
�n��́u����ɕُ�������ׂ��ł��v
����́u���傪�s�݂̊Ԃɋ����������Ƃł��B�{���̂������Ƃł��̂ŋ���̐ӔC�ł͂���܂���v
�ƌ݂��ɐ��|�_�ƂȂ�A�����ƂȂ������������Ȃ��������߂Ƃ��Ƃ����c�����̎��ɂ܂ŒB����
�����́u�ǂ����������Ƃ��ł���̂ŁA�n���S��̒l�ł���Ȃ甼�l�̌\�悾�����傪�ُ����Ă͂ǂ����H�v
�ƍْ肳�ꂽ�̂ŁA���҂Ƃ��s���Ɏv�������̂̏a�X�A���Ă������B
������Ă����쏕�͕��y�O�ɑ��āu���̂��т̔����͗�����킫�܂��ʔ����ł���v�ƌ������B
���y�O�u���X�̕����Ȃ��ꂽ���f�ł���̂ɉ����������H�v
�쏕�u�����n�傪����n���q���ł����ԂɋN�����A�Ƃ��邪�q�������ԂɑO�オ����͂��ł���B
���͑���Ɍ������ē˂��̂��K���Ȃ̂ŁA��Ōq����������ɐӔC������ƌ����悤�v
����������y�O�͎��ł��Ď]�Q���A���ꂪ�]���ƂȂ蒷���̎��ɒB�����B
�����ʼn��߂Ĕn��A�������������ƁA��ɔn�傪�q���A��ŋ��傪�q�������Ƃ����������B
�������ċ���͑S�z�S���n��ɕ������ƂƂȂ�A�n��͓��R��B
����͍ŏ��̔������\�摽���������ƂɂȂ������̂́A���x�͗������ʂ��Ă������߁A�[�����ċA�邱�ƂƂȂ����B
�������Ē����͊쏕���u��̐l���ł͂Ȃ��v�ƔF�߁A�\���̍�����]��O�ɓ���A���̂̂����͓`�E�q��̗{�q�Ƃ��Ė��������Ɖ��߂������B
�����̂��璉�V�̑�܂ŁA���ł���Γ�A�O�\�l�ł�����悤�Ȏd�u����������l�ɔC�������A�ォ�����������ꌾ�����o�Ȃ�����
�o�T:�|�������E���c�ח��Z���u�����ˏ����ƘV�@���͓�����V���u���͓����V�唶�o���ʑS�v��ǂށv
�����傪�܂��쏕�ƌ����Ă����\�Z�̎��A�̓��̕S���̔n�������˂��E���Ă��܂����B
�n��́u����ɕُ�������ׂ��ł��v
����́u���傪�s�݂̊Ԃɋ����������Ƃł��B�{���̂������Ƃł��̂ŋ���̐ӔC�ł͂���܂���v
�ƌ݂��ɐ��|�_�ƂȂ�A�����ƂȂ������������Ȃ��������߂Ƃ��Ƃ����c�����̎��ɂ܂ŒB����
�����́u�ǂ����������Ƃ��ł���̂ŁA�n���S��̒l�ł���Ȃ甼�l�̌\�悾�����傪�ُ����Ă͂ǂ����H�v
�ƍْ肳�ꂽ�̂ŁA���҂Ƃ��s���Ɏv�������̂̏a�X�A���Ă������B
������Ă����쏕�͕��y�O�ɑ��āu���̂��т̔����͗�����킫�܂��ʔ����ł���v�ƌ������B
���y�O�u���X�̕����Ȃ��ꂽ���f�ł���̂ɉ����������H�v
�쏕�u�����n�傪����n���q���ł����ԂɋN�����A�Ƃ��邪�q�������ԂɑO�オ����͂��ł���B
���͑���Ɍ������ē˂��̂��K���Ȃ̂ŁA��Ōq����������ɐӔC������ƌ����悤�v
����������y�O�͎��ł��Ď]�Q���A���ꂪ�]���ƂȂ蒷���̎��ɒB�����B
�����ʼn��߂Ĕn��A�������������ƁA��ɔn�傪�q���A��ŋ��傪�q�������Ƃ����������B
�������ċ���͑S�z�S���n��ɕ������ƂƂȂ�A�n��͓��R��B
����͍ŏ��̔������\�摽���������ƂɂȂ������̂́A���x�͗������ʂ��Ă������߁A�[�����ċA�邱�ƂƂȂ����B
�������Ē����͊쏕���u��̐l���ł͂Ȃ��v�ƔF�߁A�\���̍�����]��O�ɓ���A���̂̂����͓`�E�q��̗{�q�Ƃ��Ė��������Ɖ��߂������B
�����̂��璉�V�̑�܂ŁA���ł���Γ�A�O�\�l�ł�����悤�Ȏd�u����������l�ɔC�������A�ォ�����������ꌾ�����o�Ȃ�����
�o�T:�|�������E���c�ח��Z���u�����ˏ����ƘV�@���͓�����V���u���͓����V�唶�o���ʑS�v��ǂށv
345�l�Ԏ����l�N
2022/08/31(��) 22:27:09.19ID:ulBDHuFY �i���q�E���v�����̒��j���x�A�G�g�͖k�ɐ��ɏo�n���A�G�邪�ꃖ������Εt��𐔑����点���B
���̂悤�ȏ��ɁA�O��a�i�D�c�M�Y�j���̍��]�ɂ��a�����������A�O�Y�a���́A���̉���a�Ƃ����҂�
�l���Ƃ��ďo�����Ƃ����B�Óc���������l�����o�����B
����ƍN����͎��q�i���j���`�ہj�A�d�b�ł���ΐ씌�ˎ���l���Ƃ��Ď��q�����ɏo�����B
�����ĎO��a�ƏG�g�͉���A�G�g��莆�q��A����\���A�k�ɐ��Ꝅ���̂Ă����Ƃ����u���Ă������́A
�ܐ�U�����̂܂O��a�i�サ���B���̉�̂Ƃ��A�e�����̚��s�ƁA���̕���U���O��a�i�サ�A
���q�̖��������Ƃ����B
�ƍN�ɂ��āA�G�g�͑������c���Ă���Ƃ��āA�����Ƃ������ɂ��Ă͓��S�����������A�O��a���
�l�X�Ɍ䍧�]�����������߂ɁA�ƍN�ɂ��Ă��͖ƂƂȂ����Ƃ����B
�����\�ܓ��ɁA�ƍN�͎O�B�ɋA�������B
�i�F��吅�L�j
���q���v��̍u�a�ɂ��āB
���̂悤�ȏ��ɁA�O��a�i�D�c�M�Y�j���̍��]�ɂ��a�����������A�O�Y�a���́A���̉���a�Ƃ����҂�
�l���Ƃ��ďo�����Ƃ����B�Óc���������l�����o�����B
����ƍN����͎��q�i���j���`�ہj�A�d�b�ł���ΐ씌�ˎ���l���Ƃ��Ď��q�����ɏo�����B
�����ĎO��a�ƏG�g�͉���A�G�g��莆�q��A����\���A�k�ɐ��Ꝅ���̂Ă����Ƃ����u���Ă������́A
�ܐ�U�����̂܂O��a�i�サ���B���̉�̂Ƃ��A�e�����̚��s�ƁA���̕���U���O��a�i�サ�A
���q�̖��������Ƃ����B
�ƍN�ɂ��āA�G�g�͑������c���Ă���Ƃ��āA�����Ƃ������ɂ��Ă͓��S�����������A�O��a���
�l�X�Ɍ䍧�]�����������߂ɁA�ƍN�ɂ��Ă��͖ƂƂȂ����Ƃ����B
�����\�ܓ��ɁA�ƍN�͎O�B�ɋA�������B
�i�F��吅�L�j
���q���v��̍u�a�ɂ��āB
346�l�Ԏ����l�N
2022/09/01(��) 15:30:45.48ID:ugOBGEFV �u���͓����V�唶�o���ʑS�v����сu�Ë�����v���u�����a��(������)�v
���͓�����(���͔V��)������ɏ�����܂ɓr���̐��˂ł��傤�Ǐ������������̂ŁA�D���⎘�O�́u��X�̓��a�ł��ȁv�Ɗ�B
������������͂܂��������
�u���̑D�͂悢���A����̑D�ɂƂ��Ă͌��������ł���A�}���ł���҂�����ł��낤�̂ɓ�V�Ȃ��Ƃł���B
���҂ɂ�����҂ɂ��D�ł̉������ǂ��Ȃ���u�悫���a�v�ƌ����邾�낤���v�ƌ������B
���̂̂��d����ŏ㉺�̑D�Ƃ����邱�Ƃ��ł��镗�����������߁A���ꂱ�����u�����a���v���ƌ����������B
���̂̂����˂̎҂ǂ��͂�����A�������������Ǝv���A�㉺���ɔ����悤�ȕ������ł��u�����a���v���ƌ����Ă��邻���ł���B
�܂��������̌��������ł���A�l�X�ɑ��čD���̏�������Ƃ��Ȃ��A�����ɍl����l�ł������B
���͓�����(���͔V��)������ɏ�����܂ɓr���̐��˂ł��傤�Ǐ������������̂ŁA�D���⎘�O�́u��X�̓��a�ł��ȁv�Ɗ�B
������������͂܂��������
�u���̑D�͂悢���A����̑D�ɂƂ��Ă͌��������ł���A�}���ł���҂�����ł��낤�̂ɓ�V�Ȃ��Ƃł���B
���҂ɂ�����҂ɂ��D�ł̉������ǂ��Ȃ���u�悫���a�v�ƌ����邾�낤���v�ƌ������B
���̂̂��d����ŏ㉺�̑D�Ƃ����邱�Ƃ��ł��镗�����������߁A���ꂱ�����u�����a���v���ƌ����������B
���̂̂����˂̎҂ǂ��͂�����A�������������Ǝv���A�㉺���ɔ����悤�ȕ������ł��u�����a���v���ƌ����Ă��邻���ł���B
�܂��������̌��������ł���A�l�X�ɑ��čD���̏�������Ƃ��Ȃ��A�����ɍl����l�ł������B
347�l�Ԏ����l�N
2022/09/02(��) 16:09:09.81ID:AsvhKVAq �u���͓����V�唶�o���ʑS�v���珬�͏��(���͔V���̒��q)�̎����Ă����G(������)�̘b
���͏�͂��܂������Z�݂ō����ƌ����Ă������A�G�������ւ�������Ă����B
�Ă��J�����G���o���ƕ������щ��A��������������o�����̎�ɗ��܂�قǎ������炵�Ă����B
������A����������̎��ɂ����̏����������G�����~�ɏo���ėV��ł����Ƃ���A�L�����A����o�Ă��ĐH���Ă��܂����B
�����͒Z�C�ł��������߁A�A���Ă�����ǂ��Ȃ邾�낤�Ƌ���A�܂�������ɂ��Ƃ̎�����������B
������u�Ύ~�Ȃ��Ƃ��������̂��A��������������Ђǂ�������ł��낤�B
�܂��͒��ɍs���G����H�����Ă��Ă����Ăɓ����v�ƌ�����
���������́u�����������l�Ƃ����ǁA���̍r�X�����G���莔�����G�̂悤�Ɍ����������悤���v
�Ǝv�������̂́A�����G����H�����Ă����Ăɓ��ꂽ�B
���č������A���������͑����������Ă��
�u���O���G�̕]���͕����Ă������A���낢��Z�����Ă���܂Ō��ĂȂ������B�������Ă͂���ʂ��v
�ƌ����ƁA�����͂������Ă������Ă��āA�Ă̌����J���A�G���o�����B
�����̂悤�Ɏ���o���ė��܂点�悤�Ƃ������A�G�͂���������ƁA���̂܂܉�������O�֔��ł����Ă��܂����B
�������c�O�����āu�����͎�ɗ��܂�܂��̂ɓ�����Ƃ́A�ɂ������Ƃł��v�ƌ�����
������́u������m���Ă���l�Ԃł����A�d����Y��ē��S����̂͂悭���邱�Ƃł���B
�܂��Ă⍡�܂Œ��������o���Ȃ����������s�v�c���B
�܂������G�������Ă��邤���Ɍ̋��ɖ߂����ƍl����A���߂��{�����Ƃ����悤�v�ƈԂ߂��B
�������ē�����̋@�]�ɂ�菬�������͑��ꂽ���߁A����������������̉Ƒ��͗܂𗬂��Ċ��ӂ����������B
���͏�͂��܂������Z�݂ō����ƌ����Ă������A�G�������ւ�������Ă����B
�Ă��J�����G���o���ƕ������щ��A��������������o�����̎�ɗ��܂�قǎ������炵�Ă����B
������A����������̎��ɂ����̏����������G�����~�ɏo���ėV��ł����Ƃ���A�L�����A����o�Ă��ĐH���Ă��܂����B
�����͒Z�C�ł��������߁A�A���Ă�����ǂ��Ȃ邾�낤�Ƌ���A�܂�������ɂ��Ƃ̎�����������B
������u�Ύ~�Ȃ��Ƃ��������̂��A��������������Ђǂ�������ł��낤�B
�܂��͒��ɍs���G����H�����Ă��Ă����Ăɓ����v�ƌ�����
���������́u�����������l�Ƃ����ǁA���̍r�X�����G���莔�����G�̂悤�Ɍ����������悤���v
�Ǝv�������̂́A�����G����H�����Ă����Ăɓ��ꂽ�B
���č������A���������͑����������Ă��
�u���O���G�̕]���͕����Ă������A���낢��Z�����Ă���܂Ō��ĂȂ������B�������Ă͂���ʂ��v
�ƌ����ƁA�����͂������Ă������Ă��āA�Ă̌����J���A�G���o�����B
�����̂悤�Ɏ���o���ė��܂点�悤�Ƃ������A�G�͂���������ƁA���̂܂܉�������O�֔��ł����Ă��܂����B
�������c�O�����āu�����͎�ɗ��܂�܂��̂ɓ�����Ƃ́A�ɂ������Ƃł��v�ƌ�����
������́u������m���Ă���l�Ԃł����A�d����Y��ē��S����̂͂悭���邱�Ƃł���B
�܂��Ă⍡�܂Œ��������o���Ȃ����������s�v�c���B
�܂������G�������Ă��邤���Ɍ̋��ɖ߂����ƍl����A���߂��{�����Ƃ����悤�v�ƈԂ߂��B
�������ē�����̋@�]�ɂ�菬�������͑��ꂽ���߁A����������������̉Ƒ��͗܂𗬂��Ċ��ӂ����������B
348�l�Ԏ����l�N
2022/09/02(��) 23:41:43.36ID:MhRgviZR �V���\�O�N�O�������A�i�G�g�́j����摠�����ɂ����Đ���̖��������W�߁A��ӏ��ɂ����āA
��@�Ձi���x�j�ƍ���@�v������_�Ă��B�܂�����A���̑����X�̒������S�̎ҋ��ɂ��Q��������悤��
�Ƃ��������A�A���������܂���悤�ɂƂ��A�����ɂ��A�����̏��L���铹��������ēo��A���g�Œ������\���A
���̐l�̖����Ȃǂ��i�G�g���j����̂��Ƃ����B
��ԂɎ���a���������������閼���������\�����B��Ԃɕ��q�Ȃǂ̂悤�ȁA�R��ׂ��S�l�O���������A
�O�Ԃ͍�̗ǂ�������O�ł���A���̑����掟��ɂ��̂悤�ɗL�����Ƃ����B
�G�g�͌����A�O���̊ԂɁA����A�邠�����Ƃ����B���̒���ŏ@�ՁA�@�v�͓s����S��������A
���l���ē_�Ă��Ƃ����B
�i�F��吅�L�j
��@�Ձi���x�j�ƍ���@�v������_�Ă��B�܂�����A���̑����X�̒������S�̎ҋ��ɂ��Q��������悤��
�Ƃ��������A�A���������܂���悤�ɂƂ��A�����ɂ��A�����̏��L���铹��������ēo��A���g�Œ������\���A
���̐l�̖����Ȃǂ��i�G�g���j����̂��Ƃ����B
��ԂɎ���a���������������閼���������\�����B��Ԃɕ��q�Ȃǂ̂悤�ȁA�R��ׂ��S�l�O���������A
�O�Ԃ͍�̗ǂ�������O�ł���A���̑����掟��ɂ��̂悤�ɗL�����Ƃ����B
�G�g�͌����A�O���̊ԂɁA����A�邠�����Ƃ����B���̒���ŏ@�ՁA�@�v�͓s����S��������A
���l���ē_�Ă��Ƃ����B
�i�F��吅�L�j
349�l�Ԏ����l�N
2022/09/03(�y) 20:56:01.72ID:xme28juG >>346
�S�̍œK���Ă̂��������Ă��
�S�̍œK���Ă̂��������Ă��
350�l�Ԏ����l�N
2022/09/04(��) 14:59:22.16ID:fPyEczsM https://mobile.twitter.com/fukuokaC_museum/status/1564137168255082496
�����s������@fukuokaC_museum
�����s�����قł́A10��8���i�y�j���u�Ɗᗳ�@�ɒB���@�v���J�Â��܂��B
�{�W�ł́A���������J�ƂȂ鐭�@���p�̍b�h�Ⓖ�M�̎莆�A����A����u�c�������g�ߊW�����v�Ȃǖ�100�_���Љ�A
���@�̖��͂ɔ���܂��B���@�Ɠ�����̕����E���c�����Ɨ��ԏ@�̍b�h���������J���܂��B
10��8���i�y�j���@11��27���i���j�܂�
���ʓW �Ɗᗳ �ɒB���@
https://rkb.jp/event/masamune/
�퍑����W�̈ꕔ�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����{�E��B�ł��ꂾ����K�͂ȈɒB�Ɠ��W�͏��߂Ăł͂Ȃ��ł��傤���H
���߂��̕��͂��Ђ��̋@������ɂ��o�ł��������B
���̂Ƃ�����s�����ق́A��N�̋����n�k�̌�A�ݔ��j���̏�Ɏ{�݂̘V�������������āi+�R���i�j�A��H���̂���2�N��܂ŕقł��E�E
�����ɑ݂��o����̂��������Ƃ������܂��̂ŁA�s�������Ȃ��ł���z���g�B
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
�����s������@fukuokaC_museum
�����s�����قł́A10��8���i�y�j���u�Ɗᗳ�@�ɒB���@�v���J�Â��܂��B
�{�W�ł́A���������J�ƂȂ鐭�@���p�̍b�h�Ⓖ�M�̎莆�A����A����u�c�������g�ߊW�����v�Ȃǖ�100�_���Љ�A
���@�̖��͂ɔ���܂��B���@�Ɠ�����̕����E���c�����Ɨ��ԏ@�̍b�h���������J���܂��B
10��8���i�y�j���@11��27���i���j�܂�
���ʓW �Ɗᗳ �ɒB���@
https://rkb.jp/event/masamune/
�퍑����W�̈ꕔ�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����{�E��B�ł��ꂾ����K�͂ȈɒB�Ɠ��W�͏��߂Ăł͂Ȃ��ł��傤���H
���߂��̕��͂��Ђ��̋@������ɂ��o�ł��������B
���̂Ƃ�����s�����ق́A��N�̋����n�k�̌�A�ݔ��j���̏�Ɏ{�݂̘V�������������āi+�R���i�j�A��H���̂���2�N��܂ŕقł��E�E
�����ɑ݂��o����̂��������Ƃ������܂��̂ŁA�s�������Ȃ��ł���z���g�B
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
351�l�Ԏ����l�N
2022/09/05(��) 14:50:01.20ID:SG6/So3y ����ƌ����̌䎡���ɁA�u�����䐭���́A���Ƌ{�̒ʂ�ɐ������ׂ��v�Ƌ��ɂȂ�ꂽ�Ƃ���A
�ɒB�����琭�@��
�u�ƍN�����A�S����������Ƃ̌䏑�t���L��܂����A���@�Ƃ��Ă����݂͌������������ł�����A
����͔��̂ł���Ƒ����Ă��܂������A���x�̋��ɂ��āA���̌�ؕ��̎ʂ����䗗�ɓ��ꂽ���v���܂��B�v
�Ƃ̌䏑�t��������ꂽ�B
���̎��͏㕷�ɒB���A�y��吆���������������
�u������ɕS���������Ƃ����̂́A�L��܂������ł͖������A����͂��̓����̌�d�ł���A���̂悤�Ȏ���
���グ�Ă��ẮA���Ƃ����܂��A���̗ނ̂��Ƃ�����Ă��邾�낤�A���������ׂ����낤���B�v
�ƌ�q�˂ɂȂ����B
�����͂���Ɂu��ɑ|�����i���F�j�Ɍ䑊�k�����ׂ��ł��傤�B�v�ƌ��サ�����߁A�����ɑ|�����������o����A
���ꂱ��̎|�����������ꂽ�Ƃ���A���F�͏����āA�ɒB�ƂɎQ��A���@�ƑΖʂ��Đ\����
�u�����A����������ɁA���x���o���ꂽ���Ƃɂ��āA���c�i�ƍN�j��艺���ꂽ��ؕ��̎ʂ���
�����o�����Ƃ̎��ł����A����͎����ł��傤���H�s�R�Ɏv���A���z���܂����B�v�Ɛ\�����B
�����瓚���āu�����ɂ����̒ʂ�ł���B�����������̂ɁA���̌䏑�t�����̂Ƒ����Ă����̂����A
���x�̋��o����ɂ��A�䗗�ɓ����̂��B�v
���F�͐q�˂��u���̌�ؕ��͌䎩�M�ł��傤���H�v
�u�S���A���c�̌�M�ł���B�v
�u�����o����̂ł���A�������������q���d�肽���v���܂��B�v
���̂悤�ɐ\�������߁A���@�͉Ɛb���Ăяo���A��ؕ��̓�����⦂����A��ɂ̑O�ɒu���ƁA
���F�͌�ؕ����o���ĉ��������A�Ƃ��Ɣq�����Đ��@�ɑ�
�u���悤�Ȏ��͌�d�ł���A�M�a�����̎��͌䑶�m�ł���͂��ł��B���ɔ��̂ɂČ�B�v
���������Ȃ��炱����O�Ɉ������B���@�͂�������ċ����߂���
�u�Ȃ�قǁA���l�ł���B����͂������q�ɋ������A���n��i�������q�ɋ������Đ�n��j��
�\�����̂ł���ȁB�v
�Ə��A��X�̋��������Č�ɁA���F�͈ɒB�Ƃ��o�Ă����蒼���ɓo�邵�āA���̎�����ƁA
�ƌ����͂��@���߂Ȃ炸�A�������傢�Ɋ��S�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
�ɒB�����琭�@��
�u�ƍN�����A�S����������Ƃ̌䏑�t���L��܂����A���@�Ƃ��Ă����݂͌������������ł�����A
����͔��̂ł���Ƒ����Ă��܂������A���x�̋��ɂ��āA���̌�ؕ��̎ʂ����䗗�ɓ��ꂽ���v���܂��B�v
�Ƃ̌䏑�t��������ꂽ�B
���̎��͏㕷�ɒB���A�y��吆���������������
�u������ɕS���������Ƃ����̂́A�L��܂������ł͖������A����͂��̓����̌�d�ł���A���̂悤�Ȏ���
���グ�Ă��ẮA���Ƃ����܂��A���̗ނ̂��Ƃ�����Ă��邾�낤�A���������ׂ����낤���B�v
�ƌ�q�˂ɂȂ����B
�����͂���Ɂu��ɑ|�����i���F�j�Ɍ䑊�k�����ׂ��ł��傤�B�v�ƌ��サ�����߁A�����ɑ|�����������o����A
���ꂱ��̎|�����������ꂽ�Ƃ���A���F�͏����āA�ɒB�ƂɎQ��A���@�ƑΖʂ��Đ\����
�u�����A����������ɁA���x���o���ꂽ���Ƃɂ��āA���c�i�ƍN�j��艺���ꂽ��ؕ��̎ʂ���
�����o�����Ƃ̎��ł����A����͎����ł��傤���H�s�R�Ɏv���A���z���܂����B�v�Ɛ\�����B
�����瓚���āu�����ɂ����̒ʂ�ł���B�����������̂ɁA���̌䏑�t�����̂Ƒ����Ă����̂����A
���x�̋��o����ɂ��A�䗗�ɓ����̂��B�v
���F�͐q�˂��u���̌�ؕ��͌䎩�M�ł��傤���H�v
�u�S���A���c�̌�M�ł���B�v
�u�����o����̂ł���A�������������q���d�肽���v���܂��B�v
���̂悤�ɐ\�������߁A���@�͉Ɛb���Ăяo���A��ؕ��̓�����⦂����A��ɂ̑O�ɒu���ƁA
���F�͌�ؕ����o���ĉ��������A�Ƃ��Ɣq�����Đ��@�ɑ�
�u���悤�Ȏ��͌�d�ł���A�M�a�����̎��͌䑶�m�ł���͂��ł��B���ɔ��̂ɂČ�B�v
���������Ȃ��炱����O�Ɉ������B���@�͂�������ċ����߂���
�u�Ȃ�قǁA���l�ł���B����͂������q�ɋ������A���n��i�������q�ɋ������Đ�n��j��
�\�����̂ł���ȁB�v
�Ə��A��X�̋��������Č�ɁA���F�͈ɒB�Ƃ��o�Ă����蒼���ɓo�邵�āA���̎�����ƁA
�ƌ����͂��@���߂Ȃ炸�A�������傢�Ɋ��S�����Ƃ����B
�i�V���Ӂj
352�l�Ԏ����l�N
2022/09/06(��) 22:34:26.40ID:Jo2FWFOc ���x�G�g����ݗ�����A�֔��ɂȂ�ꂽ�B�߉q�a�A�O�����a���O�v���̌�P�q�Ƃ��Ăł���Ƃ����B
�i�V���\�O�N�j��������ɎQ������A�֒��ɂ����Č�\������A�㉺���̎�\�̎҂����������
�G�g�����������Ƃ����B
�G�g���֔��ɂȂ�ꂽ���ŁA�����ɓa��l�A����v�ɂȂ����l���\�l���������B
��\�͌ܔԁA�|�����A�c���A�O�ցA�g�t��A�����̐B
����̌�\�ɁA�֔��a�i�G�g�j�ɑ����X���i�オ����A�㉺���O���u��Z�A���S����A�܂��ܕS�A
����炪���킹�Ē��ɖ钆������ח��Ă��A�����Ԃ���O���������B
�����ɂ͐����a�̌�ʓ��̏������Ɉ��������āA���̌䞻�������o����A���̏�ɔu��A�܈ȉ����u���ꂽ�B
�܂��A���̐܁A�u��ȉ��͏㉺���̒��l�̐i��ł������B���x�̖~�̗x�����Ƃ������ɁA����A
�܁A�u��ȉ���y������悤�ɂƏG�g�����������ꂽ�̂��B
�\�̑��v�́A�㋞����̓z���P�A���L�̓z���P���A�����̃��E�n�ł���Ƃ����B�����O�Չ��Ƃ����҂ł���B
�����̑�v�͂���܂ŁA�֗���\�ɉ���ɂĂ�����������邱�Ƃ͖����������B��v����O�ł���Ƃ��āA
��������鎖���������B�����č���͏G�g�����A�z��̛�q��S���i�コ��A���ꂪ���������ꂽ�B
�i�F��吅�L�j
�G�g�̊֔��A�C�̎��̏㋞�����̊ւ��ɂ��āB
�i�V���\�O�N�j��������ɎQ������A�֒��ɂ����Č�\������A�㉺���̎�\�̎҂����������
�G�g�����������Ƃ����B
�G�g���֔��ɂȂ�ꂽ���ŁA�����ɓa��l�A����v�ɂȂ����l���\�l���������B
��\�͌ܔԁA�|�����A�c���A�O�ցA�g�t��A�����̐B
����̌�\�ɁA�֔��a�i�G�g�j�ɑ����X���i�オ����A�㉺���O���u��Z�A���S����A�܂��ܕS�A
����炪���킹�Ē��ɖ钆������ח��Ă��A�����Ԃ���O���������B
�����ɂ͐����a�̌�ʓ��̏������Ɉ��������āA���̌䞻�������o����A���̏�ɔu��A�܈ȉ����u���ꂽ�B
�܂��A���̐܁A�u��ȉ��͏㉺���̒��l�̐i��ł������B���x�̖~�̗x�����Ƃ������ɁA����A
�܁A�u��ȉ���y������悤�ɂƏG�g�����������ꂽ�̂��B
�\�̑��v�́A�㋞����̓z���P�A���L�̓z���P���A�����̃��E�n�ł���Ƃ����B�����O�Չ��Ƃ����҂ł���B
�����̑�v�͂���܂ŁA�֗���\�ɉ���ɂĂ�����������邱�Ƃ͖����������B��v����O�ł���Ƃ��āA
��������鎖���������B�����č���͏G�g�����A�z��̛�q��S���i�コ��A���ꂪ���������ꂽ�B
�i�F��吅�L�j
�G�g�̊֔��A�C�̎��̏㋞�����̊ւ��ɂ��āB
353�l�Ԏ����l�N
2022/09/09(��) 18:29:09.73ID:XSLFTUOS �u�̖�����^�v�́u���̊��v���獲�����ɂ܂��
�E���o��e��:�����ҏ��̑�̎��ɁA�D�V�т̓r���ŊC�Ɍ���ė��Ƃ������Ƃ����������A�e���݂�����鉺�̐��܂œo��A����Ō��������߈ҏ��ɔ������ꂽ�B
�����Ҏ��̗��̎��ɂ���������Ă������A�ߍ��͍s���m�ꂸ�ɂȂ��Ă���B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13613.html
�E�̑���
���̑������₩�甲���ƃn�o�L����n�ɗ��̌`���ړ����A��Ɏh�����ɂ͗����n�o�L�̌��A��
�E�������o�w�̎��ɂ����J���~�邪�A�ւ̎q���ł��邽�ߋg��Ƃ��Ă���B
�E�������͑c��ԑ喾�_(�_)�̎q���ł��邽�ߑ�X������A�����Ғ�ɂ͎O�������B
�Ғ蒄�j�̈ҏd�ɂ͌��a�ܔN(1619�N)�\�ꌎ��\�������̉��Ɉ���o�������Ƃ����B
�E�����Ғ肪���a�l�N(1618�N)�Z������Ɉɐ��Ŗv����O���O�A�����ҍN�ȗ��`���̊�����ꂽ������Ƃ����s�v�c���������B
�E���o��e��:�����ҏ��̑�̎��ɁA�D�V�т̓r���ŊC�Ɍ���ė��Ƃ������Ƃ����������A�e���݂�����鉺�̐��܂œo��A����Ō��������߈ҏ��ɔ������ꂽ�B
�����Ҏ��̗��̎��ɂ���������Ă������A�ߍ��͍s���m�ꂸ�ɂȂ��Ă���B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13613.html
�E�̑���
���̑������₩�甲���ƃn�o�L����n�ɗ��̌`���ړ����A��Ɏh�����ɂ͗����n�o�L�̌��A��
�E�������o�w�̎��ɂ����J���~�邪�A�ւ̎q���ł��邽�ߋg��Ƃ��Ă���B
�E�������͑c��ԑ喾�_(�_)�̎q���ł��邽�ߑ�X������A�����Ғ�ɂ͎O�������B
�Ғ蒄�j�̈ҏd�ɂ͌��a�ܔN(1619�N)�\�ꌎ��\�������̉��Ɉ���o�������Ƃ����B
�E�����Ғ肪���a�l�N(1618�N)�Z������Ɉɐ��Ŗv����O���O�A�����ҍN�ȗ��`���̊�����ꂽ������Ƃ����s�v�c���������B
354�l�Ԏ����l�N
2022/09/09(��) 20:37:33.45ID:BqFjAl/o �ɐ��E�ւ̈�}�Ƃ́A�Z�g��������b�i���j�������̌���ł���B
��c�ł��鏬������b�d�����͓V�������߂�ꂽ���A���j�����V�O�ʒ������������\�O�̔N�ɁA
�a���捇�����̂��߂ɐ��B�鎭�S�֒J�v��Ƃ������ɗ�����A�Z�N�Ԃ����ɋ����A���̎��A
�q����l���o�����B
�����̐��ɂȂ�A�k���Ƃ����̎q��a���薽���������B�ނ͐����Ə̂��Ċ֓��ɂĎ��������B
���̎q�A�֔V���ߑ�v���Ď��������߂Ċ֔V�J�������A�u�ցv�ƍ������B
���̖����E�֑��l�Y�͑����������ɖ������q���ɉh�����B
�֔V�O�ƓƂ́A�鎭�S�T�R�։ƁA��ȌS�_�ˊ։ƁA�鎭�S��։Ƃł���B
��������n���l���ɁA�R����̑叫�ł���B
�������ܑ叫�Ƃ́A����ɉ����ė鎭�S���{�ւ̉ƁA���S�����e�։ƁA�e�ܕS�̑叫�ł���B
���͍��킹�Čܐ�l�ł���i�����ρj�B�����Ă��̌܉Ƃ͊F�A�������R�Ƃ̎��ł���B
���̖�͏�H���Ȃ�B
�i���B�����L�j
�ɐ��։Ƃɂ��āB
��c�ł��鏬������b�d�����͓V�������߂�ꂽ���A���j�����V�O�ʒ������������\�O�̔N�ɁA
�a���捇�����̂��߂ɐ��B�鎭�S�֒J�v��Ƃ������ɗ�����A�Z�N�Ԃ����ɋ����A���̎��A
�q����l���o�����B
�����̐��ɂȂ�A�k���Ƃ����̎q��a���薽���������B�ނ͐����Ə̂��Ċ֓��ɂĎ��������B
���̎q�A�֔V���ߑ�v���Ď��������߂Ċ֔V�J�������A�u�ցv�ƍ������B
���̖����E�֑��l�Y�͑����������ɖ������q���ɉh�����B
�֔V�O�ƓƂ́A�鎭�S�T�R�։ƁA��ȌS�_�ˊ։ƁA�鎭�S��։Ƃł���B
��������n���l���ɁA�R����̑叫�ł���B
�������ܑ叫�Ƃ́A����ɉ����ė鎭�S���{�ւ̉ƁA���S�����e�։ƁA�e�ܕS�̑叫�ł���B
���͍��킹�Čܐ�l�ł���i�����ρj�B�����Ă��̌܉Ƃ͊F�A�������R�Ƃ̎��ł���B
���̖�͏�H���Ȃ�B
�i���B�����L�j
�ɐ��։Ƃɂ��āB
355�l�Ԏ����l�N
2022/09/09(��) 20:55:02.34ID:XSLFTUOS http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7833.html
�։Ƃ𑊑�����҂́A��X������l�����Ă���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7831.html
��t�@�ƁA�y�̂̈�
�֎��̕���
�L���_�ꑰ�̍��������e�c���̗̑̂�
��t���̌����̃C�{
��c��X�p�����g�̓I�����l�^���Ăق��ɂ����邩��
�։Ƃ𑊑�����҂́A��X������l�����Ă���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7831.html
��t�@�ƁA�y�̂̈�
�֎��̕���
�L���_�ꑰ�̍��������e�c���̗̑̂�
��t���̌����̃C�{
��c��X�p�����g�̓I�����l�^���Ăق��ɂ����邩��
356�l�Ԏ����l�N
2022/09/10(�y) 20:53:11.98ID:Ggs1f0hu �V���\�O�N�\�ꌎ�\����A�����썶�q�卲�i���i�j�A�g�쎡������i�����j����ɓ������A��\����
���Ձi���@�j���Y��������g�Ƃ��āA�n��D�����킳���B����͏G�g���Q�����R��ׂ��n�ł������B
�V��l�i���@�j������n��D�����킳�ꂽ�B
��\����A������A�g��̗��l�͑��ɍs����G�g�Ɍ�炵�A�ї��E�n���i�P���j����疇�A
��������ܕS���A�g��͎O�S����i�サ���B
��\�l���ɂ͌�\������A���������q��v���\�O�Ԃ���A�|�B�O�����ĂȂ��߂��B
��\�ܓ��A����͌�ɂ������A���B��\�ܓ��A����l�i���@�j�֕ԗ�̎g�҂��������B
��������ꍘ�ƌܐ�D�A�g����ꍘ�ƌՕ^�̔�O���A�n���ł������B
�g����͓��c���̖��ܘY�Ƃ����l�����āA�����엲�i���������������ɂ܂ʼn������ƌ������B
�[���ɂ͒��������������ɎQ�����B
�i�F��吅�L�j
�����엲�i�A�g�쌳���̏㗌�ɂ���
���Ձi���@�j���Y��������g�Ƃ��āA�n��D�����킳���B����͏G�g���Q�����R��ׂ��n�ł������B
�V��l�i���@�j������n��D�����킳�ꂽ�B
��\����A������A�g��̗��l�͑��ɍs����G�g�Ɍ�炵�A�ї��E�n���i�P���j����疇�A
��������ܕS���A�g��͎O�S����i�サ���B
��\�l���ɂ͌�\������A���������q��v���\�O�Ԃ���A�|�B�O�����ĂȂ��߂��B
��\�ܓ��A����͌�ɂ������A���B��\�ܓ��A����l�i���@�j�֕ԗ�̎g�҂��������B
��������ꍘ�ƌܐ�D�A�g����ꍘ�ƌՕ^�̔�O���A�n���ł������B
�g����͓��c���̖��ܘY�Ƃ����l�����āA�����엲�i���������������ɂ܂ʼn������ƌ������B
�[���ɂ͒��������������ɎQ�����B
�i�F��吅�L�j
�����엲�i�A�g�쌳���̏㗌�ɂ���
357�l�Ԏ����l�N
2022/09/10(�y) 21:32:12.44ID:J/ZemXQR �ǂ���ӂ������b�Ȃ�
358�l�Ԏ����l�N
2022/09/10(�y) 22:08:17.57ID:3lvuD7ir �F��吅�͌��@�̔鏑��(�E�M)�A���̓��L�̂�������������̂�����ł��B
359�l�Ԏ����l�N
2022/09/11(��) 01:29:37.17ID:OLeB3Ezp360�l�Ԏ����l�N
2022/09/11(��) 08:21:42.73ID:f187KM49 �퍑������Ɩ��ʘb���ăX���ł����ĂĂ����ł���Ăق�����A�����V�o�̍r�炵���낱��
�Ō�܂œǂ܂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ�����]�v������
�Ō�܂œǂ܂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ�����]�v������
361�l�Ԏ����l�N
2022/09/11(��) 09:32:08.43ID:srxI4k4u �����Ȃ��ƃA�t�B�J�X�ɂ����Ⴆ�Ȃ���
���킢������
���킢������
362�l�Ԏ����l�N
2022/09/11(��) 09:39:00.07ID:xksSu1o2 ������������nj��l�^���Ђ̔w�i���炢�͏����Ă���B
363�l�Ԏ����l�N
2022/09/11(��) 09:41:30.26ID:0G5lvKnP �A�t�B�J�X�̃A�t�B�J�X�ɂ��A�t�B�J�X�̂��߂̃S�~�X���b�h
364�l�Ԏ����l�N
2022/09/11(��) 15:47:05.18ID:QRvICXs9 ���g�̎O�P�i�O�D�j�C�����v�i���c�j�a�́A�\���ɂĎv�������A
�u���N���O���N�̊ԁA�ĕS���Â������̖@���s�������B�v�Ɛ��ꂽ�B
�ƘV�̎҂́u����͉��̂��߂ɂ��������̂ł��傤���v�Ɛ\�����B
�C�����v�́u�����̗_�̂��߂ł���B�v�Ɠ�����ꂽ�B
�ƘV�͏���A�u�O�D�̌�Ƃɐ��܂��ꂽ�ȏ�A�������ʕ����i�ڏo�x��������̂ɁA
�ǂ����Ă��̂悤�ɖܑ̖��������s����̂ł��傤���B�v���|�������B
�O�D�a�͌���ꂽ
�u�e�X�͎��ɁA�������ʕ���L��ł͂Ȃ����ƌ����B����������͐��ʂł���B
�i�V�c�j�`����̌R�L�ɂ����Ă��A���ʂ͌����Ă���B
���͗c���ł���̂Ŗ��̋V��m��Ȃ��B�m��Ȃ���ΐ戫���Ɗo��v���̂�
�ނ��ł��낤�B
���Ƃ��ʕ�̂���l�́A�F�炸�Ƃ��g�ƂȂ邾�낤�B
�ʕ�̖����l�͋F���Ă�����ʂ��낤�B
�܂��F�炸���Ĉ������Ȃ�҂����邾�낤���A�ˑR�F���ėǂ����ʂƂȂ�l�����邾�낤�B
����F�V���ł���B
�ʕ�ɐ��܂�����l�́A�Ⴆ�Ύ��R�̂悤�Ȃ��̂��B���R�͋����ɂ������Ă�
���̂��߂Ɍ͂�邱�Ƃ͋H�ł���B�͉�����������Ƃ��Ǝv���Ă��A�����ɒ���Y����
����Ȃ���A�������̕��ł����Ă��Č͂�邱�Ƌ^���Ȃ��B
���̂��̓x�̋������́A�A�ɓY���������S�Ȃ̂��B
�M��]�����Ȃ��l�̌����������ł���B
�u�����̎Аl�A�����V��Ȃǂ��V����̕��ӎ҂ɐ��邾�낤���v�ƁA�_��M����҂�掂�B
�������Ȃ���A�Ⴆ���x�͋����@�邪�A�Ȃ̕��Ƃ͂����l�ɂ����炷�B
�܂����̂悤�ɐM��]�����Ȃ��l�X���A�����A�����̎q�������s��̕a�ƂȂ�A������
��N�̊�����ւ�ȂǁA���̓��ł����Ă���V�ɋy�Ԃ��̎��́A���_�����ɗ��肷��B
�F����l�Ԃ̖��ł���B
���ɕւ��Đg������B�l�����킸�������Ȃ�A�m��Аl�͉쎀���邾�낤�B
����ΐ̂�薼���l�́A�\�l����l�A�M�S�̖����l�͂Ȃ��B
�F����V���A�F��ʂ��V���ł���B�v
�w�b�z�R�Ӂx
�b�z�R�ӂ��A�O�D���c�ɂ��M�S�ɂ��Ă̂��b
�u���N���O���N�̊ԁA�ĕS���Â������̖@���s�������B�v�Ɛ��ꂽ�B
�ƘV�̎҂́u����͉��̂��߂ɂ��������̂ł��傤���v�Ɛ\�����B
�C�����v�́u�����̗_�̂��߂ł���B�v�Ɠ�����ꂽ�B
�ƘV�͏���A�u�O�D�̌�Ƃɐ��܂��ꂽ�ȏ�A�������ʕ����i�ڏo�x��������̂ɁA
�ǂ����Ă��̂悤�ɖܑ̖��������s����̂ł��傤���B�v���|�������B
�O�D�a�͌���ꂽ
�u�e�X�͎��ɁA�������ʕ���L��ł͂Ȃ����ƌ����B����������͐��ʂł���B
�i�V�c�j�`����̌R�L�ɂ����Ă��A���ʂ͌����Ă���B
���͗c���ł���̂Ŗ��̋V��m��Ȃ��B�m��Ȃ���ΐ戫���Ɗo��v���̂�
�ނ��ł��낤�B
���Ƃ��ʕ�̂���l�́A�F�炸�Ƃ��g�ƂȂ邾�낤�B
�ʕ�̖����l�͋F���Ă�����ʂ��낤�B
�܂��F�炸���Ĉ������Ȃ�҂����邾�낤���A�ˑR�F���ėǂ����ʂƂȂ�l�����邾�낤�B
����F�V���ł���B
�ʕ�ɐ��܂�����l�́A�Ⴆ�Ύ��R�̂悤�Ȃ��̂��B���R�͋����ɂ������Ă�
���̂��߂Ɍ͂�邱�Ƃ͋H�ł���B�͉�����������Ƃ��Ǝv���Ă��A�����ɒ���Y����
����Ȃ���A�������̕��ł����Ă��Č͂�邱�Ƌ^���Ȃ��B
���̂��̓x�̋������́A�A�ɓY���������S�Ȃ̂��B
�M��]�����Ȃ��l�̌����������ł���B
�u�����̎Аl�A�����V��Ȃǂ��V����̕��ӎ҂ɐ��邾�낤���v�ƁA�_��M����҂�掂�B
�������Ȃ���A�Ⴆ���x�͋����@�邪�A�Ȃ̕��Ƃ͂����l�ɂ����炷�B
�܂����̂悤�ɐM��]�����Ȃ��l�X���A�����A�����̎q�������s��̕a�ƂȂ�A������
��N�̊�����ւ�ȂǁA���̓��ł����Ă���V�ɋy�Ԃ��̎��́A���_�����ɗ��肷��B
�F����l�Ԃ̖��ł���B
���ɕւ��Đg������B�l�����킸�������Ȃ�A�m��Аl�͉쎀���邾�낤�B
����ΐ̂�薼���l�́A�\�l����l�A�M�S�̖����l�͂Ȃ��B
�F����V���A�F��ʂ��V���ł���B�v
�w�b�z�R�Ӂx
�b�z�R�ӂ��A�O�D���c�ɂ��M�S�ɂ��Ă̂��b
365�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 19:20:04.66ID:cZgjre5a �L�㍲�����ɂ��Ă̓`�����܂Ƃ߂��u�̖�����^�v�u���̊��v���炻�̂ق��̍������`���̓����ɂ��Ă̘b
�E��g����
�c��ԑ喾�_(�_)�̒��q�E��_�Ҋ��葊�`���ꂽ�B
���̐́A���a���N(840�N)�ɈҊ�Q����������A�����ɒu���Ē��Q�������B
�����������y�V��Ƃ������Ƃ��u��B�̏^�Ƃ͂����A���͖��������m��ʁv�Ɣ������Ƃ����������Ȃ������B
�����ʼn�y�V��͂����𗣂�A�u�Ҋ�̑����͍�蕨���낤�B���ł����ɋl�ߍ���ł�ɈႢ�Ȃ��v
�ƌ����ӂ炵�A�|�̒��ɓS�����߂ĖȂŕ��ŋ֒��̒�ɗ��Ă�
�u�Ҋ��A��ɗ��������̂�����B����ɂ��a���Ă݂�v�ƒp���������邽�߂ɖ������B
�Ҋ�꓁�̂��ƂɎa�藎�Ƃ������߁A���Ă̊O�ꂽ���ƘA���͋t���݂��Ҋ�𗬍߂ɂ��悤�Ƃ����B
���������̓��֒��ʼnΎ����N���A�Ҋ�������g���đ���������J�����������߁A�Ҋ�͖L���ɔC����ꂽ�B
���̂��ߎ�g�����͕s���̑����Ƃ������Ă���B
�E�_������
�F��������_�{���ł����Ƃ���鑾���ŁA���i��N(1183�N)���ƒǓ��̌��ɂ�茹�`�o���珏���҉h�ɉ������ꂽ�B
�����Ғ�̑��q�E�����ҏd���ɐ��ɏZ��ł������a��N(1623�N)�ɋ��Ɍ����ɑ������Ƃ���A�������}�a�Ŋ�ĂƂȂ����B
����͐_�����������ɑ��������߂ł��낤�ƁA�ǂ�����������Ẩw�Ŏ��Ԃ������Ƃɖ߂����Ƃ���A��ɓ���₢�Ȃ⑧���͉��C�����B
���̂��߉Ƃ���鑾���ł��낤�Ƃ����Ă���B
�E�b���̑���
�c��ԑ喾�_����_�Ҋ�̕�ɏ���n���������ƌ����Ă���B
���i�O�N(1626�N)�\���\���A�����ҏd�̎�N�ł���ɐ��Ô˔ˎ�E���������͈ҏd�ɓ����Ƃ̉��~�܂ő��������Q�������B
�����͒��ڐG��͈̂ꑽ���Ƃ����̂ŁA���𐙌����ŕ��Ŕ������Ƃ����������Ȃ������B
����Ɉҏd���������č����ɓn�����Ƃ���ƁA�����Ȃ���̔~������č����̌܁A�Z�l�����|�����B
���̂��ߓ��������͑�������Ɏ��̂͂�߁A�������j�����߂ɔu���Ă݂ȂŊ��k�����B
�E��g����
�c��ԑ喾�_(�_)�̒��q�E��_�Ҋ��葊�`���ꂽ�B
���̐́A���a���N(840�N)�ɈҊ�Q����������A�����ɒu���Ē��Q�������B
�����������y�V��Ƃ������Ƃ��u��B�̏^�Ƃ͂����A���͖��������m��ʁv�Ɣ������Ƃ����������Ȃ������B
�����ʼn�y�V��͂����𗣂�A�u�Ҋ�̑����͍�蕨���낤�B���ł����ɋl�ߍ���ł�ɈႢ�Ȃ��v
�ƌ����ӂ炵�A�|�̒��ɓS�����߂ĖȂŕ��ŋ֒��̒�ɗ��Ă�
�u�Ҋ��A��ɗ��������̂�����B����ɂ��a���Ă݂�v�ƒp���������邽�߂ɖ������B
�Ҋ�꓁�̂��ƂɎa�藎�Ƃ������߁A���Ă̊O�ꂽ���ƘA���͋t���݂��Ҋ�𗬍߂ɂ��悤�Ƃ����B
���������̓��֒��ʼnΎ����N���A�Ҋ�������g���đ���������J�����������߁A�Ҋ�͖L���ɔC����ꂽ�B
���̂��ߎ�g�����͕s���̑����Ƃ������Ă���B
�E�_������
�F��������_�{���ł����Ƃ���鑾���ŁA���i��N(1183�N)���ƒǓ��̌��ɂ�茹�`�o���珏���҉h�ɉ������ꂽ�B
�����Ғ�̑��q�E�����ҏd���ɐ��ɏZ��ł������a��N(1623�N)�ɋ��Ɍ����ɑ������Ƃ���A�������}�a�Ŋ�ĂƂȂ����B
����͐_�����������ɑ��������߂ł��낤�ƁA�ǂ�����������Ẩw�Ŏ��Ԃ������Ƃɖ߂����Ƃ���A��ɓ���₢�Ȃ⑧���͉��C�����B
���̂��߉Ƃ���鑾���ł��낤�Ƃ����Ă���B
�E�b���̑���
�c��ԑ喾�_����_�Ҋ�̕�ɏ���n���������ƌ����Ă���B
���i�O�N(1626�N)�\���\���A�����ҏd�̎�N�ł���ɐ��Ô˔ˎ�E���������͈ҏd�ɓ����Ƃ̉��~�܂ő��������Q�������B
�����͒��ڐG��͈̂ꑽ���Ƃ����̂ŁA���𐙌����ŕ��Ŕ������Ƃ����������Ȃ������B
����Ɉҏd���������č����ɓn�����Ƃ���ƁA�����Ȃ���̔~������č����̌܁A�Z�l�����|�����B
���̂��ߓ��������͑�������Ɏ��̂͂�߁A�������j�����߂ɔu���Ă݂ȂŊ��k�����B
366�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 20:50:43.97ID:bw+H0D7l �퍑���m����\��X������˂���
367�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 21:15:09.62ID:3X6J1wBJ ��������A�t�B�J�X�̃A�t�B�J�X�ɂ��A�t�B�J�X�̂��߂̃S�~�X���b�h�Ɖ�������
368�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 21:16:46.49ID:cZgjre5a �_�������A�b���̑����͍����ҏd�֘A�̈�b�Ȃ̂Ŗ��Ȃ��Ǝv���܂�
��g�����ɂ��Ă͈�b���͕̂�������ł�����̂́A�����Ƃ̏d��Ƃ������Ƃœ���܂���
���܂ł������̓���ɂ��ĕ��ׂ��b�͂������o�Ă��܂����A���ɖ��ɂ͂Ȃ��ĂȂ�����
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13414.html
��m�J�͈�m�J�ɕ��сA��W�͈�m�J����Ȃ�Ƃ���
��g�����ɂ��Ă͈�b���͕̂�������ł�����̂́A�����Ƃ̏d��Ƃ������Ƃœ���܂���
���܂ł������̓���ɂ��ĕ��ׂ��b�͂������o�Ă��܂����A���ɖ��ɂ͂Ȃ��ĂȂ�����
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13414.html
��m�J�͈�m�J�ɕ��сA��W�͈�m�J����Ȃ�Ƃ���
369�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 21:38:44.62ID:spNsKpOa �����ł͈�b�𓊍e�����Ȃ��ŁA���l��l�邱�Ƃ����o���Ȃ����J����
���̃X���̂����̊������瑊�肷�邾�����ʂ�B
���̃X���̂����̊������瑊�肷�邾�����ʂ�B
370�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 21:50:23.27ID:jwY5c31r ���m���ł���������
371�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 22:04:13.95ID:bw+H0D7l �悭�˂���{�P
�l�^���s�����Ȃ�X�����I���ɂ������������
�l�^���s�����Ȃ�X�����I���ɂ������������
372�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 22:13:13.18ID:vbapfo+x �N������ȃ��[�����߂Ă�w
373�l�Ԏ����l�N
2022/09/12(��) 22:44:15.07ID:bw+H0D7l �����A�܂Ƃ߃T�C�g�̊Ǘ��l���Ă邩
�����ɂ͈����ۂ��Ă��̂������
�����ɂ͈����ۂ��Ă��̂������
374�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 10:20:13.44ID:coaP4Bxa �ǂ��ɂł������ȁA�����ł͉�������ŕ�������茾�����c����
375�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 10:33:59.78ID:uJ2lt1kS ���O��A�t�B�T�C�g�ׂ̈ɃR�����g���e������Ă�w
���匾��ꂽ���Ȃ����5ch�g��Ȃ���ǂ���A�z
���匾��ꂽ���Ȃ����5ch�g��Ȃ���ǂ���A�z
376�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 11:15:52.30ID:CMco756k �A�t�B�J�X�̓z��ɂȂ��Ă�`�����������Ă�
377�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 12:01:40.09ID:uJ2lt1kS �����������܂Ƃ��ȃR�����g�Ȃt���ĂȂ����ǂ�w
������Ȃ�Ńp���`���b�p�������{�̌f���ɓ��{��ŏ�������ł�
����1���N�̃R���C�G�C�g�t�@���^�W�[�𐂂ꗬ�������̂��H
������Ȃ�Ńp���`���b�p�������{�̌f���ɓ��{��ŏ�������ł�
����1���N�̃R���C�G�C�g�t�@���^�W�[�𐂂ꗬ�������̂��H
378�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 15:26:12.27ID:d+KHpvWh �����������{�̌f���������́H�m���T�[�o�[���Ċ؍��ɂ����Ȃ�������
379�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 15:35:49.57ID:uJ2lt1kS ���o�J�`���������Ɉړ]������
�E���i���T�[�o�[�œ������Ă邩��5ch�͊؍��N���j�_�Ƃ������Ă�̂�
�}�W�Ńo�J�`�������ē�����������
�E���i���T�[�o�[�œ������Ă邩��5ch�͊؍��N���j�_�Ƃ������Ă�̂�
�}�W�Ńo�J�`�������ē�����������
380�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 18:13:48.91ID:QtVlKtqL �؍��ɗ������Ă����؍��̂��ƒ���������Ȃ��`���̔����͂����Ă��O�����
381�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 18:18:08.99ID:uJ2lt1kS ����܂�܌����ȓ��{�̌f���ɒ���t���Ă邨�O�̂��Ƃ���Ȃ���ww
���イ�����{��g���Ă�˂���e���߂���
���イ�����{��g���Ă�˂���e���߂���
382�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 18:38:11.44ID:fkUtP8ar >>380
�c����������{���������ꂽ�p���`���b�p���������ł�̂�
�c����������{���������ꂽ�p���`���b�p���������ł�̂�
383�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 20:05:30.38ID:c5IXSckZ �b�B�ɏ��}�����o�ւƂ����R�z�҂������B�ނ͗l�X�Ȋ����\���A���C�ɓ����Č˂��������������̂ɁA
�l�X�ɋC�Â��ꂸ�ɊO�ɏo�A�����͖�A�e�X����������A���Ȃ̌������ɎR�������A
�u�������̎R�ɉ����������Ă悤�B�e�X����v
�ƌ����āA�l�̍D�ނ悤�ɉ𗧂Ă�قǂ̎҂ł������B
�����悻�R�z���悭�`������A���̌R�z�̗]�����ȂāA�l�X�Ȋ����v���B
�܂��i�\�l�N�ɐ쒆������̎��������ɂ����R�{����́A�M�������{�ɂ����đ��y�叫�̒���
�ܐl�ɗD�ꂽ���l�ƌĂ�A������R�z�b�B�̎҂ł������B
���̎R�{����������S�̌R�z�́A�{�A���A�p�A���A�H�̌܂�蕪���Č���A�_�C�A�|�C�A���̑�
��A�����A�����A������l�A�s���l�A�����̊O�����`���L�邪�A����͈�i�Z�������B
�A�����}�����o�ւ̂悤�Ȋ���͖��������B
�������Ȃ���A���o�ւ��]���Ă������A����͌R�z�̐_�ςł���Ƃ����Ќ��܂ł̂��̂ŁA
�����̗��ɂ͐���ʂ��̂ł���B
���̈���́A�l�ɖ]�܂�ĎR�ɏ����𗧂Ă邭�炢�Ȃ�A�������Â����ʼnɎ������Ă��鎞�A
�����𗧂Ăē������čs����̂Ȃ�ΑR��ׂ��ł��邪�A���̂悤�ɂ͒��X���炸�A
�����l�ɖ]�܂�Ă悻�ɉ𗧂Ă����B����͏p�ł���B
�p�͍����ł���A�܂��Ƃɓ��Ɏ����ċ|��̌v���A�v��Ȃǂ̗p�ɗ����Ȃ��B
�R��A�G�����ΐw�̎��߂́A��������o�ւ����O�ł���B
�n����Z��i�M�t�j�́A�u�_�ς͖ނ��Ȃ��̂����A����͐l�ɂ���Ă̎��B
���m���|��̂��߂ɌR�z���K���āA�_�ϒv�����ꍇ�A�����̂��߂Ƃ͂����Ȃ���A
�w���̊������l��x�Ƃ��������Ă�A�H�X��R���̂悤�ɐ\����Ă��܂��B
���̂������@�Ɋ�������ƕ������Ă���A�ł���ΐ_�ς͍X�ɗv�炴����̂ł���B�v
�Ɛ\���Ă����B
�w�b�z�R�Ӂx
�R�z�҂Ɛ_�ςɂ���
�l�X�ɋC�Â��ꂸ�ɊO�ɏo�A�����͖�A�e�X����������A���Ȃ̌������ɎR�������A
�u�������̎R�ɉ����������Ă悤�B�e�X����v
�ƌ����āA�l�̍D�ނ悤�ɉ𗧂Ă�قǂ̎҂ł������B
�����悻�R�z���悭�`������A���̌R�z�̗]�����ȂāA�l�X�Ȋ����v���B
�܂��i�\�l�N�ɐ쒆������̎��������ɂ����R�{����́A�M�������{�ɂ����đ��y�叫�̒���
�ܐl�ɗD�ꂽ���l�ƌĂ�A������R�z�b�B�̎҂ł������B
���̎R�{����������S�̌R�z�́A�{�A���A�p�A���A�H�̌܂�蕪���Č���A�_�C�A�|�C�A���̑�
��A�����A�����A������l�A�s���l�A�����̊O�����`���L�邪�A����͈�i�Z�������B
�A�����}�����o�ւ̂悤�Ȋ���͖��������B
�������Ȃ���A���o�ւ��]���Ă������A����͌R�z�̐_�ςł���Ƃ����Ќ��܂ł̂��̂ŁA
�����̗��ɂ͐���ʂ��̂ł���B
���̈���́A�l�ɖ]�܂�ĎR�ɏ����𗧂Ă邭�炢�Ȃ�A�������Â����ʼnɎ������Ă��鎞�A
�����𗧂Ăē������čs����̂Ȃ�ΑR��ׂ��ł��邪�A���̂悤�ɂ͒��X���炸�A
�����l�ɖ]�܂�Ă悻�ɉ𗧂Ă����B����͏p�ł���B
�p�͍����ł���A�܂��Ƃɓ��Ɏ����ċ|��̌v���A�v��Ȃǂ̗p�ɗ����Ȃ��B
�R��A�G�����ΐw�̎��߂́A��������o�ւ����O�ł���B
�n����Z��i�M�t�j�́A�u�_�ς͖ނ��Ȃ��̂����A����͐l�ɂ���Ă̎��B
���m���|��̂��߂ɌR�z���K���āA�_�ϒv�����ꍇ�A�����̂��߂Ƃ͂����Ȃ���A
�w���̊������l��x�Ƃ��������Ă�A�H�X��R���̂悤�ɐ\����Ă��܂��B
���̂������@�Ɋ�������ƕ������Ă���A�ł���ΐ_�ς͍X�ɗv�炴����̂ł���B�v
�Ɛ\���Ă����B
�w�b�z�R�Ӂx
�R�z�҂Ɛ_�ςɂ���
384�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 21:44:05.77ID:m+yYFmZe �܂��؍���D���̃A�t�B�J�X�`���������ł�̂�w
385�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 21:46:40.03ID:uJ2lt1kS �����ȓ��{�̌f���ɒ���t���Ă邨�O�͐e���߂���
���O�̗��j�R�����肾���l�����R�œh��ł߂��Ă��ˁH
���O�̗��j�R�����肾���l�����R�œh��ł߂��Ă��ˁH
386�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 21:49:44.83ID:womp6QJm ����t���A�t�B�J�X�`��wwww
�������Ĕ���wwwwww
�������Ĕ���wwwwww
387�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 21:51:48.40ID:z1EV8n2D �܂��؍���D���`���������ł�̂�
�^���Ԃ���w
�^���Ԃ���w
388�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 21:54:12.23ID:uJ2lt1kS �L���`�������Ƃ���w
�g���X���ł�����ŗ���������`����
�g���X���ł�����ŗ���������`����
389�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 22:01:30.01ID:Uwk/BubF �E���R��D���A�x��www�܂��^���Ԃɂ��Ĕ���wwwww
390�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 22:05:49.68ID:m/HKtoSf �܂��A�t�B�J�X���r�炵�Ă�̂�w
391�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 22:05:55.41ID:uJ2lt1kS ����ɃE���R�Ƃ������n�߂邩���
�}�W�ŃE���R�𖽂Ȃ�
���f������E���R�摜�\��n�߂�������
���܃G���������������Ă���w
������ƃo�J�ɂ��ꂽ�������E���R�A��
��g�قɂ��E���R��������
�}�W�ŃE���R�𖽂Ȃ�
���f������E���R�摜�\��n�߂�������
���܃G���������������Ă���w
������ƃo�J�ɂ��ꂽ�������E���R�A��
��g�قɂ��E���R��������
392�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 22:07:48.80ID:SemTYXEN ��D���ȃE���R�̘b�ɂȂ���`�ゾ��www
393�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 22:12:35.32ID:9jbe9+Xo �`�����E���R��������Ăāi���j
394�l�Ԏ����l�N
2022/09/13(��) 22:23:45.54ID:9jbe9+Xo ��ʎВc�@�l���{�������w��@Japan Academy of Poop culture
http://sorabuta.com/��ʎВc�@�l���{�������w��T�v/
�E���R��D���W���b�vwwwww
http://sorabuta.com/��ʎВc�@�l���{�������w��T�v/
�E���R��D���W���b�vwwwww
395�l�Ԏ����l�N
2022/09/16(��) 20:13:10.82ID:Fv/jrH4D ���͍���e���Ɛ\���āA���c�M�����튯�̓��ŁA��̉��a�҂ł���B
�e�ׂ͉��X�ɂ����ē��q���̋Y���Ɂw�ۉȒe�����e���A����e���ɂ��e���x�Ɛ\���Ȃ�킵�Ă���قǂł���B
���̌�����\���A���͏t������Ƃ����čb�B���V�̑�S���ł������B�����c���̎��A������Ǝ��ɕʂ�A
�o���Ɠc�n�̌����i�ٔ��j�����������A���͕������B
���̎��A�����̏���u�����g���ׂ��v�Ƃ̏�ӂ��L��A�M������N��\��A���͏\�Z�ɂāA������
���o�A�䏬�l�Ƃ��ē��������Ƃ��ǂ��d���ł��������߂ɁA���l�O�ɐ���悤�ɂƁA�����Ƃ̊O��
�o�����A�O�\���̊ԂɋߏK�ƂȂ���A��X�ɉ��֏�����A��G���ɂČ����d�����B
������@�������ѕ���������낤���B
���͐M�����̌�ӂȂǂɑ��Ⴕ�A���ɂЂƌ��������Ă�悤�Ȏ��͖��������B
�A�X�����������A�t���e���ƍ������A�J���̏�ɍ����u����A�����͊C�Â̍���̐ՖڂƂȂ�A
����e���ƌĂ�Ă���B
���Ɏ��͌����ɔ��o�Ă���A��\�l�A�܂܂ł͏��T�y�̍����Ɂu���̂悤�Ȃق�ҁi�����ҁj��
���旧�ĂɂȂ�̂́A�ɐM�����̌�ڈႢ�ł���B�v�ƁA�㉺�̍������������B
���ꂪ�䂪���g�̖�ƂȂ����B��O���Ⴆ�A�M�����̌�ڈႢ���ƌ����Ȃ��悤�ɂƁA��w
�����ɐ����o�����̂��B
�w�b�z�R�Ӂx
����e���̑O�����̏q��
�e�ׂ͉��X�ɂ����ē��q���̋Y���Ɂw�ۉȒe�����e���A����e���ɂ��e���x�Ɛ\���Ȃ�킵�Ă���قǂł���B
���̌�����\���A���͏t������Ƃ����čb�B���V�̑�S���ł������B�����c���̎��A������Ǝ��ɕʂ�A
�o���Ɠc�n�̌����i�ٔ��j�����������A���͕������B
���̎��A�����̏���u�����g���ׂ��v�Ƃ̏�ӂ��L��A�M������N��\��A���͏\�Z�ɂāA������
���o�A�䏬�l�Ƃ��ē��������Ƃ��ǂ��d���ł��������߂ɁA���l�O�ɐ���悤�ɂƁA�����Ƃ̊O��
�o�����A�O�\���̊ԂɋߏK�ƂȂ���A��X�ɉ��֏�����A��G���ɂČ����d�����B
������@�������ѕ���������낤���B
���͐M�����̌�ӂȂǂɑ��Ⴕ�A���ɂЂƌ��������Ă�悤�Ȏ��͖��������B
�A�X�����������A�t���e���ƍ������A�J���̏�ɍ����u����A�����͊C�Â̍���̐ՖڂƂȂ�A
����e���ƌĂ�Ă���B
���Ɏ��͌����ɔ��o�Ă���A��\�l�A�܂܂ł͏��T�y�̍����Ɂu���̂悤�Ȃق�ҁi�����ҁj��
���旧�ĂɂȂ�̂́A�ɐM�����̌�ڈႢ�ł���B�v�ƁA�㉺�̍������������B
���ꂪ�䂪���g�̖�ƂȂ����B��O���Ⴆ�A�M�����̌�ڈႢ���ƌ����Ȃ��悤�ɂƁA��w
�����ɐ����o�����̂��B
�w�b�z�R�Ӂx
����e���̑O�����̏q��
396�l�Ԏ����l�N
2022/09/16(��) 20:21:16.97ID:ph509oAr �������A�t�B�J�X����Ȃ���
���̃X���ɓ������Ăǂ�ȃR�����g�ڂ����
���ڎ����̃T�C�g�ɍڂ��邾���ł�������
���̃X���ɓ������Ăǂ�ȃR�����g�ڂ����
���ڎ����̃T�C�g�ɍڂ��邾���ł�������
397�l�Ԏ����l�N
2022/09/16(��) 21:01:41.73ID:70ioijqF �u����G�ځv����c���g���Ɗ_���ےÎ�(�_�������H)
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-8387.html
�̂悤�ɔ_�v����߂āA�{���p���ɂ͂��ߑ������Ƃ��Ďd���������A�����Ɍp���ɂ��u���������x�̊�ł͂Ȃ��v�ƔF�߂��k�m�ƂȂ����B
���̂̂��˔\�E�����ɂ��ƘV�Ƃ��ē��ܕS���^����ꂽ�B
�G�g���������̊_���ےÎ���U�߂����̂��ƁA���łɏ�̕�͓͂˔j���ꂽ���ߐےÎ�͊o������߂Ď��n���悤�Ƃ����B
�����֏钆��ԏ�肵���c���g���͐ےÎ�ɑ��đ��������B
�ےÎ�����ʼn��킵�A�������܂������Ȃ������ɏG�g���̎g��������
�u���̂��ъ_������������������������̂͌����ł���B
����܂ł̙�������A�{�̏\�����g���悤�v�ƌ����Ă����B
���̂��ߋg�����ےÎ���킢����߂��B
�ےÎ�͏G�g���ɉy�����A�g���̌��т��q�ׂ��B
�G�g���͑傢�Ɋ����ċg���������o���A���̂̂��O�͊������Ƃ��Ďl����^�����B
�c���g�����\���̎��ɔ_�v�����߂āA�l����̂���܂ŁA�킸���Z�N����ł������B
(�c���g���͕���1548�N���܂�Ƃ���Ă��邪
�u����G�ځv�̋L���ł́u�c���g�����\���̎��ɋ{���p��(��)�Ɏd�����v�Ƃ��Ă��邽��
�{���p����1580�N�ɒA�n�L�����Ƃ��ēΎ��ł��邱�Ƃ���l����ƁA�u����G�ځv�ł͓c���g���̐��N��1563�N���Ƃ��Ă���悤��)
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-8387.html
�̂悤�ɔ_�v����߂āA�{���p���ɂ͂��ߑ������Ƃ��Ďd���������A�����Ɍp���ɂ��u���������x�̊�ł͂Ȃ��v�ƔF�߂��k�m�ƂȂ����B
���̂̂��˔\�E�����ɂ��ƘV�Ƃ��ē��ܕS���^����ꂽ�B
�G�g���������̊_���ےÎ���U�߂����̂��ƁA���łɏ�̕�͓͂˔j���ꂽ���ߐےÎ�͊o������߂Ď��n���悤�Ƃ����B
�����֏钆��ԏ�肵���c���g���͐ےÎ�ɑ��đ��������B
�ےÎ�����ʼn��킵�A�������܂������Ȃ������ɏG�g���̎g��������
�u���̂��ъ_������������������������̂͌����ł���B
����܂ł̙�������A�{�̏\�����g���悤�v�ƌ����Ă����B
���̂��ߋg�����ےÎ���킢����߂��B
�ےÎ�͏G�g���ɉy�����A�g���̌��т��q�ׂ��B
�G�g���͑傢�Ɋ����ċg���������o���A���̂̂��O�͊������Ƃ��Ďl����^�����B
�c���g�����\���̎��ɔ_�v�����߂āA�l����̂���܂ŁA�킸���Z�N����ł������B
(�c���g���͕���1548�N���܂�Ƃ���Ă��邪
�u����G�ځv�̋L���ł́u�c���g�����\���̎��ɋ{���p��(��)�Ɏd�����v�Ƃ��Ă��邽��
�{���p����1580�N�ɒA�n�L�����Ƃ��ēΎ��ł��邱�Ƃ���l����ƁA�u����G�ځv�ł͓c���g���̐��N��1563�N���Ƃ��Ă���悤��)
398�l�Ԏ����l�N
2022/09/17(�y) 05:49:14.04ID:wtY/uD3Z >>396
�E���R����D���Ȃ̂��o���čr�炵�Ă�̂�w
�E���R����D���Ȃ̂��o���čr�炵�Ă�̂�w
399�l�Ԏ����l�N
2022/09/17(�y) 12:24:41.50ID:Aj8vbOK9 �E���R�~���W���N�������p����
400�l�Ԏ����l�N
2022/09/17(�y) 13:27:38.95ID:lvSZvB0W �������������ّn��150�N�L�O ���ʓW�u���� �������������ق̂��ׂāv
https://tohaku150th.jp/
�����@10��18���i�j~12��11���i���j
����50�N�͊�悳��Ȃ��K�͂������ŁA��͂荡�s����������܂���B
�퍑����E����W�Ɍ��肷��ƛ����G�������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂����A����19����
���ʎ��́u�����̊ԁv�œW���Ƃ̂��ƁB
���ʓW�S���̍����w�|���͓����E�b�h�̃G�L�X�p�[�g�Ȃ̂Ŋ��ґ�ł��ˁB
�i�X���ɉ����O�̏o�Ă�����{�b�h������ۑ�����o�[�ł�����܂��j
https://tohaku150th.jp/
�����@10��18���i�j~12��11���i���j
����50�N�͊�悳��Ȃ��K�͂������ŁA��͂荡�s����������܂���B
�퍑����E����W�Ɍ��肷��ƛ����G�������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂����A����19����
���ʎ��́u�����̊ԁv�œW���Ƃ̂��ƁB
���ʓW�S���̍����w�|���͓����E�b�h�̃G�L�X�p�[�g�Ȃ̂Ŋ��ґ�ł��ˁB
�i�X���ɉ����O�̏o�Ă�����{�b�h������ۑ�����o�[�ł�����܂��j
401�l�Ԏ����l�N
2022/09/17(�y) 14:14:52.92ID:pO7rUd5j ������H
��ʎВc�@�l���{�������w��@Japan Academy of Poop culture
�E���R��D���W���b�vwwwww
��ʎВc�@�l���{�������w��@Japan Academy of Poop culture
�E���R��D���W���b�vwwwww
402�l�Ԏ����l�N
2022/09/19(��) 15:30:28.02ID:tM2mpAZc �ǂ��叫�Ƃ́A�Ⴆ����̎��A�������g�̍єz�ŏ������Ƃ��Ă��A��̎蕿�Ƃ͂����A
�ߏK�A�����A���a���A��}�A���l�A���ԏO�܂ł��J�߂��āA�F�A�ނ�̓����ɂ���č����
�������̂��Ƌ��ɐ���B�̂ɂ��̂悤�ȑ叫�̉��ɂ́A�喼�A�����A���y�A�k��}�A���l�A
���ԏO�܂ŁA���ӊo���̎ґ����o����̂̂��B
�R��Ε��c�M�����͂��̂悤�ɐ��ꂽ
�u�叫���n�ɏ���āi�o�n���āj�ȍ~�́A�k��}�A���ԁA���҂͐g�߂��҂ł���B�v�Ƃ��āA
���l�O�A���l�A���ԏO�Ɉ�w�O�������A�ڗ������Ȃē��l�O��ڕt�A���ڂƖ��t�����
�������킹�A�S�y���L��s��������ΖJ����^����ꂽ�B
�̂Ɍ�ɂ͂��̎ҋ��A���ɂ����Ėڂ������قǂ̕��ӂ̎蕿�����D���x���v�����B
�����������҂���l�O���Ƃ��A���l�A���Ԃ̏ꍇ�͏��l�����ǂƖ��t���A�m�s��������A
�n�ɏ��A���l�O���͓k��}���\�l�A��\�l����a����A���l���͏��l�A���Ԃ�
��\�l�A�O�\�l����a�������B
���̂悤�Ȏ҂����l�O�ɏ\�R�A���l���ɏ\�R�������B
����ɂ���āA�M�����̓k��}�A���l�A���ԏO�́A�i�o���́j�]�݂𑶂��S������̂ɁA���������̐��s���܂�
�܁A�Z�x�Ȃ���d��Ȃ������҂͗]�苏�Ȃ������B
���̂悤�ł������̂ŁA���݂��ڕt�͓��l�O�A���̉��ڂ͏��l���ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M���́A�����̎ҒB�̎g�����ɂ��āB
�ߏK�A�����A���a���A��}�A���l�A���ԏO�܂ł��J�߂��āA�F�A�ނ�̓����ɂ���č����
�������̂��Ƌ��ɐ���B�̂ɂ��̂悤�ȑ叫�̉��ɂ́A�喼�A�����A���y�A�k��}�A���l�A
���ԏO�܂ŁA���ӊo���̎ґ����o����̂̂��B
�R��Ε��c�M�����͂��̂悤�ɐ��ꂽ
�u�叫���n�ɏ���āi�o�n���āj�ȍ~�́A�k��}�A���ԁA���҂͐g�߂��҂ł���B�v�Ƃ��āA
���l�O�A���l�A���ԏO�Ɉ�w�O�������A�ڗ������Ȃē��l�O��ڕt�A���ڂƖ��t�����
�������킹�A�S�y���L��s��������ΖJ����^����ꂽ�B
�̂Ɍ�ɂ͂��̎ҋ��A���ɂ����Ėڂ������قǂ̕��ӂ̎蕿�����D���x���v�����B
�����������҂���l�O���Ƃ��A���l�A���Ԃ̏ꍇ�͏��l�����ǂƖ��t���A�m�s��������A
�n�ɏ��A���l�O���͓k��}���\�l�A��\�l����a����A���l���͏��l�A���Ԃ�
��\�l�A�O�\�l����a�������B
���̂悤�Ȏ҂����l�O�ɏ\�R�A���l���ɏ\�R�������B
����ɂ���āA�M�����̓k��}�A���l�A���ԏO�́A�i�o���́j�]�݂𑶂��S������̂ɁA���������̐��s���܂�
�܁A�Z�x�Ȃ���d��Ȃ������҂͗]�苏�Ȃ������B
���̂悤�ł������̂ŁA���݂��ڕt�͓��l�O�A���̉��ڂ͏��l���ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M���́A�����̎ҒB�̎g�����ɂ��āB
403�l�Ԏ����l�N
2022/09/20(��) 04:00:38.68ID:K/ArZKdS ���W���b�v����̒��H
tps://i.imgur.com/n92bj8U.jpg
tps://i.imgur.com/n92bj8U.jpg
404�l�Ԏ����l�N
2022/09/20(��) 17:04:41.30ID:vpd1SmTs ���㎛�ɂ��ď����ꂽ�u�O���R�L�v���瑝�㎛��㐢�Z���E���_��c(1515-1574)�ɂ���
�a�̐��܂�ŁA�o�Ƃ̂̂��\���̎��Ɋ֓��ɏo�đ��㎛�ŝܗ_��l�Ɋw�Ԃ��Ƌ�N�A
�t�̖��Ő��@�����邽�߂ɍ����ɏ����r���Ō��t�ɋl�܂�A���Ԃ����čQ�Ă����߁A�傢�ɂ�������ꂽ�B
���̂��ߍĂяC�s�̂��ߗ��ɏo�āA���c�s�����ɎQ�w���邱�Ɠ�\����A�������Ƃ��Ă����Ƃ��뗘�E��(�s���E�݂�)�̓��������s�����������ꂽ�B
�s�������́u�����A���A�ǂ���̌���ۂނ��H�v�Ɛq�˂Ă����B
���_���u�����v�Ɠ�����ƕs�������͗������͂炢���_�̍A�����B
�����Ĉꏡ���܂�̌���f�����Ƃ���œ��_�͖ڊo�߂����A�ɂ݂͊������Ȃ������B
���̎�����o�T����X�����s�����u���A�����ɒʂ���悤�ɂȂ����Ƃ����B
�Ȃ���O�\�Z���Z���ŗ݃����`���␅�q���{�ŗL���ȗS�V��l�ɂ������b������悤��
�a�̐��܂�ŁA�o�Ƃ̂̂��\���̎��Ɋ֓��ɏo�đ��㎛�ŝܗ_��l�Ɋw�Ԃ��Ƌ�N�A
�t�̖��Ő��@�����邽�߂ɍ����ɏ����r���Ō��t�ɋl�܂�A���Ԃ����čQ�Ă����߁A�傢�ɂ�������ꂽ�B
���̂��ߍĂяC�s�̂��ߗ��ɏo�āA���c�s�����ɎQ�w���邱�Ɠ�\����A�������Ƃ��Ă����Ƃ��뗘�E��(�s���E�݂�)�̓��������s�����������ꂽ�B
�s�������́u�����A���A�ǂ���̌���ۂނ��H�v�Ɛq�˂Ă����B
���_���u�����v�Ɠ�����ƕs�������͗������͂炢���_�̍A�����B
�����Ĉꏡ���܂�̌���f�����Ƃ���œ��_�͖ڊo�߂����A�ɂ݂͊������Ȃ������B
���̎�����o�T����X�����s�����u���A�����ɒʂ���悤�ɂȂ����Ƃ����B
�Ȃ���O�\�Z���Z���ŗ݃����`���␅�q���{�ŗL���ȗS�V��l�ɂ������b������悤��
405�l�Ԏ����l�N
2022/09/20(��) 17:55:41.34ID:vpd1SmTs �u�S�V�L�v���ƗS�V�͕s���������Ă蓰�œ�\����f�H�����Ƃ��A�s���������I�����̂����݂̌��ł͂Ȃ��A
�u���Z�̗����̂����ǂ����ۂނ��H�v�ƕs���������q�˂��Ƃ���
�S�V���u��������ۂ݂܂��v�Ɠ��������ƂɂȂ��Ă��āA���_�Ƃ͏���������B
�u���Z�̗����̂����ǂ����ۂނ��H�v�ƕs���������q�˂��Ƃ���
�S�V���u��������ۂ݂܂��v�Ɠ��������ƂɂȂ��Ă��āA���_�Ƃ͏���������B
406�l�Ԏ����l�N
2022/09/21(��) 21:48:01.96ID:PlgFYXfo �y�ߕ�z 11�Ώ����u�j���ɓ������瓐�B����܂����E�E�E�C���������v
�������t�E�����|���m�֎~�@�ᔽ�̋^���ō�N�P�P���U���A���{�x�ɏ��ޑ������ꂽ�͎̂��q���̒j�i�R�X�j
�@��N�W���A�j�͑��s�Q����̓����{�݂ŁA���e�ƈꏏ�ɒj���ɂ��������i�P�P�j��_�����B
���e�͓������A����ڂŒǂ��j�̎����������A�������u�C���������v�ƕ��e�ɑ��k�B
���������x���ړ����Ă��A�Ȃ����߂��ɒj�������B
�s�C���Ɋ������Q�l�͗�����o�����A���̒j�͒E�ߏ�ŃX�}�z�̃J���������肰�Ȃ������Ɍ����Ă����B
9���������ėǂ�������
�������t�E�����|���m�֎~�@�ᔽ�̋^���ō�N�P�P���U���A���{�x�ɏ��ޑ������ꂽ�͎̂��q���̒j�i�R�X�j
�@��N�W���A�j�͑��s�Q����̓����{�݂ŁA���e�ƈꏏ�ɒj���ɂ��������i�P�P�j��_�����B
���e�͓������A����ڂŒǂ��j�̎����������A�������u�C���������v�ƕ��e�ɑ��k�B
���������x���ړ����Ă��A�Ȃ����߂��ɒj�������B
�s�C���Ɋ������Q�l�͗�����o�����A���̒j�͒E�ߏ�ŃX�}�z�̃J���������肰�Ȃ������Ɍ����Ă����B
9���������ėǂ�������
407�l�Ԏ����l�N
2022/09/22(��) 01:32:15.59ID:4T9UE/mR ���̌�������������܂���
https://i.imgur.com/Yenxs6Z.jpg
https://i.imgur.com/Yenxs6Z.jpg
408�l�Ԏ����l�N
2022/09/22(��) 12:06:01.19ID:kvYFseLK ���j�̋��ȏ��ɐV����1�y�[�W�����������
409�l�Ԏ����l�N
2022/09/22(��) 18:18:45.76ID:ja2k1gBw �Q�n���@�O���s�����T�C�g
�u��3�� �O���ˎ� ������a��ƌ����Ձv���J�Â��܂�
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/bunkasupotsukanko/bunkakokusai/gyomu/1/1/30206.html
�����Ƃ̖���u�����v�������@�̏���I�����ɁA�V���O�����E���n�̑��Ȃǂ̏����Ɗ֘A�j�������ԓW���B
�ŏI���ɂ́A�����ƌ����傪�o������g�u�����v�������@����I�ڍu����h��A�����Ƃ䂩��̓S�C���ɂ��
�唗�͂̉Γ�e���������{���܂��I
�C�x���g�Q����ʂ��āA�O���̗��j��̊����Ă��������B
�ߘa4�N9��23���i���j���j~10��2���i���j���j�����j���x��
�ߑO9��~�ߌ�5���i����4��30���܂ŁB�������A�ŏI���͌ߌ�3����ƂȂ�܂��j
���@�Ս]�t�ʊ� 1�K ���m�� �i�O���s��蒬3����15-3�j
�W�����e
�E�����Ɩ���u�����v�������@�i��10��2���̌ߑO���͍u����Ŕ�I���邽�߁A�W�����ł͂������������܂���j
�E�V���O���� ���n�̑��i�����j�A���n�̑��i���v���J�j�������i�͓��b��ɂ��^���A���v���J�͓S�H������̖͋[���ł��B
�E����A����
�E����������̌R�z�Ɛw�H�D�i�s�w��d�v�������u�O���ˎ叼���Ɛw�H�D�E�R�z�v�j
�E�O���s�o�g���� �����P�� ��i
�E�O���s���������ށA�O���s���}���ُ����̏����Ǝj�� �ق�
�u��3�� �O���ˎ� ������a��ƌ����Ձv���J�Â��܂�
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/bunkasupotsukanko/bunkakokusai/gyomu/1/1/30206.html
�����Ƃ̖���u�����v�������@�̏���I�����ɁA�V���O�����E���n�̑��Ȃǂ̏����Ɗ֘A�j�������ԓW���B
�ŏI���ɂ́A�����ƌ����傪�o������g�u�����v�������@����I�ڍu����h��A�����Ƃ䂩��̓S�C���ɂ��
�唗�͂̉Γ�e���������{���܂��I
�C�x���g�Q����ʂ��āA�O���̗��j��̊����Ă��������B
�ߘa4�N9��23���i���j���j~10��2���i���j���j�����j���x��
�ߑO9��~�ߌ�5���i����4��30���܂ŁB�������A�ŏI���͌ߌ�3����ƂȂ�܂��j
���@�Ս]�t�ʊ� 1�K ���m�� �i�O���s��蒬3����15-3�j
�W�����e
�E�����Ɩ���u�����v�������@�i��10��2���̌ߑO���͍u����Ŕ�I���邽�߁A�W�����ł͂������������܂���j
�E�V���O���� ���n�̑��i�����j�A���n�̑��i���v���J�j�������i�͓��b��ɂ��^���A���v���J�͓S�H������̖͋[���ł��B
�E����A����
�E����������̌R�z�Ɛw�H�D�i�s�w��d�v�������u�O���ˎ叼���Ɛw�H�D�E�R�z�v�j
�E�O���s�o�g���� �����P�� ��i
�E�O���s���������ށA�O���s���}���ُ����̏����Ǝj�� �ق�
410�l�Ԏ����l�N
2022/09/22(��) 18:20:07.16ID:ja2k1gBw ���O���E��z�ˎ�̏�����a��Ƃ͌���G�N�̎q���ŁA�G�N���{�q���g�����֓��̖��ƌ��鎁�̍��J���p���ƌn�B
�������𖼏��������Ɩ䂾���͌��鎁�̂��̂ł��B
�u�������@�v�̖��́A������������ꎁ�������������̂���ɍ匴�������N���̎�ɓn��A�N������
���R�ƂɌ��コ�ꂽ�Ƃ����`������Ƃ����B
�Ȃ�����ɏo���ꂽ���͕s�������A������a��Ƃ���������ōw�����A�Ȍ�͌���`���̖����u���n�v��
�Ƃ��ɉƕ�ƂȂ������A�c�O�Ȃ��瓌����P�ŋ��ɏĎ����Ă��܂����B
���̎��A���q�ȗ��̌��鎁�̌Õ���������ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
2016�N�Ɍ��n�Ǝ������@�̕������A�O���o�g�E�ݏZ�̓��H�����P�����ƁA���̎t���̏�эP�����i�R�`�s�j�����������A
2022�N���Ɏ������@�̕������������܂����B
�����܂łɎ���o�܂͂��낢��Ƃ�����̂́A���������ł̓����t�@���������_�@�ƂȂ����̂͊ԈႢ�Ȃ��A
�u�[���̂܂��܂��̌p�����肤�Ƃ���ł��B
wikipedia�������@
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%8F%E9%83%A8%E6%AD%A3%E5%AE%97
wikipedia���n
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%89%8B%E6%9D%B5
�������𖼏��������Ɩ䂾���͌��鎁�̂��̂ł��B
�u�������@�v�̖��́A������������ꎁ�������������̂���ɍ匴�������N���̎�ɓn��A�N������
���R�ƂɌ��コ�ꂽ�Ƃ����`������Ƃ����B
�Ȃ�����ɏo���ꂽ���͕s�������A������a��Ƃ���������ōw�����A�Ȍ�͌���`���̖����u���n�v��
�Ƃ��ɉƕ�ƂȂ������A�c�O�Ȃ��瓌����P�ŋ��ɏĎ����Ă��܂����B
���̎��A���q�ȗ��̌��鎁�̌Õ���������ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
2016�N�Ɍ��n�Ǝ������@�̕������A�O���o�g�E�ݏZ�̓��H�����P�����ƁA���̎t���̏�эP�����i�R�`�s�j�����������A
2022�N���Ɏ������@�̕������������܂����B
�����܂łɎ���o�܂͂��낢��Ƃ�����̂́A���������ł̓����t�@���������_�@�ƂȂ����̂͊ԈႢ�Ȃ��A
�u�[���̂܂��܂��̌p�����肤�Ƃ���ł��B
wikipedia�������@
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%8F%E9%83%A8%E6%AD%A3%E5%AE%97
wikipedia���n
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%89%8B%E6%9D%B5
411�l�Ԏ����l�N
2022/09/22(��) 18:55:02.73ID:GKkWpaVQ �ǂ��������b�ȂH
412�l�Ԏ����l�N
2022/09/22(��) 19:59:55.16ID:M0b9Mbse �����āA���l�������悤�Ɏd��҂��u���܍D���v�ƍl���A�����@�x�ɋ��t������Ȃ�A
���l�̍�@���ǂ��Ȃ�A�l���������Ƃ������Ȃ�B���𗧂ĂȂ���Ό��܂̗L��ׂ��e�ׂ��Ȃ��B
�K���A���c�Ƃ̌�a�͌����Ɓi���R�Ɓj�̍�@�ł���B�����̌䉮�`����́A��ꏔ�l�̕t��������
���O�̖������Ƃ��̗v�ƍl���Ă���̂ɁA�������f��v�������́A����������悤�ɑ����Ă���B
����͒������q�ɂāA�����������n�܂����B���̌�A���������������̐}���Ȃēs�ɂđ���ꂽ�B
���`����ɂ��āA�l�X�ɗ��O���������|�Ƃ��Đv����̂��A�����Ƃ̉��`����Ȃ̂ł���B
���̎��ɂ��āA�����⌴���l�i�����j�����c���Ɍ�g�҂Ƃ��Č����킳�ꂽ�ہA���c�M������
��ӂ��ȂāA�A��Ɋ��q�������d�����B���̊��q�͐₦�ċv�����A���̐Ղ����邱�Ƃ͏o���Ȃ������B
�ł͂����������̒n�̒��l�A�S�����ɁA���ƌ���Ί}��E���n���~��A�����ɂ�����Ȃ�
���S���̍�@�ł������ƁA���l�͋A����M�����Ɍ��サ���B�M�����͂��������
�u���ɂ��ւ̗������̂܂育�ƁA�����X�����A�ȗ������������̎d�u�A���Ɏc���Ă��̂悤�Ȃ̂��A
�����Ă��������������ώ@�����̂͐S�̕t�������ł���B�v
������������A���l�a�ɂ��Ďߐ��炸���S���ꂽ���Ƃ��A���ꂪ���i����e���j�͗ǂ��o���Ă���B
�w�b�z�R�Ӂx
�����Ƃ̉��`���ɂ���
���l�̍�@���ǂ��Ȃ�A�l���������Ƃ������Ȃ�B���𗧂ĂȂ���Ό��܂̗L��ׂ��e�ׂ��Ȃ��B
�K���A���c�Ƃ̌�a�͌����Ɓi���R�Ɓj�̍�@�ł���B�����̌䉮�`����́A��ꏔ�l�̕t��������
���O�̖������Ƃ��̗v�ƍl���Ă���̂ɁA�������f��v�������́A����������悤�ɑ����Ă���B
����͒������q�ɂāA�����������n�܂����B���̌�A���������������̐}���Ȃēs�ɂđ���ꂽ�B
���`����ɂ��āA�l�X�ɗ��O���������|�Ƃ��Đv����̂��A�����Ƃ̉��`����Ȃ̂ł���B
���̎��ɂ��āA�����⌴���l�i�����j�����c���Ɍ�g�҂Ƃ��Č����킳�ꂽ�ہA���c�M������
��ӂ��ȂāA�A��Ɋ��q�������d�����B���̊��q�͐₦�ċv�����A���̐Ղ����邱�Ƃ͏o���Ȃ������B
�ł͂����������̒n�̒��l�A�S�����ɁA���ƌ���Ί}��E���n���~��A�����ɂ�����Ȃ�
���S���̍�@�ł������ƁA���l�͋A����M�����Ɍ��サ���B�M�����͂��������
�u���ɂ��ւ̗������̂܂育�ƁA�����X�����A�ȗ������������̎d�u�A���Ɏc���Ă��̂悤�Ȃ̂��A
�����Ă��������������ώ@�����̂͐S�̕t�������ł���B�v
������������A���l�a�ɂ��Ďߐ��炸���S���ꂽ���Ƃ��A���ꂪ���i����e���j�͗ǂ��o���Ă���B
�w�b�z�R�Ӂx
�����Ƃ̉��`���ɂ���
413�l�Ԏ����l�N
2022/09/25(��) 07:18:45.87ID:2kIRZglE �w�@�Ɖ@�L�^�x���
���̐g��S�z����H�M���̂�����Ƃ����b(�L���Șb�ł����܂Ƃ߂ɂȂ������̂ňꉞ)
���V���\�N�����A�M�������y�Ŕq��������ƂɋL���ꂽ�L��
����l�����Ƃ���ɂ��ƁA��N�̓~�ɒÓc�M��������(��a)��q�̂������ƐM���Ɋ肢�o��
�u��l�v(�M��)�́u��a�͐_���ł���A������q�ׂ�����B���̍��̏Z���͂悭�m���Ă���v�|�̘b�����A�����r�����̂ŁA�d�˂đi���͂��Ȃ�����
�M���������������R�́A��N�Ɍ��c(��)�������a�x�z�̂��߂ɔz�u�����Ƃ���A�قǂȂ����(�ΎR�{�莛)�œ������ɂ���
���̑O�̏��i�ȗ��A���Ƃ������ɗ�������Ƃ��Ƃ��Ƃ��ގU���Ă���̂ŁA���M�������������b���Ă��邩�炾�낤�Ƃ������Ƃ�����
���̐g��S�z����H�M���̂�����Ƃ����b(�L���Șb�ł����܂Ƃ߂ɂȂ������̂ňꉞ)
���V���\�N�����A�M�������y�Ŕq��������ƂɋL���ꂽ�L��
����l�����Ƃ���ɂ��ƁA��N�̓~�ɒÓc�M��������(��a)��q�̂������ƐM���Ɋ肢�o��
�u��l�v(�M��)�́u��a�͐_���ł���A������q�ׂ�����B���̍��̏Z���͂悭�m���Ă���v�|�̘b�����A�����r�����̂ŁA�d�˂đi���͂��Ȃ�����
�M���������������R�́A��N�Ɍ��c(��)�������a�x�z�̂��߂ɔz�u�����Ƃ���A�قǂȂ����(�ΎR�{�莛)�œ������ɂ���
���̑O�̏��i�ȗ��A���Ƃ������ɗ�������Ƃ��Ƃ��Ƃ��ގU���Ă���̂ŁA���M�������������b���Ă��邩�炾�낤�Ƃ������Ƃ�����
414�l�Ԏ����l�N
2022/09/25(��) 07:37:48.79ID:2kIRZglE �����b�ł��Ȃ������ł�
�w�@�Ɖ@�L�^�x���
�ǂ��̍��̕������������ア���Ƃ����s�тȋc�_�̈�Ɏg���镔����������
(�D�c�ɂ��b�B�����̓�����)�u���͏O�E�������V�O����������X�������f�V�R��A�b��E�z��V�|��V����V�R�m�V�R�����A��厖�V�w����v
���������u�����v�������ɂ������Ƃ������x�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A����
�w�@�Ɖ@�L�^�x���
�ǂ��̍��̕������������ア���Ƃ����s�тȋc�_�̈�Ɏg���镔����������
(�D�c�ɂ��b�B�����̓�����)�u���͏O�E�������V�O����������X�������f�V�R��A�b��E�z��V�|��V����V�R�m�V�R�����A��厖�V�w����v
���������u�����v�������ɂ������Ƃ������x�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A����
415�l�Ԏ����l�N
2022/09/25(��) 15:45:39.91ID:H154cQhb �����ǂ��o���ď���������a��[��
416�l�Ԏ����l�N
2022/09/26(��) 19:41:34.05ID:Fry+9SaN ���R�c��O�Y�i�M�L�j�̏��R�c�Ƃ́A�b�B�S����M�����̏\���O��艺����āA�s���S�ɍݏ邵�Ă����B
���̎e�ׂ́A���R�c�̐�c�͍s�l�ł���A�܂����̍��A���c�a�͌�S�l����Ă��āA��������R�ɂ�����
���̍s�l�ɏo������B
�u���̕��͉���̐l���v
���c�a�������q�˂�ƁA���́u�b�B�̎ҁv�Ɛ\�����B�����ĕ��c�a�����g���S�l���Ă��邱�Ƃ�
���ɂȂ������A���̐��́u���ɂĂ��A�����ɑ�����܂��傤�B�v�Ɛ\�����B
����ƕ��c�a��
�u�b�B���̎R�̌��̑吙�ɁA����E�|�����B���u���Ă���B���������Ă��Ă���Ȃ����B�v
�Ƌ��ɂȂ�ƁA���͂����ɂ�������������\���A�}���b�B�֎Q�����E�|��������ċA��A
���c�a�i�サ���B���̎����c�a�͔ނɁA�u�b�B��D�҂���Ƃ����{�ӂ�����A
�s���S�����̐��ɉ������ׂ��B�v�Ɩ����B
���N�A���c�a�͌�{�ӂ𐋂����A���̐��Ɂu���R�c�v�𖼏�点�A�s���S��������A
���̏�Ƃ��āu�M�v�̎��������ꂽ�B���R�c�Ƃ̗R���͂��̎����n�܂����̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
���̘S�l���Ă������c�a���āA�\���]�X�͂Ƃ������A���c�M�d�̎��ł�����
���̎e�ׂ́A���R�c�̐�c�͍s�l�ł���A�܂����̍��A���c�a�͌�S�l����Ă��āA��������R�ɂ�����
���̍s�l�ɏo������B
�u���̕��͉���̐l���v
���c�a�������q�˂�ƁA���́u�b�B�̎ҁv�Ɛ\�����B�����ĕ��c�a�����g���S�l���Ă��邱�Ƃ�
���ɂȂ������A���̐��́u���ɂĂ��A�����ɑ�����܂��傤�B�v�Ɛ\�����B
����ƕ��c�a��
�u�b�B���̎R�̌��̑吙�ɁA����E�|�����B���u���Ă���B���������Ă��Ă���Ȃ����B�v
�Ƌ��ɂȂ�ƁA���͂����ɂ�������������\���A�}���b�B�֎Q�����E�|��������ċA��A
���c�a�i�サ���B���̎����c�a�͔ނɁA�u�b�B��D�҂���Ƃ����{�ӂ�����A
�s���S�����̐��ɉ������ׂ��B�v�Ɩ����B
���N�A���c�a�͌�{�ӂ𐋂����A���̐��Ɂu���R�c�v�𖼏�点�A�s���S��������A
���̏�Ƃ��āu�M�v�̎��������ꂽ�B���R�c�Ƃ̗R���͂��̎����n�܂����̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
���̘S�l���Ă������c�a���āA�\���]�X�͂Ƃ������A���c�M�d�̎��ł�����
417�l�Ԏ����l�N
2022/09/26(��) 20:07:52.91ID:DvsscTwE �v���Ԃ�ɃT�C�g������R�����g���ĂȂ��̂��܂Ƃ߂Ăă����^
�A�t�B�J�X���ċ@�B�I�ȍ�ƂɂȂ邩�炻�ꂪ�Ӗ����邩�Ƃ��l���Ȃ����
���ڎ����̃T�C�g�ɏ��������̂ɂ�������
�����������N�L�ڂȂ�������5ch�A�t�B�T�C�g�K��Ɉᔽ���Ă邩��
�^�c�Ƀ`�N������ꔭ�A�E�g
�A�t�B�J�X���ċ@�B�I�ȍ�ƂɂȂ邩�炻�ꂪ�Ӗ����邩�Ƃ��l���Ȃ����
���ڎ����̃T�C�g�ɏ��������̂ɂ�������
�����������N�L�ڂȂ�������5ch�A�t�B�T�C�g�K��Ɉᔽ���Ă邩��
�^�c�Ƀ`�N������ꔭ�A�E�g
418�l�Ԏ����l�N
2022/09/26(��) 20:43:56.41ID:yZbBANHU �ʕƂ�
419�l�Ԏ����l�N
2022/09/28(��) 21:56:23.61ID:TRfck96B �w���Ɩ�b�x���
�V������Ƃ����̖����A�Ƃ������b
�����̂ŗv��A�������������̂ݓǂ݉���
�G�������ŘA���������ɂȂ�����쒷���e�q
�Γc�����Ƒ��c�E�q��ƒ���������������A����(�K��)���n�̗��Ƃ𗊂���
���Ƃ͂��������A�G�g�Ɩk�����𖧂��ɖK�˂悤�Ƃ���
����ƁA������̏��O�ɂ͔����g�̑����킴�Ƃ����������ł���A��s�����������Ă���悤������
������������Ƃ͏�蕨���牺��āA���{����
�u���̂�牽������B���͓��{�̎��͐\���ɋy���A���܂ŏ]�В��A���e��(����)���q���̎ҁA���R�s�͂̎��ɋɂ�䐬�s�Ȃ���Ƃ����ۂɔ��g���d�܂邱�ƁA���Ă����Ă������̌���Ȃ�B���l�̎����Ε�s�̓z���m��܂��B�Z�p�̎���l�̌��ɂĒɂ��\�����Ȃǂ͑����ׂ��v�Ɖ������炩�Ɏ�����
�u���̂��߁B���̑��̏�͂߂܂���(�����肭�炢�̈ӂ�)���v�Ɠ{��ƁA��Ќ�������ĕ�s�O�͘E�̒��ŏ����ɂȂ�A�u����͂ߌ�ւ���͂ߌ�ցv�Ɛ\�����̂ŁA�����Ə���͂߂�
�������Ă������̂́A���悤�ɋC���̂悢���Ƃ͌������������Ƃ��Ȃ��A���߂Č����Ƙb����
�Ȃ��A�O��Ɉ�L�Ȃ�҂��u�������v�������Ƃ����ł����A����͂Ȃ�Ȃ�ł��傤��
�V������Ƃ����̖����A�Ƃ������b
�����̂ŗv��A�������������̂ݓǂ݉���
�G�������ŘA���������ɂȂ�����쒷���e�q
�Γc�����Ƒ��c�E�q��ƒ���������������A����(�K��)���n�̗��Ƃ𗊂���
���Ƃ͂��������A�G�g�Ɩk�����𖧂��ɖK�˂悤�Ƃ���
����ƁA������̏��O�ɂ͔����g�̑����킴�Ƃ����������ł���A��s�����������Ă���悤������
������������Ƃ͏�蕨���牺��āA���{����
�u���̂�牽������B���͓��{�̎��͐\���ɋy���A���܂ŏ]�В��A���e��(����)���q���̎ҁA���R�s�͂̎��ɋɂ�䐬�s�Ȃ���Ƃ����ۂɔ��g���d�܂邱�ƁA���Ă����Ă������̌���Ȃ�B���l�̎����Ε�s�̓z���m��܂��B�Z�p�̎���l�̌��ɂĒɂ��\�����Ȃǂ͑����ׂ��v�Ɖ������炩�Ɏ�����
�u���̂��߁B���̑��̏�͂߂܂���(�����肭�炢�̈ӂ�)���v�Ɠ{��ƁA��Ќ�������ĕ�s�O�͘E�̒��ŏ����ɂȂ�A�u����͂ߌ�ւ���͂ߌ�ցv�Ɛ\�����̂ŁA�����Ə���͂߂�
�������Ă������̂́A���悤�ɋC���̂悢���Ƃ͌������������Ƃ��Ȃ��A���߂Č����Ƙb����
�Ȃ��A�O��Ɉ�L�Ȃ�҂��u�������v�������Ƃ����ł����A����͂Ȃ�Ȃ�ł��傤��
420�l�Ԏ����l�N
2022/09/28(��) 23:51:02.35ID:TRfck96B �w���Ɩ�b�x���
��U�߂̃��A���Ȏ���
���ߍ]�̋����X��(����@�A�����č��X�؎c�}�����т����Ă����Ƃ��l������A�����鑺�̏�)�U��
�]�B�����X�̏��M�������U�߂�ꂽ�Ƃ��A����L��(����)�͖��Łu��������������K�����̓��ɐi�݂Ȃ����v�ƎR���ɂ���Ė����Ŋm���ɂ�������������
�ڊo�߂�ƁA�������爤���R��M���Ă������炾�Ƃ��肪�����v���A���C�������ċ�𒅂ė��Ƃ̐w���Ɍ����������A���܂��u���O�v(�{�����O=�閾���O)�̂悤�ŁA(���Ƃ�)�u����������Ƒ҂āv�Ƃ������Ƃ�����
�����ŏ����ɋA���āu���˂Ԃ�v(������)�����Ă���ƁA�܂��������Łu���ɂ��v�Ƃ�����
���Ă܂��A�M�����̖{�w�ň�ԊL��������A�O�c���͏�Ɋ�Ƃ��A���E�ɓ������������݂ȉE��i��
�L��(��������������)�E��i���A�u���₢�₭������ƈ����R�̂��������������v�ƈ�l���������Ԃ��A���̓���i��Ŗx�́u�Đ܁v(�t�Ζ�)�ɓ���������
�ӂƌ���Ǝl�A�ܐl�̉e������A�u�G���������v�Ɗ���Ă����ƁA�u�n�ɂ���炸�ɂ����ɗ����̂͒N���B���͎ēc�C��(����)�̉��̍��v�Ԍ���(����)�ł���v�Ɩ������
���̂Ƃ��L�オ�u�O�c�ƒ��̑��䖔���q(�̂��̖L���)�ł���v�ƌ����ƁA���ׂ́u�����q��(����)�ƒ��Ŗ��O�͓��X�����Ă���B�����ŏ��߂ĉ�ĂƂĂ�������B�閾���ɂ͋t�Ζ�낤�v�Ɛ\�����킹�A���̂����ɂ��Ƃ��疡�����Ă���
���̂Ƃ��A�L��ƌ��ׂ͐����|�������A�t�Ζ���đ��������(��荞��)�����Ɏ�������
���Ƃ͐M���{�w�ɂ��āA���̎�������Ă������Ƃ���M�����̂��ڂɂ�����ꂽ
�M�����͂܂������q���蕿�𗧂Ă��Ƌ߂��ɂ������݂邵�`5���肸����^�����ق��A�����̓����̏ł���Ƃ��ē�؊}��^����
��U�߂̃��A���Ȏ���
���ߍ]�̋����X��(����@�A�����č��X�؎c�}�����т����Ă����Ƃ��l������A�����鑺�̏�)�U��
�]�B�����X�̏��M�������U�߂�ꂽ�Ƃ��A����L��(����)�͖��Łu��������������K�����̓��ɐi�݂Ȃ����v�ƎR���ɂ���Ė����Ŋm���ɂ�������������
�ڊo�߂�ƁA�������爤���R��M���Ă������炾�Ƃ��肪�����v���A���C�������ċ�𒅂ė��Ƃ̐w���Ɍ����������A���܂��u���O�v(�{�����O=�閾���O)�̂悤�ŁA(���Ƃ�)�u����������Ƒ҂āv�Ƃ������Ƃ�����
�����ŏ����ɋA���āu���˂Ԃ�v(������)�����Ă���ƁA�܂��������Łu���ɂ��v�Ƃ�����
���Ă܂��A�M�����̖{�w�ň�ԊL��������A�O�c���͏�Ɋ�Ƃ��A���E�ɓ������������݂ȉE��i��
�L��(��������������)�E��i���A�u���₢�₭������ƈ����R�̂��������������v�ƈ�l���������Ԃ��A���̓���i��Ŗx�́u�Đ܁v(�t�Ζ�)�ɓ���������
�ӂƌ���Ǝl�A�ܐl�̉e������A�u�G���������v�Ɗ���Ă����ƁA�u�n�ɂ���炸�ɂ����ɗ����̂͒N���B���͎ēc�C��(����)�̉��̍��v�Ԍ���(����)�ł���v�Ɩ������
���̂Ƃ��L�オ�u�O�c�ƒ��̑��䖔���q(�̂��̖L���)�ł���v�ƌ����ƁA���ׂ́u�����q��(����)�ƒ��Ŗ��O�͓��X�����Ă���B�����ŏ��߂ĉ�ĂƂĂ�������B�閾���ɂ͋t�Ζ�낤�v�Ɛ\�����킹�A���̂����ɂ��Ƃ��疡�����Ă���
���̂Ƃ��A�L��ƌ��ׂ͐����|�������A�t�Ζ���đ��������(��荞��)�����Ɏ�������
���Ƃ͐M���{�w�ɂ��āA���̎�������Ă������Ƃ���M�����̂��ڂɂ�����ꂽ
�M�����͂܂������q���蕿�𗧂Ă��Ƌ߂��ɂ������݂邵�`5���肸����^�����ق��A�����̓����̏ł���Ƃ��ē�؊}��^����
421�l�Ԏ����l�N
2022/09/29(��) 17:35:41.44ID:GnixVJCR >>419
�K�����n���ė��Ƃł����H�Ǝv�������Ǎ������Ă���
�K�����n���ė��Ƃł����H�Ǝv�������Ǎ������Ă���
422�l�Ԏ����l�N
2022/09/30(��) 08:45:18.01ID:w5gbckYT423�l�Ԏ����l�N
2022/09/30(��) 12:03:12.99ID:fHVJ/jqd �M���̊Â����D������
424�l�Ԏ����l�N
2022/09/30(��) 12:23:08.23ID:v2jg3NyM �ߗׂ̕S�����璥��������
�܂��ᒠ�Ȃ�ĂȂ��������������Ē��ɗ��������Ă�`
�f����
�܂��ᒠ�Ȃ�ĂȂ��������������Ē��ɗ��������Ă�`
�f����
425�l�Ԏ����l�N
2022/10/01(�y) 21:23:20.92ID:2d4/4eEe ���c�M�����͂��̂悤�ɋ��ɂȂ����B
�u���̐M�����v�����Ƃ́A�e�X���v���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����A���̐M���̐g���v���Ă���B
�ǂ����������ƌ����A�������������i����́j�������W�߁A���������A��ɏ�����Ƃ������ł���B
�R�ɏ��Ƃ������́A�������L����Ƃ������ł���B�������L���Ă����A�ʁX�A���X���l�A
�召�A�㉺���ɉ�����^���Ċ���鎖���o����B
���̂�����āA���̏�ɑ��m�s�����A���g���Ă������̖{�ӂł���B
���̖{�ӂ́u�{�v�Ƃ������́A�����A�召�A���i�����j�ҁA���ԁA���҂܂ł��A�Ղ����̖J�܂�
�ߕ��Ɏv��������悤�Ɏd�鎖�ł���A����͑叫���̗��łȂ���Ȃ�Ȃ��B
����͗Ⴆ�A�����̌��̂悤�Ȃ��̂ł���B
�����A�����̉��ꂪ�A�������g���Ƃ炷���낤���B���������ďƂ炵�Ă���̂ɓ��A���o����̂�
�Ȃ̉Ȃł���B�������������̖��������x�V�Ɛ\�����B
�����x�V�͋|��̐_�ɂ܂��܂����A���ɌR�z�c�������Đ_�̂������������A���̖����悤�ɁA
���̂��Ƃ͐\���ɋy���A���X�܂ői��������̂Ȃ獐��������I�v
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M���́u�叫�Ƃ��Ă̐S���v
�u���̐M�����v�����Ƃ́A�e�X���v���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����A���̐M���̐g���v���Ă���B
�ǂ����������ƌ����A�������������i����́j�������W�߁A���������A��ɏ�����Ƃ������ł���B
�R�ɏ��Ƃ������́A�������L����Ƃ������ł���B�������L���Ă����A�ʁX�A���X���l�A
�召�A�㉺���ɉ�����^���Ċ���鎖���o����B
���̂�����āA���̏�ɑ��m�s�����A���g���Ă������̖{�ӂł���B
���̖{�ӂ́u�{�v�Ƃ������́A�����A�召�A���i�����j�ҁA���ԁA���҂܂ł��A�Ղ����̖J�܂�
�ߕ��Ɏv��������悤�Ɏd�鎖�ł���A����͑叫���̗��łȂ���Ȃ�Ȃ��B
����͗Ⴆ�A�����̌��̂悤�Ȃ��̂ł���B
�����A�����̉��ꂪ�A�������g���Ƃ炷���낤���B���������ďƂ炵�Ă���̂ɓ��A���o����̂�
�Ȃ̉Ȃł���B�������������̖��������x�V�Ɛ\�����B
�����x�V�͋|��̐_�ɂ܂��܂����A���ɌR�z�c�������Đ_�̂������������A���̖����悤�ɁA
���̂��Ƃ͐\���ɋy���A���X�܂ői��������̂Ȃ獐��������I�v
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M���́u�叫�Ƃ��Ă̐S���v
426�l�Ԏ����l�N
2022/10/03(��) 21:23:55.42ID:HQYAPPYE �w�c���N���m�L�x���
�S�L�Q���匠���A�n����̋�����
�����̏O�Ƃ̗��������Ԃ��o�ƁA�ƍN�͐�q�ŏ��̂��S���A��������Ύ��o���Ĕu�͗p���Ȃ�����
�n�̕��ۂň��ނ��A���|���̌����炻�̂܂܈���
���̂���(��l�ň��ނ̂��₵���Ȃ�̂�)��˂�T���̂����A�����̂���ʒu�̐悩��납�A�ǂ���ɂ��邩������Ȃ��̂ŁA�Ў�j�ő��삵�A�����Ў�ɂ͏��|���������Đ�ɍs���Ό������炸�A��납�Ǝv���ė�̔����قǂ܂ő���Ɓu�n��������܂��Ă�邼�v�Ɛq�ˉ����
���������͏�˂������̂œx�X������
�lj��ŏ������u�S�Љ̂̔��q�������ȂƂƙs��B�����ւɎ�����͎�o���]�X�v�Ƃ���܂�
�u�����ւɎ��v�͍��g���H�g���H
�ɂ�����̈��A�����ɂ�����̂��Ƃł��傤��
�S�L�Q���匠���A�n����̋�����
�����̏O�Ƃ̗��������Ԃ��o�ƁA�ƍN�͐�q�ŏ��̂��S���A��������Ύ��o���Ĕu�͗p���Ȃ�����
�n�̕��ۂň��ނ��A���|���̌����炻�̂܂܈���
���̂���(��l�ň��ނ̂��₵���Ȃ�̂�)��˂�T���̂����A�����̂���ʒu�̐悩��납�A�ǂ���ɂ��邩������Ȃ��̂ŁA�Ў�j�ő��삵�A�����Ў�ɂ͏��|���������Đ�ɍs���Ό������炸�A��납�Ǝv���ė�̔����قǂ܂ő���Ɓu�n��������܂��Ă�邼�v�Ɛq�ˉ����
���������͏�˂������̂œx�X������
�lj��ŏ������u�S�Љ̂̔��q�������ȂƂƙs��B�����ւɎ�����͎�o���]�X�v�Ƃ���܂�
�u�����ւɎ��v�͍��g���H�g���H
�ɂ�����̈��A�����ɂ�����̂��Ƃł��傤��
427�l�Ԏ����l�N
2022/10/03(��) 22:42:59.42ID:yg7+fVtc http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-5061.html
�Ƃ���喼���̒n�ɋA��Ƃ��̘b
����Ɠ����b���ȁA�o�T�C�ɂȂ��Ă�
�Ƃ���喼���̒n�ɋA��Ƃ��̘b
����Ɠ����b���ȁA�o�T�C�ɂȂ��Ă�
428�l�Ԏ����l�N
2022/10/03(��) 23:10:16.86ID:HQYAPPYE >>427
�����ł���
�ƍN�A��˂Ō������Ă܂Ƃ߂ƃ_�u��Ȃ������ׂ���ł����A�����܂ʼn��҂����ƈ����|����܂���抾
���T�ł͈����b�Ƃ�����肢���b�̃j���A���X�ł�
�����A���L�͂Ȃ����̂̐������_���ł�����ď������f���Ă��������͂���܂���
�ƍN�̎��̃G�s�\�[�h�͏��Ȃ��悤�Ɏv����ł����A�܂Ƃ�ttp://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7121.html���Ɣ�r�I�A�m��I�Ȉ��
������I�́u���Ă��ĐS�n���悢�v�Ώۂ̈�l��������������ł�����
�����ł���
�ƍN�A��˂Ō������Ă܂Ƃ߂ƃ_�u��Ȃ������ׂ���ł����A�����܂ʼn��҂����ƈ����|����܂���抾
���T�ł͈����b�Ƃ�����肢���b�̃j���A���X�ł�
�����A���L�͂Ȃ����̂̐������_���ł�����ď������f���Ă��������͂���܂���
�ƍN�̎��̃G�s�\�[�h�͏��Ȃ��悤�Ɏv����ł����A�܂Ƃ�ttp://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7121.html���Ɣ�r�I�A�m��I�Ȉ��
������I�́u���Ă��ĐS�n���悢�v�Ώۂ̈�l��������������ł�����
429�l�Ԏ����l�N
2022/10/04(��) 00:40:43.89ID:N/YO0itS �a���E���R����
430�l�Ԏ����l�N
2022/10/04(��) 01:32:41.75ID:xzFPnSUI �ɒB���@�̌������L�����w�����W�x���
�g�C���œƂ茾�c���@�̋�Y�ƈӊO�Ȉ��
���X�̐\���グ�����Ƃ͂������̎��A�����ł����̉Ƃ̐l�Ԃł����ڑΖʂ���A��x����䗗�ɂȂ�ƖY��邱�Ƃ͏\��Ɉ����
�������ɖ������o������̂ŁA(������l�Ԃ�)���_�Ɋ�����
�܂��A���X�̐l�Ԃ������ȊԈႢ��Ƃ��A�������F�����ċ����i�ނɊւ�邱�Ƃ��Ǝv���Ă��A�N�������Ȃ���������̈ӌ��������ꂽ
�^���S�������������Ȃ��悤�Ɍ�����
����Ƃ����̂��A�l�X�ɕs���̎��Ԃ��Ȃ��悤�ɂ��ڂ��߂���Ă̂��Ƃ�����
���Ƃ��A�y���S���Ȃǂ̏����ł������g�ł͌��߂邱�Ƃ͂Ȃ�
�g�C���œƂ茾�c���@�̋�Y�ƈӊO�Ȉ��
���X�̐\���グ�����Ƃ͂������̎��A�����ł����̉Ƃ̐l�Ԃł����ڑΖʂ���A��x����䗗�ɂȂ�ƖY��邱�Ƃ͏\��Ɉ����
�������ɖ������o������̂ŁA(������l�Ԃ�)���_�Ɋ�����
�܂��A���X�̐l�Ԃ������ȊԈႢ��Ƃ��A�������F�����ċ����i�ނɊւ�邱�Ƃ��Ǝv���Ă��A�N�������Ȃ���������̈ӌ��������ꂽ
�^���S�������������Ȃ��悤�Ɍ�����
����Ƃ����̂��A�l�X�ɕs���̎��Ԃ��Ȃ��悤�ɂ��ڂ��߂���Ă̂��Ƃ�����
���Ƃ��A�y���S���Ȃǂ̏����ł������g�ł͌��߂邱�Ƃ͂Ȃ�
431�l�Ԏ����l�N
2022/10/04(��) 01:42:09.96ID:xzFPnSUI ����
����ł����܂�Ȃ���Ε�s�O�����̏�Ɏc���u���A��Տ�(�g�C��)�ɓ�����
��Տ�����͂͂��Ƃ茾���������A��J����Ă���l�q�ŁA�����̑P����(�g�C����)�l���A���M�̏���ŕ�s�O�Ɂu�ǂ̂悤�ȍق����悢���ᖡ����v�Ɛ\���t����
(�g�C���ɓ���O��)���̏�ő������邱�Ƃ͂Ȃ��A�����悤�ɂ��\�������A�N�����[�����錋�_���o��Ζ��������ĘS�ɓ����ꂽ
�����悤�ɂ��������������A����������A��قǂ̑厖�łȂ���Ζ���D���邱�Ƃ͂Ȃ��A��Տ��ŕ����̑P�������ɂ߂�ꂽ
����ł����܂�Ȃ���Ε�s�O�����̏�Ɏc���u���A��Տ�(�g�C��)�ɓ�����
��Տ�����͂͂��Ƃ茾���������A��J����Ă���l�q�ŁA�����̑P����(�g�C����)�l���A���M�̏���ŕ�s�O�Ɂu�ǂ̂悤�ȍق����悢���ᖡ����v�Ɛ\���t����
(�g�C���ɓ���O��)���̏�ő������邱�Ƃ͂Ȃ��A�����悤�ɂ��\�������A�N�����[�����錋�_���o��Ζ��������ĘS�ɓ����ꂽ
�����悤�ɂ��������������A����������A��قǂ̑厖�łȂ���Ζ���D���邱�Ƃ͂Ȃ��A��Տ��ŕ����̑P�������ɂ߂�ꂽ
432�l�Ԏ����l�N
2022/10/06(��) 20:15:51.63ID:0MepCS7F433�l�Ԏ����l�N
2022/10/06(��) 22:00:59.16ID:GpxPmdQX434�l�Ԏ����l�N
2022/10/06(��) 23:42:13.99ID:QGrWWrsf �O��ɂ��`�������A�����喼������Ă����ēG�ƍu�a������ł��A�Ă������叫�̗��ɐ��������Ƃ͖w�ǖ����B
����͖���ł����Ă���߂ĕς��Ȃ��ł��낤�B���̂悤�ȍl�����ɂ��A���c�M�����͍b�B�ꍑ�̓���
�镁���͂��ꂸ�A��\���́A�����x��@�����A������d�ł������B
����ɂ��Ă͉ƘV�O���ł����Ђ߂�\�����B�u��邪������������܂��B���̏�h��ݔ����e���ŁA
����ł͔@�����Ƒ����܂��B�v
�M�����͋��ɐ���ꂽ
�u���̎e�ׂʂ��Ă݂�B�����喼������Ă����ĉ^���J���Ƃ����̂͋H�ł���B�������A�������
������l�i���R�j��҂K�v������ꍇ�́A�����قǂł����łȒn����v�ɗv�Q�����邱�Ƃ��̗v�ł���B
�O�����قǂ��x�z�d��叫���A����ȏ邢���ς����Ă���قǂ̐l�������Ă���̂Ȃ�A���̐l�����g��
�G���Ă��鑊��ƍ����ɂ����āA�������Ȃ����n�ō�����d��A�����ł��ʂ����ׂ��������ނ��ł���B
�l���𑽂����̂ɂ������������킪�o���Ȃ��悤�Ȃ�A���Ƃ��ď邵�Ă��A�G�̖�E�S�C�̒���������A
�Ȏq���̂Ăđ��蓦���邾�낤�B
�叫����҂͕��𐒌h���Ė@�x���߁A�R�@���߁A���킷�邱�Ƃ[�̍쎖�ƐS���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�S�̂Ȃ��ŁA������l�ō���̌v��Ƃ����������d��̂́A�����������y���ɑ�쎖�ł���B
�����Ă��ꂱ�����A�叫����l�ő��l���̓���������ꏊ�ł���B
�ł��邩��A�升��ŁA�A�O���̌R���ŏ����������A�u�M���̏����v�ƌĂ��̂��B
�叫��l�̊o����Ȃď��l�ɏ������A���l�̏������叫�̏����ƌĂ��B���ꂱ�����叫�̑���
�肢�ł���B�F�X�����A�V�ዤ�ɁA���̎���S����悤�ɁB�v
�w�b�z�R�Ӂx
�����炭�u�l�͏�A�l�͐Ί_~�v�̌��l�^�̈�ƍl������A���c�M���̏�ɂ��Ă̍l�����B
����͖���ł����Ă���߂ĕς��Ȃ��ł��낤�B���̂悤�ȍl�����ɂ��A���c�M�����͍b�B�ꍑ�̓���
�镁���͂��ꂸ�A��\���́A�����x��@�����A������d�ł������B
����ɂ��Ă͉ƘV�O���ł����Ђ߂�\�����B�u��邪������������܂��B���̏�h��ݔ����e���ŁA
����ł͔@�����Ƒ����܂��B�v
�M�����͋��ɐ���ꂽ
�u���̎e�ׂʂ��Ă݂�B�����喼������Ă����ĉ^���J���Ƃ����̂͋H�ł���B�������A�������
������l�i���R�j��҂K�v������ꍇ�́A�����قǂł����łȒn����v�ɗv�Q�����邱�Ƃ��̗v�ł���B
�O�����قǂ��x�z�d��叫���A����ȏ邢���ς����Ă���قǂ̐l�������Ă���̂Ȃ�A���̐l�����g��
�G���Ă��鑊��ƍ����ɂ����āA�������Ȃ����n�ō�����d��A�����ł��ʂ����ׂ��������ނ��ł���B
�l���𑽂����̂ɂ������������킪�o���Ȃ��悤�Ȃ�A���Ƃ��ď邵�Ă��A�G�̖�E�S�C�̒���������A
�Ȏq���̂Ăđ��蓦���邾�낤�B
�叫����҂͕��𐒌h���Ė@�x���߁A�R�@���߁A���킷�邱�Ƃ[�̍쎖�ƐS���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�S�̂Ȃ��ŁA������l�ō���̌v��Ƃ����������d��̂́A�����������y���ɑ�쎖�ł���B
�����Ă��ꂱ�����A�叫����l�ő��l���̓���������ꏊ�ł���B
�ł��邩��A�升��ŁA�A�O���̌R���ŏ����������A�u�M���̏����v�ƌĂ��̂��B
�叫��l�̊o����Ȃď��l�ɏ������A���l�̏������叫�̏����ƌĂ��B���ꂱ�����叫�̑���
�肢�ł���B�F�X�����A�V�ዤ�ɁA���̎���S����悤�ɁB�v
�w�b�z�R�Ӂx
�����炭�u�l�͏�A�l�͐Ί_~�v�̌��l�^�̈�ƍl������A���c�M���̏�ɂ��Ă̍l�����B
435�l�Ԏ����l�N
2022/10/07(��) 12:05:41.31ID:LvhANc1y ����͕��c�͗���ŖłԂƂ��\������Ă�
�M�����ǂ�ȋ�������ĂĂ����̂͏邶�ᖳ��������
���Ӗ�������w���ŏ\��
�M�����ǂ�ȋ�������ĂĂ����̂͏邶�ᖳ��������
���Ӗ�������w���ŏ\��
436�l�Ԏ����l�N
2022/10/07(��) 13:52:22.78ID:Ca5bN3lM ���ɕ{���ό����Ă�������{�l������A�ꂽ�؍��l�j���ɔn���ɂ��ꂽ
�`�r�œ��{�̒j�͉��݂������Ȃ�
�����������{�l�������ȒP�ɗ��ɂł���؍��l�j�����A�܂���������
����ɂ���ĂȂ��؍��l�����Ȃ�ɗ��Ƃ���Ǝv�����������Ă��u�W���b�v�̃T���͐��E�ň�ԃu�T�C�N�ł������j�����ڂ����烂�e�Ȃ��A���f��w�v�ƕ@�ŏ�ꂽ�A���ɂ���
�`�r�œ��{�̒j�͉��݂������Ȃ�
�����������{�l�������ȒP�ɗ��ɂł���؍��l�j�����A�܂���������
����ɂ���ĂȂ��؍��l�����Ȃ�ɗ��Ƃ���Ǝv�����������Ă��u�W���b�v�̃T���͐��E�ň�ԃu�T�C�N�ł������j�����ڂ����烂�e�Ȃ��A���f��w�v�ƕ@�ŏ�ꂽ�A���ɂ���
437�l�Ԏ����l�N
2022/10/08(�y) 22:07:37.19ID:WVs9ucKA ���{��Ɋ��\�ȃC�G�Y�X��鋳�t�W���A���E���h���Q�X�ɂ��u���{�ꏬ���T�v���疼��ɂ���
���������̂ɗp�����́A�ǂ̂悤�Ȗ��ł���82��Ɍ����A����82��̂Ȃ���2���g�ݍ��킹�Ĉ�̖�������B
���������Ă��閼���A���ꂪ����(���݂傤)��łȂ�����ł��邱�Ƃ̌��ɂ߂͒����ɂ��B
���Ɏ����̂�82��Ƌ�̗��Y�������̂ł���
(���X�̓A���t�@�x�b�g���ł��������A�\�����ɕ��ёւ�)
1����(��������)2������(���ꂠ����)3����(������)4����(����悵)5��6����(��������)7��8����9����(��������)10����
11��12����(��������)13����(�Ȃ�����)14����15����(������)16����(�܂�����)17����(�Ђł���)18����(�Ђł���)19����
20��21����22����23����(������)24����(���ɂ݂�)25����26����27����(�������)
���������̂ɗp�����́A�ǂ̂悤�Ȗ��ł���82��Ɍ����A����82��̂Ȃ���2���g�ݍ��킹�Ĉ�̖�������B
���������Ă��閼���A���ꂪ����(���݂傤)��łȂ�����ł��邱�Ƃ̌��ɂ߂͒����ɂ��B
���Ɏ����̂�82��Ƌ�̗��Y�������̂ł���
(���X�̓A���t�@�x�b�g���ł��������A�\�����ɕ��ёւ�)
1����(��������)2������(���ꂠ����)3����(������)4����(����悵)5��6����(��������)7��8����9����(��������)10����
11��12����(��������)13����(�Ȃ�����)14����15����(������)16����(�܂�����)17����(�Ђł���)18����(�Ђł���)19����
20��21����22����23����(������)24����(���ɂ݂�)25����26����27����(�������)
438�l�Ԏ����l�N
2022/10/08(�y) 22:08:40.50ID:WVs9ucKA 28����(��������)29����30����(���˂���)31����(��������A��������)32����(��������)33����(������)34����(���݂���)
35����36����37����(��������)38����39����40����(�Ђ�����)41����(��������)
42��(�Ђł�)43��44��(�䂫��)45��(�˂���)46��(��䂫)47�Ă�(�Ă����)48�Ƃ�49�Ƃ�(�Ƃ�����)50�Ƃ�(�Ƃ��݂�)51�Ƃ�52�Ƃ�(�Ƃ�����)53�Ƃ�
54��55�Ȃ�(�Ȃ�����)56�Ȃ�57�Ȃ�(�Ȃ��݂�)58�Ȃ�(�����Ȃ�)59�Ȃ�(�Ȃ肿��)60�̂�(�̂ԂȂ�)61�̂�(�̂肢��)
62�͂�(�͂����)63�Ђ�(�Ђ�����)64�Ђ�(�Ђł��)65�Ђ�66�Ђ�(�䂫�Ђ�)67�Ђ�(�悵�Ђ�)68�ӂ�69�ӂ�70�ӂ�H(���˂ӂ�)
71�܂�(�܂��ނ�)72�܂�73�܂�74�܂�75��76�݂�(�݂���)77�ނ�(�ނ˂���)78�ނ�79����80����(���Ƃ���)81����82����(���낵��)
35����36����37����(��������)38����39����40����(�Ђ�����)41����(��������)
42��(�Ђł�)43��44��(�䂫��)45��(�˂���)46��(��䂫)47�Ă�(�Ă����)48�Ƃ�49�Ƃ�(�Ƃ�����)50�Ƃ�(�Ƃ��݂�)51�Ƃ�52�Ƃ�(�Ƃ�����)53�Ƃ�
54��55�Ȃ�(�Ȃ�����)56�Ȃ�57�Ȃ�(�Ȃ��݂�)58�Ȃ�(�����Ȃ�)59�Ȃ�(�Ȃ肿��)60�̂�(�̂ԂȂ�)61�̂�(�̂肢��)
62�͂�(�͂����)63�Ђ�(�Ђ�����)64�Ђ�(�Ђł��)65�Ђ�66�Ђ�(�䂫�Ђ�)67�Ђ�(�悵�Ђ�)68�ӂ�69�ӂ�70�ӂ�H(���˂ӂ�)
71�܂�(�܂��ނ�)72�܂�73�܂�74�܂�75��76�݂�(�݂���)77�ނ�(�ނ˂���)78�ނ�79����80����(���Ƃ���)81����82����(���낵��)
439�l�Ԏ����l�N
2022/10/08(�y) 22:11:25.30ID:WVs9ucKA �ȏ�ł��邪�A��������̐l���������̂͐���������ɂ́u�����L�v��u���ƕ���v�̌��t���w�Ԃ悤�ɁA�Ə����Ă��邩�炾�낤�B
�������u�����v�u�₷�v�u�悵�v�Ȃǂ��Ȃ��悤����
�������u�����v�u�₷�v�u�悵�v�Ȃǂ��Ȃ��悤����
440�l�Ԏ����l�N
2022/10/10(��) 20:40:27.29ID:N12PfjLC ���c�M�����͗c���������a�Ɛ\���B���̎e�ׂ́A�䕃�M�Ռ�����\���̎��A�x�͂̂����܁i�����j�Ƃ������m�A
����a���y�A����ɍb�B������ČȂ̍��Ɏd���Ƃ��āA���E�x�̐l���𗦂��čb�B�ѓc�͌��܂ŗ����B
�������Z�\�ܓ����܂�w���Ă������A���̊ԍb�B���Ɓi���c���j�̏O�͐s���g�\�������ē������A
���c�̌�Ƃ͂��͂�ŖS���ƌ��������ɁA�M�Ռ��̉ƘV�ł��鉬���헤��Ƃ����卄�̕��m���A�������Ȃ�
�M�Ռ��̏������B
�G�̑叫�ł��邭���܂����ꂽ���̓��̂��̎��A�a�����ꂽ�̂ɁA�M�����́u�����a�v��
�c����t����ꂽ�̂ł���B���Ȃ킿���̎��̍���͏����a�̍���ł���Ƃ����A���c�M�Ռ��ƘV��
�����ł������B
�܂������a�̒a���O�Ɏ�X�̕s�v�c���A�M�B�z�K���_��荐�������ƌ����Ă���B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M���̗c���ɂ��Ă̂��b�B
����a���y�A����ɍb�B������ČȂ̍��Ɏd���Ƃ��āA���E�x�̐l���𗦂��čb�B�ѓc�͌��܂ŗ����B
�������Z�\�ܓ����܂�w���Ă������A���̊ԍb�B���Ɓi���c���j�̏O�͐s���g�\�������ē������A
���c�̌�Ƃ͂��͂�ŖS���ƌ��������ɁA�M�Ռ��̉ƘV�ł��鉬���헤��Ƃ����卄�̕��m���A�������Ȃ�
�M�Ռ��̏������B
�G�̑叫�ł��邭���܂����ꂽ���̓��̂��̎��A�a�����ꂽ�̂ɁA�M�����́u�����a�v��
�c����t����ꂽ�̂ł���B���Ȃ킿���̎��̍���͏����a�̍���ł���Ƃ����A���c�M�Ռ��ƘV��
�����ł������B
�܂������a�̒a���O�Ɏ�X�̕s�v�c���A�M�B�z�K���_��荐�������ƌ����Ă���B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M���̗c���ɂ��Ă̂��b�B
441�l�Ԏ����l�N
2022/10/10(��) 21:02:15.88ID:QBpDoS3b ����A���c�Ƒ�X�̗c���ƈႤ�́H
�c�M�Ղ��p�p����Ȃ��Ƃ���ƐF��Ȏ����D�ɗ�������ǂǂ��Ȃ�
�c�M�Ղ��p�p����Ȃ��Ƃ���ƐF��Ȏ����D�ɗ�������ǂǂ��Ȃ�
442�l�Ԏ����l�N
2022/10/10(��) 22:46:20.57ID:I5XffvIN �M�Ղ͎햳�������������
443�l�Ԏ����l�N
2022/10/10(��) 22:53:17.60ID:RSFjfb0/ �M���̗c���͑��Y�����ǂ�
444�l�Ԏ����l�N
2022/10/11(��) 19:34:25.37ID:sjUKDtPG ����͒ʏ̂��
445�l�Ԏ����l�N
2022/10/14(��) 02:27:34.48ID:X7Ck2XWY ������邶���
446�l�Ԏ����l�N
2022/10/14(��) 09:36:24.27ID:cE+9kySr ���Ƃ��q
447�l�Ԏ����l�N
2022/10/14(��) 14:07:21.65ID:1S1HyJBX �y�^�N�V�[�\�����́z�@�C�O�ł͊�A���{����������
://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/traf/1577003763/l50
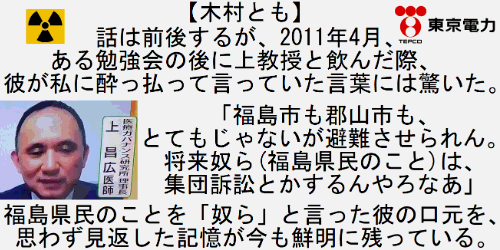
://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/traf/1577003763/l50
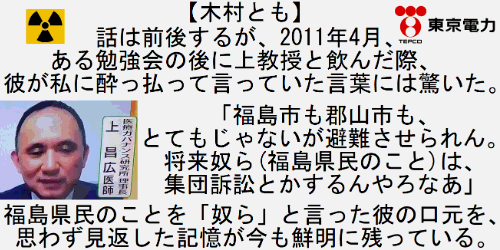
448�l�Ԏ����l�N
2022/10/14(��) 22:13:16.01ID:9Ftdyy30 ���c���M���͓V���\��N�\����\�O���ɁA�M�B��哻�ɂ����č���ɏ����A�C�K�܂Ō�n�����A
�G�̐��͌��Ƃ̋��ڂ̎d�u���Ȃ��ꂽ�B
���̐M�B�O�Ƃ����l�X�́A���肪���G������Ƃ����Ă������F���������A�G���ɖ������悤�Ƃ���
�҂����Ȃ��B�����̍��ł́A����ɕ������ꍇ�A���̐��͂��ێ����Ă�������A����O���K��
��������̂��ƕ����y��ł��邪�A�M�Z�̍��ɂ����ẮA�����̐��͂������������œG���̏���ł����Ă�
���l�߂�悤�Ȏ�������A�M�Z�O�́u���������ɂ����������ɂĎd�Ԃ���B�v�ƍl���A��������ł�
�����̌�l��҂��Ďx��������B
����A��l�̌R���̐l�X�́A�e�q�A�Z��A�f���A���A�]��A�͂Ƃ��A���ށA�m���A�߂����l�X���ꕮ���Ă���A
����ɓG������U�߂Ă��鎖�ɁA���悢��ȂČ��ɂ����A�u����Ƃ���x�d�Ԃ������A�����������ꂽ�̂�
�����悤�ɓG���A�����͒ǂ������A�s������G�̂����������Ȃ���A���m�Ƃ��ċ|������b�オ�Ȃ��B�v
���̂悤�Ɍ����������ł���B
�̂ɁA�������������������Ă��܂��ƁA��X�����ɂ��Ă��܂��B�Ƃ������ŁA���M���͏�������́A
�P�Ȃđ厖�ɂ������ꂽ���A����͐M�Z�̍��������̂悤�ɋ������̂ł��������߂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�Ƃ��猩���M�Z�O�ɂ��āB
�G�̐��͌��Ƃ̋��ڂ̎d�u���Ȃ��ꂽ�B
���̐M�B�O�Ƃ����l�X�́A���肪���G������Ƃ����Ă������F���������A�G���ɖ������悤�Ƃ���
�҂����Ȃ��B�����̍��ł́A����ɕ������ꍇ�A���̐��͂��ێ����Ă�������A����O���K��
��������̂��ƕ����y��ł��邪�A�M�Z�̍��ɂ����ẮA�����̐��͂������������œG���̏���ł����Ă�
���l�߂�悤�Ȏ�������A�M�Z�O�́u���������ɂ����������ɂĎd�Ԃ���B�v�ƍl���A��������ł�
�����̌�l��҂��Ďx��������B
����A��l�̌R���̐l�X�́A�e�q�A�Z��A�f���A���A�]��A�͂Ƃ��A���ށA�m���A�߂����l�X���ꕮ���Ă���A
����ɓG������U�߂Ă��鎖�ɁA���悢��ȂČ��ɂ����A�u����Ƃ���x�d�Ԃ������A�����������ꂽ�̂�
�����悤�ɓG���A�����͒ǂ������A�s������G�̂����������Ȃ���A���m�Ƃ��ċ|������b�オ�Ȃ��B�v
���̂悤�Ɍ����������ł���B
�̂ɁA�������������������Ă��܂��ƁA��X�����ɂ��Ă��܂��B�Ƃ������ŁA���M���͏�������́A
�P�Ȃđ厖�ɂ������ꂽ���A����͐M�Z�̍��������̂悤�ɋ������̂ł��������߂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�Ƃ��猩���M�Z�O�ɂ��āB
449�l�Ԏ����l�N
2022/10/17(��) 17:59:25.61ID:lDCaiCXx �܂��{���X���Ƃ͊W�Ȃ����ǁA���E�I�ȃT�����C�R���e���c�̐l�C�Ƃ������̂͊m���ɂ���Ȃ���
�����Đ��Ɨv�f�͂��������ǂ���
https://www.cinematoday.jp/news/N0132915
�w47RONIN�x���҉f��A�\���҂����J�@����͌���̃u�_�y�X�g
�L�A�k�E���[���X���剉�����f��w47RONIN�x�i2013�j�̑��ҁw�u���C�h�E�I�u�E�U�E47 ���[�j���i����j / Blade of the 47 Ronin�x��
�\���҂��A�f��̕Č���Twitter�Ō��J���ꂽ�B
���{�́u���b���v���_�A�����W�����w47RONIN�x�́A��N�̓G�ׂ��W�܂���47�l�̘Q�m�Ƃ͂���҂̃T�����C�E�J�C�i�L�A�k�j��
���g�݁A�����̐킢�ɒ��ރt�@���^�W�[�A�N�V�����B�L�A�k���͂��߁A�^�c�L�V�A��쒉�M�A�e�n�z�q�A�č�R�E�A�Ԑ��m����{��
��\����l�C�o�D�̏o�����b��ƂȂ����B
�L���X�g����V�������҂̕���́A����̃u�_�y�X�g�B�c���Q�m�̈�l�ɎE���ꂽ���Ȗ������o�����A���̕��Q���ʂ����ׂ�
�������̖��E����Ă�B������|����̂́A47�l�̘Q�m�̎q�������B���ꂼ��̎g�����ʂ������߁A�����c������m�����������オ��B
�\���҂ɂ́A�o�[���ԓ��ȂǂœW�J���锗�͂̓��A�N�V���������߂��Ă���B
���K�z����������̂́A�f�B�Y�j�[���ʔŁw���[�����x�ɂ��o�����Ă��������E���A���ēBNetflix�h���}�u�W���s�^�[�Y�E���K�V�[�v��
�A�i�E�A�J�i��w�W�����E�E�B�b�N�F�p���x�����x�̃}�[�N�E�_�J�X�R�X�ɉ����āA�e���T�E�e�B���A�}�C�N�E���[�A�_�X�e�B���E�k�G���A�N���X�E�p���A
���R�q�q�A���{���i�A���ƎR�W�A�Ô��V�V�炪�L���X�g�ɖ���A�˂�B�A�����J�����ł�10��25�����Netflix�z�M�ABlu-ray��DVD
�������ɔ����ƂȂ�B
�����Đ��Ɨv�f�͂��������ǂ���
https://www.cinematoday.jp/news/N0132915
�w47RONIN�x���҉f��A�\���҂����J�@����͌���̃u�_�y�X�g
�L�A�k�E���[���X���剉�����f��w47RONIN�x�i2013�j�̑��ҁw�u���C�h�E�I�u�E�U�E47 ���[�j���i����j / Blade of the 47 Ronin�x��
�\���҂��A�f��̕Č���Twitter�Ō��J���ꂽ�B
���{�́u���b���v���_�A�����W�����w47RONIN�x�́A��N�̓G�ׂ��W�܂���47�l�̘Q�m�Ƃ͂���҂̃T�����C�E�J�C�i�L�A�k�j��
���g�݁A�����̐킢�ɒ��ރt�@���^�W�[�A�N�V�����B�L�A�k���͂��߁A�^�c�L�V�A��쒉�M�A�e�n�z�q�A�č�R�E�A�Ԑ��m����{��
��\����l�C�o�D�̏o�����b��ƂȂ����B
�L���X�g����V�������҂̕���́A����̃u�_�y�X�g�B�c���Q�m�̈�l�ɎE���ꂽ���Ȗ������o�����A���̕��Q���ʂ����ׂ�
�������̖��E����Ă�B������|����̂́A47�l�̘Q�m�̎q�������B���ꂼ��̎g�����ʂ������߁A�����c������m�����������オ��B
�\���҂ɂ́A�o�[���ԓ��ȂǂœW�J���锗�͂̓��A�N�V���������߂��Ă���B
���K�z����������̂́A�f�B�Y�j�[���ʔŁw���[�����x�ɂ��o�����Ă��������E���A���ēBNetflix�h���}�u�W���s�^�[�Y�E���K�V�[�v��
�A�i�E�A�J�i��w�W�����E�E�B�b�N�F�p���x�����x�̃}�[�N�E�_�J�X�R�X�ɉ����āA�e���T�E�e�B���A�}�C�N�E���[�A�_�X�e�B���E�k�G���A�N���X�E�p���A
���R�q�q�A���{���i�A���ƎR�W�A�Ô��V�V�炪�L���X�g�ɖ���A�˂�B�A�����J�����ł�10��25�����Netflix�z�M�ABlu-ray��DVD
�������ɔ����ƂȂ�B
450�l�Ԏ����l�N
2022/10/17(��) 18:16:26.97ID:vO2YfhP9 ���͂␅���`���낻��
451�l�Ԏ����l�N
2022/10/17(��) 18:34:21.06ID:QhGaOkKC �L���X�g������
�����`�ł��������
�����`�ł��������
452�l�Ԏ����l�N
2022/10/17(��) 19:32:50.85ID:XfdunYWt >>449
�g�ǖ������
�g�ǖ������
453�l�Ԏ����l�N
2022/10/17(��) 22:30:50.64ID:GJZgmUi9 �V���\��N�����O���ɁA���c�̉ƘV�O�͑ł�����āA���̔N�̕��c���M���̌���ɂ��Ēk�������B
�u�z�K�A�����͍��v�A���p�̓G�����̋��ɂ����Ė����̏���\�z����ꍇ�A���̏�̐v��\���v���A
��̐l���ŕێ������ł����Ă��A�O�S�ŕۂ����o����B����͏�̎��l�A�꒣��ɉ��`������
���߂ł���B
���̂悤�ȏ�̐v��\���������鍄�̎҂��A�x�͂̍���`�����̌��ƁA�����a�̒��O�ɋ���B
�ނ͍���a�̒��b�Ɛ��邱�Ƃ�]���A�`���͏��������Ȃ������B
���̎҂͎O�B���v�ۂ̎������A�l���A�㍑�i��B�j�A�����A�֓��܂ł�������������ł���A
�R�{�����Ɛ\���A�卄�̕��m�ł���ƕ����B���̊����������������ׂ��ł���B�v
���̎��͔_�M����萰�M���\���グ���A����ɂ��A�m�s�S�т̖ɂāA���̔N�O���A
�x�͂�芨��������ꂽ�B
����̌������A���M���͑����ɋ��t����ꂽ
�u����͈��A����Ɏ菝�𐔃��������Ă��邽�߁A�葫�����X�s���R�Ɍ�����B
�F�����A����قǂ̖��j�ł���Ȃ��炻�̖���������������̂́A�\�X�ق܂ꑽ�����ł���Ɗo����B
���̂悤�ȕ��m�ɕS�т͏����ł���B�v
�Ƃ̋V�ɂāA��S�т������ꂽ�B
���āA���̔N�̕�A�����i�\�ꌎ�j���{�ɐ��M���͐M�B��o�n����A���{���\�\�ܓ��܂ł̊ԂɁA
�������Đ��M���̌��ɓ������̂����A����͕ɎR�{�����̕����̌̂ł������B
���M����\��̌䎞�̎��ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�u�z�K�A�����͍��v�A���p�̓G�����̋��ɂ����Ė����̏���\�z����ꍇ�A���̏�̐v��\���v���A
��̐l���ŕێ������ł����Ă��A�O�S�ŕۂ����o����B����͏�̎��l�A�꒣��ɉ��`������
���߂ł���B
���̂悤�ȏ�̐v��\���������鍄�̎҂��A�x�͂̍���`�����̌��ƁA�����a�̒��O�ɋ���B
�ނ͍���a�̒��b�Ɛ��邱�Ƃ�]���A�`���͏��������Ȃ������B
���̎҂͎O�B���v�ۂ̎������A�l���A�㍑�i��B�j�A�����A�֓��܂ł�������������ł���A
�R�{�����Ɛ\���A�卄�̕��m�ł���ƕ����B���̊����������������ׂ��ł���B�v
���̎��͔_�M����萰�M���\���グ���A����ɂ��A�m�s�S�т̖ɂāA���̔N�O���A
�x�͂�芨��������ꂽ�B
����̌������A���M���͑����ɋ��t����ꂽ
�u����͈��A����Ɏ菝�𐔃��������Ă��邽�߁A�葫�����X�s���R�Ɍ�����B
�F�����A����قǂ̖��j�ł���Ȃ��炻�̖���������������̂́A�\�X�ق܂ꑽ�����ł���Ɗo����B
���̂悤�ȕ��m�ɕS�т͏����ł���B�v
�Ƃ̋V�ɂāA��S�т������ꂽ�B
���āA���̔N�̕�A�����i�\�ꌎ�j���{�ɐ��M���͐M�B��o�n����A���{���\�\�ܓ��܂ł̊ԂɁA
�������Đ��M���̌��ɓ������̂����A����͕ɎR�{�����̕����̌̂ł������B
���M����\��̌䎞�̎��ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
454�l�Ԏ����l�N
2022/10/18(��) 17:32:30.84ID:FCT13yXf ���Ë`�v�z���̖��l��t�E���O���́A���N�̖��̌v��𖾂֒ʕ��b�ŗL���ł�����ǂ�
���{�̈�t�Ƌ��ɓ���ƍN��f�@�������Ƃ���������ł���
wikipedia���V��
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B1%E5%84%80%E5%BE%8C
���`�v�Ƌ��ɏG�g�։y�������ۂɁA�G�g�͋���ȓ�𒒑����������ώE�����Ƃ����B�������A
������ƍN���G�g��G�߂����ƂŖ��E�����A���͂��̂Ƃ��̕ԗ�Ƃ��āA�ƍN���a�ɂȂ����ۂ�
����܂��ĉ���Ԃ��Ă���B
�܂Ƃ߂̂�����A��ɓ��Ë`�O����Ă̍ۂɂ͓���Ɓi�G���j����A�Ȓ����剺�̖��オ�f�@�ɉ������Ă܂���
����Ƃ̈㊯�́A�G�g�h���̈�t�����Ɗ�Ԃ�E�l�����Ԃ��Ă�͂��ł���
�u�����@���R�̉{���ɂ��āv
http://iiwarui.blog90.fc2.com/?q=%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E7%8E%84%E7%94%B1
���{�̈�t�Ƌ��ɓ���ƍN��f�@�������Ƃ���������ł���
wikipedia���V��
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B1%E5%84%80%E5%BE%8C
���`�v�Ƌ��ɏG�g�։y�������ۂɁA�G�g�͋���ȓ�𒒑����������ώE�����Ƃ����B�������A
������ƍN���G�g��G�߂����ƂŖ��E�����A���͂��̂Ƃ��̕ԗ�Ƃ��āA�ƍN���a�ɂȂ����ۂ�
����܂��ĉ���Ԃ��Ă���B
�܂Ƃ߂̂�����A��ɓ��Ë`�O����Ă̍ۂɂ͓���Ɓi�G���j����A�Ȓ����剺�̖��オ�f�@�ɉ������Ă܂���
����Ƃ̈㊯�́A�G�g�h���̈�t�����Ɗ�Ԃ�E�l�����Ԃ��Ă�͂��ł���
�u�����@���R�̉{���ɂ��āv
http://iiwarui.blog90.fc2.com/?q=%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E7%8E%84%E7%94%B1
455�l�Ԏ����l�N
2022/10/19(��) 22:48:37.75ID:O1hpUpuD �b�{�ɗH���ꂽ�z�K���d�̎��n�ɂ��A�z�K�̉Ƃ͒f�₵���B���������d�̑������A���̔N�\�l��
�Ȃ�ꂽ���A�q��B��Ȃ����l�ł������B������A���c���M���͏��ɂ������ƍl�����Ă����B
����������ɑ��A�_�M���A�ѕx�����A�×����O�̎O�l���n�߂Ƃ����e�ƘV�O�͂�����Ђߐ\���グ��
�u�ގ��Ȃ��ꂽ���d�̑����������u�����Ƃ������A�ޏ��͏��l�Ƃ����Ă��G�ł���̂ł�����@������
�l���܂��B�v
�������Ȃ���A�O�N�O�ɏx�͂�菢����ꂽ�A�����͎O�͋��v�ۂ̎��A�R�{�������i�ݏo�āA
�_�a�A�ѕx�a�A�×��a�O�l�̎��叫�ɐ\���グ��
�u���M���̌�Ќ����ア���̂ł���A�����҂��`�����Ƃ��K���Ɖx�сA����ʊ�݂��d�|���邱�Ƃ�
����ł��傤�B�������A���M���̌�Ќ��͐��̂ł͂���܂���B
���̗��R�́A���͓��{�����������������Ă��܂����B�����ł͈��|�̖ї����A���A�{�m���S�т��|���
��肷����A���⒆���̑�������]���A�l����B�܂ł���Ќ��������āA���ɈȂēV���ٌ̈����d���Ă��܂��B
�E���̎O�D�����A���A�̋@��������Ă���͉̂B��Ȃ����ł���܂��B
���̖ї����A�ɑ��Ă��A���M����\�܍̓��ɂ����Ă���A���قǗ���Ă��Ȃ����̌�Ќ����A����
�x�͂ɂ����ď����Ă��܂����B
����Ȃ��玄�̍l���ł́A���M���ɂ��ē��{�������A���̋|����̑�\�Ƒ������@���ł��B
�b�{�֎����Q���ē�N�]�����܂����B���̊ԁA���M���̔���������A�܂��G�ւ̑Ή��̗l�q�������A
���̉��`�l�������ɂ�������A�K�����{���o�E�����̖��叫�Ɛl�X���珥������ł��傤�B
�ł��̂ŁA�z�K�Ƃ̐e�ނ�튯�������A���̊�݂�������鎖�͂���܂���B
�ł���ȏ�A���d�̑����������u�����A�z�K�O�͉x�сA���̌䕠�Ɍ䑂�i���a���������A�z�K�̉Ƃ�
�����\���ׂ��ƁA�o�d��]�݁A���c�̕���O�ɗ��\���܂��ƁA����\���ł��傤�B
���̂悤�ɁA���d�̑����𐰐M���������u����鎖�͑R��ׂ��ł��B�v
�R�{���������̂悤�ɍH�v���Đ\�����̂ɁA���d�̑����𐰐M���͏����u���ꂽ�B�����Ċ���̕��ʂ̔@��
�z�K�O�͂�����x�сA�l�����b�{�i�サ���B
���̔N�A�V���\�ܔN�Ɏl�Y�a�i�����j���a�����ꂽ�B����ɂ���Đz�K�O�����`�l���ɑ�����鎖�A
����O���O�ƂȂ����B
�w�b�z�R�Ӂx
���c���M���z�K���d�̖��𑤎��Ƃ��Č}����܂̂��b
�Ȃ�ꂽ���A�q��B��Ȃ����l�ł������B������A���c���M���͏��ɂ������ƍl�����Ă����B
����������ɑ��A�_�M���A�ѕx�����A�×����O�̎O�l���n�߂Ƃ����e�ƘV�O�͂�����Ђߐ\���グ��
�u�ގ��Ȃ��ꂽ���d�̑����������u�����Ƃ������A�ޏ��͏��l�Ƃ����Ă��G�ł���̂ł�����@������
�l���܂��B�v
�������Ȃ���A�O�N�O�ɏx�͂�菢����ꂽ�A�����͎O�͋��v�ۂ̎��A�R�{�������i�ݏo�āA
�_�a�A�ѕx�a�A�×��a�O�l�̎��叫�ɐ\���グ��
�u���M���̌�Ќ����ア���̂ł���A�����҂��`�����Ƃ��K���Ɖx�сA����ʊ�݂��d�|���邱�Ƃ�
����ł��傤�B�������A���M���̌�Ќ��͐��̂ł͂���܂���B
���̗��R�́A���͓��{�����������������Ă��܂����B�����ł͈��|�̖ї����A���A�{�m���S�т��|���
��肷����A���⒆���̑�������]���A�l����B�܂ł���Ќ��������āA���ɈȂēV���ٌ̈����d���Ă��܂��B
�E���̎O�D�����A���A�̋@��������Ă���͉̂B��Ȃ����ł���܂��B
���̖ї����A�ɑ��Ă��A���M����\�܍̓��ɂ����Ă���A���قǗ���Ă��Ȃ����̌�Ќ����A����
�x�͂ɂ����ď����Ă��܂����B
����Ȃ��玄�̍l���ł́A���M���ɂ��ē��{�������A���̋|����̑�\�Ƒ������@���ł��B
�b�{�֎����Q���ē�N�]�����܂����B���̊ԁA���M���̔���������A�܂��G�ւ̑Ή��̗l�q�������A
���̉��`�l�������ɂ�������A�K�����{���o�E�����̖��叫�Ɛl�X���珥������ł��傤�B
�ł��̂ŁA�z�K�Ƃ̐e�ނ�튯�������A���̊�݂�������鎖�͂���܂���B
�ł���ȏ�A���d�̑����������u�����A�z�K�O�͉x�сA���̌䕠�Ɍ䑂�i���a���������A�z�K�̉Ƃ�
�����\���ׂ��ƁA�o�d��]�݁A���c�̕���O�ɗ��\���܂��ƁA����\���ł��傤�B
���̂悤�ɁA���d�̑����𐰐M���������u����鎖�͑R��ׂ��ł��B�v
�R�{���������̂悤�ɍH�v���Đ\�����̂ɁA���d�̑����𐰐M���͏����u���ꂽ�B�����Ċ���̕��ʂ̔@��
�z�K�O�͂�����x�сA�l�����b�{�i�サ���B
���̔N�A�V���\�ܔN�Ɏl�Y�a�i�����j���a�����ꂽ�B����ɂ���Đz�K�O�����`�l���ɑ�����鎖�A
����O���O�ƂȂ����B
�w�b�z�R�Ӂx
���c���M���z�K���d�̖��𑤎��Ƃ��Č}����܂̂��b
456�l�Ԏ����l�N
2022/10/20(��) 00:20:51.49ID:HQmP2XuJ �����b���c�H
457�l�Ԏ����l�N
2022/10/20(��) 07:01:11.88ID:04wJO1Z2 �W���b�v�ُ̈퐫���_�Ԍ�����
458�l�Ԏ����l�N
2022/10/20(��) 13:08:58.36ID:7Ngem8q6 >>454
�܂Ƃ߂̂����炩�炷��ƁA�c���E�������R�Ƃ̎���E��ÊW�҂̐l�����G�g�����p���A���������P�����Ƃ������Ƃł�����
�����̏��J
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13451.html
�܂Ƃ߂̂����炩�炷��ƁA�c���E�������R�Ƃ̎���E��ÊW�҂̐l�����G�g�����p���A���������P�����Ƃ������Ƃł�����
�����̏��J
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13451.html
459�l�Ԏ����l�N
2022/10/22(�y) 11:17:14.81ID:qF9HUZG8 ���c���M�����R�{�����ɖ��ꂽ
�u���āA�����̐l�̗l�q�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��낤���B�v
�����͐\���グ��
�u������k���ɁA�l������\���قǂ̑叫�́A�����̌X���ɂ���܂����A���ɂ����
���߁A���͈Ⴂ������A���܂���͈�ł͂Ȃ��ƕ����Ă��܂��B�v
�u�叫�͂��̒ʂ�ł��낤�B��������������e���l�܂ŁA���ɂ���ĕς��̂��B�v
�u���͏���������A���X�̉ƕ������Ă��܂����B���̏㍡��`�����̌�Ƃ�]��ŏx�͂ɋ�N�݂�ԂɁA
�����̘S�l�ƌ𗬂��l�X�Ȃ��Ƃ����������܂����B���̌o�����A���̖{���ł���O�͂�蓌�̐l�X�́A
�����ł��B
�܂��������a����܂ł���̋C���ł���A�l���A�����A��B�́A�C����������ł��B
�}���̉��́A���B�O�Ɏ��Ă��܂��B
�悸�A�����������ɂ����ẮA�\�l����l�A����ł��邱�Ƃ͋H�ł���A�����ł��邱�Ƃ��B�����A
�ۛ��̐l�ł���Εs���⌇�_�������Ă��_�߁A����������Ύ蕿�̐l�ł����A���m�̏㒆���̓�����
���w�������A�������Ίo���Ƃ��A�����o�������������������A���S�̎傪���ɗ������ꍇ�A
���̔튯����Ƃ��āA�튯�̖����𐿂��Ė���邱�Ƃ��������߁A�����w�Ɍ����܂��B
�튯�����g����̖����𖼏��͎̂蕿�ł���܂��B�u����͋g�ǂɏオ��A�g�Ǔa�͌����֏オ��v��
�����Ă��܂��B
���āA�����ɂ����Ă͔튯���d�オ���̖�����\���邱�Ƃ͂���܂����A�d��������Ɛ\���āA
�튯����Ƃ��Ė{�����̂āA�튯�̖����ɐ��鎖�͂���܂���B
�֓��ɂ����Ă͌���͎�ł���Ȃ��珬�g�ł���A����J�͔튯�ł���Ȃ����g�ł����A����ƑΖʂ��鎞�A
��g�̑���J�͈܂�܂��B�v
�����ŁA���M���͋�����\���ꂽ
�u����̏��l�������w�Ȃ̂́A���l�̌��ł͂Ȃ��B�叫�����ΉƘV�����A�ƘV�����Ώ����Ҍ��A
�����҂����Ή��X�������̂��B�v
�w�b�z�R�Ӂx
�����̋C���ɂ��Ă̑Θb�B
�Ȃɂ��Ɂu�䏊���₦��A�g�ǂ��p���A�g�ǂ��₦����삪�p���v�̌��l�^�炵�����̂�����܂��ˁB
�u���āA�����̐l�̗l�q�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��낤���B�v
�����͐\���グ��
�u������k���ɁA�l������\���قǂ̑叫�́A�����̌X���ɂ���܂����A���ɂ����
���߁A���͈Ⴂ������A���܂���͈�ł͂Ȃ��ƕ����Ă��܂��B�v
�u�叫�͂��̒ʂ�ł��낤�B��������������e���l�܂ŁA���ɂ���ĕς��̂��B�v
�u���͏���������A���X�̉ƕ������Ă��܂����B���̏㍡��`�����̌�Ƃ�]��ŏx�͂ɋ�N�݂�ԂɁA
�����̘S�l�ƌ𗬂��l�X�Ȃ��Ƃ����������܂����B���̌o�����A���̖{���ł���O�͂�蓌�̐l�X�́A
�����ł��B
�܂��������a����܂ł���̋C���ł���A�l���A�����A��B�́A�C����������ł��B
�}���̉��́A���B�O�Ɏ��Ă��܂��B
�悸�A�����������ɂ����ẮA�\�l����l�A����ł��邱�Ƃ͋H�ł���A�����ł��邱�Ƃ��B�����A
�ۛ��̐l�ł���Εs���⌇�_�������Ă��_�߁A����������Ύ蕿�̐l�ł����A���m�̏㒆���̓�����
���w�������A�������Ίo���Ƃ��A�����o�������������������A���S�̎傪���ɗ������ꍇ�A
���̔튯����Ƃ��āA�튯�̖����𐿂��Ė���邱�Ƃ��������߁A�����w�Ɍ����܂��B
�튯�����g����̖����𖼏��͎̂蕿�ł���܂��B�u����͋g�ǂɏオ��A�g�Ǔa�͌����֏オ��v��
�����Ă��܂��B
���āA�����ɂ����Ă͔튯���d�オ���̖�����\���邱�Ƃ͂���܂����A�d��������Ɛ\���āA
�튯����Ƃ��Ė{�����̂āA�튯�̖����ɐ��鎖�͂���܂���B
�֓��ɂ����Ă͌���͎�ł���Ȃ��珬�g�ł���A����J�͔튯�ł���Ȃ����g�ł����A����ƑΖʂ��鎞�A
��g�̑���J�͈܂�܂��B�v
�����ŁA���M���͋�����\���ꂽ
�u����̏��l�������w�Ȃ̂́A���l�̌��ł͂Ȃ��B�叫�����ΉƘV�����A�ƘV�����Ώ����Ҍ��A
�����҂����Ή��X�������̂��B�v
�w�b�z�R�Ӂx
�����̋C���ɂ��Ă̑Θb�B
�Ȃɂ��Ɂu�䏊���₦��A�g�ǂ��p���A�g�ǂ��₦����삪�p���v�̌��l�^�炵�����̂�����܂��ˁB
460�l�Ԏ����l�N
2022/10/22(�y) 12:33:27.28ID:1mTUQqSV �n�b�^�����܂��Ă邯�ǁA���͂������������܂ł����m��Ȃ����Ă�Ă邼����
461�l�Ԏ����l�N
2022/10/27(��) 00:57:29.50ID:vN2GInnE ����ƍN�̎q�� �@�Ƃ������� 19��ƍL�����Ɠp���� [��̂��������]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1666792359/1
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1666792359/1
462�l�Ԏ����l�N
2022/10/27(��) 11:52:18.39ID:WHqaTSMd ���h����l�͐����l����Ŕ������ł��I�Ȃ�Đ錾���Ė���}�n���痧��₵�����삳��ł���
���̍����o�J�a���������������v���낤��(�l�I�Ȋ��z�ł�)
���̍����o�J�a���������������v���낤��(�l�I�Ȋ��z�ł�)
463�l�Ԏ����l�N
2022/10/28(��) 21:33:15.59ID:e/wWnGUB ���鎞�A���c���M���͎R�{�����������Ă��̂悤�ɋ��ɂȂ����B
�u���₵�������̐��M�A�l�̎g���悤�́A�l���g���̂ł͂Ȃ��A�Z���g���̂��B�܂�������v�����A�Z��v���̂��B
�������Z�̖����悤�ɐl���g�������S�n�悭�Ȃ�B
���̒��ɂ����āA���M�̐l�̌��l�́A���S���̎҂͖��ē��ł���B���ē��̎҂͕s���w�ł���B�s���w�Ȏ҂�
�K�����O�ł���B���O�Ȃ�҂͕K���ߌ���\���B�ߌ���\���҂͕K������Ղ��߂�₷���B����Ղ��߂�₷��
�҂͎���s���ł���B����s���Ȃ�҂͕K���p��m�炸�A�p��m�炴��҂͉��ɂ��Ă��A�F�d��Z������
���ł���B
�����������������҂ł����Ă��A���̕i�X�ɂ����Ďg�����́A�����叫�̂ЂƂ̎��߂ł���B
�����叫�̎��ߌ����Ƃ́A���З̂�t���A�o�Ƃ�y���d��A�����͑����̏�傪�S�l�����̂�����u���A
���̍�������Ė{�ӂ̒n�ֈ��g�����A�܂����g�̘S�l�ł����Ă��}�����A��������Ă͂��̐��������A
���l�̖��f�����悤�Ɍb�ށB
���̔@�����ߌ����̎{���ɂ���āA���荇����������A����U�ߗ��Ƃ��A�܂��͍����d�u�̂��߂ɉȐl��
���߁A���߂Ƃ������߂������đނ��B���̗��ɂ���āA�����̎��ߌ����̗͊v�Ȃ̂��B
��X�A���l�̐\�����ƂɁA�ߌ��ƈЌ��͈�̎��Ƃ��Ă��邪�A�Ќ��͗L�鎖��\�����̂ł���A
�ߌ��͖�������\�����̂ł���B�ł��邽�߁A���m�̈Ќ��͐\���Ă����قǕs���ł͂Ȃ��B
�Ќ��̎��ɂ͊o��������̂��B���ނׂ��炸�B
�ߌ���\�����́A���̓��e����莖�ł���̂ɁA�O�x���O�l�ɕς���ē��e���قȂ�B����͋�����
�����Ă��邽�߁A���̂悤�ɂȂ�̂��B����͕K���A�����ׂ����Ƃł���B�v
���̐��M���̋��ɁA�R�{�����������������B
�w�b�z�R�Ӂx
�u���₵�������̐��M�A�l�̎g���悤�́A�l���g���̂ł͂Ȃ��A�Z���g���̂��B�܂�������v�����A�Z��v���̂��B
�������Z�̖����悤�ɐl���g�������S�n�悭�Ȃ�B
���̒��ɂ����āA���M�̐l�̌��l�́A���S���̎҂͖��ē��ł���B���ē��̎҂͕s���w�ł���B�s���w�Ȏ҂�
�K�����O�ł���B���O�Ȃ�҂͕K���ߌ���\���B�ߌ���\���҂͕K������Ղ��߂�₷���B����Ղ��߂�₷��
�҂͎���s���ł���B����s���Ȃ�҂͕K���p��m�炸�A�p��m�炴��҂͉��ɂ��Ă��A�F�d��Z������
���ł���B
�����������������҂ł����Ă��A���̕i�X�ɂ����Ďg�����́A�����叫�̂ЂƂ̎��߂ł���B
�����叫�̎��ߌ����Ƃ́A���З̂�t���A�o�Ƃ�y���d��A�����͑����̏�傪�S�l�����̂�����u���A
���̍�������Ė{�ӂ̒n�ֈ��g�����A�܂����g�̘S�l�ł����Ă��}�����A��������Ă͂��̐��������A
���l�̖��f�����悤�Ɍb�ށB
���̔@�����ߌ����̎{���ɂ���āA���荇����������A����U�ߗ��Ƃ��A�܂��͍����d�u�̂��߂ɉȐl��
���߁A���߂Ƃ������߂������đނ��B���̗��ɂ���āA�����̎��ߌ����̗͊v�Ȃ̂��B
��X�A���l�̐\�����ƂɁA�ߌ��ƈЌ��͈�̎��Ƃ��Ă��邪�A�Ќ��͗L�鎖��\�����̂ł���A
�ߌ��͖�������\�����̂ł���B�ł��邽�߁A���m�̈Ќ��͐\���Ă����قǕs���ł͂Ȃ��B
�Ќ��̎��ɂ͊o��������̂��B���ނׂ��炸�B
�ߌ���\�����́A���̓��e����莖�ł���̂ɁA�O�x���O�l�ɕς���ē��e���قȂ�B����͋�����
�����Ă��邽�߁A���̂悤�ɂȂ�̂��B����͕K���A�����ׂ����Ƃł���B�v
���̐��M���̋��ɁA�R�{�����������������B
�w�b�z�R�Ӂx
464�l�Ԏ����l�N
2022/10/29(�y) 08:59:24.12ID:DUqMqWs2 ���Ղ̎����w���Ă�̂���
465�l�Ԏ����l�N
2022/10/29(�y) 23:45:18.29ID:5mymJD+5 �ߌ���\�����́A���̓��e����莖�ł���̂ɁA�O�x���O�l�ɕς���ē��e���قȂ�B����͋�����
�����Ă��邽�߁A���̂悤�ɂȂ�̂��B����͕K���A�����ׂ����Ƃł���B�v
���������ł悭�Ȃ��H
�����Ă��邽�߁A���̂悤�ɂȂ�̂��B����͕K���A�����ׂ����Ƃł���B�v
���������ł悭�Ȃ��H
466�l�Ԏ����l�N
2022/10/30(��) 13:35:25.66ID:Eh2d3Waw >>202
�͂��߂܂��āB
��c�������Ă��肱����̋L���ɂ��ǂ���܂����B
�ڂ������Љ�肪�Ƃ��������܂��B
���X�E���i�̎q���ŌÕ��������Ă���̂ł����A
���X��̈Ғ��Ƃ͂ǂ������W�ɂ��邩�����m�ł��傤���H
���������Ă�����������K���ł��B
�͂��߂܂��āB
��c�������Ă��肱����̋L���ɂ��ǂ���܂����B
�ڂ������Љ�肪�Ƃ��������܂��B
���X�E���i�̎q���ŌÕ��������Ă���̂ł����A
���X��̈Ғ��Ƃ͂ǂ������W�ɂ��邩�����m�ł��傤���H
���������Ă�����������K���ł��B
467�l�Ԏ����l�N
2022/10/30(��) 15:26:26.72ID:dLte+MCx ���B�̐D�c�e�����i�M�G�j�������āA���̎q���A���̐M���ł��邪�A�ނ͍���`�����̊����ƂȂ炸�A
������`�������������̍��ł������O�͂̓��A�g�ǂ̏�֎��|���A������Ă�����U�߂��B
���̎��̂ɋ`�����͌�n���o���ꂽ���A�Ղ��C�������B���n�ɐ�������A��O���ȂĒe�����q���i�D�c�M�L�j��
�n������Ԃ��͂��A���ɍU�ߎE����Ƃ��鏊�ɁA�D�c�͍~�Q���ĕ��̔@���`�����t�`����܂�����
�N���������l�ь��������߁A�`�����ƒe�����q���̘a�r�����������̂ł��邪�A����͔��B���ł���
�}���̐V�E�q��i�˕������j�����˂Ă��`�������ɑ����Ă���A���̐܂ɒ����������Ƃ����B
�܂����̎��`������
�u�O�B����̏��E�����L���̎q�A�|��㓖�N�\�O�ɂȂ���A�ꗼ�N�ȑO��蓐�ݎ��A�M�c��
�B���u���Ƃ����B��������X�ɂ�����֓n���v
�Ƌ��ɂȂ�A�`�����͂��̏����|�����x�{�ɏ����u���ꂽ�B���̉��B�l���܂ŕ��肵�ĕl���ɍ݂�
����ƍN���A���̒|���ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
������������̐킢�ɂ��Ă̂��b�B���̎��_�ł͐D�c�M�G�͂܂������Ă���̂ƁA
�ǂ����M���ƐD�c�M�L���������Ă����t�V������܂��ˁB
������`�������������̍��ł������O�͂̓��A�g�ǂ̏�֎��|���A������Ă�����U�߂��B
���̎��̂ɋ`�����͌�n���o���ꂽ���A�Ղ��C�������B���n�ɐ�������A��O���ȂĒe�����q���i�D�c�M�L�j��
�n������Ԃ��͂��A���ɍU�ߎE����Ƃ��鏊�ɁA�D�c�͍~�Q���ĕ��̔@���`�����t�`����܂�����
�N���������l�ь��������߁A�`�����ƒe�����q���̘a�r�����������̂ł��邪�A����͔��B���ł���
�}���̐V�E�q��i�˕������j�����˂Ă��`�������ɑ����Ă���A���̐܂ɒ����������Ƃ����B
�܂����̎��`������
�u�O�B����̏��E�����L���̎q�A�|��㓖�N�\�O�ɂȂ���A�ꗼ�N�ȑO��蓐�ݎ��A�M�c��
�B���u���Ƃ����B��������X�ɂ�����֓n���v
�Ƌ��ɂȂ�A�`�����͂��̏����|�����x�{�ɏ����u���ꂽ�B���̉��B�l���܂ŕ��肵�ĕl���ɍ݂�
����ƍN���A���̒|���ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
������������̐킢�ɂ��Ă̂��b�B���̎��_�ł͐D�c�M�G�͂܂������Ă���̂ƁA
�ǂ����M���ƐD�c�M�L���������Ă����t�V������܂��ˁB
468�l�Ԏ����l�N
2022/10/30(��) 16:33:47.13ID:t+SIK8yx >>467
��������͔s�����Ĉ���̖h�����ł߂����܂ŁA���闎��͂��̌�̘b�ł���B�f�l�݂����ȊԈႢ�������ł��ˁB
��������͔s�����Ĉ���̖h�����ł߂����܂ŁA���闎��͂��̌�̘b�ł���B�f�l�݂����ȊԈႢ�������ł��ˁB
469�l�Ԏ����l�N
2022/11/04(��) 19:23:34.51ID:A2ZHoV7J �b�{�ɂĂ��̓x�A���R��w�i�i�\6�N�i1563�j�̖k���B���c�A���R�ɂ�鏼�R��U�߁j�ɏo�w���邽�߂ɕĂ�
�ؗp�������O�ɂ��Ē����Ȃ���A�\�X�g�㐬�炴��ƁA���c�M�����͌䕪�ʂ�������A�ނ�̊�e�O��
���t�����A����玘�O�̏��̂̓��A���n�̈����n�����グ�A���̑���Ƃ��ď�[�̓y�n�������A
�������͂��̌�̒��߁A�����ɂ���āA���̂̏��Ȃ��҂ɂ͌�������Ȃ��ꂽ�B
���̎��ɏ��l�͐M������z�Ȃ������A���̂����҂����Ȃ��҂��A�u���������叫���ȁv��
����������B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M�����A�R���̂��߂ɎؕĂ��������m�������~�ς����Ƃ������b�ł��ˁB
�ؗp�������O�ɂ��Ē����Ȃ���A�\�X�g�㐬�炴��ƁA���c�M�����͌䕪�ʂ�������A�ނ�̊�e�O��
���t�����A����玘�O�̏��̂̓��A���n�̈����n�����グ�A���̑���Ƃ��ď�[�̓y�n�������A
�������͂��̌�̒��߁A�����ɂ���āA���̂̏��Ȃ��҂ɂ͌�������Ȃ��ꂽ�B
���̎��ɏ��l�͐M������z�Ȃ������A���̂����҂����Ȃ��҂��A�u���������叫���ȁv��
����������B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M�����A�R���̂��߂ɎؕĂ��������m�������~�ς����Ƃ������b�ł��ˁB
470�l�Ԏ����l�N
2022/11/05(�y) 15:57:25.02ID:kQd4l8F6 �i�D�c�M���̓ڎ���j�ēc�i���Ɓj�a���O���i�D�c�M�F�j�a��V���̎�Ɏ�藧�Ă����ƕ��ʂ����̂́A
�ēc�a���O���a�̋���߂��d��ꂽ�̂ł���ƕ����Ă���B���̌�_��̂ɁA��Ɍ䍧�ȊW��
�������̂��Ƃ����B
�i�H�āj�G�g�ɂ��ẮA���i�D�c�M���j�a�ƌ䍧�ł������Ƃ����B���̎e�ׂ́A���a����O�̎��ɁA
����ƏO�ȂǂɌ����Ȃ���A��������v�������ꂽ��C�F���G�g�͌��Ď���āA���a��
�u�Ȃ�A���Ɍ�ڂ��|���Ă���Ɛ��Ԃɔ�I���ĉ������B��������Ό�C������ȂǗL��܂���B
���̏㎄�ɂ����Ă��A���X�ɓ�����Ƃ�\���グ�邱�Ƃ͗L��܂���B�\�ʏゾ���ł��A���̂悤��
�Ȃ����ׂ��ł��B�i�O�V���E�̒ʂɉ퐬�j�v
�M���l���u���̒ʂ肾�v�Ǝv��������A�G�g�͐M���l�̌�m���̂悤�ɁA���Ԃł͔F�����ꂽ�B
�����Č�X����ڂ�������悤�ɐ���ꂽ�B
�i��p���}�L�j
�G�g���M���Ɏ��������i�H�j���b�B����͏G�g�����ŕ�s�����Ă�������A�G�g�����
���ƏO�ƐM���̒�����莟����A�݂����Șb�Ȃ�ł����ˁB
�ēc�a���O���a�̋���߂��d��ꂽ�̂ł���ƕ����Ă���B���̌�_��̂ɁA��Ɍ䍧�ȊW��
�������̂��Ƃ����B
�i�H�āj�G�g�ɂ��ẮA���i�D�c�M���j�a�ƌ䍧�ł������Ƃ����B���̎e�ׂ́A���a����O�̎��ɁA
����ƏO�ȂǂɌ����Ȃ���A��������v�������ꂽ��C�F���G�g�͌��Ď���āA���a��
�u�Ȃ�A���Ɍ�ڂ��|���Ă���Ɛ��Ԃɔ�I���ĉ������B��������Ό�C������ȂǗL��܂���B
���̏㎄�ɂ����Ă��A���X�ɓ�����Ƃ�\���グ�邱�Ƃ͗L��܂���B�\�ʏゾ���ł��A���̂悤��
�Ȃ����ׂ��ł��B�i�O�V���E�̒ʂɉ퐬�j�v
�M���l���u���̒ʂ肾�v�Ǝv��������A�G�g�͐M���l�̌�m���̂悤�ɁA���Ԃł͔F�����ꂽ�B
�����Č�X����ڂ�������悤�ɐ���ꂽ�B
�i��p���}�L�j
�G�g���M���Ɏ��������i�H�j���b�B����͏G�g�����ŕ�s�����Ă�������A�G�g�����
���ƏO�ƐM���̒�����莟����A�݂����Șb�Ȃ�ł����ˁB
471�l�Ԏ����l�N
2022/11/06(��) 01:59:48.84ID:gzZeLy/7472�l�Ԏ����l�N
2022/11/06(��) 11:39:37.23ID:3YVvZo8d ���X���̓��b�`���C�L��ɂ��܂��H
�Ȃ�Ȃ�IP�L��ł��\���܂���
�Ȃ�Ȃ�IP�L��ł��\���܂���
473�l�Ԏ����l�N
2022/11/06(��) 13:03:06.05ID:XkItWTWy �����A���ꂢ����
�A�t�B�J�X���ق��Ă�S�~�̓��肪�����
�A�t�B�J�X���ق��Ă�S�~�̓��肪�����
474�l�Ԏ����l�N
2022/11/06(��) 16:46:48.05ID:XrQtncg6 �i�˃��x�̏����̌�A�ēc���Ƃ̏��̂ł���z�O�肵���H�ďG�g�́A�ނɏ]�������O�c���Ƃ��̂���\�o���֓������B�j
�\�o���������������G�g�́A�z���Ƃ̋��ڂł��閖�X�����藧�Ă�悤�ɂƌ����A�����
������������A�O�c�����q��i���Ɓj�Ɉς��������܂߂��B
���̎��A�O�c�����q�傪�\���グ��
�u���̐����ŁA�z���֎��|����A�������i���X�����j����ގ������ׂ��ł��B�v
�G�g�͕ԓ���
�u���̎��ɂ��āA�v���o�������Ƃ��L��B�����ƌ����A�V���O�N�܌���\����ɁA�b�㍑���c�l�Y�i�����j��
�O�B���ɂ����ĐM�������䍇�퐬���ꂽ���A�ꖜ���]�蓢�����叟�������ƁA�M�a���䋟����
�̂ɔ\�������m�ł��낤�B
���̎��A���̂܂܍b�㍑�։������ނ̂��낤�ƁA�����l���l���Ă����B�Ƃ��낪�M�����͂��������A
��������A�w�Ȃ��ꂽ�B���̎��A�䐨���A�䗘�^�ł���ȏ�͂Ȃ��Ǝv��ꂽ���A������������
�V���̏��ƂƂ������̂�����A�܁C�O�N�����̂܂̂Ēu���A�����ɖd�����o���A�ƒ����܂��܂���
���邱�Ƃ���������悤�ɂ��Ȃ邾�낤�B���̎��ɔn���o���đގ�����̂��A�Ƃ����䕪�ʂł�������
��������B
�����q��a���F�X�������Ăق����B���Ƃɑł��������ȏ�A���̏G�g������ɉ߂�����g�͂Ȃ��B
���̏�ŐS�Ȃ炸�����S���邱�Ƃ�����Ɗo����B���̏�A���X�ȉ��ɋy�Ԃ܂ŏ����ɏ��̂ŁA
���X�E�݉x�сA���ɏ��悤�ȗl�q�ł���B
���X�������͍��Ȃ��Ɏ蕷�̏��ł���B�܂�����̏K���Ƃ��āA���s�͐l���̑����ɕK������������
�ł͂Ȃ��B����āA������ꑫ��Ɉ�����낤�Ǝv���B���̓��ɁA�G�g���ĂьR������o�w���Ă������́A
�ʋl�߂ɐ��邾�낤�Ɠ��������A�܂����̉ƒ��̎ҒB���l���o���ł��낤���Ƃ͕K��ł���B�����Ȃ��
�ƒ��ɂ��d���҂��o�Ă��邾�낤�B
�����ɂ��Ă��A�ł��g���낤��������̂͐������߂��Ă��鎞�ł���A�����炱�����������ׂ��ł���B�v
���̂悤�ɐ\���āA���B���R��ɓ����A���B�����Ɣ\�o�ꍑ��O�c�����q�嗘�Ƃɗ^�����B
�܂��\�o�ɉ����Ē���Y���q��i�A���j�ɑ��A�u�O�c�����q��ɕt���u���B���������Ǝ���Ƃ���悤�ɁB�v
�Ƌ��u���ꂽ�B
�i��p���}�L�j
�\�o���������������G�g�́A�z���Ƃ̋��ڂł��閖�X�����藧�Ă�悤�ɂƌ����A�����
������������A�O�c�����q��i���Ɓj�Ɉς��������܂߂��B
���̎��A�O�c�����q�傪�\���グ��
�u���̐����ŁA�z���֎��|����A�������i���X�����j����ގ������ׂ��ł��B�v
�G�g�͕ԓ���
�u���̎��ɂ��āA�v���o�������Ƃ��L��B�����ƌ����A�V���O�N�܌���\����ɁA�b�㍑���c�l�Y�i�����j��
�O�B���ɂ����ĐM�������䍇�퐬���ꂽ���A�ꖜ���]�蓢�����叟�������ƁA�M�a���䋟����
�̂ɔ\�������m�ł��낤�B
���̎��A���̂܂܍b�㍑�։������ނ̂��낤�ƁA�����l���l���Ă����B�Ƃ��낪�M�����͂��������A
��������A�w�Ȃ��ꂽ�B���̎��A�䐨���A�䗘�^�ł���ȏ�͂Ȃ��Ǝv��ꂽ���A������������
�V���̏��ƂƂ������̂�����A�܁C�O�N�����̂܂̂Ēu���A�����ɖd�����o���A�ƒ����܂��܂���
���邱�Ƃ���������悤�ɂ��Ȃ邾�낤�B���̎��ɔn���o���đގ�����̂��A�Ƃ����䕪�ʂł�������
��������B
�����q��a���F�X�������Ăق����B���Ƃɑł��������ȏ�A���̏G�g������ɉ߂�����g�͂Ȃ��B
���̏�ŐS�Ȃ炸�����S���邱�Ƃ�����Ɗo����B���̏�A���X�ȉ��ɋy�Ԃ܂ŏ����ɏ��̂ŁA
���X�E�݉x�сA���ɏ��悤�ȗl�q�ł���B
���X�������͍��Ȃ��Ɏ蕷�̏��ł���B�܂�����̏K���Ƃ��āA���s�͐l���̑����ɕK������������
�ł͂Ȃ��B����āA������ꑫ��Ɉ�����낤�Ǝv���B���̓��ɁA�G�g���ĂьR������o�w���Ă������́A
�ʋl�߂ɐ��邾�낤�Ɠ��������A�܂����̉ƒ��̎ҒB���l���o���ł��낤���Ƃ͕K��ł���B�����Ȃ��
�ƒ��ɂ��d���҂��o�Ă��邾�낤�B
�����ɂ��Ă��A�ł��g���낤��������̂͐������߂��Ă��鎞�ł���A�����炱�����������ׂ��ł���B�v
���̂悤�ɐ\���āA���B���R��ɓ����A���B�����Ɣ\�o�ꍑ��O�c�����q�嗘�Ƃɗ^�����B
�܂��\�o�ɉ����Ē���Y���q��i�A���j�ɑ��A�u�O�c�����q��ɕt���u���B���������Ǝ���Ƃ���悤�ɁB�v
�Ƌ��u���ꂽ�B
�i��p���}�L�j
475�l�Ԏ����l�N
2022/11/08(��) 21:30:21.63ID:KK3AKmtk �i�\�Z�N���������A���B�|��̚������Ƃ������@�̎����o�ƈ�l���b�{�ւƗ����B
���Ⓑ�Ղɕt���Č�O�ɎQ��A�M�����ɐ\���グ�����e�́A�䕃�M�Ռ����A���쎁�����̌�C��
����A���̏t���ɓs�ɏオ����\��ł���Ƃ����B���̎���\���グ����ŁA
�u���g�̎��ŐM��������S�₷���v�������A�����ɂ��������肵�����ʂ��鎘�v����l�A���̑m�Ƌ���
��z���Ăق����Ƃ̎��ł������B�����ŐM�����͓��������ւɐ����\�O���ɖ������̓��̓���
�b�{�𗧂����A���B�|�욢�����ւƔh�������B
�����ւ͏\�����Ɋ|�욢�����ɓ������A���̖�ɐM�Ռ��̌�ڂɂ��������B
�M�Ռ��͋��ɂȂ���
�u���������ւƖ�����Ă���悤�����A���O�͉��҂Ȃ̂��B�v
�u������a�̐e�ނł���܂��B�M�l���b�B�����S�l�ƂȂ�ꂽ���A�������\�Z�N�O��
���͕�����������Ă��炸�A������a�𗊂�A�N�����\�ɂ��͂��Ă��܂���ł����B
�܂������A�M�Z���{���ł���܂��B�v
�M�Ռ��͕���������
�u���Ƃ����҂ł����Ă��A�M�����S�����v���Ă���̂ł���ꂵ���炸�B�v�Ƌ��ɂȂ���
�i�����j
���̖锼�A�l�X���݂ȐÂ܂��������ɐM�Ռ��͌����ւ������ċ��ɂȂ����B
�u���͐M���ɑ��č��݂�����ƌ����Ă��A����͊��ɉ߂��ċv���������B�܂��M���̕��̓�����
���X�����B
���̍��́A�\����ɂ��\�����ꂩ���Ǝv���ĐܟB�����̂����A���l����Ƃ��̐M�Ղ̂�������Ƃ�
�S�ĊԈႢ�ł������Ǝv���B�i���V�͂悫���ւɂ��\�����ꂩ���Ƒ��āA�ܟB�d��ǂ��A�M�Ղ݂�
�����ЂȂ�Ǝv�Ӂj
���̂Ȃ�A���M���̗_��͖������������A�M�Z�͊F��ɓ���āA��ˍ��A��썑�܂ł��ꗼ�N�̊Ԃ�
���߂�Ƃ����������A�M�Ղ̏j������ɉ߂����B
�����A�M���Ɍ����Ăق����B�v
���̂悤�ɋ��ɐ���ƁA�����ւ́u�܂�Č�v�Ɛ\���グ���B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M�Ղ��M���̔h���������ɑ��A�����̊ԈႢ�𗦒��ɔF�߂��Ƃ������b�B
���Ⓑ�Ղɕt���Č�O�ɎQ��A�M�����ɐ\���グ�����e�́A�䕃�M�Ռ����A���쎁�����̌�C��
����A���̏t���ɓs�ɏオ����\��ł���Ƃ����B���̎���\���グ����ŁA
�u���g�̎��ŐM��������S�₷���v�������A�����ɂ��������肵�����ʂ��鎘�v����l�A���̑m�Ƌ���
��z���Ăق����Ƃ̎��ł������B�����ŐM�����͓��������ւɐ����\�O���ɖ������̓��̓���
�b�{�𗧂����A���B�|�욢�����ւƔh�������B
�����ւ͏\�����Ɋ|�욢�����ɓ������A���̖�ɐM�Ռ��̌�ڂɂ��������B
�M�Ռ��͋��ɂȂ���
�u���������ւƖ�����Ă���悤�����A���O�͉��҂Ȃ̂��B�v
�u������a�̐e�ނł���܂��B�M�l���b�B�����S�l�ƂȂ�ꂽ���A�������\�Z�N�O��
���͕�����������Ă��炸�A������a�𗊂�A�N�����\�ɂ��͂��Ă��܂���ł����B
�܂������A�M�Z���{���ł���܂��B�v
�M�Ռ��͕���������
�u���Ƃ����҂ł����Ă��A�M�����S�����v���Ă���̂ł���ꂵ���炸�B�v�Ƌ��ɂȂ���
�i�����j
���̖锼�A�l�X���݂ȐÂ܂��������ɐM�Ռ��͌����ւ������ċ��ɂȂ����B
�u���͐M���ɑ��č��݂�����ƌ����Ă��A����͊��ɉ߂��ċv���������B�܂��M���̕��̓�����
���X�����B
���̍��́A�\����ɂ��\�����ꂩ���Ǝv���ĐܟB�����̂����A���l����Ƃ��̐M�Ղ̂�������Ƃ�
�S�ĊԈႢ�ł������Ǝv���B�i���V�͂悫���ւɂ��\�����ꂩ���Ƒ��āA�ܟB�d��ǂ��A�M�Ղ݂�
�����ЂȂ�Ǝv�Ӂj
���̂Ȃ�A���M���̗_��͖������������A�M�Z�͊F��ɓ���āA��ˍ��A��썑�܂ł��ꗼ�N�̊Ԃ�
���߂�Ƃ����������A�M�Ղ̏j������ɉ߂����B
�����A�M���Ɍ����Ăق����B�v
���̂悤�ɋ��ɐ���ƁA�����ւ́u�܂�Č�v�Ɛ\���グ���B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M�Ղ��M���̔h���������ɑ��A�����̊ԈႢ�𗦒��ɔF�߂��Ƃ������b�B
476�l�Ԏ����l�N
2022/11/09(��) 14:32:11.08ID:hBj+9dfM >>475
���O���ԈႢ��f���ɔF�߂�
���O���ԈႢ��f���ɔF�߂�
477�l�Ԏ����l�N
2022/11/15(��) 20:41:39.74ID:bTevtSEj �i���q���v�荇���A�D�c�M�Y�Ƙa�r�𐬗����������Ɓj
�G�g�͓���ƍN����������t���������悤�Ǝv�������A���̂��߂̌䕪�ʁA��H�v�ɔY�݁A
�Q�t���Ȃ��قǂł������ƕ��������B
���̒i�X�̌䕪�ʂ̎��悾���A�G�g�͌䂠�����i�a�r�j���|���邽�߂ɁA�ƍN�̗l�q���������悤�Ǝv�������A
�ƍN���̍��̗l�q���䕷���ɐ��邽�߂ɁA�l��F�X�ɕϑ������A�O�͉��]�����������B
���̎��A�G�g�̌䕪�ʂƂ��ẮA�u�ƍN�����ď�̎x�x������Ȃǂ��蓾�Ȃ��B�����ꍇ��Ƃ̂�
��߂Ă��邾�낤�B�v�Ǝv��������Ă����B
��̖ڕt�������A�����A���q�˂ɐ������Ƃ���A�u�ƍN���ď�̗p�ӂȂǑS�������܂���B
�������̂悤�ȈԂݎ����肵�Ă��܂��B�v�ƌ����B�ォ��Q�����ڕt�����l�̕ł���A
�G�g�̐��ʂ͏��������Ȃ������B
�����ŏG�g�́A�䂠�����ׂ̈ɉƍN�ɖ���^���A���̏�͌Z��ɐ���ׂ��ƁA�䂠�������|�����B
���̏�ʼnƍN�����܂����_������A��Ə��ǂ��A����ɖ��̎O�l���ƍN���l���ɏo���ׂ��ƁA
�I�{��F�E�q��i�����j�⍕�c�����q�A���̑���A�O�l�ɋ����������B
�i��p���}�L�j
�G�g�͓���ƍN����������t���������悤�Ǝv�������A���̂��߂̌䕪�ʁA��H�v�ɔY�݁A
�Q�t���Ȃ��قǂł������ƕ��������B
���̒i�X�̌䕪�ʂ̎��悾���A�G�g�͌䂠�����i�a�r�j���|���邽�߂ɁA�ƍN�̗l�q���������悤�Ǝv�������A
�ƍN���̍��̗l�q���䕷���ɐ��邽�߂ɁA�l��F�X�ɕϑ������A�O�͉��]�����������B
���̎��A�G�g�̌䕪�ʂƂ��ẮA�u�ƍN�����ď�̎x�x������Ȃǂ��蓾�Ȃ��B�����ꍇ��Ƃ̂�
��߂Ă��邾�낤�B�v�Ǝv��������Ă����B
��̖ڕt�������A�����A���q�˂ɐ������Ƃ���A�u�ƍN���ď�̗p�ӂȂǑS�������܂���B
�������̂悤�ȈԂݎ����肵�Ă��܂��B�v�ƌ����B�ォ��Q�����ڕt�����l�̕ł���A
�G�g�̐��ʂ͏��������Ȃ������B
�����ŏG�g�́A�䂠�����ׂ̈ɉƍN�ɖ���^���A���̏�͌Z��ɐ���ׂ��ƁA�䂠�������|�����B
���̏�ʼnƍN�����܂����_������A��Ə��ǂ��A����ɖ��̎O�l���ƍN���l���ɏo���ׂ��ƁA
�I�{��F�E�q��i�����j�⍕�c�����q�A���̑���A�O�l�ɋ����������B
�i��p���}�L�j
478�l�Ԏ����l�N
2022/11/18(��) 20:38:56.88ID:NfUjnO14 ���c�ˑ��n���ɂ��ĘV�m�����Ƃ����̍ق́u�Ë�����v���獕�c�ˉƘV�̈�l�E���͓�����(���͔V��)�̏o��
������:���͓�����Ƃ����l�͍����̎d�u������l�łȂ����������ł����A�����m�����ʂɗD��A���E���������̂ł��傤�B
�V�m:������͂��Ƃ��Ƌg�c�P���q�Ƃ������̂��u���v�������Ȃ��̂ő������ɂł������g���Ă��������v�ƍ��c�������ɍ����o�����쏕�Ƃ����҂ł��B
�����A�����ɂ������̂悤�ŗ����ȂƂ��낪�Ȃ��������ߏ����E�T�y���炢���߂��Ă��܂����B
���������C����l��苭���A�����l�̂��𗣂ꂸ�A������������A�����܂����������A�������Ԃ���������Ԃ�������܂���ł����B
�V���Ă����܂��͂����A�Ⴊ���ł��Ă���ŗD�����������������������ł��B
�ق��̏��������Ȃ��Ă��쏕�͂��ɂ���̂ŁA���R�ƒ������͊쏕�ɗp����������悤�ɂȂ�A�\�l�A�܂̍��ɂ͏o�����ƂȂ�܂����B
�����Œ������͒��N�ɂ������A��A�������������Ȃ����𗝗R�ɏo�������悤�Ǝv��ꂽ�̂ł����A�s�^�Ȃ��ƂɊ쏕���s���Ƃ���Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɓG�����ꑱ�������߁A��x���������グ�邱�Ƃ�����܂���ł����B
�Ƃ͂������a���������킯�ł͂Ȃ����߁A�j�q�Ȃ����ē��傪�����͉Ƃɖ��{�q�Ƃ��ē���A�ܐ���Ƃ邱�ƂƂȂ�܂����B
�ӂ��o������Ƃ�������̂ł����A������ɂ��Ă͏����̎��̐S������ς��Ȃ��������߁A���ނ��̂͂��܂���ł����B
�փ����ɂ��Q�w�����̂ł����A����܂��^�����������������܂���ł����B
�������A�}�O���q�̂̎��ɔ���ɉ������A�����E�ƒ��̎d�u�������ɔC���܂����B
����������Ƃ������̂�m�炸�A�Â�������i�����A�S�����l�ł����Ă����蒼�ɒʂ��A�J�̎��͗����ʼn����ɍs���A���X�̑i�����܂����B
��̔��f���K�v�Ȏ��ɂ͔N��O�Ƙb����������Œ������ɐq�ˁA�̂��̂��ƒf�Ŗ��ƂȂ邱�Ƃ��Ȃ��������߁A�N��O���u���Ƃɂ͓�����قǎ��ߐ������V���Ɋ����Ă���o���l�͂��Ȃ����낤�v�Ƃ�낱�т܂����B
�������Ē}�O�����ܔN�ڂɂ͓��Ή�������A�ꖜ�Ύ��ƂȂ����̂ł��B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-1801.html
���͓�����A��N���c�����ɁE�����b
�܂��A���̂悤�Șb������A�ҁX�����������ł���������̏_�a�̑O�ł͎���ĉ�Ă��܂��ƁA�F�s�v�c�����Ă���܂����B
������:���͓�����Ƃ����l�͍����̎d�u������l�łȂ����������ł����A�����m�����ʂɗD��A���E���������̂ł��傤�B
�V�m:������͂��Ƃ��Ƌg�c�P���q�Ƃ������̂��u���v�������Ȃ��̂ő������ɂł������g���Ă��������v�ƍ��c�������ɍ����o�����쏕�Ƃ����҂ł��B
�����A�����ɂ������̂悤�ŗ����ȂƂ��낪�Ȃ��������ߏ����E�T�y���炢���߂��Ă��܂����B
���������C����l��苭���A�����l�̂��𗣂ꂸ�A������������A�����܂����������A�������Ԃ���������Ԃ�������܂���ł����B
�V���Ă����܂��͂����A�Ⴊ���ł��Ă���ŗD�����������������������ł��B
�ق��̏��������Ȃ��Ă��쏕�͂��ɂ���̂ŁA���R�ƒ������͊쏕�ɗp����������悤�ɂȂ�A�\�l�A�܂̍��ɂ͏o�����ƂȂ�܂����B
�����Œ������͒��N�ɂ������A��A�������������Ȃ����𗝗R�ɏo�������悤�Ǝv��ꂽ�̂ł����A�s�^�Ȃ��ƂɊ쏕���s���Ƃ���Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɓG�����ꑱ�������߁A��x���������グ�邱�Ƃ�����܂���ł����B
�Ƃ͂������a���������킯�ł͂Ȃ����߁A�j�q�Ȃ����ē��傪�����͉Ƃɖ��{�q�Ƃ��ē���A�ܐ���Ƃ邱�ƂƂȂ�܂����B
�ӂ��o������Ƃ�������̂ł����A������ɂ��Ă͏����̎��̐S������ς��Ȃ��������߁A���ނ��̂͂��܂���ł����B
�փ����ɂ��Q�w�����̂ł����A����܂��^�����������������܂���ł����B
�������A�}�O���q�̂̎��ɔ���ɉ������A�����E�ƒ��̎d�u�������ɔC���܂����B
����������Ƃ������̂�m�炸�A�Â�������i�����A�S�����l�ł����Ă����蒼�ɒʂ��A�J�̎��͗����ʼn����ɍs���A���X�̑i�����܂����B
��̔��f���K�v�Ȏ��ɂ͔N��O�Ƙb����������Œ������ɐq�ˁA�̂��̂��ƒf�Ŗ��ƂȂ邱�Ƃ��Ȃ��������߁A�N��O���u���Ƃɂ͓�����قǎ��ߐ������V���Ɋ����Ă���o���l�͂��Ȃ����낤�v�Ƃ�낱�т܂����B
�������Ē}�O�����ܔN�ڂɂ͓��Ή�������A�ꖜ�Ύ��ƂȂ����̂ł��B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-1801.html
���͓�����A��N���c�����ɁE�����b
�܂��A���̂悤�Șb������A�ҁX�����������ł���������̏_�a�̑O�ł͎���ĉ�Ă��܂��ƁA�F�s�v�c�����Ă���܂����B
479�l�Ԏ����l�N
2022/11/19(�y) 09:37:49.54ID:c1b3DFvx ���͏����E���c�Ƃ������̂���p�ۏ�v�A��͏��͐M�͂̎o�ŁA�����S���Ȃ藬�Q�̌�A��͍��c��\�l�R�E�ˎR�M�s�ƍč��i��ȁj����B
��ɏ]���ˎR�Ƃɐ��b�ɂȂ�����A�f���̖��{�q�ƂȂ�i���O���炩�����{�q���͂�����ƕs���j�B���c�����ł͔ˎ咉�V��⍲�B
���͔V���̌o���͎��ۂ̂Ƃ��낱��Ȋ����炵���̂ł����A�Ë����ꂪ�Ҏ[�����܂łɍ��c�ƒ��͂ǂ��Ȃ��Ă���ł��傤�ˁH
��ɏ]���ˎR�Ƃɐ��b�ɂȂ�����A�f���̖��{�q�ƂȂ�i���O���炩�����{�q���͂�����ƕs���j�B���c�����ł͔ˎ咉�V��⍲�B
���͔V���̌o���͎��ۂ̂Ƃ��낱��Ȋ����炵���̂ł����A�Ë����ꂪ�Ҏ[�����܂łɍ��c�ƒ��͂ǂ��Ȃ��Ă���ł��傤�ˁH
480�l�Ԏ����l�N
2022/11/19(�y) 20:38:42.75ID:rRD8bnz+ �M���ƘV�i�̐l�������͉����̏o���������Ă̂́A�i���ł܂��Ĉȍ~���Ƃ��낢�댾��ꂻ���Ȃ�
���ۂ̌����ѕ��݂������l�Ȃ̂ɂ���ȏ������������Ƃ����̂́A���������ĒN�����匾��Ȃ��悤�Ȃ��ƒf�₾�����́H
���ۂ̌����ѕ��݂������l�Ȃ̂ɂ���ȏ������������Ƃ����̂́A���������ĒN�����匾��Ȃ��悤�Ȃ��ƒf�₾�����́H
481�l�Ԏ����l�N
2022/11/19(�y) 23:12:48.94ID:47ZLOosC �ȑO�Љ���u���͓����V�唶�o���ʁv�ɂ��Ă̖{�ɂ���B��w�����́u���͓�����a��o���ʁv�̉ƕ��ɂ�
�u�V����G�\������҂̎q�Ɍ�ԁA�����f�X�Ɏd�A���ɂ��։Ɨ��̎q�̗R��u�\�Η]�薘�O�g�����\�v
�Ƃ���̂ŁA���͔V���̕��̉p�ۏ�v���d���U�߂̎��ɏG�g�R�ɒ�R�������Ƃ��u�Ë�����v�̋L�q�ɊW���Ă���̂ł́A�Ƃ��Ă����B
�܂��g�c�d���֘A�ňȑO�o�Ă����u�g�c�Ɠ`�^�v�ɂ��g�c�m�N�̍Ȃ͏��͓�����̖��Ƃ����̂ŏ��͓�����̏o���ɂ��Ă�������Ă���
����(�p��)��v�͓V���̍��ɉH�ďG�g�ɂ���Ēǂ��o����A�ɗ\���Ŗv�������A�Ɠ��l�̂��Ƃ�������Ă���̂ŏo���ɂ��Ă͐��ԂɍL�܂��ĂȂ������̂�������Ȃ��B
�u�Ë�����v�̕M�҂͂Ƃ肠�����g�c�Ƃƈ��ʂɂ��邩��Ƌg�c���Ƃ������Ƃɂ����̂ł͂Ȃ����ƁB
�u�V����G�\������҂̎q�Ɍ�ԁA�����f�X�Ɏd�A���ɂ��։Ɨ��̎q�̗R��u�\�Η]�薘�O�g�����\�v
�Ƃ���̂ŁA���͔V���̕��̉p�ۏ�v���d���U�߂̎��ɏG�g�R�ɒ�R�������Ƃ��u�Ë�����v�̋L�q�ɊW���Ă���̂ł́A�Ƃ��Ă����B
�܂��g�c�d���֘A�ňȑO�o�Ă����u�g�c�Ɠ`�^�v�ɂ��g�c�m�N�̍Ȃ͏��͓�����̖��Ƃ����̂ŏ��͓�����̏o���ɂ��Ă�������Ă���
����(�p��)��v�͓V���̍��ɉH�ďG�g�ɂ���Ēǂ��o����A�ɗ\���Ŗv�������A�Ɠ��l�̂��Ƃ�������Ă���̂ŏo���ɂ��Ă͐��ԂɍL�܂��ĂȂ������̂�������Ȃ��B
�u�Ë�����v�̕M�҂͂Ƃ肠�����g�c�Ƃƈ��ʂɂ��邩��Ƌg�c���Ƃ������Ƃɂ����̂ł͂Ȃ����ƁB
482�l�Ԏ����l�N
2022/11/21(��) 19:01:01.76ID:kbOd9V3r �u�z�����̍��X�������i�����j�́A�G�g���l����B�ւƌR�����o���Ȃ�A��߂Č������o�����Ƃ��āA
���f��˂����Ƃ��邾�낤�B�ł���̂ŁA���������U�߂�R�����o���ׂ��v�ƌ�c�肵�����ɁA
�I�{��F�E�q��i�����j���\���グ��
�u�������ɂ��Ăł����A�ނ͋��̎ҘZ�l�������A��A�����}�ɗ����ĕl���ɎQ�����Ə����Ă���܂��B
���͍��X�^���q��A�����튨�E�q��A���ؓ����A���̑��v�Z�l�A���̂悤�ɏ����Ă��܂��B
�䕪�ʂ̂��ߐ\���グ�܂��B�v
����ɑ��A�G�g���̌�ӂɂ�
�u�ƍN�������V�ł��鏊�ɖڂ����A�������͂����ɍ���Ƃ����Ŗ������߂ɁA���k�����ׂ���
�v�����̂��낤�B���������X�ƍN���ɐS�u�������悤�Ƃ���ȂǁA����������ċp���āA
�т𐁂����r�����ނƂ������Ɠ������B���������Ȃ���ɕ����o���悤�ȍ����́A�K����肭
�s���Ȃ����낤�B
�ƍN���ɕ\���͂Ȃ��i�ƍN���\���L�ԕ~�Ȃ�j�B��v�ł���ƍN�𓌂̉������ɗ���u�������ł���A
�����̋C�����͖����Ȃ�B�ł���Ήz���ɔn���o�����B�v
�Ƃ̌�c��ł������B
�ƍN���ւ͉z���ɁA�w��n�o��A���������҂Ȃ�x�Ƌ����킵�����A�{���L��ɓs���O��̕��A
���̂����S�C�O�S���ɂĉƍN�����̌�����Ƃ��đf�����㗌�ɋy�B
����ɂ���ď�l�i�G�g�j�͑����A�єN�i�V���\�O�N�j������\�����ɏo�w���ꂽ�B
���̎��̌䕪�ʂɂ́A�u�������Ƃ͂��̊Ԃ܂ŁA������ׂ�T�y�ł������̂�����A��߂Ď��ɑ���
�^�����[�����낤�B�Ⴆ���̏G�g�ɍ~�Q�����Ƃ��Ă��A�����ł��낤�B
�D�c�M�Y�͐M�����̌���q�ł��邩��A�M�Y�����̊��{�ƒ�߂悤�B�������͌����ł��邩��A
�M�Y�ɑ��č~�Q���邾�낤�B�v
���̂悤�Ɏv�������A�R���̘H�n������M�Y�ɑΖʂ������A���g�̌���{�̂悤�Ɏ��舵�����̂́A
���̗l�q���z���ɋ������邽�߂ł������ƕ��������B
�i��p���}�L�j
���f��˂����Ƃ��邾�낤�B�ł���̂ŁA���������U�߂�R�����o���ׂ��v�ƌ�c�肵�����ɁA
�I�{��F�E�q��i�����j���\���グ��
�u�������ɂ��Ăł����A�ނ͋��̎ҘZ�l�������A��A�����}�ɗ����ĕl���ɎQ�����Ə����Ă���܂��B
���͍��X�^���q��A�����튨�E�q��A���ؓ����A���̑��v�Z�l�A���̂悤�ɏ����Ă��܂��B
�䕪�ʂ̂��ߐ\���グ�܂��B�v
����ɑ��A�G�g���̌�ӂɂ�
�u�ƍN�������V�ł��鏊�ɖڂ����A�������͂����ɍ���Ƃ����Ŗ������߂ɁA���k�����ׂ���
�v�����̂��낤�B���������X�ƍN���ɐS�u�������悤�Ƃ���ȂǁA����������ċp���āA
�т𐁂����r�����ނƂ������Ɠ������B���������Ȃ���ɕ����o���悤�ȍ����́A�K����肭
�s���Ȃ����낤�B
�ƍN���ɕ\���͂Ȃ��i�ƍN���\���L�ԕ~�Ȃ�j�B��v�ł���ƍN�𓌂̉������ɗ���u�������ł���A
�����̋C�����͖����Ȃ�B�ł���Ήz���ɔn���o�����B�v
�Ƃ̌�c��ł������B
�ƍN���ւ͉z���ɁA�w��n�o��A���������҂Ȃ�x�Ƌ����킵�����A�{���L��ɓs���O��̕��A
���̂����S�C�O�S���ɂĉƍN�����̌�����Ƃ��đf�����㗌�ɋy�B
����ɂ���ď�l�i�G�g�j�͑����A�єN�i�V���\�O�N�j������\�����ɏo�w���ꂽ�B
���̎��̌䕪�ʂɂ́A�u�������Ƃ͂��̊Ԃ܂ŁA������ׂ�T�y�ł������̂�����A��߂Ď��ɑ���
�^�����[�����낤�B�Ⴆ���̏G�g�ɍ~�Q�����Ƃ��Ă��A�����ł��낤�B
�D�c�M�Y�͐M�����̌���q�ł��邩��A�M�Y�����̊��{�ƒ�߂悤�B�������͌����ł��邩��A
�M�Y�ɑ��č~�Q���邾�낤�B�v
���̂悤�Ɏv�������A�R���̘H�n������M�Y�ɑΖʂ������A���g�̌���{�̂悤�Ɏ��舵�����̂́A
���̗l�q���z���ɋ������邽�߂ł������ƕ��������B
�i��p���}�L�j
483�l�Ԏ����l�N
2022/11/22(��) 08:27:03.82ID:1wYkIu2B �z�O�Ɣ��Z�ł���A�g�Ɏ��s���Ă�̂ɉz���Ɖ��]�Ȃ珮�X
484�l�Ԏ����l�N
2022/11/22(��) 20:54:01.75ID:NkZpqg5g �V���\�l�N�\��\�������ɁA�L�㍑��葁�ł��̔�r�����������B���̓��e�́A
�L�㍑�D��Ƃ����ꏊ�̋ߕӂɂ���A���c��Ƃ����ꏊ������A���̐���u�Ă�
��Ήz�O��i�G�v�j�A���@�䕔���q�i���e�A�M�e�j���w������Ă������A���������
�F���O�����w�����B���Õ��̑叫�́A���Ò����i�Ƌv�j�ƌ������B
�\�\���A�����̍��A��Ήz�O�A���@�䕔���q�͂��̐���č�����d�|�����B
�����A��͖����̗��叫�̏����ƂȂ�A�ܕS�]���������B���������������A
�L�㍑�̒n�̎ҁA�s���Ꝅ���N�����A�F�����ƈ�ɐ����ď�����𒆂Ɏ���Ă߁A
������d�����̂ɁA���@�䕔�̑y�́i�M�e�j���������ɂ����B
�����藼�叫�͔s�R�����ƁA�L�O�ɍ݂������c�����q�̏��ɕ��ꂽ�̂ł���B
�����m���������q�̕��ʂɂ�
�u�L��ł͔s�k�������A���ꂵ���̂��Ƃ͖��Ȃ��i�����̎��͒��X�s���j�B
���̎���閧�ɂ���A�A���Đw���͑������낤�B�����L��̘Ԃɖї��a�w���ɕ���̂��B
��Ήz�O�A���@�䕔���x�̎҂��ܐl�O�l���ʂĂ悤�ƁA��l�i�G�g�j�͎��g�̎�݂Ɛ������Ƃ�
�v��Ȃ��B�i��Ήz�O�A���@�䕔�����Ҍܐl�O�l���ʌ�Ɛ\���A��l���݂Ɣ�v���ԕ~�j
��߂ď�����ɂ����ɖ����āA��B�ւƂ�����ɂȂ邾�낤�B�v
�i��p���}�L�j
��p���}�L�Ɍ�����ˎ���̐킢�Ƃ��̔s��ɂ��Ă̍��c�����q�̔����B
�L�㍑�D��Ƃ����ꏊ�̋ߕӂɂ���A���c��Ƃ����ꏊ������A���̐���u�Ă�
��Ήz�O��i�G�v�j�A���@�䕔���q�i���e�A�M�e�j���w������Ă������A���������
�F���O�����w�����B���Õ��̑叫�́A���Ò����i�Ƌv�j�ƌ������B
�\�\���A�����̍��A��Ήz�O�A���@�䕔���q�͂��̐���č�����d�|�����B
�����A��͖����̗��叫�̏����ƂȂ�A�ܕS�]���������B���������������A
�L�㍑�̒n�̎ҁA�s���Ꝅ���N�����A�F�����ƈ�ɐ����ď�����𒆂Ɏ���Ă߁A
������d�����̂ɁA���@�䕔�̑y�́i�M�e�j���������ɂ����B
�����藼�叫�͔s�R�����ƁA�L�O�ɍ݂������c�����q�̏��ɕ��ꂽ�̂ł���B
�����m���������q�̕��ʂɂ�
�u�L��ł͔s�k�������A���ꂵ���̂��Ƃ͖��Ȃ��i�����̎��͒��X�s���j�B
���̎���閧�ɂ���A�A���Đw���͑������낤�B�����L��̘Ԃɖї��a�w���ɕ���̂��B
��Ήz�O�A���@�䕔���x�̎҂��ܐl�O�l���ʂĂ悤�ƁA��l�i�G�g�j�͎��g�̎�݂Ɛ������Ƃ�
�v��Ȃ��B�i��Ήz�O�A���@�䕔�����Ҍܐl�O�l���ʌ�Ɛ\���A��l���݂Ɣ�v���ԕ~�j
��߂ď�����ɂ����ɖ����āA��B�ւƂ�����ɂȂ邾�낤�B�v
�i��p���}�L�j
��p���}�L�Ɍ�����ˎ���̐킢�Ƃ��̔s��ɂ��Ă̍��c�����q�̔����B
485�l�Ԏ����l�N
2022/11/23(��) 21:44:48.05ID:NGU3s3zC �L�b�G�g�ɂ�鏬�c�������̌�w���ւ́A����ƕ��̕��X���A�א�H�ւ��̂Ȃǂ�
��R�ɑ���ꂽ�B
�R����U�߂ň���i�����j���펀�������A���̎����ꏗ�@�l��著��ꂽ�̂��A���̂̏��߂ł������B
�@���͂�Ȃ�@����̂߂��t�Ɂ@���ւ��œn���ׂ̂��ӂ��
�H�ւ͕ԉ̂�
�@���Ƃ��Ȃ��@�������������ēS�C�́@�ʂɂ��ʂ�������
�����������䋶�̂̕ԉ́A�܂����L�Ȃǂ�咟�i�傫�ț����j�Ɏd���ĂďG�g���̌�ڂɂ��������A��̊O
�䊴�ɂȂ����ƕ��������B
���̓��L�A���̂̑咟�i�����j������������������Ƃ���A��o�ƕ��̌��ɗL�邾�낤�Ƃ̎����B
�i��p���}�L�j
��R�ɑ���ꂽ�B
�R����U�߂ň���i�����j���펀�������A���̎����ꏗ�@�l��著��ꂽ�̂��A���̂̏��߂ł������B
�@���͂�Ȃ�@����̂߂��t�Ɂ@���ւ��œn���ׂ̂��ӂ��
�H�ւ͕ԉ̂�
�@���Ƃ��Ȃ��@�������������ēS�C�́@�ʂɂ��ʂ�������
�����������䋶�̂̕ԉ́A�܂����L�Ȃǂ�咟�i�傫�ț����j�Ɏd���ĂďG�g���̌�ڂɂ��������A��̊O
�䊴�ɂȂ����ƕ��������B
���̓��L�A���̂̑咟�i�����j������������������Ƃ���A��o�ƕ��̌��ɗL�邾�낤�Ƃ̎����B
�i��p���}�L�j
486�l�Ԏ����l�N
2022/11/30(��) 19:50:13.49ID:9cUq6Z2A �Ёi1566�j�̘Z����\�l���ɁA���c�M�Ռ���蓯�N�܌��ܓ��̓��t�ɂāA�M�����֏��g�킳�ꂽ�B
���̓��e�́A
�w����b�q�i1564�j�O���A���������@�a�i�����`�P�j�M�Ղ����\���グ���A�鏊�A
�����l�͍L���܂Ŏ�����������ɂȂ����B���̂��߂��̐M�Ղ́A����n�ɕt���Đ\���グ���B
�u���c�̉Ƃ���������́A�L���܂Ō������䑗�肠��B�䂪�Ƃ̌n�}�����B�v
�������Ȃ���O�D�����Ȃ��̂ɁA�����@�a�̌䖅���ۂƂȂ�䉶��e���A���N���N�i1565�j�A
�`�P�l�����B�i�i�\�̕ρj
���̂悤�Ȏ��������Ă��A���Ƃ������݂��L�����́A�������₦�������͖����B
���̐S���L��ׂ��B�v
���̂悤�ɐ܁X�A�M�����M�Ռ������z���ꂽ�B���̋����܂��܂��M�Ռ����A�䕃�q�̊ԂȂ�A
�M������g���̋`��܁X���ɐ���ƁA���c�̉ƘV�������܂𗬂����B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M�Ղ��猩�����R�`�P��i�\�̕ςɂ���
���̓��e�́A
�w����b�q�i1564�j�O���A���������@�a�i�����`�P�j�M�Ղ����\���グ���A�鏊�A
�����l�͍L���܂Ŏ�����������ɂȂ����B���̂��߂��̐M�Ղ́A����n�ɕt���Đ\���グ���B
�u���c�̉Ƃ���������́A�L���܂Ō������䑗�肠��B�䂪�Ƃ̌n�}�����B�v
�������Ȃ���O�D�����Ȃ��̂ɁA�����@�a�̌䖅���ۂƂȂ�䉶��e���A���N���N�i1565�j�A
�`�P�l�����B�i�i�\�̕ρj
���̂悤�Ȏ��������Ă��A���Ƃ������݂��L�����́A�������₦�������͖����B
���̐S���L��ׂ��B�v
���̂悤�ɐ܁X�A�M�����M�Ռ������z���ꂽ�B���̋����܂��܂��M�Ռ����A�䕃�q�̊ԂȂ�A
�M������g���̋`��܁X���ɐ���ƁA���c�̉ƘV�������܂𗬂����B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M�Ղ��猩�����R�`�P��i�\�̕ςɂ���
487�l�Ԏ����l�N
2022/12/01(��) 03:25:54.83ID:8YHKCnPj488�l�Ԏ����l�N
2022/12/01(��) 08:25:51.64ID:nEsIqGw1 >>486
�ƍN�u���������������������Ĕq�߂�M���V��v
�ƍN�u���������������������Ĕq�߂�M���V��v
489�l�Ԏ����l�N
2022/12/01(��) 10:06:47.47ID:HkgsbAAh ������
490�l�Ԏ����l�N
2022/12/02(��) 19:51:15.04ID:JTYTDe7c ���Y�𖽂��i�w�㐙���M���s�^�x���j
���M�����Ɨ����]���ċ��ɍs�������̂��ƁB
�l���W�܂��Ă����̂ʼn������Ǝv���A�����T��ɂ����~�Í����ɖ₢���������B����Ɓu����͍��n�Ŏ��𓐂S�l�̎҂������Y�ɂȂ낤�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��v�Ɠ������B
���͐Â��������A�u�������ɖ�l�͖@�Ɋ�Â��ď��Y���悤�Ƃ��Ă���B�����������l����Ƃ��낪����̂ŁA�������s��������Ȃ牄���Ă��v�Ɣ~�Â��g�҂Ƃ��ď��Y����U�~�߂������B
���͊قA��ƘV�b�������W�߁A�u��������̂̍ł��傫�ȍЂ��͎��ł���B��������܂Ŏ��͖������Ă����B���ɖ��O�ł���B
�ǂ�������͓��l�Ɋ���ɂ��Ă�肽���B�E�����ɂ��ނ̂Ȃ炱�̏�Ȃ��B���͍˖��������ɈÂ����߁A���f�͂��Ȃ������̍l���ɔC���v
�Ƃ���ƂȂ��͖Ƃ��Ă��Ƃ̈ӂ߂������B
�V�b�����͏n�c���A���ʓI�ɂS�l�̂����P�l�͎��߂ɂ��A�c��R�l�͎����Q�{�����č���Ǖ������Ƃ̂��ƁB
���M�����Ɨ����]���ċ��ɍs�������̂��ƁB
�l���W�܂��Ă����̂ʼn������Ǝv���A�����T��ɂ����~�Í����ɖ₢���������B����Ɓu����͍��n�Ŏ��𓐂S�l�̎҂������Y�ɂȂ낤�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��v�Ɠ������B
���͐Â��������A�u�������ɖ�l�͖@�Ɋ�Â��ď��Y���悤�Ƃ��Ă���B�����������l����Ƃ��낪����̂ŁA�������s��������Ȃ牄���Ă��v�Ɣ~�Â��g�҂Ƃ��ď��Y����U�~�߂������B
���͊قA��ƘV�b�������W�߁A�u��������̂̍ł��傫�ȍЂ��͎��ł���B��������܂Ŏ��͖������Ă����B���ɖ��O�ł���B
�ǂ�������͓��l�Ɋ���ɂ��Ă�肽���B�E�����ɂ��ނ̂Ȃ炱�̏�Ȃ��B���͍˖��������ɈÂ����߁A���f�͂��Ȃ������̍l���ɔC���v
�Ƃ���ƂȂ��͖Ƃ��Ă��Ƃ̈ӂ߂������B
�V�b�����͏n�c���A���ʓI�ɂS�l�̂����P�l�͎��߂ɂ��A�c��R�l�͎����Q�{�����č���Ǖ������Ƃ̂��ƁB
491�l�Ԏ����l�N
2022/12/02(��) 22:25:14.45ID:cjHriNtb �@���˂��Ȃ��Ď��Ȗ�������n���Ȏ�N�ɋ�J�����V�b�̋�S���������
492�l�Ԏ����l�N
2022/12/03(�y) 08:49:55.77ID:giIWnroe ���𓐂҂�������������Ȃ�
493�l�Ԏ����l�N
2022/12/03(�y) 12:34:10.43ID:0ZMCCLVr �ł���̕����܂��ȋC������
494�l�Ԏ����l�N
2022/12/03(�y) 15:02:53.62ID:f13TQAwz ���2�{�Â��Ă��������ė���藎�Ƃ���Ă�?
495�l�Ԏ����l�N
2022/12/05(��) 00:16:57.95ID:c4fe6fH1 >>490
�ɐ��@�����n���l����Ƃ��Ă�锶�ƒʒꂷ����̂�������B
�����I���W�i���������Ċe���e���ɐݒ��ւ��čL�����z���ꂽ��Ȃ����B
�J�k�����̗ނɂ͂悭����p�^�[���B
�@
�ɐ��@�����n���l����Ƃ��Ă�锶�ƒʒꂷ����̂�������B
�����I���W�i���������Ċe���e���ɐݒ��ւ��čL�����z���ꂽ��Ȃ����B
�J�k�����̗ނɂ͂悭����p�^�[���B
�@
496�l�Ԏ����l�N
2022/12/05(��) 03:45:01.85ID:DCaykmVp497�l�Ԏ����l�N
2022/12/05(��) 08:19:09.91ID:RH68z/I1 >>495
�����ăR�s�[����邤���ɃI���W�i���̑厖�ȂƂ��낪�������āA���̘b�݂����ɒP�Ȃ�A�z��N�̘b�ɂ����̂��悭�����
�����ăR�s�[����邤���ɃI���W�i���̑厖�ȂƂ��낪�������āA���̘b�݂����ɒP�Ȃ�A�z��N�̘b�ɂ����̂��悭�����
498�l�Ԏ����l�N
2022/12/06(��) 22:52:48.42ID:bvkRYqkY �u����G�ځv���玳�ˎ��̖ї����ւ̋A��
���˗��Ƃ̐�c�͌��`���Ə��Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ���c�m�Ƃł������B
�����̗��̎��Ɍ������Ђɂ��������߁A�������̎q�Ƃ��ē��A�̂��ɗ����ɑ������B
���̔��㑷�͈��|�ɉ���A���˒��Ƃƍ������B
���ꂩ��܂�����̎q���ł��鎳�ˌ����͍b����(�ܗ���)��̗L���A�ї����A�̌S�R��A��������(���������H)�̒��|��ƓC���𐬂��������ɑ����Ă����B
����Ƃ��ї����A�͍b����ɏo�����Ď��ˌ����ƑΖʂ�
�u�䂪�c��E��]�L���͌������̉Ɛb�ł���A��ӂ̐�c�͗����̌Z��ł���܂��B
����Ȃ̂Ɍ�ӂɑ��Đ������̂͂͂Ȃ͂�����Ƃ����܂��̂ŁA�~�Q�������܂��v
�ƌ����ƌ����͑傢�Ɋ�����
�u��ӂ͉����g�ł��邩��~�Q�Ƃ͂��������Ȃ��B��炪�~���������܂��傤�B
�ǂ������q����(���˗��Ƃ͌����̑�)�𖹂Ƃ��Ď�藧�ĂĂ�������(���A�̖��̌ܗ��ǂ𐳎��ɂ���)�v
���̂Ƃ����玳�ˎ��͔ɉh���A���Ƃ̎O��(�����@)�͖ї��P���̓����ƂȂ�A���ƒ��q�̎��ˌ��G�A���̒��q�̎��ˌ�����������L�����N�ɂĐ��x�����𐬂����B
�����̖����P���̗{�q�Ƃ��A������G�H�ɉł������B
���˗��Ƃ̐�c�͌��`���Ə��Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ���c�m�Ƃł������B
�����̗��̎��Ɍ������Ђɂ��������߁A�������̎q�Ƃ��ē��A�̂��ɗ����ɑ������B
���̔��㑷�͈��|�ɉ���A���˒��Ƃƍ������B
���ꂩ��܂�����̎q���ł��鎳�ˌ����͍b����(�ܗ���)��̗L���A�ї����A�̌S�R��A��������(���������H)�̒��|��ƓC���𐬂��������ɑ����Ă����B
����Ƃ��ї����A�͍b����ɏo�����Ď��ˌ����ƑΖʂ�
�u�䂪�c��E��]�L���͌������̉Ɛb�ł���A��ӂ̐�c�͗����̌Z��ł���܂��B
����Ȃ̂Ɍ�ӂɑ��Đ������̂͂͂Ȃ͂�����Ƃ����܂��̂ŁA�~�Q�������܂��v
�ƌ����ƌ����͑傢�Ɋ�����
�u��ӂ͉����g�ł��邩��~�Q�Ƃ͂��������Ȃ��B��炪�~���������܂��傤�B
�ǂ������q����(���˗��Ƃ͌����̑�)�𖹂Ƃ��Ď�藧�ĂĂ�������(���A�̖��̌ܗ��ǂ𐳎��ɂ���)�v
���̂Ƃ����玳�ˎ��͔ɉh���A���Ƃ̎O��(�����@)�͖ї��P���̓����ƂȂ�A���ƒ��q�̎��ˌ��G�A���̒��q�̎��ˌ�����������L�����N�ɂĐ��x�����𐬂����B
�����̖����P���̗{�q�Ƃ��A������G�H�ɉł������B
499�l�Ԏ����l�N
2022/12/06(��) 23:50:43.00ID:EFubGdPK ���q�D��
500�l�Ԏ����l�N
2022/12/07(��) 11:50:22.25ID:ZltX1f5j �ł��s�H���Ɛ��`���邵���肪�Ȃ��q���J���C�\�X
501�l�Ԏ����l�N
2022/12/07(��) 12:34:53.74ID:14zCj7Y+ �s�H�Ȃ̂͌ܗ��ǂƒ��̈��������A�V����(�g�쌳�t�̍�)
502�l�Ԏ����l�N
2022/12/07(��) 16:01:38.83ID:p+Byk4xj �s�H�͐��i����������F�B���ł��Ȃ�
���O��S�����肠�邾��w
���O��S�����肠�邾��w
503�l�Ԏ����l�N
2022/12/09(��) 16:54:48.68ID:G5Lawqq3 ���N��͂̕��c�M���͏㐙���M�Ȃ̂�
�������i2009�u�V�n�l�v�㐙���M�A2022�u�ǂ�����ƍN�v���c�M���j
�������i2009�u�V�n�l�v�㐙���M�A2022�u�ǂ�����ƍN�v���c�M���j
504�l�Ԏ����l�N
2022/12/09(��) 16:58:22.51ID:5iAusHYr ����Ȃ��Ƃ�������M���͊����q
505�l�Ԏ����l�N
2022/12/09(��) 17:57:02.08ID:uhIMmw+J �L���v���u����G�ځv���珼���M�N�Ɍ��o���ꂽ�x���
�V���Z�N(1578�N)?����A�O�́E���]�ɗx�肪��N�����s�������A����͉���O�Y�a(�����M�N)���D���߂ł������B
��N�A�x�͂ŗx�肪���s�������ɂ͍��쎁�^���ł̂ŕs�g�ł���A�Ə��l�͐\�����B
�O�Y�a�͂����ւ\�ȕ��ŁA����ȗx��肪����|�ŎˎE�����B
���̂��ߗx��͂����Ԃ������Ȃ��̂ƂȂ����B
���̂����l�̗x��q�̂Ȃ��ɁA���ۂ�ł��Ă���\�܂قǂ̗e�����ȓ��������B
�O�Y�a�����̖���q�˂�Ɓu��l���_�̎Аl�E���c���E�q��(���c�d���A����ɂ͉i�c���{�̌Z)�̑��q�ł��v�Ɛ\�����B
���E�q��͗L���ȗE�m�ł��������߁A�����ɂ��̎q�������g�����B
���c�`���Ƃ������ŏo���������A�O�Y�a�̎�(1579�N)�̂̂��͉ƍN���ɏ����o���ꂽ�B
���c���(���`�����E�Q�������c���v)�̖���ł��������߁A�c�����i��Ɖ��߂������B
���v��̐킢�Œr�c����(�r�c�P��)�����Ƃ��������𐬂��������i��E�ߑ�v(�i�䒼��)���̐l�ł���
�V���Z�N(1578�N)?����A�O�́E���]�ɗx�肪��N�����s�������A����͉���O�Y�a(�����M�N)���D���߂ł������B
��N�A�x�͂ŗx�肪���s�������ɂ͍��쎁�^���ł̂ŕs�g�ł���A�Ə��l�͐\�����B
�O�Y�a�͂����ւ\�ȕ��ŁA����ȗx��肪����|�ŎˎE�����B
���̂��ߗx��͂����Ԃ������Ȃ��̂ƂȂ����B
���̂����l�̗x��q�̂Ȃ��ɁA���ۂ�ł��Ă���\�܂قǂ̗e�����ȓ��������B
�O�Y�a�����̖���q�˂�Ɓu��l���_�̎Аl�E���c���E�q��(���c�d���A����ɂ͉i�c���{�̌Z)�̑��q�ł��v�Ɛ\�����B
���E�q��͗L���ȗE�m�ł��������߁A�����ɂ��̎q�������g�����B
���c�`���Ƃ������ŏo���������A�O�Y�a�̎�(1579�N)�̂̂��͉ƍN���ɏ����o���ꂽ�B
���c���(���`�����E�Q�������c���v)�̖���ł��������߁A�c�����i��Ɖ��߂������B
���v��̐킢�Œr�c����(�r�c�P��)�����Ƃ��������𐬂��������i��E�ߑ�v(�i�䒼��)���̐l�ł���
506�l�Ԏ����l�N
2022/12/09(��) 22:13:12.98ID:mCa/kIWL �e�q�Ō��Z�킩
507�l�Ԏ����l�N
2022/12/10(�y) 20:25:42.27ID:LP3IGkV/ >>505
�M�N�̎��̑O�N����Ǝv�������߁A�V���Z�N�Ƃ��܂�����
�u�O�͌㕗�y�L�v����\�Z�@�O�������x���s�E�t�i��`�������̎�
�ł́u�V���l�N���q�Ă̎n�߂��v�ƂȂ��Ă��܂����B
�܂��A�M�N�ɂ��Ă�
�u�M�N�N�͌�N�Ⴍ�җE���C�̑叫�A���̗x����߂ł��܂����Ǝ߂Ȃ炸�B�������x����̂䗗�����B
�����x�q�ǂ��e��(�e���ȕ�)�𒅂��A�x����v�����ɂ��Ȃ��ʂ͍����ɎˎE�����܂��A��X�͋яJ�����d�ˋ��������ߓ������m�����ꂪ���߂ɍ�����₵����B
�S�����Ɛl�ǂ��͐�N���쎁�^�x����D�ݎm���ǂ��ƋƂ��킷��x��ɍ�����₵����قǂ�
�����͕�����������݂����ɏ悶���c�M���x�B��D���Ƃ�A��a�����̎����B���Ό��ɓ��ꂽ�܂�
�O�Ԃ̕�������Č�Ԃ̉���(�Q�܂Ȃ�)�A�u�Ӊ����炸�A��S�����点���܂��ׂ��ɂ�A���|�߂�҂����Ȃ��炸�v
�Ɨx��̏�肢����ƂƂ��ɁA�ߑ��������ǂ������ˎE�̊�ƂȂ��Ă��܂����B
�M�N�̎��̑O�N����Ǝv�������߁A�V���Z�N�Ƃ��܂�����
�u�O�͌㕗�y�L�v����\�Z�@�O�������x���s�E�t�i��`�������̎�
�ł́u�V���l�N���q�Ă̎n�߂��v�ƂȂ��Ă��܂����B
�܂��A�M�N�ɂ��Ă�
�u�M�N�N�͌�N�Ⴍ�җE���C�̑叫�A���̗x����߂ł��܂����Ǝ߂Ȃ炸�B�������x����̂䗗�����B
�����x�q�ǂ��e��(�e���ȕ�)�𒅂��A�x����v�����ɂ��Ȃ��ʂ͍����ɎˎE�����܂��A��X�͋яJ�����d�ˋ��������ߓ������m�����ꂪ���߂ɍ�����₵����B
�S�����Ɛl�ǂ��͐�N���쎁�^�x����D�ݎm���ǂ��ƋƂ��킷��x��ɍ�����₵����قǂ�
�����͕�����������݂����ɏ悶���c�M���x�B��D���Ƃ�A��a�����̎����B���Ό��ɓ��ꂽ�܂�
�O�Ԃ̕�������Č�Ԃ̉���(�Q�܂Ȃ�)�A�u�Ӊ����炸�A��S�����点���܂��ׂ��ɂ�A���|�߂�҂����Ȃ��炸�v
�Ɨx��̏�肢����ƂƂ��ɁA�ߑ��������ǂ������ˎE�̊�ƂȂ��Ă��܂����B
508�l�Ԏ����l�N
2022/12/11(��) 22:31:18.66ID:cJv5e76e �c����N�т̔N�A���}�l�̌��ł��������A���̎l���̍��A�i�ɒB�j���@�a�����O�ɂ����ĉԌ��̗V�R�����ꂽ�������B
���m���̓���������A�ꗼ�����߂����A���̐X�̓��]�̉Ԍ����A�����ɂ������ɁA�V�ю҂Ȃǂ������A��ėV�R�̏��ɁA�����̃X������������o���A���@�ꍀ���Ђ��Ђ��Ǝ�芪����
�u��X�͋Q���Ă���A����������̂ł��B�v�Ɛ\���|�������A
�u�������̋`�ł���B�����������ɂ͋���������Ă��Ă��Ȃ��B�v���̂悤�ɒf�������A
�u�Ȃ�Ό䍘�̕��A�䋟�̏O���̂��̂�������܂��悤�ɁB�v
�Ɛ\���グ���B����ɑ��āu���A�e���͔@���ł��낤���B�v�Ɖ��~�l���g�킵�ċ������A�ނ�Ɏ�点�Ă悤�₭��������ނ����Ƃ��o�����B
�����痢�ƌ������A�ܓ��̂����ɂ��̘b�͋������ɍL�܂�A���Ԃł́u���@�a�������̕��܂ŒD�����ꂽ�A�Ƃ̕���������荹�����ꂽ�B
���̂悤�ȏ��ɁA���̍������[���i�O�c���Ɓj�a�Ɛ��@�Ƃ́A�W�����܂�ǂ��Ȃ������̂����A��[���a�͂��̎��������A�g�Ԃ̖k���Ƃ�����҂ɂ��������܂߂�ꂽ
�u���@�a�̏��֎Q��A�w�ŋߏ��������ɂ́A���̐X�ɂăX���ɂ������ɐ������Ƃ̂��ƁB�Ύ~�i�C�̓Łj�Ɏv���܂��B�x�Ɠ`����悤�ɁB�v
���̎��A��[���a�̑����ɋ������R�ܕ��q�i�G�h�j�͂�����Ƃ��̂悤�ɍl����
�w�ȂĂ̊O�̑厖�Ȃ鎖�����g�킳�����肾�낤���H���̎g���ɑ��A��߂����@�a����́w����Ȃ�g�A�z�Ȃ������܂��B�����āi��X���X���ɑ������Ƃ����j�؋���������܂��悤�ɁB�x
�ƌ����ė��邾�낤�B��������ꂽ�ꍇ�A��X�Ɋm���ȏ؋��͖����B�ƂȂ�ΈɒB�ƂƂ̊W���厖�ɂȂ鎖�͕K��ł���x
���̂悤�ɕ��ʂ��A�w���̂悤�Ȏg���͌䖳�p�ɂČ�x�Ɛ\���ׂ����Ƌ����ɂ͎v���Ă������A��[���a�̕ȂƂ��āA��U���i��x�����o�������Ƃ͔��_���Ȃ��j�Ȃ�l�ł��邩��A
����Ȏ��������ΗP�Ȃđ��X�Ɏg�����o�����˂Ȃ��ƈĂ��A�����Ĕ��������u�g���ɂ͎����Q��܂��傤�B�v�Ɛ\���グ���B
�u�Ȃ�Όܕ��q���Q��悤�Ɂv�Ƌ��ɂȂ���ƁA���̎g���̎����ܕ��q�͗��߂āA��A�O�����߂����B
��[���a���u�ܕ��q�A���@�a�̉������ɂ��Ă͂ǂ��Ȃ����̂��v�Ɛq�˂�ꂽ���A����ɑ��u����͑厖�̌�g�ł���܂��B�ɒB�Ƃ��؋������߂�ꂽ���͂��������ׂ��ł��傤���B�v
�Ɛ\���グ���B�������u�X���ɑ��������͕K��ł���B�ܕ��q���Q��ʂ̂Ȃ瑼�̎҂����킷�v�Ƌ��ɂȂ����B�����Łu�Ȃ�Ύ����Q��܂��B�v�Ƃ̎��ɐ������B
���R�ܕ��q�͐��@�a�̌��ɎQ��A��[���a�̌������ʂ�ɐ\���n���ƁA�Ă̒�A���@�a�͎��g�ŏo�Ă��ď��@�ɂ����đΖʂ��A���̕Ԏ��ɂ�
�u���̂悤�Ȏ���\��������͂����܂����B��킭���̏؋����o���A��X�ɉ�����܂��悤�ɁB�v
�Ƃ̎��ł������B�ܕ��q�͈��A�d��A�u���̎��́A��ɐ\���グ���悤�ɐ��Ԃ�������荹�����Ă��鎖�ł��B
��[���ɑ��A�؋����o���悤�ɂƂ̌�Ԏ��ł���܂����A���̂悤�Ό�Ԏ��ł́A���͔��A�邱�Ƃ��o���܂���B�g�����s���@�ł������A�Ƃ������ɐ��邩��ł��B�ł���ȏ�A���O�ł͂���܂����A
�䞻�������\���܂��B�i�����Őؕ�����Ƃ������Ɓj
�ܕ��q�̊o�傪�����������̂��A���@�a�͂Ƃ����ɂ��̋C�F�����A
�u�����������ł���̂Ȃ�A���Ԃ̎�荹��������̂��낤���A�����u�����B����͐��Ԃ̈����ł�����̂��낤���A��S�����v���Ē��������B���̂悤�Ȏ��͌��Ɋo���������B
����A�z�Ȃ���������v
�ƁA���ɕԎ������ꂽ�B���R�ܕ��q�͕��ʂ��A���̕Ԏ����Ă��؋��������ƍl���A�u���b���A�\���グ������������܂��B�v�ƌ����Ă��̍��𗧂��A���@�a�̉��~�ɋ߂��A
�������V�a�A�y�������q�֎g���𗧂āw����֑��X��o������܂��悤�ɁA�}�p�̂��ƌ����x�Ɛ\�����킵�����A���̗��l���Q��u���̂悤�Ȏg���̂��߁A��[���̏����Q��܂����B�v��
�������A���̗��l���ɗ��āA�Ăѐ��@�a�Ɉ����A
�u�őO�̌�Ԏ��͂��̂悤�ł������A���̌�Ɍ䌾�t���L��A��̗��Ƃ̐\�����ɐ����Ă��܂��܂��B�؋��̂��߂ɁA���̗��l����O�ɍ݂��āA��Ԏ��̓��e������܂��B�v
�Ɛ\���グ���B
���̌�Ɏ�荹�����ꂽ���Ƃɂ́A���̓��R�ܕ��q�̕��ʂ̂��߂ɁA���@�a�Ƒ�[���a�Ƃ̊Ԃɕ��������N����Ȃ������B����͕ɐb���̓��R�̂������ł���ƁA���̘b���҂�����
�ܕ��q�Ɋ����������ƕ������Ă���B
�i��p���}�L�j
���m���̓���������A�ꗼ�����߂����A���̐X�̓��]�̉Ԍ����A�����ɂ������ɁA�V�ю҂Ȃǂ������A��ėV�R�̏��ɁA�����̃X������������o���A���@�ꍀ���Ђ��Ђ��Ǝ�芪����
�u��X�͋Q���Ă���A����������̂ł��B�v�Ɛ\���|�������A
�u�������̋`�ł���B�����������ɂ͋���������Ă��Ă��Ȃ��B�v���̂悤�ɒf�������A
�u�Ȃ�Ό䍘�̕��A�䋟�̏O���̂��̂�������܂��悤�ɁB�v
�Ɛ\���グ���B����ɑ��āu���A�e���͔@���ł��낤���B�v�Ɖ��~�l���g�킵�ċ������A�ނ�Ɏ�点�Ă悤�₭��������ނ����Ƃ��o�����B
�����痢�ƌ������A�ܓ��̂����ɂ��̘b�͋������ɍL�܂�A���Ԃł́u���@�a�������̕��܂ŒD�����ꂽ�A�Ƃ̕���������荹�����ꂽ�B
���̂悤�ȏ��ɁA���̍������[���i�O�c���Ɓj�a�Ɛ��@�Ƃ́A�W�����܂�ǂ��Ȃ������̂����A��[���a�͂��̎��������A�g�Ԃ̖k���Ƃ�����҂ɂ��������܂߂�ꂽ
�u���@�a�̏��֎Q��A�w�ŋߏ��������ɂ́A���̐X�ɂăX���ɂ������ɐ������Ƃ̂��ƁB�Ύ~�i�C�̓Łj�Ɏv���܂��B�x�Ɠ`����悤�ɁB�v
���̎��A��[���a�̑����ɋ������R�ܕ��q�i�G�h�j�͂�����Ƃ��̂悤�ɍl����
�w�ȂĂ̊O�̑厖�Ȃ鎖�����g�킳�����肾�낤���H���̎g���ɑ��A��߂����@�a����́w����Ȃ�g�A�z�Ȃ������܂��B�����āi��X���X���ɑ������Ƃ����j�؋���������܂��悤�ɁB�x
�ƌ����ė��邾�낤�B��������ꂽ�ꍇ�A��X�Ɋm���ȏ؋��͖����B�ƂȂ�ΈɒB�ƂƂ̊W���厖�ɂȂ鎖�͕K��ł���x
���̂悤�ɕ��ʂ��A�w���̂悤�Ȏg���͌䖳�p�ɂČ�x�Ɛ\���ׂ����Ƌ����ɂ͎v���Ă������A��[���a�̕ȂƂ��āA��U���i��x�����o�������Ƃ͔��_���Ȃ��j�Ȃ�l�ł��邩��A
����Ȏ��������ΗP�Ȃđ��X�Ɏg�����o�����˂Ȃ��ƈĂ��A�����Ĕ��������u�g���ɂ͎����Q��܂��傤�B�v�Ɛ\���グ���B
�u�Ȃ�Όܕ��q���Q��悤�Ɂv�Ƌ��ɂȂ���ƁA���̎g���̎����ܕ��q�͗��߂āA��A�O�����߂����B
��[���a���u�ܕ��q�A���@�a�̉������ɂ��Ă͂ǂ��Ȃ����̂��v�Ɛq�˂�ꂽ���A����ɑ��u����͑厖�̌�g�ł���܂��B�ɒB�Ƃ��؋������߂�ꂽ���͂��������ׂ��ł��傤���B�v
�Ɛ\���グ���B�������u�X���ɑ��������͕K��ł���B�ܕ��q���Q��ʂ̂Ȃ瑼�̎҂����킷�v�Ƌ��ɂȂ����B�����Łu�Ȃ�Ύ����Q��܂��B�v�Ƃ̎��ɐ������B
���R�ܕ��q�͐��@�a�̌��ɎQ��A��[���a�̌������ʂ�ɐ\���n���ƁA�Ă̒�A���@�a�͎��g�ŏo�Ă��ď��@�ɂ����đΖʂ��A���̕Ԏ��ɂ�
�u���̂悤�Ȏ���\��������͂����܂����B��킭���̏؋����o���A��X�ɉ�����܂��悤�ɁB�v
�Ƃ̎��ł������B�ܕ��q�͈��A�d��A�u���̎��́A��ɐ\���グ���悤�ɐ��Ԃ�������荹�����Ă��鎖�ł��B
��[���ɑ��A�؋����o���悤�ɂƂ̌�Ԏ��ł���܂����A���̂悤�Ό�Ԏ��ł́A���͔��A�邱�Ƃ��o���܂���B�g�����s���@�ł������A�Ƃ������ɐ��邩��ł��B�ł���ȏ�A���O�ł͂���܂����A
�䞻�������\���܂��B�i�����Őؕ�����Ƃ������Ɓj
�ܕ��q�̊o�傪�����������̂��A���@�a�͂Ƃ����ɂ��̋C�F�����A
�u�����������ł���̂Ȃ�A���Ԃ̎�荹��������̂��낤���A�����u�����B����͐��Ԃ̈����ł�����̂��낤���A��S�����v���Ē��������B���̂悤�Ȏ��͌��Ɋo���������B
����A�z�Ȃ���������v
�ƁA���ɕԎ������ꂽ�B���R�ܕ��q�͕��ʂ��A���̕Ԏ����Ă��؋��������ƍl���A�u���b���A�\���グ������������܂��B�v�ƌ����Ă��̍��𗧂��A���@�a�̉��~�ɋ߂��A
�������V�a�A�y�������q�֎g���𗧂āw����֑��X��o������܂��悤�ɁA�}�p�̂��ƌ����x�Ɛ\�����킵�����A���̗��l���Q��u���̂悤�Ȏg���̂��߁A��[���̏����Q��܂����B�v��
�������A���̗��l���ɗ��āA�Ăѐ��@�a�Ɉ����A
�u�őO�̌�Ԏ��͂��̂悤�ł������A���̌�Ɍ䌾�t���L��A��̗��Ƃ̐\�����ɐ����Ă��܂��܂��B�؋��̂��߂ɁA���̗��l����O�ɍ݂��āA��Ԏ��̓��e������܂��B�v
�Ɛ\���グ���B
���̌�Ɏ�荹�����ꂽ���Ƃɂ́A���̓��R�ܕ��q�̕��ʂ̂��߂ɁA���@�a�Ƒ�[���a�Ƃ̊Ԃɕ��������N����Ȃ������B����͕ɐb���̓��R�̂������ł���ƁA���̘b���҂�����
�ܕ��q�Ɋ����������ƕ������Ă���B
�i��p���}�L�j
509�l�Ԏ����l�N
2022/12/12(��) 14:01:29.35ID:r1ZE6v21 �����R������
510�l�Ԏ����l�N
2022/12/12(��) 17:23:24.85ID:AEhmbMhj �ܕ��q����̂����b�ł���
���Ƃ̈����b�ł�����
���Ƃ̈����b�ł�����
511�l�Ԏ����l�N
2022/12/12(��) 18:46:55.40ID:GZ/44Pjx >>509
�܂���Ă��
�܂���Ă��
512�l�Ԏ����l�N
2022/12/13(��) 20:40:53.15ID:d5lZzaHf �i�\��N�i1566�j�����A�z���̏㐙�P�Ղ͏�썑�a�c��֎��l�߁A���ɗ���ƌ����鏊�ɁA
���c�M�����̊��{�ŁA���y�叫�̉��c�\�Y���q�i�N�i�j�����̉������Ă����Ă���A�ނ�
�����̓��S�A���y�ɂ��Ă͌����ɋy���A�a�c�̎ҋ����\�Y���q���ǂ����m�����B
�P�Ղ͈ꖜ�O��̐l�����ȂčU�߂����A��͗����Ȃ������B����͐悸��ؖڂƂ��āA��̎������������A
��z�肪�ǂ�������������B�����ď\�Y���q�͘E�֏オ��A�����K�������S�C���ȂāA�P�Ղ̊��{������
�Ă��鏊������߁A�ǂ����҂𑽂��������Ƃ����B
���̒��ŋP�Ղ̌���𐬂����������E���A����ɏ\�Y���q�̌��S�C�Ɋ���ċP�Վ��g���낤���������B
����̂ɋP�Ղ͑��X�ɕ�͂������āA�z�㐨�͑ގU�����B
�a�c�邪���łɎ�����߂邱�Ƃ��o�����̂́A���c�\�Y���q���卄���ŁA�������|��ɔ\�����҂̌̂ł������B
���̉��c�\�Y���q�͎l�\������A�\�Z��葖����A��\���N�̊Ԃɐ��x�̕��ӂ��d��A�D��Ď���ӂ���
���������������߂ɁA�a�c���C���ꂽ�B����ɂ��Đl�X�͖J�ߏ̂������A���c���M�͂��قǎ蕿�Ƃ�
�l���Ă��Ȃ������B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M�����̊��{�ŁA���y�叫�̉��c�\�Y���q�i�N�i�j�����̉������Ă����Ă���A�ނ�
�����̓��S�A���y�ɂ��Ă͌����ɋy���A�a�c�̎ҋ����\�Y���q���ǂ����m�����B
�P�Ղ͈ꖜ�O��̐l�����ȂčU�߂����A��͗����Ȃ������B����͐悸��ؖڂƂ��āA��̎������������A
��z�肪�ǂ�������������B�����ď\�Y���q�͘E�֏オ��A�����K�������S�C���ȂāA�P�Ղ̊��{������
�Ă��鏊������߁A�ǂ����҂𑽂��������Ƃ����B
���̒��ŋP�Ղ̌���𐬂����������E���A����ɏ\�Y���q�̌��S�C�Ɋ���ċP�Վ��g���낤���������B
����̂ɋP�Ղ͑��X�ɕ�͂������āA�z�㐨�͑ގU�����B
�a�c�邪���łɎ�����߂邱�Ƃ��o�����̂́A���c�\�Y���q���卄���ŁA�������|��ɔ\�����҂̌̂ł������B
���̉��c�\�Y���q�͎l�\������A�\�Z��葖����A��\���N�̊Ԃɐ��x�̕��ӂ��d��A�D��Ď���ӂ���
���������������߂ɁA�a�c���C���ꂽ�B����ɂ��Đl�X�͖J�ߏ̂������A���c���M�͂��قǎ蕿�Ƃ�
�l���Ă��Ȃ������B
�w�b�z�R�Ӂx
513�l�Ԏ����l�N
2022/12/14(��) 02:31:04.59ID:N5ONe28H 1566�N�̎��_�ōb��ɂ���ȓS�C�̖��肪�����̂��[
514�l�Ԏ����l�N
2022/12/14(��) 11:31:32.61ID:gpimPw/N �R��
515�l�Ԏ����l�N
2022/12/15(��) 22:49:24.71ID:wmHpMfPX ����͗v��ʋ`�ɂČ����ւǂ��A���̂���܂��������t���Ă����B
�փ����̎��A���喼�O�̒��ł��A���ʂ��ȂĂ��̉Ƃ��������������l���Ƃ��ẮA
�瓇�����i���j�Ɛ\���A���̓瓇�a�i���j�̐e�����L��B���̓����܂ł͒B�҂ŋ���ꂽ�B
�����͌䏊�l�i����ƍN�j������n���o���ꂽ�����ƁA
�u�����炭���̐ՂŌ�d������Ă�O���o�Ă��邾�낤�B�䏊�l�ւ̌�y���Ƃ��āA
���喼�O�͂��炩�����̌䋟�ɎQ��ƕ����Ă���B
�䂪�Ƃ͓��ւ̌䋟���d��Ȃ����A��������Ȃ����߂̕��ʂ��L��B
��q�ܕS�іڂ𓌂ւƎ����ĉ���A����������䏊�l�䕪���͐\���ɋy���A�㐙�i���Ƃ̋��ڂ܂ł�
���X�̒����ɂāA�܊і���ÂA�������������ɕ��Ƃ����߂ɁA���̒��X�̔N�ɗa�������ׂ��B
����Ɏ����N�����Ƃ̏��������A�䏊�l�\���グ����e�Ƃ��Ă�
�w�瓇�͌䏊�l�ւ̌�y��������o��ł��������ɁA������I�N�������߁A���͂�瓇���������
�o�邱�Ƃ͔��ɍ���ɂȂ�܂����B�ł��̂ł��̕��Ƃ͉�X�ɂ͕K�p���Ȃ��Ȃ�܂����B�x
�����]���āA���X�ɂ����ĕ��Ƃ������グ���悤�ɁB�v
���̂悤�ɐ\���t���A��s�O�l�𓌂֍����������B
�䏊�l���͂�F�s�{�ɓ��������̂Ɠ������A��������i�Γc�O���j�̖d���̏�������B
���̓瓇�̎ҋ��͌䏊�l�ɐ�̌�f��\���グ�A�������F�s�{�ɂ����ĕ��Ƃ������グ���B
�����ĉ��B���ڂ܂ł̕���Ă��u���Ă�������ژ^�ɂ��āA��������̕��ƕĂ�i�サ���Ƃ����B
���̎��䏊�l�̌䕪�ʂɂ��u���Ă͓瓇�A�S���͕ʏ��v�Ǝv���������ƕ������Ă���B
�瓇�̉��ӂ́A���ۂɂ͏��f���Ă����̂��ƌ����Ă��邪�A�e�̉����̕��ʂ��Ȃ�
�i���ՂŁj�����痣��鎖�����������̂��ƁA���Ԃł͂��̍����\���Ă����Ƃ����B
�i��p���}�L�j
�փ����̎��A���喼�O�̒��ł��A���ʂ��ȂĂ��̉Ƃ��������������l���Ƃ��ẮA
�瓇�����i���j�Ɛ\���A���̓瓇�a�i���j�̐e�����L��B���̓����܂ł͒B�҂ŋ���ꂽ�B
�����͌䏊�l�i����ƍN�j������n���o���ꂽ�����ƁA
�u�����炭���̐ՂŌ�d������Ă�O���o�Ă��邾�낤�B�䏊�l�ւ̌�y���Ƃ��āA
���喼�O�͂��炩�����̌䋟�ɎQ��ƕ����Ă���B
�䂪�Ƃ͓��ւ̌䋟���d��Ȃ����A��������Ȃ����߂̕��ʂ��L��B
��q�ܕS�іڂ𓌂ւƎ����ĉ���A����������䏊�l�䕪���͐\���ɋy���A�㐙�i���Ƃ̋��ڂ܂ł�
���X�̒����ɂāA�܊і���ÂA�������������ɕ��Ƃ����߂ɁA���̒��X�̔N�ɗa�������ׂ��B
����Ɏ����N�����Ƃ̏��������A�䏊�l�\���グ����e�Ƃ��Ă�
�w�瓇�͌䏊�l�ւ̌�y��������o��ł��������ɁA������I�N�������߁A���͂�瓇���������
�o�邱�Ƃ͔��ɍ���ɂȂ�܂����B�ł��̂ł��̕��Ƃ͉�X�ɂ͕K�p���Ȃ��Ȃ�܂����B�x
�����]���āA���X�ɂ����ĕ��Ƃ������グ���悤�ɁB�v
���̂悤�ɐ\���t���A��s�O�l�𓌂֍����������B
�䏊�l���͂�F�s�{�ɓ��������̂Ɠ������A��������i�Γc�O���j�̖d���̏�������B
���̓瓇�̎ҋ��͌䏊�l�ɐ�̌�f��\���グ�A�������F�s�{�ɂ����ĕ��Ƃ������グ���B
�����ĉ��B���ڂ܂ł̕���Ă��u���Ă�������ژ^�ɂ��āA��������̕��ƕĂ�i�サ���Ƃ����B
���̎��䏊�l�̌䕪�ʂɂ��u���Ă͓瓇�A�S���͕ʏ��v�Ǝv���������ƕ������Ă���B
�瓇�̉��ӂ́A���ۂɂ͏��f���Ă����̂��ƌ����Ă��邪�A�e�̉����̕��ʂ��Ȃ�
�i���ՂŁj�����痣��鎖�����������̂��ƁA���Ԃł͂��̍����\���Ă����Ƃ����B
�i��p���}�L�j
516�l�Ԏ����l�N
2022/12/26(��) 17:37:30.57ID:hS9JgHQL >>515�̑���
���Ƃ̏d�b�ł���锌�ˎ�i�������j�͓��X�̕��ʂɁA
�u�V�����A���̐D�c�O�Y�M������x�͎��Ƃ����ٌ�������B�܂��ނɂ͖����L��Ƃ����B
���O��i��䒷���j�ɂ͓��V�������A���X��艏�g�ɂ��Đ\���ė��Ă��邪�A�ǂ��ɂ����ʂ��Ē����A
�M���a�̌�Z��ɒv�������Ǝv���Ă���̂����A�M���ւ̒ʘH���G�ɍǂ���Ă���A���ʂ����藧���Ȃ��B
�Ƃ���Ŏ��̔ς��������ւ����������̂͊m���ł���B�����ō��X�֎g�҂𗧂āA������Ă݂悤�B�v
�����l���A���X�̏�X�֓�����Ă��̂悤�ɐ\����
�u���͓��t�A�s���ɔς��������肩�ł͂Ȃ��ł������A���e�������߂��݁A�_�X�֖�������Ă��ꂽ�ׂ��A
�s���ɏ����邱�Ƃ��o���܂����B���̎��e�́A���͈ɓ������O���̖��_�A�x�m�̌�R�֗���������܂����B
�����Đ_�������̂悤�ɐ��������߁A�����܂ł̓��̌���ʍs���邱�Ƃ���͖Ƃ��Ē��������̂ł��B
���͍��N�̘Z����S���A�����ւ̎ЎQ�𐋂������̂ł��B�v
���̂悤�Ɏg�҂𗧂ĂĐ\���o�����A���c���܂ł̊Ԃ̏��͐s������ɓ��ӂ�
�u��ς��̗l�q�͏����Ă���܂��B���Ă͐_�X�ւ̖���ł��傤���B�_���ɑ��d��ʉ߂������܂��傤�B�v�ƁA
���c������]�B�܂ł̓��̌��𐿂������ł����B
����ƂāA���̉Ăɔ��ˎ�͔��X�����l�q�ɂĎЎQ�Ə̂��ē����ւƉ������B���X�̏邩��͎c�鏊�����y�����ꂽ�B
���{�܂œ����������A�����ɂ����āu跗��i���˕a�A�M�a�j�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�M�����Ɍ��҂𗊂݂���
�����܂��v�Ɛ\���グ���B����Ɓu�䓹���ł���A�������ł���B�����Ɏb���������ė{�������悤�ɁB�v��
��y�����c�鏊�������t�����B�܁A�O���̊ԁA�{���Ƃ��Đ��������B
���̖�A���ˎ�͍��v�ԉE�q��i�M���j�a���ɂ킩�ɌĂъ��B
�u�k���������e�ׂ�����܂��B���������Ɋ��ƁA�M�����ɂ͌䖅�������邻���ł��B
�䂪�����O���������V������܂���B�����ŁA�䖅��\�����������̂ł��B�v
���̂悤�ɉE�q��a�\���n���A����͐M�����̌䎨�ɓ��������A�M���������
�u���Ƃ̊Ԃɂ͓G�������B���𑗂铹���ǂ̂悤�Ɏd��ׂ����B���̕��ʂ����m���ɗL��̂Ȃ�
�������킻���B�����������Ȃ̂Œ��k�������B�v�Ƃ̌�Ԏ��ł������B
�Ȃ�ƂāA���ˎ�͂����Ɍ�Ζʂ��\���グ��
�u���̎��ɂ��Ă̎e�ׂł����A����A���͂��̂��ƁA���ւƒʉ߂��܂��B�k��a�A�`���A���̑��ւ��̂悤�ɐ\���܂��B
�w���̌���ʉ߂����͖Ƃ����������ŁA���ɎЎQ���o���܂����B���̏�A�܂���l�ь���\���グ������
�ł����A���x�͏������������A��A�v�w���ɎЎQ�d��ׂ��Ƃ̗���𐬂������A���N�͕v�w�Ƃ��ɂ������
���肽���̂ł��B�x
���̂悤�ɓ��̑喼�O�Ɍ�l�ь���\���グ�܂��B�v�w�A�˂ĂƂ������ł���A�Ȃ��Ȃĕʏ�͖����ƁA
���̌��ʉ߂�Ə����Ă���������ł��傤�B���̓��ӂ��Ƃ������ł̋A��ɁA�܂���k���������܂��傤�B�v
�����A���ˎ�͓��ւƌ������A�l�����̋{�X�ւ̎ЎQ�𐋂��A�k��a�A�`���Ȃǂ�̌���\���グ�A
�u���N�͕v�w�A�˂Ēʍs���邱�Ƃ����������������B�v�ƒf��\�������A�Ă̒�u�������ł���B
�_���ɑ��d���́A��S�������N�A�v�w�����Č�ЎQ�����悤�ɁB�v�Ƃ̖������d�����B
�����Đ��{�ɖ߂�ƁA�Ă�跗��C�ƂȂ����Ɛ\���o���B���̏��
�u�����ł͂��̂悤�ɁA���N�Ȃ����������A�ꉺ�邱�Ƃɂ��Ă�������Ɛ\���ɂ߂܂����B
���������̍Ȃ������A��͂��܂���B��蕨�����A�����͂����҂Ɏ���܂ŁA�O�\�l�A�܋R�������A��A
�����v�w�����ĂƏ̂��ĉ���܂��B�����Ă��̏��������ւ��āA�䖅��\�������ɔ��オ��܂��B
����ł���A���������͂���܂���B�v
�M���͂�����͂��A�u�Ȃ�Ζ�����ڂɂ����悤�B�v�ƁA���ˎ��l�������A��ĉ��֓���A���ˎ�͌䖅�̎p����������B
�u�ڏo�x�����N�̌�j���A�������܂����v
�������k�d��A�A�������Ƃ����B
�i��p���}�L�j
���Ƃ̏d�b�ł���锌�ˎ�i�������j�͓��X�̕��ʂɁA
�u�V�����A���̐D�c�O�Y�M������x�͎��Ƃ����ٌ�������B�܂��ނɂ͖����L��Ƃ����B
���O��i��䒷���j�ɂ͓��V�������A���X��艏�g�ɂ��Đ\���ė��Ă��邪�A�ǂ��ɂ����ʂ��Ē����A
�M���a�̌�Z��ɒv�������Ǝv���Ă���̂����A�M���ւ̒ʘH���G�ɍǂ���Ă���A���ʂ����藧���Ȃ��B
�Ƃ���Ŏ��̔ς��������ւ����������̂͊m���ł���B�����ō��X�֎g�҂𗧂āA������Ă݂悤�B�v
�����l���A���X�̏�X�֓�����Ă��̂悤�ɐ\����
�u���͓��t�A�s���ɔς��������肩�ł͂Ȃ��ł������A���e�������߂��݁A�_�X�֖�������Ă��ꂽ�ׂ��A
�s���ɏ����邱�Ƃ��o���܂����B���̎��e�́A���͈ɓ������O���̖��_�A�x�m�̌�R�֗���������܂����B
�����Đ_�������̂悤�ɐ��������߁A�����܂ł̓��̌���ʍs���邱�Ƃ���͖Ƃ��Ē��������̂ł��B
���͍��N�̘Z����S���A�����ւ̎ЎQ�𐋂������̂ł��B�v
���̂悤�Ɏg�҂𗧂ĂĐ\���o�����A���c���܂ł̊Ԃ̏��͐s������ɓ��ӂ�
�u��ς��̗l�q�͏����Ă���܂��B���Ă͐_�X�ւ̖���ł��傤���B�_���ɑ��d��ʉ߂������܂��傤�B�v�ƁA
���c������]�B�܂ł̓��̌��𐿂������ł����B
����ƂāA���̉Ăɔ��ˎ�͔��X�����l�q�ɂĎЎQ�Ə̂��ē����ւƉ������B���X�̏邩��͎c�鏊�����y�����ꂽ�B
���{�܂œ����������A�����ɂ����āu跗��i���˕a�A�M�a�j�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�M�����Ɍ��҂𗊂݂���
�����܂��v�Ɛ\���グ���B����Ɓu�䓹���ł���A�������ł���B�����Ɏb���������ė{�������悤�ɁB�v��
��y�����c�鏊�������t�����B�܁A�O���̊ԁA�{���Ƃ��Đ��������B
���̖�A���ˎ�͍��v�ԉE�q��i�M���j�a���ɂ킩�ɌĂъ��B
�u�k���������e�ׂ�����܂��B���������Ɋ��ƁA�M�����ɂ͌䖅�������邻���ł��B
�䂪�����O���������V������܂���B�����ŁA�䖅��\�����������̂ł��B�v
���̂悤�ɉE�q��a�\���n���A����͐M�����̌䎨�ɓ��������A�M���������
�u���Ƃ̊Ԃɂ͓G�������B���𑗂铹���ǂ̂悤�Ɏd��ׂ����B���̕��ʂ����m���ɗL��̂Ȃ�
�������킻���B�����������Ȃ̂Œ��k�������B�v�Ƃ̌�Ԏ��ł������B
�Ȃ�ƂāA���ˎ�͂����Ɍ�Ζʂ��\���グ��
�u���̎��ɂ��Ă̎e�ׂł����A����A���͂��̂��ƁA���ւƒʉ߂��܂��B�k��a�A�`���A���̑��ւ��̂悤�ɐ\���܂��B
�w���̌���ʉ߂����͖Ƃ����������ŁA���ɎЎQ���o���܂����B���̏�A�܂���l�ь���\���グ������
�ł����A���x�͏������������A��A�v�w���ɎЎQ�d��ׂ��Ƃ̗���𐬂������A���N�͕v�w�Ƃ��ɂ������
���肽���̂ł��B�x
���̂悤�ɓ��̑喼�O�Ɍ�l�ь���\���グ�܂��B�v�w�A�˂ĂƂ������ł���A�Ȃ��Ȃĕʏ�͖����ƁA
���̌��ʉ߂�Ə����Ă���������ł��傤�B���̓��ӂ��Ƃ������ł̋A��ɁA�܂���k���������܂��傤�B�v
�����A���ˎ�͓��ւƌ������A�l�����̋{�X�ւ̎ЎQ�𐋂��A�k��a�A�`���Ȃǂ�̌���\���グ�A
�u���N�͕v�w�A�˂Ēʍs���邱�Ƃ����������������B�v�ƒf��\�������A�Ă̒�u�������ł���B
�_���ɑ��d���́A��S�������N�A�v�w�����Č�ЎQ�����悤�ɁB�v�Ƃ̖������d�����B
�����Đ��{�ɖ߂�ƁA�Ă�跗��C�ƂȂ����Ɛ\���o���B���̏��
�u�����ł͂��̂悤�ɁA���N�Ȃ����������A�ꉺ�邱�Ƃɂ��Ă�������Ɛ\���ɂ߂܂����B
���������̍Ȃ������A��͂��܂���B��蕨�����A�����͂����҂Ɏ���܂ŁA�O�\�l�A�܋R�������A��A
�����v�w�����ĂƏ̂��ĉ���܂��B�����Ă��̏��������ւ��āA�䖅��\�������ɔ��オ��܂��B
����ł���A���������͂���܂���B�v
�M���͂�����͂��A�u�Ȃ�Ζ�����ڂɂ����悤�B�v�ƁA���ˎ��l�������A��ĉ��֓���A���ˎ�͌䖅�̎p����������B
�u�ڏo�x�����N�̌�j���A�������܂����v
�������k�d��A�A�������Ƃ����B
�i��p���}�L�j
517�l�Ԏ����l�N
2022/12/26(��) 19:14:46.92ID:hS9JgHQL >>516
�����܂���ԈႦ�܂����B�����b�X����665 �̑����ł��B�\����܂���
�����܂���ԈႦ�܂����B�����b�X����665 �̑����ł��B�\����܂���
518�l�Ԏ����l�N
2022/12/27(��) 23:01:39.62ID:xZUKIk8a �㐙���M���֓��U�߂��s���A������D�҂������̂��ƁB
���M�͎R���㐙�Ƃ̉Ɛb�����Ɏg�҂𑗂�A�����`���������B
�u�R�����i�㐙�����j�͎����q�Ƃ��A�֓��Ǘ̐E������ꂽ�B����ɂ���Ď������̂��߂ɕ��������Ԃ����B���Ȃ��������R�����Ɏd���Ă����̂�����A���̂܂��Ɏd���Ȃ����v
����Ɛ��͏��Ȃ��猾�����B
�u�z����i���M�j�̌��J�͍ł������B���������ɕ����Ă��j���\���グ�悤�B�����A�Ɛb�ɂȂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v
�g�҂����̓��e��`����ƌ��M�͓{��A�����Ȃ��čU�߂悤�Ƃ����B
����ƁA���łɌ��M�ɍ~���Ă��ɂ������c�����������������B
�u�Ɛ��͊�łȘV���ŁA��ɂ��̂悤�Ȋ����ł��B�������A�S�͑P�ǂł킴�킴���ނׂ��҂ł��Ȃ��ł��B�����K��������Ɉ��A�ɗ���ł��傤�B�������Ȃ���Ύ����U�߂����W���܂��v
���̓��A�Ɛ����������������Ƃ����Ƃ���A�V�b�����͂�����|�߂��B
�Ɛ��́u���ʂ̂ł���Ό��M�����A�ꂾ�B�J�����Ƃ͂Ȃ����v�ƌ����A���̂܂ܕ����֕����A���M�ɉy�������B
���M�́u���Ȃ���������̎g�҂Ɍ������ĉƐb�ɂȂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ������͖̂{�����v�ƕ������B
����ƋƐ��͂����������B
�u���̒ʂ�ł��B�����q�ɉƓ�����ۂ́A�܂��V�b�Ɏ���A���̌�ɓV�q���邢�͏��R�ɍ����Ă��̋�������̂ł��B�܂��Ă�Ǘ̐E�̂悤�Ȃ��͎̂������R���C������̂ł���A�������ɏ�����̂ł��Ȃ��A�q���������邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A�R���ƍċ��̂��߂Ƃ���Ύ��͂��Ȃ��̎w���ɏ]���A��N�߂܂��傤�v
����������M�͏��Ȃ��猾�����B
�u�����̌����Ƃ���A���Ȃ��͌�蛂̊�v�i�킩�炸��ł������ȂȒj�j�ł���ȁv
���̌�͉���ƂȂ�A����I�������ɋƐ��͖��ւA��A���M���R���z��Ɋ҂����B
����L���
���M�͎R���㐙�Ƃ̉Ɛb�����Ɏg�҂𑗂�A�����`���������B
�u�R�����i�㐙�����j�͎����q�Ƃ��A�֓��Ǘ̐E������ꂽ�B����ɂ���Ď������̂��߂ɕ��������Ԃ����B���Ȃ��������R�����Ɏd���Ă����̂�����A���̂܂��Ɏd���Ȃ����v
����Ɛ��͏��Ȃ��猾�����B
�u�z����i���M�j�̌��J�͍ł������B���������ɕ����Ă��j���\���グ�悤�B�����A�Ɛb�ɂȂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v
�g�҂����̓��e��`����ƌ��M�͓{��A�����Ȃ��čU�߂悤�Ƃ����B
����ƁA���łɌ��M�ɍ~���Ă��ɂ������c�����������������B
�u�Ɛ��͊�łȘV���ŁA��ɂ��̂悤�Ȋ����ł��B�������A�S�͑P�ǂł킴�킴���ނׂ��҂ł��Ȃ��ł��B�����K��������Ɉ��A�ɗ���ł��傤�B�������Ȃ���Ύ����U�߂����W���܂��v
���̓��A�Ɛ����������������Ƃ����Ƃ���A�V�b�����͂�����|�߂��B
�Ɛ��́u���ʂ̂ł���Ό��M�����A�ꂾ�B�J�����Ƃ͂Ȃ����v�ƌ����A���̂܂ܕ����֕����A���M�ɉy�������B
���M�́u���Ȃ���������̎g�҂Ɍ������ĉƐb�ɂȂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ������͖̂{�����v�ƕ������B
����ƋƐ��͂����������B
�u���̒ʂ�ł��B�����q�ɉƓ�����ۂ́A�܂��V�b�Ɏ���A���̌�ɓV�q���邢�͏��R�ɍ����Ă��̋�������̂ł��B�܂��Ă�Ǘ̐E�̂悤�Ȃ��͎̂������R���C������̂ł���A�������ɏ�����̂ł��Ȃ��A�q���������邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A�R���ƍċ��̂��߂Ƃ���Ύ��͂��Ȃ��̎w���ɏ]���A��N�߂܂��傤�v
����������M�͏��Ȃ��猾�����B
�u�����̌����Ƃ���A���Ȃ��͌�蛂̊�v�i�킩�炸��ł������ȂȒj�j�ł���ȁv
���̌�͉���ƂȂ�A����I�������ɋƐ��͖��ւA��A���M���R���z��Ɋ҂����B
����L���
519�l�Ԏ����l�N
2022/12/28(��) 12:51:57.96ID:6Yi16Vhc >>518
�Ȃɂ����Ă�����
�Ȃɂ����Ă�����
520�l�Ԏ����l�N
2022/12/30(��) 13:00:00.90ID:fPD5q2c/ >>516�̑���
���ꂩ��A�A���̂ق����X�A��X�ցA��̕v�w�ŎЎQ�������Ƃ����f����A�����̎��ɐ\�������A
�u�����䎖�Ɍ�B���N�͕v�w�A��ɂĂ������ցB�����ɂ����Ă͐�����y���������܂��傤�B�v�ƁA
���X�Ɩ��A�锌�ˎ�i�������j�͍��ւƋA�����B�����ė��N�̘Z�����A��Ɍv�悵�Ă���
���`�d��A�敨�����̒��ɁA�����]�Ɛ\���������̏��Ȃ���d�O�������A��A�������V�̂悤��
���ĂȂ������o���B
�l���Ă����悤�ɁA����̏鉺�ɂ����ẮA���̗����i�����j��艹�M���ȂǎQ�����B���̏����]��
�������̂Ɏ��炻�̕Ԏ����d�����B
���̂悤�ɓ��X����ʂ�A���̎l�����̎ЎQ���d��A���̌㐴�{�܂Ŗ߂�A�M�����̌䖅��\�������A
�����̏敨�́A���d�O�A����юO�\�l�A�ܐl�̉����A�͂����������ւ��A�M�����͌䎩���̏��d�O�A
�͂����҈ȉ��Ɏ���܂ŁA�����O���䖅�q�ɕt���A����ɔ��ˎ炪�������ċߍ]�ւƏオ�����B
���̍ہA����܂ŘA��Ă��������B�͐��{�ɒu���Ă��������A��ɐ\���������]�Ɛ\���������̏��́A
�敨�̒��ɓ��ꂽ�B����͋A���r���̏�X��蕶�Ȃǂ��͂������A��̕M�Ղƈ��Ȃ��悤�ɂƂ�
�z������ł������B
���a�̗̕��ɋ߂Â��Ɣ��ˎ�́A�w���̂悤�ɒ��`�d��A�M�����̖��̌䋟�����Ĕ��オ���Ă���܂��B
�ł��̂Ō�ƒ��̔N�̑��c�炸�A���ڂ܂Ō�}���ɏo���܂��悤�ɁB�x�Ɛ\���グ���B
���̂��ߐ��ƒ��̎҂����͎c�炸��}���ɏo�A���̋V���A�c�鏊������`���}�����A���֒���
������A���̓��̖ڏo�x����j�����グ���B
���̎��A�M���������Ɛ\�������A���l�̎p�ɕϑ����A����������тт��A���̌�j�������͂����
���{�ւƖ߂����B�M�����͂��̕���ƁA�u��x����ɉ߂����v�Ƃ��j�����ꂽ�Ƃ����B
�i��p���}�L�j
���s�̕��́A���Ƃւ̗`����ɂ���
���ꂩ��A�A���̂ق����X�A��X�ցA��̕v�w�ŎЎQ�������Ƃ����f����A�����̎��ɐ\�������A
�u�����䎖�Ɍ�B���N�͕v�w�A��ɂĂ������ցB�����ɂ����Ă͐�����y���������܂��傤�B�v�ƁA
���X�Ɩ��A�锌�ˎ�i�������j�͍��ւƋA�����B�����ė��N�̘Z�����A��Ɍv�悵�Ă���
���`�d��A�敨�����̒��ɁA�����]�Ɛ\���������̏��Ȃ���d�O�������A��A�������V�̂悤��
���ĂȂ������o���B
�l���Ă����悤�ɁA����̏鉺�ɂ����ẮA���̗����i�����j��艹�M���ȂǎQ�����B���̏����]��
�������̂Ɏ��炻�̕Ԏ����d�����B
���̂悤�ɓ��X����ʂ�A���̎l�����̎ЎQ���d��A���̌㐴�{�܂Ŗ߂�A�M�����̌䖅��\�������A
�����̏敨�́A���d�O�A����юO�\�l�A�ܐl�̉����A�͂����������ւ��A�M�����͌䎩���̏��d�O�A
�͂����҈ȉ��Ɏ���܂ŁA�����O���䖅�q�ɕt���A����ɔ��ˎ炪�������ċߍ]�ւƏオ�����B
���̍ہA����܂ŘA��Ă��������B�͐��{�ɒu���Ă��������A��ɐ\���������]�Ɛ\���������̏��́A
�敨�̒��ɓ��ꂽ�B����͋A���r���̏�X��蕶�Ȃǂ��͂������A��̕M�Ղƈ��Ȃ��悤�ɂƂ�
�z������ł������B
���a�̗̕��ɋ߂Â��Ɣ��ˎ�́A�w���̂悤�ɒ��`�d��A�M�����̖��̌䋟�����Ĕ��オ���Ă���܂��B
�ł��̂Ō�ƒ��̔N�̑��c�炸�A���ڂ܂Ō�}���ɏo���܂��悤�ɁB�x�Ɛ\���グ���B
���̂��ߐ��ƒ��̎҂����͎c�炸��}���ɏo�A���̋V���A�c�鏊������`���}�����A���֒���
������A���̓��̖ڏo�x����j�����グ���B
���̎��A�M���������Ɛ\�������A���l�̎p�ɕϑ����A����������тт��A���̌�j�������͂����
���{�ւƖ߂����B�M�����͂��̕���ƁA�u��x����ɉ߂����v�Ƃ��j�����ꂽ�Ƃ����B
�i��p���}�L�j
���s�̕��́A���Ƃւ̗`����ɂ���
521�l�Ԏ����l�N
2023/01/01(��) 16:17:46.70ID:lFI7BjNp �i�\�\��N�����\�����A���c���̖k�����N�E�q�������́A�l���ܐ�̐l�����ȂāA�i���c�R�̐N�U�̂���
�x�{��蓦�S�����j���쎁�^���x�͂A�������邽�ߏo�w���A���O�͎F?�R�A�������A�R��A�����܂Ŏ�葱�����B
���c�M�����͎g���̕�����ɓ��̖k���̂��Ƃɑ��������A�ނ͘S�ւƓ����ꂽ�B
�M�����͎��N�̌�l�����ƎR�p�O�Y���q�i���i�j�́A��ܕS�̔����R���}���̂��߂ɏx�{�ւƎc���u���A
�ꖜ���炠�܂�̐l���ɂċ��É͌��֑ł��o�āA�k��e�q�l���̐l���ƁA�M�����ꖜ����]��̌R���Ƃ�
��ΐw�ƂȂ����B
���̎����͐������{�����̎��ł�����A�l�������������āA�G�������Ɋ������ɐw�������B
�M�����͌䒆�ԓ��̏O�ɋ��t�����A�x�{�̎����A�w�O�̓�����l�Ɏ������ċ��ÂւƎ��A
�݂̊���������W�߂Ă��̎������A�M���������������݁A�u�ƒ��̑�g�A���g�A�㉺�̋�ʂȂ�
���̎�����U�镑���悤�Ɂv�Ƌ��o���ꂽ�B���̂��߁A���c�̏����݂͂Ȃ��̎������B
���̎��M�����͐q�˂�ꂽ
�u�e�X���̎��������A�����͂Ȃ����H�v
���l�́A�u��������܂���B�v�Ɛ\���҂�����A�u���������ł������ł��B�v�Ɛ\���҂��������B
�����ŁA�M�����͋��ɂȂ�ꂽ
�u���n�ɂ����Ď�������ł��������Ƃ����̂ɁA����R�̏�ɗL�鎁�N�̏O�́A�������܂��ɍ�����
�w�����|�����Ƃ����Ă��A�l�͎R�̘[�ɉ���Ă��邾�낤�B
���N�O�̕��ӂɂ��āA�ނ�͋P�Ձi�㐙���M�j�Ə\���N�ɂ킽���荇�������Ă��邪�A�P�Ղ̖{��
�z��Ə��c���͉����u�����Ă���A��N�Ɉ�x�Âo��A�ܓ��A�\���������āA���قǒ���
���N�ƌ��M���ΐw���鎖�͂Ȃ��B�ł��邩��A�㐙�͑�G�Ƃ����Ȃ���A�叫�ł������㐙�����͎キ�A
�����s�ē��̂ɁA���N�ɕ����𐬌��������ɉ߂��Ȃ��B
���N�O�͍��܂Őr�������G�ɑ������������������߂ɁA���f���Ă��邾�낤�B�����������������߂Ȃ����ɁA
�k���Ƃ̐�O�̊|�����w����j��A���ԂȂ����Ȃ��G�Ɉ���t����I�v
�������t�����A�b�B����O�͎F?�R�֍U�ߏオ�������A���ۂɐw���ɂ͈�A��l�قǂ������炸�A
�{������ׂ��҂����͊F�[�ւƉ���Ă������߁A�����Ɉ��X�Ɛw����j��A���̏㏬�c����O�̕���A�n��A
���Ȃǂ̌��\�ȑ㕨���b�B���c����������B����͐M�����̌�����q���̌̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�x�{��蓦�S�����j���쎁�^���x�͂A�������邽�ߏo�w���A���O�͎F?�R�A�������A�R��A�����܂Ŏ�葱�����B
���c�M�����͎g���̕�����ɓ��̖k���̂��Ƃɑ��������A�ނ͘S�ւƓ����ꂽ�B
�M�����͎��N�̌�l�����ƎR�p�O�Y���q�i���i�j�́A��ܕS�̔����R���}���̂��߂ɏx�{�ւƎc���u���A
�ꖜ���炠�܂�̐l���ɂċ��É͌��֑ł��o�āA�k��e�q�l���̐l���ƁA�M�����ꖜ����]��̌R���Ƃ�
��ΐw�ƂȂ����B
���̎����͐������{�����̎��ł�����A�l�������������āA�G�������Ɋ������ɐw�������B
�M�����͌䒆�ԓ��̏O�ɋ��t�����A�x�{�̎����A�w�O�̓�����l�Ɏ������ċ��ÂւƎ��A
�݂̊���������W�߂Ă��̎������A�M���������������݁A�u�ƒ��̑�g�A���g�A�㉺�̋�ʂȂ�
���̎�����U�镑���悤�Ɂv�Ƌ��o���ꂽ�B���̂��߁A���c�̏����݂͂Ȃ��̎������B
���̎��M�����͐q�˂�ꂽ
�u�e�X���̎��������A�����͂Ȃ����H�v
���l�́A�u��������܂���B�v�Ɛ\���҂�����A�u���������ł������ł��B�v�Ɛ\���҂��������B
�����ŁA�M�����͋��ɂȂ�ꂽ
�u���n�ɂ����Ď�������ł��������Ƃ����̂ɁA����R�̏�ɗL�鎁�N�̏O�́A�������܂��ɍ�����
�w�����|�����Ƃ����Ă��A�l�͎R�̘[�ɉ���Ă��邾�낤�B
���N�O�̕��ӂɂ��āA�ނ�͋P�Ձi�㐙���M�j�Ə\���N�ɂ킽���荇�������Ă��邪�A�P�Ղ̖{��
�z��Ə��c���͉����u�����Ă���A��N�Ɉ�x�Âo��A�ܓ��A�\���������āA���قǒ���
���N�ƌ��M���ΐw���鎖�͂Ȃ��B�ł��邩��A�㐙�͑�G�Ƃ����Ȃ���A�叫�ł������㐙�����͎キ�A
�����s�ē��̂ɁA���N�ɕ����𐬌��������ɉ߂��Ȃ��B
���N�O�͍��܂Őr�������G�ɑ������������������߂ɁA���f���Ă��邾�낤�B�����������������߂Ȃ����ɁA
�k���Ƃ̐�O�̊|�����w����j��A���ԂȂ����Ȃ��G�Ɉ���t����I�v
�������t�����A�b�B����O�͎F?�R�֍U�ߏオ�������A���ۂɐw���ɂ͈�A��l�قǂ������炸�A
�{������ׂ��҂����͊F�[�ւƉ���Ă������߁A�����Ɉ��X�Ɛw����j��A���̏㏬�c����O�̕���A�n��A
���Ȃǂ̌��\�ȑ㕨���b�B���c����������B����͐M�����̌�����q���̌̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
522�l�Ԏ����l�N
2023/01/01(��) 17:15:31.77ID:fw7z4nFs http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-1665.html
�^�c���K�uGIANT KILLING�v�O�b�E�����b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-5356.html
�M���Ɛ헪��
�^�c���K���������Ƃ����b������悤��
�^�c���K�uGIANT KILLING�v�O�b�E�����b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-5356.html
�M���Ɛ헪��
�^�c���K���������Ƃ����b������悤��
523�l�Ԏ����l�N
2023/01/03(��) 20:33:31.63ID:dH72IYYe �i�\�\��N�̏x�͂ɂ����镐�c�Ɩk���̑ΐw�́A�����\�������瓯�N�l����\���܂ł̋�\�O���ł������B
����̂��荇���ɂ����ẮA���c���̐Օ��吆���x���c�����ɒǂ�ꂽ���ƈȊO�́A�݂ȏ��c���k���O��
���c�ɒx�ꂽ�B
�R����炠�܂�̒��w�̂ɁA�M�����͉ƘV�O�������o���A���ꂼ��̈ӌ������B
�����C���i���L�j�́A
�u��t�͊�̗{���ɁA���˂̎O���ɋ������낵�܂��B�v
�n����Z�i�M�t�j��
�u������i�L�c�c�L�j������H�ׂ�ɁA���̒��ƈ���Č��̌���˂��A���ɏo�Ă���̂����܂��B�v
�Ɛ\�����B
�M�����u���Ă͊e�X�̕��ʁA����������ӂł���B�v�ƁA�R���̗}���ł���R�p�O�Y���q�i���i�j���x�{���
���A�k����̐w���������U�炳���A�R�p�̓��S�ł���A�݂��ȁA�L���A�����A���̑��蕿�̎҂�����
��ؕ���������A����ڂ̖�͔n��A�R�p���叫�ɋ��t���A�R��̌��O�Y�Ƃ����āA���N���̓�Ԃ߂�
�q���ŕ��������q�̏��i���Ɓj�̐w���̑O�ɍ���ӂ�A⥂ɂĈ͂����B����Ă��ꂽ�̂�
�s�����ݔj�点���A
�l����\�����ɐM���������o������A���̓��̓�\�����ɂ͐M�����͐w���A�x�͈����̎R���z���āA
�����������������l���i�����j�̍H�v�ɔC���A�I�ɍb�{�ւƋA�҂����B
�k���Ƃł͂��̎��ɂ��āu���c�M���͌����čb�{�ɓ������܂ꂽ�v�Ɛ\�����Ƃ����B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�R�̏x�͂���̓P�ނɂ���
����̂��荇���ɂ����ẮA���c���̐Օ��吆���x���c�����ɒǂ�ꂽ���ƈȊO�́A�݂ȏ��c���k���O��
���c�ɒx�ꂽ�B
�R����炠�܂�̒��w�̂ɁA�M�����͉ƘV�O�������o���A���ꂼ��̈ӌ������B
�����C���i���L�j�́A
�u��t�͊�̗{���ɁA���˂̎O���ɋ������낵�܂��B�v
�n����Z�i�M�t�j��
�u������i�L�c�c�L�j������H�ׂ�ɁA���̒��ƈ���Č��̌���˂��A���ɏo�Ă���̂����܂��B�v
�Ɛ\�����B
�M�����u���Ă͊e�X�̕��ʁA����������ӂł���B�v�ƁA�R���̗}���ł���R�p�O�Y���q�i���i�j���x�{���
���A�k����̐w���������U�炳���A�R�p�̓��S�ł���A�݂��ȁA�L���A�����A���̑��蕿�̎҂�����
��ؕ���������A����ڂ̖�͔n��A�R�p���叫�ɋ��t���A�R��̌��O�Y�Ƃ����āA���N���̓�Ԃ߂�
�q���ŕ��������q�̏��i���Ɓj�̐w���̑O�ɍ���ӂ�A⥂ɂĈ͂����B����Ă��ꂽ�̂�
�s�����ݔj�点���A
�l����\�����ɐM���������o������A���̓��̓�\�����ɂ͐M�����͐w���A�x�͈����̎R���z���āA
�����������������l���i�����j�̍H�v�ɔC���A�I�ɍb�{�ւƋA�҂����B
�k���Ƃł͂��̎��ɂ��āu���c�M���͌����čb�{�ɓ������܂ꂽ�v�Ɛ\�����Ƃ����B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�R�̏x�͂���̓P�ނɂ���
524�l�Ԏ����l�N
2023/01/04(��) 07:13:17.97ID:1ewKKFZE �܂��s��������ł���
525�l�Ԏ����l�N
2023/01/04(��) 08:35:22.64ID:lpy2kxKk �ց[�A�����҂Ƃ��ɂ͊��o�Ȃ낤���ǒm��Ȃ������Ȃ�
�Y�o�V���@�i�n�ɑ��Y���a�P�O�O�N
�P�T�ԂŎ莆�Q��ʂ���ꂽ�u���n���䂭�v
��l���̃��f���͂Q�l�����B�P�l�́u���n�������Ăق����v�Ƃ������m�o�g�̎i�n����̌�y�L�ҁB
�����炩�Ȑ��i�Ŗ�P�W�O�Z���`�̈̏�v�������B������l�́A�n���K���[�����ŖS���������w�@��
�w��ł����X�e�B�[�u���E�g���N����B�u������ꍑ�ɖ߂��đ哝�̂ɂȂ�v�ƌ��ނɁA�y���˂�
�E�˂�����l���̐l�������d�Ȃ����悤�������B
�Y�o�V���@�i�n�ɑ��Y���a�P�O�O�N
�P�T�ԂŎ莆�Q��ʂ���ꂽ�u���n���䂭�v
��l���̃��f���͂Q�l�����B�P�l�́u���n�������Ăق����v�Ƃ������m�o�g�̎i�n����̌�y�L�ҁB
�����炩�Ȑ��i�Ŗ�P�W�O�Z���`�̈̏�v�������B������l�́A�n���K���[�����ŖS���������w�@��
�w��ł����X�e�B�[�u���E�g���N����B�u������ꍑ�ɖ߂��đ哝�̂ɂȂ�v�ƌ��ނɁA�y���˂�
�E�˂�����l���̐l�������d�Ȃ����悤�������B
526�l�Ԏ����l�N
2023/01/04(��) 08:36:46.82ID:lpy2kxKk ���A�딚���܂���
527�l�Ԏ����l�N
2023/01/04(��) 23:54:14.80ID:OnRDo+3F528�l�Ԏ����l�N
2023/01/05(��) 07:02:14.66ID:uWu0t0A3 ������i�n�j�ς͊ԈႢ����������C�����悤�ˏ����Ȃ��A�̂͂���
�i�n�ɑ��Y�̏�����ǂނȂ�ė��j���m��Ȃ��n���Ȃ���ȁA�Ƃ����悤�Ȕl�|��SNS�ɑ������̂���
�������y���߂Ȃ����N�����҂Ƃ��
�i�n�ɑ��Y�̏�����ǂނȂ�ė��j���m��Ȃ��n���Ȃ���ȁA�Ƃ����悤�Ȕl�|��SNS�ɑ������̂���
�������y���߂Ȃ����N�����҂Ƃ��
529�l�Ԏ����l�N
2023/01/05(��) 21:05:26.94ID:aN5OpNqs 18���I�O���ɏ����ꂽ�u�����ƊՒk�v����u���B�����v�Ɠ���ƍN�̉��B�N�U
���쎁�^�̎��A���B�l���̈��ԏ�͔є��L�O�i�є��A���j�����ł������B
�܂�������͍��쎁�^�̖����E����]���i����@�P�H�j�����������Ă����B
����̎�莝���Ŕє��L�O�̖Â����^�̏��ƂȂ������߁A��������͔є��E����Ƃ��o���l�ƂȂ����B
������槎ҁi�V��e��H�j�̂��ߎ��^�͗��҂ɑ��ē{��A�є��L�O���x�{��ɌĂъĎE�Q�����B
�є��ƘV�ł���]�Ԉ��|�i�]�n���j�A�]�ԉ���i�]�Ԏ����j�͌����l�ɖ������A�L�O�㎺�i���c�߂̕��j����삵���ԏ���ď邵���B
���������^������U�߂�Ə���͋������R�킩�ł��߁A���|�Ɖ���͓��m���������ʂĂĂ��܂����B
�Ɛb�̖�c�F�E�q��͖S��̎u�����Ō����l�ɉ��R�𗊂B
�����l�͉��B���Ԃ����o�n�����ӂ���A�ē����p�Y�����q��ɖ������B
�Y�����q��́u�l���ɂ��z���ɂȂ�ɂ͖{��E�����Ƃ�����̓��ʂ�˂Ȃ�ʂ����A�{��ł͍��안��̕l�����Ɂi�l�����L�j���Ꝅ�𗦂��Ă���A����Ƒ����܂��B
�K�����w�̕��ʂ͂��₩�ł��̂ł���������ʂ�ɂȂ�Ƃ�낵���ł��傤�v
�Ɛ\�����������l�́u�{��ł��ꂵ���͂Ȃ����낤�v�ƌY�����q��̍l����ނ���ꂽ�B
���̂̂��o�w����i�ɂȂ�A�����l�͖{��Ɍ������A���̖ʁX�͍b�h���ԂŖڗ����Ȃ����ċ��w�E�C����ʂɏo�w�������B
�Y�����q��͗t�̂Ȃ�Ŗ{�⓻�܂Ŗ{�����ē�����ƕl���Ɍ������A�l���̋��̂܂�⎛�E��ڎ��Ƃ�����̎��ɕ����A���̑����ɂ܂���Ė{���͖{�⓻���z���A���w���o�R�������ƍ��������B
���̌��ɂ��Y�����q��́A�����l���l������ɓ��ꂽ�̂��A��̓�̋ȗւɂƂ߂�����A�{���썶�q��i�{���d���j�z���ƂȂ����B
�������{���썶�q��͏��c���̐w�ŗ̒n�������������Ă��܂��A�p�Y�����q��͗��Q�̐g�ƂȂ�A�a�������Ƃ����B
����ɂ͌����l�͍������n��ɂȂ�A�l������ꗢ���̉F�z�����ɂ������ɂȂ�A�����̕��ώ��̏Z�m�̈ē��ň��ԏ�ɓ���ꂽ�Ƃ����B
�钆�̊F�͂�낱�сA�]�ԉ���̍Ȏq�͌����l�ɏ����������J���������ꂽ�B
�����ɂ������ē�̏���]���������l�ɏ�������n���đނ������߁A�����l�͒������ƂƐؒ厡�ɓ����点�Ȃ������B
����Ŗ{��̈Ꝅ�������Ƃ��Ƃ���ގ��Ȃ���A�E�S�����C�ꑺ�Ŋ|����ꂽ�Ƃ����B
���쎁�^�̎��A���B�l���̈��ԏ�͔є��L�O�i�є��A���j�����ł������B
�܂�������͍��쎁�^�̖����E����]���i����@�P�H�j�����������Ă����B
����̎�莝���Ŕє��L�O�̖Â����^�̏��ƂȂ������߁A��������͔є��E����Ƃ��o���l�ƂȂ����B
������槎ҁi�V��e��H�j�̂��ߎ��^�͗��҂ɑ��ē{��A�є��L�O���x�{��ɌĂъĎE�Q�����B
�є��ƘV�ł���]�Ԉ��|�i�]�n���j�A�]�ԉ���i�]�Ԏ����j�͌����l�ɖ������A�L�O�㎺�i���c�߂̕��j����삵���ԏ���ď邵���B
���������^������U�߂�Ə���͋������R�킩�ł��߁A���|�Ɖ���͓��m���������ʂĂĂ��܂����B
�Ɛb�̖�c�F�E�q��͖S��̎u�����Ō����l�ɉ��R�𗊂B
�����l�͉��B���Ԃ����o�n�����ӂ���A�ē����p�Y�����q��ɖ������B
�Y�����q��́u�l���ɂ��z���ɂȂ�ɂ͖{��E�����Ƃ�����̓��ʂ�˂Ȃ�ʂ����A�{��ł͍��안��̕l�����Ɂi�l�����L�j���Ꝅ�𗦂��Ă���A����Ƒ����܂��B
�K�����w�̕��ʂ͂��₩�ł��̂ł���������ʂ�ɂȂ�Ƃ�낵���ł��傤�v
�Ɛ\�����������l�́u�{��ł��ꂵ���͂Ȃ����낤�v�ƌY�����q��̍l����ނ���ꂽ�B
���̂̂��o�w����i�ɂȂ�A�����l�͖{��Ɍ������A���̖ʁX�͍b�h���ԂŖڗ����Ȃ����ċ��w�E�C����ʂɏo�w�������B
�Y�����q��͗t�̂Ȃ�Ŗ{�⓻�܂Ŗ{�����ē�����ƕl���Ɍ������A�l���̋��̂܂�⎛�E��ڎ��Ƃ�����̎��ɕ����A���̑����ɂ܂���Ė{���͖{�⓻���z���A���w���o�R�������ƍ��������B
���̌��ɂ��Y�����q��́A�����l���l������ɓ��ꂽ�̂��A��̓�̋ȗւɂƂ߂�����A�{���썶�q��i�{���d���j�z���ƂȂ����B
�������{���썶�q��͏��c���̐w�ŗ̒n�������������Ă��܂��A�p�Y�����q��͗��Q�̐g�ƂȂ�A�a�������Ƃ����B
����ɂ͌����l�͍������n��ɂȂ�A�l������ꗢ���̉F�z�����ɂ������ɂȂ�A�����̕��ώ��̏Z�m�̈ē��ň��ԏ�ɓ���ꂽ�Ƃ����B
�钆�̊F�͂�낱�сA�]�ԉ���̍Ȏq�͌����l�ɏ����������J���������ꂽ�B
�����ɂ������ē�̏���]���������l�ɏ�������n���đނ������߁A�����l�͒������ƂƐؒ厡�ɓ����点�Ȃ������B
����Ŗ{��̈Ꝅ�������Ƃ��Ƃ���ގ��Ȃ���A�E�S�����C�ꑺ�Ŋ|����ꂽ�Ƃ����B
530�l�Ԏ����l�N
2023/01/06(��) 22:26:41.15ID:k5YdyoG6 �u�����ƊՒk�v���璆�R����R(���R�Ɣ�)
�ƍN���͕l���Ɉڂ��A�x�]��̑��(�����)�A�����̒���(�������)�A���c�����̖؎��{(����V�c�̍c�q�E�M�ǐe���̎q��)�Ȃǂ��U�߂�ꂽ�B
������̋ߓ����E�q��(�ߓ��N�p�A��ɒJ�O�l�O�̈�l)�͕��킵�����҂�˂���Ă��܂����B
�����������ēG�͖x�]����Ă�҂ǂ��݂̂ƂȂ������A���͂͑�͂ł���A�G���͊O���Ƃ��Ƃ肪�ł��Ȃ��Ȃ����B
���̎��A���c������̉����ł��镐�B�����q�̒��R����R�Ɣ͂����𗬔n�p�ł݂Ȃ����͂ɏ�����A��܂œn�����B
������݂����c�M���͑傢�Ɋ�����
�u�����E�ߍ��Ő�m���Ă����Ƃ��Ă����̂悤�ɓn�邱�Ƃ͖����ł���̂ɁA�����̎҂����̂悤�Ȕn�p���I����Ƃ́B
�܂��Ƃɋ��E���o�ł���v�Ə̎^�̂��܂�h��n�����B
���݁A���R�B�����řh�A���R�O�g�����頰���Ă��`����Ă���Ƃ����B
���R����R�͓V���\���N�ɔ����q��Ő펀�����Ƃ����B
�ƍN���͕l���Ɉڂ��A�x�]��̑��(�����)�A�����̒���(�������)�A���c�����̖؎��{(����V�c�̍c�q�E�M�ǐe���̎q��)�Ȃǂ��U�߂�ꂽ�B
������̋ߓ����E�q��(�ߓ��N�p�A��ɒJ�O�l�O�̈�l)�͕��킵�����҂�˂���Ă��܂����B
�����������ēG�͖x�]����Ă�҂ǂ��݂̂ƂȂ������A���͂͑�͂ł���A�G���͊O���Ƃ��Ƃ肪�ł��Ȃ��Ȃ����B
���̎��A���c������̉����ł��镐�B�����q�̒��R����R�Ɣ͂����𗬔n�p�ł݂Ȃ����͂ɏ�����A��܂œn�����B
������݂����c�M���͑傢�Ɋ�����
�u�����E�ߍ��Ő�m���Ă����Ƃ��Ă����̂悤�ɓn�邱�Ƃ͖����ł���̂ɁA�����̎҂����̂悤�Ȕn�p���I����Ƃ́B
�܂��Ƃɋ��E���o�ł���v�Ə̎^�̂��܂�h��n�����B
���݁A���R�B�����řh�A���R�O�g�����頰���Ă��`����Ă���Ƃ����B
���R����R�͓V���\���N�ɔ����q��Ő펀�����Ƃ����B
531530
2023/01/07(�y) 12:15:19.36ID:zcSgtF6o �������ƒ��R����R�͑�͂�n�����A�Ƃ��������Ă�̂�
���̂��߂ɖx�]�邩��n���Ă����ƍl�����������R����
���̂��߂ɖx�]�邩��n���Ă����ƍl�����������R����
532�l�Ԏ����l�N
2023/01/07(�y) 18:12:50.73ID:IHNWrgsW �P�R�삯�ԕ���
533�l�Ԏ����l�N
2023/01/07(�y) 20:41:41.12ID:EgOhblty ��H�ƍN�Ɨ����č���̐�Ƃ��Ă�Ƃ��̘b����ȁH
�M���ǂ��Ō��Ă��H�H
�M���ǂ��Ō��Ă��H�H
534530
2023/01/07(�y) 21:09:44.65ID:RAPuE3SW �M���͉ƍN�ɍ��킹�č����(�x��)�ɐN�U�����Ƃ͂����A�M���̖x�]��U�߂͎O�������̌ゾ���琳���悭�킩��Ȃ�
���R����R�̎q�������𗬔n�p�ɔ������邽�߂ɂł����������̂�������Ȃ�
���R����R�̎q�������𗬔n�p�ɔ������邽�߂ɂł����������̂�������Ȃ�
535530
2023/01/07(�y) 21:13:34.02ID:RAPuE3SW �u�����ƊՒk�v���瓿��ƍN�̎�ꕨ�Ɩ{���d��
�����l����ꕨ���킸�炢�ɂȂ�ꂽ�߁A�^���o�����Ƃ͂܂���̊L�k�łق�ꂽ���A�������Ēɂ݂��������B
�u�O�Ȃ������o���v�Ɩ�����ꂽ�Ƃ���A�������ܖ{���썶�q�傪���ՂƐ\�����l��҂̖���Љ���B
�����ł��̖�����Ă��Ă݂����A�Ђǂ����݂��ł��������߂Ƃ��߂��B
�������썶�q��́u���̖��h��ꂽ��ɋ����������܂��悤�v�ƌ����l�ɑi�������߁A�����l�͏a�X���̒ʂ�ɂ��ꂽ�B
��������������͂���܂ł����Ђǂ��ɂ݂ł��������A���炭����Ǝ�ꕨ��������j��Ēɂ݂������Ȃ����B
�����l�͍썶�q��Ɂu���܂��̂������Ŗ������������B
���܂��͕Њ����̏X�j�ł��邪�A�킵�̈ӌ��ɂ��t����Ăł��A�킵�̂��߂ɋ����|������Ƃ͒��`�Ȃ��Ƃł���v
�Ɗ��S�Ȃ������������B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-498.html
�{���썶�q��ƉƍN�̎�ꕨ�E�����b
������͓�����b�����ǁA���e�͂��������قȂ�
�����l����ꕨ���킸�炢�ɂȂ�ꂽ�߁A�^���o�����Ƃ͂܂���̊L�k�łق�ꂽ���A�������Ēɂ݂��������B
�u�O�Ȃ������o���v�Ɩ�����ꂽ�Ƃ���A�������ܖ{���썶�q�傪���ՂƐ\�����l��҂̖���Љ���B
�����ł��̖�����Ă��Ă݂����A�Ђǂ����݂��ł��������߂Ƃ��߂��B
�������썶�q��́u���̖��h��ꂽ��ɋ����������܂��悤�v�ƌ����l�ɑi�������߁A�����l�͏a�X���̒ʂ�ɂ��ꂽ�B
��������������͂���܂ł����Ђǂ��ɂ݂ł��������A���炭����Ǝ�ꕨ��������j��Ēɂ݂������Ȃ����B
�����l�͍썶�q��Ɂu���܂��̂������Ŗ������������B
���܂��͕Њ����̏X�j�ł��邪�A�킵�̈ӌ��ɂ��t����Ăł��A�킵�̂��߂ɋ����|������Ƃ͒��`�Ȃ��Ƃł���v
�Ɗ��S�Ȃ������������B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-498.html
�{���썶�q��ƉƍN�̎�ꕨ�E�����b
������͓�����b�����ǁA���e�͂��������قȂ�
536�l�Ԏ����l�N
2023/01/07(�y) 23:03:34.50ID:eTIKiZeg537�l�Ԏ����l�N
2023/01/08(��) 12:51:28.25ID:3OeZANhT ���ĕ��R�ďC�̋��ɔ��ƍN��
538�l�Ԏ����l�N
2023/01/08(��) 18:36:51.99ID:3OeZANhT ��͑��b
�h��ȋ��Z��͑���`������́A���N�i�ƎO�͏O�j�ւ̐M���̏Ƃ��Ă̑��蕨���ĉ��o�͂����ł���
�h��ȋ��Z��͑���`������́A���N�i�ƎO�͏O�j�ւ̐M���̏Ƃ��Ă̑��蕨���ĉ��o�͂����ł���
539�l�Ԏ����l�N
2023/01/08(��) 18:39:41.30ID:3OeZANhT ������R�c�i���ɖ���点���̂́A�ߋ��́u���Ձv�l�^������Ƃ������I�Ȉ�ɒ����ɂȂ��邽�߂��ȁH
�R�c�̎q�̐��Ǒ��́u���Ձv���X�g�ň�u�����o�Ԃ�������
�R�c�̎q�̐��Ǒ��́u���Ձv���X�g�ň�u�����o�Ԃ�������
540�l�Ԏ����l�N
2023/01/08(��) 19:05:31.20ID:3OeZANhT �ƍN�ƐM�������̗ǂ��c����ł͂Ȃ��A�L�����t���b�V���o�b�N���Đg�k������قǂ̂����߂����q��
���C�ɓ���̂����ߑ���������������߂��q�Ƃ����̂��a�V��
���C�ɓ���̂����ߑ���������������߂��q�Ƃ����̂��a�V��
541�l�Ԏ����l�N
2023/01/08(��) 21:28:49.20ID:FlEGboV6542�l�Ԏ����l�N
2023/01/09(��) 02:27:23.85ID:yBmC8zxO ����ȃN�\�h���}���Ă�z�����̃X���ɂ���Ȃ�Ă�
�����ƃW���j�I�^�̂��Ԕ��Ȃ�
�A���Ŋ�Ⴄ��
�����ƃW���j�I�^�̂��Ԕ��Ȃ�
�A���Ŋ�Ⴄ��
543�l�Ԏ����l�N
2023/01/09(��) 12:18:14.20ID:3iNTOqrm �ǂ������A�Ȃ������̂��H
���ɂł��ӂ�ꂽ���H
���ɂł��ӂ�ꂽ���H
544�l�Ԏ����l�N
2023/01/09(��) 13:10:34.89ID:AWGkuSD4 �������ɂӂ�ꂽ�W���j�^����������ł���`
�ȁ[�Ɂ[������܂����Ȃ��I
�ȁ[�Ɂ[������܂����Ȃ��I
545�l�Ԏ����l�N
2023/01/09(��) 16:48:47.43ID:1bvbqDz0 �������ĒE��
��ɋA���ĕs��Q
�Q�N���Ɉ��A
��ɋA���ĕs��Q
�Q�N���Ɉ��A
546�l�Ԏ����l�N
2023/01/09(��) 17:39:25.35ID:UaZUy/56 ���A�܍s��
547�l�Ԏ����l�N
2023/01/09(��) 19:10:33.28ID:vjiAFdO6 ���}�ƂȂ����L�b�G�g�������������A���璃�𗧂Ă����̂��ƁB
�����ɎQ�����Ă�����J�Y������g���̓��C�a�������Ă����B
���q���������Ԃ����A�₪�ċg���̎�Ɉڂ����B
���}�a�������痧�Ă����ł���A���������q�������ɉ^�Ƃ���A���^�̍��������@�`�����q�̒��ɗ����Ă��܂����B
�|�������Ă͖��v�s���̗E�҂ł���g��������ɂ͍����Ă��܂����B
�����ԖʁX�͒N���C�Â��Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ł��̂܂܉����Ǝv�������A���^�̍������������킩��ʂƂ͂������l�Ɉ��܂���̂͂������ɐS���p����B
���Ă��̏���ǂ����U�������̂��Ɠr���ɂ���Ă���ƁA���̗l�q�����Ă������}�͂�����ʊ�Łu�Y���A���̒��͉������s������������P�x���Ē������B���q��������֕Ԃ��v�Ǝ��L���Ă����B
����ɂ���ĉv�X�f���Ă��܂����Y�����܂��܂����Ă���ƁA���}�͂Ђ�������悤�ɒ��q�������Ƃ�ƁA���^�̓����������O�b�ƈ��݊����Ă��܂����B�����ĐV�������𗧂ĂȂ����Ă܂킵���B
�ʖڂ�ۂ��Ƃ��ł����g���́A�ق��Ɠf����R�炵���Ƃ����B
�L���G�s�\�[�h�̏����Ⴄ�ŁB�w�L�b�G�g���s�^�x���
�����ɎQ�����Ă�����J�Y������g���̓��C�a�������Ă����B
���q���������Ԃ����A�₪�ċg���̎�Ɉڂ����B
���}�a�������痧�Ă����ł���A���������q�������ɉ^�Ƃ���A���^�̍��������@�`�����q�̒��ɗ����Ă��܂����B
�|�������Ă͖��v�s���̗E�҂ł���g��������ɂ͍����Ă��܂����B
�����ԖʁX�͒N���C�Â��Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ł��̂܂܉����Ǝv�������A���^�̍������������킩��ʂƂ͂������l�Ɉ��܂���̂͂������ɐS���p����B
���Ă��̏���ǂ����U�������̂��Ɠr���ɂ���Ă���ƁA���̗l�q�����Ă������}�͂�����ʊ�Łu�Y���A���̒��͉������s������������P�x���Ē������B���q��������֕Ԃ��v�Ǝ��L���Ă����B
����ɂ���ĉv�X�f���Ă��܂����Y�����܂��܂����Ă���ƁA���}�͂Ђ�������悤�ɒ��q�������Ƃ�ƁA���^�̓����������O�b�ƈ��݊����Ă��܂����B�����ĐV�������𗧂ĂȂ����Ă܂킵���B
�ʖڂ�ۂ��Ƃ��ł����g���́A�ق��Ɠf����R�炵���Ƃ����B
�L���G�s�\�[�h�̏����Ⴄ�ŁB�w�L�b�G�g���s�^�x���
548�l�Ԏ����l�N
2023/01/09(��) 19:55:01.91ID:CkYvUW1c ���݂��ҕa�}���R���N���j�������̃G�s���v���o������
549�l�Ԏ����l�N
2023/01/09(��) 20:08:24.69ID:MT5WkgtU >>548
�I�[�����D���͊��ɂȂ�₷����������
�I�[�����D���͊��ɂȂ�₷����������
550�l�Ԏ����l�N
2023/01/11(��) 00:12:50.48ID:91aVkVe0 �u�����ƊՒk�v���珬��V���̕��E
���B�|��V���R�̐킢�ɂ����āA��̂��ɓG�̎蕉���̎҂������B
�����̗E�m���G�̎����낤�ƐS���������̂́A�G�w�̂������ł��肠����߂Ă����Ƃ���ɁA
�O�͏O�̏���V������Ȃ��s���ēG�̎������ċA���Ă����B
����͖��̒��̓����ł������B
����A�����l���V���Ɂu���������Ƃ���́A�G�����̋����͂����قǂ��������H�v�Ɛq�˂��Ƃ���
�V���́u�\�l�A�܊Ԃق�(25m�ق�)�������Ǝv���܂��v�Ɛ\���グ���B
�����Ō����l����܂ōs���ċ������v�点���Ƃ���|��2��������ł��������߁A���悢�抴�S�Ȃ��ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
���B�|��V���R�̐킢�ɂ����āA��̂��ɓG�̎蕉���̎҂������B
�����̗E�m���G�̎����낤�ƐS���������̂́A�G�w�̂������ł��肠����߂Ă����Ƃ���ɁA
�O�͏O�̏���V������Ȃ��s���ēG�̎������ċA���Ă����B
����͖��̒��̓����ł������B
����A�����l���V���Ɂu���������Ƃ���́A�G�����̋����͂����قǂ��������H�v�Ɛq�˂��Ƃ���
�V���́u�\�l�A�܊Ԃق�(25m�ق�)�������Ǝv���܂��v�Ɛ\���グ���B
�����Ō����l����܂ōs���ċ������v�点���Ƃ���|��2��������ł��������߁A���悢�抴�S�Ȃ��ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
551�l�Ԏ����l�N
2023/01/11(��) 23:32:06.05ID:91aVkVe0 �u�����ƊՒk�v�Ɠ������҂ɂ��A�ؑ����ցu���ƊՒk�v����u����ƍN�̑卂�镺�Ɠ���v
����`���͖����̉L�a������D�c�M���̗}���Ƃ��đ卂��ɒu���Ă����B
�������M���͊ۍ���A�h�Ï��z���A�卂����Ǘ������A���̏�Ɏ�����A�����A�L����̎O��ɂ�����u�������ߑ卂��ւ̕��Ɣ������ł��Ȃ������B
���̂��ߍ��삩�猠���l�ɉi�\��N?(1559�N)�l���\���ɕ��Ƃ�����悤�������������B
�����l�͉�����������ł����A���䐳�e�A���䒉���A�ΐ쐔�����
�u�M�������Ă��X�̑O�ŕ��Ƃ��^�ԂȂǕs�\�ł��v���|�߂��B
�����l�͓����\���ł��������A�Ɛb�̌��t��p���Ȃ��炸
�u��ɍl�������邩�猾���ʂ�ɂ������v�Ƃ�����������B
���Č����l�͋���̖锼�Ɏ��䐳�e�E�ΐ쐔���Ɏl��R�𗦂������A�卂����͂ޘh�ÁE�ۍ��̗�����������Ď�������U�߂������B
����Ō����l�͔��S�R�ŏ��בʐ��S�D�������A�ꎩ��卂��Ɍ��������B
������̐D�c���́u�Ȃ��G���͂͂邩���̂��̎�����Ɏ��|����̂��낤�H�v�ƕs�v�c�Ɏv���Ȃ�����Ƃ肠�����h�킵���B
����̉N���̂��߁A�Â����Â��A�O�͕��͂�����x�U�߂Ă����ƈ����Ԃ��A
�߂��̔~���؏���U�߂ē�̊ہA�O�̊ۂ܂ʼn��������ĉ������B
����`���͖����̉L�a������D�c�M���̗}���Ƃ��đ卂��ɒu���Ă����B
�������M���͊ۍ���A�h�Ï��z���A�卂����Ǘ������A���̏�Ɏ�����A�����A�L����̎O��ɂ�����u�������ߑ卂��ւ̕��Ɣ������ł��Ȃ������B
���̂��ߍ��삩�猠���l�ɉi�\��N?(1559�N)�l���\���ɕ��Ƃ�����悤�������������B
�����l�͉�����������ł����A���䐳�e�A���䒉���A�ΐ쐔�����
�u�M�������Ă��X�̑O�ŕ��Ƃ��^�ԂȂǕs�\�ł��v���|�߂��B
�����l�͓����\���ł��������A�Ɛb�̌��t��p���Ȃ��炸
�u��ɍl�������邩�猾���ʂ�ɂ������v�Ƃ�����������B
���Č����l�͋���̖锼�Ɏ��䐳�e�E�ΐ쐔���Ɏl��R�𗦂������A�卂����͂ޘh�ÁE�ۍ��̗�����������Ď�������U�߂������B
����Ō����l�͔��S�R�ŏ��בʐ��S�D�������A�ꎩ��卂��Ɍ��������B
������̐D�c���́u�Ȃ��G���͂͂邩���̂��̎�����Ɏ��|����̂��낤�H�v�ƕs�v�c�Ɏv���Ȃ�����Ƃ肠�����h�킵���B
����̉N���̂��߁A�Â����Â��A�O�͕��͂�����x�U�߂Ă����ƈ����Ԃ��A
�߂��̔~���؏���U�߂ē�̊ہA�O�̊ۂ܂ʼn��������ĉ������B
552�l�Ԏ����l�N
2023/01/11(��) 23:35:24.70ID:91aVkVe0 �͈Ŗ�����X�ƋP�������B
�h�ÁE�ۍ��̕��ǂ��͂��̌��i������
�u������A�~���؏�̎�������I�v�Ƌ삯�o�����B
�������Č����l�͉��̏�Q���Ȃ��v���̂܂܂ɕ��Ƃ�卂��ɉ^�ѓ��ꂽ�B
�卂��ւ̕��Ɣ����������h�ÁE�ۍ�����̎���������͎��ł��ċ����A����~���ĉ���B
�ΐ�E����������Ɉ����Ԃ��A�����l�ƂƂ��ɉ����ɋA�҂����B
�A���A�݂Ȃ݂Ȍ����l�̌�O�ɏo��
�u���č����͌����ɕ��Ƃ�卂��ɉ^�ѓ�����܂������A�Ȃ���X�Ɏ�����E�~���؏���U�߂������̂ł��H�v�Ɛq�˂��B
�����l�̋��ɂ́u�h�Ï�E�ۍ���͑卂��ւ̕��Ɠ����j�~���邽�߂̏�ł��邪�A������E�~���؏邩��̌�l�߂𗊂�Ƃ��Ă���B
����������E�~���؏邪���邵���Ȃ�h�Ï�E�ۍ�������オ��̂�����A���邪�U�߂�ꂽ�ƕ���������ɕ��������邾�낤�B
���̌��ɉ�͍U�߂���S�z�������ɕ��Ƃ�卂��ɉ^�ѓ����ꂽ�A�Ƃ����킯���B
�u���@�͐_���ԁv�ƌ������A�l�̗\�z�O��˂��̂��̗v�ł���B�v
��������ƘV�O��
�u�N�͗c�������Սώ��̑�����ւɏK���A������ǂ܂ꂽ�ƕ����Ă���܂������A�\���ɂ��Ă���قǂ̒m���Ƃ́B
�܂��ɐ����̖����Ō�����܂��B��X���̂������v���܂��B�v
�ƌ��X�Ɍ������Ƃ����B
�Ȃ����̑卂��ւ̕��Ɠ��ꂪ�����l�̌�蕨�̏��߂��������B
�h�ÁE�ۍ��̕��ǂ��͂��̌��i������
�u������A�~���؏�̎�������I�v�Ƌ삯�o�����B
�������Č����l�͉��̏�Q���Ȃ��v���̂܂܂ɕ��Ƃ�卂��ɉ^�ѓ��ꂽ�B
�卂��ւ̕��Ɣ����������h�ÁE�ۍ�����̎���������͎��ł��ċ����A����~���ĉ���B
�ΐ�E����������Ɉ����Ԃ��A�����l�ƂƂ��ɉ����ɋA�҂����B
�A���A�݂Ȃ݂Ȍ����l�̌�O�ɏo��
�u���č����͌����ɕ��Ƃ�卂��ɉ^�ѓ�����܂������A�Ȃ���X�Ɏ�����E�~���؏���U�߂������̂ł��H�v�Ɛq�˂��B
�����l�̋��ɂ́u�h�Ï�E�ۍ���͑卂��ւ̕��Ɠ����j�~���邽�߂̏�ł��邪�A������E�~���؏邩��̌�l�߂𗊂�Ƃ��Ă���B
����������E�~���؏邪���邵���Ȃ�h�Ï�E�ۍ�������オ��̂�����A���邪�U�߂�ꂽ�ƕ���������ɕ��������邾�낤�B
���̌��ɉ�͍U�߂���S�z�������ɕ��Ƃ�卂��ɉ^�ѓ����ꂽ�A�Ƃ����킯���B
�u���@�͐_���ԁv�ƌ������A�l�̗\�z�O��˂��̂��̗v�ł���B�v
��������ƘV�O��
�u�N�͗c�������Սώ��̑�����ւɏK���A������ǂ܂ꂽ�ƕ����Ă���܂������A�\���ɂ��Ă���قǂ̒m���Ƃ́B
�܂��ɐ����̖����Ō�����܂��B��X���̂������v���܂��B�v
�ƌ��X�Ɍ������Ƃ����B
�Ȃ����̑卂��ւ̕��Ɠ��ꂪ�����l�̌�蕨�̏��߂��������B
553�l�Ԏ����l�N
2023/01/12(��) 23:03:56.12ID:CkZ1eLq0 �u���ƊՒk�v��蓿��ƍN�̌����̔���
�����l�͓V���ꓝ�̂̂����A���ɂ����ɂ���邱�ƂȂ��A���ʂ̂��U�镑���͂Ȃ���Ȃ������B
�M���̖��̌����@(�M�������Ō��R�~�ᐳ���̌����@)�ƌ�ڌ��̂Ƃ��́A������i����~���ĉ�߂��Ȃ������B
�܂������ŁA����`���펀�̏�ł��鉱���Ԃ̓c�y���E�̋߂���ʂ�ۂɂ͖��x���n�Ȃ������B
���Ɍ����̌�S���[�����ƁA���t�ɂł��Ȃ��قǂł���B
�����l�͓V���ꓝ�̂̂����A���ɂ����ɂ���邱�ƂȂ��A���ʂ̂��U�镑���͂Ȃ���Ȃ������B
�M���̖��̌����@(�M�������Ō��R�~�ᐳ���̌����@)�ƌ�ڌ��̂Ƃ��́A������i����~���ĉ�߂��Ȃ������B
�܂������ŁA����`���펀�̏�ł��鉱���Ԃ̓c�y���E�̋߂���ʂ�ۂɂ͖��x���n�Ȃ������B
���Ɍ����̌�S���[�����ƁA���t�ɂł��Ȃ��قǂł���B
554�l�Ԏ����l�N
2023/01/13(��) 22:26:27.80ID:iXo+cHzD �u���ƊՒk�v�����������̕Њ����ɂ���
�V���\�Z�N(1588�N)�����ܓ��A���������͓V���ɓ���(�V���팳)�Ƃ̈��̎��ɏ\��������˂��܂��Ă��܂����B
����ȗ��A�Њ��ɂȂ������Ƃ͓V�����ꓯ�ɒm��Ƃ���ł���B
�����Ƃ��A���X�Њ��������Ƃ�����������B
���ɓ�����(����)�̉Ɛl�������ɂ́A����������܂����͕̂��؍�Ƃ������ŁA���̐܂ꂽ�Њ������ł����؍�̎Ђɕۊǂ���Ă���Ƃ����B
���]�̐l������Ύ��o�����Ƃ��ł��邻�����B
�܂������̕Њ����������l�̘b�ɂ��A�\�����̌����ł���A�u�Â̍�Œ��n�A����̕�͌F�̖сA����͍����V�����Ƃ����B
�(������)�������Ă���҂�����A�F�̖т��P�{�����ē��ɍڂ����ኂ�������Ƃ����B
�V���\�Z�N(1588�N)�����ܓ��A���������͓V���ɓ���(�V���팳)�Ƃ̈��̎��ɏ\��������˂��܂��Ă��܂����B
����ȗ��A�Њ��ɂȂ������Ƃ͓V�����ꓯ�ɒm��Ƃ���ł���B
�����Ƃ��A���X�Њ��������Ƃ�����������B
���ɓ�����(����)�̉Ɛl�������ɂ́A����������܂����͕̂��؍�Ƃ������ŁA���̐܂ꂽ�Њ������ł����؍�̎Ђɕۊǂ���Ă���Ƃ����B
���]�̐l������Ύ��o�����Ƃ��ł��邻�����B
�܂������̕Њ����������l�̘b�ɂ��A�\�����̌����ł���A�u�Â̍�Œ��n�A����̕�͌F�̖сA����͍����V�����Ƃ����B
�(������)�������Ă���҂�����A�F�̖т��P�{�����ē��ɍڂ����ኂ�������Ƃ����B
555�l�Ԏ����l�N
2023/01/15(��) 00:04:03.76ID:wbs1odIZ �u���ƊՒk�v���㐙���M�ɂ��Ȏ������ْ̍�
�i�\�O�N�O��(�i�\�l�N�[�O���H)�A�㐙���M�P�Ռ����߉������{�̐_�O�ŊǗ̂ɔC����ꂽ�B
�֔��߉q�O�v������������A�����`�P���͑�a�������オ��g�ł������B
���̎��A�֓����B�̑喼�E����������������ɁA��t����(��t�M���͓����͗c���B���e�̐�t���x)�Ə��R����(���R����͐��܂��O�B�c���̏��R����)���Ȏ����������B
����������M����
�u��t�a�͊֓����B���m�̏�ł���ׂ��ł���B
�܂����R�a�͊֓����B���m�̉��ɂȂ�ׂ��ł͂Ȃ��B�v
�ƍٔ������Ƃ���A���͐Â܂����B
���M�͓��ӑ����̍˒m�ł���A�ƓV���̗_��ƂȂ����B
�i�\�O�N�O��(�i�\�l�N�[�O���H)�A�㐙���M�P�Ռ����߉������{�̐_�O�ŊǗ̂ɔC����ꂽ�B
�֔��߉q�O�v������������A�����`�P���͑�a�������オ��g�ł������B
���̎��A�֓����B�̑喼�E����������������ɁA��t����(��t�M���͓����͗c���B���e�̐�t���x)�Ə��R����(���R����͐��܂��O�B�c���̏��R����)���Ȏ����������B
����������M����
�u��t�a�͊֓����B���m�̏�ł���ׂ��ł���B
�܂����R�a�͊֓����B���m�̉��ɂȂ�ׂ��ł͂Ȃ��B�v
�ƍٔ������Ƃ���A���͐Â܂����B
���M�͓��ӑ����̍˒m�ł���A�ƓV���̗_��ƂȂ����B
556�l�Ԏ����l�N
2023/01/15(��) 02:02:07.90ID:9vgYVuhb �܂�c�ǂ��������́H
557�l�Ԏ����l�N
2023/01/15(��) 08:10:46.60ID:bAsuNukx �ׂɕ��������
558�l�Ԏ����l�N
2023/01/15(��) 08:38:50.88ID:FKjG8Ito https://ja.m.wikipedia.org/wiki/���R����
�i�\4�N�i1561�N�j�A���c����̐킢�ł͏㐙���M�ɖ������A�㐙�R�̈���Ƃ��ĕ�͐�ɎQ���Ă���B
�������A���M�̊֓��Ǘ̏A�C���̍ۂɐ�t���x�Ɋ֓������̎�ʂ̍���D��ꂽ���Ƃɕs����������ƌ����Ă���A����ɖk�����N�Ǝ�������߂Ɍ��M�̓{����A
���i�\5�N�i1562�N�j�ɍēx�֓����肵�����M�ɍU�߂��č����͍~�������B
�P�Ɍ��M���֓�����o����k���ɂȂт���������������Ȃ�����
�i�\4�N�i1561�N�j�A���c����̐킢�ł͏㐙���M�ɖ������A�㐙�R�̈���Ƃ��ĕ�͐�ɎQ���Ă���B
�������A���M�̊֓��Ǘ̏A�C���̍ۂɐ�t���x�Ɋ֓������̎�ʂ̍���D��ꂽ���Ƃɕs����������ƌ����Ă���A����ɖk�����N�Ǝ�������߂Ɍ��M�̓{����A
���i�\5�N�i1562�N�j�ɍēx�֓����肵�����M�ɍU�߂��č����͍~�������B
�P�Ɍ��M���֓�����o����k���ɂȂт���������������Ȃ�����
559�l�Ԏ����l�N
2023/01/15(��) 18:10:46.30ID:kfqxqRmx ��͓͂��Z�����
560�l�Ԏ����l�N
2023/01/15(��) 18:23:47.29ID:kfqxqRmx �c�ɂ̎O�͂��x�{�D���Ɩ��������Ƃ�������
1�N�ԓ˂����݂Ȃ���y�߂�Ƃ���SNS���ŎҌ������ۂ���
1�N�ԓ˂����݂Ȃ���y�߂�Ƃ���SNS���ŎҌ������ۂ���
561�l�Ԏ����l�N
2023/01/15(��) 21:54:06.89ID:k2gnhAsB �u����G�ځv���瓿��ƍN�a��
�ƍN���͓V���\��N�p�Џ\��\���(�ʐ��ł͓�\�Z���Őp�Ђ̓�)�A�O�͍�����̏�ɂČ�a�����ꂽ�B
�ٓ��ɏ\���������������Ƃ����B
�ƍN���ƌ��N�����ʂ��ꂽ�̂��A���N�͏���̓��S�v�����n��(�v���r��)�ɍĉł���A�O�j����������ꂽ�B
�ƍN���ɂ͈ꐶ�ꕠ(����������H)�̒j�q�̌Z�킪�Ȃ������̂ŁA�݂ȏ����̐��������Ē�ƂȂ�A�G�����̐l���ؐl�Ƃ��āA���̌Z��ƕς��ʗ���݂悤�ł������Ƃ����B
�_�i���̂��߂��ٓ��ɏ\�������Ƃ����`�����B
�Ȃ��ƍN���g���������蕶�ł͓V���\��N���܂�Ƃ��ĔN��𐔂��Ă���̂ŁA���ۂ͓ДN�ł͂Ȃ��K�N�������̂�������Ȃ�
�ƍN���͓V���\��N�p�Џ\��\���(�ʐ��ł͓�\�Z���Őp�Ђ̓�)�A�O�͍�����̏�ɂČ�a�����ꂽ�B
�ٓ��ɏ\���������������Ƃ����B
�ƍN���ƌ��N�����ʂ��ꂽ�̂��A���N�͏���̓��S�v�����n��(�v���r��)�ɍĉł���A�O�j����������ꂽ�B
�ƍN���ɂ͈ꐶ�ꕠ(����������H)�̒j�q�̌Z�킪�Ȃ������̂ŁA�݂ȏ����̐��������Ē�ƂȂ�A�G�����̐l���ؐl�Ƃ��āA���̌Z��ƕς��ʗ���݂悤�ł������Ƃ����B
�_�i���̂��߂��ٓ��ɏ\�������Ƃ����`�����B
�Ȃ��ƍN���g���������蕶�ł͓V���\��N���܂�Ƃ��ĔN��𐔂��Ă���̂ŁA���ۂ͓ДN�ł͂Ȃ��K�N�������̂�������Ȃ�
562�l�Ԏ����l�N
2023/01/15(��) 23:01:06.74ID:owfMtILr >>560
�ӔN�ɏx�{�ʼn߂�����������
�ӔN�ɏx�{�ʼn߂�����������
563�l�Ԏ����l�N
2023/01/16(��) 12:49:33.83ID:Z0LWwUBl �����V���@�ƍN���ɔ���@�É��s���j�����ق��傤�S�ʊJ��2023�N1��13��
https://www.chunichi.co.jp/article/616759
https://scmh.jp/
�V�K�Ɍ��݂��ꂽ�É��s���j�����فi���E�É��s�����������فj���O�����h�I�[�v�����܂��B
���Ԓ�����̓W��������܂��̂ŁA���Ђ��o�ł��������B
�ق̏�ݓW���̖ڋʂ́A����Ȗ��Ȓ����ʼn��l�̐����b�h�H�[�ɂ��쐻���ꂽ�A����ƍN�̍ŏ��ƍŌ�̍b�h�̕����i�ł��B
�Z�̒����߂ɍ���`����葡��ꂽ�Ƃ����u�g���Е����v�i�É���Ԑ_�Џ����j
���̐w�Œ��p�����Ƃ�����u�ɗ\�D�����Г��ۋ�i���S��j�v�i�v�\�R���Ƌ{�����j
���̐Ԃƍ��̐F�ʂ̓�ł��ˁB
http://www.shizuoka-bunkazai.jp/project/images/%E7%B4%85.JPG
https://static.chunichi.co.jp/image/article/size1/5/2/2/a/522acac13bc5790445fe0176db300055_1.jpg
�g���Е����̎����͈Жсi���ǂ����A���j�̑ސF�������A��������ڂ������ڂȂ�ł�����ǂ�
�����i�̑N�₩�ȍg�͌����Ȃ��̂ł��B��͂�ʐ^��茻�������Ă������������ł��ˁB
�x�͍��쎁�̔��ӎ���A�ƍN�ւ̊��҂����Ď���悤�ȋC�����܂����B
�������̋L�^�@
�i���́j�É��s���j�����{�݂̓W���Ɍ����āA�ƍN���̍b�h�����܂����I
http://www.shizuoka-bunkazai.jp/project/2018/06/post-4.html
http://www.shizuoka-bunkazai.jp/project/2019/04/201916.html
https://www.chunichi.co.jp/article/616759
https://scmh.jp/
�V�K�Ɍ��݂��ꂽ�É��s���j�����فi���E�É��s�����������فj���O�����h�I�[�v�����܂��B
���Ԓ�����̓W��������܂��̂ŁA���Ђ��o�ł��������B
�ق̏�ݓW���̖ڋʂ́A����Ȗ��Ȓ����ʼn��l�̐����b�h�H�[�ɂ��쐻���ꂽ�A����ƍN�̍ŏ��ƍŌ�̍b�h�̕����i�ł��B
�Z�̒����߂ɍ���`����葡��ꂽ�Ƃ����u�g���Е����v�i�É���Ԑ_�Џ����j
���̐w�Œ��p�����Ƃ�����u�ɗ\�D�����Г��ۋ�i���S��j�v�i�v�\�R���Ƌ{�����j
���̐Ԃƍ��̐F�ʂ̓�ł��ˁB
http://www.shizuoka-bunkazai.jp/project/images/%E7%B4%85.JPG
https://static.chunichi.co.jp/image/article/size1/5/2/2/a/522acac13bc5790445fe0176db300055_1.jpg
�g���Е����̎����͈Жсi���ǂ����A���j�̑ސF�������A��������ڂ������ڂȂ�ł�����ǂ�
�����i�̑N�₩�ȍg�͌����Ȃ��̂ł��B��͂�ʐ^��茻�������Ă������������ł��ˁB
�x�͍��쎁�̔��ӎ���A�ƍN�ւ̊��҂����Ď���悤�ȋC�����܂����B
�������̋L�^�@
�i���́j�É��s���j�����{�݂̓W���Ɍ����āA�ƍN���̍b�h�����܂����I
http://www.shizuoka-bunkazai.jp/project/2018/06/post-4.html
http://www.shizuoka-bunkazai.jp/project/2019/04/201916.html
564�l�Ԏ����l�N
2023/01/16(��) 12:51:27.53ID:Z0LWwUBl �m���Ǝs���̂��������͒n�����̕��ł��肢�ł��˂�
�C���t���ƓW���̐������]�X�Ɣ�p���̓z���g�ǂ��ł������B
�C���t���ƓW���̐������]�X�Ɣ�p���̓z���g�ǂ��ł������B
565�l�Ԏ����l�N
2023/01/16(��) 16:05:07.58ID:Z0LWwUBl >>554
https://bunka.nii.ac.jp/heritage/131010/_478275/131010_478275520837061644187_900.jpg
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/523895
���������̕Њ����́A����ꢗщ@���I�B���엊��ɗ`���ꂷ��ۂɎ��Q�����œ��蓹��Ƃ��ċI�B�Ƃ̂��̂ƂȂ�A
���݂͓������������قɏ�������Ă��܂��B
��ݓW���ł͂���܂��^�C�~���O�������܂����琥�����������B
https://bunka.nii.ac.jp/heritage/131010/_478275/131010_478275520837061644187_900.jpg
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/523895
���������̕Њ����́A����ꢗщ@���I�B���엊��ɗ`���ꂷ��ۂɎ��Q�����œ��蓹��Ƃ��ċI�B�Ƃ̂��̂ƂȂ�A
���݂͓������������قɏ�������Ă��܂��B
��ݓW���ł͂���܂��^�C�~���O�������܂����琥�����������B
566�l�Ԏ����l�N
2023/01/16(��) 20:49:29.60ID:PJyhHbaY �i�\�\��N�\�A�x�{�̍���a�قɉ������Y�E�q��i���j�j�Ɛ\���O�S�т̒m�s���́A����Ƃ�
�ߏK�A���g�̎��B�𐔑��̐l���W�߂ė����Ă������B
����c�M���͎b���U�߂����A�u���Y�E�q�傪���g�ɂĂ���قǂ̒�R������Ƃ́A�@���l���҂ł͂Ȃ��v
�Ǝv�������ꂽ
�u�畺�͓��₷�����ꏫ���ߓ�B���̎��Y�E�q��������u���A��藧�Ăĉ䂪��N��������ΑR��ׂ��B�v
�Ƃ��ču�a����A�������Y�E�q��͐M�����̌�튯�O�ƂȂ����B�����ČÎ�ł��鍡��a�����
��������邱�Ƃ̂Ȃ������l�����\�R�A���Y�E�q��ɉ�����A�܂��O�S�т��O��тɂȂ���A
���̎���艪�����Y�E�q������叫�Ɛ����ꂽ�B
�w�b�z�R�Ӂx
�ߏK�A���g�̎��B�𐔑��̐l���W�߂ė����Ă������B
����c�M���͎b���U�߂����A�u���Y�E�q�傪���g�ɂĂ���قǂ̒�R������Ƃ́A�@���l���҂ł͂Ȃ��v
�Ǝv�������ꂽ
�u�畺�͓��₷�����ꏫ���ߓ�B���̎��Y�E�q��������u���A��藧�Ăĉ䂪��N��������ΑR��ׂ��B�v
�Ƃ��ču�a����A�������Y�E�q��͐M�����̌�튯�O�ƂȂ����B�����ČÎ�ł��鍡��a�����
��������邱�Ƃ̂Ȃ������l�����\�R�A���Y�E�q��ɉ�����A�܂��O�S�т��O��тɂȂ���A
���̎���艪�����Y�E�q������叫�Ɛ����ꂽ�B
�w�b�z�R�Ӂx
567�l�Ԏ����l�N
2023/01/16(��) 21:41:09.28ID:Dz3TdecJ �u���ƊՒk�v�̏��߂̘b�u�����̌�ƌ䑊���ɐ��ƂȂ鎖�v
�����l�͓V���\��(�\��)�p�ДN�\��\�Z���A����̏�ɂČ�a���B��ٓ��\���Ƃ����B
�䓶���͒|���Ə̂��ꂽ���A�V���\�O�N�O���̖�Ɍ䕃�E�����L�����̖���
�u�_�X�́@�i���������@�܂��邩�ȁ@���̂�����́@���|�̏h�v
�Ƃ����̂����̒Z���ɏ����A���ɂ����Ƃ���Ŗڂ��o�߂��Ƃ����B
�L�����͕s�v�c�Ɏv���A�O�͂̑�l�̖̏����\�ܐ��̏Z�E�E������ɖ��̘b�������Ƃ���A��l�������������Ă����B
�����ł���͒|���a����ɐ�����Ƃ����g�����낤�Ƃ������ƂŁA��j���̘A�̋��s���Ȃ��ꂽ�B
�܂��c���O�N(1598�N)�����A�����Ō����l�͋g��������ꂽ���߁A����ɐΐ��������{�Ɍw�ł�ꂽ�Ƃ����B
����Ɛ����\�l���ɁA�]�˂̎��䒉������g�҂�����A����ɂ���
�ĒÐ��E�q��(�ĒÐ���)�̍Ȃ������̖錩�����ɁA�����l�������{�Ɍ�Q�w���ꂽ�B
�����ĉG�X�q�̐_�l���}�ɒZ�������Č����l�ɍ����o���ĉ̂��r�Ƃ����B
�u����Ȃ�@�s�̉Ԃ��@�h�͂Ł@���̏��́@�����Όp�����v
���̎�����O�N�̂����Ɋփ����̍���œV�������ɂ��ꂽ�B
�܂��V���\�N(1582�N)�܌���\�����A���q���G���d���̊�Ă����߂ĊJ���������S�C�̏\���Ə\���ɂ����Ɣɐ��̋g��������Ƃ����B
�u�����Â��@���̏���@��������v��q���ɐ��̋g��
�u�Q�ɂ܂��Ђ́@���C�̗��v�]�˔ɐ��̒�
�����l�͓V���\��(�\��)�p�ДN�\��\�Z���A����̏�ɂČ�a���B��ٓ��\���Ƃ����B
�䓶���͒|���Ə̂��ꂽ���A�V���\�O�N�O���̖�Ɍ䕃�E�����L�����̖���
�u�_�X�́@�i���������@�܂��邩�ȁ@���̂�����́@���|�̏h�v
�Ƃ����̂����̒Z���ɏ����A���ɂ����Ƃ���Ŗڂ��o�߂��Ƃ����B
�L�����͕s�v�c�Ɏv���A�O�͂̑�l�̖̏����\�ܐ��̏Z�E�E������ɖ��̘b�������Ƃ���A��l�������������Ă����B
�����ł���͒|���a����ɐ�����Ƃ����g�����낤�Ƃ������ƂŁA��j���̘A�̋��s���Ȃ��ꂽ�B
�܂��c���O�N(1598�N)�����A�����Ō����l�͋g��������ꂽ���߁A����ɐΐ��������{�Ɍw�ł�ꂽ�Ƃ����B
����Ɛ����\�l���ɁA�]�˂̎��䒉������g�҂�����A����ɂ���
�ĒÐ��E�q��(�ĒÐ���)�̍Ȃ������̖錩�����ɁA�����l�������{�Ɍ�Q�w���ꂽ�B
�����ĉG�X�q�̐_�l���}�ɒZ�������Č����l�ɍ����o���ĉ̂��r�Ƃ����B
�u����Ȃ�@�s�̉Ԃ��@�h�͂Ł@���̏��́@�����Όp�����v
���̎�����O�N�̂����Ɋփ����̍���œV�������ɂ��ꂽ�B
�܂��V���\�N(1582�N)�܌���\�����A���q���G���d���̊�Ă����߂ĊJ���������S�C�̏\���Ə\���ɂ����Ɣɐ��̋g��������Ƃ����B
�u�����Â��@���̏���@��������v��q���ɐ��̋g��
�u�Q�ɂ܂��Ђ́@���C�̗��v�]�˔ɐ��̒�
568�l�Ԏ����l�N
2023/01/17(��) 22:06:13.58ID:an6A5pJj �u���ƊՒk�v����u����ƍN�A�ۛ��ɂ��Č��v
�����l�̌䌾�t�ɂ���
�u�����ۛ������Ƃ����A�����̂��̂͋U�ł���B
�܂��Ƃ��ۛ��Ƃ����͍̂��|�`�邪�Γc����(�Γc�O��)���ۛ������悤�Ȃ̂������̂��B
���������鏭��(����G�N)���ؐl�Ƃ��č��a�R�ɑ����鎞�A���|��
�u�����Ŏ����Ƃ��Ƃ����҂�����Ή�炪����ƂȂ�v
�ƌ����Đl�����o���đҋ@���Ă��������v
�u�x�͓y�Y�v�ɂ́u���|�`��͗��V�Ȃ���́v�Ƃ��Ăقړ����b�����邪�A
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-11433.html
���V�Ȃ鍲�|�`��
�u���V�v�Ƃ͂������u�ۛ��v���Ɠ���̐l���ɑ��Ă����A�ƂȂ��ĈӖ����قȂ�C������
�����l�̌䌾�t�ɂ���
�u�����ۛ������Ƃ����A�����̂��̂͋U�ł���B
�܂��Ƃ��ۛ��Ƃ����͍̂��|�`�邪�Γc����(�Γc�O��)���ۛ������悤�Ȃ̂������̂��B
���������鏭��(����G�N)���ؐl�Ƃ��č��a�R�ɑ����鎞�A���|��
�u�����Ŏ����Ƃ��Ƃ����҂�����Ή�炪����ƂȂ�v
�ƌ����Đl�����o���đҋ@���Ă��������v
�u�x�͓y�Y�v�ɂ́u���|�`��͗��V�Ȃ���́v�Ƃ��Ăقړ����b�����邪�A
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-11433.html
���V�Ȃ鍲�|�`��
�u���V�v�Ƃ͂������u�ۛ��v���Ɠ���̐l���ɑ��Ă����A�ƂȂ��ĈӖ����قȂ�C������
569�l�Ԏ����l�N
2023/01/18(��) 20:24:02.20ID:/Jl3ViJy �u���ƊՒk�v�ɂ́A����ۛ��̘b�̑O�ɏG���̗��V�̘b�ɉƍN�����M��ʂ��ċꌾ��悵���b���������B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-4879.html
����G���u���{�l�̉R�A�����̉R�v
(�̏o�Ă������̘b�ł́u�R�v�Ƃ���Ă邪�u���ƊՒk�v�ł́u�����������Ă��v�ƂȂ��Ă���)
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-4879.html
����G���u���{�l�̉R�A�����̉R�v
(�̏o�Ă������̘b�ł́u�R�v�Ƃ���Ă邪�u���ƊՒk�v�ł́u�����������Ă��v�ƂȂ��Ă���)
570�l�Ԏ����l�N
2023/01/18(��) 20:25:40.76ID:/Jl3ViJy �u���ƊՒk�v����ʒ����Y��Y�̕����ɂ���
�����l�����������ɂ�
�ʒ����Y��Y�͋�C(����)�ł͂��邪���ł͊Ⴊ������قǂ̓���������B
�V���\�O�N(1585�N)�̏�c�̏�U�߂̎��A���䍶�q���(���䒉��)�������������B
���Y��Y�̌Z�̏�a��(�鏹��)���u�y�X�����U�镑�����v�Ƃ��������Ƃ���A
���Y��Y�́u���̏㐙���M�ł��畨�����Ȃ������B
�܂����M�����̂悤�ȑ�g�ł���Ε����ł͂Ȃ������ƌ����ׂ����낤�B
�����l�Y���q��(��������)���炪�Ȃ��̂��܂��Ƃ̕����ł���B�v
�ƌ������������B�\���ׂ��i���ł���B
�����l�����������ɂ�
�ʒ����Y��Y�͋�C(����)�ł͂��邪���ł͊Ⴊ������قǂ̓���������B
�V���\�O�N(1585�N)�̏�c�̏�U�߂̎��A���䍶�q���(���䒉��)�������������B
���Y��Y�̌Z�̏�a��(�鏹��)���u�y�X�����U�镑�����v�Ƃ��������Ƃ���A
���Y��Y�́u���̏㐙���M�ł��畨�����Ȃ������B
�܂����M�����̂悤�ȑ�g�ł���Ε����ł͂Ȃ������ƌ����ׂ����낤�B
�����l�Y���q��(��������)���炪�Ȃ��̂��܂��Ƃ̕����ł���B�v
�ƌ������������B�\���ׂ��i���ł���B
571�l�Ԏ����l�N
2023/01/21(�y) 00:18:13.57ID:pg+Ii9kW �u���ƊՒk�v����u�^�c���{���v(���c����̏�c���{���Ƃ͕�)
�u�ԏ����⎵�{���v�͐M���L�ɁA�u�˃��x�̎��{���v�͑��}�L�ɂ���B
�u�^�c���{���v�͉��Ƃ��L�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ����A���ł�����ĕ������悤�Ƃ���V�l���������̂�
���鎞�A�O�䎛�̍��ω��̕��Ԃ֏��A�џ���~���A�����Ȃ���V�l�̘b�����̂ł����ɏ�������B
���߂̐^�c�w(��c����)�͓V���\�O�N(1585�N)�[�����̂��Ƃł������B
����̍���ŁA���������̐F�H�̏��������������������B(�u�M�B��c�R�L�v�ɂ��ΐ펀)
����\���ێR(�ێq)�̏鉺�։������V�������̈�肪�悭�����A�Ɛl�̏������ܘY����ԑ��A���̂ق����R�V�Z�A�������A�ߓ������A�����v�ܘY�A���R�v���A�J���������悭�������B
�����l��艪�����V���肩�Ɛl���l�ɂ��䊴�������ꂽ�B
���̓��A�������͑����̍����Ƃ��ꂽ�B
�������ܘY�́u��ԑ������킹�邱�ƁA�疜��g�̊o��A�����ɔ�����o�Ă���v�Ƃ������䊴��ł������B
���̏������ܘY�͏x�͏O�ł���A����͒��̌��j�A�������ܘY�͋G�H�̌���Ƃ����B
�u�ԏ����⎵�{���v�͐M���L�ɁA�u�˃��x�̎��{���v�͑��}�L�ɂ���B
�u�^�c���{���v�͉��Ƃ��L�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ����A���ł�����ĕ������悤�Ƃ���V�l���������̂�
���鎞�A�O�䎛�̍��ω��̕��Ԃ֏��A�џ���~���A�����Ȃ���V�l�̘b�����̂ł����ɏ�������B
���߂̐^�c�w(��c����)�͓V���\�O�N(1585�N)�[�����̂��Ƃł������B
����̍���ŁA���������̐F�H�̏��������������������B(�u�M�B��c�R�L�v�ɂ��ΐ펀)
����\���ێR(�ێq)�̏鉺�։������V�������̈�肪�悭�����A�Ɛl�̏������ܘY����ԑ��A���̂ق����R�V�Z�A�������A�ߓ������A�����v�ܘY�A���R�v���A�J���������悭�������B
�����l��艪�����V���肩�Ɛl���l�ɂ��䊴�������ꂽ�B
���̓��A�������͑����̍����Ƃ��ꂽ�B
�������ܘY�́u��ԑ������킹�邱�ƁA�疜��g�̊o��A�����ɔ�����o�Ă���v�Ƃ������䊴��ł������B
���̏������ܘY�͏x�͏O�ł���A����͒��̌��j�A�������ܘY�͋G�H�̌���Ƃ����B
572�l�Ԏ����l�N
2023/01/22(��) 09:37:27.78ID:5cYmx69V ������̎��{���Ƃ��E�E�E�E�E
573�l�Ԏ����l�N
2023/01/22(��) 18:27:59.49ID:gdIY12hr �u�ǂ�����ƍN�v��X����@�u�C�V�������v�ōg���o���_���H�@�u����ɓq���Ă���v
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f52f893b94ca2e020c1575907d8d39e9e91900f
��X�͎��䒉�������ӂƂ��Ă������u�C�V�������v����������Ŕ�I�������Ƃɂ���
�u2�J�����炢�O����S�̏��������ė��K�����v�Ɛ����B���̏�Łu�ǂ��܂ʼn���|�Ƃ���
�����������邩�c�B�J�b�g����Ă���Ƃ�������邪�A�q���Ă���B���N�̍g����
����ŏo�悤�Ǝv���Ă���v�Ə�k�܂���ɘb�����B
�������ɊC�V�������̏o�ԑ�����Ȃ܂������Ȃ̂ɁE�E
���̂�����͗x��Ȃ��݂����Ȃ̂ɃC�x���g�ŋ��v����邽�肷��낤���H
���䒉���̖��Z�C�V������
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-8634.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f52f893b94ca2e020c1575907d8d39e9e91900f
��X�͎��䒉�������ӂƂ��Ă������u�C�V�������v����������Ŕ�I�������Ƃɂ���
�u2�J�����炢�O����S�̏��������ė��K�����v�Ɛ����B���̏�Łu�ǂ��܂ʼn���|�Ƃ���
�����������邩�c�B�J�b�g����Ă���Ƃ�������邪�A�q���Ă���B���N�̍g����
����ŏo�悤�Ǝv���Ă���v�Ə�k�܂���ɘb�����B
�������ɊC�V�������̏o�ԑ�����Ȃ܂������Ȃ̂ɁE�E
���̂�����͗x��Ȃ��݂����Ȃ̂ɃC�x���g�ŋ��v����邽�肷��낤���H
���䒉���̖��Z�C�V������
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-8634.html
574�l�Ԏ����l�N
2023/01/22(��) 20:01:05.47ID:WTuh0zul �܂���͊�n�O���N���Ă�̂�
575�l�Ԏ����l�N
2023/01/22(��) 21:45:38.06ID:vbYgp9gn >>571�̑���
�u���ƊՒk�v����u�^�c���{���v(���c����̏�c���{��)
�܂���̐^�c�w(���c����)�͌c���ܔN(1600)�N�㌎�Z���ł������B
�䓿�@�G�������䔭�����A�^�c���K�����U�߂ɂȂ�ꂽ���A��̖k�̖�͍��Ò��q�傪�����Ă����B
����{�̐����q����l�Ŗ�ɖx�̐[���𑪂��Ă����Ƃ���A�钆����S�C�ʂ��J�̂��Ƃ��~�蒍���Ō����ꂽ�B
��̏\����̎w�������������ɂȂ�A�͒n�ɕ������B
����ȏ��Ɍ䖡���̏��I���E�q����Â��Ă���Ă���ƁA��傩��^�c�̍b����\�]������J���ĐE���I���l�ɓS�C��ł����A�S�C�����͂ꂽ�Ƃ���ő���˂����ĂĂ����B
�̏��҂̌ՎႪ�����������������ē�l�̌��ɍs�����Ƃ���A���I�͋��O�ӏ���������ē������ɂ��Ă����B
������������Ēn�ɕ����Ă����̂��A�Վ�̗͐������Ƃ��Ĉ����o�����B
�́u�Z�̏��I��ނ���v�Ɩ��������A�Վ�͕��𗧂Ăāu��l���̂Ăđ��l��ނ���҂�����܂��傤���v�Ɣw�����đދp�����B
�ՎႩ��w���ɂ��Ė��ꂽ��
�u�����킹�̎��ɗ��Ƃ��ꂽ�ƌ����邪�A���߂��킯�ɂ������܂��ȁv�ƌ�����
�Վ�́u�ދp���ɗ��Ƃ����̂ł���Ε����̗����x�ƂȂ�܂��傤���A�����킹�̎��ɗ��Ƃ����̂ł���Ζ��͂Ȃ��ł��傤�v�ƈ������������B
�u���ƊՒk�v����u�^�c���{���v(���c����̏�c���{��)
�܂���̐^�c�w(���c����)�͌c���ܔN(1600)�N�㌎�Z���ł������B
�䓿�@�G�������䔭�����A�^�c���K�����U�߂ɂȂ�ꂽ���A��̖k�̖�͍��Ò��q�傪�����Ă����B
����{�̐����q����l�Ŗ�ɖx�̐[���𑪂��Ă����Ƃ���A�钆����S�C�ʂ��J�̂��Ƃ��~�蒍���Ō����ꂽ�B
��̏\����̎w�������������ɂȂ�A�͒n�ɕ������B
����ȏ��Ɍ䖡���̏��I���E�q����Â��Ă���Ă���ƁA��傩��^�c�̍b����\�]������J���ĐE���I���l�ɓS�C��ł����A�S�C�����͂ꂽ�Ƃ���ő���˂����ĂĂ����B
�̏��҂̌ՎႪ�����������������ē�l�̌��ɍs�����Ƃ���A���I�͋��O�ӏ���������ē������ɂ��Ă����B
������������Ēn�ɕ����Ă����̂��A�Վ�̗͐������Ƃ��Ĉ����o�����B
�́u�Z�̏��I��ނ���v�Ɩ��������A�Վ�͕��𗧂Ăāu��l���̂Ăđ��l��ނ���҂�����܂��傤���v�Ɣw�����đދp�����B
�ՎႩ��w���ɂ��Ė��ꂽ��
�u�����킹�̎��ɗ��Ƃ��ꂽ�ƌ����邪�A���߂��킯�ɂ������܂��ȁv�ƌ�����
�Վ�́u�ދp���ɗ��Ƃ����̂ł���Ε����̗����x�ƂȂ�܂��傤���A�����킹�̎��ɗ��Ƃ����̂ł���Ζ��͂Ȃ��ł��傤�v�ƈ������������B
576�l�Ԏ����l�N
2023/01/22(��) 21:48:58.23ID:vbYgp9gn ����͎�n�߂ɑ�����̓�l���E���A�����������A�Ƃ������ƂŐ^�c���̎R�{���E�q��ƈ˓c������������l�Œǂ��ł��������ɂ����B
���l�����藣�ꂽ��̏�ɗ����Ē�@�����Ƃ���A�䓿��(����G��)�̌���{�̕��ҁA��A�O�\�R���R�n�̕@����ׂĂ���Ă����B
�R�{�E�˓c���������{�O�́A�u���A���������Ă������ɗ���^�c���̍֓�����v�Ƃ��̒�q��l���A�����ȁv�Ƃ������Ă������B
�Ȃ��ł����쎟�Y�E�q��(���쒉��)�A�ґ��Y��(�ҋv�g)���ЂƑ���ɋ삯����Ă������߁A�֓�����v�͏�ɓ����A�����B
����ƒ҂͂����Œ�ۂ֍s���A�˓c�E�R�{��ɂ��邱�Ƃɂ����B
�������Ē�̏�Ɖ��ł��ꂼ�ꑄ��˂����킹���B
�����֒��q���\�Y(���q�鐳)�A���R���Z(���R�Ǝ�)�A�˓c����(�˓c����)�A���ڈꍶ�q��(���ڈҖ�)�A���c�r�l�Y�A�֓��v�E�q��(�֓��M�g)�������đ������킹���B
(���c�r�l�Y�ȊO�̌ܐl�Ə���E�҂���c���{��)
�������Ĉ˓c�����͎��ŕ��킵�����|�ꕚ�����B
����ƒ҂��˓c�̎����낤�Ƃ����Ƃ���A�R�{���E�q�傪��l��ł������A�˓c�����ɒS���ŏ钆�Ɉ����Ԃ����B
����Ⴂ�ɏ钆����삯�o���Ă����^�c���O�\�]�l�ɑ��A���c�r�l�Y�͓S�C��e��茂���������B
�������̐^�c���Ђ�Ƃ�����A���R�E���q�E����E�ҁE���ځE�˓c�E�֓������������Ēnj����悤�Ƃ������߁A�^�c�͂��Ƃ��Ƃ���Ɉ����Ԃ����B
�����Ŗ{�����M�͏���U�߂Ă���̔�Q�������邾�����Ɖ��m�����B
(���̂��Ƃ͑��c����ɂ��Ă̋L�q)
���l�����藣�ꂽ��̏�ɗ����Ē�@�����Ƃ���A�䓿��(����G��)�̌���{�̕��ҁA��A�O�\�R���R�n�̕@����ׂĂ���Ă����B
�R�{�E�˓c���������{�O�́A�u���A���������Ă������ɗ���^�c���̍֓�����v�Ƃ��̒�q��l���A�����ȁv�Ƃ������Ă������B
�Ȃ��ł����쎟�Y�E�q��(���쒉��)�A�ґ��Y��(�ҋv�g)���ЂƑ���ɋ삯����Ă������߁A�֓�����v�͏�ɓ����A�����B
����ƒ҂͂����Œ�ۂ֍s���A�˓c�E�R�{��ɂ��邱�Ƃɂ����B
�������Ē�̏�Ɖ��ł��ꂼ�ꑄ��˂����킹���B
�����֒��q���\�Y(���q�鐳)�A���R���Z(���R�Ǝ�)�A�˓c����(�˓c����)�A���ڈꍶ�q��(���ڈҖ�)�A���c�r�l�Y�A�֓��v�E�q��(�֓��M�g)�������đ������킹���B
(���c�r�l�Y�ȊO�̌ܐl�Ə���E�҂���c���{��)
�������Ĉ˓c�����͎��ŕ��킵�����|�ꕚ�����B
����ƒ҂��˓c�̎����낤�Ƃ����Ƃ���A�R�{���E�q�傪��l��ł������A�˓c�����ɒS���ŏ钆�Ɉ����Ԃ����B
����Ⴂ�ɏ钆����삯�o���Ă����^�c���O�\�]�l�ɑ��A���c�r�l�Y�͓S�C��e��茂���������B
�������̐^�c���Ђ�Ƃ�����A���R�E���q�E����E�ҁE���ځE�˓c�E�֓������������Ēnj����悤�Ƃ������߁A�^�c�͂��Ƃ��Ƃ���Ɉ����Ԃ����B
�����Ŗ{�����M�͏���U�߂Ă���̔�Q�������邾�����Ɖ��m�����B
(���̂��Ƃ͑��c����ɂ��Ă̋L�q)
577�l�Ԏ����l�N
2023/01/23(��) 09:23:28.93ID:tVZXFX/4 >>573
����������ځ����������ς�[] 2010/01/23(�y) 21:00:26 ID:Le1hu93a0
������̑��ۂ͉̕���̉��ڂɂȂ��Ă��邭�炢�L���Șb�����A���j��̏o�����Ƃ��Ắu�j���v�ƌ������邱�Ƃ��ł�����̂ł͂Ȃ��A
���u��b�v�ƌĂԂׂ����̂ł��傤�B���������x�莩�̂͒m���Ă�����������Ȃ����A�C�V�������̘b�������悤�Ɂu��b�v�ƌ����ׂ�����
���v���܂��B�Ƃ̂��Ƃł����B
�����A���ꂩ��A�x��Ȃ������ł��i��
�C�V�������͌�����̂��̌��t�ɐs�����
�j���ƈ�b�̈Ⴂ���Ă����̂��̂ɖ����܂���
����������ځ����������ς�[] 2010/01/23(�y) 21:00:26 ID:Le1hu93a0
������̑��ۂ͉̕���̉��ڂɂȂ��Ă��邭�炢�L���Șb�����A���j��̏o�����Ƃ��Ắu�j���v�ƌ������邱�Ƃ��ł�����̂ł͂Ȃ��A
���u��b�v�ƌĂԂׂ����̂ł��傤�B���������x�莩�̂͒m���Ă�����������Ȃ����A�C�V�������̘b�������悤�Ɂu��b�v�ƌ����ׂ�����
���v���܂��B�Ƃ̂��Ƃł����B
�����A���ꂩ��A�x��Ȃ������ł��i��
�C�V�������͌�����̂��̌��t�ɐs�����
�j���ƈ�b�̈Ⴂ���Ă����̂��̂ɖ����܂���
578�l�Ԏ����l�N
2023/01/23(��) 11:54:54.51ID:zgNZWEvs >>577
�j���Ƒn��ȁA�����疳�m���Č������
�j���Ƒn��ȁA�����疳�m���Č������
579�l�Ԏ����l�N
2023/01/23(��) 12:19:46.76ID:OYjTP/Ci ����Ƃ̌䓖��m�Ă��Ƃ́A�ŒႾ��
580�l�Ԏ����l�N
2023/01/23(��) 12:57:39.65ID:bxaU7vVB ����ȂƂ���Ɏj���~�Ƃ�
581�l�Ԏ����l�N
2023/01/23(��) 18:07:40.17ID:zgNZWEvs >>579
�_�N�̃N�\�ł��d���Ă��
�_�N�̃N�\�ł��d���Ă��
582�l�Ԏ����l�N
2023/01/23(��) 18:20:57.65ID:XwedlS8z �j���~�����ǂ����y����ł��
�Ƃ͂����j���~�Ȃ���ŏ������ނƂ��͎j���̉\�������長�������Ƃ������ɂ��Ă邯��
���т������͂ǂ��Ȃ��
�Ƃ͂����j���~�Ȃ���ŏ������ނƂ��͎j���̉\�������長�������Ƃ������ɂ��Ă邯��
���т������͂ǂ��Ȃ��
583�l�Ԏ����l�N
2023/01/23(��) 18:38:48.02ID:XwedlS8z ������ƌ��������炷���ꎟ�j�����łĂ�����
�c�C�b�^�[�̃p�N��T�C�g������
ttps://togetter.com/li/1178178
��A������V���A��B���l�E�ƍN�x�T����~����ҁA�����A�e�䕑�A���I���䗐���A���䍶�q��щH�ߕ��A�C�V�������V�����m�j��V�ԁA���x���䏊�]��A��l�V�o�����ʁA�S�N�ߗ��Җ������V�R�A���{���㉺�������j��A�ȏ�
�V��14�N�̓���k��ʉ��`���鐼�R�{�厛�����̈ꕔ
���䂪�C�V�������̖��l���Ă͎̂j���ƍl���Ă悩�낤
�ꎟ�j���ɖ��L���ꂽ�������P�[�X
�c�C�b�^�[�̃p�N��T�C�g������
ttps://togetter.com/li/1178178
��A������V���A��B���l�E�ƍN�x�T����~����ҁA�����A�e�䕑�A���I���䗐���A���䍶�q��щH�ߕ��A�C�V�������V�����m�j��V�ԁA���x���䏊�]��A��l�V�o�����ʁA�S�N�ߗ��Җ������V�R�A���{���㉺�������j��A�ȏ�
�V��14�N�̓���k��ʉ��`���鐼�R�{�厛�����̈ꕔ
���䂪�C�V�������̖��l���Ă͎̂j���ƍl���Ă悩�낤
�ꎟ�j���ɖ��L���ꂽ�������P�[�X
584�l�Ԏ����l�N
2023/01/23(��) 18:51:17.84ID:XwedlS8z ���A�f����������Ȃ���œ��L�Ƃ�����ꎟ�j�����Ă��Ƃ�
585�l�Ԏ����l�N
2023/01/24(��) 21:32:04.96ID:bZTeiPzH �߂̔N�i���T���N�j�̋Ɍ��ɕ��c�M�����́A�n����Z�A�����C���A�R�p�O�Y���q�A����e���A
���R�c���q�сA�����l���A�Օ��吆��̎��l�������āA�e���ɂ��̂悤�ɋ��ɂȂ����B
�u�M���̎g���ł���D�c�|���i�����j�́A�ƍN�̐l���i�����N�r�j���b�{���瓦�S�������ɂ���
�ǂ̂悤�ɐ\���Ă������B�v
���⏳��
�u�|�����\�����Ƃɂ��ƁA
�w�M����������A�ƍN���͂��Ȃ����Ƃ��ƍl����ł��傤���A��߂Ă���͉ƍN���m��Ȃ����ł��傤�B
���O�Y�i�����N�r�j���s�o��ł��������߂ɁA���̂悤�Ȏ��ԂɂȂ����̂��Ɛ��ʂ������܂��B
�ł��̂ŁA�₪�Ė��A��߂ĕʂ̐l�����A�ƍN��蕐�c�ɐi�シ��ł��傤���A�������Ȃ������Ƃ��Ă��A
�M���͐M�����Ɍ䖳�����\���グ��悤�Ȏ��͏������L��܂���̂ŁA�Ȍ�͐M��������A
�ɒ�Ȃ�Ƃ��q���Ȃ�Ƃ��A�i��v�����ł��傤�B�x
���̂悤�ɁA�����ɂ��ًc�����悤�ɁA�D�c�|���͐��������܂����B�v
�M�����͂������
�u�M���͋��N�ߍ]��{�ɂ����Ē��q�`�i�Ƒΐw���i�u��̐w�j�A���͓��N�������V�����x�z�d��ɂ��A
��X�Ƃ��Ă͐M���ƒ��̎҂�[�����Ȃ��A�|��̋`��\�X���Ȃ���A�e���ɑ��Ė{����\���悤��
���͖������낤�B���l�A�吆��ɑ��Ă��\���Ȃ����낤�B��X�ł����Ă��A�e�X�̔튯���Ɍ�����悤��
���͂Ȃ��������H�v
��������l�A�吆�������u���炸��B�����ĐM���̎g���Ɍ��炸�A�ǂ�����̎g�ҏO���A�����ɎQ����
���ҎG�k�Ȃǂ͏I�ɂ������܂���B�v�Ɛ\���グ�����A�n����Z�����̂悤�ɐ\����
�u���B���R�̏��ł������Óc�����i�D�c�M���j�́A�M���̎o���ł������A�M���ɕ����Ēǂ��o����A
������S�X�������A�O�N�O��蓌���֎Q��A��ɒ�̈���E�q�呾�v�i�M���j�a�̂͂Ȃ��̏O�ɐ���A
���R�N�ւƏ̂��Ă���܂��B���̐l�̌�������ɂ��ƁA�M���͕��ӌ`�`�ɂ��āA���e�����i�M�G�j��
�������^�����A�n�ł������֓��R���i���O�j�́A�|��`�`���d��ƁB�����Ă��������i����Ă��炵���Ȃ��j
�悤�Ɍ����Ă��A���ۂ͎�̊O���߂����������Ă���A���̂悤�ɍ����v���܂����B�v
�M�����͋��ɂȂ���
�u�M���̕��E�e�����͔����������߂邱�Ƃ��o�����A���g�̂ɍ���`���̊����ƂȂ�x�{�ɏo�d�����B
�֓��R��́A��ɉ��𗊂܂�Ă����y��i���|�j�a�S�X�̌�A���Z�ꍑ�̎�ƂȂ�A�z�O�̕��܂ŗ��߁A
�R��̒��q�E�`���̑�ɂ͉z�O��蒩�q��Z�V�Ɛ\���]��V�����Z�l���Ɏ��قǂł���A�֓��̋|���
�e�����Ɣ�ׂ�ƁA�͂邩�ɂ��̋|��̈ʂ͏�ł���B�M�����֓��R��̋|��̉ƕ��������ꂽ�͖̂ނ��ł���B
�������A�R��̑��ł��间����M���͉����U�炵�A���Z���𐔑��������̂ł��邩��A���e���̑�ɂ͏��ƒ�
�ł���̂ɁA���͂ǂ����Ă��傫�ȉƒ��̉ƕ���^������̂ł���A���̂�����M���O����̂̎��́A
�֓��R��̂���Ă����悤�ɒv���̂��B����͈Ӑ}�I�ɐ^���悤�Ƃ��Ȃ��Ă��A�Ⴆ�Ώ�y���֍s���A
���R�ƔO����\����������S���N���̂Ɠ������ł���B�v
�܂��M�����͔n����Z�ɖ��ꂽ
�u�M���̋|����܂��Ă���Ƃ́A�ǂ����������������Ɍ��R�N�ւ͐\���Ă���̂��B�v
�n���
�u���鎞�A���R�������f���A�����݁X�֊F�Ԃ������A�M���͎���̐l�����ȂČ��R�̏h���܂ŗ������܂����B
�������N�֕��\���l���������ނ��ǂ��o���A���̌�M������ǔ����A��������ꗢ���܂�ǂ������̂́A
�M�����͕Ԃ��Ă���Ɛ킨���Ƃ����A�����U�����悤�Ȍ`�ƂȂ�܂����B�������������͊F�M���ɍ~�Q�d��A
���R��l�ŐM���ɏ|�˂����Ƃ��͍��㐬���Ȃ������߁A�I�ɏ��n���S�l�d��܂����B
�M���̎���̐l�����A�\���R�ɒǂ��o�����Ƃ������Ƃ͖����ł��傤���A�����ꍑ���F�M����
�]����́A���R�����Ȃ���ɓ�����̂ł���Ɣ��f�������߁A���ʂ��ēN�ւ����قNj��d�ɍU�߂Ȃ������A
�Ƃ���������A�u���肠��v�ƓN�ւ͕�������̂ł��B�v
�Ɛ\����
�w�b�z�R�Ӂx
���c�Ƃɂ�����M���̌R���ɂ��Ă̔F���ɂ���
���R�c���q�сA�����l���A�Օ��吆��̎��l�������āA�e���ɂ��̂悤�ɋ��ɂȂ����B
�u�M���̎g���ł���D�c�|���i�����j�́A�ƍN�̐l���i�����N�r�j���b�{���瓦�S�������ɂ���
�ǂ̂悤�ɐ\���Ă������B�v
���⏳��
�u�|�����\�����Ƃɂ��ƁA
�w�M����������A�ƍN���͂��Ȃ����Ƃ��ƍl����ł��傤���A��߂Ă���͉ƍN���m��Ȃ����ł��傤�B
���O�Y�i�����N�r�j���s�o��ł��������߂ɁA���̂悤�Ȏ��ԂɂȂ����̂��Ɛ��ʂ������܂��B
�ł��̂ŁA�₪�Ė��A��߂ĕʂ̐l�����A�ƍN��蕐�c�ɐi�シ��ł��傤���A�������Ȃ������Ƃ��Ă��A
�M���͐M�����Ɍ䖳�����\���グ��悤�Ȏ��͏������L��܂���̂ŁA�Ȍ�͐M��������A
�ɒ�Ȃ�Ƃ��q���Ȃ�Ƃ��A�i��v�����ł��傤�B�x
���̂悤�ɁA�����ɂ��ًc�����悤�ɁA�D�c�|���͐��������܂����B�v
�M�����͂������
�u�M���͋��N�ߍ]��{�ɂ����Ē��q�`�i�Ƒΐw���i�u��̐w�j�A���͓��N�������V�����x�z�d��ɂ��A
��X�Ƃ��Ă͐M���ƒ��̎҂�[�����Ȃ��A�|��̋`��\�X���Ȃ���A�e���ɑ��Ė{����\���悤��
���͖������낤�B���l�A�吆��ɑ��Ă��\���Ȃ����낤�B��X�ł����Ă��A�e�X�̔튯���Ɍ�����悤��
���͂Ȃ��������H�v
��������l�A�吆�������u���炸��B�����ĐM���̎g���Ɍ��炸�A�ǂ�����̎g�ҏO���A�����ɎQ����
���ҎG�k�Ȃǂ͏I�ɂ������܂���B�v�Ɛ\���グ�����A�n����Z�����̂悤�ɐ\����
�u���B���R�̏��ł������Óc�����i�D�c�M���j�́A�M���̎o���ł������A�M���ɕ����Ēǂ��o����A
������S�X�������A�O�N�O��蓌���֎Q��A��ɒ�̈���E�q�呾�v�i�M���j�a�̂͂Ȃ��̏O�ɐ���A
���R�N�ւƏ̂��Ă���܂��B���̐l�̌�������ɂ��ƁA�M���͕��ӌ`�`�ɂ��āA���e�����i�M�G�j��
�������^�����A�n�ł������֓��R���i���O�j�́A�|��`�`���d��ƁB�����Ă��������i����Ă��炵���Ȃ��j
�悤�Ɍ����Ă��A���ۂ͎�̊O���߂����������Ă���A���̂悤�ɍ����v���܂����B�v
�M�����͋��ɂȂ���
�u�M���̕��E�e�����͔����������߂邱�Ƃ��o�����A���g�̂ɍ���`���̊����ƂȂ�x�{�ɏo�d�����B
�֓��R��́A��ɉ��𗊂܂�Ă����y��i���|�j�a�S�X�̌�A���Z�ꍑ�̎�ƂȂ�A�z�O�̕��܂ŗ��߁A
�R��̒��q�E�`���̑�ɂ͉z�O��蒩�q��Z�V�Ɛ\���]��V�����Z�l���Ɏ��قǂł���A�֓��̋|���
�e�����Ɣ�ׂ�ƁA�͂邩�ɂ��̋|��̈ʂ͏�ł���B�M�����֓��R��̋|��̉ƕ��������ꂽ�͖̂ނ��ł���B
�������A�R��̑��ł��间����M���͉����U�炵�A���Z���𐔑��������̂ł��邩��A���e���̑�ɂ͏��ƒ�
�ł���̂ɁA���͂ǂ����Ă��傫�ȉƒ��̉ƕ���^������̂ł���A���̂�����M���O����̂̎��́A
�֓��R��̂���Ă����悤�ɒv���̂��B����͈Ӑ}�I�ɐ^���悤�Ƃ��Ȃ��Ă��A�Ⴆ�Ώ�y���֍s���A
���R�ƔO����\����������S���N���̂Ɠ������ł���B�v
�܂��M�����͔n����Z�ɖ��ꂽ
�u�M���̋|����܂��Ă���Ƃ́A�ǂ����������������Ɍ��R�N�ւ͐\���Ă���̂��B�v
�n���
�u���鎞�A���R�������f���A�����݁X�֊F�Ԃ������A�M���͎���̐l�����ȂČ��R�̏h���܂ŗ������܂����B
�������N�֕��\���l���������ނ��ǂ��o���A���̌�M������ǔ����A��������ꗢ���܂�ǂ������̂́A
�M�����͕Ԃ��Ă���Ɛ킨���Ƃ����A�����U�����悤�Ȍ`�ƂȂ�܂����B�������������͊F�M���ɍ~�Q�d��A
���R��l�ŐM���ɏ|�˂����Ƃ��͍��㐬���Ȃ������߁A�I�ɏ��n���S�l�d��܂����B
�M���̎���̐l�����A�\���R�ɒǂ��o�����Ƃ������Ƃ͖����ł��傤���A�����ꍑ���F�M����
�]����́A���R�����Ȃ���ɓ�����̂ł���Ɣ��f�������߁A���ʂ��ēN�ւ����قNj��d�ɍU�߂Ȃ������A
�Ƃ���������A�u���肠��v�ƓN�ւ͕�������̂ł��B�v
�Ɛ\����
�w�b�z�R�Ӂx
���c�Ƃɂ�����M���̌R���ɂ��Ă̔F���ɂ���
586�l�Ԏ����l�N
2023/01/25(��) 00:08:10.64ID:AqQAHLQG �����Ƃ����̂��������������ɂ��݂��
587�l�Ԏ����l�N
2023/01/26(��) 21:57:02.77ID:NCUki9En ����R�ߋ����̎��䒉�������̋L���ɋL���ꂽ�A�k���ƂƂ̍����̏�ʂł́�������
ttps://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/T38/1596/17-3-1/10/0030?m=all&s=0019&n=20
�匠�������Ƒy�͌��ɂĎQ�W�����܂ЁA��������̂Ƃ��A����ӂ�(����ނ�)�ɁA�(������)�����А���܂�(����)�A�����x�̂��܂�A�ꕶ���̍�����@��������(����)
�����݂����C�V�����͂Ƃ������A�j���������ƍl���Ă悩��
ttps://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/T38/1596/17-3-1/10/0030?m=all&s=0019&n=20
�匠�������Ƒy�͌��ɂĎQ�W�����܂ЁA��������̂Ƃ��A����ӂ�(����ނ�)�ɁA�(������)�����А���܂�(����)�A�����x�̂��܂�A�ꕶ���̍�����@��������(����)
�����݂����C�V�����͂Ƃ������A�j���������ƍl���Ă悩��
588�l�Ԏ����l�N
2023/01/28(�y) 09:20:00.34ID:v90iFr0W �������ꂪ����
https://www.yamagata-np.jp/news/202301/24/img_2023012400647.jpg
https://www.yamagata-np.jp/news/202301/24/kj_2023012400631.php?utm_content=uzou_5&utm_source=uzou
�c���A������đ�𑖂�@���b�s���O�o�X�A���傤24������^�s
�R�`�V��2023/1/24
�đ�ŔӔN���߂������퍑�����E�O�c�c���̖���L�����N�^�[��`�������b�s���O�o�X�̈����n������23���A
�s�����O�ōs��ꂽ�B24���ɉ^�s���J�n���A�c���䂩��̓��X�P���������铯�s�����n��̏Z����̐����H����
�^�p�����ق��A�ό��U�q�ɂ�����B
�����n����o�R���A�s�����ƕđ�X�L�[������Ԏs���o�X�������̐V�ԗ��ƂȂ�B�ԗ��X�V���@�ɗU�q��
�N���܂ɂ��悤�ƁA�����ʂɑO�c�c�����͂��߁A�ɒB���@�A���]�����Ȃǖ���u�Ԃ̌c���v�ɓo�ꂷ��
�đ�䂩��̐퍑�������`�����B1��17�֒�10�ւŎg���A�C�x���g�Ȃǂɂ��o�ꂷ��\�肾�B���Ɣ�͖�270���~�ŁA
���̂ق��ɁA������Ǘ�����R�A�~�b�N�X�i�����j�ւ̎g�p����������B
https://www.yamagata-np.jp/news/202301/24/img_2023012400647.jpg
https://www.yamagata-np.jp/news/202301/24/kj_2023012400631.php?utm_content=uzou_5&utm_source=uzou
�c���A������đ�𑖂�@���b�s���O�o�X�A���傤24������^�s
�R�`�V��2023/1/24
�đ�ŔӔN���߂������퍑�����E�O�c�c���̖���L�����N�^�[��`�������b�s���O�o�X�̈����n������23���A
�s�����O�ōs��ꂽ�B24���ɉ^�s���J�n���A�c���䂩��̓��X�P���������铯�s�����n��̏Z����̐����H����
�^�p�����ق��A�ό��U�q�ɂ�����B
�����n����o�R���A�s�����ƕđ�X�L�[������Ԏs���o�X�������̐V�ԗ��ƂȂ�B�ԗ��X�V���@�ɗU�q��
�N���܂ɂ��悤�ƁA�����ʂɑO�c�c�����͂��߁A�ɒB���@�A���]�����Ȃǖ���u�Ԃ̌c���v�ɓo�ꂷ��
�đ�䂩��̐퍑�������`�����B1��17�֒�10�ւŎg���A�C�x���g�Ȃǂɂ��o�ꂷ��\�肾�B���Ɣ�͖�270���~�ŁA
���̂ق��ɁA������Ǘ�����R�A�~�b�N�X�i�����j�ւ̎g�p����������B
589�l�Ԏ����l�N
2023/01/28(�y) 10:48:46.83ID:NFuXwtQf ���@�ނ�͂悭�A�Љ�ɍv���������ƌ��ɂ���B
���@�Ȃ�ł��Љ�̃l�g�E�������E�ɒǂ����ނ��Ƃ��A�Љ�ɍv�����邱�ƂȂ����ŁB
���@�C�W���⌙���点�ŎЉ�ɍv���ł��鋳�t��x���ɂȂ邽�߂ɁA�����ċA��������ł����āA�c�����E�𗠐����킯�ł͂Ȃ��A�S�́����l�Ȃ������B
���@
���@�̂͋A������Ɨ���҂ƌĂꂽ�肵�����A�c���ɍ��Ђ��c�����܂܋A��������@���m�����ꂽ���݂ł́A�Љ�ɍv�����邽�߂ɂނ���A�����邱�Ƃ���������Ă���B
���@���e�����őO�Ȃ̂��鐶���̔����Ƃł���A���ł͕��ʂɋA�����Ă���B
���@
���@�����w��Ȃǂ̓l�g�E���F�肵�����{�l�𓐎B���āA�s���̎ʐ^���ƌ����Ă�܂��Ă���B
���@�����̎ʐ^�́A�W�c�X�g�[�J�[�Ɏg�p�����B
���@�ނ�͏W�c�X�g�[�J�[���A�m�n��Ŏq���������S���S�p�g���[���n�Ə̂��Ă���B
���@�Ȃ�ł��Љ�̃l�g�E�������E�ɒǂ����ނ��Ƃ��A�Љ�ɍv�����邱�ƂȂ����ŁB
���@�C�W���⌙���点�ŎЉ�ɍv���ł��鋳�t��x���ɂȂ邽�߂ɁA�����ċA��������ł����āA�c�����E�𗠐����킯�ł͂Ȃ��A�S�́����l�Ȃ������B
���@
���@�̂͋A������Ɨ���҂ƌĂꂽ�肵�����A�c���ɍ��Ђ��c�����܂܋A��������@���m�����ꂽ���݂ł́A�Љ�ɍv�����邽�߂ɂނ���A�����邱�Ƃ���������Ă���B
���@���e�����őO�Ȃ̂��鐶���̔����Ƃł���A���ł͕��ʂɋA�����Ă���B
���@
���@�����w��Ȃǂ̓l�g�E���F�肵�����{�l�𓐎B���āA�s���̎ʐ^���ƌ����Ă�܂��Ă���B
���@�����̎ʐ^�́A�W�c�X�g�[�J�[�Ɏg�p�����B
���@�ނ�͏W�c�X�g�[�J�[���A�m�n��Ŏq���������S���S�p�g���[���n�Ə̂��Ă���B
590�l�Ԏ����l�N
2023/01/29(��) 16:22:59.59ID:zGUfX6EG �����X���Ŗ��O�ɂ������̂�
�u��F���p�L�v����u���̏�������̎��v
�}�O�����c(������)����O�����ꂽ�Ƃ���ɐ�(����)�̏����Ƃ����ꏊ������B
��N(�V����N�A1574�N)�A���c�e�킪���c��Ŗd���̂����n���ꂽ���A���c�e�G�͍��c��ŏH������Ɠ��ʂ��A��F����̗�������B
�����m�������ԓ���͏���a���(������K)�A�R�z���(�R�z�ቺ�A�R�z�ҐM)���w�̑叫�Ƃ��ĎO��R�]�ŏ鉺�ɕ����A���c��ɔ������B
����ɑ��Č��c�e�G�͗ьc�ɘZ��]�R�𗦂��������B
�ьc�͑����̗͂ŗ��ԌR�������ǂ��A���̏����ɐw������B
���ԓ���͈����Ԃ����A�C��w�ɂ��Đw������B
���c�̌R���́u������͑����Ő���������̂ō������U�߂܂��傤�v�ƊЂ߂���
�ьc�́u���͖����ł���A�����炪�U�߂�ƌ������͔w���̐w�Ŏ��ɕ������Ő키�ł��낤�B�����Ђ��̂�҂ׂ����v�ƌ������B
����A����a�������ԓ���ɑ�
�u���͖����ł���܂����A�����Ђ��Ċ����ƂȂ�Ε��ǂ��ɂ����a�̐S�������܂��傤�B
������͏����Ƃ͂����A���U�߂�ׂ��ł��B�v�ƊЂ߂��B
���ԓ���́u���c�����U�߂Ă��Ȃ��̂������炭�����l���Ă��邩��ł��낤�B
�G���v���[���҂ł��邩��A���炭�l�n���x�߂��̂��ɁA�����炩�牟����B�v�ƌ������B
���̂̂�����A�R�z���ꂼ��ܕS�R�𗦂����c�̐�w�Ɍ���������A���ԓ�����nj������B
���c�R�͍��c�̏鉺�܂ł�������ދp�������A�ьc�͑卄�̎҂Ȃ̂ŁA�t�ɏ���a������A�ǂ��Ԃ����B
�����֗R�z�����������ėьc�����͂݁A���ɏ���a���̎�ŗьc��������B
���ԓ��ᗦ�����w�����̐����ɏ��A���c��̓�̊ہA�O�̊ۂ܂ōU�ߍ��݁A�Ă����āA��騂��グ�ċA�҂����B
���̐�Ō��c���̎蕉�E���l�͐��S�]�B
����ɑ����Ԑ��͎蕉�O�\�l�A���l�\�l�������Ƃ����B
���̊����̍����Ɋ֘A�Â��镪�ʂ́A�ьc������a���������悤�Ɏ����Ă����B
���������ԓ���قǂ̐l������ǂ����ĂāA���̂܂�Ɉ�������Ă����Ȃ�Α叟���ƌ��������낤�ɁA������Ă��܂����Ƃ́A�ьc�̌R�z���O�ꂽ�Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�u��F���p�L�v����u���̏�������̎��v
�}�O�����c(������)����O�����ꂽ�Ƃ���ɐ�(����)�̏����Ƃ����ꏊ������B
��N(�V����N�A1574�N)�A���c�e�킪���c��Ŗd���̂����n���ꂽ���A���c�e�G�͍��c��ŏH������Ɠ��ʂ��A��F����̗�������B
�����m�������ԓ���͏���a���(������K)�A�R�z���(�R�z�ቺ�A�R�z�ҐM)���w�̑叫�Ƃ��ĎO��R�]�ŏ鉺�ɕ����A���c��ɔ������B
����ɑ��Č��c�e�G�͗ьc�ɘZ��]�R�𗦂��������B
�ьc�͑����̗͂ŗ��ԌR�������ǂ��A���̏����ɐw������B
���ԓ���͈����Ԃ����A�C��w�ɂ��Đw������B
���c�̌R���́u������͑����Ő���������̂ō������U�߂܂��傤�v�ƊЂ߂���
�ьc�́u���͖����ł���A�����炪�U�߂�ƌ������͔w���̐w�Ŏ��ɕ������Ő키�ł��낤�B�����Ђ��̂�҂ׂ����v�ƌ������B
����A����a�������ԓ���ɑ�
�u���͖����ł���܂����A�����Ђ��Ċ����ƂȂ�Ε��ǂ��ɂ����a�̐S�������܂��傤�B
������͏����Ƃ͂����A���U�߂�ׂ��ł��B�v�ƊЂ߂��B
���ԓ���́u���c�����U�߂Ă��Ȃ��̂������炭�����l���Ă��邩��ł��낤�B
�G���v���[���҂ł��邩��A���炭�l�n���x�߂��̂��ɁA�����炩�牟����B�v�ƌ������B
���̂̂�����A�R�z���ꂼ��ܕS�R�𗦂����c�̐�w�Ɍ���������A���ԓ�����nj������B
���c�R�͍��c�̏鉺�܂ł�������ދp�������A�ьc�͑卄�̎҂Ȃ̂ŁA�t�ɏ���a������A�ǂ��Ԃ����B
�����֗R�z�����������ėьc�����͂݁A���ɏ���a���̎�ŗьc��������B
���ԓ��ᗦ�����w�����̐����ɏ��A���c��̓�̊ہA�O�̊ۂ܂ōU�ߍ��݁A�Ă����āA��騂��グ�ċA�҂����B
���̐�Ō��c���̎蕉�E���l�͐��S�]�B
����ɑ����Ԑ��͎蕉�O�\�l�A���l�\�l�������Ƃ����B
���̊����̍����Ɋ֘A�Â��镪�ʂ́A�ьc������a���������悤�Ɏ����Ă����B
���������ԓ���قǂ̐l������ǂ����ĂāA���̂܂�Ɉ�������Ă����Ȃ�Α叟���ƌ��������낤�ɁA������Ă��܂����Ƃ́A�ьc�̌R�z���O�ꂽ�Ƃ����ׂ��ł��낤�B
591�l�Ԏ����l�N
2023/01/29(��) 21:45:31.22ID:ystmpJiH �ǂ�����@����ύō��ɖʔ���������
���^���C�P�����������T�̍���V�[�����y����
�w�^���̉ƍN�ȂE���������Ⴆ
���^���C�P�����������T�̍���V�[�����y����
�w�^���̉ƍN�ȂE���������Ⴆ
592�l�Ԏ����l�N
2023/01/30(��) 11:42:36.68ID:PQJEHz6z �Y�o�V��2023.01.29
����P�X��A�Ɠp����@�e����Ɂu�����ւȂ��v
https://www.sankei.com/article/20230129-GK2FGRVSJVIFHIV224P75RHLYE/
����ƍN���瑱������@�ƂP�X��ړ���Ƃ��ĂP���P���ɉƓ��p��������ƍL���i�T�V�j���Q�X���A�����s�`��̑��㎛�ŊJ���ꂽ�u�p�@�̋V�v�ŁA
�e����W�҂ɑ�ւ�������B�V����̋L�҉�ł́u�ӔC�̏d���ɐg���������܂�B�i���́j��������Ă������̂𖢗��ɂȂ��ł����v�ƈӋC���B
�V���͔���J�ŁA����⏼���̈��ȂǂS�O�O�l�ȏオ�Q���B�ƍL���͕��łP�W��ړ���̍P�F���i�W�Q�j����Ɠ����̍ۂɈ����p���i��������Ƃ����B
��ŁA�������̂m�g�j��̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v�ɂ��Ė���u�l�Ԃ炵����҂炵���ƍN���ɂȂ��Ă���B����ړ����Ă����Ɨ������Ă��炦����ꂵ���v�ƌ�����B
����̌��͂U�O�N�Ԃ�B
�����s�o�g�̉ƍL���͐����o�ϕ]�_�Ƃ�|��ƂƂ��Ċ������A����L�O���c�̗������߂�B�Q�O�P�X�N�̎Q�@�I�ŗ�������}���F���Ƃ��ĐÉ��I���悩��o�n���A���I�����B
����P�X��A�Ɠp����@�e����Ɂu�����ւȂ��v
https://www.sankei.com/article/20230129-GK2FGRVSJVIFHIV224P75RHLYE/
����ƍN���瑱������@�ƂP�X��ړ���Ƃ��ĂP���P���ɉƓ��p��������ƍL���i�T�V�j���Q�X���A�����s�`��̑��㎛�ŊJ���ꂽ�u�p�@�̋V�v�ŁA
�e����W�҂ɑ�ւ�������B�V����̋L�҉�ł́u�ӔC�̏d���ɐg���������܂�B�i���́j��������Ă������̂𖢗��ɂȂ��ł����v�ƈӋC���B
�V���͔���J�ŁA����⏼���̈��ȂǂS�O�O�l�ȏオ�Q���B�ƍL���͕��łP�W��ړ���̍P�F���i�W�Q�j����Ɠ����̍ۂɈ����p���i��������Ƃ����B
��ŁA�������̂m�g�j��̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v�ɂ��Ė���u�l�Ԃ炵����҂炵���ƍN���ɂȂ��Ă���B����ړ����Ă����Ɨ������Ă��炦����ꂵ���v�ƌ�����B
����̌��͂U�O�N�Ԃ�B
�����s�o�g�̉ƍL���͐����o�ϕ]�_�Ƃ�|��ƂƂ��Ċ������A����L�O���c�̗������߂�B�Q�O�P�X�N�̎Q�@�I�ŗ�������}���F���Ƃ��ĐÉ��I���悩��o�n���A���I�����B
593�l�Ԏ����l�N
2023/01/30(��) 12:16:40.43ID:EzzKntzF ���A����ƍN�̐S��Ȃ�����˂���I
594�l�Ԏ����l�N
2023/01/30(��) 19:59:21.02ID:r6sM9i9Y >>576�̑���
�u���ƊՒk�v������c����
�{�����M����̉��m�ɂ��U�ߎ�������A�q��N�������̎�Ɍ������ĉ������Ă����Ƃ���
�^�c���K�͐M��(����:�^�c�K��)�甪�\�R�ƁA���������т��ɏo�Ă����B
�q��N���Ƃ��̎q�A�q�쒉���͂����ǂ��������B
�^�c���̓��c���E�q���\�]�l����������đނ����B
�q��N���̕��̉J�����Z�A�Җ��q��A���Y��A�����㑾�v�炪�Ȃ����ǂ��������B
���̎��A�����Ő^�c���q�Ɛ^�c�����\���肪��ۂ�ł��č�����w�����B
�匴�N���͂�������āu���Ă��������d���ł���B���������(���̂̂���)�Ƃ��v���Ă���ʁv
�Ɣn�������Ď萨���]�Ő^�c�̐Ղ�����Ƌ삯�A�n�ӏd�j�͓��ɓS�C���������B
�^�c���q�E���͐F�߂���������܍��q��ɍ匴�N���R�ւ̔������������X�Ə���ɑނ����B
�������Đ^�c�ɍ�����r���Ő�グ�����ď钆�ɒǂ��������Ƃ���ŁA�ēx�������悤�ɂƂ������m���������B
�匴�N���A�q��N�����������A�R�]�肪�����Ċփ����ւ̐i�R�����܂����B
�������ĐX�E�ߑ�v(�X����)�A������}���(������g�d)�A�ΐ쌺�ד�(�ΐ�N��)��^�c�\�Ɏc���A�G�����͔��Z�ւ��}���ɂȂ�ꂽ�B
�ؑ]�ւ͖{�����M���͘a�c���������蓹���A�匴�N���̈��̓��R�͊����������ĂĘa�c�����z�����B
�������Đ^�c�̍�͓V�̗^���Ɠ`�����Ă��邪�A��l�������邱�ƂȂ����Ƃ��Ƃ��G�����ɕ����B
�u���ƊՒk�v������c����
�{�����M����̉��m�ɂ��U�ߎ�������A�q��N�������̎�Ɍ������ĉ������Ă����Ƃ���
�^�c���K�͐M��(����:�^�c�K��)�甪�\�R�ƁA���������т��ɏo�Ă����B
�q��N���Ƃ��̎q�A�q�쒉���͂����ǂ��������B
�^�c���̓��c���E�q���\�]�l����������đނ����B
�q��N���̕��̉J�����Z�A�Җ��q��A���Y��A�����㑾�v�炪�Ȃ����ǂ��������B
���̎��A�����Ő^�c���q�Ɛ^�c�����\���肪��ۂ�ł��č�����w�����B
�匴�N���͂�������āu���Ă��������d���ł���B���������(���̂̂���)�Ƃ��v���Ă���ʁv
�Ɣn�������Ď萨���]�Ő^�c�̐Ղ�����Ƌ삯�A�n�ӏd�j�͓��ɓS�C���������B
�^�c���q�E���͐F�߂���������܍��q��ɍ匴�N���R�ւ̔������������X�Ə���ɑނ����B
�������Đ^�c�ɍ�����r���Ő�グ�����ď钆�ɒǂ��������Ƃ���ŁA�ēx�������悤�ɂƂ������m���������B
�匴�N���A�q��N�����������A�R�]�肪�����Ċփ����ւ̐i�R�����܂����B
�������ĐX�E�ߑ�v(�X����)�A������}���(������g�d)�A�ΐ쌺�ד�(�ΐ�N��)��^�c�\�Ɏc���A�G�����͔��Z�ւ��}���ɂȂ�ꂽ�B
�ؑ]�ւ͖{�����M���͘a�c���������蓹���A�匴�N���̈��̓��R�͊����������ĂĘa�c�����z�����B
�������Đ^�c�̍�͓V�̗^���Ɠ`�����Ă��邪�A��l�������邱�ƂȂ����Ƃ��Ƃ��G�����ɕ����B
595�l�Ԏ����l�N
2023/01/30(��) 20:15:34.60ID:r6sM9i9Y �Ƃ����킯�ōJ�ԓ`�����Ă�����c����Ɣ�ׂ�ƒn���Ȋ����ł͂���B
�G���R����s�k�����Ƃ��Ă������Ȃ����낤���ǁA������̏�c���{���̊���������ĂȂ��������B
���łɏ�c���{���̒��R�Ǝ�̕��e��>>530�̒��R�Ɣ͂Œ��R�Ǝ�����𗬔n�p�̖���(���R�Ǝw����H)
���쒉���͏��여�꓁���̊J�c�ŏG���̌��p�w���
�G���R����s�k�����Ƃ��Ă������Ȃ����낤���ǁA������̏�c���{���̊���������ĂȂ��������B
���łɏ�c���{���̒��R�Ǝ�̕��e��>>530�̒��R�Ɣ͂Œ��R�Ǝ�����𗬔n�p�̖���(���R�Ǝw����H)
���쒉���͏��여�꓁���̊J�c�ŏG���̌��p�w���
596�l�Ԏ����l�N
2023/01/31(��) 01:24:12.63ID:UwY/Td2H ����@�Ƃ̉Ɠ��ɔ����u�p�@�̋V�v185�N�Ԃ�̏j�V�@19��ƍL����u�s�o�ɂ��܂��v [���l����]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1675031664/1
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1675031664/1
597�l�Ԏ����l�N
2023/01/31(��) 07:26:26.98ID:l6g6q5OT >>596
�����͒E������
�����͒E������
598�l�Ԏ����l�N
2023/02/01(��) 09:36:45.98ID:MGm2S+jR �q���̂���͏������M���������N�ɂȂ��ē���ƍN�ɂȂ�̂͂Ȃ�ƂȂ��[�����Ă���
�_�q��T�V�����쒉���ɂȂ�̂͂ȂߑR�Ƃ��Ȃ�����
�ł��܂��؉����g�Y���L�b�G�g�ɂȂ�悤�Ȃ��̂��Ǝv�����炻���ł��Ȃ��Ȃ���
�_�q��T�V�����쒉���ɂȂ�̂͂ȂߑR�Ƃ��Ȃ�����
�ł��܂��؉����g�Y���L�b�G�g�ɂȂ�悤�Ȃ��̂��Ǝv�����炻���ł��Ȃ��Ȃ���
599�l�Ԏ����l�N
2023/02/01(��) 09:49:28.37ID:D7JT3dPf ����͒��b�������̂�
����͏���
����͏���
600�l�Ԏ����l�N
2023/02/01(��) 10:24:46.15ID:4eyn7Yor ���b�ƗV��
601�l�Ԏ����l�N
2023/02/01(��) 10:56:34.56ID:hkI6Xem/ �������@��
602�l�Ԏ����l�N
2023/02/01(��) 13:56:05.01ID:P8IYCqWh >>598
�ƍN���G�g���A�Ȃ�Ȃ�l�a�蔼���Y�ł��h��ȉ����Ȃ̂ɁA�_�q�コ��͒n���ȕ��ɕς��Ă邩���a������̂����H
�ƍN���G�g���A�Ȃ�Ȃ�l�a�蔼���Y�ł��h��ȉ����Ȃ̂ɁA�_�q�コ��͒n���ȕ��ɕς��Ă邩���a������̂����H
603�l�Ԏ����l�N
2023/02/01(��) 14:21:51.72ID:vGeYoreI �y����z�@��18�㓿��Ɠ���A����P�F����i82�j�A���ށ@19��ڂ͒��j�̉ƍL����i57�j [886559449]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1675134268/1
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1675134268/1
604�l�Ԏ����l�N
2023/02/01(��) 15:19:50.69ID:hkI6Xem/ �Ȃ�Œʎ�����Ȃ��́H
��������Ȃ��Ȃ璎���瓯�R�����
��������Ȃ��Ȃ璎���瓯�R�����
605�l�Ԏ����l�N
2023/02/01(��) 18:55:20.52ID:+Gwn3Mrn �u���ƊՒk�v����^�c�M�ɂ̋�x�R�E�o
�^�c���q�卲�K��(�^�c�M��)�͕����[�珹�K�Ƃ�������ɍ���R��x�R�ɔz������A���K�͌c���̖��Ɏ��B
���q�卲�͈�l��x�R�ɏZ��ł������A���̐w�̏��߁A�G���������C��������������A������Ă�Ƃ����䌾�t�����������ߎx�x�����B
�I�ɍ���̐��A�n�璷��͋��{�����ߕӂ̕S���ǂ��ɉ��m��
�u����̉\�ɁA�^�c���q�卲�����ւ̕Ԏ��������ƕ����B���f����܂����v�ƐG����o�����B
����R�w���Ȃ�тɏ@�k�ɂ���x�R����ِ̓l�Ď���\���t�����B
�^�c�K���͋�x�R�ߕӁA���{���A���J�̏������珬�S���ɂ�����܂Ŏc�炸�U�������ƐG����܂킵�A��x�R�ɏ������B
���S�l�̕�����҂����ɑ����܂��܂ɋ������A�����o���A��˂����˂���킸���������邱�Ǝ߂Ȃ炸�A�F�����ĉ点�đO��s�o�ƂȂ����B
���̎��A�S���ǂ�������Ă����n�ɉׂ����A�Ȏq���敨�ɑł��悹�A�㉺�S�]�ŋ|�S�C�������ĉ������āA�I�m���n��A���{���A���J��ʂ�A�ؖڒÂ��z���A�͓��ɓ���A���ɂނ����čs�����B
���̕S���ǂ��͎c�炸��x�R�ɍs���Đ����炵�Ă������߁A�c���Ă����̂͏��q�������ł������B
�������^�c�͑��Ⓛ���A�S�C�ɉΓ�������Ă������߁A�Ƃ��Ă��~�߂�����̂ł͂Ȃ������B
���ĕS�������͖������ɐ���������߂����A����Ώh���ɂ͈�l�����炸�A�G��܂Ŏ�蕥���Ռ`���Ȃ������B
����͏o�������ꂽ�Ɠ�����q�˂����A��ӂ̂����ɗ����ނ������ߒǂ����͂����Ȃ������B
���{���A���J�̌Ȃ̉ƂɋA��A�Ƒ��ɐq�˂��
�u���̔����ɐ^�c�a��������q�A��Ŕn�ɉׂ����A�|�S�C���������Ăĉ͓��̕��ւ����čs���܂����v
�ƍ��������߁A�S���ǂ��݂͂ȓ���~�������ǂ��ɂ����悤���Ȃ������B
�^�c���q�卲�K��(�^�c�M��)�͕����[�珹�K�Ƃ�������ɍ���R��x�R�ɔz������A���K�͌c���̖��Ɏ��B
���q�卲�͈�l��x�R�ɏZ��ł������A���̐w�̏��߁A�G���������C��������������A������Ă�Ƃ����䌾�t�����������ߎx�x�����B
�I�ɍ���̐��A�n�璷��͋��{�����ߕӂ̕S���ǂ��ɉ��m��
�u����̉\�ɁA�^�c���q�卲�����ւ̕Ԏ��������ƕ����B���f����܂����v�ƐG����o�����B
����R�w���Ȃ�тɏ@�k�ɂ���x�R����ِ̓l�Ď���\���t�����B
�^�c�K���͋�x�R�ߕӁA���{���A���J�̏������珬�S���ɂ�����܂Ŏc�炸�U�������ƐG����܂킵�A��x�R�ɏ������B
���S�l�̕�����҂����ɑ����܂��܂ɋ������A�����o���A��˂����˂���킸���������邱�Ǝ߂Ȃ炸�A�F�����ĉ点�đO��s�o�ƂȂ����B
���̎��A�S���ǂ�������Ă����n�ɉׂ����A�Ȏq���敨�ɑł��悹�A�㉺�S�]�ŋ|�S�C�������ĉ������āA�I�m���n��A���{���A���J��ʂ�A�ؖڒÂ��z���A�͓��ɓ���A���ɂނ����čs�����B
���̕S���ǂ��͎c�炸��x�R�ɍs���Đ����炵�Ă������߁A�c���Ă����̂͏��q�������ł������B
�������^�c�͑��Ⓛ���A�S�C�ɉΓ�������Ă������߁A�Ƃ��Ă��~�߂�����̂ł͂Ȃ������B
���ĕS�������͖������ɐ���������߂����A����Ώh���ɂ͈�l�����炸�A�G��܂Ŏ�蕥���Ռ`���Ȃ������B
����͏o�������ꂽ�Ɠ�����q�˂����A��ӂ̂����ɗ����ނ������ߒǂ����͂����Ȃ������B
���{���A���J�̌Ȃ̉ƂɋA��A�Ƒ��ɐq�˂��
�u���̔����ɐ^�c�a��������q�A��Ŕn�ɉׂ����A�|�S�C���������Ăĉ͓��̕��ւ����čs���܂����v
�ƍ��������߁A�S���ǂ��݂͂ȓ���~�������ǂ��ɂ����悤���Ȃ������B
606�l�Ԏ����l�N
2023/02/02(��) 09:53:48.31ID:x7+VVPmf ���c�������〈�d���Y���Ȃ�Ƃ����Ăق����Ƃ���
607�l�Ԏ����l�N
2023/02/02(��) 12:21:14.77ID:UecNvwyY �^�c�K�����T�i�_���V�Ȃ̂��Ȃ�Ƃ�����
608�l�Ԏ����l�N
2023/02/02(��) 13:10:41.82ID:rizj1g81 ���E�̕R���܂������Ɏ��Ă��Ƃ͂Ȃ�
609�l�Ԏ����l�N
2023/02/02(��) 15:08:51.09ID:sVmltDNx ���������ĕR�ɂ����̂��R���炵��
610�l�Ԏ����l�N
2023/02/02(��) 19:32:25.06ID:y38eWKJL http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-476.html
�̌����Ǝv����
�u���ƊՒk�v�^�c�M�ɂ̑������
�^�c�͑��ɒ����A���̐g�̂܂ܑ��C��(��쎡��)�a�̂Ƃ���ɍs���B
���̍��͓`�S����Ƃ��ē㔯�ł���A���ւňē�������B
�t�҂��o�Ă��āu�R���͂ǂ����痈���H�v�Ɛq�˂Ă����̂�
�^�c�͂킴�Ɓu����ӂ̎R���ł���܂��B��F���̊��������Q�������܂����̂Ō�ڌ����肢�܂��v�ƌ������B
�t�҂́u�a�͏�ɂ�����̂ł�����ɒʂ邪�����v�Ɣԗ�̘e�ɌĂѓ����ꂽ�B
��ڌ���҂᎘�������\�l���肢�āA�����̖ڗ��������Ă����B
��l���^�c�Ɍ������u��m�̓��������Ă���ʂ��H�v�ƌ���������
�^�c�́u�����̎R���̌����ǂ��̓��ł��̂łȂ��Ȃ����ڂɂ�����K�v������܂��܂����A���Ԃ݂ɂȂ�v�Ǝ��o�����B
�����Ɣ����ĕ�������A�i�D�͐\���ɂ�����A���̓����������������B
�᎘�����́u���Ă����Ă������Ȃ�v�ƌ��X�ɂق߁A�u�����g�͂ǂ����낤�v�Ɩ�������Ɓu��@�������@�v�Ƃ���A�u�����g���������v�ƌ����������B
�����ŊF�X�����݁A���Ă͑��҂ł͂Ȃ����낤�A�Ǝv���Ă���Ƃ���ɑ��C���a������A�����B
�t�҂��u���ւɂČ�ڌ��Ȃ����Ă��������v�Ƒ҂��Ă������̂����������o���Ă����B
���͐^�c�̑O�Ɏ�����āu�ߓ����z���ɂȂ�Ƃ͎f���Ă���܂������A�䑫�J�����������Ƃ́B
�������ŏ�ɖ߂�G�����̂����ɓ���܂��傤�B�ǂ����ɉ@�ɂ����肭�������v�ƌ����ď�ɒy���߂����B
���ďG������葬���b���(������v)���g���Ƃ��Ēy���Q���A������S���A��O�\�іڂ������ꂽ�B
������������ւ̎᎘�ǂ��͂����ꂩ�������B
�^�c�͂��������������߁A���̂̂����̎᎘�����ɉ���Ắu���̖ڗ����͓������Ă����悤���ȁv�ƌ����ƁA�F�Ԗʂ����Ƃ����B
�̌����Ǝv����
�u���ƊՒk�v�^�c�M�ɂ̑������
�^�c�͑��ɒ����A���̐g�̂܂ܑ��C��(��쎡��)�a�̂Ƃ���ɍs���B
���̍��͓`�S����Ƃ��ē㔯�ł���A���ւňē�������B
�t�҂��o�Ă��āu�R���͂ǂ����痈���H�v�Ɛq�˂Ă����̂�
�^�c�͂킴�Ɓu����ӂ̎R���ł���܂��B��F���̊��������Q�������܂����̂Ō�ڌ����肢�܂��v�ƌ������B
�t�҂́u�a�͏�ɂ�����̂ł�����ɒʂ邪�����v�Ɣԗ�̘e�ɌĂѓ����ꂽ�B
��ڌ���҂᎘�������\�l���肢�āA�����̖ڗ��������Ă����B
��l���^�c�Ɍ������u��m�̓��������Ă���ʂ��H�v�ƌ���������
�^�c�́u�����̎R���̌����ǂ��̓��ł��̂łȂ��Ȃ����ڂɂ�����K�v������܂��܂����A���Ԃ݂ɂȂ�v�Ǝ��o�����B
�����Ɣ����ĕ�������A�i�D�͐\���ɂ�����A���̓����������������B
�᎘�����́u���Ă����Ă������Ȃ�v�ƌ��X�ɂق߁A�u�����g�͂ǂ����낤�v�Ɩ�������Ɓu��@�������@�v�Ƃ���A�u�����g���������v�ƌ����������B
�����ŊF�X�����݁A���Ă͑��҂ł͂Ȃ����낤�A�Ǝv���Ă���Ƃ���ɑ��C���a������A�����B
�t�҂��u���ւɂČ�ڌ��Ȃ����Ă��������v�Ƒ҂��Ă������̂����������o���Ă����B
���͐^�c�̑O�Ɏ�����āu�ߓ����z���ɂȂ�Ƃ͎f���Ă���܂������A�䑫�J�����������Ƃ́B
�������ŏ�ɖ߂�G�����̂����ɓ���܂��傤�B�ǂ����ɉ@�ɂ����肭�������v�ƌ����ď�ɒy���߂����B
���ďG������葬���b���(������v)���g���Ƃ��Ēy���Q���A������S���A��O�\�іڂ������ꂽ�B
������������ւ̎᎘�ǂ��͂����ꂩ�������B
�^�c�͂��������������߁A���̂̂����̎᎘�����ɉ���Ắu���̖ڗ����͓������Ă����悤���ȁv�ƌ����ƁA�F�Ԗʂ����Ƃ����B
611�l�Ԏ����l�N
2023/02/03(��) 11:53:24.30ID:+VrU+S7l �킴�킴���̂��B���Ƃ͐��i���P���Ȃ������z����
����ȃN�Y�ł����̂����j��l�X�ƑΉ������C���͂�������
����ȃN�Y�ł����̂����j��l�X�ƑΉ������C���͂�������
612�l�Ԏ����l�N
2023/02/03(��) 14:34:43.05ID:LD9TP4LV �����Ȃ�^�c���q�卲�ł���Ƃ������Ƃ��ŁA���m���Ă镪���Ȃ��q�m�������A�͂������ł����ƒʂ��킯���Ȃ��A�y���M���Ă�낤�ƂȂ�͎̂d���Ȃ���Ȃ�����
�b��������l�͂����l�����낤
�b��������l�͂����l�����낤
613�l�Ԏ����l�N
2023/02/03(��) 15:19:43.40ID:D1kKXrEE614�l�Ԏ����l�N
2023/02/03(��) 18:42:25.15ID:G38mHENW �M�����A�l�̌�g���Ȃ���悤
�M�����͑��ɁA���Â��������悤�ɂƂ��ꂽ�B���l�����Â��Ȃ�̂́A�䉶�������ہA
�㒆���̑F�����Ȃ��A���߁A�����̑�����������l�X�ɏ��̂������悤�Ȏ�������A
�蕿�̂Ȃ��l�X�͕K���y�����ȂāA����U���ė��g����̂ɁA���ۂɒ��߁A�����𐬂����l�����݁A
�������ċt�ɌȂ̓}�̎҂�J�߂�B�����������҂����̉��ӂ͎�N�ւ̌�ׂ��v�킸�A
�Ӓn���Â��āA�ւ炢�܂��S�ł���B�̂ɁA���Â��Ȃ�̂ł���B
�M�����͒��߁A�����̕��m�ɂ͑�g�A���g�ɂ�炷�A���ڂɂ���炸�A���̐g�̎蕿����Ɋ���A�܂�
�䉶�������ꂽ�B�̂ɐl���ۛ������萬�������A����������Ȃ������B���̂��߁A���l�̌��Â�����
���Ȃ��Ȃ����̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�M�����͑��ɁA���Â��������悤�ɂƂ��ꂽ�B���l�����Â��Ȃ�̂́A�䉶�������ہA
�㒆���̑F�����Ȃ��A���߁A�����̑�����������l�X�ɏ��̂������悤�Ȏ�������A
�蕿�̂Ȃ��l�X�͕K���y�����ȂāA����U���ė��g����̂ɁA���ۂɒ��߁A�����𐬂����l�����݁A
�������ċt�ɌȂ̓}�̎҂�J�߂�B�����������҂����̉��ӂ͎�N�ւ̌�ׂ��v�킸�A
�Ӓn���Â��āA�ւ炢�܂��S�ł���B�̂ɁA���Â��Ȃ�̂ł���B
�M�����͒��߁A�����̕��m�ɂ͑�g�A���g�ɂ�炷�A���ڂɂ���炸�A���̐g�̎蕿����Ɋ���A�܂�
�䉶�������ꂽ�B�̂ɐl���ۛ������萬�������A����������Ȃ������B���̂��߁A���l�̌��Â�����
���Ȃ��Ȃ����̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
615�l�Ԏ����l�N
2023/02/06(��) 11:38:57.47ID:70s7l+zE616�l�Ԏ����l�N
2023/02/06(��) 14:41:09.96ID:jjDXF4mA ���E����ӂ̓z�������뉽�������Ă�
����ۂnj��ɂ��������̂���w
����ۂnj��ɂ��������̂���w
617�l�Ԏ����l�N
2023/02/06(��) 16:55:03.99ID:lx6h6AZ+ �Ɓ@����������^���Ԃɂ��Ēp�̏�h�������̂ł�����🤭
618�l�Ԏ����l�N
2023/02/06(��) 17:23:04.64ID:RfSryFxq ���E����Ȃ��ď��w���������̂�
619�l�Ԏ����l�N
2023/02/06(��) 17:57:53.16ID:wz8OvnMp �܂����F���b�Ȃ���J�b�J���Ȃ����
����͂���Ƃ��ĖL�b���炷��Ⴝ���Ղ�O�������n���Ă���痧�h�Ȑg�Ȃ�ŗ��ė~�����������낤����
����͂���Ƃ��ĖL�b���炷��Ⴝ���Ղ�O�������n���Ă���痧�h�Ȑg�Ȃ�ŗ��ė~�����������낤����
620�l�Ԏ����l�N
2023/02/06(��) 18:05:11.62ID:IDwx5uuz �ǂ������ɋ����g���Ă��܂�����Ȃ��ĎR���̊i�D�Ō��ꂽ��
���������z�����ɂł�������
���������z�����ɂł�������
621�l�Ԏ����l�N
2023/02/06(��) 18:17:10.52ID:wYXGpwx3 �u�����ƊՒk�v����u���Č�w�O����n�x�͂ɔE�ю҂����킷�̑��k�̂��Ɓv
���Ă̐w�̑O�ɁA����n(��쎡�[)���x�{�ɕ����悤�ƁA�E�т���﨟�O�̏��̉��ɔE�ѓ��ꂳ���A�����l�����������鎞�����f���āA�����Ă��܂����Ɛ\���t�����B
���̂Ƃ����������q(�����i��)���u���̂悤�Ȏ�i�ł͐������Ȃ��ł��傤�B
�l���ɂ��炵�������A�u���̋��Z�̉����͍~��₷���悤�ɒႭ���v�Ƃ�������������߁A�ǂ̏����Ⴍ�Ȃ��Ă��邻���ł��B
�{���͐l���E�т���̂�h�����߂������ł��v�Ɛ\�������߁A���~�ƂȂ����B
���͏����͉Ă̐w�̑O�ɊԎ҂Ƃ��đ�����ď�ɉ�����Ă����Ƃ����B
���Ă̐w�̑O�ɁA����n(��쎡�[)���x�{�ɕ����悤�ƁA�E�т���﨟�O�̏��̉��ɔE�ѓ��ꂳ���A�����l�����������鎞�����f���āA�����Ă��܂����Ɛ\���t�����B
���̂Ƃ����������q(�����i��)���u���̂悤�Ȏ�i�ł͐������Ȃ��ł��傤�B
�l���ɂ��炵�������A�u���̋��Z�̉����͍~��₷���悤�ɒႭ���v�Ƃ�������������߁A�ǂ̏����Ⴍ�Ȃ��Ă��邻���ł��B
�{���͐l���E�т���̂�h�����߂������ł��v�Ɛ\�������߁A���~�ƂȂ����B
���͏����͉Ă̐w�̑O�ɊԎ҂Ƃ��đ�����ď�ɉ�����Ă����Ƃ����B
622�l�Ԏ����l�N
2023/02/07(��) 12:28:02.50ID:MRURELVk �܂������ɂ͂����Ƃ����i�D�œ������͂��B�Ă��킴�킴�����������傭���ĉ������v�ɂȂ邩�ƌ����c
623�l�Ԏ����l�N
2023/02/07(��) 13:37:21.89ID:+64kPC89624�l�Ԏ����l�N
2023/02/07(��) 17:26:15.78ID:YQxXboj/ ����M�ɂ̘b�Ȃ�ł���
625�l�Ԏ����l�N
2023/02/07(��) 19:41:00.85ID:KiNG3wst �@�\�����ӕ|��
626�l�Ԏ����l�N
2023/02/08(��) 03:44:55.88ID:sOzZnXDD >>623
���w���������Ȃ�w
���w���������Ȃ�w
627�l�Ԏ����l�N
2023/02/08(��) 09:48:06.39ID:l2+NMJgp �ŏ��͕��������̂����ɎE���ɂȂ��Ăď���
628�l�Ԏ����l�N
2023/02/08(��) 10:50:08.33ID:bCajFm19 �Ύ����N�����č������Ă�Œ��ɎE���v�悾������ł���
����Ȃ��Ƃ�������Ȃ�����l���o���̖R�������E���Č�����낤��
����Ȃ��Ƃ�������Ȃ�����l���o���̖R�������E���Č�����낤��
629�l�Ԏ����l�N
2023/02/08(��) 10:53:40.64ID:l2+NMJgp ���Ғʂ�̃��X�����ď���
����ȂƂ��͂킴�킴�����ɂ��Ȃ��Ă����킩��ł���ˁH���Ęb�Ȃ̂�
����ȂƂ��͂킴�킴�����ɂ��Ȃ��Ă����킩��ł���ˁH���Ęb�Ȃ̂�
630�l�Ԏ����l�N
2023/02/08(��) 11:00:22.64ID:ZzXhpsma ���E�����Ғʂ�̔��������Ă���ď���
�킴�킴���X���Ă���Ȃ��Ă��m���Ă�̂�
�킴�킴���X���Ă���Ȃ��Ă��m���Ă�̂�
631�l�Ԏ����l�N
2023/02/08(��) 17:37:13.78ID:SARpYva+ �Óc�D�����ł�
�u�����ƊՒk�v���u�Óc�D�����̐ؕ��̂��Ɓv
�Óc�D���������֕Ԃ蒉���Ȃ������A�u(�ƍN�̈ӌ��ŁH)�ؕ��̋`�͎b�����������悤�Ɂv�Ƃ������e�̌Еt���ɂ������q�ɉ�珟�d�Ɍ��킳�ꂽ�B
�ɉ��͏����ǂ݁A�u���̂悤�ȋ}��v���邱�Ƃ͏�X�̏���Ƃ͈Ⴂ�A�Еt������ɋy�Ȃ��v�Ɛ\�����������B
(���闎����)�Z���\����A�D�����͐ؕ��ƂȂ�A����y����(���������H)�Ɠ����E�q�傪���g�Ƃ��Ă���Ă����Ƃ����B
�u�����ƊՒk�v���u�Óc�D�����̐ؕ��̂��Ɓv
�Óc�D���������֕Ԃ蒉���Ȃ������A�u(�ƍN�̈ӌ��ŁH)�ؕ��̋`�͎b�����������悤�Ɂv�Ƃ������e�̌Еt���ɂ������q�ɉ�珟�d�Ɍ��킳�ꂽ�B
�ɉ��͏����ǂ݁A�u���̂悤�ȋ}��v���邱�Ƃ͏�X�̏���Ƃ͈Ⴂ�A�Еt������ɋy�Ȃ��v�Ɛ\�����������B
(���闎����)�Z���\����A�D�����͐ؕ��ƂȂ�A����y����(���������H)�Ɠ����E�q�傪���g�Ƃ��Ă���Ă����Ƃ����B
632�l�Ԏ����l�N
2023/02/09(��) 16:51:29.47ID:793QnLC8 �X���ɒ���t���ăI�E���Ԃ��̐Ґ����˂͑�������
633�l�Ԏ����l�N
2023/02/09(��) 19:21:30.30ID:7bZBp8YZ �u�����ƊՒk�v���u�ƍN�����艪��֓��҂̎��Ȃ�тɌ䓖�ƈɉ�O�̎��v
�V���\�N�i1582�N�j�t�A�����e����\����̖���A�ɉ�̍��̎m�A�ѐA�O�V��i�ѐA���L�j���l���ɂ��Ĉɉ�̎m���ƍN���ɑ��������ނˌ��サ���B
�ɉ�͂�������͐M���ɏ]���{�̈��g�����A���̂̂��w�������߁A���̔N�M���ɂ���s��j���ǂ������A���邢�͎R�тɓ���A���邢�͐�c�`���̒n�������Ă����B
���̔N�M���͍b�B�������M�������̂ŁA�����l�͌c�j�̂��߈��y��ɂ��������B
�M���͌�z�����A����Ƃ̗��X�O�̉i�䒼���Ȃǂɂ��ʐȂŋ��V���o���A�M�����產�ō��z�V���ꂽ�B
�ƍN���͌�㋞�Ȃ���A��̒Â�V�����ꂽ�Ƃ���ɁA���{�\���ŐM�����Q�̒m�点���͂����B
���̂��ߍ���������ɂȂ�A��Ɛl���|���ɏ]���A���J��|�ہi���J��G��j���ē��l�Ƃ��Ĉɉ�E�ɐ����o�ĉ����A�҂Ƃ������ƂɂȂ�A�F����ɂ��������B
����n��ɍۂ��A���䒉�������D���z�����ߓ��Č����l����点������B
�D�l���^����������߁A�䍘��⠂����������B
��Ɛl�����͎��䒉���͂��߂݂Ȕn�ʼnF�����n�����B
��D���݂ɒ����Ƒ鏠�̐_�J���삪�D�l����⠂����߂������߁A�����l����_�J��⠂������ꂽ�B
�R���i���i���q�R��W�Q���邽�߂ɐ��c���𗎂Ƃ����j�̒�E�R���i���͐��c���炱�̒n�ɗ��ē��ē��������B
�F���c���̎҂ǂ����I�N���Ă��邽�߁A���̒n�ɂ�������i����͂Ƃ�j�喾�_�̎Ђɓ���Εʓ��̕�����M���ē����邾�낤�ƌ䔻�f���ꂽ�B
���̕ʓ����Ɛl��A��ĎR���ē�����ƁA�앐�m��݂͂ȕʓ��Ɛe�����������߁A���Ƃ��Ƃ��������B
�V���\�N�i1582�N�j�t�A�����e����\����̖���A�ɉ�̍��̎m�A�ѐA�O�V��i�ѐA���L�j���l���ɂ��Ĉɉ�̎m���ƍN���ɑ��������ނˌ��サ���B
�ɉ�͂�������͐M���ɏ]���{�̈��g�����A���̂̂��w�������߁A���̔N�M���ɂ���s��j���ǂ������A���邢�͎R�тɓ���A���邢�͐�c�`���̒n�������Ă����B
���̔N�M���͍b�B�������M�������̂ŁA�����l�͌c�j�̂��߈��y��ɂ��������B
�M���͌�z�����A����Ƃ̗��X�O�̉i�䒼���Ȃǂɂ��ʐȂŋ��V���o���A�M�����產�ō��z�V���ꂽ�B
�ƍN���͌�㋞�Ȃ���A��̒Â�V�����ꂽ�Ƃ���ɁA���{�\���ŐM�����Q�̒m�点���͂����B
���̂��ߍ���������ɂȂ�A��Ɛl���|���ɏ]���A���J��|�ہi���J��G��j���ē��l�Ƃ��Ĉɉ�E�ɐ����o�ĉ����A�҂Ƃ������ƂɂȂ�A�F����ɂ��������B
����n��ɍۂ��A���䒉�������D���z�����ߓ��Č����l����点������B
�D�l���^����������߁A�䍘��⠂����������B
��Ɛl�����͎��䒉���͂��߂݂Ȕn�ʼnF�����n�����B
��D���݂ɒ����Ƒ鏠�̐_�J���삪�D�l����⠂����߂������߁A�����l����_�J��⠂������ꂽ�B
�R���i���i���q�R��W�Q���邽�߂ɐ��c���𗎂Ƃ����j�̒�E�R���i���͐��c���炱�̒n�ɗ��ē��ē��������B
�F���c���̎҂ǂ����I�N���Ă��邽�߁A���̒n�ɂ�������i����͂Ƃ�j�喾�_�̎Ђɓ���Εʓ��̕�����M���ē����邾�낤�ƌ䔻�f���ꂽ�B
���̕ʓ����Ɛl��A��ĎR���ē�����ƁA�앐�m��݂͂ȕʓ��Ɛe�����������߁A���Ƃ��Ƃ��������B
634�l�Ԏ����l�N
2023/02/09(��) 19:24:15.75ID:7bZBp8YZ ������M�͍]�B�M�y�܂ňē������B
���̒n�͑�X�����������߂�n�Ȃ̂ő��������r�Ƌ����̂��钷�J��|�������l�̌��V�ɂ��Č��r�ɍ����A���r�͂����Ɏ����̉��~�ɓ��������B
�����l�͕�����M�̒��`���������ɂȂ�A�����̌�J���Ƃ��ė������̌䓁���������ꂽ�B
�̂��ɕ�����M�͕l���ɎQ��S�Z�\�Ύ��̌�Ɛl�ƂȂ����B���݁A�����v�E�q��E�����я������̌䍘����`�����Ă���ƕ����B
�����l�͑������̏h�Ɍ�ꔑ����A�������̈ē��ňɉ�̒ѐA�ɂ������������B
���̒n�̒ѐA���L�i�O�q�j�̈ꑰ�͐M���ɍU�ߖłڂ��ꂽ���߂ɖ��Ԃɐ���ł����̂ł������B
�ѐA��͐l�����o���A�r���̈Ꝅ����ǂ������A�����d���Ď����e�i���ԂƁA�����j�܂Ō����l�𑗂����B
����ɂ�茠���l�͒ѐA�������䊴�������炸���v���ɂȂ����B
�����ق��̓�S�l�̈ɉ�Q�l�͒��r�܂ł��������߁A��Ɛl�Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B
���������q�͈ɐ��̊ւ܂ő����������߁A�������̖{�̂����g���Č�Ɛl�Ƃ����B
�������q�܂œ����Ȃ���ƁA�p�q���Y���Y�i�p���G���j�Ƃ������̂������̑D��݂���������߁A���̂̂����Ɏ���܂Ŏq���ɐ����Ă���B
�ɉ�̒ѐA�E�S�n�Ȃǂ͂����Ō�ɂ��������B
�O�͂̑�l�Ɍ����l�����������ƒ��c�d�����}������ČN�b�Ƃ��ɋ��������B���c�d���͉i�䒼���̕��ł���B
�������Č����l�̌�̂����Ȃ��Ƃ������ƂŖ����̂��A���N���q�ގ��̂��߂ɔ�����i�R�����Ƃ���ɉ�̏��m�͂��Ƃ��Ƃ��Q�w����Ɛl�ƂȂ����B
�����ѐA�E�S�n���͂��߂Ƃ��������e�܂ł����������҂݂͂Ȍ䒼�Q�Ƃ��Č�n���ƂȂ������A���r�܂łŋA������S�l�͓k���E���S�̊i�Ƃ��ď���������ꂽ�B
���̓�S�l�����̈ɉ�O�̐�c�ł���B
���̒n�͑�X�����������߂�n�Ȃ̂ő��������r�Ƌ����̂��钷�J��|�������l�̌��V�ɂ��Č��r�ɍ����A���r�͂����Ɏ����̉��~�ɓ��������B
�����l�͕�����M�̒��`���������ɂȂ�A�����̌�J���Ƃ��ė������̌䓁���������ꂽ�B
�̂��ɕ�����M�͕l���ɎQ��S�Z�\�Ύ��̌�Ɛl�ƂȂ����B���݁A�����v�E�q��E�����я������̌䍘����`�����Ă���ƕ����B
�����l�͑������̏h�Ɍ�ꔑ����A�������̈ē��ňɉ�̒ѐA�ɂ������������B
���̒n�̒ѐA���L�i�O�q�j�̈ꑰ�͐M���ɍU�ߖłڂ��ꂽ���߂ɖ��Ԃɐ���ł����̂ł������B
�ѐA��͐l�����o���A�r���̈Ꝅ����ǂ������A�����d���Ď����e�i���ԂƁA�����j�܂Ō����l�𑗂����B
����ɂ�茠���l�͒ѐA�������䊴�������炸���v���ɂȂ����B
�����ق��̓�S�l�̈ɉ�Q�l�͒��r�܂ł��������߁A��Ɛl�Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B
���������q�͈ɐ��̊ւ܂ő����������߁A�������̖{�̂����g���Č�Ɛl�Ƃ����B
�������q�܂œ����Ȃ���ƁA�p�q���Y���Y�i�p���G���j�Ƃ������̂������̑D��݂���������߁A���̂̂����Ɏ���܂Ŏq���ɐ����Ă���B
�ɉ�̒ѐA�E�S�n�Ȃǂ͂����Ō�ɂ��������B
�O�͂̑�l�Ɍ����l�����������ƒ��c�d�����}������ČN�b�Ƃ��ɋ��������B���c�d���͉i�䒼���̕��ł���B
�������Č����l�̌�̂����Ȃ��Ƃ������ƂŖ����̂��A���N���q�ގ��̂��߂ɔ�����i�R�����Ƃ���ɉ�̏��m�͂��Ƃ��Ƃ��Q�w����Ɛl�ƂȂ����B
�����ѐA�E�S�n���͂��߂Ƃ��������e�܂ł����������҂݂͂Ȍ䒼�Q�Ƃ��Č�n���ƂȂ������A���r�܂łŋA������S�l�͓k���E���S�̊i�Ƃ��ď���������ꂽ�B
���̓�S�l�����̈ɉ�O�̐�c�ł���B
635�l�Ԏ����l�N
2023/02/09(��) 22:01:24.25ID:zSQP2NxC ���w�������猻�㕶�̐��т������͓̂��R����
�܂��P�ɓ����������ȋC�����邪w
�܂��P�ɓ����������ȋC�����邪w
636�l�Ԏ����l�N
2023/02/10(��) 10:46:03.47ID:GWEK21bA >>585
����ƍN�ٕ̈��E�����N�r�i���r�j�́A���쎁�ւ̐l���ɏo���ꂽ��A���̎��͕��c���̌��ɁA����ɂ�����E�o���Ă�
�g���̐l�����߂������ЂƂł������A�����ɖS���Ȃ�܂����B
������l�������Ȃ������̂Ő���Ƃ���]�Z��ɂ����鏼�����������{�q�ƂȂ��ē���A�q���͌��̑�g���{�Ƃ��đ����A
�]�˒����̉����ő��Ôˁi��t������S���Ò��j�̑喼�ƂȂ��Ă��܂��B
���j�̂��Ƒ��Â����
https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018013100486/file_contents/11_TakoKanko_A4_p2229m.pdf
���āA�N�r�̖��i�������͏����j�͓`���ł͓V��14�N�i1586�j�����̉ƍN����J��̐_�ʗ͂����间���u?�֓��i��傤����Ƃ��j�v��������A
��X�̉ƕ�Ƃ��ē`���A���݂͂��q�����瑽�Ò��Ɋ���Ă��܂��B
����?�֓��̓����N��̒����Ɏʐ^�������ł����A�ǂ����Ă��~�C�����������j�����B���E�X�R�E���j�H
���̓����܂߂āA�ƍN�͑����������甕���i�D���ł���ˁB
����ƍN�ٕ̈��E�����N�r�i���r�j�́A���쎁�ւ̐l���ɏo���ꂽ��A���̎��͕��c���̌��ɁA����ɂ�����E�o���Ă�
�g���̐l�����߂������ЂƂł������A�����ɖS���Ȃ�܂����B
������l�������Ȃ������̂Ő���Ƃ���]�Z��ɂ����鏼�����������{�q�ƂȂ��ē���A�q���͌��̑�g���{�Ƃ��đ����A
�]�˒����̉����ő��Ôˁi��t������S���Ò��j�̑喼�ƂȂ��Ă��܂��B
���j�̂��Ƒ��Â����
https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018013100486/file_contents/11_TakoKanko_A4_p2229m.pdf
���āA�N�r�̖��i�������͏����j�͓`���ł͓V��14�N�i1586�j�����̉ƍN����J��̐_�ʗ͂����间���u?�֓��i��傤����Ƃ��j�v��������A
��X�̉ƕ�Ƃ��ē`���A���݂͂��q�����瑽�Ò��Ɋ���Ă��܂��B
����?�֓��̓����N��̒����Ɏʐ^�������ł����A�ǂ����Ă��~�C�����������j�����B���E�X�R�E���j�H
���̓����܂߂āA�ƍN�͑����������甕���i�D���ł���ˁB
637�l�Ԏ����l�N
2023/02/10(��) 11:13:58.34ID:DRzxnt9X ����M�c�œ�Ɩf�Ղ��Ă�M���T��������
�Ɠz���A���e�i�����������
�Ɠz���A���e�i�����������
638�l�Ԏ����l�N
2023/02/10(��) 15:03:07.54ID:GWEK21bA �v���Ɖƕ�E?�֓�(��傤����Ƃ�)
https://adeac.jp/tako-town/texthtml/d100010/mp000010-100010/images/1-kuchie007-2.jpg
�V���\�l�N(��ܔ��Z)�N�r�̏��ɉƍN����?�֓�(��傤����Ƃ�)(���G�Q��)�������Ă���B�����Ƃł͑�X�����`���A���݂�
���Ƃ��瑽�Ò��Ɋ��꒬����ŕۊǂ��Ă���B����ɂ܂��`�������q���Ƃ��ĕt�����Ă���A����ɂ��A�u���̗�����
���̐̋��s�䏊�ɖ�Ȗ�ȉ������o�����A���̂��ߌ䏊���ŕa�����₦�Ȃ������B����œ���(�v��)�̐�c��������|�Ŏ˗��Ƃ����B
���ׂ̈ɕa�����₦���Ƃ̗R�A������L�O���v���Ƃɉ������������̂ł���B�܂������̏����ɝ��(�����)�������A�_����
�����Ă��鎞�ɁA���̗����ɂ������������������Ă��J����������J���~��_���ɑ傢�Ɋ�ꂽ�Ƃ̗R�v(���a�\�O�N�\���Z����)�Ƃ���B
https://adeac.jp/tako-town/text-list/d100010/ht000720
������͑��Ò��j�̊Y������
https://adeac.jp/tako-town/texthtml/d100010/mp000010-100010/images/1-kuchie007-2.jpg
�V���\�l�N(��ܔ��Z)�N�r�̏��ɉƍN����?�֓�(��傤����Ƃ�)(���G�Q��)�������Ă���B�����Ƃł͑�X�����`���A���݂�
���Ƃ��瑽�Ò��Ɋ��꒬����ŕۊǂ��Ă���B����ɂ܂��`�������q���Ƃ��ĕt�����Ă���A����ɂ��A�u���̗�����
���̐̋��s�䏊�ɖ�Ȗ�ȉ������o�����A���̂��ߌ䏊���ŕa�����₦�Ȃ������B����œ���(�v��)�̐�c��������|�Ŏ˗��Ƃ����B
���ׂ̈ɕa�����₦���Ƃ̗R�A������L�O���v���Ƃɉ������������̂ł���B�܂������̏����ɝ��(�����)�������A�_����
�����Ă��鎞�ɁA���̗����ɂ������������������Ă��J����������J���~��_���ɑ傢�Ɋ�ꂽ�Ƃ̗R�v(���a�\�O�N�\���Z����)�Ƃ���B
https://adeac.jp/tako-town/text-list/d100010/ht000720
������͑��Ò��j�̊Y������
639�l�Ԏ����l�N
2023/02/10(��) 18:32:27.56ID:9CUTqSK9 >>634�̑���
�u�����ƊՒk�v���u�ɉ�̏��m�R���̎��v
�ɉ�̗��X���̒��ɂ��ȑO����ɉ���o�č���⌠���l�Ɏd���Ă����҂������B
�������������͓x�X�̕���������S�����ƌĂ�A���s�Y�E�q��(�����ۉp�A�����̒��Z�̑��q)�͎o��ɂĕ��킵�A�������q(�����ې��A�����̌Z)�͎O�������œ������ɁA�����ې�(���������ƕ����ې��A�����q�Ƃ͕ʐl)�͓x�X�̌M�������艶�^�����������B
�E�̓�S�l�̈ɉ�҂͕��������g�ƂȂ����B
���������͑����̉ƕ��ł���Ƃ͂�������`���̍�����铢�����삯�̓����ō����A��Ɛl�̒��ł����E��m���Ă����B
���̂��߈ɉ�҂̓��ƂȂ��Ă���͓�S�l�̈ɉ�҂͎��R�ɉƗ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�ɉ�҂͖��O�Ȃ�������ɏ]���A���̔N(1582�N)�ɓ��B�R�̉������Ƃ��ēV�_�a�Ƃ����~���g������Ă����B
�㌎�����A�G���吨�Ă��Ă���ɓ��̍��쏬���Ƃ����Ԃ̒�@���������h��N�e�ɖ������A�ɉ�m��l���E�ѓ���Ԃ��Ď����邽�߂́u�E�т��܁v�Ƃ����z�������肱�Ƃ��Ƃ������T�����B
���\�ܓ��ɖ��ɏ]���ɉ�̎҂ǂ��͖�X���ɍԂ����������B
�������ĐM���E�����e�q��オ�ׂ��Ȃ������k���̍Ԃ��ׂƂ��ɉ�O�͍������B
���N�A�b��̂�����(�]���A���q���)�Ƃ����Ԃ��ɉ�O�͍U�ߎ��A���N���N(1583�N)�ɂ͕������͊��a(��a��)�A���������͒J������ɉ�O��S�l���]���Ĕ�������\�܂Ŏ�����B
�u�ɉ�җR�����v���Q�l�ɂ��Ă���悤��
�u�����ƊՒk�v���u�ɉ�̏��m�R���̎��v
�ɉ�̗��X���̒��ɂ��ȑO����ɉ���o�č���⌠���l�Ɏd���Ă����҂������B
�������������͓x�X�̕���������S�����ƌĂ�A���s�Y�E�q��(�����ۉp�A�����̒��Z�̑��q)�͎o��ɂĕ��킵�A�������q(�����ې��A�����̌Z)�͎O�������œ������ɁA�����ې�(���������ƕ����ې��A�����q�Ƃ͕ʐl)�͓x�X�̌M�������艶�^�����������B
�E�̓�S�l�̈ɉ�҂͕��������g�ƂȂ����B
���������͑����̉ƕ��ł���Ƃ͂�������`���̍�����铢�����삯�̓����ō����A��Ɛl�̒��ł����E��m���Ă����B
���̂��߈ɉ�҂̓��ƂȂ��Ă���͓�S�l�̈ɉ�҂͎��R�ɉƗ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�ɉ�҂͖��O�Ȃ�������ɏ]���A���̔N(1582�N)�ɓ��B�R�̉������Ƃ��ēV�_�a�Ƃ����~���g������Ă����B
�㌎�����A�G���吨�Ă��Ă���ɓ��̍��쏬���Ƃ����Ԃ̒�@���������h��N�e�ɖ������A�ɉ�m��l���E�ѓ���Ԃ��Ď����邽�߂́u�E�т��܁v�Ƃ����z�������肱�Ƃ��Ƃ������T�����B
���\�ܓ��ɖ��ɏ]���ɉ�̎҂ǂ��͖�X���ɍԂ����������B
�������ĐM���E�����e�q��オ�ׂ��Ȃ������k���̍Ԃ��ׂƂ��ɉ�O�͍������B
���N�A�b��̂�����(�]���A���q���)�Ƃ����Ԃ��ɉ�O�͍U�ߎ��A���N���N(1583�N)�ɂ͕������͊��a(��a��)�A���������͒J������ɉ�O��S�l���]���Ĕ�������\�܂Ŏ�����B
�u�ɉ�җR�����v���Q�l�ɂ��Ă���悤��
640�l�Ԏ����l�N
2023/02/11(�y) 10:36:28.10ID:V7PRnp0X >>636
�����A�ٕ�킶��Ȃ���A�v���͈ٕ���ł��˂�
�����A�ٕ�킶��Ȃ���A�v���͈ٕ���ł��˂�
641�l�Ԏ����l�N
2023/02/11(�y) 11:59:15.16ID:Jx7Icl4Q ���鎞���c�M�����͂��̂悤�Ɍ���ꂽ
�u���̒��̐l�͐F�X�ł���B���ɕ��ʂ��L���Ă��ˊo�̂Ȃ��l���L��A�ˊo���L���Ă����߂̂Ȃ��l������B
���߂��L���Ă��l�����m��ʎ҂�����B
�l�����m��ʎ҂͑�g�̏ꍇ�A�ނ��Ƃ�܂��Ă���ҋ��͂��̏\�l�̓����l�قǂɁA���ɗ����Ȃ��҂������B
���g�̏ꍇ�A�ނ��e�����t���������y�́A�������F�l�ɋ߂Â��B
���̂悤�ɁA�l�͐F�X�l�X�ɕς���Č����邪�A�v�͂����A���ʂ̎���ʐS�̂䂦�ł���B
���ʂ����\�X�D��Ă���l�́A�ˊo�ɂ������ɂ��A�l��m��ɂ����𐬂��ɂ��A�����ɂ��Ă��\��
�s�����̂��B���̂悤�ɁA�l�Ԃ́u���ʁv�̓������F�̌��ł���ƔF�����A���Ɏu���A�[�ׂɎv���قǂ�
���ʂ��悭����B�v
���̂悤�ɐM�����͋������ꂽ�̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�u���̒��̐l�͐F�X�ł���B���ɕ��ʂ��L���Ă��ˊo�̂Ȃ��l���L��A�ˊo���L���Ă����߂̂Ȃ��l������B
���߂��L���Ă��l�����m��ʎ҂�����B
�l�����m��ʎ҂͑�g�̏ꍇ�A�ނ��Ƃ�܂��Ă���ҋ��͂��̏\�l�̓����l�قǂɁA���ɗ����Ȃ��҂������B
���g�̏ꍇ�A�ނ��e�����t���������y�́A�������F�l�ɋ߂Â��B
���̂悤�ɁA�l�͐F�X�l�X�ɕς���Č����邪�A�v�͂����A���ʂ̎���ʐS�̂䂦�ł���B
���ʂ����\�X�D��Ă���l�́A�ˊo�ɂ������ɂ��A�l��m��ɂ����𐬂��ɂ��A�����ɂ��Ă��\��
�s�����̂��B���̂悤�ɁA�l�Ԃ́u���ʁv�̓������F�̌��ł���ƔF�����A���Ɏu���A�[�ׂɎv���قǂ�
���ʂ��悭����B�v
���̂悤�ɐM�����͋������ꂽ�̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
642�l�Ԏ����l�N
2023/02/11(�y) 12:21:33.73ID:x/H7JQan �b�z�R�ӂ̕��c�J�߂͋�X�����Ċ��X����
643�l�Ԏ����l�N
2023/02/11(�y) 12:32:37.58ID:lk3JOlum �u����G�ځv���瓇���߂̑��q����
�����߂̒��q�V�g(���M��)�͊փ����œ������ɂ����B
���j�O�j�͐��A�Ȏq�ő��܁A�Z�l�قǂ��R���Ɉ����A��ĉB��Ă����B
�\�N�قnjZ��ŕ��{���Ă������Ƃ��Ƃ��Ƃ̉����₦�����ɂȂ����B
�����ŌZ��͖��k���A��𓇍��߂̑��q�Ƃ��ē�������ďx�{�ɎQ�����B
����͉��܂ČZ�����{�����Ƃ���v���ł������B
�������Ē�͘S�ɓ���A�Z�͖J�����B
�������Z�͒�Ɨ����̂��߂��������̂��A���̂܂x�{�ɂƂǂ܂��Ȗ�Ȓ�̘S�̗l�q�����ɍs�����B
�Ƃ��Ƃ��S�̔Ԑl�Ɍ���߂��A����Ȃ��Ǝv�����Z��
�u���͎��������߂̑��q�ł��B���{�����߂��̂悤�ɂ͂��炢�܂����B
�ǂ����������Z�킪���߂ɂ������̂��́A��ɗ���݂�����Ă��������v�Ɛ\�����B
�ƍN���͌Z��̍F�s�S�Ɋ��S���A����x�͂ɏ����A��q�O�l�ɒ�����}����^���Ȃ������Ƃ����B
�����߂̒��q�V�g(���M��)�͊փ����œ������ɂ����B
���j�O�j�͐��A�Ȏq�ő��܁A�Z�l�قǂ��R���Ɉ����A��ĉB��Ă����B
�\�N�قnjZ��ŕ��{���Ă������Ƃ��Ƃ��Ƃ̉����₦�����ɂȂ����B
�����ŌZ��͖��k���A��𓇍��߂̑��q�Ƃ��ē�������ďx�{�ɎQ�����B
����͉��܂ČZ�����{�����Ƃ���v���ł������B
�������Ē�͘S�ɓ���A�Z�͖J�����B
�������Z�͒�Ɨ����̂��߂��������̂��A���̂܂x�{�ɂƂǂ܂��Ȗ�Ȓ�̘S�̗l�q�����ɍs�����B
�Ƃ��Ƃ��S�̔Ԑl�Ɍ���߂��A����Ȃ��Ǝv�����Z��
�u���͎��������߂̑��q�ł��B���{�����߂��̂悤�ɂ͂��炢�܂����B
�ǂ����������Z�킪���߂ɂ������̂��́A��ɗ���݂�����Ă��������v�Ɛ\�����B
�ƍN���͌Z��̍F�s�S�Ɋ��S���A����x�͂ɏ����A��q�O�l�ɒ�����}����^���Ȃ������Ƃ����B
644�l�Ԏ����l�N
2023/02/11(�y) 13:40:34.46ID:zixhe24u �Z���D�ꂽ��͂��Ȃ�
645�l�Ԏ����l�N
2023/02/11(�y) 21:08:55.35ID:2iPvre8q >>644
��v��(�Z)�Ɛ�ΏG�v(��)
�{������(�Z)�Ɩ{�����d(��)
�ǂ�����Z�̕����ӔN�w�^�ł������炻�������邾�����������
��v��(�Z)�Ɛ�ΏG�v(��)
�{������(�Z)�Ɩ{�����d(��)
�ǂ�����Z�̕����ӔN�w�^�ł������炻�������邾�����������
646�l�Ԏ����l�N
2023/02/12(��) 18:48:58.34ID:8AdD7kWK �u�����ƊՒk�v����u�匴�������ƕ��╽�E�q�化�܂̎��v
�����v���e�g�̒�̕��E�q�傪�匴�������N���ƌ��܂��A���E�q�傪���������Ƃ���ŊF�ň����������B
���̎��A����e�g�͌�Ɛl�̏h�V�ō匴�N���͏��g�Ŏ�N�ł������B
�e�g���\�����ɂ́u�������͂��̐g�̍˒q�E�ɂ����ĕC�G������̂��Ȃ��A��̌�p�ɂ����Ɨ��ׂ��l�ނł���B
����ł킪��͂��قǂ̎҂ł͂Ȃ��A��p�ɗ��悤�ɂ��v���Ȃ��A���N�ǂ����悤�v�ƒǂ����B
�͂����č匴�N���͓V���̎O���Ə̂����Í��̉p���ƂȂ����B
����e�g�̐S���ɒq�E���Ȃ������Ȃ�A���l�̂��������p���čN�������ł��낤�B
�u�����O�\�O�����̊ԁA����㐙���c�̉ƒ��ɂ��\�l�����Ȃ��ł��낤���E�̏��ł���v
�ƕ����l�݂͂ȗ܂𗬂��A�e�g��}��҂͈�l�����Ȃ������B
�u�������s�^�v�ɂ������悤�Șb������悤��
�e�g�̒�̕��E�q��͕���N���̂��Ƃ炵��
�����v���e�g�̒�̕��E�q�傪�匴�������N���ƌ��܂��A���E�q�傪���������Ƃ���ŊF�ň����������B
���̎��A����e�g�͌�Ɛl�̏h�V�ō匴�N���͏��g�Ŏ�N�ł������B
�e�g���\�����ɂ́u�������͂��̐g�̍˒q�E�ɂ����ĕC�G������̂��Ȃ��A��̌�p�ɂ����Ɨ��ׂ��l�ނł���B
����ł킪��͂��قǂ̎҂ł͂Ȃ��A��p�ɗ��悤�ɂ��v���Ȃ��A���N�ǂ����悤�v�ƒǂ����B
�͂����č匴�N���͓V���̎O���Ə̂����Í��̉p���ƂȂ����B
����e�g�̐S���ɒq�E���Ȃ������Ȃ�A���l�̂��������p���čN�������ł��낤�B
�u�����O�\�O�����̊ԁA����㐙���c�̉ƒ��ɂ��\�l�����Ȃ��ł��낤���E�̏��ł���v
�ƕ����l�݂͂ȗ܂𗬂��A�e�g��}��҂͈�l�����Ȃ������B
�u�������s�^�v�ɂ������悤�Șb������悤��
�e�g�̒�̕��E�q��͕���N���̂��Ƃ炵��
647�l�Ԏ����l�N
2023/02/12(��) 20:06:18.79ID:DoJh3FWu �r���܂ŏ�����������������N�̉��ՂɊ������܂�Ĉ�x�j�ł����v���݂����Ȑ������͌�������Ȃ�
648�l�Ԏ����l�N
2023/02/12(��) 20:34:35.32ID:7lnbcluG ���O�̊��z�Ȃǂ��ł���������
649�l�Ԏ����l�N
2023/02/12(��) 22:51:51.07ID:/PJailbK ����납�H
650�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 09:18:02.88ID:vRFDUa9W >>641
�悭�킩��Ȃ������ʂ����Ƃ���l�͍ˊo�ɂ����Ă��悭�s���Ƃ������_�Ȃ̂ɖ`���ɕ��ʂ����Ă��ˊo�̂Ȃ��l��������̂͂ǂ������킯�Ȃ낤
�悭�킩��Ȃ������ʂ����Ƃ���l�͍ˊo�ɂ����Ă��悭�s���Ƃ������_�Ȃ̂ɖ`���ɕ��ʂ����Ă��ˊo�̂Ȃ��l��������̂͂ǂ������킯�Ȃ낤
651�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 09:40:07.54ID:f0v8HfSC �܂����㕶�̐��т����������A�z������̂�
������Ē����ł��������Ȃ��̂��H
������Ē����ł��������Ȃ��̂��H
652�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 09:56:52.71ID:vRFDUa9W ���Ⴀ�����������Ă�������
653�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 10:39:23.95ID:f/hNEtrI �l�ɋ�������O�ɒ��ׂ��o�J
�������̎����w�Z�����蒼��
�������̎����w�Z�����蒼��
654�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 10:45:44.65ID:vRFDUa9W ���ǂ킩���ĂȂ��đ�
655�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 11:04:20.08ID:sKk5amfd https://dl.ndl.go.jp/pid/2563278/1/60
�u�b�z�R�Ӂv���l�\���猴�������o����
�Ȃ����̒��O�ɐM���͕��ʂƍˊo�͕ʂƂ����b�������Ă�
�����M����
�����̐l�X�F�X�L�B
���ɕ��ʗL�čˊo�Ȃ��l�L�B
�ˊo�L�ĉ����Ȃ��l�L�B
�����L�Ď��߂̂Ȃ��l�ɗL�B
���ߗL�Đl��������ʐl�L�B
�l��������ʎ҂͑�g�͐��h����ҋ��\�l�̓����l���ɂ����ʎґ��B
���g�͑���������T�y�̂�������ɋߕt��B
�@���F�X�l�X�ւĂ݂�ꋤ����͑����ʂ̂�����ʐS��B
���ʂ��֔\�X������ėL�l�͍ˊo�ɂ������ɂ��l������ɂ����Ȃ��ɂ������ɕt�Ă��悩���B
������ɐl�Ԃ͕��ʂ̓��F�̖{�Ƒ��m���ɐS�����[�ւɂ����ӂĂ����ʂ�\�����
�M�������
�u�b�z�R�Ӂv���l�\���猴�������o����
�Ȃ����̒��O�ɐM���͕��ʂƍˊo�͕ʂƂ����b�������Ă�
�����M����
�����̐l�X�F�X�L�B
���ɕ��ʗL�čˊo�Ȃ��l�L�B
�ˊo�L�ĉ����Ȃ��l�L�B
�����L�Ď��߂̂Ȃ��l�ɗL�B
���ߗL�Đl��������ʐl�L�B
�l��������ʎ҂͑�g�͐��h����ҋ��\�l�̓����l���ɂ����ʎґ��B
���g�͑���������T�y�̂�������ɋߕt��B
�@���F�X�l�X�ւĂ݂�ꋤ����͑����ʂ̂�����ʐS��B
���ʂ��֔\�X������ėL�l�͍ˊo�ɂ������ɂ��l������ɂ����Ȃ��ɂ������ɕt�Ă��悩���B
������ɐl�Ԃ͕��ʂ̓��F�̖{�Ƒ��m���ɐS�����[�ւɂ����ӂĂ����ʂ�\�����
�M�������
656�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 11:13:00.06ID:vRFDUa9W �����������ƂȂ�킩��܂�
657�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 11:19:30.93ID:f/hNEtrI ���ǂ킩���ĂȂ��đ�
658�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 11:37:12.52ID:ATiw+wnZ �����@�킩��܂���
���@���@�킩��܂�
����ς茻�㕶�̐��т�����������w
���@���@�킩��܂�
����ς茻�㕶�̐��т�����������w
659�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 11:41:17.35ID:vRFDUa9W �O�Ɍ��㕶�̐��ш����������ł����H�ƚ}���Ă��������ĂĂ��炢
660�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 11:45:59.48ID:ATiw+wnZ ���������猋�ǂ킩��Ȃ������o�J�܂�������w
661�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 11:47:29.40ID:ATiw+wnZ >>659
���ꂨ�O����A���������Ƃ���̂��H
���ꂨ�O����A���������Ƃ���̂��H
662�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 13:06:51.87ID:x8m+BH9t ����ȂƂ���Ń}�E���g
663�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 13:37:36.17ID:3dIo1dMb �P��s��
664�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 14:09:57.39ID:vRFDUa9W �I�E���Ԃ��j�L���n�b�X�����Ăď�
665�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 14:13:40.07ID:/JwyCt26 �Ӗ���������Ȃ��o�J���������^���Ԃő��������
666�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 14:20:28.31ID:47wXVBBv >>656
�����L�ڂ��Ă�����ė��������H��
�����L�ڂ��Ă�����ė��������H��
667�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 17:50:04.60ID:ZBd4SaRa ���ǂ킩���ĂȂ��đ�
668�l�Ԏ����l�N
2023/02/14(��) 20:42:38.59ID:UZkk1VwY ���鎞�A�n����Z��i�M�t�j�����̂悤�ɐ\�����B
�u���c�M�����̐l�������g�����́A���Ƃ����̕��ʂɋy�Ȃ��B�ǂ����������ƌ����A
�Ⴆ�ΐE�i�ٔ����j��p���Ă̌����i�ٔ��j�����Ȃǂ̍ق��悤�́A����ǂݕ���m���āA�����ɂ�����
���炩�Ȃ�l�̋Z�ł���Ǝv����̂����A����N�ɂ͌����Z��i�Ո��j�Ƃ����卄���̂���i�r�j�l��
�E�����t����ꂽ�B���������������s�v�c���Ɛ\�����͎̂�����ł͂Ȃ��A�e�X����荹�������̂����A
���ʂƂ��Ă��̌����Z��̔��F�́A�Ȃ�Ƃ��ǂ��d�u�ł������B
�����ł͂��������A���̌����Z�炪�����ɂ����肫��ɂȂ�ƁA���X�̋��ځi�����j�ɂ����镐�m���̌�p��
����ɂȂ�Ƃ��ĕ�s���グ��ꂽ���A���̌サ�炭�A��C�O��������C�̐E����܂�Ȃ��������A
�܂������Z��a�قnj����ɗ����A�ᔻ��p����ٔ����͖����ƌ���ꂽ���Ƃ́A�M�����̌�H�v��
�Ȃ��������炱���ł���B
���̂悤�ł��������炱���A�M������������n���������A�������G���[���ł̓������L�鎞���A
���X�̕��m�A�召���Ɏ��O�̎��͐\���ɋy���A���ɎG�l�܂Łu��߂Ă���͏����낤�v�Ǝv���A
�������P�ނ��ׂ��ȂǂƂ͍l���Ȃ������B����͐M�����̒q�������܂��܂��̂ł���B�v
�w�b�z�R�Ӂx
�u���c�M�����̐l�������g�����́A���Ƃ����̕��ʂɋy�Ȃ��B�ǂ����������ƌ����A
�Ⴆ�ΐE�i�ٔ����j��p���Ă̌����i�ٔ��j�����Ȃǂ̍ق��悤�́A����ǂݕ���m���āA�����ɂ�����
���炩�Ȃ�l�̋Z�ł���Ǝv����̂����A����N�ɂ͌����Z��i�Ո��j�Ƃ����卄���̂���i�r�j�l��
�E�����t����ꂽ�B���������������s�v�c���Ɛ\�����͎̂�����ł͂Ȃ��A�e�X����荹�������̂����A
���ʂƂ��Ă��̌����Z��̔��F�́A�Ȃ�Ƃ��ǂ��d�u�ł������B
�����ł͂��������A���̌����Z�炪�����ɂ����肫��ɂȂ�ƁA���X�̋��ځi�����j�ɂ����镐�m���̌�p��
����ɂȂ�Ƃ��ĕ�s���グ��ꂽ���A���̌サ�炭�A��C�O��������C�̐E����܂�Ȃ��������A
�܂������Z��a�قnj����ɗ����A�ᔻ��p����ٔ����͖����ƌ���ꂽ���Ƃ́A�M�����̌�H�v��
�Ȃ��������炱���ł���B
���̂悤�ł��������炱���A�M������������n���������A�������G���[���ł̓������L�鎞���A
���X�̕��m�A�召���Ɏ��O�̎��͐\���ɋy���A���ɎG�l�܂Łu��߂Ă���͏����낤�v�Ǝv���A
�������P�ނ��ׂ��ȂǂƂ͍l���Ȃ������B����͐M�����̒q�������܂��܂��̂ł���B�v
�w�b�z�R�Ӂx
669�l�Ԏ����l�N
2023/02/15(��) 17:10:30.83ID:7xbgD4U9 ���̊��ɐ����͒Ⴂ�̂�
670�l�Ԏ����l�N
2023/02/17(��) 15:22:56.61ID:JlT8fkiM ���c�M��������\���̎��̎��B
�R�{����Ɛ\���卄�̕��i����́j�́A�����̎蕿����ł͂Ȃ����@���ł������B
���鎞�A�M�B�z�K�ɉ����ē암�i�@�G�j�a�̓��̎҂ł������Έ䓡�O�Y�Ƃ����j��암�a��
���s���悤�Ƃ������A���s�����̎҂͎a���蓦���悤�Ƃ����B
���̍��A�R�{����͂��̓암�a�̌��֗��Ă���A�ނ��߂��ɋ������~�ɁA���̓��O�Y��
�a�艟������ł����B
����Ɋ���͓�����荇�킳���A�����ɖ_���������̂����ƁA�������đg�݂�����A
��������ē암�a�֓n�����B���̎���������A�O�������������A�����Ɛ\���قǂ̂��̂ł��Ȃ������B
���̂Ȃ�O�\���̓��ɂ��ׂĕ�����������ł���B
�y�ʁA����͕��ӂ̎������������̎������x�ɂ����ď������������A���\�Z�������r���������B
���̎����̓암�a�͈������������Ă����̂����A���̎��͉��������Ȃ������B
�w�b�z�R�Ӂx
�R�{����Ɛ\���卄�̕��i����́j�́A�����̎蕿����ł͂Ȃ����@���ł������B
���鎞�A�M�B�z�K�ɉ����ē암�i�@�G�j�a�̓��̎҂ł������Έ䓡�O�Y�Ƃ����j��암�a��
���s���悤�Ƃ������A���s�����̎҂͎a���蓦���悤�Ƃ����B
���̍��A�R�{����͂��̓암�a�̌��֗��Ă���A�ނ��߂��ɋ������~�ɁA���̓��O�Y��
�a�艟������ł����B
����Ɋ���͓�����荇�킳���A�����ɖ_���������̂����ƁA�������đg�݂�����A
��������ē암�a�֓n�����B���̎���������A�O�������������A�����Ɛ\���قǂ̂��̂ł��Ȃ������B
���̂Ȃ�O�\���̓��ɂ��ׂĕ�����������ł���B
�y�ʁA����͕��ӂ̎������������̎������x�ɂ����ď������������A���\�Z�������r���������B
���̎����̓암�a�͈������������Ă����̂����A���̎��͉��������Ȃ������B
�w�b�z�R�Ӂx
671�l�Ԏ����l�N
2023/02/18(�y) 19:22:49.71ID:PgV/ljYw �u�����ƊՒk�v���u�G�g���@�ƍN���̗��h�䗈�Ղ̂��Ɓv
�匴�N�����㗌��������ƁA�G�g�������ɂ��̗��h�Ɍ䗈�Ղ���A���b�ł���Ə܂���
�u���Ė����y���̎��́A�̗�������߂ɗ��G�X�q�łȂ������悤�ɂ�����ʔ������낤�B���̂悤�ɐS������v
�Ən�ӂ�s�����Ȃ������B
�����o��Ȃ��ꂽ���A�ʂ����ĉE�̎�߂ƉG�X�q�őΖʂȂ��ꂽ�Ƃ����B
�G�g�ƉƍN�Ƃ̘a�r�̎��A�܂��匴�N�����g�҂Ƃ��ď㗌�������̘b�̂悤�����A�^�C�g���ɂ͉ƍN�Ə�����Ă���B
�ƍN�Ƃ̑Ζʂ̑O��ɏh�ɖK�˂čs������b�Ƃ̍������낤���B
�匴�N�����㗌��������ƁA�G�g�������ɂ��̗��h�Ɍ䗈�Ղ���A���b�ł���Ə܂���
�u���Ė����y���̎��́A�̗�������߂ɗ��G�X�q�łȂ������悤�ɂ�����ʔ������낤�B���̂悤�ɐS������v
�Ən�ӂ�s�����Ȃ������B
�����o��Ȃ��ꂽ���A�ʂ����ĉE�̎�߂ƉG�X�q�őΖʂȂ��ꂽ�Ƃ����B
�G�g�ƉƍN�Ƃ̘a�r�̎��A�܂��匴�N�����g�҂Ƃ��ď㗌�������̘b�̂悤�����A�^�C�g���ɂ͉ƍN�Ə�����Ă���B
�ƍN�Ƃ̑Ζʂ̑O��ɏh�ɖK�˂čs������b�Ƃ̍������낤���B
672�l�Ԏ����l�N
2023/02/20(��) 20:17:28.56ID:XEaRtdGo �u���ƊՒk�v�����Ă̐w�̎��̓���G���̗l�q
���̐w�ł̌܌������̍���O�ɏG�����͖����̌R���������Ȃ������B
���c�����A�����Ö��ɂ��Ă͓Ɨ����������ł͂Ȃ��{������(�{�����M�̎O�j)�̕����ɑ����Ă����B
�����̒��O�A��R�������Ă���Ƃ���ɒN����Ƃ��Ȃ��u���R�l�䐬�v�ƌ����o�������߁A�����̉Ö��͂��ڌ����̂��߂ɒʘH�֏o���B
�G�����͈�R�ō����Z�A�R���̔��̉H�D�����߂���A����Ƃ��������O���̔n�ɍE���̔��̓��������ď�����Ă����B
����͏\�����̒����A���̂ق��k���̎m��\�l�قǂ��������Ă����B
���c�����E�����Ö��������ɂȂ藼�l�̕��֏�肩����ꂽ���߁A���l�͔n�̍��E�̌��ɂ����B
�G�����́u�G��ł����炵��ֈ����ꂽ�͎̂c�O���v�Ƃ������������
���l���u���̂����G�͂܂��l�����o���̂ŁA�����ɂ������ɂȂ�ł��傤�B�v���̂܂܂̌���ƂȂ�܂��傤�v
�ƌ����Ƃ��@�����悭�Ȃ����B
�����E�Ö��Ɂu�����߂��Ă悢���v�Ƃ��������ꂽ���߁A���l�͔����ɖ߂����B
�r���A�{�����M��������������A�c��Ŕ����Ȃ���敨�ɏ���Ēʂ����B
���c�������u���R�l�͂����ƈႢ�y���l�q���ȁv�Ɛ\����
�����Ö��́u�����ɂ������ɂ��A���̂悤�Ɍy���̂͌�Ƃ̕Ȃ��낤�v�Ɠ������B
�����͐[�����S���u�G�����͏�X��s�V���������A�R�@�ɂ����Ă͖����y���s���Ƃ������Ƃ��v
�Ə^�����Ƃ����B
���̐w�ł̌܌������̍���O�ɏG�����͖����̌R���������Ȃ������B
���c�����A�����Ö��ɂ��Ă͓Ɨ����������ł͂Ȃ��{������(�{�����M�̎O�j)�̕����ɑ����Ă����B
�����̒��O�A��R�������Ă���Ƃ���ɒN����Ƃ��Ȃ��u���R�l�䐬�v�ƌ����o�������߁A�����̉Ö��͂��ڌ����̂��߂ɒʘH�֏o���B
�G�����͈�R�ō����Z�A�R���̔��̉H�D�����߂���A����Ƃ��������O���̔n�ɍE���̔��̓��������ď�����Ă����B
����͏\�����̒����A���̂ق��k���̎m��\�l�قǂ��������Ă����B
���c�����E�����Ö��������ɂȂ藼�l�̕��֏�肩����ꂽ���߁A���l�͔n�̍��E�̌��ɂ����B
�G�����́u�G��ł����炵��ֈ����ꂽ�͎̂c�O���v�Ƃ������������
���l���u���̂����G�͂܂��l�����o���̂ŁA�����ɂ������ɂȂ�ł��傤�B�v���̂܂܂̌���ƂȂ�܂��傤�v
�ƌ����Ƃ��@�����悭�Ȃ����B
�����E�Ö��Ɂu�����߂��Ă悢���v�Ƃ��������ꂽ���߁A���l�͔����ɖ߂����B
�r���A�{�����M��������������A�c��Ŕ����Ȃ���敨�ɏ���Ēʂ����B
���c�������u���R�l�͂����ƈႢ�y���l�q���ȁv�Ɛ\����
�����Ö��́u�����ɂ������ɂ��A���̂悤�Ɍy���̂͌�Ƃ̕Ȃ��낤�v�Ɠ������B
�����͐[�����S���u�G�����͏�X��s�V���������A�R�@�ɂ����Ă͖����y���s���Ƃ������Ƃ��v
�Ə^�����Ƃ����B
673�l�Ԏ����l�N
2023/02/20(��) 20:18:55.44ID:XEaRtdGo >�����̉Ö��͂��ڌ����̂��߂ɒʘH�֏o���B
��
>�����ƉÖ��͂��ڌ����̂��߂ɒʘH�֏o���B
�ł��B�����܂���
��
>�����ƉÖ��͂��ڌ����̂��߂ɒʘH�֏o���B
�ł��B�����܂���
674�l�Ԏ����l�N
2023/02/21(��) 20:27:41.98ID:bL5twcMw �u���ƊՒk�v����^�c�叕
�܌������̍���O�ɐ^�c���q�卲(�^�c�M��)�͏G��������o�n����Ȃ����߁A�q���叕��l���ɏ�֒u���A���g�͏o�w���邱�Ƃɂ����B
�叕�͏\�܍ł�������
�u����͂����������ӂ���Ă���悤�ł��B
���͕���̉��ɐ��܂�Ă��A����܂ŕЎ������ꂸ���܂����B
���N�A����ɓ��鎞�ɕ��Ƃ͐����ʂ�A���̌�̕ꂩ��̕��ł�
�u�݂��ɉ���Ƃ͂����Ȃ��ł��傤�B
�ǂ������̌�Ō�����͂��Ȃ����B�����悤�Ƃ����A�������œ������ɂ��Đ^�c�̖��������Ȃ����v
�Ə�X�����Ă���܂��B
�������������̂Ăď�ɖ߂邱�Ƃ͂ł��܂���v
�ƍ��q�卲�̑��Ɏ��t���ċ������B
���q�卲���^�c�̌R���������ʂ��̂͂Ȃ������B
���q�卲�͗܂�@���A�͂����Ƒ叕�����߂�
�u���m�̉Ƃɐ��ꂽ�҂͒��`�������ɂ��ĕ����Y��A�����̐g��Y�����̂��B��֓���B
�G�����䉮�`�̌䑤�Ŏ��˂����ɖ��r�ɂď��荇�����낤�B
�b���̕ʂ��߂��ނ̂͋|���̉Ƃɐ��܂ꂽ�҂Ƃ��Đr���������܂����B������֓���v
�Ǝ��t��������������ƁA�叕�͖��c�ɂ����ɕ�������
�u���悤�ł������ɎQ��܂��B�����ł܂�������܂��傤�v�ƕʂꂽ�B
���q�卲�͋C�ɂ��Ȃ��ӂ�����Ă������̂́A�܂œ������킩��ʂقǂł������B
�܌������̍���O�ɐ^�c���q�卲(�^�c�M��)�͏G��������o�n����Ȃ����߁A�q���叕��l���ɏ�֒u���A���g�͏o�w���邱�Ƃɂ����B
�叕�͏\�܍ł�������
�u����͂����������ӂ���Ă���悤�ł��B
���͕���̉��ɐ��܂�Ă��A����܂ŕЎ������ꂸ���܂����B
���N�A����ɓ��鎞�ɕ��Ƃ͐����ʂ�A���̌�̕ꂩ��̕��ł�
�u�݂��ɉ���Ƃ͂����Ȃ��ł��傤�B
�ǂ������̌�Ō�����͂��Ȃ����B�����悤�Ƃ����A�������œ������ɂ��Đ^�c�̖��������Ȃ����v
�Ə�X�����Ă���܂��B
�������������̂Ăď�ɖ߂邱�Ƃ͂ł��܂���v
�ƍ��q�卲�̑��Ɏ��t���ċ������B
���q�卲���^�c�̌R���������ʂ��̂͂Ȃ������B
���q�卲�͗܂�@���A�͂����Ƒ叕�����߂�
�u���m�̉Ƃɐ��ꂽ�҂͒��`�������ɂ��ĕ����Y��A�����̐g��Y�����̂��B��֓���B
�G�����䉮�`�̌䑤�Ŏ��˂����ɖ��r�ɂď��荇�����낤�B
�b���̕ʂ��߂��ނ̂͋|���̉Ƃɐ��܂ꂽ�҂Ƃ��Đr���������܂����B������֓���v
�Ǝ��t��������������ƁA�叕�͖��c�ɂ����ɕ�������
�u���悤�ł������ɎQ��܂��B�����ł܂�������܂��傤�v�ƕʂꂽ�B
���q�卲�͋C�ɂ��Ȃ��ӂ�����Ă������̂́A�܂œ������킩��ʂقǂł������B
675�l�Ԏ����l�N
2023/02/21(��) 20:29:36.12ID:bL5twcMw �叕�͏�ɓ���A�Y�����������݁A������l�ŏG�����̌䋟�����Ĉ��c�ȗւ̎�O��q���Ă����B
�����̒��H�����痂�����̌߂̍��܂ŁA�G�����Ƃ��̌䋟�O�\��l�͖�q�ɋl�߂Ă����B
�叕�͕��̍s�����C�ɂ��āA�钆�ɓ��ꂽ�l�ɕ��ɂ��Đq�˂��Ƃ���
�u�^�c�a�͓V�����O�ő吨�̓G�w�ɋ삯����A�n��Ő킢�A���̂̂����\�{�قǂɑ��ʂɂ������Ă���������܂����v
�Əڂ����\���҂����������߁A�叕�͗܂������ʂ����A
��ƕʂꂽ���u�Ŋ��ɂ͂���������ē������ɂ���v�Ɠn���ꂽ�����̐�������o���A�O�����������B
�������ďG�����̌䎩�Q��҂��Ă���ƁA�����b��(������v)�͕s���Ɏv��
�u�M�a�͈����_�c�̐킢�Ō҂ɑ��������ƕ����܂��B
�×{�̂��߂ɂ������o�Ȃ���B�^�c�̉��҂̂Ƃ���܂ő���͂������܂��傤�v
�ƌ��������A�叕�͕ԓ������A�O���������������B
�����߂̍��A�G�����͌䎩�Q�Ȃ���A���̒j���O�\��l�����Q���A��q�ɉ������������ɏ������B
�叕�������\�����ɑ~���莩�Q�������߁A����l�����l�u���������m�̎q���ł���v�Ɨ_�߂ʂ��̂͂Ȃ������Ƃ����B
�����̒��H�����痂�����̌߂̍��܂ŁA�G�����Ƃ��̌䋟�O�\��l�͖�q�ɋl�߂Ă����B
�叕�͕��̍s�����C�ɂ��āA�钆�ɓ��ꂽ�l�ɕ��ɂ��Đq�˂��Ƃ���
�u�^�c�a�͓V�����O�ő吨�̓G�w�ɋ삯����A�n��Ő킢�A���̂̂����\�{�قǂɑ��ʂɂ������Ă���������܂����v
�Əڂ����\���҂����������߁A�叕�͗܂������ʂ����A
��ƕʂꂽ���u�Ŋ��ɂ͂���������ē������ɂ���v�Ɠn���ꂽ�����̐�������o���A�O�����������B
�������ďG�����̌䎩�Q��҂��Ă���ƁA�����b��(������v)�͕s���Ɏv��
�u�M�a�͈����_�c�̐킢�Ō҂ɑ��������ƕ����܂��B
�×{�̂��߂ɂ������o�Ȃ���B�^�c�̉��҂̂Ƃ���܂ő���͂������܂��傤�v
�ƌ��������A�叕�͕ԓ������A�O���������������B
�����߂̍��A�G�����͌䎩�Q�Ȃ���A���̒j���O�\��l�����Q���A��q�ɉ������������ɏ������B
�叕�������\�����ɑ~���莩�Q�������߁A����l�����l�u���������m�̎q���ł���v�Ɨ_�߂ʂ��̂͂Ȃ������Ƃ����B
676�l�Ԏ����l�N
2023/02/22(��) 21:55:36.40ID:ZjICsJeG �u���ƊՒk�v����^�c�叕�ƎO�l�̏���
�G�����Ɍ䋟�����O�\��l�̂����A�������O�Y�͏\�܍A�y�쏯�ܘY�͏\���A�����\�O�Y�͏\�O�ŁA�O�l�͂�������G�����̌䏬���ł������B
�G�����䎩�Q�̎��A�G�����̏�ӂɂ��A��﨟�ǂ��͊F������邱�ƂƂȂ����B
�O�l�̎������Ɛ^�c�叕�͗c���ł���A�����핽���ƕ��c���g�������\������ꂽ�B
�O�l�̎������Ɛ^�c�叕�͂���������E���A�l�l�Ƃ����Ɍ������ĕ���Ŏ�������A�O�������炩�ɏ����A
��̂悤�Ȕ��������E���ƁA�l�l��x�ɐ��������A�������悭�ؕ������B
�핽���ƍ��g�͉�����I���Ɠ����̂āA�܂��ނ��ы������Ƃ����B
�G�����Ɍ䋟�����O�\��l�̂����A�������O�Y�͏\�܍A�y�쏯�ܘY�͏\���A�����\�O�Y�͏\�O�ŁA�O�l�͂�������G�����̌䏬���ł������B
�G�����䎩�Q�̎��A�G�����̏�ӂɂ��A��﨟�ǂ��͊F������邱�ƂƂȂ����B
�O�l�̎������Ɛ^�c�叕�͗c���ł���A�����핽���ƕ��c���g�������\������ꂽ�B
�O�l�̎������Ɛ^�c�叕�͂���������E���A�l�l�Ƃ����Ɍ������ĕ���Ŏ�������A�O�������炩�ɏ����A
��̂悤�Ȕ��������E���ƁA�l�l��x�ɐ��������A�������悭�ؕ������B
�핽���ƍ��g�͉�����I���Ɠ����̂āA�܂��ނ��ы������Ƃ����B
677�l�Ԏ����l�N
2023/02/22(��) 23:07:30.48ID:muSIJZw6 �N�������悻�̏��
678�l�Ԏ����l�N
2023/02/22(��) 23:15:28.01ID:QsUorrkW �_�N�ł�
679�l�Ԏ����l�N
2023/02/23(��) 19:40:08.37ID:0RbDe1Xr �u���ƊՒk�v���瓇���̗��̎��̓��엊��
���i�\�ܔN(1638�N)��\����̖�A�����̏邩�獕�c�A����A�瓇���ɖ铢���Ȃ���A���c���V�̋���̎����\�l�������ɂ����ƍ]�˂֒��i���������B
�瓇���u��O��|���Ȃǂ��Ă��ꂽ�B�Ȃ��Ȃ�����̈Ꝅ���͋����v�ƍ����Ă����B
��O�Ƃ����̂��ߍ]�ˏ�ɓo�邵�A���喼���F�ǂ��������̂��Ǝv�Ă��Ă���ƁA
�I�ɑ�[�����鋨�A���l�͂��̒m�点��
�u���Ă��߂ł������ł���B�ߓ����ɏ�͗����邾�낤�B
�瓇�͈�O���Ă��ꂽ�Ƃ͂����A����ɂ���҂ǂ��̕����Ƃ��Ă̊�ʂ̂قǂ��m�����ƌ�����v
�Ƃ��������ƁA���喼�͊F�X�����낦�ʊ�����Ă����B
�����������Ă��邤���ɗ����������g�҂��������߁A���l�͗��鋨�ɐ[�����S�����Ƃ����B
���i�\�ܔN(1638�N)��\����̖�A�����̏邩�獕�c�A����A�瓇���ɖ铢���Ȃ���A���c���V�̋���̎����\�l�������ɂ����ƍ]�˂֒��i���������B
�瓇���u��O��|���Ȃǂ��Ă��ꂽ�B�Ȃ��Ȃ�����̈Ꝅ���͋����v�ƍ����Ă����B
��O�Ƃ����̂��ߍ]�ˏ�ɓo�邵�A���喼���F�ǂ��������̂��Ǝv�Ă��Ă���ƁA
�I�ɑ�[�����鋨�A���l�͂��̒m�点��
�u���Ă��߂ł������ł���B�ߓ����ɏ�͗����邾�낤�B
�瓇�͈�O���Ă��ꂽ�Ƃ͂����A����ɂ���҂ǂ��̕����Ƃ��Ă̊�ʂ̂قǂ��m�����ƌ�����v
�Ƃ��������ƁA���喼�͊F�X�����낦�ʊ�����Ă����B
�����������Ă��邤���ɗ����������g�҂��������߁A���l�͗��鋨�ɐ[�����S�����Ƃ����B
680�l�Ԏ����l�N
2023/02/24(��) 23:06:25.68ID:b2jcO/M3 �u���ƊՒk�v���獕�c�F���q��
���闎��̎��A�����̐ԕ�ߏO���匴�N���Ɛb�̍��c�F���q�傪�����A�����낤�Ƃ����B
�����֓��y�̎O�}�����q������Ă���
�u�F���q���A���̎�͂Ƃ��ɓ��������Ƃɂ��悤�v�ƌ����ƕF���q��͎��ł��̂āA��ɍs�����B
�����q�͒p���u���̎�͕F���q�傪������v�Ɛ������������F���q��͐U������Ȃ������B
�_���s�܂̎��A�O�}�����q�́u���̎�͍��c�F���q�傪�������ł��v�Ƃ��Ƃ̂���܂�������������
���c�F���q����Ă�Ŏ�̂��Ƃ�q�˂����A�F���q��́u�܂������o���̂Ȃ����Ƃł��v�Ɠ������B
�����q�͎�����Ԃ��ɏq�ׂāA�F���q��ɉ��x���F�߂����悤�Ƃ������F���q��́u�o�����Ȃ��v�Ƃ��������Ȃ������B
���̂��Ƃ����䏊(�ƍN�ƏG��)�̏㕷�ɒB���A�܂��ƂɊ��S�Ȃ��ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
�ДV�����a�R�����Ă��u�i��œa�R�������̂ł͂Ȃ��A�n���i�܂Ȃ��������炾�v�ƌ��(�u�_��v�Ɍ�����)�A
�g�ق�������̌��œx�X�蕿�𗧂Ă��ɂ��ւ�炸�����ւ�Ȃ������悤�Ȃ��̂��B
���闎��̎��A�����̐ԕ�ߏO���匴�N���Ɛb�̍��c�F���q�傪�����A�����낤�Ƃ����B
�����֓��y�̎O�}�����q������Ă���
�u�F���q���A���̎�͂Ƃ��ɓ��������Ƃɂ��悤�v�ƌ����ƕF���q��͎��ł��̂āA��ɍs�����B
�����q�͒p���u���̎�͕F���q�傪������v�Ɛ������������F���q��͐U������Ȃ������B
�_���s�܂̎��A�O�}�����q�́u���̎�͍��c�F���q�傪�������ł��v�Ƃ��Ƃ̂���܂�������������
���c�F���q����Ă�Ŏ�̂��Ƃ�q�˂����A�F���q��́u�܂������o���̂Ȃ����Ƃł��v�Ɠ������B
�����q�͎�����Ԃ��ɏq�ׂāA�F���q��ɉ��x���F�߂����悤�Ƃ������F���q��́u�o�����Ȃ��v�Ƃ��������Ȃ������B
���̂��Ƃ����䏊(�ƍN�ƏG��)�̏㕷�ɒB���A�܂��ƂɊ��S�Ȃ��ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
�ДV�����a�R�����Ă��u�i��œa�R�������̂ł͂Ȃ��A�n���i�܂Ȃ��������炾�v�ƌ��(�u�_��v�Ɍ�����)�A
�g�ق�������̌��œx�X�蕿�𗧂Ă��ɂ��ւ�炸�����ւ�Ȃ������悤�Ȃ��̂��B
681�l�Ԏ����l�N
2023/02/25(�y) 20:25:06.11ID:iwVM1kCD �u���ƊՒk�v���瓿�엊��̎���
������A�]�ˌ�Q�݂̂���Ɉɐ��̍����R(�_���V�c�̔��@�G�̓����ɂ�铌���`���̕���)���z����ꂽ��
������u���m(���̂̂�)�̋|��(��݂�)�Ƃ閼�̍����R�A�P���x���z��Ƃ������Ӂv
�܂��F��։Ԍ��ɓo�R�Ȃ��ꂽ���A�J���~�藷�h�Ŏ莝���������ƂȂ������߁A�l�c�Ƃ�����t�Ȃǂ��䉾�Ƃ��ĘA����s�����B
�l�c�͓�����
�u�s�v�I�R�J�A�N�J�S��(�v�킴�肫�I�R�̉J�A�N�ׂ̈ɕS�Ԃ��J����Ƃ�)�v���u�s���I�R�J�A�N�X�S�ԁv�Ƃ����o�[�W������
�ƈ������܂�ƁA�������
�u���ΔՒJ���A�q�i�V��(�ނɊ�������ՒJ�̐��A�q�ɑЂĐV�����i��)�v
�Ɖr�܂ꂽ�Ƃ����B
�l�c���g���������u�X�v�̏ꍇ�A�u���v�u�v�Ƃ킴�Ɓu�r�v�����������g�������ƂɂȂ�
�܂��u�ՒJ�v�Ō�������ƃ^�C�̎�s�o���R�N�̊����\�L�Əo�Ă������A�ؖ��́u���Â̔ՒJ�ɋA��𑗂鏘�v�ɏo�Ă���
�u���s�̗z(�݂Ȃ�)�ɔՒJ����B�ՒJ�̊ԁA��Â��y���v�̕����낤�B
������A�]�ˌ�Q�݂̂���Ɉɐ��̍����R(�_���V�c�̔��@�G�̓����ɂ�铌���`���̕���)���z����ꂽ��
������u���m(���̂̂�)�̋|��(��݂�)�Ƃ閼�̍����R�A�P���x���z��Ƃ������Ӂv
�܂��F��։Ԍ��ɓo�R�Ȃ��ꂽ���A�J���~�藷�h�Ŏ莝���������ƂȂ������߁A�l�c�Ƃ�����t�Ȃǂ��䉾�Ƃ��ĘA����s�����B
�l�c�͓�����
�u�s�v�I�R�J�A�N�J�S��(�v�킴�肫�I�R�̉J�A�N�ׂ̈ɕS�Ԃ��J����Ƃ�)�v���u�s���I�R�J�A�N�X�S�ԁv�Ƃ����o�[�W������
�ƈ������܂�ƁA�������
�u���ΔՒJ���A�q�i�V��(�ނɊ�������ՒJ�̐��A�q�ɑЂĐV�����i��)�v
�Ɖr�܂ꂽ�Ƃ����B
�l�c���g���������u�X�v�̏ꍇ�A�u���v�u�v�Ƃ킴�Ɓu�r�v�����������g�������ƂɂȂ�
�܂��u�ՒJ�v�Ō�������ƃ^�C�̎�s�o���R�N�̊����\�L�Əo�Ă������A�ؖ��́u���Â̔ՒJ�ɋA��𑗂鏘�v�ɏo�Ă���
�u���s�̗z(�݂Ȃ�)�ɔՒJ����B�ՒJ�̊ԁA��Â��y���v�̕����낤�B
682�l�Ԏ����l�N
2023/02/26(��) 22:46:16.88ID:EAgpXPFs �u�����ƊՒk�v����u����ɂĈꝄ�ǂ��ƌ䍇��̂��Ɓv
��䏊�l������Ɍ䋏�邠�����ꂽ���A�M�����֘Z���Ձi�{�莛�A�������Z���Ղ͖x��Z���ɐ��{�莛���ł��Ă���̌ď́j���t�S�����Ƃ������ƂŁA�@�|�̎҂ǂ������X�ňꝄ���N�������B
�O�͈ꍑ�̏@�|�̎҂����Ƃ��Ƃ��Ꝅ���������A�Ꝅ���ɂ͉ƒ��̗��X�̕��m�����������B
����͓����A��䏊�l���M�����Ɍ䖡�����Ă������������߂ł���B
�Ꝅ�̎҂ǂ�����ގ��Ȃ���ׂ��]����s���A�����䍇����Ȃ���Ƃ����߂ɂȂ����B
�����Z�͂��̖�܂ő�䏊�l�̋߂��ɂ���A��藧�Ă̗l�q�̈ύׂ����m���Ă������A���̖�ɈꝄ�����ɉ����A�Ꝅ�̑叫�ƂȂ��Ă��܂����B
��䏊�l�͂�������m��ɂȂ菬���ǂ��ɂ��G����Ȃ�
�u�����̍���ł킵���������ɂ���悤�Ȃ��Ƃ�����A���`�̂��̂͐ΐ�V���Ɠ��Z�̎���Ƃ��Ă킪�O�Ɏ����Ď����������悤�ɁB
������Γ܂ł̒��߂Ǝv�������v�Ƃ�����������B
���č���œ��Z�Ɛΐ�V���͐�ɐi�݁A�V���͐���a��i���쒉�d�j�ɓ˂��������Ă����B
�V���́u�a��a�͓�����͈�Ƃ̎�Ƃ����߂Ă������A�����͓G�ƂȂ�������ɂ͈ꑄ���܂낤�v�ƌ����Ęa��Ƒ������킹�A�������ɂ����B
�����Z�͑��Y��i���쐳�d�j�Əo��A���Y��͓������܂��Ɛi�ނ�
���Z�́u��������߁A�ˎE���Ă�����v�Ƒ�|���������B
�������đ��Y��͑��A���Z�͋|���������܂܁A�݂��ɂɂ�݂������B
����Ƃǂ����炩����ʂ��������Z�̕I�ɓ˂��������B
���Z�͋|���̂Ė�����Ȃ���̂Ă����߁A���Y��́u���ꂵ��v�ƈꑄ�˂�������ǂ��A�ǂ���ł��������ߑ����͂����ē��Z�ƕ@���킹�ɂȂ��Ă��܂����B
���Z�͓����A���Y��̊��̔�����a�������̂́A���͂悢���ł��������ߎa��Ȃ������B
���Y��͑����̂āA�����Ĉ�ł�����ƁA���Z�͓|��Ȃ���u��������ɂ����Ƃ͖��O�̎���v�ƌ����A�O���������u��������Ƃ�v�Ɛ\�����B
�������Đΐ�V���Ɛ����Z�������ꂽ���߁A�Ꝅ���������ɓ�����Ĕs�k�����B
���̌�A���Y�삪���Z�̎�����Q����Ƒ�䏊�l��
�u���Z�����̂͂��̕����B�܂��Ƃɖ����łȂɂɂ��Ƃ��悤���B
���Y��ꐢ�̕���Ǝv�����Ƃɂ���v�Əd�X���������ꂽ�������B
����ɂ��Ăَ͐҂����n�Ӑ}��(�n�Ӕ����̎O�j�̎q���H)���Ԃ��ɑ������Ă���B
�Ȃ����̎��A���Y��͓�\�������Ƃ����B
�M���Ɩ{�莛�Ƃ̑Η��͂����Ƃ��Ƃ̂͂��B
�܂��u�O�͕���v�ł͐��쒉�d���������Ꝅ���Ƃ��ĐΉ͐V��Y�A�����r�ܘY�A�匩���Z�Y�������Ă���B
��䏊�l������Ɍ䋏�邠�����ꂽ���A�M�����֘Z���Ձi�{�莛�A�������Z���Ղ͖x��Z���ɐ��{�莛���ł��Ă���̌ď́j���t�S�����Ƃ������ƂŁA�@�|�̎҂ǂ������X�ňꝄ���N�������B
�O�͈ꍑ�̏@�|�̎҂����Ƃ��Ƃ��Ꝅ���������A�Ꝅ���ɂ͉ƒ��̗��X�̕��m�����������B
����͓����A��䏊�l���M�����Ɍ䖡�����Ă������������߂ł���B
�Ꝅ�̎҂ǂ�����ގ��Ȃ���ׂ��]����s���A�����䍇����Ȃ���Ƃ����߂ɂȂ����B
�����Z�͂��̖�܂ő�䏊�l�̋߂��ɂ���A��藧�Ă̗l�q�̈ύׂ����m���Ă������A���̖�ɈꝄ�����ɉ����A�Ꝅ�̑叫�ƂȂ��Ă��܂����B
��䏊�l�͂�������m��ɂȂ菬���ǂ��ɂ��G����Ȃ�
�u�����̍���ł킵���������ɂ���悤�Ȃ��Ƃ�����A���`�̂��̂͐ΐ�V���Ɠ��Z�̎���Ƃ��Ă킪�O�Ɏ����Ď����������悤�ɁB
������Γ܂ł̒��߂Ǝv�������v�Ƃ�����������B
���č���œ��Z�Ɛΐ�V���͐�ɐi�݁A�V���͐���a��i���쒉�d�j�ɓ˂��������Ă����B
�V���́u�a��a�͓�����͈�Ƃ̎�Ƃ����߂Ă������A�����͓G�ƂȂ�������ɂ͈ꑄ���܂낤�v�ƌ����Ęa��Ƒ������킹�A�������ɂ����B
�����Z�͑��Y��i���쐳�d�j�Əo��A���Y��͓������܂��Ɛi�ނ�
���Z�́u��������߁A�ˎE���Ă�����v�Ƒ�|���������B
�������đ��Y��͑��A���Z�͋|���������܂܁A�݂��ɂɂ�݂������B
����Ƃǂ����炩����ʂ��������Z�̕I�ɓ˂��������B
���Z�͋|���̂Ė�����Ȃ���̂Ă����߁A���Y��́u���ꂵ��v�ƈꑄ�˂�������ǂ��A�ǂ���ł��������ߑ����͂����ē��Z�ƕ@���킹�ɂȂ��Ă��܂����B
���Z�͓����A���Y��̊��̔�����a�������̂́A���͂悢���ł��������ߎa��Ȃ������B
���Y��͑����̂āA�����Ĉ�ł�����ƁA���Z�͓|��Ȃ���u��������ɂ����Ƃ͖��O�̎���v�ƌ����A�O���������u��������Ƃ�v�Ɛ\�����B
�������Đΐ�V���Ɛ����Z�������ꂽ���߁A�Ꝅ���������ɓ�����Ĕs�k�����B
���̌�A���Y�삪���Z�̎�����Q����Ƒ�䏊�l��
�u���Z�����̂͂��̕����B�܂��Ƃɖ����łȂɂɂ��Ƃ��悤���B
���Y��ꐢ�̕���Ǝv�����Ƃɂ���v�Əd�X���������ꂽ�������B
����ɂ��Ăَ͐҂����n�Ӑ}��(�n�Ӕ����̎O�j�̎q���H)���Ԃ��ɑ������Ă���B
�Ȃ����̎��A���Y��͓�\�������Ƃ����B
�M���Ɩ{�莛�Ƃ̑Η��͂����Ƃ��Ƃ̂͂��B
�܂��u�O�͕���v�ł͐��쒉�d���������Ꝅ���Ƃ��ĐΉ͐V��Y�A�����r�ܘY�A�匩���Z�Y�������Ă���B
683�l�Ԏ����l�N
2023/02/28(��) 21:16:51.50ID:rNDNB3Wk �u�����ƊՒk�v����o��̍���Ƒ��Y�쐳�@
�]�k�o��ő�䏊�l�Ȃ�тɐM�������������ꂽ�B
�M�������������ɂ�
�u�ƍN�ƒ��̂��̂͂悭���킷��Ƃ͏�X�����Ă�������ǂ��A����O�Ō���Ɉ����ׂ��҂ǂ��̓����ł������B
�ƍN�̎҂ǂ����A�����������̂тēG�ɂ��ė���Ȃ����Ƃ�m��Ȃ��������v
�Ƃ��Y��ɂȂ�ꂽ�������B
��䏊�l�A��ƒ��O�̗_�ƂȂ����B
���̍���̎��A���Y��(���쐳�d)�̓����悭��A���̔���芄��A���܂Ő�t�����Ƃ����B
���̓��͐��쉺��a(���쒉���H)���炽�܂�����A������Ȃ������ł������Ƃ����B
��䏊�l���悭�����m�ł���A���̓��ɂ͗l�X�ȕs�v�c�̂��Ƃ��������Ƃ����B
(���̂��Ƃ͗L���Ȑ�䒷����O�l���鐂̘b)
�]�k�o��ő�䏊�l�Ȃ�тɐM�������������ꂽ�B
�M�������������ɂ�
�u�ƍN�ƒ��̂��̂͂悭���킷��Ƃ͏�X�����Ă�������ǂ��A����O�Ō���Ɉ����ׂ��҂ǂ��̓����ł������B
�ƍN�̎҂ǂ����A�����������̂тēG�ɂ��ė���Ȃ����Ƃ�m��Ȃ��������v
�Ƃ��Y��ɂȂ�ꂽ�������B
��䏊�l�A��ƒ��O�̗_�ƂȂ����B
���̍���̎��A���Y��(���쐳�d)�̓����悭��A���̔���芄��A���܂Ő�t�����Ƃ����B
���̓��͐��쉺��a(���쒉���H)���炽�܂�����A������Ȃ������ł������Ƃ����B
��䏊�l���悭�����m�ł���A���̓��ɂ͗l�X�ȕs�v�c�̂��Ƃ��������Ƃ����B
(���̂��Ƃ͗L���Ȑ�䒷����O�l���鐂̘b)
684�l�Ԏ����l�N
2023/02/28(��) 21:29:21.32ID:rNDNB3Wk �Ƃ����킯��>>682
���Z�̓��͑��Y��̊�������Ȃ��������A���Y��̓��͊��ꂽ�悤���B
�Ȃ����a18�N���s�́u���{���Ɩ��G���v�ɂ�
�u�O�c��݉Ƃ̉ƕY���@�͐��@���̌���ł���݂̂łȂ��A���̗��j�͍��̖����Ɉ�i�̌��P��Y�ւ���̂ł���B
���̓��͖��㖳���ŁA�����͓�ڈꐡ�A�ؐ悩�甪���ܕ��������̂ɁA�������n���ڂꂪ����B
���ؐ悩��ܐ������̏��ɁA��ڂƂ����Ė�̓��������l�p�ȏ����Ȍ�������B
(>>683�̘b)�n���ڂ�͍��̎��̌������ł���B
���v(���Y��)�����@�̐ꖡ���]��ɂ悢�̂ŁA�����Ȃ�������ĉƍN�ɘb���ƁA
�ƍN�u����͉���炪��X�������Ă������ł��낤�v�Ƃ����āA�����ɂƂ茩�āA�u���͐������ܘY�����ł���A��ɏ��������v�Ɖ]�͂ꂽ�B
������ɓ����㏫�R�G���ɓ���A�O��ƌ��ɓ`�͂�A�ƍN�̗{�������B�l��ˎ�O�c�����ɉł������A�����֑����ȗ��O�c�Ƃ̉ƕ�̈�ƂȂ����B�v
�Ə�����Ă���B���ݍ���w��B
���Z�̓��͑��Y��̊�������Ȃ��������A���Y��̓��͊��ꂽ�悤���B
�Ȃ����a18�N���s�́u���{���Ɩ��G���v�ɂ�
�u�O�c��݉Ƃ̉ƕY���@�͐��@���̌���ł���݂̂łȂ��A���̗��j�͍��̖����Ɉ�i�̌��P��Y�ւ���̂ł���B
���̓��͖��㖳���ŁA�����͓�ڈꐡ�A�ؐ悩�甪���ܕ��������̂ɁA�������n���ڂꂪ����B
���ؐ悩��ܐ������̏��ɁA��ڂƂ����Ė�̓��������l�p�ȏ����Ȍ�������B
(>>683�̘b)�n���ڂ�͍��̎��̌������ł���B
���v(���Y��)�����@�̐ꖡ���]��ɂ悢�̂ŁA�����Ȃ�������ĉƍN�ɘb���ƁA
�ƍN�u����͉���炪��X�������Ă������ł��낤�v�Ƃ����āA�����ɂƂ茩�āA�u���͐������ܘY�����ł���A��ɏ��������v�Ɖ]�͂ꂽ�B
������ɓ����㏫�R�G���ɓ���A�O��ƌ��ɓ`�͂�A�ƍN�̗{�������B�l��ˎ�O�c�����ɉł������A�����֑����ȗ��O�c�Ƃ̉ƕ�̈�ƂȂ����B�v
�Ə�����Ă���B���ݍ���w��B
685�l�Ԏ����l�N
2023/03/03(��) 20:05:29.67ID:OTZl9wjf �u���ƊՒk�v������̐w�̎��̌F��k�R�Ꝅ
�L���Q�l�����o���ɂ��A���A�n�璷����ɍݐw���Ă���Œ��ɌF��k�R�Ꝅ���N�����B
�Ꝅ�̑叫�́A��Ԃ̑O�S�Ë��юR���Ƃ����҂������Ƃ����B
������F�ɂ�叫�Ƃ��ē����h�������B
�O�S�Ë�͌F��R���������ߐV�{���琼�̐�֓���A��ɍ~�荞�܂꓀�����ɂ����B
�a�B��䑺�̈Ꝅ�̑叫�R���͖k�R�֓��ꂽ���߁A�F�ǂ�������ƁA�R���͈Ꝅ���ɉ��m���ē�A�O�x�h�킵�đނ����B
�F�ɂ͂���ł��ǂ������A������E�|�����̊Ԃɔ������B
�R���͐��n����A��̉A�ʼnB��A�F���҂��A�����ł��A�g�ݑł��Ă邤���ɕ��ɂ����ƂȂ����B
�����ɒ��c�앺�q���삯���A�R����˂��|���A���������B
���ɂƍ앺�q���R���̎�����ꂼ�ꎩ���̂��̂��Ǝ咣�������߁A�a���܉E�q��͐i�ݏo��
�u���ɂ����ߑ����ł��A�g�ݑł����Ă����̂�����앺�q�͉��������Ƃ������ƂɂȂ�B
�����͕��ɂ̂��̂��v�ƎR���̎�ɂɓn�����B
�a���̍ٔ����ǂ��Ǝv�������߁A�������߂�B
�L���Q�l�����o���ɂ��A���A�n�璷����ɍݐw���Ă���Œ��ɌF��k�R�Ꝅ���N�����B
�Ꝅ�̑叫�́A��Ԃ̑O�S�Ë��юR���Ƃ����҂������Ƃ����B
������F�ɂ�叫�Ƃ��ē����h�������B
�O�S�Ë�͌F��R���������ߐV�{���琼�̐�֓���A��ɍ~�荞�܂꓀�����ɂ����B
�a�B��䑺�̈Ꝅ�̑叫�R���͖k�R�֓��ꂽ���߁A�F�ǂ�������ƁA�R���͈Ꝅ���ɉ��m���ē�A�O�x�h�킵�đނ����B
�F�ɂ͂���ł��ǂ������A������E�|�����̊Ԃɔ������B
�R���͐��n����A��̉A�ʼnB��A�F���҂��A�����ł��A�g�ݑł��Ă邤���ɕ��ɂ����ƂȂ����B
�����ɒ��c�앺�q���삯���A�R����˂��|���A���������B
���ɂƍ앺�q���R���̎�����ꂼ�ꎩ���̂��̂��Ǝ咣�������߁A�a���܉E�q��͐i�ݏo��
�u���ɂ����ߑ����ł��A�g�ݑł����Ă����̂�����앺�q�͉��������Ƃ������ƂɂȂ�B
�����͕��ɂ̂��̂��v�ƎR���̎�ɂɓn�����B
�a���̍ٔ����ǂ��Ǝv�������߁A�������߂�B
686�l�Ԏ����l�N
2023/03/03(��) 20:19:36.10ID:tsS3dxGo �u�a�̎R���j�@�ߐ��j���O�v�́u���@�Ꝅ�E�����v�Ɏ��^����Ă���A�c���̎��ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�u�k�R�Ꝅ����W���t�v�ɂ������b��������
�u�F�ɐ�䑺�R������߃n�݃j�����Œv�A�vゟ�g�����ɂ�g���։i��앺�q�o���R������ɂēˎ����A
�������ɂƍ앺�q�_�j�����a���܉E�q��Ɖ]�Ґ\��n�A�앺�q�蕿�V���䓙���\��A
��n���ɑg�V�|���ɂ֎�n�n��ւƔ�\�v
�܂���C����u�k�R�Ꝅ�ɂ��āv�Ƃ����_�����瑷�����ƂȂ邪
�u�������ϔ��^�v(���Ƃ̉Ǝj�u�ϔ��^�v�̐�쒷��̑�)�ɖk�R�Ꝅ�ɂ��Ă��L����Ă���
�E�͈䑺�̎R���A�P�S�̒Ëv�A�x�����āA�����^�A�����^�͌܋S�Ƃ��Ēm���Ă���
�E�F�ɂ�������֍s�����Ƃ������A�\�˂���̕v�w�������ł���낤�Ƃ������A�b�h�����Ă������߂ɋt�ɑg�ݕ~����A���������o����������ŎE���ꂻ���ɂȂ����B
�����V�{�̏Z�l�i�c�ܘY���q��ɏ�����ꑊ��̎��ł�������B
��ׂ�Ƃ���͈Ꝅ�̎�d�҂̈�l�A�R���S���ł������B
�Ə�����Ă���Ƃ��B
�u�F�ɐ�䑺�R������߃n�݃j�����Œv�A�vゟ�g�����ɂ�g���։i��앺�q�o���R������ɂēˎ����A
�������ɂƍ앺�q�_�j�����a���܉E�q��Ɖ]�Ґ\��n�A�앺�q�蕿�V���䓙���\��A
��n���ɑg�V�|���ɂ֎�n�n��ւƔ�\�v
�܂���C����u�k�R�Ꝅ�ɂ��āv�Ƃ����_�����瑷�����ƂȂ邪
�u�������ϔ��^�v(���Ƃ̉Ǝj�u�ϔ��^�v�̐�쒷��̑�)�ɖk�R�Ꝅ�ɂ��Ă��L����Ă���
�E�͈䑺�̎R���A�P�S�̒Ëv�A�x�����āA�����^�A�����^�͌܋S�Ƃ��Ēm���Ă���
�E�F�ɂ�������֍s�����Ƃ������A�\�˂���̕v�w�������ł���낤�Ƃ������A�b�h�����Ă������߂ɋt�ɑg�ݕ~����A���������o����������ŎE���ꂻ���ɂȂ����B
�����V�{�̏Z�l�i�c�ܘY���q��ɏ�����ꑊ��̎��ł�������B
��ׂ�Ƃ���͈Ꝅ�̎�d�҂̈�l�A�R���S���ł������B
�Ə�����Ă���Ƃ��B
687�l�Ԏ����l�N
2023/03/04(�y) 07:22:41.41ID:QrIMP5Y9 2021�N1��6���̒����V���f�W�^���̋L���Ɍ܋S�ɂ��ď�����Ă���
�u���͋S�̖���v�L�҂ɒf���@�F��u�܋S�v���̓��ǂ�
>�`���̕���͓ޗnj��͉��k�R���̑O�S�i���j�W���B
>�������1300�N�O�A�O�S�A��S�i�����j�Ƃ����S�̕v�w�������B���̕v�w�͎R�ŏC�s����C�����̑c�ł�����s�ҁi����̂��傤����j�̎p�ɐS��������A�d����悤�ɂȂ����B
>�����āu���։���Đl�Ƃ��Đ������Ȃ����v�Ƃ̖����ĕ�炵�͂��߂��̂��O�S�W���������Ƃ����B
>�O�S�ƌ�S��5�l�̎q�́A�C���҂𐢘b����܂̏h�V���J�����B���ꂼ��u�܋S���i�����ǂ��j�v�u�܋S��i�������傤�j�v�u�܋S�p�i�������j�v�u�܋S���i��������j�v�����āu�܋S�F�v�Ɩ�������B
�u���͋S�̖���v�L�҂ɒf���@�F��u�܋S�v���̓��ǂ�
>�`���̕���͓ޗnj��͉��k�R���̑O�S�i���j�W���B
>�������1300�N�O�A�O�S�A��S�i�����j�Ƃ����S�̕v�w�������B���̕v�w�͎R�ŏC�s����C�����̑c�ł�����s�ҁi����̂��傤����j�̎p�ɐS��������A�d����悤�ɂȂ����B
>�����āu���։���Đl�Ƃ��Đ������Ȃ����v�Ƃ̖����ĕ�炵�͂��߂��̂��O�S�W���������Ƃ����B
>�O�S�ƌ�S��5�l�̎q�́A�C���҂𐢘b����܂̏h�V���J�����B���ꂼ��u�܋S���i�����ǂ��j�v�u�܋S��i�������傤�j�v�u�܋S�p�i�������j�v�u�܋S���i��������j�v�����āu�܋S�F�v�Ɩ�������B
688�l�Ԏ����l�N
2023/03/04(�y) 09:48:16.36ID:83OMXFqB �S�Ƃ����ΐl��
689�l�Ԏ����l�N
2023/03/04(�y) 09:52:42.48ID:CiDNdMPi ��������퍑����ɂǂ��q����̂��ȂƎv�������ǏI���Ȃ̂��ȁH
690�l�Ԏ����l�N
2023/03/04(�y) 13:06:52.06ID:7UlQfOc/ ID���ς���Ă��āA�킩��Â炭�Ă����܂���
�����V���̌܋S�̋L���ɂ��ď������̂́A�F��k�R�Ꝅ�̎w���҂Ƃ����
�u�͍����̎R��(�܋S���H)�v�Ɓu�P�S�̒Ëv(�O�S�p)�v���Ƃ��Ɂu�ϔ��^�v�ł͌܋S�Ƃ���Ă���
�܋S�̗R�������s�҂ɂ܂��Ƃ����b���������낢���߁A�t�������������ł�
�����V���̌܋S�̋L���ɂ��ď������̂́A�F��k�R�Ꝅ�̎w���҂Ƃ����
�u�͍����̎R��(�܋S���H)�v�Ɓu�P�S�̒Ëv(�O�S�p)�v���Ƃ��Ɂu�ϔ��^�v�ł͌܋S�Ƃ���Ă���
�܋S�̗R�������s�҂ɂ܂��Ƃ����b���������낢���߁A�t�������������ł�
692�l�Ԏ����l�N
2023/03/04(�y) 13:15:22.69ID:Gyvr4Std �łǂ�����Čq����́H
693�l�Ԏ����l�N
2023/03/04(�y) 13:29:25.72ID:HF8bfFEn �ї��̂Ƃ���ɂ������S�͎q��������
694�l�Ԏ����l�N
2023/03/04(�y) 13:53:57.64ID:V+jxazcg �S��������c�ł�
695690
2023/03/04(�y) 14:58:18.47ID:7UlQfOc/ �u���ƊՒk�v������̐w�̎��̊~��̐킢
>>685�̎��̘b
�������L���Q�l�̊o���̊~��̈��ɂ���
(���Ă̐w�̈��A�F��k�R�Ꝅ�Ɠ�����)
�I�B��(���)�͔����납��~�䒬�ɓ���A�T�c�����(�T�c���j)�͑嗜�ł̊��A��̈��т̉H�D�Ől���ɉ��m���a�R�����B
���̕��Ҏg���͂Ȃ��Ȃ������ł���A�ǂ��叫�Ɍ������B
�~�䒬�ɎO����������ꂽ���ɑ���������Ă������ߋT�c���������ƁA������w(�������j)�����̌��ɂ������Ă����B
�T�c�������Ɉ������ƁA���c�E�q��(�����V)���A���A���\�l���肪�����Ă����B
��c�吅(��c�d��)�͓�\�R�قǂŊ~�䒬�ɐ���ł������߁A�����������Ă����Ƃ���Ɉ�ԑ��ő������킹���B
��c�吅�z���̍��쌴�������A���J�����q�A���䕽���q�傪�܁A�Z�l���ő�����ǂ����Ă�ƁA�T�c��������c�吅�ɍ��������B
�����͈����Ԃ��A���c�E�q��̉Ɨ��̍�c�����Y���^����Ɏ吅�ɂ������Ă������A�吅�͑��œ˂������A�����̉��V�O�Y�Ɏ��点�A���y�ɖ����Đ�쒷��{�w�Ɏ�������ċA�点���B
�܂��T�c���͑����̎R�c�ܘY���q�����ۏ��V�ȉ�������˂����Ă��B
>>685�̎��̘b
�������L���Q�l�̊o���̊~��̈��ɂ���
(���Ă̐w�̈��A�F��k�R�Ꝅ�Ɠ�����)
�I�B��(���)�͔����납��~�䒬�ɓ���A�T�c�����(�T�c���j)�͑嗜�ł̊��A��̈��т̉H�D�Ől���ɉ��m���a�R�����B
���̕��Ҏg���͂Ȃ��Ȃ������ł���A�ǂ��叫�Ɍ������B
�~�䒬�ɎO����������ꂽ���ɑ���������Ă������ߋT�c���������ƁA������w(�������j)�����̌��ɂ������Ă����B
�T�c�������Ɉ������ƁA���c�E�q��(�����V)���A���A���\�l���肪�����Ă����B
��c�吅(��c�d��)�͓�\�R�قǂŊ~�䒬�ɐ���ł������߁A�����������Ă����Ƃ���Ɉ�ԑ��ő������킹���B
��c�吅�z���̍��쌴�������A���J�����q�A���䕽���q�傪�܁A�Z�l���ő�����ǂ����Ă�ƁA�T�c��������c�吅�ɍ��������B
�����͈����Ԃ��A���c�E�q��̉Ɨ��̍�c�����Y���^����Ɏ吅�ɂ������Ă������A�吅�͑��œ˂������A�����̉��V�O�Y�Ɏ��点�A���y�ɖ����Đ�쒷��{�w�Ɏ�������ċA�点���B
�܂��T�c���͑����̎R�c�ܘY���q�����ۏ��V�ȉ�������˂����Ă��B
696690
2023/03/04(�y) 15:01:17.76ID:7UlQfOc/ ���̂����ƂŔ��̉Ɨ��A�R�`�O�Y�E�q��(�R�p���d�B�R�p���i�̑��q)����c�吅�Ƒ������킹�����A�T�c�������������ǂ����ĂĂ������ߏ������������B
�吅���u��c�吅�ł���B�����Ԃ��ď�������v�ƎR�`�ɐ������������߁A�R�`�������Ԃ����B
�吅�͑��őł������A���̕����^����܂�Ă��܂����B
�Ԕ����ꂸ�R�`�͎吅��g�ݕ������B
�����̉��ւ͎�l�������悤�ƎR�`�ɂ����������A�R�`�͉��ւ������l�ɉ��������Ă��܂����B
��c�吅�z���̉��䕽���q��͑����̈�l���Ƃ̌����ɓ˂������A�吅�ɌĂт��������ԓ����Ȃ������B
�U��Ԃ�Ǝ�l�̎吅�͑g�ݕ������A�����̗����������Ă������߁A�˂������Ă����G���̂āA�����q��͎吅�̏�ɏ���Ă���R�`�̍���(��������)��藎�Ƃ��A�����|�����B
�吅�͋N���オ��u���̎�͏����̐V�O�Y�Ɏ�点��v�Ɩ��������߁A�V�O�Y�̍����ƂȂ����B
����͎R�`�̉��l�����蕚���A����̎�ƍ��킹��������Ȃ����B
���c�E�q��͓c�q�����q��Ɠn�荇���Ă������A�c�q����������c�E�q��̏�тɓ�����A�����肽�����c�E�q��͏\�������œc�q�̋|�̌�������B
�����֔��ؐV���q�傪���ēn�荇���A�c�E�q��͎蕉�ł��������ʊ��ɐ킢�������ɂ���������Ƃ����B
�������đ����̓������ɂ́A���c�����A���䎡���q��A�R�c���O�Y�A�{�����E�q��A�F�J�����v�A���i��E�q��A��c�����Y�A�R�`�O�Y�E�q��A���̂ق��l�l�œs���\��̊���ƂȂ����B
�������֎����A��A��쒷��炱�̎|�����B
�吅���u��c�吅�ł���B�����Ԃ��ď�������v�ƎR�`�ɐ������������߁A�R�`�������Ԃ����B
�吅�͑��őł������A���̕����^����܂�Ă��܂����B
�Ԕ����ꂸ�R�`�͎吅��g�ݕ������B
�����̉��ւ͎�l�������悤�ƎR�`�ɂ����������A�R�`�͉��ւ������l�ɉ��������Ă��܂����B
��c�吅�z���̉��䕽���q��͑����̈�l���Ƃ̌����ɓ˂������A�吅�ɌĂт��������ԓ����Ȃ������B
�U��Ԃ�Ǝ�l�̎吅�͑g�ݕ������A�����̗����������Ă������߁A�˂������Ă����G���̂āA�����q��͎吅�̏�ɏ���Ă���R�`�̍���(��������)��藎�Ƃ��A�����|�����B
�吅�͋N���オ��u���̎�͏����̐V�O�Y�Ɏ�点��v�Ɩ��������߁A�V�O�Y�̍����ƂȂ����B
����͎R�`�̉��l�����蕚���A����̎�ƍ��킹��������Ȃ����B
���c�E�q��͓c�q�����q��Ɠn�荇���Ă������A�c�q����������c�E�q��̏�тɓ�����A�����肽�����c�E�q��͏\�������œc�q�̋|�̌�������B
�����֔��ؐV���q�傪���ēn�荇���A�c�E�q��͎蕉�ł��������ʊ��ɐ킢�������ɂ���������Ƃ����B
�������đ����̓������ɂ́A���c�����A���䎡���q��A�R�c���O�Y�A�{�����E�q��A�F�J�����v�A���i��E�q��A��c�����Y�A�R�`�O�Y�E�q��A���̂ق��l�l�œs���\��̊���ƂȂ����B
�������֎����A��A��쒷��炱�̎|�����B
697689
2023/03/04(�y) 21:09:04.15ID:/s1Ow7Jx698690
2023/03/05(��) 01:02:03.61ID:aoFtKw4a ���������C�ɂȂ��炸
�u���ƊՒk�v�����c�@��(��c�d��)
��c�吅�����@��(�@��)�͊փ����̎��ɎO�����ɂނ������߁A���K���ɗa����ꂽ�B
����܂ł͈ꖜ�ŁA���q���G�t�S�̎��ɐD�c�����q�M��(�Óc�M��)�̎����������Ƃ����������A�������̓��Ŗ������������B
���鎞�A�a�̎R�̖x�ŕ���������A�@�ӂ͑�������Ă����B
�`�̖ؖȉH�D�Ŕn�ɏ���Ă������������̂��A�M�̑ǂ���ɂ��A�a��ЂŔ������A�̏�ɓo���ĉ��m�������B
�Ⴂ���ǂ��́u�a�l�͂Ȃ�قǑ喼���B�Ȃɂ��ꖜ�̒��V�������Ă������v�ƚ}�����B
���̂��Ƃ��ƒ��ɒm��n�������߁A���K���͏@�ӂ̂��Ƃ��C�ɂ����A���m�̑O�ŏ@�ӂɘe��������
�u�ƒ��ʼn����Ɣᔻ����Ă��邪�C�ɂ�����ȁB��厖�̎��ɖ����߂Ă���v�ƌ������B
�@�ӂ��e�������������u���̘e�����������邱�Ƃ�����āA�E�т܂��傤�v�Ƒޏo�����B
�ƒ��̂��̂͂܂����āu�q�̘̂e���ɉ��̌�������̂��낤�B�l�Y�~���H�L���H�v�ƚ}�����B
�K�������̂̂��A���̐w�Ō��a���N(1615�N�A���������a�����͑��̐w��)�l����\����ɐ�B�~�䍇��ŏ�c�@�ӂ͈�ԑ����Ȃ��A�������R�p�O�Y�E�q���g�ݑł��ɂ����B
���A�n�璷��̖{�w�ɎQ��ƁA����͊��x���ɂł������B
�@�ӂ͍��𗧂��āu�݂Ȃ݂ȈȑO��𒃖V��Ɛ\���A���̂̂��K���l���e���������������A�䂪�u���̘e���Ɍ������܂��傤�v�Ɛ\���Ɓu���V�傪�����Ƃ́v�Ƃ܂��}��܂����ȁB
�����͒����̏@�ӂقǂ̓������������͂��Ȃ��悤�Ɍ����܂����v
�ƌ����ƁA�N���ꌾ������Ȃ������B
�u���ƊՒk�v�����c�@��(��c�d��)
��c�吅�����@��(�@��)�͊փ����̎��ɎO�����ɂނ������߁A���K���ɗa����ꂽ�B
����܂ł͈ꖜ�ŁA���q���G�t�S�̎��ɐD�c�����q�M��(�Óc�M��)�̎����������Ƃ����������A�������̓��Ŗ������������B
���鎞�A�a�̎R�̖x�ŕ���������A�@�ӂ͑�������Ă����B
�`�̖ؖȉH�D�Ŕn�ɏ���Ă������������̂��A�M�̑ǂ���ɂ��A�a��ЂŔ������A�̏�ɓo���ĉ��m�������B
�Ⴂ���ǂ��́u�a�l�͂Ȃ�قǑ喼���B�Ȃɂ��ꖜ�̒��V�������Ă������v�ƚ}�����B
���̂��Ƃ��ƒ��ɒm��n�������߁A���K���͏@�ӂ̂��Ƃ��C�ɂ����A���m�̑O�ŏ@�ӂɘe��������
�u�ƒ��ʼn����Ɣᔻ����Ă��邪�C�ɂ�����ȁB��厖�̎��ɖ����߂Ă���v�ƌ������B
�@�ӂ��e�������������u���̘e�����������邱�Ƃ�����āA�E�т܂��傤�v�Ƒޏo�����B
�ƒ��̂��̂͂܂����āu�q�̘̂e���ɉ��̌�������̂��낤�B�l�Y�~���H�L���H�v�ƚ}�����B
�K�������̂̂��A���̐w�Ō��a���N(1615�N�A���������a�����͑��̐w��)�l����\����ɐ�B�~�䍇��ŏ�c�@�ӂ͈�ԑ����Ȃ��A�������R�p�O�Y�E�q���g�ݑł��ɂ����B
���A�n�璷��̖{�w�ɎQ��ƁA����͊��x���ɂł������B
�@�ӂ͍��𗧂��āu�݂Ȃ݂ȈȑO��𒃖V��Ɛ\���A���̂̂��K���l���e���������������A�䂪�u���̘e���Ɍ������܂��傤�v�Ɛ\���Ɓu���V�傪�����Ƃ́v�Ƃ܂��}��܂����ȁB
�����͒����̏@�ӂقǂ̓������������͂��Ȃ��悤�Ɍ����܂����v
�ƌ����ƁA�N���ꌾ������Ȃ������B
699�l�Ԏ����l�N
2023/03/06(��) 12:43:20.98ID:Y3zjxpvb �u���ƊՒk�v���珬�c���̐w�ł̉ƍN�ƐM�Y
�V���\���N(1590�N)�O����\�����A���}�G�g�����O�����Ɍ䒅�w���ꂽ���߁A���̏��叫�����������܂ł܂���o���B
�D�c�M�Y���A�����l����������ӂɏo��ꂽ�B
�G�g���͋����D����Ђ̊Z�A�����̊��A���̑����l�t���̑�����U��т��A���̓y�U���̏�ɐ�����t���A���Ђ������Ȃ����Ă����B
��Ό����q���i�サ���鎠�̋|���������ɂȂ�A��������̔n�Z�������������̔n�ɏ���Ă����B
���̖ʁX�͈ٗވٌ`�̏o�����ŁA�痘�x�͋��̒�⤂̂������߂̂�����w���Ƃ��A�ɂ̌�(����H)�Ό��͌ۂ̓��̎w���A�����t�̔ԓ��͎O�ԎO(�O�ԙ�)�̑����ŁA���̑����܂��܂ȏo�����ł������B
�����l�A�M�Y���͂��i�݂Ȃ���A���ƂɐM�Y���͏G�g���̎�ł��邽�ߏ��ł��͂ǂ����悤���Ǝv���߂����B
���̏�A���叫�Ƃ����c���Ƃ̓��ʂ̎G�������邽�߁A��V�Ƃ͂����䗼���̑O�ŏG�g���͔n����Ђ��Ƃ��~��ɂȂ�A���������ɂ���
�u�M�Y�A�ƍN�t�S�Ə���B�����オ����A�ꑾ���Q�邼�v�Ƃ�����������B
�M�Y���͐Ԗʂ��Č��t�������Ȃ������B
�����l�͏��l�Ɍ�����
�u��w���߂ɑ����Ɍ�����������Ƃ͂߂ł������Ƃł��B���������߂ł����v
�ƍ��炩�ɂ��������ƁA�G�g���͉������킸�Ɍ�n�ɏ��A���ʂ�ɂȂ����B
���R�͌����l�̌�q�E�Ɋ��S�����B
�V���\���N(1590�N)�O����\�����A���}�G�g�����O�����Ɍ䒅�w���ꂽ���߁A���̏��叫�����������܂ł܂���o���B
�D�c�M�Y���A�����l����������ӂɏo��ꂽ�B
�G�g���͋����D����Ђ̊Z�A�����̊��A���̑����l�t���̑�����U��т��A���̓y�U���̏�ɐ�����t���A���Ђ������Ȃ����Ă����B
��Ό����q���i�サ���鎠�̋|���������ɂȂ�A��������̔n�Z�������������̔n�ɏ���Ă����B
���̖ʁX�͈ٗވٌ`�̏o�����ŁA�痘�x�͋��̒�⤂̂������߂̂�����w���Ƃ��A�ɂ̌�(����H)�Ό��͌ۂ̓��̎w���A�����t�̔ԓ��͎O�ԎO(�O�ԙ�)�̑����ŁA���̑����܂��܂ȏo�����ł������B
�����l�A�M�Y���͂��i�݂Ȃ���A���ƂɐM�Y���͏G�g���̎�ł��邽�ߏ��ł��͂ǂ����悤���Ǝv���߂����B
���̏�A���叫�Ƃ����c���Ƃ̓��ʂ̎G�������邽�߁A��V�Ƃ͂����䗼���̑O�ŏG�g���͔n����Ђ��Ƃ��~��ɂȂ�A���������ɂ���
�u�M�Y�A�ƍN�t�S�Ə���B�����オ����A�ꑾ���Q�邼�v�Ƃ�����������B
�M�Y���͐Ԗʂ��Č��t�������Ȃ������B
�����l�͏��l�Ɍ�����
�u��w���߂ɑ����Ɍ�����������Ƃ͂߂ł������Ƃł��B���������߂ł����v
�ƍ��炩�ɂ��������ƁA�G�g���͉������킸�Ɍ�n�ɏ��A���ʂ�ɂȂ����B
���R�͌����l�̌�q�E�Ɋ��S�����B
700�l�Ԏ����l�N
2023/03/08(��) 19:50:34.21ID:5gsbhMFH �u���ƊՒk�v���璩�N�ł̉��������̗p�S�Ԃ�
�������E�q��(��������)������邱�Ƃɂ́A���������͂�����Q�ȑ叫�ł��邪�A��X��������Ă����Ƃ����B
����w�̂Ƃ��A���R�C����\���قǂ̒n��͓��{���������߂Ă���A���A�������Ƃɏ��z���āu�q���̏�v�Ƃ����Ă����B
�˓c��������(�˓c����)�͖��z�̏�ɁA�����͑S�B�ɂ������ɁA���{����̎w���Ő������A�����邱�ƂɂȂ����B
�S�B����ܓ��ڂɖ��z�ɂ͒������ƂɂȂ��Ă����B
�˓c�͐����̋��F�Ȃ̂ł�낱�сA���|�����Ēy������������p�ӂ����B
�����ĉƘV�ł���^���ܘY�E�q��(�^��听)�Ɛ_�J���E�q��܂Ō}���ɏo�����B
�߂̍������ɐ^��E�_�J�͖��z�̏邩��l���قǂ̂Ƃ���ɏo��ƁA�����̐�萨���������B
���̂���͓�����\���A��k�\���̒��N�̒n��͎����Ă���A�G�����Ȃ��������߁A�˓c�̉ƘV��l���₩�ȉH�D�тŊZ�𒅂邱�Ƃ��Ȃ������B
�����������̕��������͂���������̂��̂����A�\�H(�ٓ���)���̊��w�����Ȃт����A�S�C�̉Γ�ɂ������A�������܂ŊZ�A�ʖj�܂ł��Ă����߂����p�ł������B
���@�@�؋��̊����������āA�������S�C���ܕS��^����ɗ��ĂĂ����B
�������E�q��(��������)������邱�Ƃɂ́A���������͂�����Q�ȑ叫�ł��邪�A��X��������Ă����Ƃ����B
����w�̂Ƃ��A���R�C����\���قǂ̒n��͓��{���������߂Ă���A���A�������Ƃɏ��z���āu�q���̏�v�Ƃ����Ă����B
�˓c��������(�˓c����)�͖��z�̏�ɁA�����͑S�B�ɂ������ɁA���{����̎w���Ő������A�����邱�ƂɂȂ����B
�S�B����ܓ��ڂɖ��z�ɂ͒������ƂɂȂ��Ă����B
�˓c�͐����̋��F�Ȃ̂ł�낱�сA���|�����Ēy������������p�ӂ����B
�����ĉƘV�ł���^���ܘY�E�q��(�^��听)�Ɛ_�J���E�q��܂Ō}���ɏo�����B
�߂̍������ɐ^��E�_�J�͖��z�̏邩��l���قǂ̂Ƃ���ɏo��ƁA�����̐�萨���������B
���̂���͓�����\���A��k�\���̒��N�̒n��͎����Ă���A�G�����Ȃ��������߁A�˓c�̉ƘV��l���₩�ȉH�D�тŊZ�𒅂邱�Ƃ��Ȃ������B
�����������̕��������͂���������̂��̂����A�\�H(�ٓ���)���̊��w�����Ȃт����A�S�C�̉Γ�ɂ������A�������܂ŊZ�A�ʖj�܂ł��Ă����߂����p�ł������B
���@�@�؋��̊����������āA�������S�C���ܕS��^����ɗ��ĂĂ����B
701�l�Ԏ����l�N
2023/03/08(��) 19:52:41.95ID:5gsbhMFH �����͗��ߓh��̋�ɋ��̎ւ̖ڂ������A��̋�̒��G�X�q�̊��̏�����߁A頰���A�͂����A���˓��A�ђ\�܂ł��A���܂����߁A
��̋�{�n���̔n������g�̔w�Ɏw���A���т̔n�ɔ��A�����܂��ė����B
�˓c�̉ƘV��������������Ĕ��̒��ɉ��n���Ă���̂�����������
�u�˓c�����a�̎g�҂��A���V�ł���B
��������ɒ��w���邪�A��������������Ă���̂ŁA���C��p�ӂ��A���X�ɂ܂œ����������т��Ă������������B
���̂悵�A�����a�ւ��肢�\���v�Ɛ����ɂ�����������B
�^��E�_�J�́u�������܂�܂����v�Ɣn�ɏ��A��ɋA���Č˓c�ɐ\���q�ׂ��B
�قǂȂ���������ɓ����������߁A�˓c���o�Ă݂�ƁA��n����w���Ă����߂����p�ł������B
�����Ō˓c�̏�����l�������̔n�a��܂₷�˓��Ȃǂ��������Ƃ���A���������ɂ��Ă������j�q�܂̌��������āA���~�̏�ɗ������B
�����ɂ͕ĎO���A�����X�A�K�O�S�������Ă��Ă��Ȃ�d�������B
�˓c�͂��ǂ낫�u�\�������ɓG�����Ȃ��̂ɁA�d�����̂����ɉ����A�������n��܂Ŏw���Ƃ͂����Ȃ邱�Ƃł����v�Ɛq�˂��
�����́u���̂��Ƃ����A�Ƃ�����厖�͖��f���o����̂ł��B
�������ɓG�����Ȃ���Έ��S������̂ł����A�}�����N���Ė��f����悤�ł͍��܂ł̕��������ƂȂ��Ă��܂��܂��B
���X�̎m���͂����ł������f�������Ȃ̂ɁA�����̐S�܂ł��ނƁA���X�͂悯���ɑт̕R�������đӂ���ł��傤�B
�䂪�g���ڂ݂����f���Ȃ��悤�ɂ���ƁA���̎҂͏�̎҂��w�Ԃƌ����܂��̂ŁA���̂悤�ɂ��Ă���܂��B
��l�̐S�����l�ɒʂ�Ƃ��\���܂����v
�ƌ����ƁA�˓c�����͊������ė܂𗬂����Ƃ����B
��̋�{�n���̔n������g�̔w�Ɏw���A���т̔n�ɔ��A�����܂��ė����B
�˓c�̉ƘV��������������Ĕ��̒��ɉ��n���Ă���̂�����������
�u�˓c�����a�̎g�҂��A���V�ł���B
��������ɒ��w���邪�A��������������Ă���̂ŁA���C��p�ӂ��A���X�ɂ܂œ����������т��Ă������������B
���̂悵�A�����a�ւ��肢�\���v�Ɛ����ɂ�����������B
�^��E�_�J�́u�������܂�܂����v�Ɣn�ɏ��A��ɋA���Č˓c�ɐ\���q�ׂ��B
�قǂȂ���������ɓ����������߁A�˓c���o�Ă݂�ƁA��n����w���Ă����߂����p�ł������B
�����Ō˓c�̏�����l�������̔n�a��܂₷�˓��Ȃǂ��������Ƃ���A���������ɂ��Ă������j�q�܂̌��������āA���~�̏�ɗ������B
�����ɂ͕ĎO���A�����X�A�K�O�S�������Ă��Ă��Ȃ�d�������B
�˓c�͂��ǂ낫�u�\�������ɓG�����Ȃ��̂ɁA�d�����̂����ɉ����A�������n��܂Ŏw���Ƃ͂����Ȃ邱�Ƃł����v�Ɛq�˂��
�����́u���̂��Ƃ����A�Ƃ�����厖�͖��f���o����̂ł��B
�������ɓG�����Ȃ���Έ��S������̂ł����A�}�����N���Ė��f����悤�ł͍��܂ł̕��������ƂȂ��Ă��܂��܂��B
���X�̎m���͂����ł������f�������Ȃ̂ɁA�����̐S�܂ł��ނƁA���X�͂悯���ɑт̕R�������đӂ���ł��傤�B
�䂪�g���ڂ݂����f���Ȃ��悤�ɂ���ƁA���̎҂͏�̎҂��w�Ԃƌ����܂��̂ŁA���̂悤�ɂ��Ă���܂��B
��l�̐S�����l�ɒʂ�Ƃ��\���܂����v
�ƌ����ƁA�˓c�����͊������ė܂𗬂����Ƃ����B
702�l�Ԏ����l�N
2023/03/10(��) 13:19:38.82ID:AqPhcBaW >>699
���������|���������ł��邩��A�G�g���ƍN��M�������낤�ȁB
���������|���������ł��邩��A�G�g���ƍN��M�������낤�ȁB
703�l�Ԏ����l�N
2023/03/10(��) 15:19:04.75ID:w0q880jL �n�����Ȃ��@���\��������ׂ��₷���̂�
�L�\�䂦�Ɉ����ɍ����
�L�\�䂦�Ɉ����ɍ����
704�l�Ԏ����l�N
2023/03/10(��) 20:37:59.68ID:6tXRKhsW �悵�@�ѐL�����I
705�l�Ԏ����l�N
2023/03/12(��) 16:05:49.62ID:nGsppXvO �u�����ƊՒk�v����{�c����
�_�q�c���E�q��(�_�q�c����)�A�{�c�씪�Y(�{�c����)�A�˓c�O�Y�l�Y(�˓c����)�A�����r�E�q��(�����m��)�͏G�g���n�̎��ɌR�����傫���������߁A�s翂ɖ����m���Ă����B
(���̂��Ɛ_�q�c�����̘b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13315.html )
�������ďG�g������_�q�c�̎N����̑O�̎D��
�u�_�q�c���E�q��͓G�O���S���������a�҂Ȃ̂ň����������v�Ə�������ꂽ�B
�{�c�ɂ��Ă����A�����ގ��̊Ԃɐ�����r�����������B
���鎞�A�_���s�܂̏�ł��ꂼ��̏��ɓ���D���������Ƃ���A�{�c�씪�Y�Ɂu�����D�v�������������B
�G�g���́u�M�����̌䎞�A�ѐV�O�Y�ɓ����D���������������߁A�M�����͌䎩���ł��̎D��V�O�Y�ɂ�������A
�M���u���a�҂ł����̕��قǂƂ͂ȁB
���̕��ł��̂悤�ł���A����D�Ȃǖ��ɗ����ʂȁv
�Ə��Ȃ��ꂽ�Ƃ����B
���̕��ɎD���������̂��������Ƃ��낤�B�v
�Ɗ씪�Y�ɎD�������ꂽ�������B
�G�g�����܂��V���ꂷ��O�ɁA�{�c�͎O�؏�U�߂Ő펀�����Ƃ����B
�˓c�O�Y�l�Y�A�̂��ɕ����͊փ����œ������ɂ����B(���ۂ͒��N�o������A�鎞�ɕa��)
�_�q�c���E�q��(�_�q�c����)�A�{�c�씪�Y(�{�c����)�A�˓c�O�Y�l�Y(�˓c����)�A�����r�E�q��(�����m��)�͏G�g���n�̎��ɌR�����傫���������߁A�s翂ɖ����m���Ă����B
(���̂��Ɛ_�q�c�����̘b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13315.html )
�������ďG�g������_�q�c�̎N����̑O�̎D��
�u�_�q�c���E�q��͓G�O���S���������a�҂Ȃ̂ň����������v�Ə�������ꂽ�B
�{�c�ɂ��Ă����A�����ގ��̊Ԃɐ�����r�����������B
���鎞�A�_���s�܂̏�ł��ꂼ��̏��ɓ���D���������Ƃ���A�{�c�씪�Y�Ɂu�����D�v�������������B
�G�g���́u�M�����̌䎞�A�ѐV�O�Y�ɓ����D���������������߁A�M�����͌䎩���ł��̎D��V�O�Y�ɂ�������A
�M���u���a�҂ł����̕��قǂƂ͂ȁB
���̕��ł��̂悤�ł���A����D�Ȃǖ��ɗ����ʂȁv
�Ə��Ȃ��ꂽ�Ƃ����B
���̕��ɎD���������̂��������Ƃ��낤�B�v
�Ɗ씪�Y�ɎD�������ꂽ�������B
�G�g�����܂��V���ꂷ��O�ɁA�{�c�͎O�؏�U�߂Ő펀�����Ƃ����B
�˓c�O�Y�l�Y�A�̂��ɕ����͊փ����œ������ɂ����B(���ۂ͒��N�o������A�鎞�ɕa��)
706�l�Ԏ����l�N
2023/03/12(��) 16:50:58.98ID:u4UaIy7F �C�C�n�i�V�i�m�J�i�[
707705
2023/03/12(��) 18:31:48.51ID:6PqIzfiZ �����炭�������͂���̂��낤���ǁA�E�B�L�y�f�B�A�̉��߂Ǝ����̉��߂����Ȃ�قȂ��Ă����̂ŁA�����L���Ă����B
�E�B�L�y�f�B�A
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/�{�c����
�����ގ������̂Ƃ��A�{�c�씪�Y�͐�����������������A
������A���m�̐����F�c�����ۂɏG�g���씪�Y�ɑ����̓��D�����ĕ]�����Ƃ���A�씪�Y�͂��̏���o�������A�i�F����́j�D�������������B
�G�g�������ɂ́A
�M�����̉Ɛb�ɂ��ѐV�O�Y�Ƃ������̂������悤�ɂ��̏�ꂽ���i�s�݂ł��������Ƃ���j�D���V���������̂ŁA�M�����͎���V�O�Y���̎^����āA
���a�҂ǂ��͂��̐g�̌�����̂��߂ɐ���F�c�ɏo�Ȃ��邪���O�̂悤�Ȏ�M�҂͂��̏��ق�Ă����Ă��V�������D�����̂�������D����܂ł��Ȃ��Ƃ����ď����A
�Ƃ������Ƃ��������B�G�g�͊씪�Y�����̋C�����낤�Ƃ����āA�D��^���ď܂����Ƃ���[3]�B
����
�����ގ��̊ԁA����r�������肫�B
�����A����F�c�ɓ��D�����v�������ӏ��ɋ{�c�씪�Y���ꂽ��ƎD�������ʁB
�G�g�����킭
�u�M���̌�Ƃ��ѐV�O�Y���D���������肵���A�M�������瑴�D�Ƃ���V�O�Y�ɉ�����
�u���a�҂ł����g�݂̂킯�Ɏz�̂��Ƃ��A�����ɂ��ւ��l�Ȃ�͓��D�p�ɗ��ʎ��Ȃ�v�ƏЋ��ӁB
�������D�����S�Ȃ�v�ƂĊ씪�Ɏ��肯��B
�E�B�L�y�f�B�A
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/�{�c����
�����ގ������̂Ƃ��A�{�c�씪�Y�͐�����������������A
������A���m�̐����F�c�����ۂɏG�g���씪�Y�ɑ����̓��D�����ĕ]�����Ƃ���A�씪�Y�͂��̏���o�������A�i�F����́j�D�������������B
�G�g�������ɂ́A
�M�����̉Ɛb�ɂ��ѐV�O�Y�Ƃ������̂������悤�ɂ��̏�ꂽ���i�s�݂ł��������Ƃ���j�D���V���������̂ŁA�M�����͎���V�O�Y���̎^����āA
���a�҂ǂ��͂��̐g�̌�����̂��߂ɐ���F�c�ɏo�Ȃ��邪���O�̂悤�Ȏ�M�҂͂��̏��ق�Ă����Ă��V�������D�����̂�������D����܂ł��Ȃ��Ƃ����ď����A
�Ƃ������Ƃ��������B�G�g�͊씪�Y�����̋C�����낤�Ƃ����āA�D��^���ď܂����Ƃ���[3]�B
����
�����ގ��̊ԁA����r�������肫�B
�����A����F�c�ɓ��D�����v�������ӏ��ɋ{�c�씪�Y���ꂽ��ƎD�������ʁB
�G�g�����킭
�u�M���̌�Ƃ��ѐV�O�Y���D���������肵���A�M�������瑴�D�Ƃ���V�O�Y�ɉ�����
�u���a�҂ł����g�݂̂킯�Ɏz�̂��Ƃ��A�����ɂ��ւ��l�Ȃ�͓��D�p�ɗ��ʎ��Ȃ�v�ƏЋ��ӁB
�������D�����S�Ȃ�v�ƂĊ씪�Ɏ��肯��B
708�l�Ԏ����l�N
2023/03/13(��) 08:56:51.11ID:I+/rUjav709�l�Ԏ����l�N
2023/03/13(��) 09:01:24.77ID:I+/rUjav >>705
������̖�̕������R�Ɍ�����ˁB
������̖�̕������R�Ɍ�����ˁB
710�l�Ԏ����l�N
2023/03/13(��) 11:55:09.74ID:Lm1LxlrS �e�X�������̐�����咣���ďꂪ����邩��A�e�X�Ɋi�t�����Ă�����đ��v�������������
�ł��Ȃ�œ����o���K�v������H
���l�̕]���Ȃ������˂��I�����C�`�o���I�Ă����z�������̂�
�ł��Ȃ�œ����o���K�v������H
���l�̕]���Ȃ������˂��I�����C�`�o���I�Ă����z�������̂�
711�l�Ԏ����l�N
2023/03/13(��) 15:05:26.52ID:eeE8J6i+ �P�ɏƂꉮ����ȋC��
712�l�Ԏ����l�N
2023/03/13(��) 16:08:50.42ID:tj7WdSLK ���Z��𗧂Ă�Ȃ��
���킟�L����
���킟�L����
713�l�Ԏ����l�N
2023/03/14(��) 21:11:06.83ID:r3YEvImd �y���E�q��сi�����j���A�R���O�Y���q�i���i�j�ɕ�����
�u������A���R�i�M�N�j�a���A�n����Z�i�M�t�j�a�ɖ��ꂽ�A���B�l���̓���ƍN�ɂ��Ẳ\�ɂ��āA
�n����Z�a�́A�w�Y�\�͂₭�����l�𗘍��ҁA���z�ǂ��l�𗘔��ҁA���ӂ̏���Ďd��l�𗘌��ҁx�ƁA
���Z�a�͋�����ꂽ�ƕ����y��ł܂��B���āA�ł́i���c�ƒ��́j�����̒��ɁA�����ɂė����ɂāA������
�����Ȃ�l�͗L��ł��傤���H�v
�R���H��
�u�M�����̌�Ƃɂ́A���叫�Ƃ��Ă͓����C�����i���L�j�A���y�叫�Ƃ��Ă͉��c�\�Y���q�i�N�i�j�ƁA
���̓�l������܂��B���̑����叫�̒��ŁA���ł͏��R�c��O�Y�i�M���j�Ȃǂ�����܂��B
�����������l���̒��ł��A�쒆������̎������Ȃ��ꂽ�̓T�X�i���c�M�Ɂj�l�Ȃǂ́A�������������A
�܂����������R�ƌ����ׂ��l���ł����B�v
�R���O�Y���q�͂��̂悤�ɐ\���ꂽ�B
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/sengoku/1630338432/702
���̂��b�̑����ł���
�w�b�z�R�Ӂx
�u������A���R�i�M�N�j�a���A�n����Z�i�M�t�j�a�ɖ��ꂽ�A���B�l���̓���ƍN�ɂ��Ẳ\�ɂ��āA
�n����Z�a�́A�w�Y�\�͂₭�����l�𗘍��ҁA���z�ǂ��l�𗘔��ҁA���ӂ̏���Ďd��l�𗘌��ҁx�ƁA
���Z�a�͋�����ꂽ�ƕ����y��ł܂��B���āA�ł́i���c�ƒ��́j�����̒��ɁA�����ɂė����ɂāA������
�����Ȃ�l�͗L��ł��傤���H�v
�R���H��
�u�M�����̌�Ƃɂ́A���叫�Ƃ��Ă͓����C�����i���L�j�A���y�叫�Ƃ��Ă͉��c�\�Y���q�i�N�i�j�ƁA
���̓�l������܂��B���̑����叫�̒��ŁA���ł͏��R�c��O�Y�i�M���j�Ȃǂ�����܂��B
�����������l���̒��ł��A�쒆������̎������Ȃ��ꂽ�̓T�X�i���c�M�Ɂj�l�Ȃǂ́A�������������A
�܂����������R�ƌ����ׂ��l���ł����B�v
�R���O�Y���q�͂��̂悤�ɐ\���ꂽ�B
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/sengoku/1630338432/702
���̂��b�̑����ł���
�w�b�z�R�Ӂx
714�l�Ԏ����l�N
2023/03/15(��) 12:17:12.30ID:ChfCPxYW �L�b�G������
https://i.imgur.com/7zJt6PI.gif
https://i.imgur.com/7zJt6PI.gif
715�l�Ԏ����l�N
2023/03/15(��) 21:05:54.17ID:ffNL6Pnx �u�����ƊՒk�v����{�����M�ɂ���
�{�����n�琳�M�̐l���ɂ��Ă͐��̐l���m�邱�Ƃł���A�M��s�����Ă�����Ȃ��B
�����l���l�ΔN��ŁA�㋞�̍ۂɏ��i�v�G��
�u�ƍN�̉Ɛb�����͊F���E���D�ނ��A�{���픪�Y���M�݂͕̂s���s�_�s���łقƂ�ǖ}�l�ł͂Ȃ��v�ƌ������Ƃ����B
���}�G�g�����M�̂��Ƃ��y��Ō����l�ɍ����ď����������B
�����ɐ��M�͍]�˂��畚���ɏo�āA��ڌ������Ƃ��A�Ђ����Ɍ�|���f�����B
�[���ɂ͑��c�����̂Ƃ���ɍs���A�����ɂ킽�薧�k���ĉɂ������āA�����]�˂ɋA�����B
���c�����Ƃ��Ƃ�Ȃ����̂��A�G�g�͂����ę�߂Ȃ������B
�܂������l���|�����D��ł����B
���̂���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-1222.html
����ƍN�A�Ɛb���|�����u�����v�����b
���M�͑傢�Ɋ��S���A�h���ő��q�̏�����ɂ��̂��Ƃ�\�����������B
�����́u���̐l�͒N�Ȃ̂ł����H�v�Ɩ₤���̂�
���M�͑傢�ɓ{��
�u������������������邱�Ƃɂ́A
�u�V�������ׂɂ����邤���ő厖�Ȃ��Ƃ́A�א��҂̐l�ƂȂ肪�P�ł��邽�߂ł͂Ȃ��B
��{���Ȃ��Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A�悭�|�߂����Č�����ӂ������A�Ɛb��p���邽�߂ɓV���͂悭���܂�v
�Ƃ������Ƃ��|�����D�܂��̂��B
���̘b���|���������҂͒q�b���s�����Ă��邽�߁A�\���Ƃ���ɂ������͂Ȃ����A����ł���a�͂��̐S���܂��Ȃ������B
���O�����̎҂̖����đ���Ȃ��Ƃ����������炨���Ƃ����S�ł���Ύ�a�̎����ɂ͂Ȃ�ׂ��ł͂Ȃ��v
���M�͏�Ɍ����l���u��a�v�A�䓿���i�G���j���u��a�v�ƌ����Ă������A����͌����l�̒������[���u�F�̂��Ƃ��v�Ƃ���Ă������߂ł���B���p������������B
�����l�͕����E���͂Ŏ���Ȃ����Ă����B
���M�͍]�˂ő䓿���̎����ł��������A�����l�̗ɒ���f���B
�����l�̋��ɂ́u�V�̎���͑��ɕ���Y��Ȃ����ƁA���ɖ��Ԃ̂��Ƃ�₤���߂ł���v�Ƃ������Ƃł������B
�Ƃ���ǂ���Ɍ䗯��i���R�Ƃ̗�j������A�����l�̒��ӂ͌��������̂ł��������߁A�䓿���͋ނ�Ő����������Ƃ����B
�{�����n�琳�M�̐l���ɂ��Ă͐��̐l���m�邱�Ƃł���A�M��s�����Ă�����Ȃ��B
�����l���l�ΔN��ŁA�㋞�̍ۂɏ��i�v�G��
�u�ƍN�̉Ɛb�����͊F���E���D�ނ��A�{���픪�Y���M�݂͕̂s���s�_�s���łقƂ�ǖ}�l�ł͂Ȃ��v�ƌ������Ƃ����B
���}�G�g�����M�̂��Ƃ��y��Ō����l�ɍ����ď����������B
�����ɐ��M�͍]�˂��畚���ɏo�āA��ڌ������Ƃ��A�Ђ����Ɍ�|���f�����B
�[���ɂ͑��c�����̂Ƃ���ɍs���A�����ɂ킽�薧�k���ĉɂ������āA�����]�˂ɋA�����B
���c�����Ƃ��Ƃ�Ȃ����̂��A�G�g�͂����ę�߂Ȃ������B
�܂������l���|�����D��ł����B
���̂���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-1222.html
����ƍN�A�Ɛb���|�����u�����v�����b
���M�͑傢�Ɋ��S���A�h���ő��q�̏�����ɂ��̂��Ƃ�\�����������B
�����́u���̐l�͒N�Ȃ̂ł����H�v�Ɩ₤���̂�
���M�͑傢�ɓ{��
�u������������������邱�Ƃɂ́A
�u�V�������ׂɂ����邤���ő厖�Ȃ��Ƃ́A�א��҂̐l�ƂȂ肪�P�ł��邽�߂ł͂Ȃ��B
��{���Ȃ��Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A�悭�|�߂����Č�����ӂ������A�Ɛb��p���邽�߂ɓV���͂悭���܂�v
�Ƃ������Ƃ��|�����D�܂��̂��B
���̘b���|���������҂͒q�b���s�����Ă��邽�߁A�\���Ƃ���ɂ������͂Ȃ����A����ł���a�͂��̐S���܂��Ȃ������B
���O�����̎҂̖����đ���Ȃ��Ƃ����������炨���Ƃ����S�ł���Ύ�a�̎����ɂ͂Ȃ�ׂ��ł͂Ȃ��v
���M�͏�Ɍ����l���u��a�v�A�䓿���i�G���j���u��a�v�ƌ����Ă������A����͌����l�̒������[���u�F�̂��Ƃ��v�Ƃ���Ă������߂ł���B���p������������B
�����l�͕����E���͂Ŏ���Ȃ����Ă����B
���M�͍]�˂ő䓿���̎����ł��������A�����l�̗ɒ���f���B
�����l�̋��ɂ́u�V�̎���͑��ɕ���Y��Ȃ����ƁA���ɖ��Ԃ̂��Ƃ�₤���߂ł���v�Ƃ������Ƃł������B
�Ƃ���ǂ���Ɍ䗯��i���R�Ƃ̗�j������A�����l�̒��ӂ͌��������̂ł��������߁A�䓿���͋ނ�Ő����������Ƃ����B
716�l�Ԏ����l�N
2023/03/15(��) 21:08:51.53ID:ffNL6Pnx ���̂���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-5962.html
�{�����M�A�ƍN�̓{���
�̘b�����ǔ����ɈႤ�̂ňꉞ�����Ă����B
���钩�A�����l���䗗�ɂȂ�ƁA�䗯���㩂ƂƂ���������������Ă����B
�N�̂��̂����ׂ��Ƃ���R�����Ɠ��������ɂ����̂ł������B
�����l�́u���R�͂��̂��Ƃ𑶂��Ă���̂��v�Ƃ��{��ɂȂ�ꂽ�B
�䓿���́u�����Ă̂ق��̌���f�ł���܂��傤���A���͒m��܂���B
���l���n���Č䕮����Ȃ��߂�ׂ��ł͂���܂����A���l�͉�ɂ��t���Ȃ����������ł���܂����A�E���ɔE�т܂���B
���炭�o�d����߂����܂��傤�v
�ƈ����ǂ���Ă�������������A�����l�͌�e�͂���Ȃ������B
�����Ő��M�́u���̂܂܂ł͑�a�̈������q�ɉz���Ă��܂��B
��a�ɍ��Ƃ��̂Ă����C�v�ɗ��Ƃ����Ƃ����ł��ɂȂ�̂ɁA�܂��ē����E�R�Ȃǂ́v
�܂��͐\���グ�悤�Ƃ������ƂŌ����l�̌����Ɏf��
�u�N����a�ɖ����ē����E�R���l�̐ؕ����Ȃ���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ����������܂����B
�܂��Ƃɕs���̂�����ŁA���ꂪ���Ȃǐ����d���������ŁA�����c���ŏ����ł����s�������������܂��߉Ȃ������ނ�ł��傤�B
�]�ˏ��Z�̏o�d����߂đ�a�̂Ƃ���œV���̎��ɐi�݂܂��傤�v�Ɛ\���ƁA�����l�̂��S���Ƃ��āA�����ǂ�
�u���R�����̂悤�ɐ\���Ă���̂�����A�F�l���E���ʂ悤�\�����킷�v�Ɩ�����ꂽ�B
�䓿���͂���������A�傢�ɉx�сA���l����邵�ĉƂɋA�点���Ƃ����B
���M�̍ˊo�̖��ł������B
�����������^�������āA�킸����̂����B�փP���̑O��A���̐w�ł̖d���ɂ��Ă͂قƂ�ǐl�����Y�t���Ă���B
���M�͌����l�䑼�E����\�����������a��N�i1616�N�j�Z�������Ɏ��\��Ŏ��B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-5962.html
�{�����M�A�ƍN�̓{���
�̘b�����ǔ����ɈႤ�̂ňꉞ�����Ă����B
���钩�A�����l���䗗�ɂȂ�ƁA�䗯���㩂ƂƂ���������������Ă����B
�N�̂��̂����ׂ��Ƃ���R�����Ɠ��������ɂ����̂ł������B
�����l�́u���R�͂��̂��Ƃ𑶂��Ă���̂��v�Ƃ��{��ɂȂ�ꂽ�B
�䓿���́u�����Ă̂ق��̌���f�ł���܂��傤���A���͒m��܂���B
���l���n���Č䕮����Ȃ��߂�ׂ��ł͂���܂����A���l�͉�ɂ��t���Ȃ����������ł���܂����A�E���ɔE�т܂���B
���炭�o�d����߂����܂��傤�v
�ƈ����ǂ���Ă�������������A�����l�͌�e�͂���Ȃ������B
�����Ő��M�́u���̂܂܂ł͑�a�̈������q�ɉz���Ă��܂��B
��a�ɍ��Ƃ��̂Ă����C�v�ɗ��Ƃ����Ƃ����ł��ɂȂ�̂ɁA�܂��ē����E�R�Ȃǂ́v
�܂��͐\���グ�悤�Ƃ������ƂŌ����l�̌����Ɏf��
�u�N����a�ɖ����ē����E�R���l�̐ؕ����Ȃ���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ����������܂����B
�܂��Ƃɕs���̂�����ŁA���ꂪ���Ȃǐ����d���������ŁA�����c���ŏ����ł����s�������������܂��߉Ȃ������ނ�ł��傤�B
�]�ˏ��Z�̏o�d����߂đ�a�̂Ƃ���œV���̎��ɐi�݂܂��傤�v�Ɛ\���ƁA�����l�̂��S���Ƃ��āA�����ǂ�
�u���R�����̂悤�ɐ\���Ă���̂�����A�F�l���E���ʂ悤�\�����킷�v�Ɩ�����ꂽ�B
�䓿���͂���������A�傢�ɉx�сA���l����邵�ĉƂɋA�点���Ƃ����B
���M�̍ˊo�̖��ł������B
�����������^�������āA�킸����̂����B�փP���̑O��A���̐w�ł̖d���ɂ��Ă͂قƂ�ǐl�����Y�t���Ă���B
���M�͌����l�䑼�E����\�����������a��N�i1616�N�j�Z�������Ɏ��\��Ŏ��B
717�l�Ԏ����l�N
2023/03/16(��) 00:09:26.38ID:UMfQ7unG �u�퍑�����̎q���v���������Ă��ċ����|�\�l�����L���O�@3�ʂ͓������Ղ̖���u����Ă��v2�ʂɖ��q���G�̖���u�N���X�E�y�v���[�v [muffin��]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1678880086/1
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1678880086/1
718�l�Ԏ����l�N
2023/03/16(��) 00:11:03.96ID:tg45pgpv ���������͈����ۂ��킫�܂��Ă����̂ɑ��q��
719�l�Ԏ����l�N
2023/03/16(��) 12:47:37.77ID:1Yy0JpW0720�l�Ԏ����l�N
2023/03/16(��) 15:53:31.21ID:hV6MjIDN �G�g�݂����Ɏq�����ɍ��\��^���Ă��玟�̑�łʂ��E����邩��Ȃ�
721�l�Ԏ����l�N
2023/03/16(��) 17:02:32.71ID:1Yy0JpW0 �M���͐e�˂ƕ��オ���͂ŁA�O�l�Ƃ�����͉̂ƍN���炢���B�����喼������ŏ��˂��Ȃ���ہB
�G�g�͐e�˂��キ�A����i�q�����j���܂��܂��A�O�l�����́B
�ƍN�͐e�˂ƊO�l����˂ŁA����͎ア�B
�܂��A�]�˖��{�ŊO�l����˂ɂȂ����̂͊փ����̌o�܂���d���Ȃ��ʂ͂���B�ł��A�{���������炢�ɂ͈ꍑ��������Ă悩�����̂ɂȁB
�G�g�͐e�˂��キ�A����i�q�����j���܂��܂��A�O�l�����́B
�ƍN�͐e�˂ƊO�l����˂ŁA����͎ア�B
�܂��A�]�˖��{�ŊO�l����˂ɂȂ����̂͊փ����̌o�܂���d���Ȃ��ʂ͂���B�ł��A�{���������炢�ɂ͈ꍑ��������Ă悩�����̂ɂȁB
722�l�Ԏ����l�N
2023/03/16(��) 18:32:22.63ID:fKzTrDzf �G���݂����ȎY�܂���@�B�����̂�����
723�l�Ԏ����l�N
2023/03/17(��) 09:06:24.94ID:ckdpC3Sb �܂��A���݂����Łu�������̂܂܂ɂ��Ƃ��ƏG������˂��c�v�ƂȂ����낤�ȁB
724�l�Ԏ����l�N
2023/03/17(��) 10:33:44.97ID:ct6DtIHM �q��R�̏G�����G������p���ɂ���Ƃ͎v���Ȃ�����ˁB�����G�g���G�������ނ��Ăł��G������p���ɂ��悤�Ƃ��Ă邭�炢�Ȃ̂�����
725�l�Ԏ����l�N
2023/03/17(��) 11:00:50.59ID:TGOPjo4/ �s�ϑ���̎q���Ȃ̂ɎS�߂���
726�l�Ԏ����l�N
2023/03/19(��) 18:45:51.31ID:3oOcadZo �����b���͔��������A�G���Ȃ���ŁB�G�����F���ɓ������т��Ƃ����b��杊C�ɂ������̂ŁB������Ɠs�s�`�������̘b�B
���g�̓�̊C����F���ւ͂قNj߂��A�D�ł��₷������ʼn����ł���B����䂦�͈̂��g�̋��t���ނ�����Ȃ���F���܂ōs���A�����ŋx�����Ĉ��g�ɋA��Ƃ��������Ƃ����X����A���R�ƒm�荇�����ł��āA�D���ĉ����̉���������������悤�ɂȂ����B���̑D���悹��ꏊ�͎F���̓�C�̕l�ӂŁA�݂̏�ɂ͌��d�Ȕԏ��̂悤�Ȃ��̂��������B�Ƃ͂����A�C�̂������ŔԐl����l����l�A�l�̂��Ȃ����X����Ƃ���ŁA��������Ă��邩���肩�ł͂Ȃ��B����ȂƂ��낾����A���g�̋��t�������C�y�ɐ��Ԙb�����ɂ��т��яW�܂��ĔԐl�����ƒ��ǂ��Ȃ����B
�@���鋙�t���D�������̂��ƁB�Ԑl�͈�l�����炸�A���炭�҂��Ă��N�����Ȃ��̂ŁA�����炢�Ɋ݂ɏオ��A�ԏ��̒��֓������B����ƁA�����߂Ă���ԏ��̌��̔��������͊J���Ă���B�����낤�Ǝv���ĉ��̋C�Ȃ��ɓ����Ă݂�ƁA�Y��ɑ|�����s���͂��Ă��Đl���q��l���Ȃ��B�т��т����Ȃ��牜�ɐi�ނƁA�傫�Ȑ̌ܗ֓�����A�O���B�s�v�c�Ɏv���Ȃ��炳��ɐi�ނƁA�ʼn��ɔ��X����������ܗ֓��������āA�_�_�������̂悤�ɂ��Ă������B�ق��ɂ͉����Ȃ��̂őD�ɖ߂��đ҂��Ă���ƁA�����̔Ԑl���d��w�����ĎR����A���Ă����̂ŁA�D����オ���ĎG�k�������B
�ӂƁA�u���̉��ɂ��邨��̂悤�Ȃ��͉̂��ł����v�Ɛq�˂�ƁA�Ԑl�傢�ɋ����āu���Ȃ����A���������ꂽ�̂��B����͔��Ȕ鎖�Ȃ̂ŁA�����Č��O���Ȃ��ł��������B�����͂������̑|����������A�R�֖�����ɍs�����̂ŁA�����������Y��Ă��܂����B�Ƃɂ����A�����Č��O�Ȃ����܂��ȁv�Ɖ��x���O���������B���t���������Ă͖L�b�G���̂�����͂��߁A�^�c���q��сA���̂ق��̐l�X�̕�Ȃ̂ł��낤�ƐS�Â����B���̂̂��́A�Ԑl�������S�|���ċ��t�Ɛe���������A�����đ����̑D���݂Ɋ�̂������ʂ悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B
���g�̓�̊C����F���ւ͂قNj߂��A�D�ł��₷������ʼn����ł���B����䂦�͈̂��g�̋��t���ނ�����Ȃ���F���܂ōs���A�����ŋx�����Ĉ��g�ɋA��Ƃ��������Ƃ����X����A���R�ƒm�荇�����ł��āA�D���ĉ����̉���������������悤�ɂȂ����B���̑D���悹��ꏊ�͎F���̓�C�̕l�ӂŁA�݂̏�ɂ͌��d�Ȕԏ��̂悤�Ȃ��̂��������B�Ƃ͂����A�C�̂������ŔԐl����l����l�A�l�̂��Ȃ����X����Ƃ���ŁA��������Ă��邩���肩�ł͂Ȃ��B����ȂƂ��낾����A���g�̋��t�������C�y�ɐ��Ԙb�����ɂ��т��яW�܂��ĔԐl�����ƒ��ǂ��Ȃ����B
�@���鋙�t���D�������̂��ƁB�Ԑl�͈�l�����炸�A���炭�҂��Ă��N�����Ȃ��̂ŁA�����炢�Ɋ݂ɏオ��A�ԏ��̒��֓������B����ƁA�����߂Ă���ԏ��̌��̔��������͊J���Ă���B�����낤�Ǝv���ĉ��̋C�Ȃ��ɓ����Ă݂�ƁA�Y��ɑ|�����s���͂��Ă��Đl���q��l���Ȃ��B�т��т����Ȃ��牜�ɐi�ނƁA�傫�Ȑ̌ܗ֓�����A�O���B�s�v�c�Ɏv���Ȃ��炳��ɐi�ނƁA�ʼn��ɔ��X����������ܗ֓��������āA�_�_�������̂悤�ɂ��Ă������B�ق��ɂ͉����Ȃ��̂őD�ɖ߂��đ҂��Ă���ƁA�����̔Ԑl���d��w�����ĎR����A���Ă����̂ŁA�D����オ���ĎG�k�������B
�ӂƁA�u���̉��ɂ��邨��̂悤�Ȃ��͉̂��ł����v�Ɛq�˂�ƁA�Ԑl�傢�ɋ����āu���Ȃ����A���������ꂽ�̂��B����͔��Ȕ鎖�Ȃ̂ŁA�����Č��O���Ȃ��ł��������B�����͂������̑|����������A�R�֖�����ɍs�����̂ŁA�����������Y��Ă��܂����B�Ƃɂ����A�����Č��O�Ȃ����܂��ȁv�Ɖ��x���O���������B���t���������Ă͖L�b�G���̂�����͂��߁A�^�c���q��сA���̂ق��̐l�X�̕�Ȃ̂ł��낤�ƐS�Â����B���̂̂��́A�Ԑl�������S�|���ċ��t�Ɛe���������A�����đ����̑D���݂Ɋ�̂������ʂ悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B
727�l�Ԏ����l�N
2023/03/20(��) 06:12:03.81ID:jc7bScQm ���@�ނ�͂悭�A�Љ�ɍv���������ƌ��ɂ���B
���@�Ȃ�ł��Љ�̃l�g�E�������E�ɒǂ����ނ��Ƃ��A�Љ�ɍv�����邱�ƂȂ����ŁB
���@�C�W���⌙���点�ŎЉ�ɍv���ł��鋳�t��x���ɂȂ邽�߂ɁA�����ċA��������ł����āA�c�����E�𗠐����킯�ł͂Ȃ��A�S�́����l�Ȃ������B
���@
���@�̂͋A������Ɨ���҂ƌĂꂽ�肵�����A�c���ɍ��Ђ��c�����܂܋A��������@���m�����ꂽ���݂ł́A�Љ�ɍv�����邽�߂ɂނ���A�����邱�Ƃ���������Ă���B
���@���e�����őO�Ȃ̂��鐶���̔����Ƃł���A���ł͕��ʂɋA�����Ă���B
���@
���@�����w��Ȃǂ̓l�g�E���F�肵�����{�l�𓐎B���āA�s���̎ʐ^���ƌ����Ă�܂��Ă���B
���@�����̎ʐ^�́A�W�c�X�g�[�J�[�Ɏg�p�����B
���@�ނ�͏W�c�X�g�[�J�[���A�m�n��Ŏq���������S���S�p�g���[���n�Ə̂��Ă���B
���@�Ȃ�ł��Љ�̃l�g�E�������E�ɒǂ����ނ��Ƃ��A�Љ�ɍv�����邱�ƂȂ����ŁB
���@�C�W���⌙���点�ŎЉ�ɍv���ł��鋳�t��x���ɂȂ邽�߂ɁA�����ċA��������ł����āA�c�����E�𗠐����킯�ł͂Ȃ��A�S�́����l�Ȃ������B
���@
���@�̂͋A������Ɨ���҂ƌĂꂽ�肵�����A�c���ɍ��Ђ��c�����܂܋A��������@���m�����ꂽ���݂ł́A�Љ�ɍv�����邽�߂ɂނ���A�����邱�Ƃ���������Ă���B
���@���e�����őO�Ȃ̂��鐶���̔����Ƃł���A���ł͕��ʂɋA�����Ă���B
���@
���@�����w��Ȃǂ̓l�g�E���F�肵�����{�l�𓐎B���āA�s���̎ʐ^���ƌ����Ă�܂��Ă���B
���@�����̎ʐ^�́A�W�c�X�g�[�J�[�Ɏg�p�����B
���@�ނ�͏W�c�X�g�[�J�[���A�m�n��Ŏq���������S���S�p�g���[���n�Ə̂��Ă���B
728�l�Ԏ����l�N
2023/03/20(��) 09:34:02.22ID:dJ+hqUf/ �l�g�E���͓�����������
729�l�Ԏ����l�N
2023/03/20(��) 18:03:21.91ID:a61r3H24 �u�ǂ�����ƍN�v�̋I�s�Łu�l���܂�v�����グ���Ă����̂ŁA
�l���̑��g�����n�߂��Ƃ��������r�ܘY�ɂ���
�����r�ܘY�Ƒ��g���̊֘A�ɂ���1974�N�́u�_���s�j�v�Ɉ��p����Ă���
����^�W�u�l����L�v(���c�߂̕������ԏ�Ő�����ƋL���u�l����ݏ�L�v�Ƃ͕�)�Ƃ��������鏑�̈��(���݂��邩�s��)�A���甲�������
��A�i�\�N���@�є��L�O��a�䋏��
���̎q���g�n��ɏZ�����A�`�L(�L�O�璷�q)�a��a���̎������r�ܘY(����̎�)���̑�Ȃ���̂Ɍ䖼���L���g���
(����)
��A�c���Z�N��菼�����n��a�@��N�䋏��
�c����N�A�O�o�����r�ܘY�A���N�ɋA�����Ē��N�l�g�߂ƂȂ�ĕl���̑����ӁA���n��a�]�˂ɐ\����A
�i��A�����̊��{�����ɑ���
�Ƃ���Ă��č����r�ܘY�͕l���̓���̐l�ԂƂȂ��Ă���B
���������r�ܘY�̕��͌n�}�ł�
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13835.html
�O�͈���Ꝅ�Ő��쒉�d�ɓ����ꂽ(�u�O�͕���v�ɂ���)�����r�ܘY�g���Ƃ����
�l���̑��g�����n�߂��Ƃ��������r�ܘY�ɂ���
�����r�ܘY�Ƒ��g���̊֘A�ɂ���1974�N�́u�_���s�j�v�Ɉ��p����Ă���
����^�W�u�l����L�v(���c�߂̕������ԏ�Ő�����ƋL���u�l����ݏ�L�v�Ƃ͕�)�Ƃ��������鏑�̈��(���݂��邩�s��)�A���甲�������
��A�i�\�N���@�є��L�O��a�䋏��
���̎q���g�n��ɏZ�����A�`�L(�L�O�璷�q)�a��a���̎������r�ܘY(����̎�)���̑�Ȃ���̂Ɍ䖼���L���g���
(����)
��A�c���Z�N��菼�����n��a�@��N�䋏��
�c����N�A�O�o�����r�ܘY�A���N�ɋA�����Ē��N�l�g�߂ƂȂ�ĕl���̑����ӁA���n��a�]�˂ɐ\����A
�i��A�����̊��{�����ɑ���
�Ƃ���Ă��č����r�ܘY�͕l���̓���̐l�ԂƂȂ��Ă���B
���������r�ܘY�̕��͌n�}�ł�
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13835.html
�O�͈���Ꝅ�Ő��쒉�d�ɓ����ꂽ(�u�O�͕���v�ɂ���)�����r�ܘY�g���Ƃ����
730�l�Ԏ����l�N
2023/03/20(��) 18:06:32.38ID:a61r3H24 http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13751.html
�u�����O�͍��㕗�y�L�v�ł́A���̂悤�ɏ����M�N�Ɏd���Ă������̂̓������ʂ��������߂ɒ��d
���̂̂����c�R�̊×��M�P�̎����y�Y�ɋA�Q�B
�b��̍����(1582�N)�Ŋ�����ƍN�ɑ��܂�Ă������ߍĂяo�z
�c���N�Ԃɒ��N�̎g�߂Ƃ��ė������Ă���
(���̘b�����ɏ����u�����r�ܘY�v���������X���O�́u�����Ɗb�v�����ɂ����A�ƋL���Ă��āA
�R���n�u�w�����r�ܘY�x���v�ł��u�����ƊՒk�v���\�O�Ɂu�����O�͍��㕗�y�L�v�̌��ɂȂ����b������Ƃ��Ă�����
�����������ق́u�����ƊՒk�v�ł͌�����Ȃ�����)
�����ł̊���ɂ��Ă�
�u�����ƊՒk�v���\��(�Ҏ҂̖ؑ����ւɂ��A���̊��́u���쏟���o���v���̂���)�́u�b�{�V�{������̂��Ɓv�ɂ���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-3686.html
���̘b�̑O�����͂قړ�����
�u���̍����r�ܘY�Ɛ\�����͎̂O�Y�l(�����M�N)�ɏ����g���Ă����҂ł������܂����B
�O�Y�l���䑼�E�Ȃ��ꂽ���ƁA�������爫�����Ƃ����ł����ďo�z���Ă����̂ł����A�ǂ��������Ƃ����̂Ƃ��ɂَ͐҂̑O�ɂ��܂����B
�̋��̑��ł悭�|���˂Ă����̂ŁA�u����͎ˎ�ł��낤�v�Ǝv���Ă���܂����B
�d���̋|�ł������܂������S�C�őł��܂�ꂽ���ߎ̂Ă܂����B
�r�ܘY���u���͂�|���܂�A����ɋy���v�Ɛ\�����̂�
�َ҂��u�|���ł��܂�Ă��������邾�낤�v�Ɛ\����
�r�ܘY�́u��O�ɂ͑����Ȃ����̓������ł��B����Ȃ��v
�Ƃ����̂��Ƃ�����U���ƁA�����ȓ����ŁA���荇���ɑł������܂����B
�Ζ�P�\�Y�A�����������A���̎O�l���傢�ɓ����܂����B
(����)�����������A�Ζ�P�\�Y��͂��̌�I�ɑ�[���l�����l��ӂɂĂ���ꂽ�����ł��v
�Ȃ��u�O�͌㕗�y�L�v���Ƃ��̗E�҂Ԃ肪�ƍN�̎��ɒB���邪�A�ƍN�͍����r�ܘY��s�`�̎҂Ƒ���ł������߁A�����������n�E�����Ă���A�o�z���Ē��N�ɁA�Ƃ��͏o�Ă��Ȃ��B
�u�����O�͍��㕗�y�L�v�ł́A���̂悤�ɏ����M�N�Ɏd���Ă������̂̓������ʂ��������߂ɒ��d
���̂̂����c�R�̊×��M�P�̎����y�Y�ɋA�Q�B
�b��̍����(1582�N)�Ŋ�����ƍN�ɑ��܂�Ă������ߍĂяo�z
�c���N�Ԃɒ��N�̎g�߂Ƃ��ė������Ă���
(���̘b�����ɏ����u�����r�ܘY�v���������X���O�́u�����Ɗb�v�����ɂ����A�ƋL���Ă��āA
�R���n�u�w�����r�ܘY�x���v�ł��u�����ƊՒk�v���\�O�Ɂu�����O�͍��㕗�y�L�v�̌��ɂȂ����b������Ƃ��Ă�����
�����������ق́u�����ƊՒk�v�ł͌�����Ȃ�����)
�����ł̊���ɂ��Ă�
�u�����ƊՒk�v���\��(�Ҏ҂̖ؑ����ւɂ��A���̊��́u���쏟���o���v���̂���)�́u�b�{�V�{������̂��Ɓv�ɂ���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-3686.html
���̘b�̑O�����͂قړ�����
�u���̍����r�ܘY�Ɛ\�����͎̂O�Y�l(�����M�N)�ɏ����g���Ă����҂ł������܂����B
�O�Y�l���䑼�E�Ȃ��ꂽ���ƁA�������爫�����Ƃ����ł����ďo�z���Ă����̂ł����A�ǂ��������Ƃ����̂Ƃ��ɂَ͐҂̑O�ɂ��܂����B
�̋��̑��ł悭�|���˂Ă����̂ŁA�u����͎ˎ�ł��낤�v�Ǝv���Ă���܂����B
�d���̋|�ł������܂������S�C�őł��܂�ꂽ���ߎ̂Ă܂����B
�r�ܘY���u���͂�|���܂�A����ɋy���v�Ɛ\�����̂�
�َ҂��u�|���ł��܂�Ă��������邾�낤�v�Ɛ\����
�r�ܘY�́u��O�ɂ͑����Ȃ����̓������ł��B����Ȃ��v
�Ƃ����̂��Ƃ�����U���ƁA�����ȓ����ŁA���荇���ɑł������܂����B
�Ζ�P�\�Y�A�����������A���̎O�l���傢�ɓ����܂����B
(����)�����������A�Ζ�P�\�Y��͂��̌�I�ɑ�[���l�����l��ӂɂĂ���ꂽ�����ł��v
�Ȃ��u�O�͌㕗�y�L�v���Ƃ��̗E�҂Ԃ肪�ƍN�̎��ɒB���邪�A�ƍN�͍����r�ܘY��s�`�̎҂Ƒ���ł������߁A�����������n�E�����Ă���A�o�z���Ē��N�ɁA�Ƃ��͏o�Ă��Ȃ��B
731�l�Ԏ����l�N
2023/03/20(��) 18:19:40.83ID:a61r3H24 �u�l����L�v�̋L�q�����������Ƃɂ��č����r�ܘY�ɂ��Ă܂Ƃ߂�ƁA
�E�i�\�Z�N(1563�N)����A�O�͈���Ꝅ�Ő��쒉�d�ɕ����E���ꂽ���߁A�l���̓���ɏZ��
�E�є��A�������^�ɎE���ꂽ�i�\���N(1565�N)�܂łɁA���ԏ�̔є��A���Ƃ��c�߂̕��̊Ԃɒ��j�����܂ꂽ���Ƃ��j���đ����g����
�E���ԏ闎���A�����M�N�Ɏd���邪�V���l�N(1576�N)�܂łɓ��y���E���ďo�z
�E�V���l�N(1576�N)�A���c�̊×��M�P�Ɏ��s���Ē������邪�A�×��̐Q���~���ē���A�Q
�E�V���\�N(1582�N)�̍����ł́A���̋w�ł��鐅�쒉�d�̒��j�̐��쏟���Ƌ���
�E�������ƍN�ɑa�܂�A�����������n�E�����
�E�������͍Ăяo�z�����N�ɓn��A�c����N(1604�N)�ɒ��N�g�߂Ƃ��ė������A�l���Ŏ����̑���g�����R���ƂȂ������g�������ď�
�Ƃ��낪�ƍN�ɐr�ܘY���ƌ��j���A�ꑰ�Ƃ̕��ʂ��ւ���ꂽ
(�͂����������Ƃɂ͂Ȃ����㓙�̐l�Q�������������Ƃ���)
�Ȃ��Ȃ��g�p����
�E�i�\�Z�N(1563�N)����A�O�͈���Ꝅ�Ő��쒉�d�ɕ����E���ꂽ���߁A�l���̓���ɏZ��
�E�є��A�������^�ɎE���ꂽ�i�\���N(1565�N)�܂łɁA���ԏ�̔є��A���Ƃ��c�߂̕��̊Ԃɒ��j�����܂ꂽ���Ƃ��j���đ����g����
�E���ԏ闎���A�����M�N�Ɏd���邪�V���l�N(1576�N)�܂łɓ��y���E���ďo�z
�E�V���l�N(1576�N)�A���c�̊×��M�P�Ɏ��s���Ē������邪�A�×��̐Q���~���ē���A�Q
�E�V���\�N(1582�N)�̍����ł́A���̋w�ł��鐅�쒉�d�̒��j�̐��쏟���Ƌ���
�E�������ƍN�ɑa�܂�A�����������n�E�����
�E�������͍Ăяo�z�����N�ɓn��A�c����N(1604�N)�ɒ��N�g�߂Ƃ��ė������A�l���Ŏ����̑���g�����R���ƂȂ������g�������ď�
�Ƃ��낪�ƍN�ɐr�ܘY���ƌ��j���A�ꑰ�Ƃ̕��ʂ��ւ���ꂽ
(�͂����������Ƃɂ͂Ȃ����㓙�̐l�Q�������������Ƃ���)
�Ȃ��Ȃ��g�p����
732�l�Ԏ����l�N
2023/03/21(��) 12:21:09.53ID:skfkcONT 杊C�ɁA����Ƀc�b�R�~�ǂ��떞�ڂ̏G����������������������̂�
���۔N�Ԓ��A�F���̉ƘV�̉��n�Ȃɂ������]�˂ɏo�āA�V���������ߏ��āi������W�j�a�̂Ƃ���ցA�����ɐ\���グ�����V����ƑΖʂ�������B���n�A���Ă���n�h�̔��������o���āA�u�F������\���グ�܂���B���N�F���ɂĂ��̐l��������܂����́A���̂悤�Ȃ��̂��������Ă��ẮA����Ȃ��珫�R�Ƃ̂��p�Ƃ��Ȃ茓�˂ʂƑ����܂��āA�����ɂ��Ԃ��\�����Ǝ��Q�������܂����v�Ɛ\���グ���B
���ߏ��ēa�A�������܂��̔��������ēo�邵�Č��シ��ƁA�L���@�����l�J�����Ă����ɂȂ�ꂽ�B�Ȃ��ɂ͓��Ɖ@���L�b�Ƃ��킳�ꂽ�N�����������Ă��āA�G�����\�܍ɒB�����琭����ԏシ��|�������Ă������B����ɂ��Ă͉��̋����Ȃ��A�����A���̐l�͉��Ŏ������ꂽ�̂��A�q���͂���̂��ȂǏڂ��������Ă���悤�ɂƏ�ӂ���A���ߏ��ēa�A��ĉ��n�������Ĉύׂ�q�˂�ꂽ�B
���n�\���グ�Ă��킭�A�u���̐l���N�S�O�\���Ŏ�������A�S��\��̎��ɒj�q�����܂�A���̎q�͍��������Ă���܂��B�ȑO���j�q��l�o�����܂������A���łɖS���Ȃ��Ă���A�ق��ɏ��q�O�l����܂����A��������ƘV�ǂ��։��g�������܂����v
���̂��Ƃ��㕷�ɒB����ƁA���t�F����Q�̂��ɂ��̒j�q������Ə�ӂ������B���N�F���炪�������ĎQ����ƁA�������Ȃ����ڌ�����������A���̒j�q�ɒm�s�ܕS�Ή�������A�ԍ�R���̐_��ɋ������A���������Ƃ������O�������ꂽ�B�q���͍��������Ă��āA�����͂��Ȃ킿�؉��̈ӂł���Ƃ̂��Ƃ��B
���������Ō�������ƁA�R���̓��}�_�Ђ̐_�傪�������ŁA���\�\�N�ɖ����ɂ��_��E���p�����Ƃ����b���o�Ă���̂ŁA�������؉����v�������N����������b�ł����ˁB
���۔N�Ԓ��A�F���̉ƘV�̉��n�Ȃɂ������]�˂ɏo�āA�V���������ߏ��āi������W�j�a�̂Ƃ���ցA�����ɐ\���グ�����V����ƑΖʂ�������B���n�A���Ă���n�h�̔��������o���āA�u�F������\���グ�܂���B���N�F���ɂĂ��̐l��������܂����́A���̂悤�Ȃ��̂��������Ă��ẮA����Ȃ��珫�R�Ƃ̂��p�Ƃ��Ȃ茓�˂ʂƑ����܂��āA�����ɂ��Ԃ��\�����Ǝ��Q�������܂����v�Ɛ\���グ���B
���ߏ��ēa�A�������܂��̔��������ēo�邵�Č��シ��ƁA�L���@�����l�J�����Ă����ɂȂ�ꂽ�B�Ȃ��ɂ͓��Ɖ@���L�b�Ƃ��킳�ꂽ�N�����������Ă��āA�G�����\�܍ɒB�����琭����ԏシ��|�������Ă������B����ɂ��Ă͉��̋����Ȃ��A�����A���̐l�͉��Ŏ������ꂽ�̂��A�q���͂���̂��ȂǏڂ��������Ă���悤�ɂƏ�ӂ���A���ߏ��ēa�A��ĉ��n�������Ĉύׂ�q�˂�ꂽ�B
���n�\���グ�Ă��킭�A�u���̐l���N�S�O�\���Ŏ�������A�S��\��̎��ɒj�q�����܂�A���̎q�͍��������Ă���܂��B�ȑO���j�q��l�o�����܂������A���łɖS���Ȃ��Ă���A�ق��ɏ��q�O�l����܂����A��������ƘV�ǂ��։��g�������܂����v
���̂��Ƃ��㕷�ɒB����ƁA���t�F����Q�̂��ɂ��̒j�q������Ə�ӂ������B���N�F���炪�������ĎQ����ƁA�������Ȃ����ڌ�����������A���̒j�q�ɒm�s�ܕS�Ή�������A�ԍ�R���̐_��ɋ������A���������Ƃ������O�������ꂽ�B�q���͍��������Ă��āA�����͂��Ȃ킿�؉��̈ӂł���Ƃ̂��Ƃ��B
���������Ō�������ƁA�R���̓��}�_�Ђ̐_�傪�������ŁA���\�\�N�ɖ����ɂ��_��E���p�����Ƃ����b���o�Ă���̂ŁA�������؉����v�������N����������b�ł����ˁB
733�l�Ԏ����l�N
2023/03/21(��) 14:21:20.83ID:07kYylV9 ���g�����Ɋ�����牎���̒j�q�����܂ꂽ���ߓ��g�ۂƖ��t����
�Ƃ��u�G�{���}�L�v�Ƃ��ɏ�����Ă邩��
�R�������̐_�傪�������Ȃ玩�R�Ǝv��������
�Ƃ��u�G�{���}�L�v�Ƃ��ɏ�����Ă邩��
�R�������̐_�傪�������Ȃ玩�R�Ǝv��������
734�l�Ԏ����l�N
2023/03/21(��) 15:46:17.00ID:s91iSmcn �G�����������ǂ��b�Ƃ������A�S�����V���l�ɂȂ����G�g�̎q���ł���G���͓V���l����S���ɂȂ����A�Ƃ����V�����I�v��������ۂ��ĂȂc
735�l�Ԏ����l�N
2023/03/21(��) 15:55:29.97ID:ZbYnv9vr ������܂�Ȃ���̏��R�͏��ɖڊo�߂Ă���͕S�����ƃp�R�p�R����̂��D���ȕϑԂ������Ƃ���
736�l�Ԏ����l�N
2023/03/21(��) 22:17:10.16ID:x6CQOMpB �b�B�ɂ����āA���c�@���@��m���M�����́A�R�@��V�����Ȃ��ꂽ���ɂ��āA���̂悤�ȌÉ̂�������������ꂽ
�E���ȂĂ��@�������R�̂��Ђɂ��ւā@�ӂ��闷�l���͂�e�Ȃ��@�@�@�������q
�E�����邩��@�Ƃ݂̂����͂̂��������@���N�݂̂Ȃ͂킷��߁@�@�B����t
�w���̉̂͐́A�������q�ƒB����t���Ζʂ����܂̉̂ł���B�B����t�����{���ɓn���āA��a���̕Љ��R�ɁA
��H�̂悤�ɂ��ďZ�܂��Ă����B�Սς̘^�ɁA�Љ��R���V��ςƂ��邪�A���̒ʂ�ł������̂��낤�B
�}�l�͂�߂ɂ�����𑶂��Ȃ��������A�������q�A�B����t�͉�����O�������œ��m�̊�荇���ł���A
�݂��ɂ����m���Ă��邩�炱���A��̉̂̏�Ɂw�B���͓��y�ɋA��ƒ�߂Ă������A����͓��{�̕��S�@���A
���̍��͎��G�����ł͂Ȃ��Ƃ����̂ł������B�������B����T�T�x�Ɖ]�����Ƃ���B
���̉̂͐����̂��̂��B���̂��̂��{�������ƒ��������̂����A����ł͐l�͉�ł��Ȃ��Ƃ��āA������Ƌ���
�Z���̓��ɉr��ŁA�l����ł���悤�ɂ��ꂽ�̂��ƕ����Ă���B
���Ė��A���₵�����M���͕��ʁE�ˊo�̐^�����ȂāA�H�v�E�v�Ă��ē����̏����E�����w���Ƃ肵���A����
�݂��ď���\����ꂽ�V��q�˂Ă���ɏK���A�w����召��ɂ��āA���̑��l���A���A�O�̍\���A����
�����悤���d��A�����̎q������ł͂Ȃ��A�N�l�ł���Ƃ����ǂ��A�}�K�i���{�j�퍑�̒��ɂ����āA
�����̏O�𗦂��č�����s���ꍇ�́A�^�����߂��܂��点���߂́A�M���̌R�@�͎z���̔@���ł���B�x
�Ɛ��ꂽ�̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�M���̌R�@�͒N�ł����Ă�����̋^��ɓ�������悤�ɍ�����A�Ƃ������Ȃ̂ł��傤�ˁB
�E���ȂĂ��@�������R�̂��Ђɂ��ւā@�ӂ��闷�l���͂�e�Ȃ��@�@�@�������q
�E�����邩��@�Ƃ݂̂����͂̂��������@���N�݂̂Ȃ͂킷��߁@�@�B����t
�w���̉̂͐́A�������q�ƒB����t���Ζʂ����܂̉̂ł���B�B����t�����{���ɓn���āA��a���̕Љ��R�ɁA
��H�̂悤�ɂ��ďZ�܂��Ă����B�Սς̘^�ɁA�Љ��R���V��ςƂ��邪�A���̒ʂ�ł������̂��낤�B
�}�l�͂�߂ɂ�����𑶂��Ȃ��������A�������q�A�B����t�͉�����O�������œ��m�̊�荇���ł���A
�݂��ɂ����m���Ă��邩�炱���A��̉̂̏�Ɂw�B���͓��y�ɋA��ƒ�߂Ă������A����͓��{�̕��S�@���A
���̍��͎��G�����ł͂Ȃ��Ƃ����̂ł������B�������B����T�T�x�Ɖ]�����Ƃ���B
���̉̂͐����̂��̂��B���̂��̂��{�������ƒ��������̂����A����ł͐l�͉�ł��Ȃ��Ƃ��āA������Ƌ���
�Z���̓��ɉr��ŁA�l����ł���悤�ɂ��ꂽ�̂��ƕ����Ă���B
���Ė��A���₵�����M���͕��ʁE�ˊo�̐^�����ȂāA�H�v�E�v�Ă��ē����̏����E�����w���Ƃ肵���A����
�݂��ď���\����ꂽ�V��q�˂Ă���ɏK���A�w����召��ɂ��āA���̑��l���A���A�O�̍\���A����
�����悤���d��A�����̎q������ł͂Ȃ��A�N�l�ł���Ƃ����ǂ��A�}�K�i���{�j�퍑�̒��ɂ����āA
�����̏O�𗦂��č�����s���ꍇ�́A�^�����߂��܂��点���߂́A�M���̌R�@�͎z���̔@���ł���B�x
�Ɛ��ꂽ�̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�M���̌R�@�͒N�ł����Ă�����̋^��ɓ�������悤�ɍ�����A�Ƃ������Ȃ̂ł��傤�ˁB
737�l�Ԏ����l�N
2023/03/25(�y) 22:46:11.27ID:hu1HyIr1 �u�����ƊՒk�v����u�M���Ό��M�`�V���v
���M�ƐM���̎捇�̎����A���M�R�������z���Ă����B
���̂Ƃ��M���͈�̎�Ɏᕐ�҂��A��̎�ɘV���̕��҂����āA���O�ɂ��ĕz�w�����B
������������M�͍���ɂ����낤�Ƃ͂��Ȃ������B
���̗��R�����A��̎�̎ᕐ�҂́u�V�l�̑O�œ������ł����悤���v�Ƃ��悢���ނ��낤��
��̎�̘V���̕��҂́u�ᕐ�҂��������撣���Ă���̂ɗ���Ă����悤���v�Ɛi�ނ��߁A�����ƂȂ邩�炾�Ƃ���
���M�ƐM���̎捇�̎����A���M�R�������z���Ă����B
���̂Ƃ��M���͈�̎�Ɏᕐ�҂��A��̎�ɘV���̕��҂����āA���O�ɂ��ĕz�w�����B
������������M�͍���ɂ����낤�Ƃ͂��Ȃ������B
���̗��R�����A��̎�̎ᕐ�҂́u�V�l�̑O�œ������ł����悤���v�Ƃ��悢���ނ��낤��
��̎�̘V���̕��҂́u�ᕐ�҂��������撣���Ă���̂ɗ���Ă����悤���v�Ɛi�ނ��߁A�����ƂȂ邩�炾�Ƃ���
738�l�Ԏ����l�N
2023/03/25(�y) 23:06:10.78ID:hu1HyIr1 (����)
�܂��A�M�����k���Ǝ捇�̎��A�k���헤��̉������̎w�����E���Ă����B
(�n������������k���j�����낤)
�k���̗E�҂ŗL���ȏ헤��䂪�R�̐���������Ďw�����̂Ăē������A�ƎR�����i���͂��ߊF����������B
�M���́u�����炭�����ւ��̎w�������l�����Ƃ����̂��낤�B
�헤��͉B��Ȃ��|��ł���B����ɂ��₩���ė_�����v
�Ƃ��̂������̂�^�c�B��(�^�c�M���H)�Ɏ������B
�^�c�B��͑��Γ�\�O�ł������B
���̐^�ӂ́A�G�ɓ{����܂܂��Ă͖����ȓ����������Ă��܂�����ł���B
�헤����O��̑叫�ł���̂ŁA���K���Ő키�悤�Ȃ��G�ƂȂ邩�炾�B
�k���Ƃł��w���𗎂Ƃ������Ƃŏ헤��}���Ă��邱�Ƃ��낤�Ɨ��_���Ă����Ƃ���ɁA�M���̔�]�����̂łق��Ƃ����B
�헤������������сA��낱��ŗ܂𗬂����Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-497.html
���c�M���ƁA�k���j���̒n�������̊��E�����b
��̕��͈ꉞ�o�Ă������ǁA�^�c���K�ɗ^����ꂽ���ƂɂȂ��Ă���
�܂��A�M�����k���Ǝ捇�̎��A�k���헤��̉������̎w�����E���Ă����B
(�n������������k���j�����낤)
�k���̗E�҂ŗL���ȏ헤��䂪�R�̐���������Ďw�����̂Ăē������A�ƎR�����i���͂��ߊF����������B
�M���́u�����炭�����ւ��̎w�������l�����Ƃ����̂��낤�B
�헤��͉B��Ȃ��|��ł���B����ɂ��₩���ė_�����v
�Ƃ��̂������̂�^�c�B��(�^�c�M���H)�Ɏ������B
�^�c�B��͑��Γ�\�O�ł������B
���̐^�ӂ́A�G�ɓ{����܂܂��Ă͖����ȓ����������Ă��܂�����ł���B
�헤����O��̑叫�ł���̂ŁA���K���Ő키�悤�Ȃ��G�ƂȂ邩�炾�B
�k���Ƃł��w���𗎂Ƃ������Ƃŏ헤��}���Ă��邱�Ƃ��낤�Ɨ��_���Ă����Ƃ���ɁA�M���̔�]�����̂łق��Ƃ����B
�헤������������сA��낱��ŗ܂𗬂����Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-497.html
���c�M���ƁA�k���j���̒n�������̊��E�����b
��̕��͈ꉞ�o�Ă������ǁA�^�c���K�ɗ^����ꂽ���ƂɂȂ��Ă���
739�l�Ԏ����l�N
2023/03/26(��) 03:14:21.88ID:6QIuKyed �e�����ĉ��ď��낤��
�s�C������
�s�C������
740�l�Ԏ����l�N
2023/03/26(��) 10:53:20.18ID:AqAmt3K9 �܂��^�c�قɊ�������悤��
741�l�Ԏ����l�N
2023/03/27(��) 16:05:02.71ID:hF7jsEmB �w�����ł�
�u�����ƊՒk�v����u���������v�w�������Ď�Ǝ�ւ鎖�v
���|���Ɩk�����N�̉���������̂Ƃ����������v�͒����̎w�������āA���őg���������Ď��������B
�������C�Â��Ă݂�Ɣw���̎w�����Ȃ��A
�u����͑g�����̍Œ��Ɏw�����������̂�G���E���Ă������̂��낤�v�Ɖ����͖��O�Ɏv�����B
�����Ŏ��������Ԃ牺���A�ދp����G�̐��ʂɉ����
�u����͖k���Ɛl�����̉��������v�Ɛ\�����̂Ȃ�B
�������܂̐�őg���������A�w������藎�Ƃ��Ă��܂����B
�����炭�ǂȂ����E���Ȃ������l�����邾�낤�B
�w���͒����ł���B���̎�͂��܂�����������Ă��Ȃ��̂ŁA����Ǝ��ւ��Ă���v�Ɛ����Ɍ������B
�G���傢�Ɋ��S���Ă���ƁA���҈�R���o�Ă���
�u�ꏟ�Ȍ䏊�]�ł���B�����̎w���͊֔��B�ł����炵�̂ŏE���������B
�����ɂ��Ԃ����悤�v�ƕԂ����B
�����͂�낱�ю��n���u��F�u���ӂ������v�Ɣw���������Ďw�����������A��炵�ė����A�����B
�u�����ς�卄�̕��m���ȁv�ƓG�����Ƃ��Ɋ��Q�����Ƃ������Ƃ��B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-785.html
�k���ƁA���������v�̎w���E����
�����炾�Ɖ���ł̑����ɂȂ��Ă��邽�߂�(���K����H)�k�������J�e�S��������
�u�����ƊՒk�v����u���������v�w�������Ď�Ǝ�ւ鎖�v
���|���Ɩk�����N�̉���������̂Ƃ����������v�͒����̎w�������āA���őg���������Ď��������B
�������C�Â��Ă݂�Ɣw���̎w�����Ȃ��A
�u����͑g�����̍Œ��Ɏw�����������̂�G���E���Ă������̂��낤�v�Ɖ����͖��O�Ɏv�����B
�����Ŏ��������Ԃ牺���A�ދp����G�̐��ʂɉ����
�u����͖k���Ɛl�����̉��������v�Ɛ\�����̂Ȃ�B
�������܂̐�őg���������A�w������藎�Ƃ��Ă��܂����B
�����炭�ǂȂ����E���Ȃ������l�����邾�낤�B
�w���͒����ł���B���̎�͂��܂�����������Ă��Ȃ��̂ŁA����Ǝ��ւ��Ă���v�Ɛ����Ɍ������B
�G���傢�Ɋ��S���Ă���ƁA���҈�R���o�Ă���
�u�ꏟ�Ȍ䏊�]�ł���B�����̎w���͊֔��B�ł����炵�̂ŏE���������B
�����ɂ��Ԃ����悤�v�ƕԂ����B
�����͂�낱�ю��n���u��F�u���ӂ������v�Ɣw���������Ďw�����������A��炵�ė����A�����B
�u�����ς�卄�̕��m���ȁv�ƓG�����Ƃ��Ɋ��Q�����Ƃ������Ƃ��B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-785.html
�k���ƁA���������v�̎w���E����
�����炾�Ɖ���ł̑����ɂȂ��Ă��邽�߂�(���K����H)�k�������J�e�S��������
742�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 18:06:48.91ID:n94hwOxL https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/130sekigahara.html
�đ�s�㐙�����ف@�v��l�Z�Z�N�L�O���ʓW�u�㐙�i���Ɗփ�������v
��@���F�O�� �S��22���i�y�j~�T��21���i���j
�@�@�@�@��� �T��27���i�y�j~�U��25���i���j
��Ԃ̍���u�㐙�{�������O�}�����v���{�W���ȊO�ɂ��A�e������݂��o�������W���i���ڔ������Ȃ̂ł��Ђ����K���������B
�ւ����֘A�̕����̖v��400���N���A���낻��ł��~�߂ł����ˁB���̐w�֘A���Ɖ��N��܂łł���̂��B
�W���i�̂������|�`��̍b�h�́A�H�c�s���|�j���ق����z�H���ł��x�݂�������Ă̂������ł��傤�B
���̑��̑ݏo�悪�H�������Ă킯�ł͂���܂��B
�đ�s�㐙�����ف@�v��l�Z�Z�N�L�O���ʓW�u�㐙�i���Ɗփ�������v
��@���F�O�� �S��22���i�y�j~�T��21���i���j
�@�@�@�@��� �T��27���i�y�j~�U��25���i���j
��Ԃ̍���u�㐙�{�������O�}�����v���{�W���ȊO�ɂ��A�e������݂��o�������W���i���ڔ������Ȃ̂ł��Ђ����K���������B
�ւ����֘A�̕����̖v��400���N���A���낻��ł��~�߂ł����ˁB���̐w�֘A���Ɖ��N��܂łł���̂��B
�W���i�̂������|�`��̍b�h�́A�H�c�s���|�j���ق����z�H���ł��x�݂�������Ă̂������ł��傤�B
���̑��̑ݏo�悪�H�������Ă킯�ł͂���܂��B
743�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 18:40:36.33ID:QINr/QdV �X���`�̃o�J���ĉ��ł���Ȃɓ��������낤��
744�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 18:59:41.95ID:0AUyz2EU �b�B���c�̕���O�A笕��́i���h�ȁj���ł��鍡����ՂƂ����l�����݂������A�ނ͎Ⴂ�����
���߂����i�����a��j��\���a��l�ŁA���������ł������B�������a���Ă���������u�ԁA
�e�������Ȃď������т��āA���ɗ��Ƃ��ʂ悤�����̓r���ŏ�ɏグ��قǂ̎���ł������B
�ނ͂��߂����̏��ł������̂ŕ��c�Ƃ̎��O�͑�g�E���g���ɂ������Ղɗ��B
���̂悤�ł������̂ŁA�N��l�\�Z�A���̍��܂łɂ́A��l�ɋy�Ԃقǎa�����ƕ]���ꂽ�B
���������ۂɂ͕S�l�����S�l�قǂł��������낤�B
���̐l�͂ǂ������킯���A���g�̔\���q�������l���a�������B������������Ղ͑T�̎Q�w�Ȃǂ���
�S���o�����l�ł������̂ŁA����Ȕᔻ�ɂ͎�荇�킸�A�q�������ʂ̂����F���ʂɉ߂��Ȃ��Ƃ��āA
����������荇��Ȃ������B
���鎞�A�M�B�⑺�c�̖@���a�����b�B�Ɍ�����������A������Ղ͂��̘a���Ɍ���i�����j�ɎQ�����B
���̐܁A�@���a���͍��������ւ̋����Ƃ��Č�����
�u���̕��͗ǂ���ł���̂ɁA���߂����̂ō߂����ܑ͖̂̂Ȃ��B�v
����������
�u�����a��̂͂ǂ����̎��l�ł���A���̉Ȃ��a��Q�炷�̂ł��B�v�ƌ���ꂽ�B
�m���i�a���j�́u����͐悸�ނ��ł���B�v�Ƃ��炭�Ԃ�u���A�@���a���͋��ɐ�����
�u���������A���̂����֒Y�����Ă���Ȃ����낤���B�v
�u�܂��Č�v�ƒY�������ĘF�ӂ֊�������A�a���͐��ꂽ
�u�傫�ȒY���Δ��ɂĂ͂������ł��낤���B��߂āA���������c�̖������X�̍��������ł���A
�w���ȂĒY�����Ă���Ȃ����낤���B�v
������Ղ͂܂��A���̋��̂���l���ŏ��|�ɒB���A���ɔ\�Ȃǂ��鎞���A�Õۏ����v�Ȃǂ̔\�y�̎҂�
��������Ă��Ă��A���卡���̕����D��Ă���قǂł������B�����������l�ł������̂ŁA���̎���
�Y�������ɂ��ʔ��������ꂽ�B
���āA�����ނ����A��Ղ͎��@�����B���̂Ƃ��a���͐������u���������͂ǂ����Ď��@���̂��B�v
�u���������Y�̂��߂ɉ��ꂽ�̂ł��B�v
�u���̒Y���Ă����Y�Ă̎���A��߂ĉ���Ă����̂ł��낤�ȁB�v
���������͐\�����u�Y�Ă͂�������ďo���̂ł����瓖�R�ł����A���͂��̒Y����������̎肪
���ꂽ�̂ł��B�v
�u���Ă����A�捏���̕������߂����ɂ��āA����ɉȂ�����ƌ��������A��������߂���a�鍡����Ղɂ��A
�i�Y��������肪���ꂽ�悤�Ɂj���̍߂��܂Ƃ����̂��B�v
���̂悤�Ȗ@���a���̂����߂ɂāA���������͂��̌�A���߂������a��Ȃ��Ȃ����Ƃ����B
�w�b�z�R�Ӂx
���߂����i�����a��j��\���a��l�ŁA���������ł������B�������a���Ă���������u�ԁA
�e�������Ȃď������т��āA���ɗ��Ƃ��ʂ悤�����̓r���ŏ�ɏグ��قǂ̎���ł������B
�ނ͂��߂����̏��ł������̂ŕ��c�Ƃ̎��O�͑�g�E���g���ɂ������Ղɗ��B
���̂悤�ł������̂ŁA�N��l�\�Z�A���̍��܂łɂ́A��l�ɋy�Ԃقǎa�����ƕ]���ꂽ�B
���������ۂɂ͕S�l�����S�l�قǂł��������낤�B
���̐l�͂ǂ������킯���A���g�̔\���q�������l���a�������B������������Ղ͑T�̎Q�w�Ȃǂ���
�S���o�����l�ł������̂ŁA����Ȕᔻ�ɂ͎�荇�킸�A�q�������ʂ̂����F���ʂɉ߂��Ȃ��Ƃ��āA
����������荇��Ȃ������B
���鎞�A�M�B�⑺�c�̖@���a�����b�B�Ɍ�����������A������Ղ͂��̘a���Ɍ���i�����j�ɎQ�����B
���̐܁A�@���a���͍��������ւ̋����Ƃ��Č�����
�u���̕��͗ǂ���ł���̂ɁA���߂����̂ō߂����ܑ͖̂̂Ȃ��B�v
����������
�u�����a��̂͂ǂ����̎��l�ł���A���̉Ȃ��a��Q�炷�̂ł��B�v�ƌ���ꂽ�B
�m���i�a���j�́u����͐悸�ނ��ł���B�v�Ƃ��炭�Ԃ�u���A�@���a���͋��ɐ�����
�u���������A���̂����֒Y�����Ă���Ȃ����낤���B�v
�u�܂��Č�v�ƒY�������ĘF�ӂ֊�������A�a���͐��ꂽ
�u�傫�ȒY���Δ��ɂĂ͂������ł��낤���B��߂āA���������c�̖������X�̍��������ł���A
�w���ȂĒY�����Ă���Ȃ����낤���B�v
������Ղ͂܂��A���̋��̂���l���ŏ��|�ɒB���A���ɔ\�Ȃǂ��鎞���A�Õۏ����v�Ȃǂ̔\�y�̎҂�
��������Ă��Ă��A���卡���̕����D��Ă���قǂł������B�����������l�ł������̂ŁA���̎���
�Y�������ɂ��ʔ��������ꂽ�B
���āA�����ނ����A��Ղ͎��@�����B���̂Ƃ��a���͐������u���������͂ǂ����Ď��@���̂��B�v
�u���������Y�̂��߂ɉ��ꂽ�̂ł��B�v
�u���̒Y���Ă����Y�Ă̎���A��߂ĉ���Ă����̂ł��낤�ȁB�v
���������͐\�����u�Y�Ă͂�������ďo���̂ł����瓖�R�ł����A���͂��̒Y����������̎肪
���ꂽ�̂ł��B�v
�u���Ă����A�捏���̕������߂����ɂ��āA����ɉȂ�����ƌ��������A��������߂���a�鍡����Ղɂ��A
�i�Y��������肪���ꂽ�悤�Ɂj���̍߂��܂Ƃ����̂��B�v
���̂悤�Ȗ@���a���̂����߂ɂāA���������͂��̌�A���߂������a��Ȃ��Ȃ����Ƃ����B
�w�b�z�R�Ӂx
745�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 19:02:03.64ID:atCz6vka ���|�`�邪1633�N�v�A�ɒB���@��1636�N�v�A���Ə\���N��400���N�L�O�s��������ł��傤��
746�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 19:12:08.10ID:s91GNlX4 �u�b�z�R�Ӂv�Ƃ������쎁�^���u�n��(��)�Ȃ�叫�v�Ə����Ă邯��
��̓h���}�̑���a�͂ނ��둫����������������
(�k���œ��������Ƃɑ��ĕ��̖k�����N���{�����l�^���g�����߁H)
�Ȃ��Ă�����n�̉ŁA�Ċ����ł͂Ȃ���
��̓h���}�̑���a�͂ނ��둫����������������
(�k���œ��������Ƃɑ��ĕ��̖k�����N���{�����l�^���g�����߁H)
�Ȃ��Ă�����n�̉ŁA�Ċ����ł͂Ȃ���
747�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 21:38:49.90ID:gONLVMMO >>746
�n�ɉł��Ə����킯������n���݂̋����̏����ƍ���Ƃ�����������������Ȃ����H
�n�ɉł��Ə����킯������n���݂̋����̏����ƍ���Ƃ�����������������Ȃ����H
748�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 21:48:12.55ID:ttbfDJcS �u�����ƊՒk�v���琳�d���r
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7323.html
�̌��ɂȂ����L��
�|���U�߂̎��A�M������ƒ��̓��������(������O�A)�̉��ł���������g�����鎞�ɏ钆�ɂ����B
����R���钆�ɍU�ߓ������Ƃ���A��̊ۂƖ{�ۂ̊Ԃő��Y��(���쐳�d)����g�ɂł������B
��g�������ɂ́u���̕��͉ƍN�ƒ��̂Ȃ�Ɛ\���҂��B
���ꂪ���͓���������̉��A�������g�Ɛ\�����̂��B
���ꂪ���̂��Ƃ͂��̕��̎�N�̉ƍN���悭�����m�Ȃ̂ŁA�킪����Ȃ�ΉƍN�Ɍ��Q������B�v
�Ɩ����A��߂��Ȃ����Y��Ƒg��ŁA������ꂽ�B
���Y�삪��g�̎������ė����オ�����Ƃ�����A�G��l�����āA��Ԕ��قǂ̂Ƃ��납�瑾�Y��̍��̂��т���˒ʂ����B
�d���ŋꂵ��ł������߁A�ێR���тƂ����O�Ȃ��䏊�l�͌�O�ɏ�����
�u���쑾�Y��̏��̋�͂ǂ����v�Ƃ��q�˂ɂȂ�ꂽ�B
���т��\���ɂ́u�}���ɏ����͂���܂����̂ł��̂����y�ɂȂ�ł��傤�v�Ɛ\�����B
��䏊�l�́u�ȂɂƂ��A�ȂɂƂ����Y��̖����~���Ă���v�Əd�ˏd�ː��тɗ��܂ꂽ�B
���������ɂ����ӂ̂Ƃ��芮�������A�ƕ�������B
(����͐��쑾�Y��̑��q�������u�������̂��ʂ����b)
������O�A�����Ɠ��l�A��������������A���쑾�Y��̑��q�͓������D�c�M���̉Ɛb�ƔF���������̂��낤��
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7323.html
�̌��ɂȂ����L��
�|���U�߂̎��A�M������ƒ��̓��������(������O�A)�̉��ł���������g�����鎞�ɏ钆�ɂ����B
����R���钆�ɍU�ߓ������Ƃ���A��̊ۂƖ{�ۂ̊Ԃő��Y��(���쐳�d)����g�ɂł������B
��g�������ɂ́u���̕��͉ƍN�ƒ��̂Ȃ�Ɛ\���҂��B
���ꂪ���͓���������̉��A�������g�Ɛ\�����̂��B
���ꂪ���̂��Ƃ͂��̕��̎�N�̉ƍN���悭�����m�Ȃ̂ŁA�킪����Ȃ�ΉƍN�Ɍ��Q������B�v
�Ɩ����A��߂��Ȃ����Y��Ƒg��ŁA������ꂽ�B
���Y�삪��g�̎������ė����オ�����Ƃ�����A�G��l�����āA��Ԕ��قǂ̂Ƃ��납�瑾�Y��̍��̂��т���˒ʂ����B
�d���ŋꂵ��ł������߁A�ێR���тƂ����O�Ȃ��䏊�l�͌�O�ɏ�����
�u���쑾�Y��̏��̋�͂ǂ����v�Ƃ��q�˂ɂȂ�ꂽ�B
���т��\���ɂ́u�}���ɏ����͂���܂����̂ł��̂����y�ɂȂ�ł��傤�v�Ɛ\�����B
��䏊�l�́u�ȂɂƂ��A�ȂɂƂ����Y��̖����~���Ă���v�Əd�ˏd�ː��тɗ��܂ꂽ�B
���������ɂ����ӂ̂Ƃ��芮�������A�ƕ�������B
(����͐��쑾�Y��̑��q�������u�������̂��ʂ����b)
������O�A�����Ɠ��l�A��������������A���쑾�Y��̑��q�͓������D�c�M���̉Ɛb�ƔF���������̂��낤��
749�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 22:09:38.84ID:Em404pRp750�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 22:12:47.14ID:Em404pRp ���̎���2�l�Ƃ�������ł����I���Ē��߂���Ȃ��ƃo�J�ɂ͗����ł��Ȃ��炵��
751�l�Ԏ����l�N
2023/03/29(��) 22:56:38.93ID:G39ficZt �����͐M���̎���̓V���\��N�̊I�]��̍���܂ł̋L��������
���쑾�Y�삪�����Ԃ̐킢�̎��ɏ\�Z�Ƃ��Ă��邽��
���̑��q���������N���l����ƁA�M�����ゾ���Ԍo���Ă���Ǝv���܂��B
���쑾�Y�삪�����Ԃ̐킢�̎��ɏ\�Z�Ƃ��Ă��邽��
���̑��q���������N���l����ƁA�M�����ゾ���Ԍo���Ă���Ǝv���܂��B
752�l�Ԏ����l�N
2023/03/30(��) 09:12:20.35ID:PCZy94dg �`���m�� �������C�s�A�̓�ɒ���
���ь����@��
https://www.chukobi.co.jp/products/detail.php?product_id=884
����͓��{���́u�m���v�Ȃ̂��H
���ꌧ�b��s�̐_�Ђɓ`����U�̒����A�������C�s�A�B���p�j�E�����w�E�����j�̌����҂����p�I�Ȏ��_����A
���m�Ɛ��m������������q�C����ɒa��������ނȂ��`���i�̎����ɔ���B
�܂Ƃ߂�2019�N�x�̂����炪���ЂɂȂ����悤�ł��B�Ҏ҂͎��ۂɒ������ꂽ���ł��̂ŁA�ڍׂȌo�܂��킩�肻���ł��ˁB
�y�j���[�X�z�u�G�g����q�́v�`���̏\���^�m���A�S�O�O�N�O�ɍ�������������
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-12141.html
���ь����@��
https://www.chukobi.co.jp/products/detail.php?product_id=884
����͓��{���́u�m���v�Ȃ̂��H
���ꌧ�b��s�̐_�Ђɓ`����U�̒����A�������C�s�A�B���p�j�E�����w�E�����j�̌����҂����p�I�Ȏ��_����A
���m�Ɛ��m������������q�C����ɒa��������ނȂ��`���i�̎����ɔ���B
�܂Ƃ߂�2019�N�x�̂����炪���ЂɂȂ����悤�ł��B�Ҏ҂͎��ۂɒ������ꂽ���ł��̂ŁA�ڍׂȌo�܂��킩�肻���ł��ˁB
�y�j���[�X�z�u�G�g����q�́v�`���̏\���^�m���A�S�O�O�N�O�ɍ�������������
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-12141.html
753�l�Ԏ����l�N
2023/03/30(��) 09:38:21.24ID:wJymD5x+ �挎�o�����j�������C�u�����[��
�k��M�F�u�V���l�����̕����헪�@�Ȋw�̊�ł݂铍�R�����v
�̃e�[�}�����R�����E���i�����̋Z�p�ɂ����鐢�E(�����A����A�W�A�A���m)�̎�����Z�p�̉��p����������d�Ȃ邩
���C�s�A�̘b�͂Ȃ���������
�k��M�F�u�V���l�����̕����헪�@�Ȋw�̊�ł݂铍�R�����v
�̃e�[�}�����R�����E���i�����̋Z�p�ɂ����鐢�E(�����A����A�W�A�A���m)�̎�����Z�p�̉��p����������d�Ȃ邩
���C�s�A�̘b�͂Ȃ���������
754�l�Ԏ����l�N
2023/03/30(��) 11:50:57.41ID:/0xlCPcr �ǂ��������b�ȂX���`����
�X�����ĂĂ����ł���Ă��
�X�����ĂĂ����ł���Ă��
755�l�Ԏ����l�N
2023/03/31(��) 09:26:50.50ID:uCy/L7mH ��k������̋ъ������݂��Ă����Ƃ́A�������w�肪40�N�O�Ƃ������ƂȂ̂ɂ����ς�m��Ȃ�����
�Ƃ������퍑����ɘQ���k�����͒f�₵�����̂Ƃ���E�E
��������2023�N3��29��
�k���Ƃ̕�4�i�@�����Ɋ^������E���_����
https://toonippo.ismcdn.jp/mwimgs/c/f/300m/img_cfea9b6a8b247878ffc8787dabb250b91012254.jpg
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1526629
�Q���k�����̎q���ɓ�����X�������o�g�̖k�����_����i59�j�������s����28���A���������K��A
�k���Ƃ����������700�N�O�̋ъ��i���j��A�Ìy�ŌÂ̖��ԋL�^�Ƃ����i�\���L�̌����Ȃ�4�i�Ɋ����B
�������1984�N�ɒ���1���̕������w������B���͋��y�����قȂǂŕۊǁA�W��������j�B
�Ƃ������퍑����ɘQ���k�����͒f�₵�����̂Ƃ���E�E
��������2023�N3��29��
�k���Ƃ̕�4�i�@�����Ɋ^������E���_����
https://toonippo.ismcdn.jp/mwimgs/c/f/300m/img_cfea9b6a8b247878ffc8787dabb250b91012254.jpg
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1526629
�Q���k�����̎q���ɓ�����X�������o�g�̖k�����_����i59�j�������s����28���A���������K��A
�k���Ƃ����������700�N�O�̋ъ��i���j��A�Ìy�ŌÂ̖��ԋL�^�Ƃ����i�\���L�̌����Ȃ�4�i�Ɋ����B
�������1984�N�ɒ���1���̕������w������B���͋��y�����قȂǂŕۊǁA�W��������j�B
756�l�Ԏ����l�N
2023/03/31(��) 12:15:12.41ID:Et8oKEjV >>755
����
����
757�l�Ԏ����l�N
2023/03/31(��) 13:50:23.23ID:iY1J9mvs �X���Ⴂ�ɂ��Ă����˂͌����߂�
758�l�Ԏ����l�N
2023/03/31(��) 19:21:04.67ID:5g8rZmk3 �Q���k���ɂ��Ẳߋ��̈�b�ɂ����邯�lj��H�ɎU��U��ɂȂ��Ăǂ̉Ƃ��ېV�}���Ă�
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7349.html
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7349.html
759�l�Ԏ����l�N
2023/03/31(��) 20:49:26.67ID:eLwg5cPw https://www.hb.pei.jp/shiro/mutsu/takii-date/photo_002b.jpg
������̐X�������̉���ɂ��ƁA>>758�̈�b�̎q����>>755�̕��炵���ł��ˁB
�����A����ƕ�����Đ����ݏZ���Ă��Ƃ��炷��ƁA���ɂ��ꑰ�͐�c��X�ِ̊Ղ��痣��Ă���̂��ȁH
������̐X�������̉���ɂ��ƁA>>758�̈�b�̎q����>>755�̕��炵���ł��ˁB
�����A����ƕ�����Đ����ݏZ���Ă��Ƃ��炷��ƁA���ɂ��ꑰ�͐�c��X�ِ̊Ղ��痣��Ă���̂��ȁH
760�l�Ԏ����l�N
2023/03/31(��) 21:15:56.89ID:qqupdpl3 �u�i�\���L�v��ǂނ�
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7067.html
�Ìy�M���ƓV���l�Z��
�̘b�������āA�Ă�����Ìy�M���̈��t�Ԃ肪�㐢�ɐ���ꂽ�̂��Ǝv������ו��������ŋ������B
���ƌ��a���N(�c����\�N)�̋L����
��◎�鎞�̏G������r��(�����̋�H)�Ƃ���
�u�A�����^�T�E�L�g�L�c���T�g���T�J�i�l�i�T�P�n���j�A���V�z�g
(���ꂽ���@�J�����A���@�F�����ȁ@�l�̏�́@���ɂ��肵�قǁH)�v���ڂ��Ă���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7067.html
�Ìy�M���ƓV���l�Z��
�̘b�������āA�Ă�����Ìy�M���̈��t�Ԃ肪�㐢�ɐ���ꂽ�̂��Ǝv������ו��������ŋ������B
���ƌ��a���N(�c����\�N)�̋L����
��◎�鎞�̏G������r��(�����̋�H)�Ƃ���
�u�A�����^�T�E�L�g�L�c���T�g���T�J�i�l�i�T�P�n���j�A���V�z�g
(���ꂽ���@�J�����A���@�F�����ȁ@�l�̏�́@���ɂ��肵�قǁH)�v���ڂ��Ă���
761�l�Ԏ����l�N
2023/03/31(��) 22:21:57.29ID:eLwg5cPw �Ƃ肠�����u�i�\���L�v�Ƃ͂����������̂炵���B
?�݂��̂��o�� ���W�w�i�\���L�x���a31�N�� ?
�@�w�i�\���L�x�͘Q�����k�����̌���A�R�莁(�Q�������ɎR��Ɛ���ς��Ă��܂������A�����\�ܔN�ɖk���ɕ������Ă��܂�)�̉ƋL�ł��邱�̓��L�́A
�u�R��L�v�����͒P�Ɂu�L�^�v�ȂǂƁ@�肳��ē�S�N�ɂ킽���X�����`�����Ă��܂������A�����������Ȃ�A���\�O(1763)�N�ɁA�R�藧�p�ɂ����
�����E�Ҏ[�ꏑ�Ƃ������̂ł��B������Ă�����e�́A�����A�V��A�V�ϒn�ف@���琭���܂ŁA�����ʂɘj���Ă��܂��B
?�݂��̂��o�� ���W�w�i�\���L�x���a31�N�� ?
�@�w�i�\���L�x�͘Q�����k�����̌���A�R�莁(�Q�������ɎR��Ɛ���ς��Ă��܂������A�����\�ܔN�ɖk���ɕ������Ă��܂�)�̉ƋL�ł��邱�̓��L�́A
�u�R��L�v�����͒P�Ɂu�L�^�v�ȂǂƁ@�肳��ē�S�N�ɂ킽���X�����`�����Ă��܂������A�����������Ȃ�A���\�O(1763)�N�ɁA�R�藧�p�ɂ����
�����E�Ҏ[�ꏑ�Ƃ������̂ł��B������Ă�����e�́A�����A�V��A�V�ϒn�ف@���琭���܂ŁA�����ʂɘj���Ă��܂��B
762�l�Ԏ����l�N
2023/04/01(�y) 12:47:18.86ID:UeNMkdTv ���O���c���ʼn��w�̔_�����l���������牴��ؑ��ɓ��ꂪ�����
�c�O�������Ȑe�K�`�����s����w
�c�O�������Ȑe�K�`�����s����w
763�l�Ԏ����l�N
2023/04/02(��) 16:24:46.07ID:0/464KFC �G�����̂��Ƃɂ��āB
�悸�A�_���鑤�̐l�͏�ɐQ����ς��A����p�S���A���̏�H�����s�����ɁA��ɓG���҂��Ă���ƕ����A
�e����ʂ��ĉI��ȂǁA�ǂ̂悤�Ɏd��Ƃ��������悤�ɂ���̂����ʖނ��ƌ�����B
���̎����A���ē��Ȑl�X����ڋ��ł���ƌ����Ă��A�S�����͂Ȃ��i���V�ē��Ȃ�l�X�䋻�Ƃ������s��j�B
�M���Ƃ̍�@�͂��̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B
���ɑ_���l�́A���̐g��������������Ƃւ̈ӎ�ł���Ȃ�A�钋���ɑ_���ē����ʂ������Ƃ������A
���̕���Ƃ��ē��A�e���A�����͖��A�㓁�܂ł͖��Ȃ��B
���Ė��A�e�Z��A�t���A�����A�]�Z��܂ł̓G�����ł���Ȃ�A�|�A�S�C�ł����Ă������ʂ��������Ƃ�
�蕿�Ƃ������ׂ��ł���B
�����̈ӎ�œ��ꍇ�ł��A�G�����ł����Ă��A���̓G�̉ƂɔE�э���œ����ʂ����̂́A�ЂƂ����ǂ�
�S�y���Ɛ\�����̂ł���B
���̉Ƃ͂ǂ��ł���A�M���Ƃ̍�@�͎z���̔@���ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�悸�A�_���鑤�̐l�͏�ɐQ����ς��A����p�S���A���̏�H�����s�����ɁA��ɓG���҂��Ă���ƕ����A
�e����ʂ��ĉI��ȂǁA�ǂ̂悤�Ɏd��Ƃ��������悤�ɂ���̂����ʖނ��ƌ�����B
���̎����A���ē��Ȑl�X����ڋ��ł���ƌ����Ă��A�S�����͂Ȃ��i���V�ē��Ȃ�l�X�䋻�Ƃ������s��j�B
�M���Ƃ̍�@�͂��̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B
���ɑ_���l�́A���̐g��������������Ƃւ̈ӎ�ł���Ȃ�A�钋���ɑ_���ē����ʂ������Ƃ������A
���̕���Ƃ��ē��A�e���A�����͖��A�㓁�܂ł͖��Ȃ��B
���Ė��A�e�Z��A�t���A�����A�]�Z��܂ł̓G�����ł���Ȃ�A�|�A�S�C�ł����Ă������ʂ��������Ƃ�
�蕿�Ƃ������ׂ��ł���B
�����̈ӎ�œ��ꍇ�ł��A�G�����ł����Ă��A���̓G�̉ƂɔE�э���œ����ʂ����̂́A�ЂƂ����ǂ�
�S�y���Ɛ\�����̂ł���B
���̉Ƃ͂ǂ��ł���A�M���Ƃ̍�@�͎z���̔@���ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
764�l�Ԏ����l�N
2023/04/02(��) 19:29:49.48ID:mxpp21ER �����̑�͂̏��R�`���̈ߑ��A���ꂠ�̐F�̈߂��ċ�����Ă������H
765�l�Ԏ����l�N
2023/04/02(��) 20:52:25.50ID:IvYZ1SFj �t�@���^�W�[�ɐH�����A�z���ނ�܂���w
766�l�Ԏ����l�N
2023/04/04(��) 09:10:38.20ID:d0SphvuW �����̕���Ƃ��ē��A�e���A�����͖��A�㓁�܂ł͖��Ȃ��B
�����Ė��A�e�Z��A�t���A�����A�]�Z��܂ł̓G�����ł���Ȃ�A�|�A�S�C�ł����Ă������ʂ��������Ƃ��蕿�Ƃ������ׂ��ł���B
��������
�����Ė��A�e�Z��A�t���A�����A�]�Z��܂ł̓G�����ł���Ȃ�A�|�A�S�C�ł����Ă������ʂ��������Ƃ��蕿�Ƃ������ׂ��ł���B
��������
767�l�Ԏ����l�N
2023/04/04(��) 11:27:47.19ID:cFINril/ >>766
�ڋ��ȃW���b�v�炵����
�ڋ��ȃW���b�v�炵����
768�l�Ԏ����l�N
2023/04/04(��) 21:14:50.13ID:Flu5Hexi ���̏��������ƁA�Ȃ�q���̓G�����Ƃ����̂́A�|��S�C�͑ʖڂȂȁB
769�l�Ԏ����l�N
2023/04/04(��) 21:21:31.29ID:7VhXufKi ���c�M�����̎d�u�ɁA���X�̋��ڂɍ݂鎘�叫�O�ɁA�ߍ��E�����̑叫�̍s�V�A��@�A�d�`�Ȃǂ�
�����o������A�P�����Ɉ�c���ɂČ��ア�����A�Ƃ������̂��������B
����N�A���B�����̓V��{���E�q��i���G�j�Ɛ\�����叫�̏����i��d�鏑��ɁA
�w���Z�̐D�c�M���ɁA���n��ځi��30�Z���`�j�ɂ��Ȃ铍���O���������̂��}�܂�ɂ��āA
�����i�\�ꌎ�j���̏\���Ɍ��サ�����A�M���͍��������̍Ⴆ����叫�ł���A��ӂ͎���j���Ă���
�悤�Ɍ����Ă��A���S�ɂ͎��ɂ��A��i�Ɨ��ꂽ�鎖�̑������m�ł���܂�����A���̓���傢��
�S�j�����āA��͐M�����g�����A������͒��q���M���֎Q�炳��A�O�c�ڂ����B�l����
����ƍN�ւƑ����܂����B
���̎��ɑ��ƍN�́A���̏�Ȃ�ʂقǜz�Ȃ����Ƃ��Ƃ����Ԏ����o���܂������A���̓��͖����Ɏ̂Ă����A
�ƍN���H�����Ƃ͂���܂���ł����B�x
�����V��{���E�q��͏����t���Ē�o�����B����͈�c���̑������ɁA�u����͂���قǂ̎��ł������v�ƁA
���ɂ����ɂ��e���ɏ��������̂ł��������A�M�����͂���������ɂȂ�A���̏��t�����Ɏ���A
���炭�ڂ��ǂ��ꂽ��A��ڂ��J���Đ\���ꂽ
�u�ƍN�͍��N�Œ�߂ĎO�\����ł��낤�B�������l�\��ɋy�ю�X��g�̐M���ɔ�ׁA�܈ʂ��������A
���܂�ǂ���݂镪�ʂł���B����ɑ��A���m�̐S�y���̖����҂������A�N��Ɏ�����ʂƂ�
�\���ł��낤���A�O�͍������߂�Ƃ��āA�\�����\�Z�܂Ŕ��N�̊Ԃɕ�����s�����A����̗_���
����ɑ������A�C����̕��m�ƌĂ�Ă��邪�A���{���ɂ����Ă��ނɕC�G���镐���͂��܂葽���͂Ȃ����낤�B
�O�g�̐Ԉ�i���쒼�����j�A�]�k�̐����O��i�����j�A�l���̒��@�䕔�i���e�j�A��Ấi�b���j�����A������
���ɂ͂��̉ƍN�ł��낤�B
���āA�����O��̂��̓����̂Ă����̕��ʂ́A��̏o�����l���Ă̂��Ƃł��낤�B���̏o���Ƃ́A�����N�𖾂���
�����ł���g���ƂȂ�Ƃ������ł���B���̈Ӗ��͔n����Z�A�����C���A�����͒�߂č��_����ł��낤�B�v
���̂悤�ɐ��ꂽ�B
�w�b�z�R�Ӂx
�����o������A�P�����Ɉ�c���ɂČ��ア�����A�Ƃ������̂��������B
����N�A���B�����̓V��{���E�q��i���G�j�Ɛ\�����叫�̏����i��d�鏑��ɁA
�w���Z�̐D�c�M���ɁA���n��ځi��30�Z���`�j�ɂ��Ȃ铍���O���������̂��}�܂�ɂ��āA
�����i�\�ꌎ�j���̏\���Ɍ��サ�����A�M���͍��������̍Ⴆ����叫�ł���A��ӂ͎���j���Ă���
�悤�Ɍ����Ă��A���S�ɂ͎��ɂ��A��i�Ɨ��ꂽ�鎖�̑������m�ł���܂�����A���̓���傢��
�S�j�����āA��͐M�����g�����A������͒��q���M���֎Q�炳��A�O�c�ڂ����B�l����
����ƍN�ւƑ����܂����B
���̎��ɑ��ƍN�́A���̏�Ȃ�ʂقǜz�Ȃ����Ƃ��Ƃ����Ԏ����o���܂������A���̓��͖����Ɏ̂Ă����A
�ƍN���H�����Ƃ͂���܂���ł����B�x
�����V��{���E�q��͏����t���Ē�o�����B����͈�c���̑������ɁA�u����͂���قǂ̎��ł������v�ƁA
���ɂ����ɂ��e���ɏ��������̂ł��������A�M�����͂���������ɂȂ�A���̏��t�����Ɏ���A
���炭�ڂ��ǂ��ꂽ��A��ڂ��J���Đ\���ꂽ
�u�ƍN�͍��N�Œ�߂ĎO�\����ł��낤�B�������l�\��ɋy�ю�X��g�̐M���ɔ�ׁA�܈ʂ��������A
���܂�ǂ���݂镪�ʂł���B����ɑ��A���m�̐S�y���̖����҂������A�N��Ɏ�����ʂƂ�
�\���ł��낤���A�O�͍������߂�Ƃ��āA�\�����\�Z�܂Ŕ��N�̊Ԃɕ�����s�����A����̗_���
����ɑ������A�C����̕��m�ƌĂ�Ă��邪�A���{���ɂ����Ă��ނɕC�G���镐���͂��܂葽���͂Ȃ����낤�B
�O�g�̐Ԉ�i���쒼�����j�A�]�k�̐����O��i�����j�A�l���̒��@�䕔�i���e�j�A��Ấi�b���j�����A������
���ɂ͂��̉ƍN�ł��낤�B
���āA�����O��̂��̓����̂Ă����̕��ʂ́A��̏o�����l���Ă̂��Ƃł��낤�B���̏o���Ƃ́A�����N�𖾂���
�����ł���g���ƂȂ�Ƃ������ł���B���̈Ӗ��͔n����Z�A�����C���A�����͒�߂č��_����ł��낤�B�v
���̂悤�ɐ��ꂽ�B
�w�b�z�R�Ӂx
770�l�Ԏ����l�N
2023/04/04(��) 21:22:08.31ID:mUM08mQR ���������ڏ�̒j���̓G�ȊO�͓G���ɂȂ�Ȃ���
771�l�Ԏ����l�N
2023/04/04(��) 22:43:19.41ID:mUM08mQR ���������ڏ�̒j���̓G�ȊO�͓G���ɂȂ�Ȃ���
772�l�Ԏ����l�N
2023/04/05(��) 03:13:26.68ID:EsqAvUW1 �Ȃ��2���ĂH
773�l�Ԏ����l�N
2023/04/05(��) 09:43:17.78ID:IEEkKZDY �������������łƂ�����������
����Ă钆�g�͍��ƕς��ʎ���
����Ă钆�g�͍��ƕς��ʎ���
774�l�Ԏ����l�N
2023/04/05(��) 09:49:39.59ID:OzRsC2U6775�l�Ԏ����l�N
2023/04/05(��) 09:50:46.44ID:OzRsC2U6 ���l�сi�H�j�Ɂw�ِ��܂��܂��x���珼�����P�̂����b��
���P����孋�����������g�҂Ƃ��Ē��R���Z�����킳�ꂽ�B���R�A�����Œ��P���̌�O�ɂ܂���o��孋��̎|��\���グ��ƁA���P���A�u���̕������������Ă킪�O�ɏo�Ă����Ȃ�ΐ��Ď̂Ă悤�Ǝv���Ă������A�����ŏo�Ă������Ƃ͓V�����B���������悤�v�Ƌ����B
���Z�������܌��ɔ�ёނ��āA�u��l�̂��Ԏ�����ł͂��悤�Ɋo�債�Ă���܂����v�Ɖ������o���Ă���������ƁA���P���A�u���Ă��āA��l�͂��l�����ł��点����v�Ɗ������ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
���P����孋�����������g�҂Ƃ��Ē��R���Z�����킳�ꂽ�B���R�A�����Œ��P���̌�O�ɂ܂���o��孋��̎|��\���グ��ƁA���P���A�u���̕������������Ă킪�O�ɏo�Ă����Ȃ�ΐ��Ď̂Ă悤�Ǝv���Ă������A�����ŏo�Ă������Ƃ͓V�����B���������悤�v�Ƌ����B
���Z�������܌��ɔ�ёނ��āA�u��l�̂��Ԏ�����ł͂��悤�Ɋo�債�Ă���܂����v�Ɖ������o���Ă���������ƁA���P���A�u���Ă��āA��l�͂��l�����ł��点����v�Ɗ������ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
776�l�Ԏ����l�N
2023/04/05(��) 19:27:04.81ID:jWaTSmOW �L���v���u����G�ځv�����F�@�ق̘a��
��F�`��(�@��)�͏��|�ɒʂ��A�̓��ɂ��B���Ă����B
����Ƃ��Y��ɃI�E���̉̂��r��
�u�Ȃт��Ȃ�A���߂Ă�����̏��Y�ԁ@�v�ӂ�����蕗�͂ӂ��Ƃ��v
�u�Ȃт��܂��A���߂Ēu�̂̏��Y�ԁ@�v�ӂ�����蕗�͂ӂ��Ƃ��v
���̗�����ǂ������킯���V�q���������߂��A�u��̒��̑��c�v�u�u�̊D�v�Ƃ�������L�㍑�ɉ����ꂽ���߁A���֑̋�ɂċ`�����r��
�ᒆ���c
�x�m����c�q�̉Y��̗��l�́@��̒��ɂ����ȂւƂ�Ȃ�
�u�ΊD
���������Ƃ����u�̉����ā@�����̐^�����ɁA�͂Ђ����肯��
�V�q����������ꂽ�邱�����
�v�Ђ���}���̊C�̉ʂ܂ł��@�a�̂̉Y�g������ׂ��Ƃ�
���̎O���t���������߁A�b�����������Ƃ����B
������(�L���v���̌Z)�������ɂ́A�I���͓̉̂���̉̂ɑ���V�q�̏^�̌䐻�ł��낤
�Ȃт��Ȃ�c�Ȃт��܂��c�̗��̂�
�א쒉���u�Ȃт��Ȃ�䂪�P�_�̏��Y�ԁ@�j�R��蕗�͐����Ƃ��v
�K���V���u�Ȃт��܂��䂪�܂��_�̏��Y�ԁ@�j�R��蕗�͐����Ƃ��v
�Ɏ��Ă��邪�A�{�̂�����̂��낤��
��F�`��(�@��)�͏��|�ɒʂ��A�̓��ɂ��B���Ă����B
����Ƃ��Y��ɃI�E���̉̂��r��
�u�Ȃт��Ȃ�A���߂Ă�����̏��Y�ԁ@�v�ӂ�����蕗�͂ӂ��Ƃ��v
�u�Ȃт��܂��A���߂Ēu�̂̏��Y�ԁ@�v�ӂ�����蕗�͂ӂ��Ƃ��v
���̗�����ǂ������킯���V�q���������߂��A�u��̒��̑��c�v�u�u�̊D�v�Ƃ�������L�㍑�ɉ����ꂽ���߁A���֑̋�ɂċ`�����r��
�ᒆ���c
�x�m����c�q�̉Y��̗��l�́@��̒��ɂ����ȂւƂ�Ȃ�
�u�ΊD
���������Ƃ����u�̉����ā@�����̐^�����ɁA�͂Ђ����肯��
�V�q����������ꂽ�邱�����
�v�Ђ���}���̊C�̉ʂ܂ł��@�a�̂̉Y�g������ׂ��Ƃ�
���̎O���t���������߁A�b�����������Ƃ����B
������(�L���v���̌Z)�������ɂ́A�I���͓̉̂���̉̂ɑ���V�q�̏^�̌䐻�ł��낤
�Ȃт��Ȃ�c�Ȃт��܂��c�̗��̂�
�א쒉���u�Ȃт��Ȃ�䂪�P�_�̏��Y�ԁ@�j�R��蕗�͐����Ƃ��v
�K���V���u�Ȃт��܂��䂪�܂��_�̏��Y�ԁ@�j�R��蕗�͐����Ƃ��v
�Ɏ��Ă��邪�A�{�̂�����̂��낤��
777�l�Ԏ����l�N
2023/04/05(��) 19:31:53.70ID:jWaTSmOW http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-3316.html
���啐�Ƃ̎�ҁA��ޗǓV�c�̋��߂�
������̘b���Ə@�ق��Ⴂ���ɎQ�����Č�ޗǓV�c�̑O�Łu�ᒆ���c�v�����r���ƂɂȂ��Ă���
���啐�Ƃ̎�ҁA��ޗǓV�c�̋��߂�
������̘b���Ə@�ق��Ⴂ���ɎQ�����Č�ޗǓV�c�̑O�Łu�ᒆ���c�v�����r���ƂɂȂ��Ă���
778�l�Ԏ����l�N
2023/04/05(��) 21:22:42.24ID:EsqAvUW1779�l�Ԏ����l�N
2023/04/06(��) 12:18:07.62ID:sy19QJwM >>769
�d�v�l���͋G�ߊO��̉ʕ��͐H�ׂȂ����āA�ʂ̈�b�ł������C������ȁB����͒N���������c�B
�d�v�l���͋G�ߊO��̉ʕ��͐H�ׂȂ����āA�ʂ̈�b�ł������C������ȁB����͒N���������c�B
780�l�Ԏ����l�N
2023/04/06(��) 12:27:27.97ID:wrO1aHin �ї��P���ƐΓc�O���u�e���ƃW���v�E�����b
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-954.html
�ŋP�����G�g�ɑ������������ۂ��Ă���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-954.html
�ŋP�����G�g�ɑ������������ۂ��Ă���
781�l�Ԏ����l�N
2023/04/06(��) 12:31:22.08ID:sy19QJwM782�l�Ԏ����l�N
2023/04/06(��) 16:53:04.10ID:QdzFzLJH �����Ӗ����Ⴄ���A�ł��O�̐Γc�O�����������܂��Ă���ƌ�������A���͂Ȃ����`�Ȃ炠�邯��ǂǂ����H�ƌ����āA�`�͕����₷���炢��Ȃ��ƌ������b����������
783�l�Ԏ����l�N
2023/04/06(��) 17:56:51.72ID:zBrquiel784�l�Ԏ����l�N
2023/04/06(��) 21:38:36.39ID:asQEHxFF ���Ⴀ���ɉʕ����̂Ɉ������Ęb����?
785�l�Ԏ����l�N
2023/04/06(��) 22:55:45.51ID:FhYovSIC �����������{���Y�̉ʕ����Ċ`��������H
�퍑����ɂ������̂��Ă��Ȃ��������
�퍑����ɂ������̂��Ă��Ȃ��������
786�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 07:37:32.94ID:pu4LY7A3 >>785
�A�P�r�B�т�
�A�P�r�B�т�
787�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 09:15:08.34ID:1D1H5gP+ �ь�A���݂���Ƃ���
�P�ь�݂����ȏ�������ނ������Ǝv�����ǁA��䒷�����c������Ă��肪�Ƃ��Ƃ����莆�������Ă����͂�
�P�ь�݂����ȏ�������ނ������Ǝv�����ǁA��䒷�����c������Ă��肪�Ƃ��Ƃ����莆�������Ă����͂�
788�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 09:37:11.47ID:APLW2NFB �O�ɏo�Ă����t�����`�F�X�R�E�J�����b�e�B�u���E���V�L�v��16���I���̗l�q
�����̑�s�s�Ɩ����̐l��������A�i�ς͗ǂ��B�Ă����ɖL���ŁA�����A��A�ʕ��ɂ��x��ł���B
���ɔ炲�ƐH�ׂ���I�����W���܂߂����k�ނ��������悤�B
�I�����W�͉�X�̃������Ɏ��Ă���Acunebes(��N��?)�ƌĂ��B�܂������قǂ̏����ȃ������Ɏ������k�ނ�����A
������炲�ƐH�ׂ��邵�A�W�����ɂ��Ă����������B
�i���̌�t�B�����`�F�Ɏ����A������̘b����j
��������A���ɑ傫���Đ��X�����B��͔��ɔ����������Ƃ͓���B���A���A�ǂ͍����Ђ��ɂ���Ɣ����ł���B
�Ԃǂ��͂قƂ�nj����Ȃ����A���E�҂��������{�s�̂��߂Ƀ��C�����������邱�Ƃ�����B
�������͑��ʂɓ���\�ł��邪�A�����A�i���͈قȂ�B
�炲�ƐH�ׂ��A�L���E���̂悤�ɐ蕪������B�̏�Ԃʼn��Ђ�����Ă���̂ŁA�ۑ��\�ł���B
�����̑�s�s�Ɩ����̐l��������A�i�ς͗ǂ��B�Ă����ɖL���ŁA�����A��A�ʕ��ɂ��x��ł���B
���ɔ炲�ƐH�ׂ���I�����W���܂߂����k�ނ��������悤�B
�I�����W�͉�X�̃������Ɏ��Ă���Acunebes(��N��?)�ƌĂ��B�܂������قǂ̏����ȃ������Ɏ������k�ނ�����A
������炲�ƐH�ׂ��邵�A�W�����ɂ��Ă����������B
�i���̌�t�B�����`�F�Ɏ����A������̘b����j
��������A���ɑ傫���Đ��X�����B��͔��ɔ����������Ƃ͓���B���A���A�ǂ͍����Ђ��ɂ���Ɣ����ł���B
�Ԃǂ��͂قƂ�nj����Ȃ����A���E�҂��������{�s�̂��߂Ƀ��C�����������邱�Ƃ�����B
�������͑��ʂɓ���\�ł��邪�A�����A�i���͈قȂ�B
�炲�ƐH�ׂ��A�L���E���̂悤�ɐ蕪������B�̏�Ԃʼn��Ђ�����Ă���̂ŁA�ۑ��\�ł���B
789�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 09:54:45.06ID:AWtvDFWa790�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 10:01:01.12ID:Hd21G4Ga >>785
������Ă݂�Ȃɘb���Ɣn���ɂ����l�^����ˁH
������Ă݂�Ȃɘb���Ɣn���ɂ����l�^����ˁH
791�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 12:17:06.10ID:nrRDFYzI >>789
�m�������̃A�z���C�L���Ăđ�
�m�������̃A�z���C�L���Ăđ�
792�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 12:21:37.91ID:nrRDFYzI �C�L�b�ā��A�z
�C�L���ā�����
�C�L���ā�����
793�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 17:10:19.52ID:CU/qrO/6 (��)�ł�(�b)�ł��ǂ����ł��������A�v�͒N���̘b����
�u���A��������Șb���v���o�����v�ƒN�ł��m���Ă�b���ɋ����āA
�u����A���̘b�Ȃ炨����m���Ă�v
�u��������������Ƃ���v
���Ă����̘b��
�u����ȒN�ł��m���Ă�b������ȁI�v���Ċ��݂���Ă��A�u�͂��H�v�Ƃ����Ȃ��킯����
�����C�L�b�ċ��肵�Ă�̂��
�}�E���g�ɂ����ɂ��Ȃ��ĂȂ���
�u���A��������Șb���v���o�����v�ƒN�ł��m���Ă�b���ɋ����āA
�u����A���̘b�Ȃ炨����m���Ă�v
�u��������������Ƃ���v
���Ă����̘b��
�u����ȒN�ł��m���Ă�b������ȁI�v���Ċ��݂���Ă��A�u�͂��H�v�Ƃ����Ȃ��킯����
�����C�L�b�ċ��肵�Ă�̂��
�}�E���g�ɂ����ɂ��Ȃ��ĂȂ���
794�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 18:28:24.12ID:9xyDb8cV ��^���Ԃɂ��đ�
�ǂ����ł������Ƃ��A�z�̌�����ۏo�����
�ǂ����ł������Ƃ��A�z�̌�����ۏo�����
795�l�Ԏ����l�N
2023/04/07(��) 18:57:41.83ID:MRBpmiHn ���́u�I���˂�v�Ɓu�I��v���ǂ����ł��g������I�u�I��v�ł������I���Č����Ă�悤�Ȃ��̂���
���{�l�Ȃ�{���̌��������g���ׂ������A�����ȓ��{�l�Ȃ�f���ɊԈႢ�͔F�߂ĎӍ߂��Ă�Ƃ�
�`�����ɂ͓��{�l�̐S�͗����ł��Ȃ������悤����
���{�l�Ȃ�{���̌��������g���ׂ������A�����ȓ��{�l�Ȃ�f���ɊԈႢ�͔F�߂ĎӍ߂��Ă�Ƃ�
�`�����ɂ͓��{�l�̐S�͗����ł��Ȃ������悤����
796�l�Ԏ����l�N
2023/04/08(�y) 11:22:07.31ID:olOpq4Ad �͂��_�j�A�`�����̃C�L�b�ČN�シ���[
797�l�Ԏ����l�N
2023/04/08(�y) 16:52:30.59ID:V1u+k6am �ȂH�R�C�c
798�l�Ԏ����l�N
2023/04/08(�y) 20:23:22.77ID:M9OGZ0x1 �������g���Ƃ����̂͂킩�邯�ǁA���ǂ͐��Ԃłǂ�Ȃӂ��Ɏg���Ă������ŕϖe����̂��d���Ȃ���Ȃ��́H
799�l�Ԏ����l�N
2023/04/08(�y) 20:40:36.65ID:wrawGclA �܂��J��Ԃ��N������Ă��������l�ɂƂ��Ă͊Ԉ���ĂĂ�����鉺�n���ł��Ă邩���
800�l�Ԏ����l�N
2023/04/09(��) 06:49:08.17ID:aEgFHgPX �Ȃ���������Ⴂ���Ȃ��S�����̃��c�ɗ��܂ꂿ������݂����E�E
801�l�Ԏ����l�N
2023/04/09(��) 08:10:33.84ID:tNUQmptV �m�������̃C�L�b�ČN�~��www
802�l�Ԏ����l�N
2023/04/09(��) 09:02:25.11ID:2s3XLOMu ���N�l�܂����Ă���
803�l�Ԏ����l�N
2023/04/09(��) 09:42:48.95ID:aEgFHgPX �P�l��ID�ς��ĘA���A����J�l�ł�
804�l�Ԏ����l�N
2023/04/09(��) 16:09:14.69ID:/w6d8Jbv �����������
805�l�Ԏ����l�N
2023/04/10(��) 11:50:41.37ID:Mq1VAjSD https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1681015699/1 �y�����z��납��������āc�A�20�㏗���ɂ킢���@���f���̖k�����s���e�^�ҁi27�j��ߕ߁@���c�J�� [���ꁚ]
>�k�����s��
https://i.imgur.com/xsRobLC.jpg
������
>�k�����s��
https://i.imgur.com/xsRobLC.jpg
������
806�l�Ԏ����l�N
2023/04/10(��) 12:37:35.37ID:CQoGnoPg >>805
�쒩(�N)���ȁH
�쒩(�N)���ȁH
807�l�Ԏ����l�N
2023/04/10(��) 13:53:49.55ID:vHOpS6kB �C�L�b�ČN�^�C�z�`
808�l�Ԏ����l�N
2023/04/15(�y) 19:04:07.05ID:9+E2Bn0r �u�����L�v����_���@�X
�_���@�X�͔�O�����Âɉ��Z�܂������Ă����B
���̂���V���ɖ��̒m�ꂽ���l�ł���痘�x��V�������@�y(�Óc�@�y)�ɂ���A���������𐢏�ɒm�炵�߂悤�Ɠ��Â��o�ē��������B
�����ɂ����ėL���ȋ����̑m���̊Ԃł�������o�Ă������߁A�G�g�����͂Ȃ͂����S�Ȃ������B
�V���\�ܔN(1587�N)�����O���A�G�g��������ŏ��喼������������Ȃ��ꂽ�Ƃ����@�X�������Ē��������点���B
���̎��A�Γc�O���̎�莝���Ŗ�����G�g���ɐi�サ���B
�Ք�A�^��ꖇ�A�ƕz(�㓙�̖��z)��ҁA������҂ł������B
�V�������@�y���������莟�����B
���̂Ƃ�����G�g���̒����A����ł��ߎ����A���喼�ɂ������ꂽ�B
�G�g���̒�̑�a��[���G�������A��a�S�R��ɍݏ邳��Ă��������Q�y�����B
�������ďG�g�����ڂ̎҂ƂȂ������߁A�G�g�����}�O�ɉ������ꂽ�������]���A(���ÌR�ɂ��)�œy�ƂȂ����������䗗�ɂȂ��������䋟�����B
�܂��V���\�ܔN�Z���\����A�G�g���͌�w���ɂĐ_���@�X�Ɠ���@���ɂ�������������A
��\�ܓ��ɂ�⦍�Ԕ��V�ŏG�g���֏@�X�͌䒃�𗧂Ă��B�א�H�ւ��䑊���ł�����
�_���@�X�͔�O�����Âɉ��Z�܂������Ă����B
���̂���V���ɖ��̒m�ꂽ���l�ł���痘�x��V�������@�y(�Óc�@�y)�ɂ���A���������𐢏�ɒm�炵�߂悤�Ɠ��Â��o�ē��������B
�����ɂ����ėL���ȋ����̑m���̊Ԃł�������o�Ă������߁A�G�g�����͂Ȃ͂����S�Ȃ������B
�V���\�ܔN(1587�N)�����O���A�G�g��������ŏ��喼������������Ȃ��ꂽ�Ƃ����@�X�������Ē��������点���B
���̎��A�Γc�O���̎�莝���Ŗ�����G�g���ɐi�サ���B
�Ք�A�^��ꖇ�A�ƕz(�㓙�̖��z)��ҁA������҂ł������B
�V�������@�y���������莟�����B
���̂Ƃ�����G�g���̒����A����ł��ߎ����A���喼�ɂ������ꂽ�B
�G�g���̒�̑�a��[���G�������A��a�S�R��ɍݏ邳��Ă��������Q�y�����B
�������ďG�g�����ڂ̎҂ƂȂ������߁A�G�g�����}�O�ɉ������ꂽ�������]���A(���ÌR�ɂ��)�œy�ƂȂ����������䗗�ɂȂ��������䋟�����B
�܂��V���\�ܔN�Z���\����A�G�g���͌�w���ɂĐ_���@�X�Ɠ���@���ɂ�������������A
��\�ܓ��ɂ�⦍�Ԕ��V�ŏG�g���֏@�X�͌䒃�𗧂Ă��B�א�H�ւ��䑊���ł�����
809�l�Ԏ����l�N
2023/04/19(��) 17:24:36.68ID:S9OmN5yQ �w�ِ��܂��܂��x���炠�鎞�̏G�g�ƉƍN�̉�b
���}�u��˂ɒޕr�𗎂Ƃ��Ă��܂����B������g�킸�ɂ���������g����ɂ͂ǂ�����H�v
�_�N�u��l���ň�˂������ݓ���A��{�̎w�ł��̒ޕr�������g���܂��傤�v
���}�u���Ɠ����l�����B���̎���́A�V���̎�͋M�a�ł��낤�v
�ꉞ�����b��
���}�u��˂ɒޕr�𗎂Ƃ��Ă��܂����B������g�킸�ɂ���������g����ɂ͂ǂ�����H�v
�_�N�u��l���ň�˂������ݓ���A��{�̎w�ł��̒ޕr�������g���܂��傤�v
���}�u���Ɠ����l�����B���̎���́A�V���̎�͋M�a�ł��낤�v
�ꉞ�����b��
810�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 08:22:38.76ID:LWei7ilA �ƍN�Ɏg���������������ݗ��Y�A�ߌ��̃L���V�^���u�W�����A�������v���̒��M����
�ǔ��V��2023/04/20
https://www.yomiuri.co.jp/culture/20230420-OYT1T50048/
�������فi�R�������s�j�͂P�X���A�L�b�G�g�̒��N�o���Œ��N����A��Ă����A����ƍN�Ɏd�����������������
���Y�ƂȂ����Ƃ����L���V�^�������u�W�����A�������v�̒��M�����߂Č��������Ɣ��\�����B���ق́u�ߌ���
�L���V�^�������ɂ܂��M�d�Ȏj���v�Ƃ��Ă���B
�������͒��N�o���ŕ߂炦���A�L���V�^���喼�Ƃ��Ēm���鏬���s���̗{���ƂȂ����B�փ����̐킢��͉ƍN�Ɏd�������A
���{�̋��ߌ���M���̂Ă��A�ɓ������ɗ����ꂽ�Ƃ����B
���قɂ��ƁA����͂R�ʂŒ��B�ˎm�̑��c�Ƃɓ`���A�q�������قɊ����B���c�Ə���̑��c�����͂������̒�
���Ƃ������B�˂̋L�^������A�Q�l�̂Ȃ���𗠕t���锭���Ƃ��Ă���B
�]�ˎ��㏉���̂P�U�O�X�N�i�c���P�S�N�j�W���P�X���t�̏���́A���������B�˂ɂ���ƒm�������������A�̂̂����̈ʒu
�Ȃǂ��L���Ė{�l�m�F������e�ŁA�ق��̂Q�ʂ͒�Ɖ�����ȂǂƖ]�ޓ��e�������B
���̂ق��A���c�Ƃ���́A�������̒���ň������ƍN�ɖʉ���ۂɗ^����ꂽ�Ƃ����ƍN�̏����i�g��P�Q�P�Z���`�A
���䂫 ��T�X�Z���`�j�����ꂽ�B
�ǔ��V��2023/04/20
https://www.yomiuri.co.jp/culture/20230420-OYT1T50048/
�������فi�R�������s�j�͂P�X���A�L�b�G�g�̒��N�o���Œ��N����A��Ă����A����ƍN�Ɏd�����������������
���Y�ƂȂ����Ƃ����L���V�^�������u�W�����A�������v�̒��M�����߂Č��������Ɣ��\�����B���ق́u�ߌ���
�L���V�^�������ɂ܂��M�d�Ȏj���v�Ƃ��Ă���B
�������͒��N�o���ŕ߂炦���A�L���V�^���喼�Ƃ��Ēm���鏬���s���̗{���ƂȂ����B�փ����̐킢��͉ƍN�Ɏd�������A
���{�̋��ߌ���M���̂Ă��A�ɓ������ɗ����ꂽ�Ƃ����B
���قɂ��ƁA����͂R�ʂŒ��B�ˎm�̑��c�Ƃɓ`���A�q�������قɊ����B���c�Ə���̑��c�����͂������̒�
���Ƃ������B�˂̋L�^������A�Q�l�̂Ȃ���𗠕t���锭���Ƃ��Ă���B
�]�ˎ��㏉���̂P�U�O�X�N�i�c���P�S�N�j�W���P�X���t�̏���́A���������B�˂ɂ���ƒm�������������A�̂̂����̈ʒu
�Ȃǂ��L���Ė{�l�m�F������e�ŁA�ق��̂Q�ʂ͒�Ɖ�����ȂǂƖ]�ޓ��e�������B
���̂ق��A���c�Ƃ���́A�������̒���ň������ƍN�ɖʉ���ۂɗ^����ꂽ�Ƃ����ƍN�̏����i�g��P�Q�P�Z���`�A
���䂫 ��T�X�Z���`�j�����ꂽ�B
811�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 08:33:09.01ID:LWei7ilA �⑫�Ƃ��āA��N��������������܂����B
��75����p�j�w��S�����(2022) �������ُ����u����t�T�b�͗l�����v�̕����j�I�ʒu�t�� ������q�i�w�K�@���q��w�j
https://www.bijutsushi.jp/c-zenkokutaikai/pdf-files/2022-5/2022_D2.pdf
�{�����̓`���ɂ��Č�������B��q�̖n���̂���ɂ́A�{�����ƂƂ��Ɂu��䏊���܌�������v�Ɓu����Ȃ��v�Ƃ̊Ԃ�
���킳�ꂽ���ȓ�����܂�Ă����B�����̊W�j���̕��͂ɂ��A���c�Ƃ̏���ł��鑺�c�܉E�q������́A�L�b�G�g��
���N�o���̍ۂɕ߂炦��ꂽ���N�l�ߗ��ł���A���́u����Ȃ��v�ł������Ƃ����B
�܂��A�����̎o�����{�ɘA��Ă����A��䏊����̓���ƍN�ɕ�����Ă���A�o��ʂ��ďx�{�ɏ����o���ꂽ�ۂɁA�ƍN����
�����ɔn�Ⓛ�ƂƂ��Ɂu�����t�V�䕞�v���������ꂽ�Ƃ̋L�q���w���˔��{�^�x�i���� 10 �N�����j�Ɍ��o����B
���̋L�q���A�{�����ɂ�����ƍl������B
����ɁA�t�����鏑�Ȃɂ݂���u��䏊���܌�������v�͈����̎o�ł���A�ߔN�̌����Ŏw�E�����u�W�����A�������v�ł������ƍl������B
���N�o���̍ۂ̒��N�l�ߗ��Ƃ����u�W�����A�������v�Ɋւ��ẮA����܂ŃL���X�g���M�j���̖ʂ��猤�����i�߂��Ă������A
�{�����ƕt�����鏑�ȗނ́A����܂Ŏw�E����Ă��Ȃ��V���ȊW�����Ƃ�����B
��75����p�j�w��S�����(2022) �������ُ����u����t�T�b�͗l�����v�̕����j�I�ʒu�t�� ������q�i�w�K�@���q��w�j
https://www.bijutsushi.jp/c-zenkokutaikai/pdf-files/2022-5/2022_D2.pdf
�{�����̓`���ɂ��Č�������B��q�̖n���̂���ɂ́A�{�����ƂƂ��Ɂu��䏊���܌�������v�Ɓu����Ȃ��v�Ƃ̊Ԃ�
���킳�ꂽ���ȓ�����܂�Ă����B�����̊W�j���̕��͂ɂ��A���c�Ƃ̏���ł��鑺�c�܉E�q������́A�L�b�G�g��
���N�o���̍ۂɕ߂炦��ꂽ���N�l�ߗ��ł���A���́u����Ȃ��v�ł������Ƃ����B
�܂��A�����̎o�����{�ɘA��Ă����A��䏊����̓���ƍN�ɕ�����Ă���A�o��ʂ��ďx�{�ɏ����o���ꂽ�ۂɁA�ƍN����
�����ɔn�Ⓛ�ƂƂ��Ɂu�����t�V�䕞�v���������ꂽ�Ƃ̋L�q���w���˔��{�^�x�i���� 10 �N�����j�Ɍ��o����B
���̋L�q���A�{�����ɂ�����ƍl������B
����ɁA�t�����鏑�Ȃɂ݂���u��䏊���܌�������v�͈����̎o�ł���A�ߔN�̌����Ŏw�E�����u�W�����A�������v�ł������ƍl������B
���N�o���̍ۂ̒��N�l�ߗ��Ƃ����u�W�����A�������v�Ɋւ��ẮA����܂ŃL���X�g���M�j���̖ʂ��猤�����i�߂��Ă������A
�{�����ƕt�����鏑�ȗނ́A����܂Ŏw�E����Ă��Ȃ��V���ȊW�����Ƃ�����B
812�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 09:00:20.70ID:64i9wLrR >>809
��˂ɐ������ݓ���邽�߂̉��Ȃǂ̗e��͓���ɂ͓���Ȃ��̂��ȁH
��˂ɐ������ݓ���邽�߂̉��Ȃǂ̗e��͓���ɂ͓���Ȃ��̂��ȁH
813�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 09:05:38.90ID:LWei7ilA >>810
���e���Ă���C�Â����A�^�C�g���̎g�����i�}�}�j�͓ǔ��̊ԈႢ�Ȃ�ł����A���T�C�g������d�����ɒ�������Ă܂����˂�
���e���Ă���C�Â����A�^�C�g���̎g�����i�}�}�j�͓ǔ��̊ԈႢ�Ȃ�ł����A���T�C�g������d�����ɒ�������Ă܂����˂�
814�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 12:01:49.03ID:4JvXiGil �V������]�ڂƂ͂����̃��x�����n�ɗ�������
815�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 13:01:36.70ID:2UYUzUmZ >>812
���������Ƃ������O������
���������Ƃ������O������
816�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 13:04:38.18ID:+6bqh/8m817�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 16:03:46.60ID:q9cETSOF �ق�ƎO������������
818�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 16:10:41.46ID:0Lk0BD22 ������`�Ȃ�
819�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 18:06:48.40ID:gtI08+75 �u�����L�v���璩�N�l�ߗ��œ��R�����j�ł��d�v�ȗ������֘A�̘b
�����R�{�x���͍͐̂��F���ɂ������B
��F�@�ق���}�O���ʕ{���̓y�n�A�\�ܒ��̊�i�̕�������������B
�܂����N�l�������Ƃ����҂������ɗ��đؗ������B
�{����(�{�x���H)�ɂ��Ă̎��L���������̂���������B
�������͌c���\��N(1614�N)�t�ɋq�����o�����ƂƁA����̓V�炩�獕�_���������ēV�������Ƃ��������������B
(���̐w�ƖL�b�ŖS�ɂ��āH)
�܂������ɑؗ��������A���������̋L�����������B
��҂ŁA�肢���悭�����Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13618.html
�G���F�����̎�
���̋L���́A���邩��㓡�����q�Ɨ������т����N�l�̂��Ƃł͂Ȃ����Ƃ����̂őO�ɏo�Ă����B
�����R�{�x���͍͐̂��F���ɂ������B
��F�@�ق���}�O���ʕ{���̓y�n�A�\�ܒ��̊�i�̕�������������B
�܂����N�l�������Ƃ����҂������ɗ��đؗ������B
�{����(�{�x���H)�ɂ��Ă̎��L���������̂���������B
�������͌c���\��N(1614�N)�t�ɋq�����o�����ƂƁA����̓V�炩�獕�_���������ēV�������Ƃ��������������B
(���̐w�ƖL�b�ŖS�ɂ��āH)
�܂������ɑؗ��������A���������̋L�����������B
��҂ŁA�肢���悭�����Ƃ����B
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13618.html
�G���F�����̎�
���̋L���́A���邩��㓡�����q�Ɨ������т����N�l�̂��Ƃł͂Ȃ����Ƃ����̂őO�ɏo�Ă����B
820�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 18:40:47.35ID:tB8DIojS ���������q��(�a��)�ɂ��Đ�������Ƃ�
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13254.html
�����ӂ̎�������������
�ɁA�V�炩��̍��_�]�X�ɂ��Đ�������Ƃ͉ƍN�����l(�ʂ��ւӂقӁH)���������Ƃ�������Ă���
�u�ꏪ�b�v�Ɉȉ��̂悤�ɏ�����Ă����B
�u�ꏪ�b�v����u���N�̈Վҁv
�c���̍��A���N���~���������߁A�ؗ�������Ԋ҂����Ȃ��ŗ������͂ǂ������킯�����{�ɂƂǂ܂����B
�b�Ђ̔N(��L��1614�N)�A���ɗ����N���낤�Ƃ������A��̓a��(�V��)�̏�ɉΉ��������Ȃ�R���オ�����B
��̓��O�����������A�삯���ď������Ƃ������A�ǂ��ɂ��͌����Ȃ������B
�����Đl���Â܂�����܂��R���オ�����B(����:�ܓ��̂��Ƃ��H)
���̂悤�Ȃ��Ƃ����т��т��������߁A�Ћˊ����ɖ����ė������ɐ�킹���B
�������u�Ŏ�(�ʼn���)�́u�сv�ɂ���Đ肤��
�u�������ɕς���B���v�B�q�������B������ǁB�s�V殽���B���\�Ж��B�ی��B�l�ʋS���B���㗘���B���j��璉�B�u�����J�B�v�Əo�܂����v
�ď�̎n�߂���I���܂ŁA���̐肢�ɂ�����Ȃ������Ƃ́A�����ꂽ�Վ҂ł������B
�Ŏ��Ղ͐̂���肢�ɑ����g�����킯�ł͂Ȃ��̂ɁA�������͂悭�`�������̂��B
�������͏��@�̒B�l�ł�����A�����ŏ����ꂽ�F�o�������Ƃ���A�����ւ��ł������B(��䎁����)
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13254.html
�����ӂ̎�������������
�ɁA�V�炩��̍��_�]�X�ɂ��Đ�������Ƃ͉ƍN�����l(�ʂ��ւӂقӁH)���������Ƃ�������Ă���
�u�ꏪ�b�v�Ɉȉ��̂悤�ɏ�����Ă����B
�u�ꏪ�b�v����u���N�̈Վҁv
�c���̍��A���N���~���������߁A�ؗ�������Ԋ҂����Ȃ��ŗ������͂ǂ������킯�����{�ɂƂǂ܂����B
�b�Ђ̔N(��L��1614�N)�A���ɗ����N���낤�Ƃ������A��̓a��(�V��)�̏�ɉΉ��������Ȃ�R���オ�����B
��̓��O�����������A�삯���ď������Ƃ������A�ǂ��ɂ��͌����Ȃ������B
�����Đl���Â܂�����܂��R���オ�����B(����:�ܓ��̂��Ƃ��H)
���̂悤�Ȃ��Ƃ����т��т��������߁A�Ћˊ����ɖ����ė������ɐ�킹���B
�������u�Ŏ�(�ʼn���)�́u�сv�ɂ���Đ肤��
�u�������ɕς���B���v�B�q�������B������ǁB�s�V殽���B���\�Ж��B�ی��B�l�ʋS���B���㗘���B���j��璉�B�u�����J�B�v�Əo�܂����v
�ď�̎n�߂���I���܂ŁA���̐肢�ɂ�����Ȃ������Ƃ́A�����ꂽ�Վ҂ł������B
�Ŏ��Ղ͐̂���肢�ɑ����g�����킯�ł͂Ȃ��̂ɁA�������͂悭�`�������̂��B
�������͏��@�̒B�l�ł�����A�����ŏ����ꂽ�F�o�������Ƃ���A�����ւ��ł������B(��䎁����)
821�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 20:31:12.80ID:PkBOkJ1I �O���W�Ȃ��̂Ƀt���{�b�R�ő�
�ِ��܂��܂��ɁA�������}(�э])���~�c�i���łȂ��~�c�q���Ɠǂނƌ����Ă����Ə����Ă������B
�����q���Ɠǂސl�N����������
�ِ��܂��܂��ɁA�������}(�э])���~�c�i���łȂ��~�c�q���Ɠǂނƌ����Ă����Ə����Ă������B
�����q���Ɠǂސl�N����������
822�l�Ԏ����l�N
2023/04/20(��) 20:33:02.59ID:UtUY7f4T >>821
����
����
823�l�Ԏ����l�N
2023/04/21(��) 00:45:13.16ID:gRmW3DNN http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-10163.html
�O�����u���������v�u�������v�ƓǂނƂ����b�͏o�Ă�����
�u�݂Ђ�v�͏��߂Č���
�O�����u���������v�u�������v�ƓǂނƂ����b�͏o�Ă�����
�u�݂Ђ�v�͏��߂Č���
824�l�Ԏ����l�N
2023/04/21(��) 04:29:48.88ID:tOJDGDR/ ���i�L�[�M�j��O���@�i�L�[�M�j���ł���
825�l�Ԏ����l�N
2023/04/21(��) 12:40:38.86ID:tOJDGDR/ �U��
826�l�Ԏ����l�N
2023/04/21(��) 21:12:57.90ID:LUHBz44e >>820
�u�сv�̈��p�������Ӗ���������Ȃ������̂Œ��ׂĂ݂��B
�ŏ��́u�q�������B������ǁB�s�V殽���v�̕����́A���V�v�́u�`��ो��C������ǁC�s��殽鄉�v���Ǝv���B
���Ɂu�`�s�����@�f�V�|�C���Ж�����C�t�s��殽�v�Ƃ����āA�`�̖s�����|�߂�p�����W���U�߂āi�`��ो��j殽�ő�s���i���i�s��殽鄉�j�A
�Ж����i�S�����̑��q�Ŗ��͎��A���͖Ж��j��O�l�̏��R���ߗ��ɂȂ������Ɓi������ǁj���w���炵���B
�G�����|�߂�p����������ď��������������Ƃ�\������̂��ȁB
�u�сv�̈��p�������Ӗ���������Ȃ������̂Œ��ׂĂ݂��B
�ŏ��́u�q�������B������ǁB�s�V殽���v�̕����́A���V�v�́u�`��ो��C������ǁC�s��殽鄉�v���Ǝv���B
���Ɂu�`�s�����@�f�V�|�C���Ж�����C�t�s��殽�v�Ƃ����āA�`�̖s�����|�߂�p�����W���U�߂āi�`��ो��j殽�ő�s���i���i�s��殽鄉�j�A
�Ж����i�S�����̑��q�Ŗ��͎��A���͖Ж��j��O�l�̏��R���ߗ��ɂȂ������Ɓi������ǁj���w���炵���B
�G�����|�߂�p����������ď��������������Ƃ�\������̂��ȁB
827�l�Ԏ����l�N
2023/04/21(��) 21:31:36.16ID:LUHBz44e �r���ő��M����������̂ő���
�u���\�Ж��v�͂悭�킩��Ȃ����ǁA�т̖{���ɂ͂Ȃ��̂Œ��������������Ȃ��ȁB
�u�l�ʋS���B���㗘���B���j���l�B�u�����J�v�͔۔V���Ɂu�l�ʋS���C����ו��G斲�j���l,�u��絕�J�v�Ƃ����̂�����B
�u�l�ʋS���v�͐̂͋S�͋�ƒʂ����炵���A�u�l�ʋ���v�Ɠ����炵���B�u����ו��v�ƍ��킹�āA���͍Ђ��̖�Ƃ�����Ȋ������B
�u斲�j���l,�u��絕�J�v�͒��ɂ��Ɓu���@�����C���q���Պ�z���C���㕐�����@�C���ŏ����v��
�����ȏ������J�̂��߂̕��������q�������ł������Ƃ������炵���B
�����̕��j���Ȃ��Ȃ����܂炸���ʂȌR�c�̂ݏd�˂čŌ�͖L�b�Ƃ��łт����Ƃ�\�����Ă���낤�B
�����A�����@�����w���Ă�̂��{�����Ƃ�����A���ƃX�g���[�g�ɏG���f�B�X���Ă邱�ƂɂȂ邯�Ǒ��v�������낤���B
�u���\�Ж��v�͂悭�킩��Ȃ����ǁA�т̖{���ɂ͂Ȃ��̂Œ��������������Ȃ��ȁB
�u�l�ʋS���B���㗘���B���j���l�B�u�����J�v�͔۔V���Ɂu�l�ʋS���C����ו��G斲�j���l,�u��絕�J�v�Ƃ����̂�����B
�u�l�ʋS���v�͐̂͋S�͋�ƒʂ����炵���A�u�l�ʋ���v�Ɠ����炵���B�u����ו��v�ƍ��킹�āA���͍Ђ��̖�Ƃ�����Ȋ������B
�u斲�j���l,�u��絕�J�v�͒��ɂ��Ɓu���@�����C���q���Պ�z���C���㕐�����@�C���ŏ����v��
�����ȏ������J�̂��߂̕��������q�������ł������Ƃ������炵���B
�����̕��j���Ȃ��Ȃ����܂炸���ʂȌR�c�̂ݏd�˂čŌ�͖L�b�Ƃ��łт����Ƃ�\�����Ă���낤�B
�����A�����@�����w���Ă�̂��{�����Ƃ�����A���ƃX�g���[�g�ɏG���f�B�X���Ă邱�ƂɂȂ邯�Ǒ��v�������낤���B
828�l�Ԏ����l�N
2023/04/21(��) 22:10:10.09ID:LUHBz44e �������Ă��܂ǁA�u�l�ʋ���v���悭�Ӗ��킩�������������ׂĂ݂���
�ǂ����A�u�l�ʋS���v�u�l�ʋ���v���u���ʋ���v�̈Ӗ����ۂ��B
���ꂾ�ƐF��Ȑl���Ă�łɎ����̈ӌ������������Ęb���S���܂Ƃ܂�Ȃ����Ċ����Ȃ̂��ȁB
�ǂ����A�u�l�ʋS���v�u�l�ʋ���v���u���ʋ���v�̈Ӗ����ۂ��B
���ꂾ�ƐF��Ȑl���Ă�łɎ����̈ӌ������������Ęb���S���܂Ƃ܂�Ȃ����Ċ����Ȃ̂��ȁB
829�l�Ԏ����l�N
2023/04/21(��) 23:33:52.19ID:XSWnTD4j �l�Ɣ��A�S�Ƌ�
���ʂ����Ă邯�NJԈႦ�Ċo��������L�܂����̂��H
���ʂ����Ă邯�NJԈႦ�Ċo��������L�܂����̂��H
830�l�Ԏ����l�N
2023/04/22(�y) 11:21:00.14ID:5o7Pygfj ���������͖̂L�b�Ƃɏd�p���ꂽ���ǁA
�肢�ɂ������ďG�g��u���@���ɂ��Ƃ��Ē��N�o����ᔻ���āA�L�b�̍��J���łт邼�A�ƌ������Ƃ�
�肢�ɂ������ďG�g��u���@���ɂ��Ƃ��Ē��N�o����ᔻ���āA�L�b�̍��J���łт邼�A�ƌ������Ƃ�
831�l�Ԏ����l�N
2023/04/22(�y) 11:49:18.71ID:adN4jV/6 >>829
�l�Ɣ��͂��Ԃ��̓ǂ݊ԈႢor�����ԈႢ���Ǝv���B
�S�Ƌ�́A�юߕ��̒��Ɂu��̖ю��É��l�ɐl�ʋ�������p����
�̂͋�ƋS���ʗp���āA�Ⴆ�����S��Ƃ��������v�Ə����Ă����ŁA
���ꂪ��������A�Â�����͋S�Ƌ�̉������Ă����i�����͓����������j���߂�
�������Ƃ��Ĉ��������Ă��Ƃ��Ǝv���B
�l�Ɣ��͂��Ԃ��̓ǂ݊ԈႢor�����ԈႢ���Ǝv���B
�S�Ƌ�́A�юߕ��̒��Ɂu��̖ю��É��l�ɐl�ʋ�������p����
�̂͋�ƋS���ʗp���āA�Ⴆ�����S��Ƃ��������v�Ə����Ă����ŁA
���ꂪ��������A�Â�����͋S�Ƌ�̉������Ă����i�����͓����������j���߂�
�������Ƃ��Ĉ��������Ă��Ƃ��Ǝv���B
832�l�Ԏ����l�N
2023/04/22(�y) 13:00:01.55ID:l5yoKC5/ William M. Baxter��Laurent Sagart�́uOld Chinese: A New Reconstruction�v�̋S�E��̏�É�(�u�ю�(���o)�v�Ȃǂ����Ƃɍč\�z)
�S: *k-ʔujʔ
��: *[k]uʔ
�����~�j�u�����̉��v�ɂ���Baxter�̍č\�����͕��G�����瓖�ĂɂȂ�Ȃ�����������
�S: *k-ʔujʔ
��: *[k]uʔ
�����~�j�u�����̉��v�ɂ���Baxter�̍č\�����͕��G�����瓖�ĂɂȂ�Ȃ�����������
833�l�Ԏ����l�N
2023/04/22(�y) 13:14:46.93ID:adN4jV/6 �x�ߌ�̏�É��ɂ��Ă͖��m�Ȃ�ŋS�Ƌオ�ʂ���Ƃ����������������ǂ����͂킩��Ȃ��B
�����A�тɂ́u�l�ʋS���v�u�l�ʋ���v�u���ʋ���v�u�����㓪�v�u���ʋ���v�Ƃ����傪
���������u����ו��v�u����j�Ɓv�Ƃ�����̑O�ɏo�Ă���݂����Ȃ�ŁA�S������D�ɗ����邩�ȂƁB
���ƁA���̗������̐肢�̈�b�͓��{�O�j�ɂ��ڂ��Ă�݂����ŁA�f�W�^���R���N�V�����Ɂu���{�O�j���`�v
�Ƃ����{�����^����Ă��ďڂ������߂��������B
�����A�тɂ́u�l�ʋS���v�u�l�ʋ���v�u���ʋ���v�u�����㓪�v�u���ʋ���v�Ƃ����傪
���������u����ו��v�u����j�Ɓv�Ƃ�����̑O�ɏo�Ă���݂����Ȃ�ŁA�S������D�ɗ����邩�ȂƁB
���ƁA���̗������̐肢�̈�b�͓��{�O�j�ɂ��ڂ��Ă�݂����ŁA�f�W�^���R���N�V�����Ɂu���{�O�j���`�v
�Ƃ����{�����^����Ă��ďڂ������߂��������B
834�l�Ԏ����l�N
2023/04/25(��) 19:27:30.85ID:uI6jtdb3 �u�����ƊՒk�v����u�������ԏH���O�҉��g�̂��Ɓv
���ԏ@�͗c�����F�Ƃ����A���̍����Љ_�̂Ƃ��납�痧�ԓ���̂��Ƃɍs���ėV��ł����B
����Ƃ��ߐl��̑O�œ������B
����́u�s�ӂ̂��ƂȂ̂Ő�F�����������낤���v�Ɛ�F�̉����Ɏ�����Ă݂����A�ۓ��͏������������Ȃ��Ă��Ȃ������B
�������ē���͐�F�����h�ȕ��l�ƂȂ�ƍl���{�q�Ƃ����B
��F�̒�̎�V(���Ԓ���)�Ƃ������Ƃ��p�����ƂɂȂ�A�H������̖��ƂȂ邱�Ƃ����܂��Ă����B
�}���L��͂�����āu�����E���ԁE���Ƃ́A��B�̉p���ł���H���ɂ��R�ł���O�H�̋|�ł���B
�����������E���ԁE�H���O�Ƃ����̂���ƂȂ�ƁA���ƏH���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��łт邾�낤�v�ƋV�����B
���̂Ƃ����Ƃ��Ƃ�������
�u���ꂪ���ɕP�����a�����������B
�����̊≮��ɍs���Ď�V�a��P�̖��Ƃ������܂��傤�B
�������m���Ȃ��悤�ł���A�P���a�莄�������܂��v
�Ɛ\�����̂ōL��ƏH���ƍ����̉��g�̔j���������Ȃ�A�ƕP��a�����B
�������Ď����P��A��Ċ≮��ɍs���A�����Љ_�ɏڂ����q�ׂ��
�����Љ_�́u�O�㖢���̒����ł���B�H���̖���Ⴄ���Ƃ͌��܂��Ă���̂�����L��Ƃ̉��g�͂Ȃ�ʁB
���X�ɕP��A��ċA����v�ƌ������B
���́u���̂悤�Ɍ�ԓ����邱�Ƃ͗\�����Ă���܂����B
�O�ƍ��̂ł���Β}���Ƃ��łԂ͕̂K��B
����M�ƂƓ��ƂƂ̍���̎��ɓ������ɂ�����A�������܂����ʂĂ�̂��������ƂȂ̂ŁA�����E���A���������A����~�������܂��傤�v
�Ǝv�����Đ\�����B
�Љ_�����̒��`�̂قǂɊ��S���A���̂܂ܖ��𗯂ߒu���Ď�V�̍ȂƂ����B
���̂��ߏH���͕���A�F���ɑ��āu�K���⍂����łڂ��܂��傤�v�Ɛ\�����B
���ԏ@�͗c�����F�Ƃ����A���̍����Љ_�̂Ƃ��납�痧�ԓ���̂��Ƃɍs���ėV��ł����B
����Ƃ��ߐl��̑O�œ������B
����́u�s�ӂ̂��ƂȂ̂Ő�F�����������낤���v�Ɛ�F�̉����Ɏ�����Ă݂����A�ۓ��͏������������Ȃ��Ă��Ȃ������B
�������ē���͐�F�����h�ȕ��l�ƂȂ�ƍl���{�q�Ƃ����B
��F�̒�̎�V(���Ԓ���)�Ƃ������Ƃ��p�����ƂɂȂ�A�H������̖��ƂȂ邱�Ƃ����܂��Ă����B
�}���L��͂�����āu�����E���ԁE���Ƃ́A��B�̉p���ł���H���ɂ��R�ł���O�H�̋|�ł���B
�����������E���ԁE�H���O�Ƃ����̂���ƂȂ�ƁA���ƏH���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��łт邾�낤�v�ƋV�����B
���̂Ƃ����Ƃ��Ƃ�������
�u���ꂪ���ɕP�����a�����������B
�����̊≮��ɍs���Ď�V�a��P�̖��Ƃ������܂��傤�B
�������m���Ȃ��悤�ł���A�P���a�莄�������܂��v
�Ɛ\�����̂ōL��ƏH���ƍ����̉��g�̔j���������Ȃ�A�ƕP��a�����B
�������Ď����P��A��Ċ≮��ɍs���A�����Љ_�ɏڂ����q�ׂ��
�����Љ_�́u�O�㖢���̒����ł���B�H���̖���Ⴄ���Ƃ͌��܂��Ă���̂�����L��Ƃ̉��g�͂Ȃ�ʁB
���X�ɕP��A��ċA����v�ƌ������B
���́u���̂悤�Ɍ�ԓ����邱�Ƃ͗\�����Ă���܂����B
�O�ƍ��̂ł���Β}���Ƃ��łԂ͕̂K��B
����M�ƂƓ��ƂƂ̍���̎��ɓ������ɂ�����A�������܂����ʂĂ�̂��������ƂȂ̂ŁA�����E���A���������A����~�������܂��傤�v
�Ǝv�����Đ\�����B
�Љ_�����̒��`�̂قǂɊ��S���A���̂܂ܖ��𗯂ߒu���Ď�V�̍ȂƂ����B
���̂��ߏH���͕���A�F���ɑ��āu�K���⍂����łڂ��܂��傤�v�Ɛ\�����B
835�l�Ԏ����l�N
2023/04/25(��) 20:53:01.76ID:j79EwqPe836�l�Ԏ����l�N
2023/04/29(�y) 16:39:29.88ID:LCBDHzIG ���鎞�A���R�c��O�Y�����̂悤�ɐ\����
�u�n��i�M�t�j�a�A�����i���L�j�a�A�R�p�i���i�j�a�A����i�Սj�j�a���������B���l�Ƃ������̂�
���ӂ̎��ɂ��Ă��A�͂̋����҂���蕿������Ǝv���Ă���悤�ŁA���L�@�a�i�����`���j��
����������ԏ�������v�i���S�j���A�ނ��ۛ����钬�l���J�߂ď������{�̒��ŁA���̐ԏ���
�w�O�S�l�́x�ł���Ə����t���Ă���܂����B�v
���̂悤�ɐ\���ď��Ă������A�n����Z��
�u����A��玘�O�������̎G�k���d�鎞�A���Ȃ����������悤�Ȗ��ē��Ȏ��������A��������������
���l�����͉����v�����Ă���B
���̓��X�ɂ���āA�ƐE�ƒ��ڊW�̖������ɂ��ẮA���̎�荹�����������Ȃ��̂Ȃ̂��B�v
�n��͂��̂悤�Ɍ���ꂽ�̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�u�n��i�M�t�j�a�A�����i���L�j�a�A�R�p�i���i�j�a�A����i�Սj�j�a���������B���l�Ƃ������̂�
���ӂ̎��ɂ��Ă��A�͂̋����҂���蕿������Ǝv���Ă���悤�ŁA���L�@�a�i�����`���j��
����������ԏ�������v�i���S�j���A�ނ��ۛ����钬�l���J�߂ď������{�̒��ŁA���̐ԏ���
�w�O�S�l�́x�ł���Ə����t���Ă���܂����B�v
���̂悤�ɐ\���ď��Ă������A�n����Z��
�u����A��玘�O�������̎G�k���d�鎞�A���Ȃ����������悤�Ȗ��ē��Ȏ��������A��������������
���l�����͉����v�����Ă���B
���̓��X�ɂ���āA�ƐE�ƒ��ڊW�̖������ɂ��ẮA���̎�荹�����������Ȃ��̂Ȃ̂��B�v
�n��͂��̂悤�Ɍ���ꂽ�̂ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
837�l�Ԏ����l�N
2023/04/29(�y) 17:53:53.27ID:5k9Mkckn http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-8915.html
���l�Ƃ����z���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-4590.html
�����m�ł����B���l�ǂ��͏��R�`�����E�����ԏ����S��
�R�p���h���}�Ƃ��ł͂ł����Ȃ邯��
���l�Ƃ����z���
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-4590.html
�����m�ł����B���l�ǂ��͏��R�`�����E�����ԏ����S��
�R�p���h���}�Ƃ��ł͂ł����Ȃ邯��
838�l�Ԏ����l�N
2023/04/29(�y) 18:55:55.05ID:LCBDHzIG >>837
�������킯����܂���B�����ɂ�����͂܂��o�ĂȂ��̎v���̂�
����i�Սj�j�����鎞�A���̂悤�Ɍ�����
�u�l���l��y�����鎞�A�����������O�c����B
��́A��҂ɑ��k���邱�ƂȂ����^���邱�ƁB
��ɁA�ߔn�i�r���ď�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��n�j�ɐl���悹�邱�ƁB
�O�ɁA�t�O��U�镑�����ƁB
���̎O�����ɂāi�y���������j�T�y�ɉ��䂪�L�����ꍇ�A�����a��˂Ό��ꂵ���B
���������ʂƂ����̂����Ȃ��ƂŗL��̂�����A�������������ɂ��Ă͏�X���������Ă����̂��ނ��ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�������킯����܂���B�����ɂ�����͂܂��o�ĂȂ��̎v���̂�
����i�Սj�j�����鎞�A���̂悤�Ɍ�����
�u�l���l��y�����鎞�A�����������O�c����B
��́A��҂ɑ��k���邱�ƂȂ����^���邱�ƁB
��ɁA�ߔn�i�r���ď�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��n�j�ɐl���悹�邱�ƁB
�O�ɁA�t�O��U�镑�����ƁB
���̎O�����ɂāi�y���������j�T�y�ɉ��䂪�L�����ꍇ�A�����a��˂Ό��ꂵ���B
���������ʂƂ����̂����Ȃ��ƂŗL��̂�����A�������������ɂ��Ă͏�X���������Ă����̂��ނ��ł���B
�w�b�z�R�Ӂx
839�l�Ԏ����l�N
2023/04/29(�y) 19:10:52.21ID:Z5d0rWeP >>838
�S�ē��Ă͂܂�_�̌N
�S�ē��Ă͂܂�_�̌N
840�l�Ԏ����l�N
2023/04/29(�y) 19:48:21.32ID:YYXijNfq ����b�z�R�ӂȂ�ĉƍN�ɂ��ׂ����g���̂��ړI������
841�l�Ԏ����l�N
2023/05/03(��) 18:56:35.17ID:bGCWxSuH ����e�����\���ꂽ���Ƃ�
�u�l���S�l�̑��㌹�V��Ɛ\���҂��A��́i����j�Љ��̎G�k�����Ƃ��āA��������Ɍ�����B
����ɂ��ƁA����҂ƒ����҂͕ʂȂ̂��Ƃ����B
�����҂Ƃ́A��O�悭����_�ĂāA�����悭���āA�����ɂ����~�悭���������~�ɂĐU�镑���l�̎���\���B
����A����҂Ƃ����̂́A�U�镑���Ɉ�`��Ȃ�Ƃ��d��A���͉_�r�i�i���̈������j�ł����Ă��A
�S���Y��Ȏ҂𐔊�҂Ɩ��t���ČĂԁB
��������͑T�m����o���l�����ł���A����Ă��̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B
�������@�ł́u����v�Ƃ��������A�T�@�́u���S�v�Ƃ����ĈӒn���d�����Ă���A�������S�ۂŎ���s��
�l�̓_�Ă钃����������҂̐U�镑���Ȃ̂��ƁA���㌹�V��͌�����B
���Ȃ킿�A����҂ƒ����҂͊e�X�ʕ��Ȃ̂��ƍl����ׂ��Ȃ̂��낤�B�v
�����A����e���͌�����B
�w�b�z�R�Ӂx
�u�l���S�l�̑��㌹�V��Ɛ\���҂��A��́i����j�Љ��̎G�k�����Ƃ��āA��������Ɍ�����B
����ɂ��ƁA����҂ƒ����҂͕ʂȂ̂��Ƃ����B
�����҂Ƃ́A��O�悭����_�ĂāA�����悭���āA�����ɂ����~�悭���������~�ɂĐU�镑���l�̎���\���B
����A����҂Ƃ����̂́A�U�镑���Ɉ�`��Ȃ�Ƃ��d��A���͉_�r�i�i���̈������j�ł����Ă��A
�S���Y��Ȏ҂𐔊�҂Ɩ��t���ČĂԁB
��������͑T�m����o���l�����ł���A����Ă��̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B
�������@�ł́u����v�Ƃ��������A�T�@�́u���S�v�Ƃ����ĈӒn���d�����Ă���A�������S�ۂŎ���s��
�l�̓_�Ă钃����������҂̐U�镑���Ȃ̂��ƁA���㌹�V��͌�����B
���Ȃ킿�A����҂ƒ����҂͊e�X�ʕ��Ȃ̂��ƍl����ׂ��Ȃ̂��낤�B�v
�����A����e���͌�����B
�w�b�z�R�Ӂx
842�l�Ԏ����l�N
2023/05/03(��) 19:16:27.48ID:VO4Kw0mB �n�̃V�����x�������̑���ƍ��ꂵ�Ă������c���͂Ƃ���(�X�L)�҂�
843�l�Ԏ����l�N
2023/05/05(��) 20:06:58.24ID:D4ZMWEXl �㌎�������n�܂�����Ï�̍���̍Œ��A
�㌎�\����̖�A�钆����G�w�֖铢�������
�Ԕ��ɓ���A�R�c�吆�A�O�c�����E�q��̖ʁX���ܕS�̕���I�o��
�Ԕ��ƎR�c���������S�l�͒}���L��̐w���P�����U�X�ɑł��j�������
�}���Ƃ̔n���D���ď�騂��グ�ď�ֈ����Ԃ���
����A�O�c�����E�q�嗦����O�S�l�͗��ԏ@�̐w�ɍU�߂����낤�Ƃ�����
�@�͒m�E�����̖ҏ��Ŗ��f�Ȃ��A���y�ɋʖ����ꂽ���F���������������ɂ��e���ʼn��킵��
�O�c���́u�����̂��Ƃ������v�Ƃ������m�����ɐ��͕��J�̂��Ƃ��ʖ�����������U�߂Ă���
���ł��ۖі��ܘY�Ɩ����҂��㓁�𐅎Ԃ̂��Ƃ��āA��l���痣�ϐ�ނ̗L�l�œG��˔j���Ă�����
���Ԃ̐w�����Z�ڂ��܂�̐m���̂��Ƃ���j������A�剹���ŏ\���ےÁi�A��j�Ɩ���菟�������
�O�ڔ����قǂ̏d�������_���r�����������ۖт̌��ɑ����Ă���
�ۖт͓㓁�ŏ\���̋���˂��т����Ƃ��邪�\���͎��������ɓ㓁��^����Ɏa��܂��
���������Ƃ���ۖт̌������Ė���Ŏ�艟�����A����������o���ĝ��ߏグ���B
������������]�����Ƃ����҂���ʓV�̂悤�ɋ삯�ė��ď\���Ɏa�肩����Z�̊O����a�������A
�\���ɐU��Ԃ肴�܌��̑�����ł��������I�Ə�����
���ɕ��̖��Y����Ƃ����҂͓G�R�l�����ꑧ���Ă������\���̓��������Ď�𓊂��̂Ă�
�ꕶ���ɏ\���Ɍ������čs������őg�ݕ����悤�Ƃ���
����͉ƒ��ł����̖͂�����肽��҂ł��������A�\���͕��Ƃ������t�ɔ���������������߂�ɂ���
�铢���̑叫�ł���O�c�����E�q��͊ۖтƖ��Y�������߂�ꂽ�̂����āA
�얳�O�Ə\���Ɍ������čs���������ɂ܂Â��|�ꂽ�Ƃ���𗧉Ԑ��̑��䕽�Z�Ƃ����҂ɕ߂���ꂽ
���Z���u�����铢���̑叫�䕽�Z�������߂����v�ƍ��炩�ɖ����̂��A
���E�q��̒��q�ł���O�c�������������A�������Ԃ���Ɨ��Ԑ��̐^���������ւƋ삯�����
�V�������䕽�Z�����E�q���A�s����Ƃ���ɏo������
�����͓{��ڂɌ��𒍂��A�����Ȃ�S�_���|����Ƃ����L�l�Ō������Ă������ߑ���͑傢�ɋ����ނ���
�����͕��Z�ɒǂ����蕽�Z���U��Ԃ낤�Ƃ���Ƃ�����꓁�ɐ�|���ĕ����~����
�\����ꐶ��ۂ������E�q�傾���A���Ԑ����������łߐV����J��o���Ă����̂�����
���͂���܂łƓG����˔j����ւƈ����グ��
�w����ď鍇��L�x
�㌎�\����̖�A�钆����G�w�֖铢�������
�Ԕ��ɓ���A�R�c�吆�A�O�c�����E�q��̖ʁX���ܕS�̕���I�o��
�Ԕ��ƎR�c���������S�l�͒}���L��̐w���P�����U�X�ɑł��j�������
�}���Ƃ̔n���D���ď�騂��グ�ď�ֈ����Ԃ���
����A�O�c�����E�q�嗦����O�S�l�͗��ԏ@�̐w�ɍU�߂����낤�Ƃ�����
�@�͒m�E�����̖ҏ��Ŗ��f�Ȃ��A���y�ɋʖ����ꂽ���F���������������ɂ��e���ʼn��킵��
�O�c���́u�����̂��Ƃ������v�Ƃ������m�����ɐ��͕��J�̂��Ƃ��ʖ�����������U�߂Ă���
���ł��ۖі��ܘY�Ɩ����҂��㓁�𐅎Ԃ̂��Ƃ��āA��l���痣�ϐ�ނ̗L�l�œG��˔j���Ă�����
���Ԃ̐w�����Z�ڂ��܂�̐m���̂��Ƃ���j������A�剹���ŏ\���ےÁi�A��j�Ɩ���菟�������
�O�ڔ����قǂ̏d�������_���r�����������ۖт̌��ɑ����Ă���
�ۖт͓㓁�ŏ\���̋���˂��т����Ƃ��邪�\���͎��������ɓ㓁��^����Ɏa��܂��
���������Ƃ���ۖт̌������Ė���Ŏ�艟�����A����������o���ĝ��ߏグ���B
������������]�����Ƃ����҂���ʓV�̂悤�ɋ삯�ė��ď\���Ɏa�肩����Z�̊O����a�������A
�\���ɐU��Ԃ肴�܌��̑�����ł��������I�Ə�����
���ɕ��̖��Y����Ƃ����҂͓G�R�l�����ꑧ���Ă������\���̓��������Ď�𓊂��̂Ă�
�ꕶ���ɏ\���Ɍ������čs������őg�ݕ����悤�Ƃ���
����͉ƒ��ł����̖͂�����肽��҂ł��������A�\���͕��Ƃ������t�ɔ���������������߂�ɂ���
�铢���̑叫�ł���O�c�����E�q��͊ۖтƖ��Y�������߂�ꂽ�̂����āA
�얳�O�Ə\���Ɍ������čs���������ɂ܂Â��|�ꂽ�Ƃ���𗧉Ԑ��̑��䕽�Z�Ƃ����҂ɕ߂���ꂽ
���Z���u�����铢���̑叫�䕽�Z�������߂����v�ƍ��炩�ɖ����̂��A
���E�q��̒��q�ł���O�c�������������A�������Ԃ���Ɨ��Ԑ��̐^���������ւƋ삯�����
�V�������䕽�Z�����E�q���A�s����Ƃ���ɏo������
�����͓{��ڂɌ��𒍂��A�����Ȃ�S�_���|����Ƃ����L�l�Ō������Ă������ߑ���͑傢�ɋ����ނ���
�����͕��Z�ɒǂ����蕽�Z���U��Ԃ낤�Ƃ���Ƃ�����꓁�ɐ�|���ĕ����~����
�\����ꐶ��ۂ������E�q�傾���A���Ԑ����������łߐV����J��o���Ă����̂�����
���͂���܂łƓG����˔j����ւƈ����グ��
�w����ď鍇��L�x
844�l�Ԏ����l�N
2023/05/06(�y) 14:50:46.01ID:MCigo0Yu ���c�M�����͑叫�O�ւ̌�d�u�ɂ����āA���̂悤�Ɍ��{���ꂽ
�u���荇���E����Ƃ������킢�ɂ́A�����l���O�L��B
�\�̂����Z���E�����̏�������B
�\�̂��������E�㕪�̏�������B
�\�̂����\�S�̏�������B
���ɁA�\�̂����Z�E�����̏����́A����\���̏����ł���B
���ɁA�\�̂������E�㕪�̏����͊낤���B
��O�ɁA�\�̂����\���̏����́A���̌�K���ߎ��������āA�Ղ̗_��ɂ��Ă��܂����낤�B�v
�܂��M�����͐��ꂽ
�u�Ⴋ�叫���\���ɏ����Ă��A���̂��߉ߎ��������ẮA���̌�ǂ�قǂ̏����Ă��A
�Ⴋ���̉ߎ��ɂ��s�k�������o����A��X�܂ł��̉ߎ����w�E�������̂ł���B
�K���叫�����Ƃ���҂ɁA�\���\�Ȃ��珟�������Ƃ����v�Ă�����A����͎����̐S�����
��G�E���G�𐔁X���o���A�����������ł��낤�B
�����������ӎ��͈������������̂Ȃ̂��ƁA���S����悤�ɁB�v
�w�b�z�R�Ӂx
�u���荇���E����Ƃ������킢�ɂ́A�����l���O�L��B
�\�̂����Z���E�����̏�������B
�\�̂��������E�㕪�̏�������B
�\�̂����\�S�̏�������B
���ɁA�\�̂����Z�E�����̏����́A����\���̏����ł���B
���ɁA�\�̂������E�㕪�̏����͊낤���B
��O�ɁA�\�̂����\���̏����́A���̌�K���ߎ��������āA�Ղ̗_��ɂ��Ă��܂����낤�B�v
�܂��M�����͐��ꂽ
�u�Ⴋ�叫���\���ɏ����Ă��A���̂��߉ߎ��������ẮA���̌�ǂ�قǂ̏����Ă��A
�Ⴋ���̉ߎ��ɂ��s�k�������o����A��X�܂ł��̉ߎ����w�E�������̂ł���B
�K���叫�����Ƃ���҂ɁA�\���\�Ȃ��珟�������Ƃ����v�Ă�����A����͎����̐S�����
��G�E���G�𐔁X���o���A�����������ł��낤�B
�����������ӎ��͈������������̂Ȃ̂��ƁA���S����悤�ɁB�v
�w�b�z�R�Ӂx
845�l�Ԏ����l�N
2023/05/06(�y) 21:33:53.62ID:ASHhliYU >>844
�����̂��Ƃ�
�����̂��Ƃ�
846�l�Ԏ����l�N
2023/05/06(�y) 22:09:38.11ID:k4psJ+xG �����̉p�������ʎ��ŁA�`���[���Y�����������є��Z���Ă܂������A����̓I�R�W���̖є炾�����ł���
���A�W�A�ł������S���ɖ��B�⒆���k���ł͉��B���l�ɃI�R�W���̖є炪���d����Ă����悤�ł���
���{�ł͕~����w�H�D�ɏ�̑����Ȃǂ̈ꕔ�ł����A���܂藘�p����Ă��܂��A�����ꕔ�Ŕ����є炪�g���Ă��܂�
�喼�s��ł��Ȃ��݂̖ё��́A�{�̉H���Ȃǂŏ���t�����ё��₪�����̂ł����A���ɂ͌F�я₪����܂���
����͔������F�т�،^�ɒ���t���č�������̂ŁA�����ɂ͖є炻�̂��̂ł���܂��A���̒��ɂ͔��F�я��
�c�L�m���O�}�����̌��̗^�̔��т������W�߂č�����F�я�Ȃ�ł���
�ÎR���y�����ُ����@�F�я�i�]�ˌ���j
https://www.e-tsuyama.com/report/assets_c/2014/07/keyari1-thumb-600xauto-76592.jpg
https://www.e-tsuyama.com/report/2014/08/post-754.html
�Ȃ��A����Ƃ���`�����n�̑��ŗL���Ȑ�z�ˁi���鏼���Ɓj�ł́A���R�Ƃ���{�q���g�������Ƃ��ɖ{���̔��F�є����ɓ���
����Ŕ��F�я��������L�^������܂�
���̖є炪�ʏ�̃N�}�����̂��z�b�L���N�O�}���͂킩���Ă��܂���
���A�W�A�ł������S���ɖ��B�⒆���k���ł͉��B���l�ɃI�R�W���̖є炪���d����Ă����悤�ł���
���{�ł͕~����w�H�D�ɏ�̑����Ȃǂ̈ꕔ�ł����A���܂藘�p����Ă��܂��A�����ꕔ�Ŕ����є炪�g���Ă��܂�
�喼�s��ł��Ȃ��݂̖ё��́A�{�̉H���Ȃǂŏ���t�����ё��₪�����̂ł����A���ɂ͌F�я₪����܂���
����͔������F�т�،^�ɒ���t���č�������̂ŁA�����ɂ͖є炻�̂��̂ł���܂��A���̒��ɂ͔��F�я��
�c�L�m���O�}�����̌��̗^�̔��т������W�߂č�����F�я�Ȃ�ł���
�ÎR���y�����ُ����@�F�я�i�]�ˌ���j
https://www.e-tsuyama.com/report/assets_c/2014/07/keyari1-thumb-600xauto-76592.jpg
https://www.e-tsuyama.com/report/2014/08/post-754.html
�Ȃ��A����Ƃ���`�����n�̑��ŗL���Ȑ�z�ˁi���鏼���Ɓj�ł́A���R�Ƃ���{�q���g�������Ƃ��ɖ{���̔��F�є����ɓ���
����Ŕ��F�я��������L�^������܂�
���̖є炪�ʏ�̃N�}�����̂��z�b�L���N�O�}���͂킩���Ă��܂���
847�l�Ԏ����l�N
2023/05/08(��) 11:10:29.98ID:H5oGRO0X ��N�̂܂Ƃ߂���
�y�j���[�X�z�L���^�N�M���u�o�w����I�v���ҍs��ɍő��S�U���l
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13724.html
��
����̃j���[�X
�����ƍN�@�l����Ȋ��@�܂�ŏI���A���ҍs��ɂU�W���l
���V��2023.5.6
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1235470.html
�l���܂�ŏI���̂T���A�l���s�͑�̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v�Ŏ�l������ƍN��������o�D�̏��{������i�R�X�j��
�o���҂S�l���������ƍN���R�n���ҍs��s����̒��S�X�ŏ��J�Â����B���{�����͗E�s�ȍb�h�i�������イ�j�p��
��W�O�O���[�g����Ԃ��p���[�h�B�����߂��吨�̊ϏO�ɏΊ�Ŏ��U��ƁA���S�X�ɔM���̉Q�������N�������B
����͓��Ɛ_�N�̏�����
�y�j���[�X�z�L���^�N�M���u�o�w����I�v���ҍs��ɍő��S�U���l
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-13724.html
��
����̃j���[�X
�����ƍN�@�l����Ȋ��@�܂�ŏI���A���ҍs��ɂU�W���l
���V��2023.5.6
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1235470.html
�l���܂�ŏI���̂T���A�l���s�͑�̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v�Ŏ�l������ƍN��������o�D�̏��{������i�R�X�j��
�o���҂S�l���������ƍN���R�n���ҍs��s����̒��S�X�ŏ��J�Â����B���{�����͗E�s�ȍb�h�i�������イ�j�p��
��W�O�O���[�g����Ԃ��p���[�h�B�����߂��吨�̊ϏO�ɏΊ�Ŏ��U��ƁA���S�X�ɔM���̉Q�������N�������B
����͓��Ɛ_�N�̏�����
848�l�Ԏ����l�N
2023/05/08(��) 11:13:03.96ID:H5oGRO0X �P���Ȑl�C�ł̓L���^�N�������Ə�Ȃ�ł��傤����ǁA���Ƃ��Ɛl���W�܂�₷�����Ղ�̒��̃C�x���g�������݂����ł��˕l���́B
849�l�Ԏ����l�N
2023/05/08(��) 15:21:04.43ID:GLweqOB8 �f��͑�R�P�݂������
���O��v�������H
���̓i���[�V�����ō��킪�I��鎞�ゾ��
���O��v�������H
���̓i���[�V�����ō��킪�I��鎞�ゾ��
850�l�Ԏ����l�N
2023/05/08(��) 18:24:35.04ID:h9LcG64t SNS�ŊF����m���������Đ���オ���Ă�悤�ɂ͌����邪
�������͂��̎S��Ƃ�����̓h���}���ˁH
�������͂��̎S��Ƃ�����̓h���}���ˁH
851�l�Ԏ����l�N
2023/05/08(��) 19:07:58.95ID:Z0n6jH8j �����������}�E���g
852�l�Ԏ����l�N
2023/05/08(��) 19:16:28.23ID:h9LcG64t �q�ϓI�Ȑl�C�̎w�W���Ă̂����ɂ���ˁH
����[�Ȃ�
����[�Ȃ�
853�l�Ԏ����l�N
2023/05/08(��) 22:13:47.53ID:ZX3IVYv2 ���j�D���ł���̓h���}��x���������ƂȂ��z�������낵
��̓h���}�D���ł����j�ɓ��ɋ����Ȃ��z��������
��̓h���}�D���ł����j�ɓ��ɋ����Ȃ��z��������
854�l�Ԏ����l�N
2023/05/09(��) 20:18:51.52ID:z2UNFaNf �叫�̎O�̍єz�Ƃ́A���ɁA��X�����E�������ɕ��m�̎蕿�A���߁A�����ɂ��āA�㒆������
�悫�]�������邱�ƁB
���ɁA�l���悭���m��A���ꂼ��ɖ���\�����鎖�B
��O�ɁA���߁A�����̕��m�ɁA�蕿�̏㒆�����悭�F��������ŁA�O�i�ɉ���^���邱�ƁB
����炪�O�̍єz�ł���A����������������������A�����͍s�V����|��A�㒆���̂���
���̎蕿�ł����Ă��A�l�X�Ȃ��悤�ŏ�ɂȂ�̂��ƐS���A���ł̓������T���A�y���Ȏ�
����ƂȂ��āA���̑叫�̖��悪�キ�Ȃ�B
�ł��邩��A���̎O�����͍����叫�̍єz�ł���B
�����Ă܂��A��ōєz��U�邤�Ƃ����̂́A�����叫�̉��ł��鎘�叫�A�����͑��y�叫�̖�ڂł���B
�w�b�z�R�Ӂx
�悫�]�������邱�ƁB
���ɁA�l���悭���m��A���ꂼ��ɖ���\�����鎖�B
��O�ɁA���߁A�����̕��m�ɁA�蕿�̏㒆�����悭�F��������ŁA�O�i�ɉ���^���邱�ƁB
����炪�O�̍єz�ł���A����������������������A�����͍s�V����|��A�㒆���̂���
���̎蕿�ł����Ă��A�l�X�Ȃ��悤�ŏ�ɂȂ�̂��ƐS���A���ł̓������T���A�y���Ȏ�
����ƂȂ��āA���̑叫�̖��悪�キ�Ȃ�B
�ł��邩��A���̎O�����͍����叫�̍єz�ł���B
�����Ă܂��A��ōєz��U�邤�Ƃ����̂́A�����叫�̉��ł��鎘�叫�A�����͑��y�叫�̖�ڂł���B
�w�b�z�R�Ӂx
855�l�Ԏ����l�N
2023/05/10(��) 10:33:50.91ID:f26oxxe6 ���Ⴀ���̎O���̋�̗Ⴊ�����̂���
����Ƃ������܂łɏ����Ă�̂���
����Ƃ������܂łɏ����Ă�̂���
856�l�Ԏ����l�N
2023/05/10(��) 12:16:35.86ID:tcUmS+y+ ���C�͐l������ڂ͊m���œK�ޓK�����ł��ēK�ȕ]���ŖJ���^�ł���叫(��
857�l�Ԏ����l�N
2023/05/14(��) 13:33:46.82ID:h/ZA9HOh ���y�叫���S����ׂ����Ƃ́A���g�Ő퓭��������͉̂ߎ��Ɍq����Ƃ������ł���B
�E�̂̏����ʂ��đ��y�������A�R�̐�B�����āA�����̏�����悤�d��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̏�Ō�ɗǂ��G������A����̂��ނ��ł���B
���叫�͎��g�S�튯���M�ނ悤�ɂ��Ȃ���A��叫�Ƃ��Đ��藧���Ȃ��B
����ł͏��������ɂ߂ď��������A�������Ђ߁A��R���d�O�d�ɍl���A��Ȃ��������悤�ɂ���̂��̗v�ł���B
�ܓx�̏Փ˂�����Έ�A��x�͓G������A���̌�G�ɔ\�����҂��L��Ύ�ɂ����Ă��R��ׂ��ł���B
�A�����g���x�X�o������l���i���g���āj�叫�ɂȂ����ꍇ�A���g�̓����͈���ׂ��ł͂Ȃ��B
�����Ⴂ���̐S���o�Ă��Ă��܂��A�傫�ȉߎ��̌��ƂȂ�B
�Ⴋ�O�͌�叫�̎g���ɐ�֑���A����Ȃ鍂���������A�x�X���d�˂đ��y�叫�ɂȂ�A������
���叫�ɂ��Ȃ�ׂ��ł���B
�M�����̌�Q���́A���̔@���ł������B
�w�b�z�R�Ӂx
���y�叫�A���叫�̐S���ɂ���
�E�̂̏����ʂ��đ��y�������A�R�̐�B�����āA�����̏�����悤�d��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̏�Ō�ɗǂ��G������A����̂��ނ��ł���B
���叫�͎��g�S�튯���M�ނ悤�ɂ��Ȃ���A��叫�Ƃ��Đ��藧���Ȃ��B
����ł͏��������ɂ߂ď��������A�������Ђ߁A��R���d�O�d�ɍl���A��Ȃ��������悤�ɂ���̂��̗v�ł���B
�ܓx�̏Փ˂�����Έ�A��x�͓G������A���̌�G�ɔ\�����҂��L��Ύ�ɂ����Ă��R��ׂ��ł���B
�A�����g���x�X�o������l���i���g���āj�叫�ɂȂ����ꍇ�A���g�̓����͈���ׂ��ł͂Ȃ��B
�����Ⴂ���̐S���o�Ă��Ă��܂��A�傫�ȉߎ��̌��ƂȂ�B
�Ⴋ�O�͌�叫�̎g���ɐ�֑���A����Ȃ鍂���������A�x�X���d�˂đ��y�叫�ɂȂ�A������
���叫�ɂ��Ȃ�ׂ��ł���B
�M�����̌�Q���́A���̔@���ł������B
�w�b�z�R�Ӂx
���y�叫�A���叫�̐S���ɂ���
858�l�Ԏ����l�N
2023/05/14(��) 21:43:38.95ID:bMQU9WSv ����̑�́A�b�h�̍l�Ɋւ��Ă͂ǂ����錾���Ă��b������܂������A��T�̉����A�{���A�匴�ƁA��������e�l�̍b�h��
���l�̃f�U�C���̍b�h�𒅗p���Ă܂�����
�u���̓��ɖ{�������v�̈�b�ɍ��킹�āA�����l�����̓��i�������N�я���j��t���Ă��̂��悩������Ȃ��ł��傩
�M�����̊��͂������㌀�Ȃ�Β�Ԃ����ĊO���Ȃ�����Ƃ������Ƃ�
���l�̃f�U�C���̍b�h�𒅗p���Ă܂�����
�u���̓��ɖ{�������v�̈�b�ɍ��킹�āA�����l�����̓��i�������N�я���j��t���Ă��̂��悩������Ȃ��ł��傩
�M�����̊��͂������㌀�Ȃ�Β�Ԃ����ĊO���Ȃ�����Ƃ������Ƃ�
859�l�Ԏ����l�N
2023/05/15(��) 07:24:35.08ID:2Hb7VNl/ >>858
�F�B���Ȃ��̂��H����������s�͐e�Ƃ��Ƃ�w
�F�B���Ȃ��̂��H����������s�͐e�Ƃ��Ƃ�w
860�l�Ԏ����l�N
2023/05/15(��) 10:25:40.96ID:ZDewH9ua �����L�掖���g��
�����̂Ȃ���70�b����̑��ہi�֓c�s�j
https://www.chuen.net/mukashi/mukashi_070.html
���̐́A����ƍN���O�����̐킢�ɔs��āA�l����֓����A���Ă�����A���c���͐����悭���̋߂��܂Œǂ��Ă��܂����B
���̂Ƃ��ƍN�́A�ォ�瓦���A���ė���҂̂��߂ɁA�����J�����܂܂ɂ��āA���̊O�ցA�ƂĂ��Ȃ��傫�Ȃ���������܂����B
���c���͂��̑傫�Ȃ�����������Ƃ���u���������ł�����̂ł͂Ȃ����v�Ə�̋߂��ŗl�q�����邱�Ƃɂ��܂����B
����Ə�̒�������Ă������䍶�q��ђ������A�ˑR�A���ۂ����X�Ƒł��炵�n�߂܂����B
���������c���́u�����Ɖ�������ɂ������Ȃ��v�Ǝv���A�}���ŕl���邩�痣��Ă����A����ƍN�́A���낤���ď����邱�Ƃ�
�ł����Ƃ������ꂪ����܂��B���̎��䒉�����ł��炵�āA�G��ގU���������ۂ��u����̑��ہv�ƌĂ�Ă��܂��B
�u����̑��ہv�Ɠ`�����Ă��鑾�ۂ́A���̌�A���t�̏��L�ƂȂ�A�����W�N�ĂɌ��t���w�Z�Z�Ɂi���݂̋����t�w�Z�j�����������ہA
���w�Z�Ɋ�t����܂����B�����đ��ۂ͂T�K�̘O��ɐ��������A����43�N�܂ŁA���k�̓o���Z�Ɛ��߂ɂ́A��������Ƃ��đł��炳��܂����B
���݁A���̑��ۂ́A�����t�w�Z�ɓW������Ă��܂��B�܂��A�n���̔֓c�s���֓c�k���w�Z�ɂ́A���ۃN���u���ł��āA
�q�����������䒉���ɕ������Ƒ��ۂ�ł��炵�Ă��܂��B
�i�֓c�ނ����Ȃ����j
�����̂Ȃ���70�b����̑��ہi�֓c�s�j
https://www.chuen.net/mukashi/mukashi_070.html
���̐́A����ƍN���O�����̐킢�ɔs��āA�l����֓����A���Ă�����A���c���͐����悭���̋߂��܂Œǂ��Ă��܂����B
���̂Ƃ��ƍN�́A�ォ�瓦���A���ė���҂̂��߂ɁA�����J�����܂܂ɂ��āA���̊O�ցA�ƂĂ��Ȃ��傫�Ȃ���������܂����B
���c���͂��̑傫�Ȃ�����������Ƃ���u���������ł�����̂ł͂Ȃ����v�Ə�̋߂��ŗl�q�����邱�Ƃɂ��܂����B
����Ə�̒�������Ă������䍶�q��ђ������A�ˑR�A���ۂ����X�Ƒł��炵�n�߂܂����B
���������c���́u�����Ɖ�������ɂ������Ȃ��v�Ǝv���A�}���ŕl���邩�痣��Ă����A����ƍN�́A���낤���ď����邱�Ƃ�
�ł����Ƃ������ꂪ����܂��B���̎��䒉�����ł��炵�āA�G��ގU���������ۂ��u����̑��ہv�ƌĂ�Ă��܂��B
�u����̑��ہv�Ɠ`�����Ă��鑾�ۂ́A���̌�A���t�̏��L�ƂȂ�A�����W�N�ĂɌ��t���w�Z�Z�Ɂi���݂̋����t�w�Z�j�����������ہA
���w�Z�Ɋ�t����܂����B�����đ��ۂ͂T�K�̘O��ɐ��������A����43�N�܂ŁA���k�̓o���Z�Ɛ��߂ɂ́A��������Ƃ��đł��炳��܂����B
���݁A���̑��ۂ́A�����t�w�Z�ɓW������Ă��܂��B�܂��A�n���̔֓c�s���֓c�k���w�Z�ɂ́A���ۃN���u���ł��āA
�q�����������䒉���ɕ������Ƒ��ۂ�ł��炵�Ă��܂��B
�i�֓c�ނ����Ȃ����j
861�l�Ԏ����l�N
2023/05/15(��) 12:44:34.52ID:7IjTCzJh �M���̑̒������邵���������l����͗��Ƃ�����Ȃ������������Ǝv�����ǂ�
862�l�Ԏ����l�N
2023/05/15(��) 23:46:36.46ID:PyxT3pxx ���̐M���ł������Ƃ��Ȃ������Ƃ��������̂��낤��w
���l�̍l�������Ȃ��Ƃ�
���l�̍l�������Ȃ��Ƃ�
863�l�Ԏ����l�N
2023/05/16(��) 07:21:51.30ID:+kSr0jow �Ђ˂��ꂷ���ł͂Ȃ�����
864�l�Ԏ����l�N
2023/05/16(��) 07:50:28.54ID:WXv0QfIU ��͂��ė��Ƃ��Ȃ��������c��
���L���ė��Ƃ��Ȃ������l��
���L���ė��Ƃ��Ȃ������l��
865�l�Ԏ����l�N
2023/05/16(��) 11:50:06.10ID:clmBcYtC >>858
��T��̓h���}�̓��̓��͗��j�l�����A����30�Z���`�I�[�o�[���炢�̃��N�̖т��A�{�������̂�1.5���[�g���͂�������H
�{���Ƀ��N�̖сH
�Ƃ��������w��̋^�₩��w
��T��̓h���}�̓��̓��͗��j�l�����A����30�Z���`�I�[�o�[���炢�̃��N�̖т��A�{�������̂�1.5���[�g���͂�������H
�{���Ƀ��N�̖сH
�Ƃ��������w��̋^�₩��w
866�l�Ԏ����l�N
2023/05/16(��) 11:58:07.84ID:tP0qaZhE >>865
���͂�Ԃł���������ł���
���͂�Ԃł���������ł���
867�l�Ԏ����l�N
2023/05/16(��) 20:04:09.02ID:xhKeKL8Y ���Ȃ݂ɉp���I�X�v���C�Ђ̃C���X�g������j�{�A�����A�b�g�A�[���Y�V���[�Y�ŕ`���ꂽ�u����̑��ہv�ł��B
https://i.pinimg.com/originals/36/dc/48/36dc48bb1213387d5b3a0fa78ddaf017.jpg
https://i.pinimg.com/originals/36/dc/48/36dc48bb1213387d5b3a0fa78ddaf017.jpg
868�l�Ԏ����l�N
2023/05/17(��) 09:05:21.01ID:S1Wv2UEF �C�O�G�t�̂悭������������قƂ�ǂȂ��Č��x�ł�����
���ۂ̔炪�Ԃ��̂͒��؉A�z�͗l������̉e�����ȁH
�݂艺���Ă���Ƃ����
���ۂ̔炪�Ԃ��̂͒��؉A�z�͗l������̉e�����ȁH
�݂艺���Ă���Ƃ����
869�l�Ԏ����l�N
2023/05/17(��) 09:26:20.01ID:Yl/PxCQx �����x�߂̉��̓����Ďx�߂̗̓y�ł���H
870�l�Ԏ����l�N
2023/05/17(��) 13:42:50.94ID:+F8Ae7wE ��������
871�l�Ԏ����l�N
2023/05/18(��) 09:54:40.80ID:k8bJj2IP >>860
�����N��̒����̂Ȃ��A�u���c�ɒǂ��ĕl���ɓ����A��܂ł����܂�ꂽ�ƍN�̘b�v�̂Ȃ�Ƒ������Ƃ悗
�����N��̒����̂Ȃ��A�u���c�ɒǂ��ĕl���ɓ����A��܂ł����܂�ꂽ�ƍN�̘b�v�̂Ȃ�Ƒ������Ƃ悗
872�l�Ԏ����l�N
2023/05/18(��) 11:28:21.65ID:rbP1hb1E �S���̉Ƃœ����Ă��Ƃ��ɖ���Ƃ��Đ��܂ꂽ�̂��G�N
873�l�Ԏ����l�N
2023/05/23(��) 15:19:31.92ID:TYAgTzqy ����G�N�̃C���[�W�͂�͂薟��u�Ԃ̌c���v�̂��̂���ԉe����炵�����A�A�ڎ��_�ł́u���n�̑��v�̕������i��ł��Ȃ������̂�
�~��I�ȕ���Ƃ��Ă̓o�ꂪ�Ȃ������̂����ƂȂ��Ă͎c�O����
�~��I�ȕ���Ƃ��Ă̓o�ꂪ�Ȃ������̂����ƂȂ��Ă͎c�O����
874�l�Ԏ����l�N
2023/05/23(��) 15:21:40.29ID:fqT3O69+ ���Ȃ�����n���ȃC���[�W
875�l�Ԏ����l�N
2023/05/23(��) 19:02:32.43ID:kxcY31LZ ������łɏH���p�u����������v����u���鐰(�Ȃ����^�C�g���ł͏t)�̖������v
�ƍN����G�N��{�q�ɂ������邱�Ƃ��Ȃ������鐰���͓����G���ȗ��̖��Ƃ̌ւ����邽�߁A
�G�N������O�Ɏ����O�����疜�~(�����̓��{��GDP��1/100)�̍����n���[�����߂Ă��܂����Ƃ����B
���̓`�������ɋ��۔N�ԁA���a�N�ԁA�V�۔N�ԂɌ����Ղ⏬�R��Ղ��@���Ă݂�������͌�����Ȃ������Ƃ����B
���̂̂�����ˎ�E���쏟���̎q���ł��鐅�쒼�q�݂��吳�Z�N�ɏ\���~�������Č����@�������A�߂ڂ������̂͏o�Ȃ������B
�q�݂́u���R�邩����@���Ă����悩�����v�Ǝ��̑O�܂ł������Ă����Ƃ����B
�Ȃ��F�s�{�̏��x�Ƃ������Ƃ���o���u�G���G�^�v�Ƃ����ËL�^�ɂ��A
���鐰���̎���A���������͂��̑����J���Ă݂�Ƌ�ł��������߁A�����̏d�b�ł������V���吅������ɂ�����ꂽ�Ƃ����B
����͑��̎w����{���藎�Ƃ��悤�ȍ������̂ł������B
���̂̂��V�����]�˂ɑ����Ď�蒲�ׂ����邱�ƂɌ��܂������A�V���吅�͍����ɂāA�ǂ������ɓ��ꂽ�̂��Z���Ŋ������E�������Ƃ����B
�ƍN����G�N��{�q�ɂ������邱�Ƃ��Ȃ������鐰���͓����G���ȗ��̖��Ƃ̌ւ����邽�߁A
�G�N������O�Ɏ����O�����疜�~(�����̓��{��GDP��1/100)�̍����n���[�����߂Ă��܂����Ƃ����B
���̓`�������ɋ��۔N�ԁA���a�N�ԁA�V�۔N�ԂɌ����Ղ⏬�R��Ղ��@���Ă݂�������͌�����Ȃ������Ƃ����B
���̂̂�����ˎ�E���쏟���̎q���ł��鐅�쒼�q�݂��吳�Z�N�ɏ\���~�������Č����@�������A�߂ڂ������̂͏o�Ȃ������B
�q�݂́u���R�邩����@���Ă����悩�����v�Ǝ��̑O�܂ł������Ă����Ƃ����B
�Ȃ��F�s�{�̏��x�Ƃ������Ƃ���o���u�G���G�^�v�Ƃ����ËL�^�ɂ��A
���鐰���̎���A���������͂��̑����J���Ă݂�Ƌ�ł��������߁A�����̏d�b�ł������V���吅������ɂ�����ꂽ�Ƃ����B
����͑��̎w����{���藎�Ƃ��悤�ȍ������̂ł������B
���̂̂��V�����]�˂ɑ����Ď�蒲�ׂ����邱�ƂɌ��܂������A�V���吅�͍����ɂāA�ǂ������ɓ��ꂽ�̂��Z���Ŋ������E�������Ƃ����B
876�l�Ԏ����l�N
2023/05/23(��) 19:07:22.04ID:kxcY31LZ �����̂�Y��Ă��܂����B
�H���p�u����������v�̏o�ł͏��a14�N(1939�N)�ŁA1940�N����̓��{�̖���GDP��370���~�Ȃ̂�1/100�Ƃ����Ӗ��ł��B
�H���p�u����������v�̏o�ł͏��a14�N(1939�N)�ŁA1940�N����̓��{�̖���GDP��370���~�Ȃ̂�1/100�Ƃ����Ӗ��ł��B
877�l�Ԏ����l�N
2023/05/24(��) 02:30:17.06ID:ktKFjjw5 �E�B�L�y�f�B�A���
����Ɉڂ�ۂɁA�����͋���E�����n���ɖ��߂��Ƃ���A�V��5�N�i1834�N�j���痂�X�N�ɂ����āA���J�ʐV���̎����q�傪�������̔��@���s���Ă���i�u��B�{�g�c���n�������@����ꌏ�v�w�����{���p���x�j
����Ɉڂ�ۂɁA�����͋���E�����n���ɖ��߂��Ƃ���A�V��5�N�i1834�N�j���痂�X�N�ɂ����āA���J�ʐV���̎����q�傪�������̔��@���s���Ă���i�u��B�{�g�c���n�������@����ꌏ�v�w�����{���p���x�j
878�l�Ԏ����l�N
2023/05/24(��) 16:00:37.47ID:TCronjTz �ƍN���ڂ������I〝���B�������̉���〟����Ƃ̍���
https://note.tokyo-sports.co.jp/n/n18ca0f1b983f
�]�˒����ɂ͂W�㏫�R�g�@�̖��ŁA�剪���������@���s���Ă���B���̂Ƃ��͌@������������āA�P�P���̋]���҂��o���A
���̗���肪�������B
�����ȍ~���A�Ō�̌�����ł��鐅�쎁�̎q�����A�đ���œ��Ă��F�q�Ǐ��Ƒg�݁A�傪����Ȕ��@���s�����B
����ɂP�X�U�V�N����́A�M�҂��m�������{�ł�����l�����������̎��т��������ՐĎ������킵�A�W�X�N�܂ł�
�Q�Q�N�ԂɁA�P���~�ȏ��������Ō@�������A����������s�ɏI������B
https://note.tokyo-sports.co.jp/n/n18ca0f1b983f
�]�˒����ɂ͂W�㏫�R�g�@�̖��ŁA�剪���������@���s���Ă���B���̂Ƃ��͌@������������āA�P�P���̋]���҂��o���A
���̗���肪�������B
�����ȍ~���A�Ō�̌�����ł��鐅�쎁�̎q�����A�đ���œ��Ă��F�q�Ǐ��Ƒg�݁A�傪����Ȕ��@���s�����B
����ɂP�X�U�V�N����́A�M�҂��m�������{�ł�����l�����������̎��т��������ՐĎ������킵�A�W�X�N�܂ł�
�Q�Q�N�ԂɁA�P���~�ȏ��������Ō@�������A����������s�ɏI������B
879�l�Ԏ����l�N
2023/05/24(��) 16:17:36.78ID:TCronjTz �e���r�����y�Ǝ��z�L�b�G�g�u������������v�����ց@3���~�̗��D�\�z�@�Ӓ�m�u���̕i���v
[2023/05/23
https://news.yahoo.co.jp/articles/1f37e727620a29a7395b110fe06dfd1589166776
�����E����́g����ꏊ�h�ɑ�ϋM�d�Ȃ��ۊǂ���Ă��܂��B���͂��̂���́A
�L�b�G�g���������Ƃ�����M�d�ȁu�����̒�����v�ł��B
�����āA���́u�����̒�����v���I�[�N�V�����ɏo�i����邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B
���D�\�z�z�́A�Ȃ��3���~���Ƃ����܂��B
�Ô˂̏���ˎ�E�������ՁB�]�ˏ�C�z�̍ہA�V��t��v����ȂǁA�z��̖���Ƃ���
�m��ꂽ�퍑�����ł��B
����A���̎q�������ʂ̎����A��c��X�`����Ă��������̒�������I�[�N�V������
�o�i���܂����B
�L�b�G�g���A1592�N����1598�N�ɂ�����2�x�ɂ킽�蒩�N�����֍U�ߍ��u���\�E�c���̖��v�B
���̎��A�������Ղ́A�D��s�Ƃ��Đ��R�𗦂��A��ʂ������܂����B
�@�G�g����A���̕��M���̂����A�̒n��8���ɉ������ꂽ���ՁB����ɁA�G�g����J���Ƃ��āA
���炪�����̒����ň��p���Ă��������̒����������ꂽ�ƁA�����Ƃɂ͓`�����Ă��܂��B
[2023/05/23
https://news.yahoo.co.jp/articles/1f37e727620a29a7395b110fe06dfd1589166776
�����E����́g����ꏊ�h�ɑ�ϋM�d�Ȃ��ۊǂ���Ă��܂��B���͂��̂���́A
�L�b�G�g���������Ƃ�����M�d�ȁu�����̒�����v�ł��B
�����āA���́u�����̒�����v���I�[�N�V�����ɏo�i����邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B
���D�\�z�z�́A�Ȃ��3���~���Ƃ����܂��B
�Ô˂̏���ˎ�E�������ՁB�]�ˏ�C�z�̍ہA�V��t��v����ȂǁA�z��̖���Ƃ���
�m��ꂽ�퍑�����ł��B
����A���̎q�������ʂ̎����A��c��X�`����Ă��������̒�������I�[�N�V������
�o�i���܂����B
�L�b�G�g���A1592�N����1598�N�ɂ�����2�x�ɂ킽�蒩�N�����֍U�ߍ��u���\�E�c���̖��v�B
���̎��A�������Ղ́A�D��s�Ƃ��Đ��R�𗦂��A��ʂ������܂����B
�@�G�g����A���̕��M���̂����A�̒n��8���ɉ������ꂽ���ՁB����ɁA�G�g����J���Ƃ��āA
���炪�����̒����ň��p���Ă��������̒����������ꂽ�ƁA�����Ƃɂ͓`�����Ă��܂��B
880�l�Ԏ����l�N
2023/05/24(��) 21:27:13.48ID:v+W2Lmab 420�N�ȏ�̔N�������������Ȃ����s�J����
�����Ƃœh�蒼���Ă��̂���
�����Ƃœh�蒼���Ă��̂���
881�l�Ԏ����l�N
2023/05/30(��) 18:31:17.87ID:q1jfEv2f ���閄�����Ɋւ��Í��H�O��
>>875��
�u���鐰(�Ȃ����^�C�g���ł͏t)�̖������v���l�b�g�Œ��ׂ���
�j�R�j�R��sm16899139
�Ƃ����A�C�h���}�X�^�[�̃L�����ɗ��j���Љ���Ă��铮�悪�q�b�g����(����������݂����Ȃ�)�B
���̓���ɂ��A��錧����s�ɂ���������̎R��̓V��Ɍ��閄�����ɂ܂��Í���������Ă���Ƃ������B
����}���ق̃f�W�^���R���N�V�����ʼn{���\�ȎG���u�R���Z���T�X�v1985�N3���ɂ��A
���鐰�����`��̍]�ˏd��(�Ȃ����R�����̖�)�ɖ����𗊂݁A�d���̏d�b���̂ɉr��ŋ������̎R��ɍ��A�Ƃ�����������炵���B
���܂��ܗׂ̓Ȗ،����R�s�ɗp��������������s���Ă����B
���̎R����ӂ͍�ƒ��ŊO�ς͎B�e�ł��Ȃ��������������߁A�Q�q�������ċA�낤�Ƃ�����A��Z�E�ɘa�̂�q�������Ă����������B
�R��ɂ͎O�̘a�̂�����悤�����A�����������Ƃ��ɂ͐^�̘a�͍̂���Ă����B
��Z�E�ɂ��ߔN�A�钆�Ɉ����l�Ԃ�����Ă����Ă��܂����Ƃ̂��ƁB
���̂����A�����ɂȂ�Ɓu���鎵���_�߂���v�Ƃ����C�x���g�œ��키�悤�ŁA�����ɋ���������l�͂��̎��ɎQ�w����̂������������B
�����Č��閄�����Ɋւ��Ƃ����Í��̘a�̎O��
(�j�R�j�R�̓���ł͎O��̘a�̈ȊO�ɂ��Í����ۂ��̂��Љ��Ă������A�R�傪��ƒ��Ȃ��Ƃ�����m�F���Ă��Ȃ�
�ق��̃j���[�X�L���Ƃ��T�C�g�ł͘a�̂ɂ��Ă����G����Ă���)
���̒����@�ӂ䂤����Ɂ@�����͂Ȃ��@�݂ǂ���̂����@����̂���
���ӂ₤�Ɂ@�ӂ�Ă���܂�@����t�@��̂Ȃ���́@���ւ̐��܂ł�
����߂����@���ɂ��낤�@�������@����͂��͂�ʁ@�Ԃ̂����
>>875��
�u���鐰(�Ȃ����^�C�g���ł͏t)�̖������v���l�b�g�Œ��ׂ���
�j�R�j�R��sm16899139
�Ƃ����A�C�h���}�X�^�[�̃L�����ɗ��j���Љ���Ă��铮�悪�q�b�g����(����������݂����Ȃ�)�B
���̓���ɂ��A��錧����s�ɂ���������̎R��̓V��Ɍ��閄�����ɂ܂��Í���������Ă���Ƃ������B
����}���ق̃f�W�^���R���N�V�����ʼn{���\�ȎG���u�R���Z���T�X�v1985�N3���ɂ��A
���鐰�����`��̍]�ˏd��(�Ȃ����R�����̖�)�ɖ����𗊂݁A�d���̏d�b���̂ɉr��ŋ������̎R��ɍ��A�Ƃ�����������炵���B
���܂��ܗׂ̓Ȗ،����R�s�ɗp��������������s���Ă����B
���̎R����ӂ͍�ƒ��ŊO�ς͎B�e�ł��Ȃ��������������߁A�Q�q�������ċA�낤�Ƃ�����A��Z�E�ɘa�̂�q�������Ă����������B
�R��ɂ͎O�̘a�̂�����悤�����A�����������Ƃ��ɂ͐^�̘a�͍̂���Ă����B
��Z�E�ɂ��ߔN�A�钆�Ɉ����l�Ԃ�����Ă����Ă��܂����Ƃ̂��ƁB
���̂����A�����ɂȂ�Ɓu���鎵���_�߂���v�Ƃ����C�x���g�œ��키�悤�ŁA�����ɋ���������l�͂��̎��ɎQ�w����̂������������B
�����Č��閄�����Ɋւ��Ƃ����Í��̘a�̎O��
(�j�R�j�R�̓���ł͎O��̘a�̈ȊO�ɂ��Í����ۂ��̂��Љ��Ă������A�R�傪��ƒ��Ȃ��Ƃ�����m�F���Ă��Ȃ�
�ق��̃j���[�X�L���Ƃ��T�C�g�ł͘a�̂ɂ��Ă����G����Ă���)
���̒����@�ӂ䂤����Ɂ@�����͂Ȃ��@�݂ǂ���̂����@����̂���
���ӂ₤�Ɂ@�ӂ�Ă���܂�@����t�@��̂Ȃ���́@���ւ̐��܂ł�
����߂����@���ɂ��낤�@�������@����͂��͂�ʁ@�Ԃ̂����
882�l�Ԏ����l�N
2023/05/30(��) 21:00:42.91ID:aSM9BdmM �������Ƀ��}��������z���Ē����Ƀ|���ƗZ�����Ă���邩��J���^������
883�l�Ԏ����l�N
2023/05/30(��) 21:01:30.59ID:aSM9BdmM �������Ƀ��}��������z���Ē����Ƀ|���ƗZ�����Ă���邩��J���^������
884�l�Ԏ����l�N
2023/05/31(��) 09:20:30.46ID:8u9xS1D8 �܂��A������
885�l�Ԏ����l�N
2023/06/04(��) 15:03:32.74ID:F4RPUIsG �V�����N�i���T�l�N�j�O����{�ɁA���c�M�����̌�a�C�͈�i�������ꂽ�B���̎e�ׂ́A�_�@���i�サ�A
���̏�l�Ԃ̋������ꋋ�������ŁA����C�ڏo�x���܂��܂��āA���O���\�ܓ��ɂ́A�D�c�M���̋��邷�鍑�̓��A
�����Z�֔����L��ׂ��Ƃ̎|�����\����A���̐w�G�ꂪ�r�����������B
���l�͑召�E�㉺���ɐs���A���̓x�̐w�ɂ͈���������܂��䊴�ɗa�����ƁA��Ԃ��ƌ���Ȃ������B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M���̐���̂�����c����ח��������㔭�a�����Ƃ���A���̌㌳�T�l�N�l���\����Ɏ�������킯�ł����A
�ꎞ�I�ɂ͉��A�����Z�U����ڎw���Ă����炵���A�Ƃ����L�q�B
���̏�l�Ԃ̋������ꋋ�������ŁA����C�ڏo�x���܂��܂��āA���O���\�ܓ��ɂ́A�D�c�M���̋��邷�鍑�̓��A
�����Z�֔����L��ׂ��Ƃ̎|�����\����A���̐w�G�ꂪ�r�����������B
���l�͑召�E�㉺���ɐs���A���̓x�̐w�ɂ͈���������܂��䊴�ɗa�����ƁA��Ԃ��ƌ���Ȃ������B
�w�b�z�R�Ӂx
���c�M���̐���̂�����c����ח��������㔭�a�����Ƃ���A���̌㌳�T�l�N�l���\����Ɏ�������킯�ł����A
�ꎞ�I�ɂ͉��A�����Z�U����ڎw���Ă����炵���A�Ƃ����L�q�B
886�l�Ԏ����l�N
2023/07/01(�y) 17:31:44.87ID:5OhX76wn ���m���ᔻ�̎�
��A�l��J�߂鎞�́A�J�߂�ɒl����\���؋��������A掂鎞�͂��̍����ƂȂ鈫���؋��������A
�@�@���ꂪ�{���ł���B
�@�@�܂��ד��́A�㐙�����̉ƒ��̂悤�ɁA�����̎҂ł���Έ��������J�߁A�n������Ηǂ��Ă�掂�B
�@�@���̂悤�ȉƒ��ɂ́A���a�Ȏ҂��\�l�����l����B
��A���Ƃ���l���\���Ƃ��A�吨�̈����Ɉ͂܂��Ɩ����̗l�ɂȂ�B���̎��͏\�l���\�l�����҂ƂȂ�A
�@�@���̂悤�ł������̂ŁA�㐙�������͎q�����̂Ăĉz��֓������܂ꂽ�B
�@�@���āA�؋��������đP���̒�߂̂���Ƃ́A�悸�^���s���Ă��̑叫�����Ƃ��Ă��A�Ղ܂�
�@�@���̉ƒ��O�͋|���ɗ����ł���B����͏؋����ȂĖJ�߁A掂�̂ɁA�\�����m�������W�܂�A
�@�@�܂������Ȏ҂��\�l�̓���A�O�l�����Ă��A�F�\���悤�Ɍ�������̂Ȃ̂��B
�w�b�z�R�Ӂx
�z���g�b�z�R�ӂ͏㐙�����ɂ͗e�͂��Ȃ���
��A�l��J�߂鎞�́A�J�߂�ɒl����\���؋��������A掂鎞�͂��̍����ƂȂ鈫���؋��������A
�@�@���ꂪ�{���ł���B
�@�@�܂��ד��́A�㐙�����̉ƒ��̂悤�ɁA�����̎҂ł���Έ��������J�߁A�n������Ηǂ��Ă�掂�B
�@�@���̂悤�ȉƒ��ɂ́A���a�Ȏ҂��\�l�����l����B
��A���Ƃ���l���\���Ƃ��A�吨�̈����Ɉ͂܂��Ɩ����̗l�ɂȂ�B���̎��͏\�l���\�l�����҂ƂȂ�A
�@�@���̂悤�ł������̂ŁA�㐙�������͎q�����̂Ăĉz��֓������܂ꂽ�B
�@�@���āA�؋��������đP���̒�߂̂���Ƃ́A�悸�^���s���Ă��̑叫�����Ƃ��Ă��A�Ղ܂�
�@�@���̉ƒ��O�͋|���ɗ����ł���B����͏؋����ȂĖJ�߁A掂�̂ɁA�\�����m�������W�܂�A
�@�@�܂������Ȏ҂��\�l�̓���A�O�l�����Ă��A�F�\���悤�Ɍ�������̂Ȃ̂��B
�w�b�z�R�Ӂx
�z���g�b�z�R�ӂ͏㐙�����ɂ͗e�͂��Ȃ���
887�l�Ԏ����l�N
2023/07/01(�y) 18:59:37.35ID:a8HcLhKp �q�����̂Ăĉz��ɓ���āA���M�𗊂�
�q���̋w�̎��N�̎q���̌i�Ղ̂��߂Ɍ�ق̗��₵�悤�Ƃ�����
�i���R�Ɍi�Ղ̑��q�Ƃ��ǂ��E����錛��
�q���̋w�̎��N�̎q���̌i�Ղ̂��߂Ɍ�ق̗��₵�悤�Ƃ�����
�i���R�Ɍi�Ղ̑��q�Ƃ��ǂ��E����錛��
888�l�Ԏ����l�N
2023/07/01(�y) 19:25:49.30ID:i1A71xwj �����Ă��Ĉ�Ă�ꂽ�{���{���ł���
889�l�Ԏ����l�N
2023/07/08(�y) 22:09:11.41ID:58EwJ9sF ���̍��̑叫�|���l�V��
��A�k�����N���͖��叫�ɂēx�X�̌R�ɏ����������ɁA��R�ɂĊǗ̏㐙�̑�G�ɂЂƂ����t���A
�@�@�I�Ɂi�㐙�j�����Ɏa�菟���ǂ������A�֓���؏]����悤�ɐ������B�܂�k���Ƃ̋|��́A
�@�@�G�̖��f���̗v�ɖڂ�t������̂Ȃ̂��B
��A�z��́i�㐙�j���M�́A��̕����ɂ����܂킸�������鍇������悤�Ƃ��邪�A����͔×��������
�@�@������ɓn��悤�Ȏd���ł���B��X���肪�܂����G�ɑ��ẮA�����ނ������r���B
�@�@���M�͉���A�z���A�����͊֓��O�X�ȂǂŔs�R�������Ƃ����邪�A���c�M�����ƑΛ����鎞��
�@�@����Ɏd�|���\���ꂽ�B
��A�D�c�M���͎��͂�̕�͂������ēP�ނ��A���ڂ̏���������U�ߗ��Ƃ���Ă����Ƃ��Ȃ��B
�@�@�ǂ�������Ď��R�̐l����ǂ������ɓ�����Ȃ���A���Ԃ̎�荹���͖����̂�����B
�@�@�U�ߓ���͋}���������A�����Ɂi�ʕ��ʂɁj�o�����č��𑽂�����Ď����A��g�Ɛ���A
�@�@�I�ɂ͂��̖��͍������̂ƂȂ�A�Ƃ������ł���B
��A�i���c�j�M�����͌R�ɑ��Q�̖����悤�ɁA�G�����đނ������r���Ȃ�Ȃ��悤�ɂ����B
�@�@��͂�����ɑ��G�̌�l�߁i���R�j�����Ă��A��������āi�Q�Ăāj��͂���������P�ނ��Ȃ��悤�A
�@�@�o�w�̑O���炻�̕��j���R���ɂ悭���������ďo��B
�@�@�����āA�䂪�̕��̏�����������Ȃ��悤�ɁA�Ղ̏����𐅂ɂ��Ȃ��悤�ɂ����L��A
�@�@����܂Ŗ��͎c����̂ł���B
�@�@���Ė��A���𑽂����߂邱�Ƃɂ��ĐM�����́A���̐g�̉ʕ�ɂ�菭�������䖳�����Ė�����������A
�@�@���̏������������ΏI�ɕ}�K�i���{�j�Z�\�]�B�̎�Ƃ����邾�낤�Ƌ��ɐ���ꂽ�B
�@�@�M�����̌��@�͌䏬���ɕ����ŏ�����Ă���A�l�����̔@���ł���B���̌Ì�Ƃ́A
�@�@�ꑴ���@��
�@�@�ꑴ���@��
�@�@�ꑴ�N���@��
�@�@�ꑴ�s���@�R
�w�b�z�R�Ӂx
��A�k�����N���͖��叫�ɂēx�X�̌R�ɏ����������ɁA��R�ɂĊǗ̏㐙�̑�G�ɂЂƂ����t���A
�@�@�I�Ɂi�㐙�j�����Ɏa�菟���ǂ������A�֓���؏]����悤�ɐ������B�܂�k���Ƃ̋|��́A
�@�@�G�̖��f���̗v�ɖڂ�t������̂Ȃ̂��B
��A�z��́i�㐙�j���M�́A��̕����ɂ����܂킸�������鍇������悤�Ƃ��邪�A����͔×��������
�@�@������ɓn��悤�Ȏd���ł���B��X���肪�܂����G�ɑ��ẮA�����ނ������r���B
�@�@���M�͉���A�z���A�����͊֓��O�X�ȂǂŔs�R�������Ƃ����邪�A���c�M�����ƑΛ����鎞��
�@�@����Ɏd�|���\���ꂽ�B
��A�D�c�M���͎��͂�̕�͂������ēP�ނ��A���ڂ̏���������U�ߗ��Ƃ���Ă����Ƃ��Ȃ��B
�@�@�ǂ�������Ď��R�̐l����ǂ������ɓ�����Ȃ���A���Ԃ̎�荹���͖����̂�����B
�@�@�U�ߓ���͋}���������A�����Ɂi�ʕ��ʂɁj�o�����č��𑽂�����Ď����A��g�Ɛ���A
�@�@�I�ɂ͂��̖��͍������̂ƂȂ�A�Ƃ������ł���B
��A�i���c�j�M�����͌R�ɑ��Q�̖����悤�ɁA�G�����đނ������r���Ȃ�Ȃ��悤�ɂ����B
�@�@��͂�����ɑ��G�̌�l�߁i���R�j�����Ă��A��������āi�Q�Ăāj��͂���������P�ނ��Ȃ��悤�A
�@�@�o�w�̑O���炻�̕��j���R���ɂ悭���������ďo��B
�@�@�����āA�䂪�̕��̏�����������Ȃ��悤�ɁA�Ղ̏����𐅂ɂ��Ȃ��悤�ɂ����L��A
�@�@����܂Ŗ��͎c����̂ł���B
�@�@���Ė��A���𑽂����߂邱�Ƃɂ��ĐM�����́A���̐g�̉ʕ�ɂ�菭�������䖳�����Ė�����������A
�@�@���̏������������ΏI�ɕ}�K�i���{�j�Z�\�]�B�̎�Ƃ����邾�낤�Ƌ��ɐ���ꂽ�B
�@�@�M�����̌��@�͌䏬���ɕ����ŏ�����Ă���A�l�����̔@���ł���B���̌Ì�Ƃ́A
�@�@�ꑴ���@��
�@�@�ꑴ���@��
�@�@�ꑴ�N���@��
�@�@�ꑴ�s���@�R
�w�b�z�R�Ӂx
890�l�Ԏ����l�N
2023/07/09(��) 19:14:59.25ID:yyEh7rNI �����l�^�ꂩ
�� ���̃X���b�h�͉ߋ����O�q�ɂɊi�[����Ă��܂�
�j���[�X
- �����̒������L�A�ꐢ���̑叟���ց@���t�W�����A�i�Ƃ́u���ӂ̏�ł̐��s�ׂ������v�ƔF�� ��14 [Ailuropoda melanoleuca��]
- �@����m�K���_���ŐV��wGQuuuuuuX�i�W�[�N�A�N�X�j�x�T�؍�46�l�^�ʼn���@�ē̒ߊ��a�Ǝ��͔T�؍�t�@�� ��3 [Anonymous��]
- �ˏo���ĒႢ���{�����̒����@�o�ς̒�⏭�q���ɂ��e�� [���ꁚ]
- �y��ʁE�O���s�̏��w���Ђ����������z�^�]���Ă����ƌ�����j���o�� ��ʌ��x [�ϗ���]
- �u�������̔s�k���ȁv�����E���s���c���@����Ō��łɔے�I�ȐΔj�̍���َ� [�a�̎s��]
- Z����̐������́u����Ȃ��v�@����1000�~�������ő� [���l����]
- �y�����z���߂����̂��������l�^�o��������������RPG2🧪
- �g�����v�u�E�H���}�[�g�͊ł𗝗R�ɒl�グ����̂���߂�B���Ă��邼�v�Ǝ�����I�ɏグ�Ĉ��� [545512288]
- �g�����v����i�l�グ��\�������E�H���}�[�g��ᔻ����i�]�ł��������悤�ɖ��w���Ŕ��� [737440712]
- 🏡👊𝑃𝑢𝑛😅𝑐ℎ👊🏡
- �R���}��810�ł������N��
- ����A�Q�O�Q�T�N������Ɖp��Ŏ��{�ցu���{��Ƃ��������[�J������g���Ă�l�A�o�J�ł����v [918862327]
- ��J�o��\��@�l�k�a�Q�O�Q�T�u�G���W�F���X�v�u�h�W���[�X�v��4
- ��J�o��\��@�l�k�a�Q�O�Q�T�u�G���W�F���X�v�u�h�W���[�X�v��5
- �T���f�[�E�W���|���@�t�W�e���rVS�_���g���l���āc����z���G�����������c���җ�@��4
- ��J�o��\��@�l�k�a�Q�O�Q�T�u�G���W�F���X�v�u�h�W���[�X�v��6
- �~������GOLD
- NHK��������Ɏ�����������X�� 225399 �ЎR���I�̋C�ۏ��
